解説記事2009年01月26日 【実務解説】 日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(2)計算書類(2009年1月26日号・№292)
実務解説
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(2)計算書類
(社)日本経済団体連合会経済第二本部経済法制グループ長 小畑良晴
Ⅲ 計算書類
1 貸借対照表 貸借対照表の記載において、「リース取引」並びに「たな卸資産」に関して、以下の改訂を行った。
(1)リース会計基準の適用(ひな型33~34頁参照)
平成19年3月30日の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の改正(これに伴い、財務諸表等規則8条の6等の改正も行われた)により、それまで賃貸借処理が原則であった所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として通常の売買取引に準じた会計処理が行われることになったことから、会社計算規則106条及び107条が改正された。
これを踏まえ、ファイナンス・リースの借主側の場合は、貸借対照表の資産の部にリース資産を、負債の部にリース債務を計上することとした(ひな型33頁参照)。貸主側の場合については、記載上の注意において、リース債権、リース投資資産として表示することを明記した(ひな型34頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型54、55頁参照)。
(2)棚卸資産に係るものの区分表示(ひな型33~34頁参照)
貸借対照表の流動資産に属する資産のうち、棚卸資産に係るものの区分表示について、従来は、「製品」「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」を掲げてきたが、四半期開示の区分が5区分(商品、製品、半製品、原材料、仕掛品)から3区分(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)に簡素化されたことに合わせて財務諸表等規則17条1項(及び連結財務諸表規則23条1項)の改正(平成20年内閣府令第50号)が行われた(2008年8月7日公布)ことを踏まえ、ひな型においても、それと同様に「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の3区分に改めた。
なお、改正府令では、3区分に属する資産についてそれぞれの科目に属する金額を注記することによって、「たな卸資産の科目をもって一括して掲記」することも認めていることから(財務諸表等規則17条3項等)、ひな型においても、「棚卸資産」として一括表示し、その内訳を示す科目及び金額を注記することも考えられる旨、記載上の注意として追加した(ひな型34頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型54、55頁参照)。
2 個別注記表
(1)資産の評価基準及び評価方法(ひな型37~38頁参照)
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」は、企業会計基準委員会から、2006年7月5日に公表されたものである。本基準では、国際的な会計基準との調和等の観点から、棚卸資産を通常の販売目的で保有する棚卸資産とトレーディング目的で保有する棚卸資産に区分し、前者については、収益性の低下による簿価引下げという考え方に基づく評価基準を定め、後者については、金融商品に関する会計基準における売買目的有価証券に関する会計処理に準じた取扱いとすることを定めている。その適用は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からであったことから、平成21年6月総会における計算書類から本格的に適用されることとなる。
そこで、ひな型では、従来、本基準の早期適用を念頭に記載上の注意として掲げていたものを記載例として位置付けた(ひな型37頁参照)。もっとも、12月決算会社等適用開始時期が遅れる場合もあることから、ひな型では、従来の記載例も記載上の注意の中に残した(ひな型38頁参照)。
なお、企業会計基準委員会は、平成20年9月26日に、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を改正し、棚卸資産の評価方法を個別法・先入先出法・平均原価法(移動平均法または総平均法)・売価還元法の4つに定め(第6-2項)、会計基準の国際的なコンバージェンスを図るため、選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除することとしたが(第34-12項)、これは、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用される(早期適用可)ことから、今回のひな型においては特段の対応は行っていない。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型60頁参照)。
(2)固定資産の減価償却の方法(ひな型38頁参照)
平成19年3月30日の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の改正(これに伴い、財務諸表等規則8条の6等の改正も行われた)により、それまで賃貸借処理が原則であった所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として通常の売買取引に準じた会計処理が行われることになった。同基準において、ファイナンス・リースの借主側では、貸借対照表の資産の部にリース資産を計上することとされ、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定することとされた。この改正を踏まえ、ひな型においても、固定資産として計上されるリース資産に関する記載を加え、記載上の注意において、決算期と適用時期の関係から同基準を適用していない場合の記載例や注記等についても掲示した(ひな型38頁参照)。
このように固定資産の減価償却の方法としてリース取引の処理方法が記載されることから、2-4.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項から、リース取引の処理方法に関する記載例を削除した(ひな型39頁参照)。ただし、財務諸表等規則の適用対象とはならない中小企業等において賃貸借処理が認められることを念頭に、記載上の注意において、リース取引の処理方法についての記載例を示した(ひな型40頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型60、61、62頁参照)。
(3)リースにより使用する固定資産に関する注記(ひな型45頁参照)
この注記は、旧商法施行規則以来の会社法独自の観点からの注記であり、賃貸借処理された場合のリースにより使用する固定資産に関するものである。
上記のようにリース会計基準の改正により、原則は売買処理とされたものの、適用期日の関係から、引き続き賃貸借処理が認められる場合や、財務諸表等規則の適用対象とはならない中小企業等において賃貸借処理が認められることを念頭に、記載例としては、従来のものを維持し、記載上の注意において、上記の趣旨を加筆した(ひな型45頁参照)。
(4)関連当事者との取引に関する注記(ひな型47~50頁参照)
平成18年10月17日に「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び同適用指針が公表された(これに伴い、財務諸表等規則8条の10の改正も行われた)ため、この改正に対応して、会社計算規則140条4項の「関連当事者」の範囲を拡大する改正が行われた(図参照)。そこで、ひな型においても、関連当事者の範囲について、「当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者」「従業員のための企業年金基金(計算書類作成会社と掛金の拠出を除く重要な取引を行う場合に限る。)」の2項目を追加するとともに、所要の修正を行った(ひな型50頁参照)。
また、会社計算規則140条1項本文括弧書の追加により、関連当事者取引に、会社と関連当事者との間のいわゆる間接取引も含まれることが明確化されたことに伴い、記載上の注意として「(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)」を加えた(ひな型49頁参照)。
(おばた・よしはる)
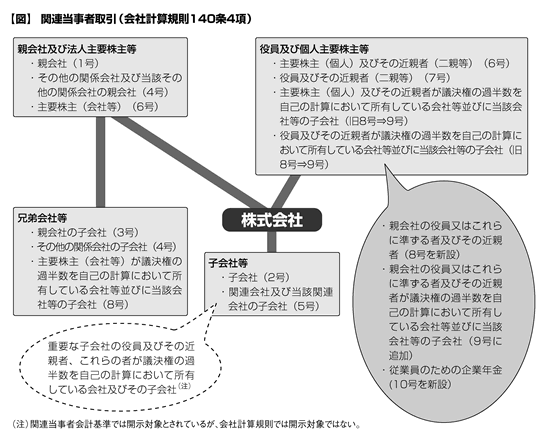
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(2)計算書類
(社)日本経済団体連合会経済第二本部経済法制グループ長 小畑良晴
Ⅲ 計算書類
1 貸借対照表 貸借対照表の記載において、「リース取引」並びに「たな卸資産」に関して、以下の改訂を行った。
(1)リース会計基準の適用(ひな型33~34頁参照)
平成19年3月30日の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の改正(これに伴い、財務諸表等規則8条の6等の改正も行われた)により、それまで賃貸借処理が原則であった所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として通常の売買取引に準じた会計処理が行われることになったことから、会社計算規則106条及び107条が改正された。
これを踏まえ、ファイナンス・リースの借主側の場合は、貸借対照表の資産の部にリース資産を、負債の部にリース債務を計上することとした(ひな型33頁参照)。貸主側の場合については、記載上の注意において、リース債権、リース投資資産として表示することを明記した(ひな型34頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型54、55頁参照)。
(2)棚卸資産に係るものの区分表示(ひな型33~34頁参照)
貸借対照表の流動資産に属する資産のうち、棚卸資産に係るものの区分表示について、従来は、「製品」「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」を掲げてきたが、四半期開示の区分が5区分(商品、製品、半製品、原材料、仕掛品)から3区分(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)に簡素化されたことに合わせて財務諸表等規則17条1項(及び連結財務諸表規則23条1項)の改正(平成20年内閣府令第50号)が行われた(2008年8月7日公布)ことを踏まえ、ひな型においても、それと同様に「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の3区分に改めた。
なお、改正府令では、3区分に属する資産についてそれぞれの科目に属する金額を注記することによって、「たな卸資産の科目をもって一括して掲記」することも認めていることから(財務諸表等規則17条3項等)、ひな型においても、「棚卸資産」として一括表示し、その内訳を示す科目及び金額を注記することも考えられる旨、記載上の注意として追加した(ひな型34頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型54、55頁参照)。
2 個別注記表
(1)資産の評価基準及び評価方法(ひな型37~38頁参照)
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」は、企業会計基準委員会から、2006年7月5日に公表されたものである。本基準では、国際的な会計基準との調和等の観点から、棚卸資産を通常の販売目的で保有する棚卸資産とトレーディング目的で保有する棚卸資産に区分し、前者については、収益性の低下による簿価引下げという考え方に基づく評価基準を定め、後者については、金融商品に関する会計基準における売買目的有価証券に関する会計処理に準じた取扱いとすることを定めている。その適用は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からであったことから、平成21年6月総会における計算書類から本格的に適用されることとなる。
そこで、ひな型では、従来、本基準の早期適用を念頭に記載上の注意として掲げていたものを記載例として位置付けた(ひな型37頁参照)。もっとも、12月決算会社等適用開始時期が遅れる場合もあることから、ひな型では、従来の記載例も記載上の注意の中に残した(ひな型38頁参照)。
なお、企業会計基準委員会は、平成20年9月26日に、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を改正し、棚卸資産の評価方法を個別法・先入先出法・平均原価法(移動平均法または総平均法)・売価還元法の4つに定め(第6-2項)、会計基準の国際的なコンバージェンスを図るため、選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法を削除することとしたが(第34-12項)、これは、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用される(早期適用可)ことから、今回のひな型においては特段の対応は行っていない。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型60頁参照)。
(2)固定資産の減価償却の方法(ひな型38頁参照)
平成19年3月30日の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の改正(これに伴い、財務諸表等規則8条の6等の改正も行われた)により、それまで賃貸借処理が原則であった所有権移転外ファイナンス・リース取引に関し、原則として通常の売買取引に準じた会計処理が行われることになった。同基準において、ファイナンス・リースの借主側では、貸借対照表の資産の部にリース資産を計上することとされ、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定することとされた。この改正を踏まえ、ひな型においても、固定資産として計上されるリース資産に関する記載を加え、記載上の注意において、決算期と適用時期の関係から同基準を適用していない場合の記載例や注記等についても掲示した(ひな型38頁参照)。
このように固定資産の減価償却の方法としてリース取引の処理方法が記載されることから、2-4.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項から、リース取引の処理方法に関する記載例を削除した(ひな型39頁参照)。ただし、財務諸表等規則の適用対象とはならない中小企業等において賃貸借処理が認められることを念頭に、記載上の注意において、リース取引の処理方法についての記載例を示した(ひな型40頁参照)。
なお、連結計算書類においても、同趣旨の改訂を行った(ひな型60、61、62頁参照)。
(3)リースにより使用する固定資産に関する注記(ひな型45頁参照)
この注記は、旧商法施行規則以来の会社法独自の観点からの注記であり、賃貸借処理された場合のリースにより使用する固定資産に関するものである。
上記のようにリース会計基準の改正により、原則は売買処理とされたものの、適用期日の関係から、引き続き賃貸借処理が認められる場合や、財務諸表等規則の適用対象とはならない中小企業等において賃貸借処理が認められることを念頭に、記載例としては、従来のものを維持し、記載上の注意において、上記の趣旨を加筆した(ひな型45頁参照)。
(4)関連当事者との取引に関する注記(ひな型47~50頁参照)
平成18年10月17日に「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び同適用指針が公表された(これに伴い、財務諸表等規則8条の10の改正も行われた)ため、この改正に対応して、会社計算規則140条4項の「関連当事者」の範囲を拡大する改正が行われた(図参照)。そこで、ひな型においても、関連当事者の範囲について、「当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者」「従業員のための企業年金基金(計算書類作成会社と掛金の拠出を除く重要な取引を行う場合に限る。)」の2項目を追加するとともに、所要の修正を行った(ひな型50頁参照)。
また、会社計算規則140条1項本文括弧書の追加により、関連当事者取引に、会社と関連当事者との間のいわゆる間接取引も含まれることが明確化されたことに伴い、記載上の注意として「(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)」を加えた(ひな型49頁参照)。
(おばた・よしはる)
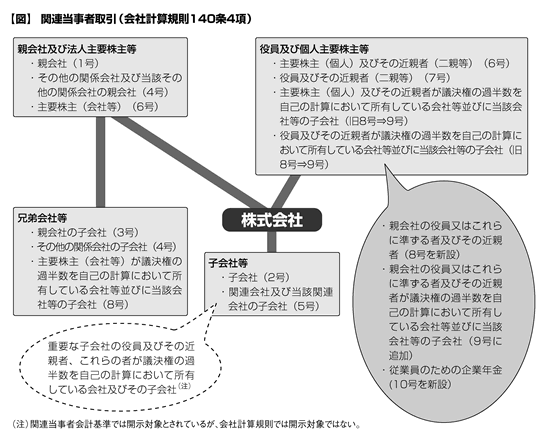
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















