解説記事2010年01月11日 【会社法関連解説】 国際会計基準(IFRS)の任意適用に関する会社計算規則の改正の要点(2010年1月11日号・№337)
解説
国際会計基準(IFRS)の任意適用に関する会社計算規則の改正の要点
法務省民事局付 黒田 裕
Ⅰ.はじめに
会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年法務省令第46号。以下「本省令」という)が平成21年12月11日に公布、施行された。
本省令は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号。以下「計算規則」という)の一部を改正するものであるが、本省令による改正前の計算規則(以下「旧計算規則」という)120条1項では、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という)において、米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法(平成17年法律第86号)上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた。
今般、連結財務諸表規則において、所定の要件を満たす企業が提出する平成22年3月期以降の連結財務諸表を国際会計基準(International Financial Reporting Standards,IFRS.以下「国際会計基準」という)に従って作成することを許容するための改正が行われることとなった(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号。以下「改正府令」という)による)。
本省令は、会社法の委任を受けた計算規則を改正し、平成22年3月期以降、国際会計基準によって連結財務諸表を作成することが許容される株式会社について、連結財務諸表と同様に、連結計算書類を国際会計基準に従って作成することを認めることとするものである。
Ⅱ.改正の概要
1.連結計算書類の規定の整備 本省令による改正後の計算規則(以下「新計算規則」という)61条においては、連結計算書類の会社法上の位置付けを明確化するための法制的な整備を行っている。
具体的には、連結計算書類は会社法444条1項の規定に基づき作成されるものであるところ、計算規則61条はこの内容を定めている。
新計算規則61条1号では、日本基準に従って作成される連結計算書類、すなわち、①連結貸借対照表、②連結損益計算書、③連結株主資本等変動計算書および④連結注記表を規定している一方、同条2号では、指定国際会計基準(後述2参照)に従って作成されるものも連結計算書類に該当する旨を明確にしており、その具体的な内容は新計算規則120条の規定に委ねることとしている。
2.連結計算書類の作成にあたっての国際会計基準の任意適用について 新計算規則120条1項前段では、連結財務諸表規則によって指定国際会計基準に従って連結財務諸表を作成することが許容される株式会社は、連結計算書類についても指定国際会計基準に従って作成することが許容される旨を定めている。
これは、旧計算規則120条1項前段と同じく、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づく連結財務諸表を指定国際会計基準に従って作成・提出する株式会社に対して日本基準で連結計算書類を作成することを義務付けることは、いたずらに会社の負担を増大するものであり適当ではなく、また、株主に対する情報開示の充実という連結計算書類の制度趣旨は、連結財務諸表を指定国際会計基準に従って作成・提出する株式会社にあっては、指定国際会計基準によって作成した連結計算書類であっても達成することができるといえることから、連結財務諸表規則における取扱いとの平仄を合わせ、連結財務諸表と同様の取扱いを許容することとしたものである。
ここで、指定国際会計基準とは、連結財務諸表規則93条に規定する指定国際会計基準をいうものとしている。
このような規定の仕方をしているのは、国際会計基準が、国際財務報告基準書(IFRS)、国際会計基準書(IAS)、IFRIC解釈指針(IFRIC)および旧解釈指針委員会(SIC)による解釈指針(SIC)から構成されており、それらは今後も改廃があり得るものであるところ、計算規則において連結財務諸表規則とは別個にそれらを逐一特定することの実益が乏しいというだけでなく、計算規則における「国際会計基準」と連結財務諸表規則における「国際会計基準」を完全に一致させる必要があるからである。
なお、新計算規則においては、旧計算規則で用いられていた「用語、様式及び作成方法」という文言を用いずに、単に「指定国際会計基準に従って作成することができる」と規定している。
これは、国際会計基準では、詳細な数値基準等を定めずに原理原則のみを定めるといういわゆるプリンシプル・ベース(原則主義)を採用しており、日本基準や米国基準と異なり、財務報告についての具体的な様式が定められているわけではないことによるものである。
3.指定国際会計基準に従って作成する場合の連結計算書類
(1)作成すべき連結計算書類(新計算規則61条2号、120条1項)
指定国際会計基準では、①財政状態計算書、②包括利益計算書、③持分変動計算書、④キャッシュ・フロー計算書および⑤注記の作成が必要とされていることから、同会計基準に厳密に従って連結計算書類を作成する場合には、これらをすべて作成することとなる(新計算規則61条2号、120条1項)。
もっとも、同規則120条1項後段において、同規則第3編第1章~第5章の規定により作成される同規則61条1号の連結計算書類に表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項については省略することが認められているから、連結貸借対照表(同号イ)に相当する①財政状態計算書、連結損益計算書(同号ロ)に相当する②包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書(同号ハ)に相当する③持分変動計算書および連結注記表(同号ニ)に相当する⑤注記を作成すれば足りる。
また、これらの各書類に記載されるべき内容についても、連結計算書類の作成会社の事務負担の軽減および注記事項等の簡略化のため、同規則120条1項後段により、同規則第1章~第5章の規定において要求される事項でない事項の全部または一部の記載を省略することができる。
(2)指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成した場合の注記(新計算規則120条2項および3項)
新計算規則120条2項および3項は、指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成する場合の当該連結計算書類に必要となる注記を定めている。
すなわち、同条1項後段の規定により省略した事項がないときは、連結計算書類は指定国際会計基準に完全に従っているといえることから、当該連結計算書類が指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨(同条2項)を、同条1項後段の規定により省略した事項があるときは、連結計算書類の作成根拠となる条文は同項前段および後段を含む同項全体であることおよび同項後段の規定によって省略した事項があることを具体的に明らかにすべきことから、当該連結計算書類が同項の規定により作成した連結計算書類である旨および同項後段の規定により省略した事項がある旨(同条3項)を、それぞれ注記することが必要となる。
なお、同規則120条1項後段の規定により省略した事項がある旨の注記(同条3項)は、省略した事項を項目ごとに個別に列挙する必要はなく、同条1項後段の規定により省略した事項がある旨を表示すれば足りる。
(3)国際会計基準の初度適用に際しての直近の連結計算書類の表示に関する取扱い 国際会計基準においては、初めて国際会計基準によって財務報告を作成する場合(初度適用)の財務報告については、当該事業年度に係る財務報告に加えて、国際会計基準に従ってそれぞれ作成された前期の財務報告および前期の開始時点の財政状態計算書の開示が要求されている(IFRS1号)。
しかし、会社法上の連結計算書類は、国際会計基準における財務報告と同等レベルの開示をさせることを目的とするものではないことから、計算規則においては国際会計基準の初度適用の際の取扱いに関する規定を設けないこととしている。
ここで、会社法上作成される連結計算書類は、各事業年度に係るものとして作成されることから(会社法444条1項)、指定国際会計基準の初度適用に際しても当期に係る連結計算書類のみを作成すれば足り、前期の連結計算書類および前期の開始時点の財政状態計算書を指定国際会計基準に従って開示することを要しない。
Ⅲ.経過措置
本省令附則2条において、新計算規則の規定に基づき指定国際会計基準により作成することができる連結計算書類は、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係るものとしており、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることとしている。
また、同附則3条において、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則3項または改正府令附則2条2項もしくは3項の規定により、連結財務諸表の用語、様式および作成方法について米国基準によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類(旧計算規則120条1項参照)については、米国基準の用語、様式および作成方法によることができることとしている。
連結財務諸表については、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで米国基準によることができるとされていることから、連結計算書類についても同日までに終了する連結会計年度に係るものまで米国基準によることができる。
経過措置の適用関係をまとめると、表のとおりとなる。(くろだ・ゆたか)
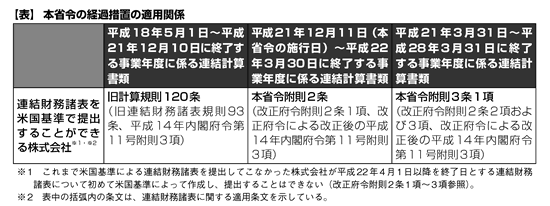
国際会計基準(IFRS)の任意適用に関する会社計算規則の改正の要点
法務省民事局付 黒田 裕
Ⅰ.はじめに
会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年法務省令第46号。以下「本省令」という)が平成21年12月11日に公布、施行された。
本省令は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号。以下「計算規則」という)の一部を改正するものであるが、本省令による改正前の計算規則(以下「旧計算規則」という)120条1項では、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という)において、米国基準によって連結財務諸表を作成することが許容されている株式会社について、会社法(平成17年法律第86号)上の連結計算書類についても米国基準によって作成することが許容されていた。
今般、連結財務諸表規則において、所定の要件を満たす企業が提出する平成22年3月期以降の連結財務諸表を国際会計基準(International Financial Reporting Standards,IFRS.以下「国際会計基準」という)に従って作成することを許容するための改正が行われることとなった(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号。以下「改正府令」という)による)。
本省令は、会社法の委任を受けた計算規則を改正し、平成22年3月期以降、国際会計基準によって連結財務諸表を作成することが許容される株式会社について、連結財務諸表と同様に、連結計算書類を国際会計基準に従って作成することを認めることとするものである。
Ⅱ.改正の概要
1.連結計算書類の規定の整備 本省令による改正後の計算規則(以下「新計算規則」という)61条においては、連結計算書類の会社法上の位置付けを明確化するための法制的な整備を行っている。
具体的には、連結計算書類は会社法444条1項の規定に基づき作成されるものであるところ、計算規則61条はこの内容を定めている。
新計算規則61条1号では、日本基準に従って作成される連結計算書類、すなわち、①連結貸借対照表、②連結損益計算書、③連結株主資本等変動計算書および④連結注記表を規定している一方、同条2号では、指定国際会計基準(後述2参照)に従って作成されるものも連結計算書類に該当する旨を明確にしており、その具体的な内容は新計算規則120条の規定に委ねることとしている。
2.連結計算書類の作成にあたっての国際会計基準の任意適用について 新計算規則120条1項前段では、連結財務諸表規則によって指定国際会計基準に従って連結財務諸表を作成することが許容される株式会社は、連結計算書類についても指定国際会計基準に従って作成することが許容される旨を定めている。
これは、旧計算規則120条1項前段と同じく、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に基づく連結財務諸表を指定国際会計基準に従って作成・提出する株式会社に対して日本基準で連結計算書類を作成することを義務付けることは、いたずらに会社の負担を増大するものであり適当ではなく、また、株主に対する情報開示の充実という連結計算書類の制度趣旨は、連結財務諸表を指定国際会計基準に従って作成・提出する株式会社にあっては、指定国際会計基準によって作成した連結計算書類であっても達成することができるといえることから、連結財務諸表規則における取扱いとの平仄を合わせ、連結財務諸表と同様の取扱いを許容することとしたものである。
ここで、指定国際会計基準とは、連結財務諸表規則93条に規定する指定国際会計基準をいうものとしている。
このような規定の仕方をしているのは、国際会計基準が、国際財務報告基準書(IFRS)、国際会計基準書(IAS)、IFRIC解釈指針(IFRIC)および旧解釈指針委員会(SIC)による解釈指針(SIC)から構成されており、それらは今後も改廃があり得るものであるところ、計算規則において連結財務諸表規則とは別個にそれらを逐一特定することの実益が乏しいというだけでなく、計算規則における「国際会計基準」と連結財務諸表規則における「国際会計基準」を完全に一致させる必要があるからである。
なお、新計算規則においては、旧計算規則で用いられていた「用語、様式及び作成方法」という文言を用いずに、単に「指定国際会計基準に従って作成することができる」と規定している。
これは、国際会計基準では、詳細な数値基準等を定めずに原理原則のみを定めるといういわゆるプリンシプル・ベース(原則主義)を採用しており、日本基準や米国基準と異なり、財務報告についての具体的な様式が定められているわけではないことによるものである。
3.指定国際会計基準に従って作成する場合の連結計算書類
(1)作成すべき連結計算書類(新計算規則61条2号、120条1項)
指定国際会計基準では、①財政状態計算書、②包括利益計算書、③持分変動計算書、④キャッシュ・フロー計算書および⑤注記の作成が必要とされていることから、同会計基準に厳密に従って連結計算書類を作成する場合には、これらをすべて作成することとなる(新計算規則61条2号、120条1項)。
もっとも、同規則120条1項後段において、同規則第3編第1章~第5章の規定により作成される同規則61条1号の連結計算書類に表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項については省略することが認められているから、連結貸借対照表(同号イ)に相当する①財政状態計算書、連結損益計算書(同号ロ)に相当する②包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書(同号ハ)に相当する③持分変動計算書および連結注記表(同号ニ)に相当する⑤注記を作成すれば足りる。
また、これらの各書類に記載されるべき内容についても、連結計算書類の作成会社の事務負担の軽減および注記事項等の簡略化のため、同規則120条1項後段により、同規則第1章~第5章の規定において要求される事項でない事項の全部または一部の記載を省略することができる。
(2)指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成した場合の注記(新計算規則120条2項および3項)
新計算規則120条2項および3項は、指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成する場合の当該連結計算書類に必要となる注記を定めている。
すなわち、同条1項後段の規定により省略した事項がないときは、連結計算書類は指定国際会計基準に完全に従っているといえることから、当該連結計算書類が指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨(同条2項)を、同条1項後段の規定により省略した事項があるときは、連結計算書類の作成根拠となる条文は同項前段および後段を含む同項全体であることおよび同項後段の規定によって省略した事項があることを具体的に明らかにすべきことから、当該連結計算書類が同項の規定により作成した連結計算書類である旨および同項後段の規定により省略した事項がある旨(同条3項)を、それぞれ注記することが必要となる。
なお、同規則120条1項後段の規定により省略した事項がある旨の注記(同条3項)は、省略した事項を項目ごとに個別に列挙する必要はなく、同条1項後段の規定により省略した事項がある旨を表示すれば足りる。
(3)国際会計基準の初度適用に際しての直近の連結計算書類の表示に関する取扱い 国際会計基準においては、初めて国際会計基準によって財務報告を作成する場合(初度適用)の財務報告については、当該事業年度に係る財務報告に加えて、国際会計基準に従ってそれぞれ作成された前期の財務報告および前期の開始時点の財政状態計算書の開示が要求されている(IFRS1号)。
しかし、会社法上の連結計算書類は、国際会計基準における財務報告と同等レベルの開示をさせることを目的とするものではないことから、計算規則においては国際会計基準の初度適用の際の取扱いに関する規定を設けないこととしている。
ここで、会社法上作成される連結計算書類は、各事業年度に係るものとして作成されることから(会社法444条1項)、指定国際会計基準の初度適用に際しても当期に係る連結計算書類のみを作成すれば足り、前期の連結計算書類および前期の開始時点の財政状態計算書を指定国際会計基準に従って開示することを要しない。
Ⅲ.経過措置
本省令附則2条において、新計算規則の規定に基づき指定国際会計基準により作成することができる連結計算書類は、平成22年3月31日以後に終了する連結会計年度に係るものとしており、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることとしている。
また、同附則3条において、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則3項または改正府令附則2条2項もしくは3項の規定により、連結財務諸表の用語、様式および作成方法について米国基準によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類(旧計算規則120条1項参照)については、米国基準の用語、様式および作成方法によることができることとしている。
連結財務諸表については、平成28年3月31日までに終了する連結会計年度に係るものまで米国基準によることができるとされていることから、連結計算書類についても同日までに終了する連結会計年度に係るものまで米国基準によることができる。
経過措置の適用関係をまとめると、表のとおりとなる。(くろだ・ゆたか)
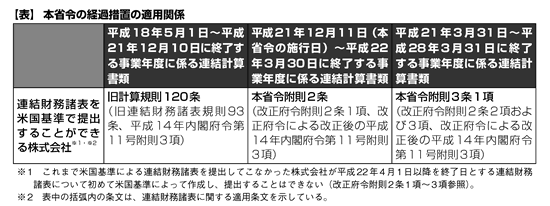
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















