解説記事2010年10月25日 【巻頭特集】 売買審査案件にみる最近のインサイダー取引の傾向(2010年10月25日号・№375)
近時の調査・審査件数、開示項目別の動向は?
売買審査案件にみる最近のインサイダー取引の傾向
東京証券取引所自主規制法人COMLEC(売買審査部)チーフコンプライアンスアドバイザー 栗田伸明 本誌ではインサイダー取引を巡る証券界を挙げての取組みについて、関係組織・発行会社における対応を踏まえながら、主に市場を開設する取引所の立場から継続してお伝えしているところである(吉松和彦「インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応」本誌306号4頁、栗田伸明「インサイダー取引に係る未然防止の取組みの現状」326号4頁参照)。本稿では、恒例の開催となった「上場会社コンプライアンス・フォーラム」での識者・市場関係者の指摘を踏まえ、最近の動向をご紹介いただく。 (編集部)
Ⅰ はじめに
東京証券取引所自主規制法人(以下「当法人」という)は、東証市場を運営する株式会社東京証券取引所から業務委託を受けて、売買審査業務を行っている。当該売買審査は、東証市場において行われる売買について相場操縦やインサイダー取引等の不公正取引またはそのおそれのある取引を発見し、これらに関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ、もって不公正取引の防止を図ること等を目的としている。
また、東証Rコンプライアンス研修センター(東証COMLEC(コムレック))(Compliance Learning Center)は、インサイダー取引を題材として8月30日(東京・文京シビックホール)および9月10日(大阪・松下IMPホール)、「上場会社コンプライアンス・フォーラム」(以下「フォーラム」という)を開催した。
本稿では、フォーラムでの有識者の発言も踏まえつつ、最近の売買審査案件から読み取れるインサイダー取引の傾向等を紹介することとする。なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 東証COMLECの活動と「上場会社コンプライアンス・フォーラム」の開催
東証COMLECは、上場会社や証券会社を始めとする市場関係者のコンプライアンス支援をより一層強化するための専門機関である。その活動は、①定期的なセミナー等の開催、専門講師の上場各社等の社内研修への派遣、②eラーニングを通じた学習環境の提供、③各種刊行物を通じたコンプライアンス関連情報の提供を三つの大きな柱としている。
本年は特に、企業担当者の利用できるコンテンツを提供することに注力しており、内部者取引防止規程事例集、取引相談FAQ、インサイダー取引防止のためのポスター作成および研修資料の作成等を行ってきた。
例年、上場会社を中心とした市場参加者の出席を募って大規模なフォーラムも開催しており、本年の東京・大阪のフォーラムでは、証券取引等監視委員会、有識者および当法人による講演を行った。今後、名古屋(11月24日)、札幌(12月1日)および福岡(12月8日)で同様のフォーラムを開催予定である。
Ⅲ 東京証券取引所自主規制法人の行う売買審査
株券等の現物市場における不公正取引に関する売買審査は、売買審査部が行っている。売買審査は、相場操縦およびインサイダー取引を中心に、その両方に関わる取引、さらには、偽計、風説の流布等についても行われている。当法人は、自主規制機関として東証市場の公正性・信頼性を担保していく観点から、極めて多くの事案を幅広く網羅的にチェック対象として抽出し、必要なものについては深度ある審査を行うことで、きめ細かい売買審査を行っている。
売買審査の流れとしては、株価・売買高等の動向および取引参加者である証券会社の売買手口等に関して初動的な分析を行う「調査」、その次のステップとして、委託者の属性、売買執行状況等についてさらに掘り下げて詳細な分析を行う「審査」の2段階で行われる。
調査銘柄への抽出にあたっては、相場操縦の観点からは、主に、株価や売買高等の動向に不自然な形態として認められる取引のシステムによる自動抽出、マーケット部門などの関連部署からの情報提供を端緒とし、また、インサイダー取引の観点からは、法令上の重要事実の開示を端緒とし、不自然な形態や疑わしい取引を抽出して調査を行うこととなる。そのほか、ホームページの情報受付窓口または電話等による外部からの情報提供やインターネット・雑誌等の情報も調査の端緒として有効に活用している。
「調査」においては、株価・売買高の推移、売買手口の偏向性の有無の分析を行い、必要に応じて証券会社に対して委託者に関するヒアリングを行う。インサイダー取引の調査においては、上場会社に対して会社情報の公表に至る経緯等を照会し、こうした情報も極めて重要な情報として調査を進める。併せて、一定期間の売買について、証券会社に対してその売買記録を「売買状況報告書」として提出を求め、売買データの集計・分析を行う。
このような調査の結果、より詳細な分析が必要と判断された事案については、審査銘柄として抽出し、証券会社に対し注文の受託・執行に関する経緯や委託者の詳細な情報(職業、口座開設日、取引内容、発行会社との関係等)に関する照会を行うなどしてより詳しい「審査」を行い、これらの情報を総合的に分析して、不公正取引またはそのおそれのある取引がないか判断を行う。
平成21年度においては、インサイダー取引について「調査」の対象となった案件が約6,700件、「調査」の結果、より深度がある詳細な分析を行った「審査」の対象となった案件が178件あった(表1参照)。
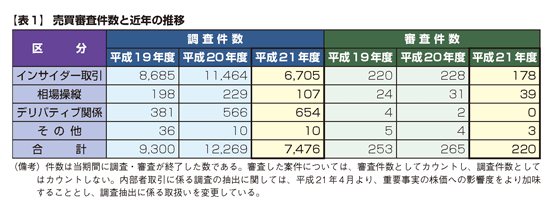
なお、売買審査の結果についてはすべて証券取引等監視委員会に報告し、こうした連携によって、不公正取引の摘発等の証券取引等監視委員会における市場監視活動をサポートしている。
Ⅳ 売買審査案件にみるインサイダー取引の傾向
インサイダー取引における売買審査案件を上場会社の開示項目別に表にしたのが、表2である。
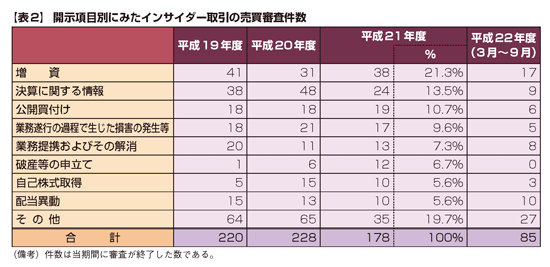
平成21年度の審査案件のうち、最多の案件は増資に係る案件である。普通株式の発行に係る案件の26件(14.6%)に、普通株式以外の株式、新株予約権、新株予約権付社債の発行および自己株式の処分の案件を加えると、合計で38件(21.3%)となる。
次に多いのが決算に係る情報の案件で、24件(13.5%)あった。3番目に多いのは公開買付けに係る案件で、19件(10.7%)あった。ここまでが、全体の10%を超えるものとなっており、それに続く5%超の案件としては、業務遂行の過程で生じた損害の発生等(いわゆる特損)(17件、9.6%)、業務提携およびその解消(13件、7.3%)、破産等の申立て(民事再生法、会社更生法等の申立ても含む)(12件、6.7%)、自己株式の取得および配当の異動(各10件、5.6%)に係る案件がある。
これら案件数上位の開示情報から明らかなのは、当該情報が公表された後の株価への影響が特に容易に推測できることである。株価の上昇または下落がより確実なものであればあるほど、インサイダー取引を行う動機付けが高いと考えられる。このような案件を含めインサイダー取引を未然に防止するためには、①業務上必要のない者への重要事実の伝達を行わない、②重要事実の社内での取扱い方法を定め、情報の伝達がトレースできるようにしておく、③社内教育を徹底するなどの方策が重要であろう。
役職員のインサイダー取引を防止するにあたってのより包括的・一般的な留意点としては、表3のようなものが挙げられる。
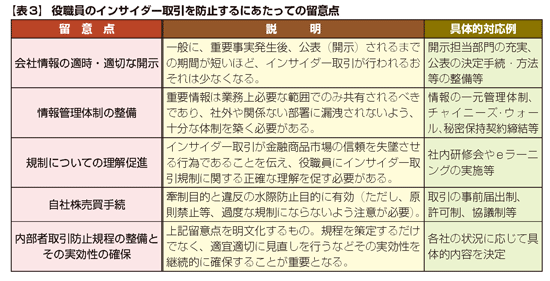
特に、役職員がどのように行動すればインサイダー取引に関与せずにすむのか、内部者取引防止規程を設け、そのなかで、情報の取扱いの方法および自社株式売買の際の手続等を具体的にわかりやすく明示することが重要である。
なお、それらの規程の整備等の際には、平成21年2月に実施した「第二回全国上場会社内部者取引管理アンケート」や、東証COMLECが同アンケート実施の際に任意に提出いただいた東京証券取引所に上場する348社の内部者取引防止規程を元に作成した「内部者取引防止規程事例集」等が参考になると思われる。
ここまで一般的な形で述べてきたが、以下では特に留意すべき点のあるいくつかの開示項目について述べておきたい。
1.公開買付け フォーラムの講演で証券取引等監視委員会も触れているが、公開買付けについては、インサイダー取引のリスクを高める三つの特徴があるといえる。その特徴とは、他の開示項目に比べ、①準備期間が長い、②関係者が多い、③価格決定の際にプレミアムが課され、株価の上昇が確実に見込まれるケースが多いということである。
インサイダー取引の売買審査を行う場合には、上場会社に対して「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」(以下「経緯報告書」という)の作成を依頼する場合がある。経緯報告書は、会社情報の発生の経緯から公表にまで至る経緯を時系列で一覧表方式にまとめた報告書であり、その添付書類として、各々の段階で関与した関係者の一覧も含まれている。
なお、上場会社においては、経緯報告書の依頼があった場合に、円滑に当経緯報告書が作成できるような管理体制を事前に構築していただき、インサイダー取引の審査を行ううえで非常に重要な資料となる同報告書の提出に速やかにご協力いただくことを切にお願いしたい。また、重要な情報に接する機会のある関係者に対し、将来、経緯報告書を作成・提出する可能性があることをあらかじめ周知すること等は、情報管理の徹底やインサイダー取引の未然防止の観点から有益と考えられる。
提出された経緯報告書をみると、上記のインサイダー取引のリスクを高める三つの特徴は顕著である。開示項目によっては、重要事実が発生してすぐに開示される場合もあるが、公開買付けの場合には、大半が2~3か月以上の準備期間を要しているし、公開買付けを行う側とされる側で、デューデリジェンスを行うなど様々なプロセスを経ることから、関係者の一覧に掲載される人数も多数に及んでいる。
上場会社のみならず市場関係者においては、公開買付けに関わる場合に、これらの特徴を十分理解し、インサイダー取引が行われないよう情報管理を徹底し、慎重にプロセスを進めていく必要がある。
なお、証券取引等監視委員会のホームページには、証券取引等監視委員会が本年7月に市場参加者向けに行ったセミナーの資料が掲示されている。こちらについても是非参考とされたい(証券取引等監視委員会ホームページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/torikumi/torikumi.htm(平成22年7月15日付講演資料)参照)。
2.破産等の申立て 破産等の申立ての案件の増加は、平成20年度および21年度の傾向としてみられるが、この背景にはわが国の経済情勢による影響が大きいと考えられる。
破産等の申立ての案件に関連して2点ほど留意点が考えられる。一つは損失回避もインサイダー取引となること、もう一つは教育の重要性である。
まず前者について触れると、一般的な感覚として、一般投資家が知らないインサイダー情報を利用して「儲ける」のは悪いことだ、不公平だと感じられはしても、損失回避については「儲けているわけではないので問題ないのではないか」と東証COMLECとして問合せを受ける場合がある。
これに関連して、よく受ける質問を紹介すると、①買い付けただけで売っていないため利益を実現していない、②売買の株数が少ないため獲得した利益が僅少である、③売買の結果損失が発生した、④株価が上がり(下がり)そうな情報に基づき売った(買った)といった場合についてもインサイダー取引となるかという問合せを受けることがあるが、前述した損失回避を含め、いずれのケースでも未公表の重要事実を知っていれば、当然にインサイダー取引となることにご留意いただきたい。
不正確な理解のためにインサイダー取引を起こすことを回避するためには、もう一つのポイントとして指摘した日頃からの教育が重要である。特に、破産等の申立ては、通常、結果として上場廃止となるため、株価の急落につながることから、たとえば、当該申立てを実施する会社に勤めている場合、未公表時にその情報を知ってしまったら、自社株売却のインセンティブが特に強く働くケースであると思われる。
しかしながら、インサイダー取引規制に対する正確な理解と、インサイダー取引が発覚することによる勤務先や本人への悪影響を認識していれば、売却を踏みとどまる十分な効果が得られると考えられる。
3.増資 増資については、通常のインサイダー取引の審査に加え、不適切な第三者割当への対応も行っている。
第三者割当の事前相談においては、開示に係る規則等に基づく審査を実施する上場管理部、上場会社の開示サポートを担う東京証券取引所上場部および不公正取引の監視を実施する売買審査部が、証券取引等監視委員会等の外部機関を含め、不適切な第三者割当について適時適切に情報共有し、その未然防止に向けて連携して取り組んでいる(上場管理部において公表した事前相談事例等について、今号32頁参照)。
4.情報受領者によるインサイダー取引 情報受領者によるインサイダー取引についてもフォーラムにおける証券取引等監視委員会の講演で触れられているが、近年重要事実を知った会社関係者から当該重要事実について伝達を受けた情報受領者によるインサイダー取引が増加傾向にある。
インサイダー取引については、証券会社、証券取引所および証券取引等監視委員会が、それぞれ連携しつつ、各々の立場から調査・審査を行っており、情報受領者のように上場会社と直接の関係がない者であってもその調査・審査から逃れられないことを十分にご理解いただき、不用意に情報受領者を増やさないよう情報管理を徹底することが肝要である。
Ⅴ J-IRISSへの登録
2009年5月から、日本証券業協会の自主規制ルールである内部者登録制度の実効性を高め、上場会社役職員の内部者取引規制違反を未然に防止することを目的として、上場会社役員情報に係るデータベース「J-IRISS(Japan-Insider Registration & Identification Support System:ジェイ・アイリス)」が稼動している(詳細については、日本証券業協会ホームページhttp://www.jsda.or.jp/html/j-iriss/index.html(J-IRISS)参照)。
これは、証券会社が注文を受託した際に当該委託者が内部者取引規制上の会社関係者に該当しないかどうかを確認するため、証券会社が保有する顧客情報と、上場会社が当該システムに登録した自社役員等の氏名・住所等の情報をマッチング・確認するものである。
J-IRISSが活用されることにより、証券会社における内部者登録の実効性向上はもとより、上場会社においても、たとえば、社内の総務・法務担当等ではチェックできなかった役職員によるインサイダー取引を証券会社での発注時に水際で防ぐことが可能となるほか、役員本人の立場からみても、自らの情報がJ-IRISSに登録されていることを自覚することでインサイダー取引に注意する動機付けとなるなどの効果が期待され、さらには、特定有価証券等の売買等の報告(金融商品取引法163条)、短期売買利益の返還(同法164条)の法令遵守の面でも副次的な効果が期待される。
公正で投資者に信頼される市場の構築のため、上場会社の自社におけるインサイダー取引未然防止体制の充実に加え、J-IRISSの積極的な活用が期待される。
Ⅵ おわりに
インサイダー取引は、個人や一企業としての問題だけにとどまらず、証券市場に対する投資者からの信頼を著しく損なわせる行為であり、資本主義経済の根幹を揺るがす、決して許されない行為である。
上場会社を始めとする関係者の方々は、証券市場に対する関わり方こそ異なるが、共に証券市場においてインサイダー取引の未然防止のために重要な役割を担う者であると位置付けられる。
今後も当法人は、これらの方々のインサイダー取引の未然防止を含むコンプライアンスを支援すべく、東証COMLEC等を通じて、積極的に取り組んでいきたいと考えている。
売買審査案件にみる最近のインサイダー取引の傾向
東京証券取引所自主規制法人COMLEC(売買審査部)チーフコンプライアンスアドバイザー 栗田伸明 本誌ではインサイダー取引を巡る証券界を挙げての取組みについて、関係組織・発行会社における対応を踏まえながら、主に市場を開設する取引所の立場から継続してお伝えしているところである(吉松和彦「インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応」本誌306号4頁、栗田伸明「インサイダー取引に係る未然防止の取組みの現状」326号4頁参照)。本稿では、恒例の開催となった「上場会社コンプライアンス・フォーラム」での識者・市場関係者の指摘を踏まえ、最近の動向をご紹介いただく。 (編集部)
Ⅰ はじめに
東京証券取引所自主規制法人(以下「当法人」という)は、東証市場を運営する株式会社東京証券取引所から業務委託を受けて、売買審査業務を行っている。当該売買審査は、東証市場において行われる売買について相場操縦やインサイダー取引等の不公正取引またはそのおそれのある取引を発見し、これらに関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ、もって不公正取引の防止を図ること等を目的としている。
また、東証Rコンプライアンス研修センター(東証COMLEC(コムレック))(Compliance Learning Center)は、インサイダー取引を題材として8月30日(東京・文京シビックホール)および9月10日(大阪・松下IMPホール)、「上場会社コンプライアンス・フォーラム」(以下「フォーラム」という)を開催した。
本稿では、フォーラムでの有識者の発言も踏まえつつ、最近の売買審査案件から読み取れるインサイダー取引の傾向等を紹介することとする。なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 東証COMLECの活動と「上場会社コンプライアンス・フォーラム」の開催
東証COMLECは、上場会社や証券会社を始めとする市場関係者のコンプライアンス支援をより一層強化するための専門機関である。その活動は、①定期的なセミナー等の開催、専門講師の上場各社等の社内研修への派遣、②eラーニングを通じた学習環境の提供、③各種刊行物を通じたコンプライアンス関連情報の提供を三つの大きな柱としている。
本年は特に、企業担当者の利用できるコンテンツを提供することに注力しており、内部者取引防止規程事例集、取引相談FAQ、インサイダー取引防止のためのポスター作成および研修資料の作成等を行ってきた。
例年、上場会社を中心とした市場参加者の出席を募って大規模なフォーラムも開催しており、本年の東京・大阪のフォーラムでは、証券取引等監視委員会、有識者および当法人による講演を行った。今後、名古屋(11月24日)、札幌(12月1日)および福岡(12月8日)で同様のフォーラムを開催予定である。
Ⅲ 東京証券取引所自主規制法人の行う売買審査
株券等の現物市場における不公正取引に関する売買審査は、売買審査部が行っている。売買審査は、相場操縦およびインサイダー取引を中心に、その両方に関わる取引、さらには、偽計、風説の流布等についても行われている。当法人は、自主規制機関として東証市場の公正性・信頼性を担保していく観点から、極めて多くの事案を幅広く網羅的にチェック対象として抽出し、必要なものについては深度ある審査を行うことで、きめ細かい売買審査を行っている。
売買審査の流れとしては、株価・売買高等の動向および取引参加者である証券会社の売買手口等に関して初動的な分析を行う「調査」、その次のステップとして、委託者の属性、売買執行状況等についてさらに掘り下げて詳細な分析を行う「審査」の2段階で行われる。
調査銘柄への抽出にあたっては、相場操縦の観点からは、主に、株価や売買高等の動向に不自然な形態として認められる取引のシステムによる自動抽出、マーケット部門などの関連部署からの情報提供を端緒とし、また、インサイダー取引の観点からは、法令上の重要事実の開示を端緒とし、不自然な形態や疑わしい取引を抽出して調査を行うこととなる。そのほか、ホームページの情報受付窓口または電話等による外部からの情報提供やインターネット・雑誌等の情報も調査の端緒として有効に活用している。
「調査」においては、株価・売買高の推移、売買手口の偏向性の有無の分析を行い、必要に応じて証券会社に対して委託者に関するヒアリングを行う。インサイダー取引の調査においては、上場会社に対して会社情報の公表に至る経緯等を照会し、こうした情報も極めて重要な情報として調査を進める。併せて、一定期間の売買について、証券会社に対してその売買記録を「売買状況報告書」として提出を求め、売買データの集計・分析を行う。
このような調査の結果、より詳細な分析が必要と判断された事案については、審査銘柄として抽出し、証券会社に対し注文の受託・執行に関する経緯や委託者の詳細な情報(職業、口座開設日、取引内容、発行会社との関係等)に関する照会を行うなどしてより詳しい「審査」を行い、これらの情報を総合的に分析して、不公正取引またはそのおそれのある取引がないか判断を行う。
平成21年度においては、インサイダー取引について「調査」の対象となった案件が約6,700件、「調査」の結果、より深度がある詳細な分析を行った「審査」の対象となった案件が178件あった(表1参照)。
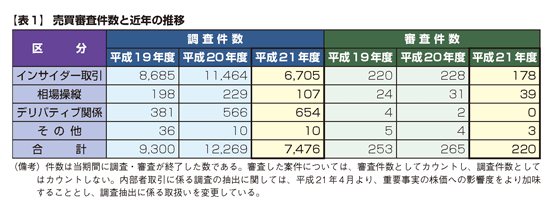
なお、売買審査の結果についてはすべて証券取引等監視委員会に報告し、こうした連携によって、不公正取引の摘発等の証券取引等監視委員会における市場監視活動をサポートしている。
Ⅳ 売買審査案件にみるインサイダー取引の傾向
インサイダー取引における売買審査案件を上場会社の開示項目別に表にしたのが、表2である。
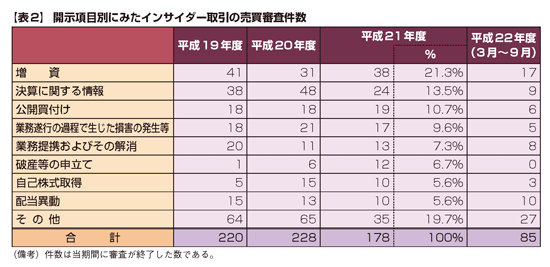
平成21年度の審査案件のうち、最多の案件は増資に係る案件である。普通株式の発行に係る案件の26件(14.6%)に、普通株式以外の株式、新株予約権、新株予約権付社債の発行および自己株式の処分の案件を加えると、合計で38件(21.3%)となる。
次に多いのが決算に係る情報の案件で、24件(13.5%)あった。3番目に多いのは公開買付けに係る案件で、19件(10.7%)あった。ここまでが、全体の10%を超えるものとなっており、それに続く5%超の案件としては、業務遂行の過程で生じた損害の発生等(いわゆる特損)(17件、9.6%)、業務提携およびその解消(13件、7.3%)、破産等の申立て(民事再生法、会社更生法等の申立ても含む)(12件、6.7%)、自己株式の取得および配当の異動(各10件、5.6%)に係る案件がある。
これら案件数上位の開示情報から明らかなのは、当該情報が公表された後の株価への影響が特に容易に推測できることである。株価の上昇または下落がより確実なものであればあるほど、インサイダー取引を行う動機付けが高いと考えられる。このような案件を含めインサイダー取引を未然に防止するためには、①業務上必要のない者への重要事実の伝達を行わない、②重要事実の社内での取扱い方法を定め、情報の伝達がトレースできるようにしておく、③社内教育を徹底するなどの方策が重要であろう。
役職員のインサイダー取引を防止するにあたってのより包括的・一般的な留意点としては、表3のようなものが挙げられる。
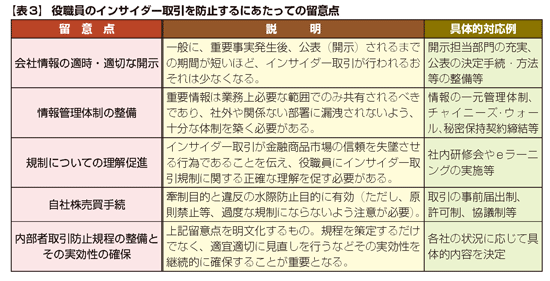
特に、役職員がどのように行動すればインサイダー取引に関与せずにすむのか、内部者取引防止規程を設け、そのなかで、情報の取扱いの方法および自社株式売買の際の手続等を具体的にわかりやすく明示することが重要である。
なお、それらの規程の整備等の際には、平成21年2月に実施した「第二回全国上場会社内部者取引管理アンケート」や、東証COMLECが同アンケート実施の際に任意に提出いただいた東京証券取引所に上場する348社の内部者取引防止規程を元に作成した「内部者取引防止規程事例集」等が参考になると思われる。
ここまで一般的な形で述べてきたが、以下では特に留意すべき点のあるいくつかの開示項目について述べておきたい。
1.公開買付け フォーラムの講演で証券取引等監視委員会も触れているが、公開買付けについては、インサイダー取引のリスクを高める三つの特徴があるといえる。その特徴とは、他の開示項目に比べ、①準備期間が長い、②関係者が多い、③価格決定の際にプレミアムが課され、株価の上昇が確実に見込まれるケースが多いということである。
インサイダー取引の売買審査を行う場合には、上場会社に対して「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」(以下「経緯報告書」という)の作成を依頼する場合がある。経緯報告書は、会社情報の発生の経緯から公表にまで至る経緯を時系列で一覧表方式にまとめた報告書であり、その添付書類として、各々の段階で関与した関係者の一覧も含まれている。
なお、上場会社においては、経緯報告書の依頼があった場合に、円滑に当経緯報告書が作成できるような管理体制を事前に構築していただき、インサイダー取引の審査を行ううえで非常に重要な資料となる同報告書の提出に速やかにご協力いただくことを切にお願いしたい。また、重要な情報に接する機会のある関係者に対し、将来、経緯報告書を作成・提出する可能性があることをあらかじめ周知すること等は、情報管理の徹底やインサイダー取引の未然防止の観点から有益と考えられる。
提出された経緯報告書をみると、上記のインサイダー取引のリスクを高める三つの特徴は顕著である。開示項目によっては、重要事実が発生してすぐに開示される場合もあるが、公開買付けの場合には、大半が2~3か月以上の準備期間を要しているし、公開買付けを行う側とされる側で、デューデリジェンスを行うなど様々なプロセスを経ることから、関係者の一覧に掲載される人数も多数に及んでいる。
上場会社のみならず市場関係者においては、公開買付けに関わる場合に、これらの特徴を十分理解し、インサイダー取引が行われないよう情報管理を徹底し、慎重にプロセスを進めていく必要がある。
なお、証券取引等監視委員会のホームページには、証券取引等監視委員会が本年7月に市場参加者向けに行ったセミナーの資料が掲示されている。こちらについても是非参考とされたい(証券取引等監視委員会ホームページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/torikumi/torikumi.htm(平成22年7月15日付講演資料)参照)。
2.破産等の申立て 破産等の申立ての案件の増加は、平成20年度および21年度の傾向としてみられるが、この背景にはわが国の経済情勢による影響が大きいと考えられる。
破産等の申立ての案件に関連して2点ほど留意点が考えられる。一つは損失回避もインサイダー取引となること、もう一つは教育の重要性である。
まず前者について触れると、一般的な感覚として、一般投資家が知らないインサイダー情報を利用して「儲ける」のは悪いことだ、不公平だと感じられはしても、損失回避については「儲けているわけではないので問題ないのではないか」と東証COMLECとして問合せを受ける場合がある。
これに関連して、よく受ける質問を紹介すると、①買い付けただけで売っていないため利益を実現していない、②売買の株数が少ないため獲得した利益が僅少である、③売買の結果損失が発生した、④株価が上がり(下がり)そうな情報に基づき売った(買った)といった場合についてもインサイダー取引となるかという問合せを受けることがあるが、前述した損失回避を含め、いずれのケースでも未公表の重要事実を知っていれば、当然にインサイダー取引となることにご留意いただきたい。
不正確な理解のためにインサイダー取引を起こすことを回避するためには、もう一つのポイントとして指摘した日頃からの教育が重要である。特に、破産等の申立ては、通常、結果として上場廃止となるため、株価の急落につながることから、たとえば、当該申立てを実施する会社に勤めている場合、未公表時にその情報を知ってしまったら、自社株売却のインセンティブが特に強く働くケースであると思われる。
しかしながら、インサイダー取引規制に対する正確な理解と、インサイダー取引が発覚することによる勤務先や本人への悪影響を認識していれば、売却を踏みとどまる十分な効果が得られると考えられる。
3.増資 増資については、通常のインサイダー取引の審査に加え、不適切な第三者割当への対応も行っている。
第三者割当の事前相談においては、開示に係る規則等に基づく審査を実施する上場管理部、上場会社の開示サポートを担う東京証券取引所上場部および不公正取引の監視を実施する売買審査部が、証券取引等監視委員会等の外部機関を含め、不適切な第三者割当について適時適切に情報共有し、その未然防止に向けて連携して取り組んでいる(上場管理部において公表した事前相談事例等について、今号32頁参照)。
4.情報受領者によるインサイダー取引 情報受領者によるインサイダー取引についてもフォーラムにおける証券取引等監視委員会の講演で触れられているが、近年重要事実を知った会社関係者から当該重要事実について伝達を受けた情報受領者によるインサイダー取引が増加傾向にある。
インサイダー取引については、証券会社、証券取引所および証券取引等監視委員会が、それぞれ連携しつつ、各々の立場から調査・審査を行っており、情報受領者のように上場会社と直接の関係がない者であってもその調査・審査から逃れられないことを十分にご理解いただき、不用意に情報受領者を増やさないよう情報管理を徹底することが肝要である。
Ⅴ J-IRISSへの登録
2009年5月から、日本証券業協会の自主規制ルールである内部者登録制度の実効性を高め、上場会社役職員の内部者取引規制違反を未然に防止することを目的として、上場会社役員情報に係るデータベース「J-IRISS(Japan-Insider Registration & Identification Support System:ジェイ・アイリス)」が稼動している(詳細については、日本証券業協会ホームページhttp://www.jsda.or.jp/html/j-iriss/index.html(J-IRISS)参照)。
これは、証券会社が注文を受託した際に当該委託者が内部者取引規制上の会社関係者に該当しないかどうかを確認するため、証券会社が保有する顧客情報と、上場会社が当該システムに登録した自社役員等の氏名・住所等の情報をマッチング・確認するものである。
J-IRISSが活用されることにより、証券会社における内部者登録の実効性向上はもとより、上場会社においても、たとえば、社内の総務・法務担当等ではチェックできなかった役職員によるインサイダー取引を証券会社での発注時に水際で防ぐことが可能となるほか、役員本人の立場からみても、自らの情報がJ-IRISSに登録されていることを自覚することでインサイダー取引に注意する動機付けとなるなどの効果が期待され、さらには、特定有価証券等の売買等の報告(金融商品取引法163条)、短期売買利益の返還(同法164条)の法令遵守の面でも副次的な効果が期待される。
公正で投資者に信頼される市場の構築のため、上場会社の自社におけるインサイダー取引未然防止体制の充実に加え、J-IRISSの積極的な活用が期待される。
Ⅵ おわりに
インサイダー取引は、個人や一企業としての問題だけにとどまらず、証券市場に対する投資者からの信頼を著しく損なわせる行為であり、資本主義経済の根幹を揺るがす、決して許されない行為である。
上場会社を始めとする関係者の方々は、証券市場に対する関わり方こそ異なるが、共に証券市場においてインサイダー取引の未然防止のために重要な役割を担う者であると位置付けられる。
今後も当法人は、これらの方々のインサイダー取引の未然防止を含むコンプライアンスを支援すべく、東証COMLEC等を通じて、積極的に取り組んでいきたいと考えている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















