解説記事2011年07月25日 【法令解説】 審査手続・審査基準に係る企業結合規制の見直しの要点(2011年7月25日号・№412)
法令解説
審査手続・審査基準に係る企業結合規制の見直しの要点
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 企業結合調査官(主査) 原田 郁
はじめに
公正取引委員会は本年6月14日、昨年夏から行ってきた企業結合規制(審査手続および審査基準)の見直しの結果を公表した。見直しの対象となったのは、次の公正取引委員会規則等である。見直し後の公正取引委員会規則等は、本年7月1日から施行されている。
① 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」(昭和28年公正取引委員会規則第1号。以下「届出規則」という)《一部改正》
② 「企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針」(平成14年12月11日公正取引委員会。以下「事前相談対応方針」という)《廃止》
「企業結合審査の手続に関する対応方針」(平成23年6月14日公正取引委員会。以下「手続対応方針」という)《新規策定》
③ 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成16年5月31日公正取引委員会。以下「企業結合ガイドライン」という)《一部改正》
本稿では、企業結合規制の概要、今般の企業結合規制の見直しの背景・経緯および見直しの概要を解説する。なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的な見解である。
Ⅰ 企業結合規制の概要
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)は、株式取得、合併等の企業結合のうち、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるものを禁止している。
このような規制を行うにあたって、独占禁止法は、一定規模以上の企業結合について事前に届け出ることを義務付けており、公正取引委員会は、届出の行われた企業結合計画を中心に企業結合審査を行っている(脚注1)。届出受理の日から30日を経過するまでの期間は、企業結合計画を実行してはならない「禁止期間」とされているところ、公正取引委員会は必要があると認める場合にはこの禁止期間を短縮することができる(独占禁止法10条8項および15条3項等の企業結合類型ごとの準用規定)。
事前に届出を義務付けられている企業結合の類型は、株式取得(独占禁止法10条)、合併(同法15条)、分割(共同新設分割および吸収分割。同法15条の2)、共同株式移転(同法15条の3)および事業譲受け等(同法16条)である。届出対象の範囲については、表のとおり、企業結合類型ごとに国内売上高合計額(脚注2)等を基に定められている。
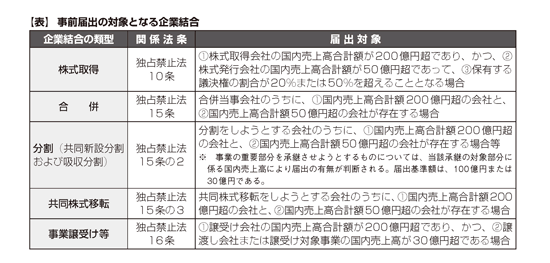
Ⅱ 企業結合規制の見直しの背景・経緯
今般の企業結合規制の見直しの契機となった「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)では、企業の戦略的な事業再編の促進に資する施策の1つとして、グローバル市場にも配慮した企業結合規制(審査手続および審査基準)の検証と必要な見直しを行うこととされた。企業結合規制の見直しについては、その後の累次の閣議決定においてもその必要性が確認されている(脚注3)。
これを受けて、公正取引委員会は、昨年8月に有識者等からのヒアリングや海外の競争当局の制度との比較を行って、企業結合規制についての検証を実施した。また、公正取引委員会が見直しに向けての検討を行っている過程において、社団法人日本経済団体連合会および社団法人関西経済連合会から、企業結合規制の見直しに関する意見書が提出されている(脚注4)。
これらの意見書においては、①事前相談制度の位置付けを見直し、実質的な企業結合審査と独占禁止法上の判断については届出後に行うべきであること、②公正取引委員会が当事会社に対し、企業結合審査の過程で検討事項等について説明するなど、届出会社と公正取引委員会との審査中のコミュニケーションを充実させるべきであること、③グローバルな競争を踏まえた企業結合審査を行うべきであること等が提言されている。
検証結果および上記の提言等を踏まえ、企業結合審査の迅速性、透明性および予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から、公正取引委員会は本年3月4日、企業結合規制の見直しに伴う公正取引委員会規則の一部改正等の原案を公表し、パブリックコメント(意見募集)手続を実施した。その後、パブリックコメント手続において寄せられた意見を踏まえて原案の一部を修正したうえで、公正取引委員会は、本年6月14日に成案を公表した。成案は、本年7月1日から施行されている。
Ⅲ 企業結合規制の見直しの概要
1 審査手続
(1)事前相談制度の廃止 従前、公正取引委員会は、届出を予定する会社等から、企業結合計画について独占禁止法上の問題があるか否かについての相談(以下「事前相談」という)があった場合、事前相談対応方針に則って対応し、当該計画に対する独占禁止法上の判断を届出前に回答してきた。これは、企業結合を行う企業の側から、届出前に公正取引委員会の当該企業結合計画に対する独占禁止法上の判断を知りたいとの要望があったことに応えてきたものである。
しかし、前記Ⅱで述べたように、主な経済団体から事前相談制度の位置付けを見直すべきという要望が提出されており、事前相談制度の必要性は薄れてきたものと考えられた。これは、平成21年の独占禁止法改正法(平成22年1月施行)により、株式取得についても他の企業結合(合併等)と同様に事後報告義務から事前届出義務に改められたため、事前に公正取引委員会の判断を得るという事前相談の意義が低下したことも影響していると考えられる。また、欧米競争当局における企業結合審査においても届出前の相談は行われているものの、届出前の段階では当局の最終的な判断は示されていない。このため、国際的整合性の観点からも、これまでの事前相談制度を廃止することが望ましいと考えられた。見直し後は、届出を要する企業結合計画に対する独占禁止法上の判断は、届出後の手続において示すこととなる(脚注5)。
一方、届出前に企業結合計画について公正取引委員会に相談できる仕組みは有用であるとの意見があったことを踏まえ、届出会社が希望する場合には、届出を行う前に届出書の記載方法等に関する相談(以下「届出前相談」という)を行うことができることとした。このような相談は任意で行われるものであり、届出予定会社が届出前相談を行わなかったとしても、当該会社が、届出後の審査において不利益に取り扱われることはない(脚注6)。
(2)届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションの充実 前記(1)のとおり、届出を要する企業結合計画に対する独占禁止法上の判断は、届出後の手続において示される。見直し後の手続の流れについては、図を参照されたい。
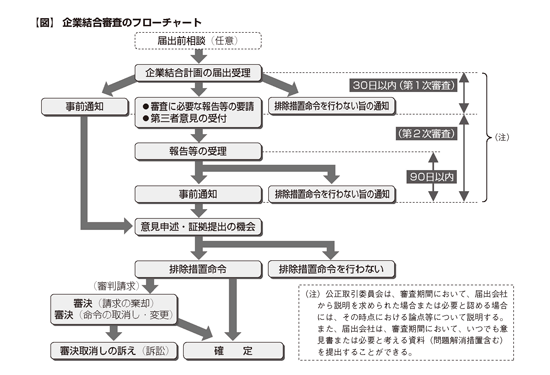
届出後の手続については、従前から独占禁止法10条8項~10項(15条3項等で準用)において規定されているとおり、届出書の受理から30日間で審査(第1次審査)が行われ、より詳細な審査(第2次審査)を要するものについては、審査に必要な報告等の要請が行われてすべての報告等を受理した日から90日間で判断が示されることになる。
今般の見直しでこの法定の審査期間(届出書を受理した日から排除措置命令前の通知〔以下「事前通知」という〕または排除措置命令を行わない旨の通知を行う日までの期間をいう。以下同じ)の枠組みは変更されていないが、審査期間における届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションをさらに充実させるという観点から、次のとおり手続を整備することとした。
ア 報告等を求める趣旨の記載 届出会社に報告等の要請(独占禁止法10条9項および15条3項等の企業結合類型ごとの準用規定)を行う際には、その報告等を求める趣旨について報告等要請書に記載する(脚注7)。これは、届出会社に対する資料要求について、その趣旨が必ずしも明らかにされてこなかったのではないかとの指摘に応えたものであると考えられる。
イ 論点等の説明 審査期間において、届出会社から求めがあった場合または必要がある場合には、公正取引委員会は、その時点における企業結合審査の論点等について説明する(脚注8)。このような説明は従前の企業結合審査においても場合によって行われていたものであると考えられるが、手続対応方針に明記することで、企業結合審査の過程において届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションがより密になることが期待される。
ウ 届出会社の意見書および資料の提出 届出会社は、審査期間において、いつでも公正取引委員会に対し意見書または必要と考える資料の提出(問題解消措置の申出を含む)ができる(脚注9)。これは、従前も事前相談対応方針に記載されていたことであり、届出後の審査においても当然に可能なものとして手続対応方針に盛り込まれた。
公正取引委員会は、手続対応方針の別添に記載されている資料を企業結合審査の判断要素を検討するうえで参考とすることが多い(脚注10)。当然ながら、届出会社が提出できる資料はこの別添に記載されたものに限られない。届出会社が公正取引委員会の企業結合審査に有用と考える資料は積極的に提出し、企業結合審査の過程において届出会社と公正取引委員会との議論が深められることが期待される。
(3)企業結合審査の結果の届出会社への通知、企業結合審査の結果の公表 企業結合審査の結果、独占禁止法上問題がない事案について、届出会社に対しその旨を知らせる規定は置かれておらず、届出会社は、審査期間中に公正取引委員会から事前通知が行われなかったことをもって、当該事案に独占禁止法上問題がなかったことを知るという仕組みになっていた。
今般の見直しにおいて、独占禁止法上問題がない事案については、届出会社に対して「排除措置命令を行わない旨の通知」が交付されることとなり(脚注11)、企業結合審査の結果がより明確に、また迅速に届出会社に伝えられることになると考えられる。また、今般の見直しに合わせて、禁止期間の短縮を認める場合も拡大されており(脚注12)、企業結合計画の実行がこれまでよりも迅速に行われることが期待される。
第2次審査の結果、独占禁止法上問題がないとされた事案については、そのような結論に至った理由が記載された書面も「排除措置命令を行わない旨の通知」とともに交付される(脚注13)。
独占禁止法上問題があるとされた事案については、事前通知において、予定される排除措置命令の内容とともに、公正取引委員会の認定した事実およびこれに対する法令の適用も書面により通知されることとなるので、第2次審査が行われた事案については、独占禁止法上の問題の存否にかかわらず、公正取引委員会が結論に至った理由が書面で示されることになり、審査結果がより分かりやすいものになることが期待される。
また、第2次審査を行った事案は、審査結果について公表する(脚注14)。これにより、公正取引委員会の審査結果の透明性がより一層高まることが期待される。
2 審査基準
(1)企業結合審査の対象とならない場合を明確化 会社の株式保有については、株式を所有する会社(株式所有会社)と株式を所有される会社(株式発行会社)との間に結合関係が形成・維持・強化され、企業結合審査の対象となる場合が企業結合ガイドラインに示されている。
今般の見直しにおいては、①議決権保有比率(株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の保有する株式に係る議決権の割合をいう。以下同じ)が10%以下、または②議決権保有比率の順位が第4位以下のときは、企業結合審査の対象とならない旨を明示した(脚注15)。
なお、届出会社の負担に配慮して、届出書の記載内容を一部簡素化した。具体的には、届出会社が10%超の議決権を保有する会社について情報の提出が求められていたところ、当該項目が削除され、届出会社の属する企業結合集団が20%超の議決権を保有する会社についての情報に限定されている(脚注16)。
(2)世界市場・東アジア市場を認定する場合の例示を追加 従前の企業結合ガイドラインでも、一定の取引分野の地理的範囲の画定に関する箇所で、国境を越えて地理的範囲が画定される場合については記載されており、実際にこの考え方に則って世界市場が画定された事例も存在する(脚注17)。
国境を越えて地理的範囲が画定されるような場合においても、一定の取引分野の画定の基本的な考え方に則り、「ある地域において、ある事業者が、ある商品を独占して供給しているという仮定の下で、当該独占事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅ではあるが、実質的かつ一時的ではない価格引上げをした場合に、当該商品及び地域について、需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する」(脚注18)こととなる。
今般の見直しにおいて、企業結合ガイドラインの国境を越えて地理的範囲が画定される場合に関する記載を整理するとともに、世界市場・東アジア市場を認定する場合の例示を追加し、「内外の主要な供給者が世界(又は東アジア)中の販売地域において実質的に同等の価格で販売しており、需要者が世界(又は東アジア)各地の供給者から主要な調達先を選定している場合は、世界(又は東アジア)市場が画定され得る」ことを明示した(脚注19)。
(3)需要が縮小している場合の考え方を追記 需要の縮小については、近年、わが国で企業結合を行う理由に挙げられる場合があるところ、従前の企業結合ガイドラインでは、企業結合審査において需要の縮小がどのように考慮されるかが必ずしも明らかではなかった。
このため、今般の見直しにおいて、需要の縮小が競争を実質的に制限することとなるか否かの判断要素に影響する場合について、その考え方を次のとおり企業結合ガイドラインに追記した。
ア 「競争者の供給余力」 ある商品の需要が継続的構造的に減少しており、競争者の供給余力が十分である場合には、当事会社グループの価格引上げに対する牽制力になり得る(脚注20)。
イ 「隣接市場からの競争圧力」 需要の減少により市場が縮小している商品について、競合品が当該商品に対する需要を代替する蓋然性が高い場合は、競争を促進する要素として評価し得る(脚注21)。
ウ 「需要者からの競争圧力」 ある商品の需要が減少して継続的構造的に需要量が供給量を大きく下回ることにより、需要者からの競争圧力が働いている場合には、当事会社グループが価格等をある程度自由に左右することをある程度妨げる要因となり得る(脚注22)。
(4)現在輸入が行われているかどうかにかかわらず、輸入圧力を評価することを明示 輸入圧力が十分働いていれば、当該企業結合が一定の取引分野における競争を制限することとなるおそれは小さいものとなると考えられる。
輸入圧力が十分働いているか否かを考慮するにあたっては、現在輸入が行われているかどうかにかかわらず、輸入に係る状況を勘案して判断することを明示した(脚注23)。
(5)近い将来における競合品の競争圧力についても考慮の対象とすることを明示 画定された一定の取引分野に関連する市場、たとえば、地理的に隣接する市場および当該商品と類似の効用等を有する商品(以下「競合品」という)の市場における競争の状況についても、考慮の対象となる。
競合品の競争圧力については、現在、隣接市場において十分に活発な競争が行われている場合のみならず、近い将来において競合品が当該商品に対する需要を代替する蓋然性が高い場合にも、当該一定の取引分野における競争を促進する要素として評価し得る場合があることを明示した(脚注24)。
(6)業績不振と認定される場合の例示を追加 当事会社の一方、または当事会社の一方の企業結合の対象となる事業部門が、企業結合がなければ近い将来において市場から退出する蓋然性が高いことが明らかな場合において、これを企業結合により救済することが可能な事業者で、他方当事会社による企業結合よりも競争に与える影響が小さいものの存在が認め難いときは、水平型企業結合が単独行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれは小さいと通常考えられる。
このような業績不振と認められるような状況について、当事会社の一方が継続的に大幅な経常損失を計上していることおよび事業部門が継続的に大幅な損失を計上していることを例示として追加した(脚注25)。
おわりに
これまでの審査手続からの大きな変更点は、事前相談制度が廃止され、同時に届出後の企業結合審査期間中における各種の手続が整備されたことである。これにより、企業結合審査の手続の流れがより明確になり、届出会社が審査スケジュールを見通しやすくなったのではないかと考える。
また、審査基準についても、公正取引委員会が企業結合審査を行ううえでの指針である企業結合ガイドラインを改正することで、公正取引委員会の企業結合審査における検討の枠組みと判断要素が、届出会社に対しより一層明らかになったと考える。
今般の企業結合規制の見直しは、審査手続および審査基準の両面にわたる大幅なものとなった。今般の見直しの趣旨を踏まえ、より迅速かつ透明性の高い、また、事業者の予見可能性の高い企業結合審査が引き続き行われるものと期待される。
脚注
1 事前届出制度は、公正取引委員会が独占禁止法に違反するような企業結合に係る端緒を得ることを目的として設けられているものである。届出対象となる企業結合の範囲は、会社の届出負担と上記のような目的とを勘案のうえ、定められているが、届出対象となっていない企業結合計画についても、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがあるものについては、審査の対象となる。
2 「国内売上高」とは、国内において供給された商品および役務の価額の最終事業年度における合計額である。「国内売上高合計額」を算出する際には、届出会社の属する企業結合集団(届出会社の最終親会社とその子会社からなる企業グループ)に属する会社等の国内売上高を合計することとされている。国内売上高合計額の具体的な算出方法は、届出規則2条~2条の5に規定されている。
3 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済政策」(平成22年9月10日閣議決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizaitaisaku.pdf)、「新成長戦略実現2011」(平成23年1月25日閣議決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/shinseicho2011.pdf)参照。
4 社団法人日本経済団体連合会「企業結合に関する独占禁止法上の審査手続・審査基準の適正化を求める」(平成22年10月19日)(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/094.html)、社団法人関西経済連合会「企業結合審査手続きの見直しに関する意見」(平成22年11月15日)(http://www.kankeiren.or.jp/material/pdf/2009/101115ikenshokigyoketugo.pdf)参照。
5 届出を要しない企業結合の計画についても、公正取引委員会に対し、具体的な企業結合計画の内容を示して相談があった場合には対応する。手続対応方針7「届出を要しない企業結合の計画に関する相談」参照。
6 手続対応方針2「届出前相談」参照。
7 届出規則8条、手続対応方針6(1)「報告等の要請」参照。
8 手続対応方針4「当委員会による企業結合審査における論点等の説明並びに届出会社の意見書及び資料の提出」参照。
9 届出規則7条の2、手続対応方針4「当委員会による企業結合審査における論点等の説明並びに届出会社の意見書及び資料の提出」参照。
10 手続対応方針別添「公正取引委員会が企業結合審査において参考とする資料の例」参照。
11 届出規則9条、様式第43号~第48号、手続対応方針3「届出後の手続の流れ」・5(2)「第1次審査の終了」・6(3)「第2次審査の終了」参照。
12 届出会社から書面により禁止期間の短縮の申出があった場合であって、公正取引委員会が当該事案について独占禁止法上問題がないと判断したときは、速やかに「排除措置命令を行わない旨の通知」をするとともに、禁止期間を短縮する(企業結合ガイドライン(付)、手続対応方針5(2)「第1次審査の終了」参照)。
13 手続対応方針6(3)「第2次審査の終了」参照。
14 手続対応方針6(3)「第2次審査の終了」参照。なお、第1次審査で終了した事案についても、公正取引委員会が、届出会社が問題解消措置を採ることを前提に、独占禁止法上問題がないと判断した事案など、他の事業者の参考となるものは公表する(手続対応方針5(2)「第1次審査の終了」参照)。
15 企業結合ガイドライン第1の1(1)「会社の株式保有」参照。
16 企業結合類型ごとの届出書(届出規則様式第4号、第5号、第8号~第12号)参照。
17 たとえば、「ソニー(株)と日本電気(株)による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立について」(平成17年度における主要な企業結合事例、事例8)参照。
18 いわゆる仮定的独占者基準(SSNIP〔Small but Significant and Non-transitory Increase in Price〕テスト)。企業結合ガイドライン第2の1「一定の取引分野の画定の基本的考え方」参照。
19 企業結合ガイドライン第2の3(2)「国境を越えて地理的範囲が画定される場合についての考え方」参照。
20 企業結合ガイドライン第4の2(1)オ「競争者の供給余力及び差別化の程度」参照。
21 企業結合ガイドライン第4の2(4)「隣接市場からの競争圧力」参照。
22 企業結合ガイドライン第4の2(5)「需要者からの競争圧力」参照。
23 企業結合ガイドライン第4の2(2)「輸入」参照。
24 企業結合ガイドライン第4の2(4)「隣接市場からの競争圧力」参照。
25 企業結合ガイドライン第4の2(8)「当事会社グループの経営状況」参照。
審査手続・審査基準に係る企業結合規制の見直しの要点
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 企業結合調査官(主査) 原田 郁
はじめに
公正取引委員会は本年6月14日、昨年夏から行ってきた企業結合規制(審査手続および審査基準)の見直しの結果を公表した。見直しの対象となったのは、次の公正取引委員会規則等である。見直し後の公正取引委員会規則等は、本年7月1日から施行されている。
① 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」(昭和28年公正取引委員会規則第1号。以下「届出規則」という)《一部改正》
② 「企業結合計画に関する事前相談に対する対応方針」(平成14年12月11日公正取引委員会。以下「事前相談対応方針」という)《廃止》
「企業結合審査の手続に関する対応方針」(平成23年6月14日公正取引委員会。以下「手続対応方針」という)《新規策定》
③ 「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成16年5月31日公正取引委員会。以下「企業結合ガイドライン」という)《一部改正》
本稿では、企業結合規制の概要、今般の企業結合規制の見直しの背景・経緯および見直しの概要を解説する。なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的な見解である。
Ⅰ 企業結合規制の概要
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)は、株式取得、合併等の企業結合のうち、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるものを禁止している。
このような規制を行うにあたって、独占禁止法は、一定規模以上の企業結合について事前に届け出ることを義務付けており、公正取引委員会は、届出の行われた企業結合計画を中心に企業結合審査を行っている(脚注1)。届出受理の日から30日を経過するまでの期間は、企業結合計画を実行してはならない「禁止期間」とされているところ、公正取引委員会は必要があると認める場合にはこの禁止期間を短縮することができる(独占禁止法10条8項および15条3項等の企業結合類型ごとの準用規定)。
事前に届出を義務付けられている企業結合の類型は、株式取得(独占禁止法10条)、合併(同法15条)、分割(共同新設分割および吸収分割。同法15条の2)、共同株式移転(同法15条の3)および事業譲受け等(同法16条)である。届出対象の範囲については、表のとおり、企業結合類型ごとに国内売上高合計額(脚注2)等を基に定められている。
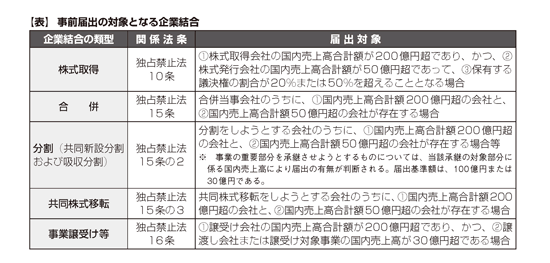
Ⅱ 企業結合規制の見直しの背景・経緯
今般の企業結合規制の見直しの契機となった「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)では、企業の戦略的な事業再編の促進に資する施策の1つとして、グローバル市場にも配慮した企業結合規制(審査手続および審査基準)の検証と必要な見直しを行うこととされた。企業結合規制の見直しについては、その後の累次の閣議決定においてもその必要性が確認されている(脚注3)。
これを受けて、公正取引委員会は、昨年8月に有識者等からのヒアリングや海外の競争当局の制度との比較を行って、企業結合規制についての検証を実施した。また、公正取引委員会が見直しに向けての検討を行っている過程において、社団法人日本経済団体連合会および社団法人関西経済連合会から、企業結合規制の見直しに関する意見書が提出されている(脚注4)。
これらの意見書においては、①事前相談制度の位置付けを見直し、実質的な企業結合審査と独占禁止法上の判断については届出後に行うべきであること、②公正取引委員会が当事会社に対し、企業結合審査の過程で検討事項等について説明するなど、届出会社と公正取引委員会との審査中のコミュニケーションを充実させるべきであること、③グローバルな競争を踏まえた企業結合審査を行うべきであること等が提言されている。
検証結果および上記の提言等を踏まえ、企業結合審査の迅速性、透明性および予見可能性を一層高めるとともに、国際的整合性の向上を図る観点から、公正取引委員会は本年3月4日、企業結合規制の見直しに伴う公正取引委員会規則の一部改正等の原案を公表し、パブリックコメント(意見募集)手続を実施した。その後、パブリックコメント手続において寄せられた意見を踏まえて原案の一部を修正したうえで、公正取引委員会は、本年6月14日に成案を公表した。成案は、本年7月1日から施行されている。
Ⅲ 企業結合規制の見直しの概要
1 審査手続
(1)事前相談制度の廃止 従前、公正取引委員会は、届出を予定する会社等から、企業結合計画について独占禁止法上の問題があるか否かについての相談(以下「事前相談」という)があった場合、事前相談対応方針に則って対応し、当該計画に対する独占禁止法上の判断を届出前に回答してきた。これは、企業結合を行う企業の側から、届出前に公正取引委員会の当該企業結合計画に対する独占禁止法上の判断を知りたいとの要望があったことに応えてきたものである。
しかし、前記Ⅱで述べたように、主な経済団体から事前相談制度の位置付けを見直すべきという要望が提出されており、事前相談制度の必要性は薄れてきたものと考えられた。これは、平成21年の独占禁止法改正法(平成22年1月施行)により、株式取得についても他の企業結合(合併等)と同様に事後報告義務から事前届出義務に改められたため、事前に公正取引委員会の判断を得るという事前相談の意義が低下したことも影響していると考えられる。また、欧米競争当局における企業結合審査においても届出前の相談は行われているものの、届出前の段階では当局の最終的な判断は示されていない。このため、国際的整合性の観点からも、これまでの事前相談制度を廃止することが望ましいと考えられた。見直し後は、届出を要する企業結合計画に対する独占禁止法上の判断は、届出後の手続において示すこととなる(脚注5)。
一方、届出前に企業結合計画について公正取引委員会に相談できる仕組みは有用であるとの意見があったことを踏まえ、届出会社が希望する場合には、届出を行う前に届出書の記載方法等に関する相談(以下「届出前相談」という)を行うことができることとした。このような相談は任意で行われるものであり、届出予定会社が届出前相談を行わなかったとしても、当該会社が、届出後の審査において不利益に取り扱われることはない(脚注6)。
(2)届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションの充実 前記(1)のとおり、届出を要する企業結合計画に対する独占禁止法上の判断は、届出後の手続において示される。見直し後の手続の流れについては、図を参照されたい。
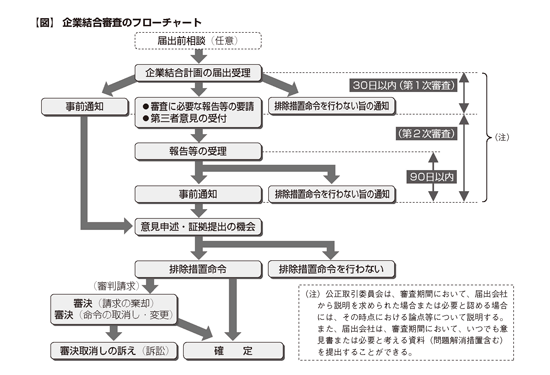
届出後の手続については、従前から独占禁止法10条8項~10項(15条3項等で準用)において規定されているとおり、届出書の受理から30日間で審査(第1次審査)が行われ、より詳細な審査(第2次審査)を要するものについては、審査に必要な報告等の要請が行われてすべての報告等を受理した日から90日間で判断が示されることになる。
今般の見直しでこの法定の審査期間(届出書を受理した日から排除措置命令前の通知〔以下「事前通知」という〕または排除措置命令を行わない旨の通知を行う日までの期間をいう。以下同じ)の枠組みは変更されていないが、審査期間における届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションをさらに充実させるという観点から、次のとおり手続を整備することとした。
ア 報告等を求める趣旨の記載 届出会社に報告等の要請(独占禁止法10条9項および15条3項等の企業結合類型ごとの準用規定)を行う際には、その報告等を求める趣旨について報告等要請書に記載する(脚注7)。これは、届出会社に対する資料要求について、その趣旨が必ずしも明らかにされてこなかったのではないかとの指摘に応えたものであると考えられる。
イ 論点等の説明 審査期間において、届出会社から求めがあった場合または必要がある場合には、公正取引委員会は、その時点における企業結合審査の論点等について説明する(脚注8)。このような説明は従前の企業結合審査においても場合によって行われていたものであると考えられるが、手続対応方針に明記することで、企業結合審査の過程において届出会社と公正取引委員会とのコミュニケーションがより密になることが期待される。
ウ 届出会社の意見書および資料の提出 届出会社は、審査期間において、いつでも公正取引委員会に対し意見書または必要と考える資料の提出(問題解消措置の申出を含む)ができる(脚注9)。これは、従前も事前相談対応方針に記載されていたことであり、届出後の審査においても当然に可能なものとして手続対応方針に盛り込まれた。
公正取引委員会は、手続対応方針の別添に記載されている資料を企業結合審査の判断要素を検討するうえで参考とすることが多い(脚注10)。当然ながら、届出会社が提出できる資料はこの別添に記載されたものに限られない。届出会社が公正取引委員会の企業結合審査に有用と考える資料は積極的に提出し、企業結合審査の過程において届出会社と公正取引委員会との議論が深められることが期待される。
(3)企業結合審査の結果の届出会社への通知、企業結合審査の結果の公表 企業結合審査の結果、独占禁止法上問題がない事案について、届出会社に対しその旨を知らせる規定は置かれておらず、届出会社は、審査期間中に公正取引委員会から事前通知が行われなかったことをもって、当該事案に独占禁止法上問題がなかったことを知るという仕組みになっていた。
今般の見直しにおいて、独占禁止法上問題がない事案については、届出会社に対して「排除措置命令を行わない旨の通知」が交付されることとなり(脚注11)、企業結合審査の結果がより明確に、また迅速に届出会社に伝えられることになると考えられる。また、今般の見直しに合わせて、禁止期間の短縮を認める場合も拡大されており(脚注12)、企業結合計画の実行がこれまでよりも迅速に行われることが期待される。
第2次審査の結果、独占禁止法上問題がないとされた事案については、そのような結論に至った理由が記載された書面も「排除措置命令を行わない旨の通知」とともに交付される(脚注13)。
独占禁止法上問題があるとされた事案については、事前通知において、予定される排除措置命令の内容とともに、公正取引委員会の認定した事実およびこれに対する法令の適用も書面により通知されることとなるので、第2次審査が行われた事案については、独占禁止法上の問題の存否にかかわらず、公正取引委員会が結論に至った理由が書面で示されることになり、審査結果がより分かりやすいものになることが期待される。
また、第2次審査を行った事案は、審査結果について公表する(脚注14)。これにより、公正取引委員会の審査結果の透明性がより一層高まることが期待される。
2 審査基準
(1)企業結合審査の対象とならない場合を明確化 会社の株式保有については、株式を所有する会社(株式所有会社)と株式を所有される会社(株式発行会社)との間に結合関係が形成・維持・強化され、企業結合審査の対象となる場合が企業結合ガイドラインに示されている。
今般の見直しにおいては、①議決権保有比率(株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の保有する株式に係る議決権の割合をいう。以下同じ)が10%以下、または②議決権保有比率の順位が第4位以下のときは、企業結合審査の対象とならない旨を明示した(脚注15)。
なお、届出会社の負担に配慮して、届出書の記載内容を一部簡素化した。具体的には、届出会社が10%超の議決権を保有する会社について情報の提出が求められていたところ、当該項目が削除され、届出会社の属する企業結合集団が20%超の議決権を保有する会社についての情報に限定されている(脚注16)。
(2)世界市場・東アジア市場を認定する場合の例示を追加 従前の企業結合ガイドラインでも、一定の取引分野の地理的範囲の画定に関する箇所で、国境を越えて地理的範囲が画定される場合については記載されており、実際にこの考え方に則って世界市場が画定された事例も存在する(脚注17)。
国境を越えて地理的範囲が画定されるような場合においても、一定の取引分野の画定の基本的な考え方に則り、「ある地域において、ある事業者が、ある商品を独占して供給しているという仮定の下で、当該独占事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅ではあるが、実質的かつ一時的ではない価格引上げをした場合に、当該商品及び地域について、需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する」(脚注18)こととなる。
今般の見直しにおいて、企業結合ガイドラインの国境を越えて地理的範囲が画定される場合に関する記載を整理するとともに、世界市場・東アジア市場を認定する場合の例示を追加し、「内外の主要な供給者が世界(又は東アジア)中の販売地域において実質的に同等の価格で販売しており、需要者が世界(又は東アジア)各地の供給者から主要な調達先を選定している場合は、世界(又は東アジア)市場が画定され得る」ことを明示した(脚注19)。
(3)需要が縮小している場合の考え方を追記 需要の縮小については、近年、わが国で企業結合を行う理由に挙げられる場合があるところ、従前の企業結合ガイドラインでは、企業結合審査において需要の縮小がどのように考慮されるかが必ずしも明らかではなかった。
このため、今般の見直しにおいて、需要の縮小が競争を実質的に制限することとなるか否かの判断要素に影響する場合について、その考え方を次のとおり企業結合ガイドラインに追記した。
ア 「競争者の供給余力」 ある商品の需要が継続的構造的に減少しており、競争者の供給余力が十分である場合には、当事会社グループの価格引上げに対する牽制力になり得る(脚注20)。
イ 「隣接市場からの競争圧力」 需要の減少により市場が縮小している商品について、競合品が当該商品に対する需要を代替する蓋然性が高い場合は、競争を促進する要素として評価し得る(脚注21)。
ウ 「需要者からの競争圧力」 ある商品の需要が減少して継続的構造的に需要量が供給量を大きく下回ることにより、需要者からの競争圧力が働いている場合には、当事会社グループが価格等をある程度自由に左右することをある程度妨げる要因となり得る(脚注22)。
(4)現在輸入が行われているかどうかにかかわらず、輸入圧力を評価することを明示 輸入圧力が十分働いていれば、当該企業結合が一定の取引分野における競争を制限することとなるおそれは小さいものとなると考えられる。
輸入圧力が十分働いているか否かを考慮するにあたっては、現在輸入が行われているかどうかにかかわらず、輸入に係る状況を勘案して判断することを明示した(脚注23)。
(5)近い将来における競合品の競争圧力についても考慮の対象とすることを明示 画定された一定の取引分野に関連する市場、たとえば、地理的に隣接する市場および当該商品と類似の効用等を有する商品(以下「競合品」という)の市場における競争の状況についても、考慮の対象となる。
競合品の競争圧力については、現在、隣接市場において十分に活発な競争が行われている場合のみならず、近い将来において競合品が当該商品に対する需要を代替する蓋然性が高い場合にも、当該一定の取引分野における競争を促進する要素として評価し得る場合があることを明示した(脚注24)。
(6)業績不振と認定される場合の例示を追加 当事会社の一方、または当事会社の一方の企業結合の対象となる事業部門が、企業結合がなければ近い将来において市場から退出する蓋然性が高いことが明らかな場合において、これを企業結合により救済することが可能な事業者で、他方当事会社による企業結合よりも競争に与える影響が小さいものの存在が認め難いときは、水平型企業結合が単独行為により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれは小さいと通常考えられる。
このような業績不振と認められるような状況について、当事会社の一方が継続的に大幅な経常損失を計上していることおよび事業部門が継続的に大幅な損失を計上していることを例示として追加した(脚注25)。
おわりに
これまでの審査手続からの大きな変更点は、事前相談制度が廃止され、同時に届出後の企業結合審査期間中における各種の手続が整備されたことである。これにより、企業結合審査の手続の流れがより明確になり、届出会社が審査スケジュールを見通しやすくなったのではないかと考える。
また、審査基準についても、公正取引委員会が企業結合審査を行ううえでの指針である企業結合ガイドラインを改正することで、公正取引委員会の企業結合審査における検討の枠組みと判断要素が、届出会社に対しより一層明らかになったと考える。
今般の企業結合規制の見直しは、審査手続および審査基準の両面にわたる大幅なものとなった。今般の見直しの趣旨を踏まえ、より迅速かつ透明性の高い、また、事業者の予見可能性の高い企業結合審査が引き続き行われるものと期待される。
脚注
1 事前届出制度は、公正取引委員会が独占禁止法に違反するような企業結合に係る端緒を得ることを目的として設けられているものである。届出対象となる企業結合の範囲は、会社の届出負担と上記のような目的とを勘案のうえ、定められているが、届出対象となっていない企業結合計画についても、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがあるものについては、審査の対象となる。
2 「国内売上高」とは、国内において供給された商品および役務の価額の最終事業年度における合計額である。「国内売上高合計額」を算出する際には、届出会社の属する企業結合集団(届出会社の最終親会社とその子会社からなる企業グループ)に属する会社等の国内売上高を合計することとされている。国内売上高合計額の具体的な算出方法は、届出規則2条~2条の5に規定されている。
3 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済政策」(平成22年9月10日閣議決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizaitaisaku.pdf)、「新成長戦略実現2011」(平成23年1月25日閣議決定)(http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/shinseicho2011.pdf)参照。
4 社団法人日本経済団体連合会「企業結合に関する独占禁止法上の審査手続・審査基準の適正化を求める」(平成22年10月19日)(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/094.html)、社団法人関西経済連合会「企業結合審査手続きの見直しに関する意見」(平成22年11月15日)(http://www.kankeiren.or.jp/material/pdf/2009/101115ikenshokigyoketugo.pdf)参照。
5 届出を要しない企業結合の計画についても、公正取引委員会に対し、具体的な企業結合計画の内容を示して相談があった場合には対応する。手続対応方針7「届出を要しない企業結合の計画に関する相談」参照。
6 手続対応方針2「届出前相談」参照。
7 届出規則8条、手続対応方針6(1)「報告等の要請」参照。
8 手続対応方針4「当委員会による企業結合審査における論点等の説明並びに届出会社の意見書及び資料の提出」参照。
9 届出規則7条の2、手続対応方針4「当委員会による企業結合審査における論点等の説明並びに届出会社の意見書及び資料の提出」参照。
10 手続対応方針別添「公正取引委員会が企業結合審査において参考とする資料の例」参照。
11 届出規則9条、様式第43号~第48号、手続対応方針3「届出後の手続の流れ」・5(2)「第1次審査の終了」・6(3)「第2次審査の終了」参照。
12 届出会社から書面により禁止期間の短縮の申出があった場合であって、公正取引委員会が当該事案について独占禁止法上問題がないと判断したときは、速やかに「排除措置命令を行わない旨の通知」をするとともに、禁止期間を短縮する(企業結合ガイドライン(付)、手続対応方針5(2)「第1次審査の終了」参照)。
13 手続対応方針6(3)「第2次審査の終了」参照。
14 手続対応方針6(3)「第2次審査の終了」参照。なお、第1次審査で終了した事案についても、公正取引委員会が、届出会社が問題解消措置を採ることを前提に、独占禁止法上問題がないと判断した事案など、他の事業者の参考となるものは公表する(手続対応方針5(2)「第1次審査の終了」参照)。
15 企業結合ガイドライン第1の1(1)「会社の株式保有」参照。
16 企業結合類型ごとの届出書(届出規則様式第4号、第5号、第8号~第12号)参照。
17 たとえば、「ソニー(株)と日本電気(株)による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立について」(平成17年度における主要な企業結合事例、事例8)参照。
18 いわゆる仮定的独占者基準(SSNIP〔Small but Significant and Non-transitory Increase in Price〕テスト)。企業結合ガイドライン第2の1「一定の取引分野の画定の基本的考え方」参照。
19 企業結合ガイドライン第2の3(2)「国境を越えて地理的範囲が画定される場合についての考え方」参照。
20 企業結合ガイドライン第4の2(1)オ「競争者の供給余力及び差別化の程度」参照。
21 企業結合ガイドライン第4の2(4)「隣接市場からの競争圧力」参照。
22 企業結合ガイドライン第4の2(5)「需要者からの競争圧力」参照。
23 企業結合ガイドライン第4の2(2)「輸入」参照。
24 企業結合ガイドライン第4の2(4)「隣接市場からの競争圧力」参照。
25 企業結合ガイドライン第4の2(8)「当事会社グループの経営状況」参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















