解説記事2017年04月03日 【レポート】 直接審査請求での答弁書作成、課税当局に一定のリスク(2017年4月3日号・№685)
レポート
直接審査請求での答弁書作成、課税当局に一定のリスク
短期間で再調査請求書並みの記載必要
昨年4月に施行された改正国税不服申立制度について、課税当局では、直接審査請求や証拠書類の閲覧・謄写の範囲拡大などへの対応を迫られた模様だ。特に、直接審査請求における答弁書の作成に関しては、国税不服審判所が定める提出期限が短いなか、再調査請求書と同程度の記載を求められることから、答弁書作成に係る実践的な研修も行われている。
改正国税不服申立制度は多大な影響及ぼす 改正国税不服申立制度が、不服申立事務に限らず、調査事務および審理事務にも多大な影響を及ぼすとする課税当局では、改正により可能となった直接審査請求への対応に追われたようだ。特に、課題とされたのは、直接審査請求における答弁書の作成だ。
答弁書は、国税不服審判所長が、原処分庁に対して、審査請求の趣旨および理由に対する原処分庁の主張の記載を求めるもの(図参照)。ただし、不服審査通達(国税庁関係)93-1(答弁書の記載程度)では、審査請求の理由の内容・程度が再調査の請求と同様であり、原処分庁の主張も再調査決定書に記載した決定理由と同様であれば、その決定の理由を答弁書に引用しても差し支えないとされている。再調査の請求の場合、その標準審理期間は3か月とされていることから、その間、事案の調査・審理を行い、再調査決定書に決定の理由を記載することができる。
答弁書未提出による審理手続の終結を懸念 一方、直接審査請求における答弁書の提出期限については、国税不服審判所長が、「相当の期間」を定めると規定されている(通則法93①)。この「相当の期間」について、不服審査通達(国税不服審判所関係)93-1では、審査請求の対象とされた処分の内容やその審査請求が再調査の請求についての決定を経たものであるかなどの事情に応じて定められるべきものとされているが、国税不服審判所は、課税当局に対して、4週間以内の答弁書提出を求めている模様だ。
審査請求事案における答弁書の作成について課税当局は、提出期間内に答弁書を提出しないことで、担当審判官が審理手続を終了する場合(通則法97の4②)があることを懸念。答弁書を早期作成することで、提出期限を遵守するよう努めるとしている。そのうえで、「特に、直接審査請求事案については、短期間で再調査請求書と同程度の記載が求められることから、その進捗状況や問題点等の把握に努めるとともに、適切かつ迅速な事案の処理が行われるよう、必要となる事務量を確保する」旨を指示。答弁書作成の実践的な研修を実施するなど、対応を図っている。
なお、国税不服審判所は、課税当局に対し、請求人の反論書に対する意見書、審判官からの主張内容の確認に対する回答書の提出期限を3週間以内と定めているようだ。
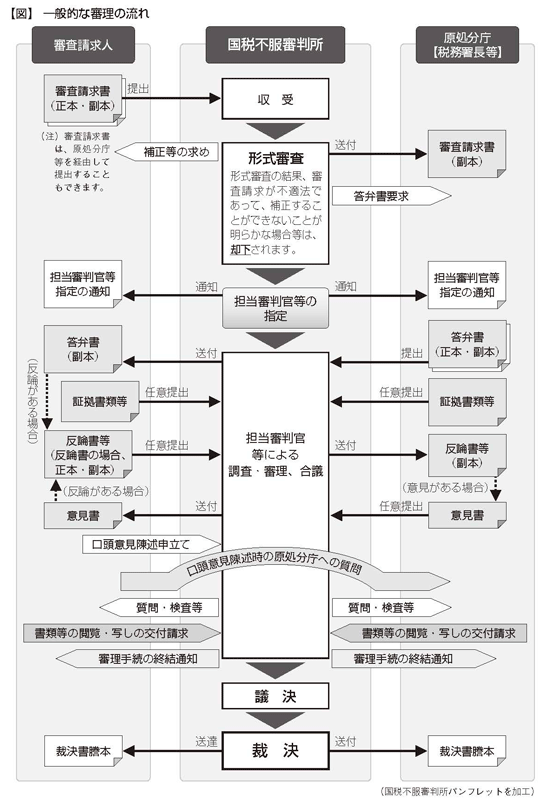
直接審査請求での答弁書作成、課税当局に一定のリスク
短期間で再調査請求書並みの記載必要
昨年4月に施行された改正国税不服申立制度について、課税当局では、直接審査請求や証拠書類の閲覧・謄写の範囲拡大などへの対応を迫られた模様だ。特に、直接審査請求における答弁書の作成に関しては、国税不服審判所が定める提出期限が短いなか、再調査請求書と同程度の記載を求められることから、答弁書作成に係る実践的な研修も行われている。
改正国税不服申立制度は多大な影響及ぼす 改正国税不服申立制度が、不服申立事務に限らず、調査事務および審理事務にも多大な影響を及ぼすとする課税当局では、改正により可能となった直接審査請求への対応に追われたようだ。特に、課題とされたのは、直接審査請求における答弁書の作成だ。
答弁書は、国税不服審判所長が、原処分庁に対して、審査請求の趣旨および理由に対する原処分庁の主張の記載を求めるもの(図参照)。ただし、不服審査通達(国税庁関係)93-1(答弁書の記載程度)では、審査請求の理由の内容・程度が再調査の請求と同様であり、原処分庁の主張も再調査決定書に記載した決定理由と同様であれば、その決定の理由を答弁書に引用しても差し支えないとされている。再調査の請求の場合、その標準審理期間は3か月とされていることから、その間、事案の調査・審理を行い、再調査決定書に決定の理由を記載することができる。
答弁書未提出による審理手続の終結を懸念 一方、直接審査請求における答弁書の提出期限については、国税不服審判所長が、「相当の期間」を定めると規定されている(通則法93①)。この「相当の期間」について、不服審査通達(国税不服審判所関係)93-1では、審査請求の対象とされた処分の内容やその審査請求が再調査の請求についての決定を経たものであるかなどの事情に応じて定められるべきものとされているが、国税不服審判所は、課税当局に対して、4週間以内の答弁書提出を求めている模様だ。
審査請求事案における答弁書の作成について課税当局は、提出期間内に答弁書を提出しないことで、担当審判官が審理手続を終了する場合(通則法97の4②)があることを懸念。答弁書を早期作成することで、提出期限を遵守するよう努めるとしている。そのうえで、「特に、直接審査請求事案については、短期間で再調査請求書と同程度の記載が求められることから、その進捗状況や問題点等の把握に努めるとともに、適切かつ迅速な事案の処理が行われるよう、必要となる事務量を確保する」旨を指示。答弁書作成の実践的な研修を実施するなど、対応を図っている。
なお、国税不服審判所は、課税当局に対し、請求人の反論書に対する意見書、審判官からの主張内容の確認に対する回答書の提出期限を3週間以内と定めているようだ。
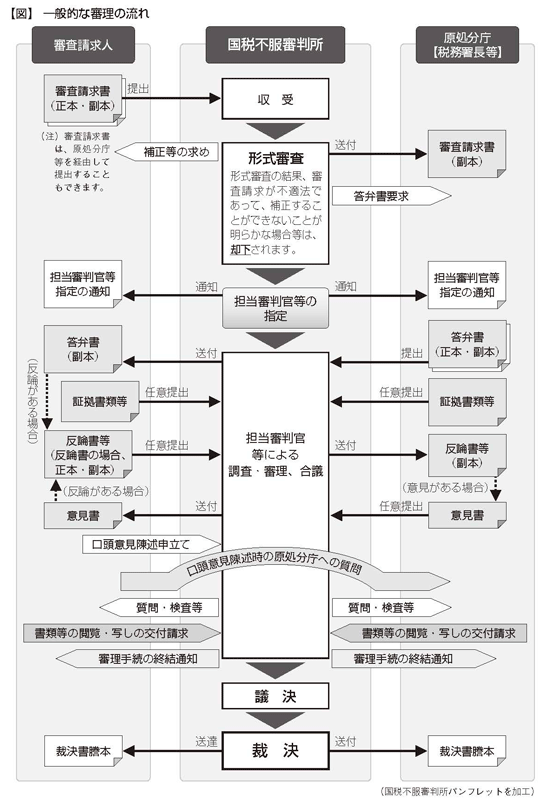
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















