解説記事2024年09月09日 SCOPE 通達評価額とのかい離のみで“特段の事情”ありとは言えず(2024年9月9日号・№1042)
総則6項適用事案、控訴審でも国側敗訴
通達評価額とのかい離のみで“特段の事情”ありとは言えず
総則6項の適用を巡っては、令和4年4月19日の最高裁判決により総則6項の適用と租税法における平等原則の関係についての考え方が示されたが、当該最高裁判決以来初の総則6項適用事案となった令和6年1月18日東京地裁判決では、総則6項の適用を否認する判決が下されたところだ。
国の控訴に対しどのような判断が示されるのか注目を集めていたが、東京高裁第12民事部(梅本圭一郎裁判長)は令和6年8月28日、総則6項を適用すべき“特段の事情”はないとした原判決を支持し、国の控訴を棄却した。
地裁、租税負担の公平に反する“特段の事情”なし
本件の事案の概要は図表のとおり。被相続人A氏は生前、Y社に対し自身が代表取締役を務めるX社株式を譲渡することについて基本合意を締結したが死亡。被相続人A氏が所有していた株式はA氏の妻と原告である子らが相続し、その後、全株主の保有する株式が妻に譲渡されてから、本件基本合意で合意された価額と同じ価額(1株当たり10万5,068円)で妻からY社に譲渡された。
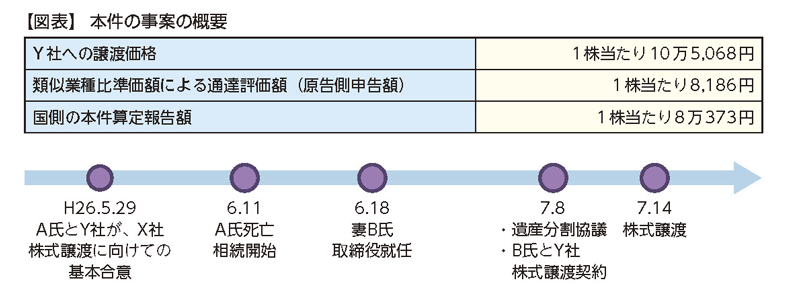
本件相続人らは、相続税の申告において、本件相続株式の価額を評価通達180に定める類似業種比準価額によって1株当たり8,186円(本件通達評価額)と算定したが、処分行政庁は評価通達6(総則6項)を適用。本件相続株式の価額は、国税庁長官の指示を受けて算定した価額である本件算定報告額(1株当たり8万373円)によるべきとして更正処分等を行った。
本件は、これを不服とした原告らが当該更正処分等の取消しを求め、訴訟に至った事案である。
令和4年最高裁判決の判断枠組みを引用
一審の東京地裁は、令和4年最高裁判決の判断枠組みを引用し、本件相続株式について、「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」(特段の事情)があるか否かを検討した。
東京地裁は、本件のように、相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が評価通達の定める方法による評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利得があるという評価をすることは相当ではないとし、評価通達6を納税者にとって不利に適用するに当たっては、一定の納税者側の事情が必要との考えを示した。
その上で、本件にはそのような事情がないから、評価通達6を適用した本件更正処分等は、平等原則という観点から違法であると結論づけていた。
高裁、本件売却価格が客観的交換価値を反映したものとは言えず
東京高裁も原判決を支持。ただし、判決文の「当てはめ」の部分はすべて補正した。
東京高裁はまず、評価通達6を適用すべき根拠として、「本件通達評価額と本件相続開始日における交換価値との間に著しいかい離があり、被控訴人らがそのことを十分に認識することは可能であった」とする国の主張に対し、「取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得ないものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。とりわけ、M&Aが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない」とした。そして、譲渡予定価格と通達評価額が大きく乖離しているからといって、上記の“特段の事情”が存在していたとはいえないという、原判決と同様の考えを示した。
続いて、「相続開始時に売買契約成立に至っていなかったとしても、近い将来売買契約が成立し、売買代金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値が現実的に実現する蓋然性が高いものとして、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が一つの基準になり得る」との国の主張に対しては、「近い将来における売買契約の成立及び売買代金債権への転化の蓋然性の程度を基準にすることは適切でない」し、本件については、その蓋然性が高かったと認めることはできないとした。
さらに、本件被相続人又は被控訴人らが相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたと認めることはできず、本件被相続人又は被控訴人らの行為に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はないとの考えも示した。
なお、評価通達6の適用に当たり、租税回避行為があることは要件とならないとする国の主張に対しては、「当裁判所はそのような要件が存するものと説示しているものではないから、同主張に対する判断の必要はない」としている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















