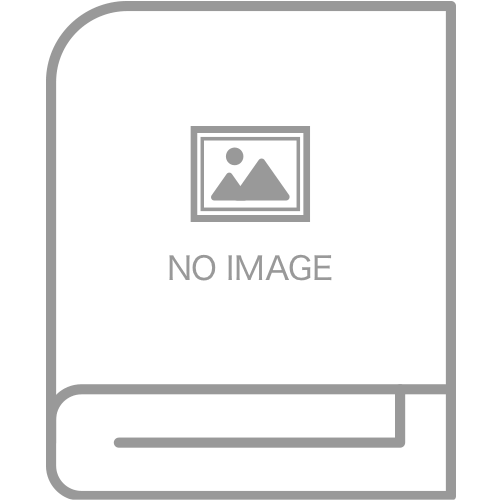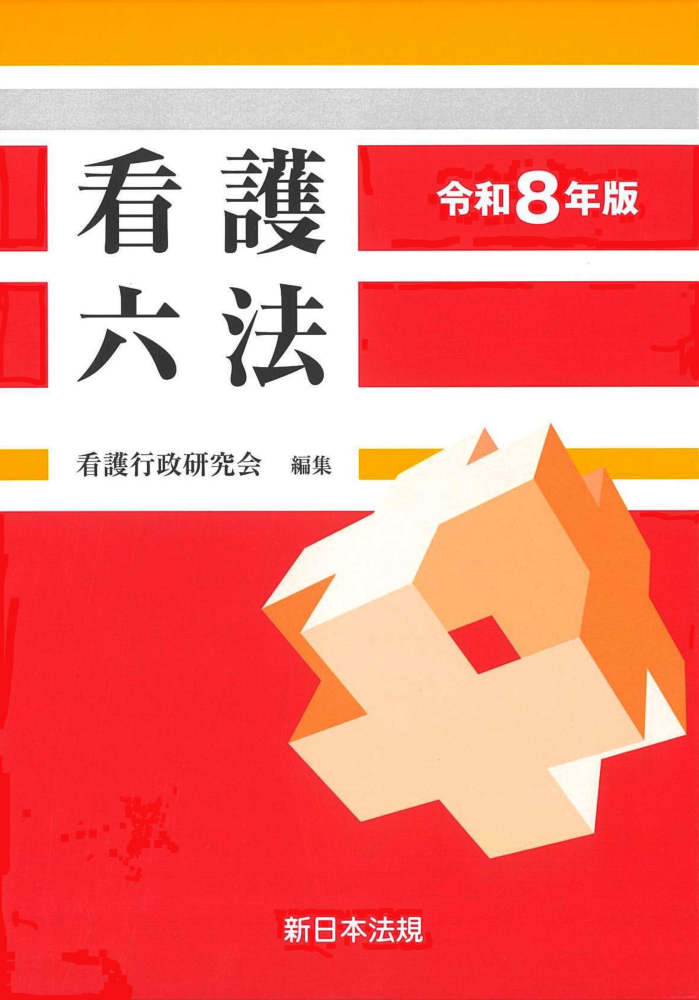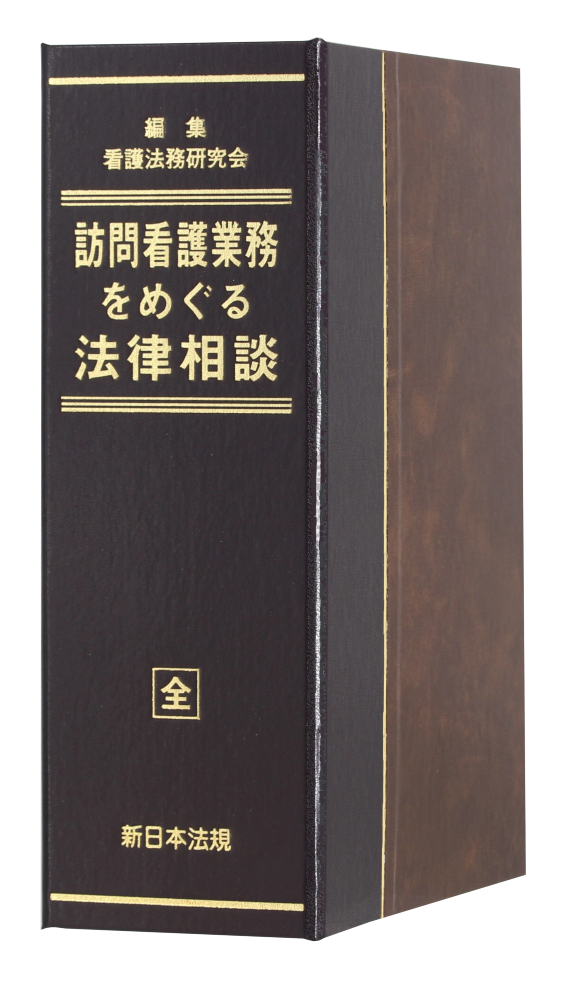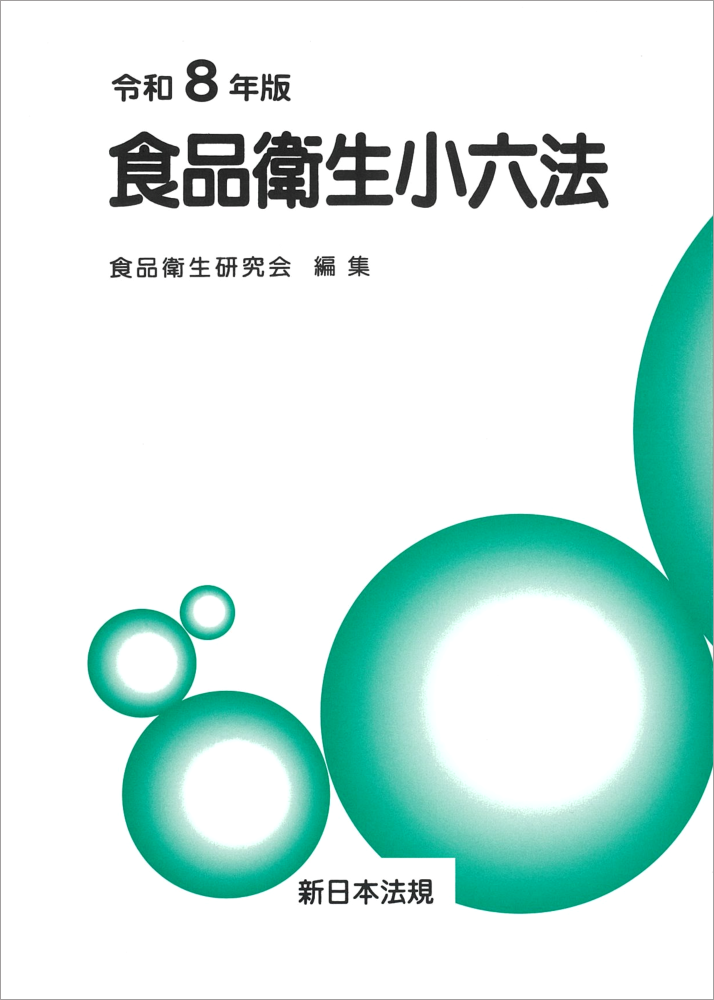概要
◆食品衛生に関する実務書の決定版!
食品衛生法の内容をはじめ、食品関連企業が日常業務で直面する諸問題を幅広く採り上げて、わかりやすく解説しています。食品関連業務に携わる方なら、せびとも備えておきたい一書です。
◆Q&Aでわかりやすく解説!
Q&A方式を採用し、具体的な質問に対して平易な言葉で解説しています。また、随所にイラストを用いて説明を補っていますので、容易に内容を理解することができます。
本書は、加除式電子版をご利用いただける書籍です。(無料)
加除式電子版閲覧サービスはこちら
商品情報
- 商品コード
- 0486
- サイズ
- B5判
- 巻数
- 全2巻・ケース付
- ページ数
- 1,646
- 発行年月
- 1999年11月
目次
第1 はじめに
食品衛生行政とは
新たな食品安全行政とは
食品安全基本法とは
食品衛生法とは
食品衛生法の改正(平成15年法律第55号)の内容は
食品衛生に関し、国・都道府県などはどのような責務を負うか
食品衛生に関し、食品等事業者はどのような責務を負うか
食品等事業者の記録の作成、保存にかかる指針(ガイドライン)とは
厚生労働大臣の実施するリスクコミュニケーションとは
法における食品等の取扱上の原則とは
高度化基盤整備の支援対象とは
コーデックス規格とは
第2 食品一般
1 一般的な禁止事項等
「食品」とは
販売が禁止されている不衛生食品とは
有毒・有害な物質を含む魚介類はどう取り扱うべきか
カビ毒(アフラトキシン)を含む食品はどう取り扱うべきか
ホルムアルデヒドを自然に含む食品はどう取り扱うべきか
ダニ類の付着した食品はどう取り扱うべきか
暫定的に販売が禁止される食品とは
食品または添加物が販売、輸入禁止となるのはどのような場合か
販売、輸入禁止となった食品の禁止措置を解除してもらうにはどうするか
販売が制限されている病肉とは
輸出水産食品に関する衛生証明書発行の手続は
輸出乳および乳製品に関する衛生証明書発行の手続は
自由販売証明書とは
2 規格および基準
「規格」および「基準」とは
食品に関する規格基準の概要は
食品中の放射性物質(セシウム)の基準値は
食品衛生法における「食品製造用水」および「飲用適の水」とは
清涼飲料水の規格基準は
食肉の規格基準は
生食用食肉の規格基準は
食鳥卵の規格基準は
食肉製品の規格基準は
魚肉ねり製品の規格基準は
魚卵加工品にはどのような規制があるか
ゆでだこの規格基準は
ゆでがにの規格基準は
生食用鮮魚介類の規格基準は
生食用かきの規格基準は
穀類、豆類および野菜の規格基準は
清浄野菜とは
生あんの規格基準は
豆腐の規格基準は
即席めん類の規格基準は
冷凍食品の規格基準は
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準は
油脂で処理した菓子にはどのような規制があるか
血液、血球および血漿の規格基準は
牛の肝臓の基準は
豚の食肉の基準は
指定成分等含有食品の基準は
「衛生規範」の廃止の背景とは
規格基準に違反したらどうなるか
3 各食品の取扱事項
ベビーフードの取扱指針とは
遺伝子組換え食品はどう取り扱われているか
遺伝子組換え食品の安全審査はどうなっているか
ゲノム編集技術応用食品はどう取り扱われているか
シンフィツム(いわゆるコンフリー)を含む食品の取扱いはどうなっているか
指定成分等含有食品の取扱いと届出
指定成分等含有食品による健康被害情報の届出は
4 食品の安全確保に関するリスクコミュニケーション
食品健康影響評価(リスク評価)とは
リスクコミュニケーションとは
リスクコミュニケーションの必要性
リスクコミュニケーションはどのようなときに行うのか
リスクコミュニケーションの具体的な取組みは
有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響評価は
第3 乳および乳製品
生乳・生山羊乳・生めん羊乳・生水牛乳の定義および規格基準は
牛乳・特別牛乳・殺菌山羊乳・成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳の定義および規格基準は
クリームの定義および規格基準は
バター・バターオイルの定義および規格基準は
チーズ・濃縮ホエイの定義および規格基準は
アイスクリーム類の定義および規格基準は
濃縮乳・練乳の定義および規格基準は
粉乳の定義および規格基準は
調製粉乳の定義および規格基準は
調製液状乳の定義および規格基準は
育児用調整粉乳の衛生的取扱いは
発酵乳・乳酸菌飲料の定義および規格基準は
乳飲料の定義および規格基準は
乳等の容器包装や原材料の規格基準は
常温保存可能品とは
第4 添加物
「添加物」とは
添加物にはどのような規制があるか
添加物に関する規格基準の概要は
添加物の使用基準はどうなっているか
甘味料とは
着色料とは
保存料とは
増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料とは
酸化防止剤とは
発色剤とは
漂白剤とは
防カビ・防ばい剤とは
生鮮野菜や鮮魚に対する添加物の使用制限はどうなっているか
添加物の指定手続は
食品添加物公定書とは
第5 残留農薬等
残留農薬の規制とは
残留農薬基準とその設定方法は
残留農薬等におけるポジティブリスト制度とは
コーデックス食品規格と残留農薬基準の関係は
食品に含まれる農薬等の規制は
農薬取締法における登録保留基準や農薬使用基準とは
基準未設定の農薬はどう取り扱われるか
ポストハーベスト農薬の規制はどうなっているか
食品中のPCB規制はどうなっているか
食品中のダイオキシン類の現状とその対策はどうなっているか
魚介類の水銀の規制はどうなっているか
食品中の残留農薬等試験法は
残留農薬迅速分析法とは
加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の迅速検出法は
動物用医薬品や飼料添加物にはどのような規制があるか
養殖魚に使用される水産用医薬品にはどのような規制があるか
内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)とは
第6 器具および容器包装
「器具」および「容器包装」とは
器具および容器包装にはどのような規制があるか
器具および容器包装が販売、輸入禁止となるのはどのような場合か
器具等の規格基準の概要は
ガラス製・陶磁器製・ホウロウ引きの器具または容器包装の規格基準は
合成樹脂製の器具または容器包装の規格基準は
ゴム製の器具および容器包装の規格基準は
金属缶の規格基準は
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装の規格は
清涼飲料水の容器包装の規格は
氷菓の製造等に使用する器具の規格は
食品の自動販売機および使用容器の規格は
コップ販売式自動販売機等に収められる清涼飲料水等の原液の運搬器具または容器包装の規格は
器具および容器包装に添加される着色料はどう取り扱われるか
器具および容器包装におけるリサイクル材料の使用はどう取り扱われるか
器具および容器包装における再生紙の使用はどう取り扱われるか
第7 おもちゃ・洗浄剤
おもちゃの規制とは
おもちゃの規格基準は
洗浄剤の規制とは
洗浄剤の成分規格および使用基準は
第8 表 示
1 表示の基準
食品表示法とは
表示の基準とは
法律による表示の規制は
一般用加工食品の表示すべき事項は
業務用加工食品の表示すべき事項は
食品等の名称の表示はどのようにすべきか
消費期限または賞味期限の記載はどのようにすべきか
消費期限・賞味期限はどのように決定すべきか
製造所所在地・製造者氏名等の表示はどのようにすべきか
製造所固有の記号による表示とは
食品に含まれる添加物およびその製剤の表示はどのようにすべきか
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは
保存方法や使用方法の表示はどのようにすべきか
詰合せ食品の表示方法について気をつけることは
容器包装の面積が狭い場合の表示はどのようにすべきか
輸入食品の表示はどのようにすべきか
遺伝子組換え食品の表示はどうなっているか
ゲノム編集技術応用食品の表示はどうなっているか
アレルギー物質を含む食品の表示はどうなっているか
新しい原料原産地の表示方法は
冠表示とは
旧来の対象となっていた加工食品の原料原産地の表示の取扱いは
栄養成分表示はどうなっているのか
特色のある原材料に関する表示はどのようにすべきか
乳児用規格適用食品の表示はどのようにすべきか
インストア加工された食品の表示事項は
外食やインストア加工用の食品に表示すべき事項は
一般用生鮮食品の表示すべき事項は
業務用生鮮食品の表示すべき事項は
販売用の添加物の表示すべき事項は
2 各食品における表示
乳等に関する表示はどのようにすべきか
缶詰食品の表示はどのようにすべきか
食肉・食肉製品の表示はどのようにすべきか
生食用食肉の表示はどのようにすべきか
容器包装に入れられた玄米・精米に関する表示はどのようにすべきか
清涼飲料水の表示はどのようにすべきか
酒類の表示はどのようにすべきか
折詰弁当、サンドウィッチなどの表示はどのようにすべきか
ふぐ加工品等の表示はどのようにすべきか
魚肉練り製品の表示はどのようにすべきか
調理冷凍食品の表示はどのようにすべきか
3 健康食品の表示・広告
「健康食品」とは
「健康食品」の表示はどのようにすべきか
「いわゆる健康食品」の摂取量・摂取方法の表示はどのようにすべきか
錠剤、カプセル状等食品の製造における留意点は
痩身効果等を表示してもよいか
誇大表示かどうかの判断基準は
他の食品との比較を表示できるか
「バナー広告」の食品広告としての取扱いは
「バイブル本」の食品広告としての取扱いは
「健康食品」の安全性・有効性データベースとは
ゲルマニウムやアミノ酸を含む健康食品はどう取り扱われているか
大豆イソフラボンを含む「いわゆる健康食品」はどう取り扱われているか
コエンザイムQ10を含む「いわゆる健康食品」はどう取り扱われているか
JHFAマークとは
GMP認定制度とは
安全性自主点検認証登録制度とは
4 保健機能食品等の表示
保健機能食品とは
特定保健用食品の表示基準とは
特定保健用食品の表示許可申請の手続は
特定保健用食品の再許可等の申請は
特定保健用食品による健康被害情報の届出は
条件付き特定保健用食品とは
規格基準型の特定保健用食品とは
疾病リスク低減表示とは
特別用途食品の表示許可制度と申請の手続は
病者用食品の表示に関する取扱いは
乳児用・妊産婦または授乳婦用特別用途食品の表示の取扱いは
特別用途食品のえん下困難者用食品(とろみ調整用食品を含む)の表示に関する取扱いは
機能性表示食品とは
機能性表示食品に必要な表示は
機能性表示を行うための手続は
機能性表示食品の対象は
機能性表示食品等における錠剤、カプセル剤等食品の製造管理および品質管理における適正製造規範(GMP)基準の適合とは
機能性表示食品における遵守事項に関する届出者の自己チェック等に係る事項とは
機能性表示食品による健康被害情報の届出は
第9 検査、監視指導
1 検査制度
製品検査の制度とは
製品検査を受ける場合の手続きは
製品検査の方法および合格の基準は
製品検査合格証の表示はどうするか
食品等に対する検査命令の制度とは
検査命令を受けた場合の手続きは
獣畜のと畜検査とは
と畜場法が定める衛生管理責任者および作業衛生責任者の業務や資格は
食鳥の検査制度とは
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に定める食鳥処理衛生管理者の業務や資格は
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザウイルスが存在した鶏肉・鶏卵は食べても大丈夫か
牛海綿状脳症(BSE)とは
牛海綿状脳症(BSE)に関する検査は
牛海綿状脳症対策特別措置法とは
牛海綿状脳症対策基本計画とは
2 輸入食品等の監視指導
輸入食品等に対してどのような安全対策がとられているか
輸入食品監視指導計画とは
食品の輸入事業者が自主的に実施することとされている衛生管理とは
輸入加工食品の自主管理はどのようにすべきか
輸入食品のモニタリング検査の方法は
届出が必要な輸入食品等とは
届出の不要な輸入食品にはどのようなものがあるか
食品等の輸入届出の手続は
登録番号の取得方法はどうなっているか
食品等の輸入届出手続の特例とは
届出事項に訂正または変更があった場合の手続きは
同一食品等を継続的に輸入する場合の手続はどうなるか
検査はどのような基準で行われるか
外国で行われた検査結果は有効か
輸入食品等事前確認制度とは
事前確認制度を受ける場合の手続等は
シアン化合物含有豆類はどう取り扱われるか
輸入食品の放射能濃度に対する監視指導は
輸入食品衛生管理者制度とは
野菜や果実を輸入する場合の注意すべきことは
食肉等の輸入とHACCPの衛生管理
輸入食肉等の衛生証明書とは
輸入乳製品の衛生証明書とは
輸入魚介類の衛生証明書と取扱い
健康食品・無承認無許可医薬品健康被害の防止に向けての対応は
抗生物質耐性菌による食品汚染とは
3 検査機関、監視機関等
食品衛生検査施設とは
衛生検査施設の業務管理(GLP)基準とは
食品衛生監視員による監視制度とは
食品衛生監視員にはどのような職務権限があるか
食品衛生監視員が交付する収去証とは
食品衛生監視票とは
監視指導指針にはどのようなことが定められているか
都道府県等食品衛生監視指導計画とは
登録検査機関制度とは
登録検査機関となるための具体的要件は
登録検査機関の登録申請手続は
登録検査機関の遵守事項は
二枚貝の貝毒の検査・監視指導は
食品衛生にかかわる審議はどこで行うのか
食品衛生推進員とは
第10 衛生管理
1 衛生管理体制
HACCP導入について
コーデックス委員会のHACCPガイドラインとは
コーデックス委員会のHACCP12手順とは
HACCPシステムにおける5Sの必要性とは
食品衛生法51条に規定する「公衆衛生上必要な基準」とは
食品衛生法施行規則66条の2に規定する「衛生管理計画」とは
食品衛生法施行規則66条の2に規定する「手順書」とは
HACCPを実施するためにどのような社内管理体制とするか
総合衛生管理製造過程の承認はどのようなものか
食品衛生管理者の制度とは
食品衛生管理者に必要な資格は
食品衛生管理者の届出等の手続は
2 一般的衛生管理
一般衛生管理とは
一般的な衛生管理とHACCPの関係は
HACCPのCCP管理に関する誤解とは
(1) 食品衛生責任者等の選任
食品衛生責任者等の制度とは
(2) 施設の衛生管理
施設の衛生管理はどのように行うべきか
施設設備はどのような構造にすべきか
消毒・洗浄にはどのような方法があるか
(3) 設備の衛生管理
冷蔵庫・冷凍庫の衛生管理はどのように行うべきか
食品庫の衛生管理はどのように行うべきか
器具等の衛生管理はどのように行うべきか
食器の衛生管理はどのように行うべきか
ふきん・タオル等の衛生管理はどのように行うべきか
営業用おしぼりの衛生管理はどのように行うべきか
食品販売用自動販売機の衛生的な取扱いはどうすべきか
病院給食の衛生管理はどのように行うべきか
生食用かきのむき身作業や施設等において注意すべきことは
包装冷凍食肉の自動販売機における衛生管理はどうなっているか
掃除道具の衛生管理はどのように行うべきか
(4) 使用水等の管理
使用水の衛生管理はどのように行うべきか
(5) ねずみおよび害虫対策
害虫駆除はどのように行うべきか
(6) 廃棄物および排水の取扱い
調理廃棄物の衛生管理はどのように行うべきか
(7) 食品または添加物を取り扱う者の衛生管理
食品に携わる人の正しい服装とは
正しい手洗いの方法は
正しいアルコール消毒の方法は
検便の目的と方法は
(8) 検食の実施
検食の採取および量は
製造業における検査用検体の保存はどのようにするのか
(9) 情報の提供
製品についての消費者への情報提供は
(10) 回 収
回収のシミュレーションはどのように行うか
回収報告への対応(食品リコール)とは
(11) 運 搬
食品安全のための食品事業者の運搬に対する自主管理と2024年問題への対応
(12) 販 売
販売における衛生管理の責任は
(13) 教育訓練
食品事業者の衛生教育は
教育・訓練の実施
(14) その他
食品安全文化に関連して
5S活動について
3 一般衛生管理(個別の食品等の衛生的取扱い)
個別の食品の一般衛生管理の概要
食肉類を取り扱う場合に気をつけることは
魚介類を扱う場合に気をつけることは
野菜・果物を取り扱う場合に気をつけることは
鶏卵を取り扱う場合に気をつけることは
乳製品を取り扱う場合に気をつけることは
飲料を取り扱う場合に気をつけることは
調理の下処理作業で気をつけることは
加熱調理作業で気をつけることは
調理済食品を取り扱う場合に気をつけることは
イクラ製品の取扱いはどうなっているか
野生鳥獣肉を食肉処理する場合に気をつけることは
野生鳥獣肉を調理・販売する場合に気をつけることは
4 HACCPによる衛生管理
HACCPに沿った衛生管理とは
「HACCPに基づく衛生管理」とは
危害要因の分析はどのような手順で行うか(手順6)
重要管理点(CCP)の設定の方法はどのようにすればよいか(手順7)
管理基準の設定とは
モニタリング方法の設定(手順9・原則4)
改善措置(是正措置)の設定とは
HACCPプランの妥当性確認および検証手順の確認・構築方法とは
記録の作成とは
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは
食品衛生法施行令34条の2に規定する「小規模な営業者等」とは
HACCPの第三者認証とは
ハザード分析の方法は
機器の校正に関して
5 ロボットシステム
「食品製造現場におけるロボット等導入及び運用時の衛生管理ガイドライン」とは
ロボットシステムの設置から運用開始前までの留意点および運用開始後の維持管理はどのようにすればよいか
第11 食中毒
1 食中毒とは
食中毒とは
細菌性食中毒とは
自然毒食中毒とは
化学性食中毒とは
赤痢菌による食中毒
ノロウイルス食中毒とは
ウエルシュ菌食中毒とは
カンピロバクター食中毒とは
寄生虫を原因とする食中毒とは
ヒスタミンによる食中毒とは
E型肝炎ウイルス感染事例について
いわゆる感染症予防法で定める「感染症」と食品衛生のかかわりとは
2 食中毒の予防対策
食中毒予防のポイントは
腸管出血性大腸菌による食中毒の予防対策は
容器包装詰食品のボツリヌス食中毒の予防対策は
黄色ブドウ球菌食中毒とその予防対策とは
災害時における食の安全・予防対策(または確保)とは
3 食中毒事故の処理
食中毒事故に対してどのような処理体制がとられているか
食中毒調査はどのように行われるか
食中毒事故が生じた場合、どのような行政措置がとられるか
「死体の解剖」はどのような場合に行われるか
第12 営 業
1 営業許可制度
営業の許可制度とは
他の営業許可制度との関係は
2 営業施設基準
営業許可を受けるための施設基準とは
営業施設基準の内容は
調理機能を有する自動販売機の営業許可と衛生管理はどのように行うべきか
生食用食肉を取り扱う場合の営業施設基準は
3 営業の許可
営業の許可申請手続は
登記手続未了法人から営業許可申請がなされる場合は
未成年者から営業許可申請がなされる場合は
営業許可の欠格事由とは
営業許可に条件が付される場合とは
飲食店営業の許可を要する「調理」行為とは
ホテル・旅館における飲食店営業の取扱いは
ホテル・旅館の経営を兼ねる飲食店営業の取扱いは
菓子製造業の範囲は
食品の小分け業および密封包装食品製造業の範囲は
漬物製造の範囲
同一施設内で複数の営業を営む場合の取扱いは
同一施設内で個別に調理室を設ける場合の取扱いは
パチンコ屋の食品提供行為の取扱いは
露店飲食店等営業者の取扱いは
自動車の移動販売に関する取扱いは
飲食店がテイクアウトサービス等を始める場合の注意事項は
相続・合併・分割・事業譲渡による地位承継と届出について
食品関係営業者に対する融資制度は
食品衛生申請等システムとは
4 営業届出制度
営業届出制度とは
営業届出制度の対象事業者とは
水の量り売りを行う自動販売機の取扱いは
集団給食施設とは
5 行政処分、罰則等
営業者の食品衛生法違反に対する処分とは
長期にわたって休業している施設の許可は取り消されるか
無許可営業者が事故を起こした場合の処分は
行政処分に不服がある場合は
食品衛生法における罰則は
食品リコール情報の報告制度
第13 食品リサイクル
食品リサイクル法とは
食品リサイクルの対象者は
「食品循環資源」とは
「食品関連事業者」とは
「再生利用等」とは
食品関連事業者の「判断の基準となるべき事項」とは
再生利用等の取組みの評価は
食品リサイクル法における罰則は
附 録
食品添加物使用基準等一覧
食品衛生法に定める登録検査機関
食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設一覧
保健所一覧
食品衛生関係団体一覧
食品衛生行政とは
新たな食品安全行政とは
食品安全基本法とは
食品衛生法とは
食品衛生法の改正(平成15年法律第55号)の内容は
食品衛生に関し、国・都道府県などはどのような責務を負うか
食品衛生に関し、食品等事業者はどのような責務を負うか
食品等事業者の記録の作成、保存にかかる指針(ガイドライン)とは
厚生労働大臣の実施するリスクコミュニケーションとは
法における食品等の取扱上の原則とは
高度化基盤整備の支援対象とは
コーデックス規格とは
第2 食品一般
1 一般的な禁止事項等
「食品」とは
販売が禁止されている不衛生食品とは
有毒・有害な物質を含む魚介類はどう取り扱うべきか
カビ毒(アフラトキシン)を含む食品はどう取り扱うべきか
ホルムアルデヒドを自然に含む食品はどう取り扱うべきか
ダニ類の付着した食品はどう取り扱うべきか
暫定的に販売が禁止される食品とは
食品または添加物が販売、輸入禁止となるのはどのような場合か
販売、輸入禁止となった食品の禁止措置を解除してもらうにはどうするか
販売が制限されている病肉とは
輸出水産食品に関する衛生証明書発行の手続は
輸出乳および乳製品に関する衛生証明書発行の手続は
自由販売証明書とは
2 規格および基準
「規格」および「基準」とは
食品に関する規格基準の概要は
食品中の放射性物質(セシウム)の基準値は
食品衛生法における「食品製造用水」および「飲用適の水」とは
清涼飲料水の規格基準は
食肉の規格基準は
生食用食肉の規格基準は
食鳥卵の規格基準は
食肉製品の規格基準は
魚肉ねり製品の規格基準は
魚卵加工品にはどのような規制があるか
ゆでだこの規格基準は
ゆでがにの規格基準は
生食用鮮魚介類の規格基準は
生食用かきの規格基準は
穀類、豆類および野菜の規格基準は
清浄野菜とは
生あんの規格基準は
豆腐の規格基準は
即席めん類の規格基準は
冷凍食品の規格基準は
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格基準は
油脂で処理した菓子にはどのような規制があるか
血液、血球および血漿の規格基準は
牛の肝臓の基準は
豚の食肉の基準は
指定成分等含有食品の基準は
「衛生規範」の廃止の背景とは
規格基準に違反したらどうなるか
3 各食品の取扱事項
ベビーフードの取扱指針とは
遺伝子組換え食品はどう取り扱われているか
遺伝子組換え食品の安全審査はどうなっているか
ゲノム編集技術応用食品はどう取り扱われているか
シンフィツム(いわゆるコンフリー)を含む食品の取扱いはどうなっているか
指定成分等含有食品の取扱いと届出
指定成分等含有食品による健康被害情報の届出は
4 食品の安全確保に関するリスクコミュニケーション
食品健康影響評価(リスク評価)とは
リスクコミュニケーションとは
リスクコミュニケーションの必要性
リスクコミュニケーションはどのようなときに行うのか
リスクコミュニケーションの具体的な取組みは
有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響評価は
第3 乳および乳製品
生乳・生山羊乳・生めん羊乳・生水牛乳の定義および規格基準は
牛乳・特別牛乳・殺菌山羊乳・成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳の定義および規格基準は
クリームの定義および規格基準は
バター・バターオイルの定義および規格基準は
チーズ・濃縮ホエイの定義および規格基準は
アイスクリーム類の定義および規格基準は
濃縮乳・練乳の定義および規格基準は
粉乳の定義および規格基準は
調製粉乳の定義および規格基準は
調製液状乳の定義および規格基準は
育児用調整粉乳の衛生的取扱いは
発酵乳・乳酸菌飲料の定義および規格基準は
乳飲料の定義および規格基準は
乳等の容器包装や原材料の規格基準は
常温保存可能品とは
第4 添加物
「添加物」とは
添加物にはどのような規制があるか
添加物に関する規格基準の概要は
添加物の使用基準はどうなっているか
甘味料とは
着色料とは
保存料とは
増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料とは
酸化防止剤とは
発色剤とは
漂白剤とは
防カビ・防ばい剤とは
生鮮野菜や鮮魚に対する添加物の使用制限はどうなっているか
添加物の指定手続は
食品添加物公定書とは
第5 残留農薬等
残留農薬の規制とは
残留農薬基準とその設定方法は
残留農薬等におけるポジティブリスト制度とは
コーデックス食品規格と残留農薬基準の関係は
食品に含まれる農薬等の規制は
農薬取締法における登録保留基準や農薬使用基準とは
基準未設定の農薬はどう取り扱われるか
ポストハーベスト農薬の規制はどうなっているか
食品中のPCB規制はどうなっているか
食品中のダイオキシン類の現状とその対策はどうなっているか
魚介類の水銀の規制はどうなっているか
食品中の残留農薬等試験法は
残留農薬迅速分析法とは
加工食品中に高濃度に含まれる農薬等の迅速検出法は
動物用医薬品や飼料添加物にはどのような規制があるか
養殖魚に使用される水産用医薬品にはどのような規制があるか
内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)とは
第6 器具および容器包装
「器具」および「容器包装」とは
器具および容器包装にはどのような規制があるか
器具および容器包装が販売、輸入禁止となるのはどのような場合か
器具等の規格基準の概要は
ガラス製・陶磁器製・ホウロウ引きの器具または容器包装の規格基準は
合成樹脂製の器具または容器包装の規格基準は
ゴム製の器具および容器包装の規格基準は
金属缶の規格基準は
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装の規格は
清涼飲料水の容器包装の規格は
氷菓の製造等に使用する器具の規格は
食品の自動販売機および使用容器の規格は
コップ販売式自動販売機等に収められる清涼飲料水等の原液の運搬器具または容器包装の規格は
器具および容器包装に添加される着色料はどう取り扱われるか
器具および容器包装におけるリサイクル材料の使用はどう取り扱われるか
器具および容器包装における再生紙の使用はどう取り扱われるか
第7 おもちゃ・洗浄剤
おもちゃの規制とは
おもちゃの規格基準は
洗浄剤の規制とは
洗浄剤の成分規格および使用基準は
第8 表 示
1 表示の基準
食品表示法とは
表示の基準とは
法律による表示の規制は
一般用加工食品の表示すべき事項は
業務用加工食品の表示すべき事項は
食品等の名称の表示はどのようにすべきか
消費期限または賞味期限の記載はどのようにすべきか
消費期限・賞味期限はどのように決定すべきか
製造所所在地・製造者氏名等の表示はどのようにすべきか
製造所固有の記号による表示とは
食品に含まれる添加物およびその製剤の表示はどのようにすべきか
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは
保存方法や使用方法の表示はどのようにすべきか
詰合せ食品の表示方法について気をつけることは
容器包装の面積が狭い場合の表示はどのようにすべきか
輸入食品の表示はどのようにすべきか
遺伝子組換え食品の表示はどうなっているか
ゲノム編集技術応用食品の表示はどうなっているか
アレルギー物質を含む食品の表示はどうなっているか
新しい原料原産地の表示方法は
冠表示とは
旧来の対象となっていた加工食品の原料原産地の表示の取扱いは
栄養成分表示はどうなっているのか
特色のある原材料に関する表示はどのようにすべきか
乳児用規格適用食品の表示はどのようにすべきか
インストア加工された食品の表示事項は
外食やインストア加工用の食品に表示すべき事項は
一般用生鮮食品の表示すべき事項は
業務用生鮮食品の表示すべき事項は
販売用の添加物の表示すべき事項は
2 各食品における表示
乳等に関する表示はどのようにすべきか
缶詰食品の表示はどのようにすべきか
食肉・食肉製品の表示はどのようにすべきか
生食用食肉の表示はどのようにすべきか
容器包装に入れられた玄米・精米に関する表示はどのようにすべきか
清涼飲料水の表示はどのようにすべきか
酒類の表示はどのようにすべきか
折詰弁当、サンドウィッチなどの表示はどのようにすべきか
ふぐ加工品等の表示はどのようにすべきか
魚肉練り製品の表示はどのようにすべきか
調理冷凍食品の表示はどのようにすべきか
3 健康食品の表示・広告
「健康食品」とは
「健康食品」の表示はどのようにすべきか
「いわゆる健康食品」の摂取量・摂取方法の表示はどのようにすべきか
錠剤、カプセル状等食品の製造における留意点は
痩身効果等を表示してもよいか
誇大表示かどうかの判断基準は
他の食品との比較を表示できるか
「バナー広告」の食品広告としての取扱いは
「バイブル本」の食品広告としての取扱いは
「健康食品」の安全性・有効性データベースとは
ゲルマニウムやアミノ酸を含む健康食品はどう取り扱われているか
大豆イソフラボンを含む「いわゆる健康食品」はどう取り扱われているか
コエンザイムQ10を含む「いわゆる健康食品」はどう取り扱われているか
JHFAマークとは
GMP認定制度とは
安全性自主点検認証登録制度とは
4 保健機能食品等の表示
保健機能食品とは
特定保健用食品の表示基準とは
特定保健用食品の表示許可申請の手続は
特定保健用食品の再許可等の申請は
特定保健用食品による健康被害情報の届出は
条件付き特定保健用食品とは
規格基準型の特定保健用食品とは
疾病リスク低減表示とは
特別用途食品の表示許可制度と申請の手続は
病者用食品の表示に関する取扱いは
乳児用・妊産婦または授乳婦用特別用途食品の表示の取扱いは
特別用途食品のえん下困難者用食品(とろみ調整用食品を含む)の表示に関する取扱いは
機能性表示食品とは
機能性表示食品に必要な表示は
機能性表示を行うための手続は
機能性表示食品の対象は
機能性表示食品等における錠剤、カプセル剤等食品の製造管理および品質管理における適正製造規範(GMP)基準の適合とは
機能性表示食品における遵守事項に関する届出者の自己チェック等に係る事項とは
機能性表示食品による健康被害情報の届出は
第9 検査、監視指導
1 検査制度
製品検査の制度とは
製品検査を受ける場合の手続きは
製品検査の方法および合格の基準は
製品検査合格証の表示はどうするか
食品等に対する検査命令の制度とは
検査命令を受けた場合の手続きは
獣畜のと畜検査とは
と畜場法が定める衛生管理責任者および作業衛生責任者の業務や資格は
食鳥の検査制度とは
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に定める食鳥処理衛生管理者の業務や資格は
鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザウイルスが存在した鶏肉・鶏卵は食べても大丈夫か
牛海綿状脳症(BSE)とは
牛海綿状脳症(BSE)に関する検査は
牛海綿状脳症対策特別措置法とは
牛海綿状脳症対策基本計画とは
2 輸入食品等の監視指導
輸入食品等に対してどのような安全対策がとられているか
輸入食品監視指導計画とは
食品の輸入事業者が自主的に実施することとされている衛生管理とは
輸入加工食品の自主管理はどのようにすべきか
輸入食品のモニタリング検査の方法は
届出が必要な輸入食品等とは
届出の不要な輸入食品にはどのようなものがあるか
食品等の輸入届出の手続は
登録番号の取得方法はどうなっているか
食品等の輸入届出手続の特例とは
届出事項に訂正または変更があった場合の手続きは
同一食品等を継続的に輸入する場合の手続はどうなるか
検査はどのような基準で行われるか
外国で行われた検査結果は有効か
輸入食品等事前確認制度とは
事前確認制度を受ける場合の手続等は
シアン化合物含有豆類はどう取り扱われるか
輸入食品の放射能濃度に対する監視指導は
輸入食品衛生管理者制度とは
野菜や果実を輸入する場合の注意すべきことは
食肉等の輸入とHACCPの衛生管理
輸入食肉等の衛生証明書とは
輸入乳製品の衛生証明書とは
輸入魚介類の衛生証明書と取扱い
健康食品・無承認無許可医薬品健康被害の防止に向けての対応は
抗生物質耐性菌による食品汚染とは
3 検査機関、監視機関等
食品衛生検査施設とは
衛生検査施設の業務管理(GLP)基準とは
食品衛生監視員による監視制度とは
食品衛生監視員にはどのような職務権限があるか
食品衛生監視員が交付する収去証とは
食品衛生監視票とは
監視指導指針にはどのようなことが定められているか
都道府県等食品衛生監視指導計画とは
登録検査機関制度とは
登録検査機関となるための具体的要件は
登録検査機関の登録申請手続は
登録検査機関の遵守事項は
二枚貝の貝毒の検査・監視指導は
食品衛生にかかわる審議はどこで行うのか
食品衛生推進員とは
第10 衛生管理
1 衛生管理体制
HACCP導入について
コーデックス委員会のHACCPガイドラインとは
コーデックス委員会のHACCP12手順とは
HACCPシステムにおける5Sの必要性とは
食品衛生法51条に規定する「公衆衛生上必要な基準」とは
食品衛生法施行規則66条の2に規定する「衛生管理計画」とは
食品衛生法施行規則66条の2に規定する「手順書」とは
HACCPを実施するためにどのような社内管理体制とするか
総合衛生管理製造過程の承認はどのようなものか
食品衛生管理者の制度とは
食品衛生管理者に必要な資格は
食品衛生管理者の届出等の手続は
2 一般的衛生管理
一般衛生管理とは
一般的な衛生管理とHACCPの関係は
HACCPのCCP管理に関する誤解とは
(1) 食品衛生責任者等の選任
食品衛生責任者等の制度とは
(2) 施設の衛生管理
施設の衛生管理はどのように行うべきか
施設設備はどのような構造にすべきか
消毒・洗浄にはどのような方法があるか
(3) 設備の衛生管理
冷蔵庫・冷凍庫の衛生管理はどのように行うべきか
食品庫の衛生管理はどのように行うべきか
器具等の衛生管理はどのように行うべきか
食器の衛生管理はどのように行うべきか
ふきん・タオル等の衛生管理はどのように行うべきか
営業用おしぼりの衛生管理はどのように行うべきか
食品販売用自動販売機の衛生的な取扱いはどうすべきか
病院給食の衛生管理はどのように行うべきか
生食用かきのむき身作業や施設等において注意すべきことは
包装冷凍食肉の自動販売機における衛生管理はどうなっているか
掃除道具の衛生管理はどのように行うべきか
(4) 使用水等の管理
使用水の衛生管理はどのように行うべきか
(5) ねずみおよび害虫対策
害虫駆除はどのように行うべきか
(6) 廃棄物および排水の取扱い
調理廃棄物の衛生管理はどのように行うべきか
(7) 食品または添加物を取り扱う者の衛生管理
食品に携わる人の正しい服装とは
正しい手洗いの方法は
正しいアルコール消毒の方法は
検便の目的と方法は
(8) 検食の実施
検食の採取および量は
製造業における検査用検体の保存はどのようにするのか
(9) 情報の提供
製品についての消費者への情報提供は
(10) 回 収
回収のシミュレーションはどのように行うか
回収報告への対応(食品リコール)とは
(11) 運 搬
食品安全のための食品事業者の運搬に対する自主管理と2024年問題への対応
(12) 販 売
販売における衛生管理の責任は
(13) 教育訓練
食品事業者の衛生教育は
教育・訓練の実施
(14) その他
食品安全文化に関連して
5S活動について
3 一般衛生管理(個別の食品等の衛生的取扱い)
個別の食品の一般衛生管理の概要
食肉類を取り扱う場合に気をつけることは
魚介類を扱う場合に気をつけることは
野菜・果物を取り扱う場合に気をつけることは
鶏卵を取り扱う場合に気をつけることは
乳製品を取り扱う場合に気をつけることは
飲料を取り扱う場合に気をつけることは
調理の下処理作業で気をつけることは
加熱調理作業で気をつけることは
調理済食品を取り扱う場合に気をつけることは
イクラ製品の取扱いはどうなっているか
野生鳥獣肉を食肉処理する場合に気をつけることは
野生鳥獣肉を調理・販売する場合に気をつけることは
4 HACCPによる衛生管理
HACCPに沿った衛生管理とは
「HACCPに基づく衛生管理」とは
危害要因の分析はどのような手順で行うか(手順6)
重要管理点(CCP)の設定の方法はどのようにすればよいか(手順7)
管理基準の設定とは
モニタリング方法の設定(手順9・原則4)
改善措置(是正措置)の設定とは
HACCPプランの妥当性確認および検証手順の確認・構築方法とは
記録の作成とは
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは
食品衛生法施行令34条の2に規定する「小規模な営業者等」とは
HACCPの第三者認証とは
ハザード分析の方法は
機器の校正に関して
5 ロボットシステム
「食品製造現場におけるロボット等導入及び運用時の衛生管理ガイドライン」とは
ロボットシステムの設置から運用開始前までの留意点および運用開始後の維持管理はどのようにすればよいか
第11 食中毒
1 食中毒とは
食中毒とは
細菌性食中毒とは
自然毒食中毒とは
化学性食中毒とは
赤痢菌による食中毒
ノロウイルス食中毒とは
ウエルシュ菌食中毒とは
カンピロバクター食中毒とは
寄生虫を原因とする食中毒とは
ヒスタミンによる食中毒とは
E型肝炎ウイルス感染事例について
いわゆる感染症予防法で定める「感染症」と食品衛生のかかわりとは
2 食中毒の予防対策
食中毒予防のポイントは
腸管出血性大腸菌による食中毒の予防対策は
容器包装詰食品のボツリヌス食中毒の予防対策は
黄色ブドウ球菌食中毒とその予防対策とは
災害時における食の安全・予防対策(または確保)とは
3 食中毒事故の処理
食中毒事故に対してどのような処理体制がとられているか
食中毒調査はどのように行われるか
食中毒事故が生じた場合、どのような行政措置がとられるか
「死体の解剖」はどのような場合に行われるか
第12 営 業
1 営業許可制度
営業の許可制度とは
他の営業許可制度との関係は
2 営業施設基準
営業許可を受けるための施設基準とは
営業施設基準の内容は
調理機能を有する自動販売機の営業許可と衛生管理はどのように行うべきか
生食用食肉を取り扱う場合の営業施設基準は
3 営業の許可
営業の許可申請手続は
登記手続未了法人から営業許可申請がなされる場合は
未成年者から営業許可申請がなされる場合は
営業許可の欠格事由とは
営業許可に条件が付される場合とは
飲食店営業の許可を要する「調理」行為とは
ホテル・旅館における飲食店営業の取扱いは
ホテル・旅館の経営を兼ねる飲食店営業の取扱いは
菓子製造業の範囲は
食品の小分け業および密封包装食品製造業の範囲は
漬物製造の範囲
同一施設内で複数の営業を営む場合の取扱いは
同一施設内で個別に調理室を設ける場合の取扱いは
パチンコ屋の食品提供行為の取扱いは
露店飲食店等営業者の取扱いは
自動車の移動販売に関する取扱いは
飲食店がテイクアウトサービス等を始める場合の注意事項は
相続・合併・分割・事業譲渡による地位承継と届出について
食品関係営業者に対する融資制度は
食品衛生申請等システムとは
4 営業届出制度
営業届出制度とは
営業届出制度の対象事業者とは
水の量り売りを行う自動販売機の取扱いは
集団給食施設とは
5 行政処分、罰則等
営業者の食品衛生法違反に対する処分とは
長期にわたって休業している施設の許可は取り消されるか
無許可営業者が事故を起こした場合の処分は
行政処分に不服がある場合は
食品衛生法における罰則は
食品リコール情報の報告制度
第13 食品リサイクル
食品リサイクル法とは
食品リサイクルの対象者は
「食品循環資源」とは
「食品関連事業者」とは
「再生利用等」とは
食品関連事業者の「判断の基準となるべき事項」とは
再生利用等の取組みの評価は
食品リサイクル法における罰則は
附 録
食品添加物使用基準等一覧
食品衛生法に定める登録検査機関
食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設一覧
保健所一覧
食品衛生関係団体一覧
この商品に関連するキーワード
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。