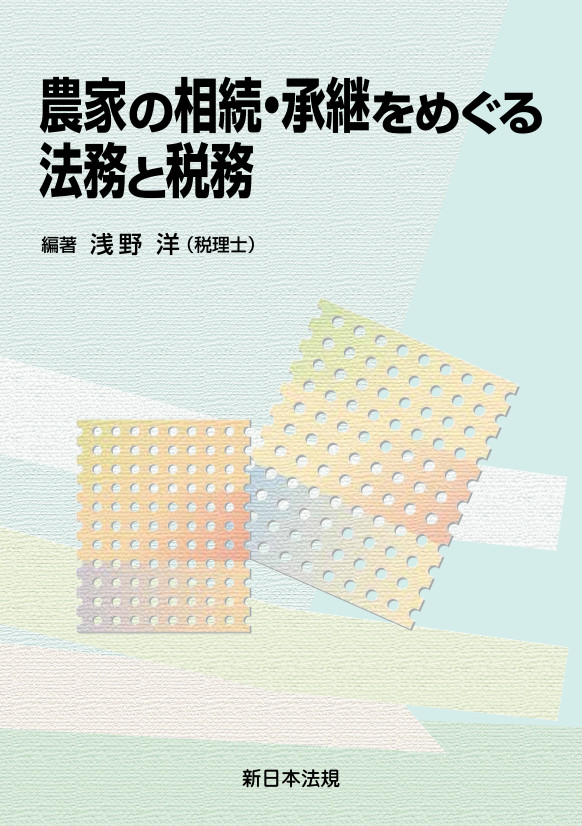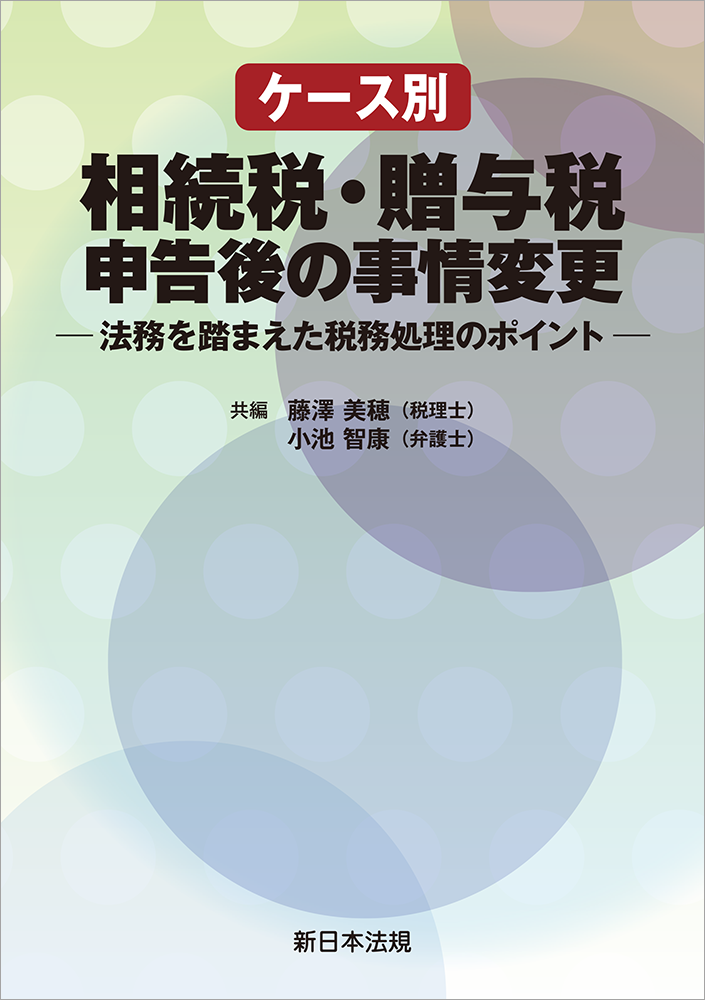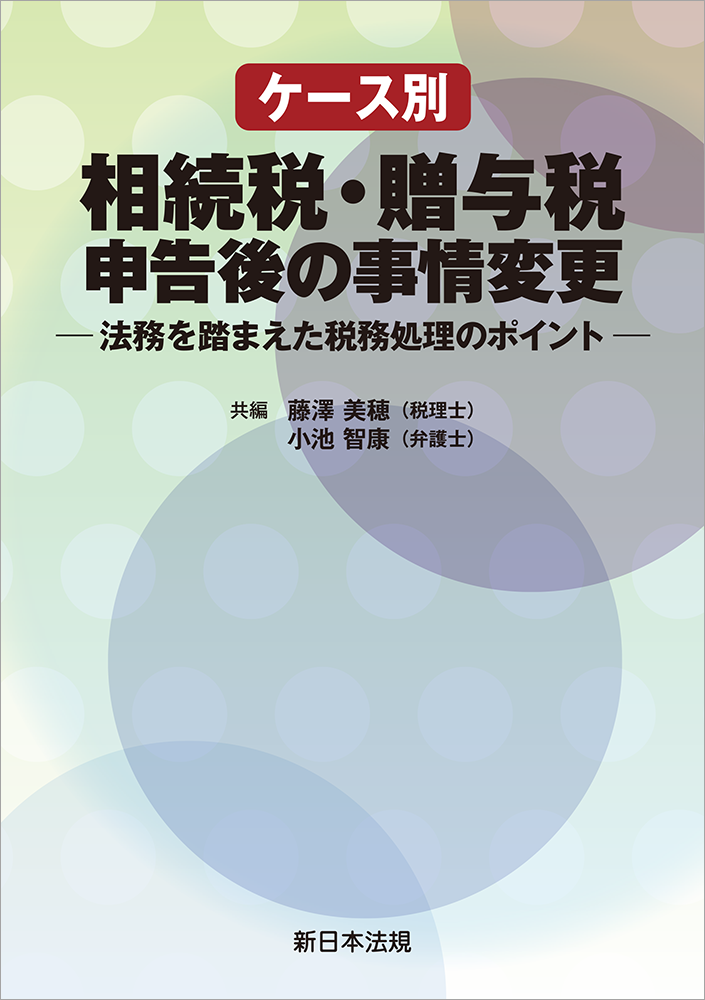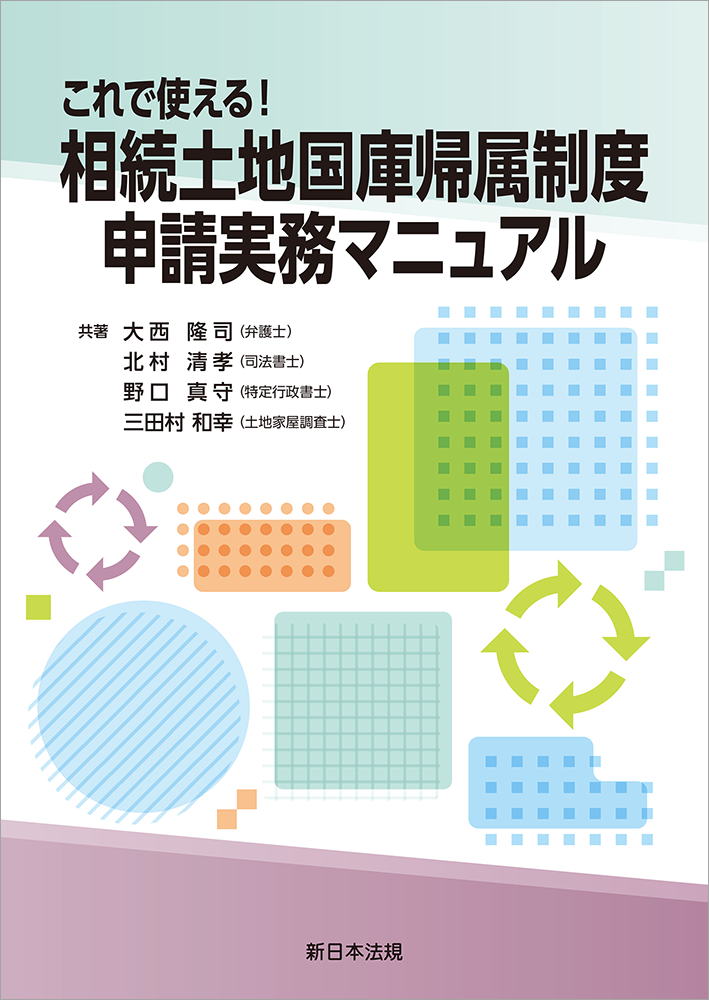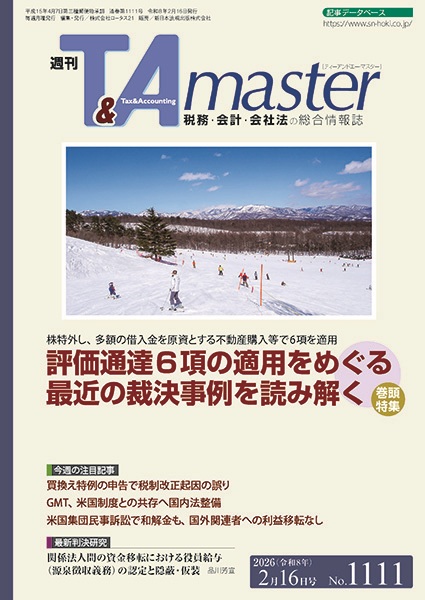概要
農地法の手続や納税猶予など相続・承継への対応方法がよくわかる!
◆農家の相続・承継において起こりがちな法務・税務に関する諸問題をQ&A形式でわかりやすく解説しています。
◆相続税・贈与税の納税猶予制度など「農業を承継する場合」に加え、農地の転用・譲渡など「農業を承継しない場合」についても触れています。
◆実務上の注意点や知っておくと役立つ知識を【memo】として掲げています。
商品情報
- 商品コード
- 50783
- ISBN
- 978-4-7882-7589-8
- JAN
- 9784788275898/1923032042000
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 430
- 発行年月
- 2012年5月
目次
第1章 農家における相続の概要
第1 相続と贈与
1 相続・贈与の税金
2 財産の分け方
3 相続税の課税財産と非課税財産
4 財産の評価と税額計算
第2 農業の承継
1 農業・農家をめぐる現代の情勢
2 農地をめぐる諸制度
第2章 農家の相続
第1 相続税額の計算
Q1 課税価格の計算
Q2 非課税財産・債務控除・生前贈与加算
Q3 遺産が未分割の場合
Q4 相続税の総額の計算
Q5 納付税額の計算
第2 贈与税額の計算
Q6 暦年課税額の計算
Q7 贈与税の非課税財産
第3 農地の相続・贈与
Q8 農地の相続・贈与に要する手続のあらまし
Q9 農地とは何か
Q10 市街化区域と市街化調整区域
Q11 生産緑地制度
Q12 農業後継者でなくてもいい
第4 農地以外の土地の相続
Q13 相続税の小規模宅地等の適用要件の厳格化
Q14 自宅の土地の取得者を誰にするか
第5 土地以外の相続
Q15 死亡共済金を受け取った場合
第3章 財産の評価
第1 土地および土地の上に存する権利の評価
Q16 土地の評価
Q17 農地の評価
Q18 宅地比準方式による市街地農地の評価
Q19 造成費の計算
Q20 耕作権の目的となっている農地の評価
Q21 市民農園として貸し付けられている農地の評価
Q22 生産緑地の評価
Q23 広大地の評価
Q24 接道義務を満たしていない土地の評価
Q25 がけ地等を有する土地の評価
Q26 農業用施設用地の評価
Q27 セットバックを必要とする土地の評価
Q28 土地区画整理事業中の宅地の評価
Q29 造成中の宅地の評価
Q30 河川を隔てて道路がある土地の評価
Q31 市街化調整区域内の雑種地の評価
Q32 定期借地権の底地の評価
第2 家屋および構築物の評価
Q33 家屋の評価
Q34 構築物の評価
第3 株式および出資の評価
Q35 上場株式の評価
Q36 出資金の評価
Q37 公社債の評価
第4 預貯金の評価
Q38 預貯金の評価
第5 その他の財産の評価
Q39 一般動産の評価
Q40 定期金に関する権利の評価(給付事由が発生している場合)
Q41 定期金に関する権利の評価(給付事由の発生していない場合)
Q42 生命保険契約に関する権利の評価
第4章 農業を承継する場合の法務と税務
第1 農業を承継する場合の法務
1 農地法上の手続
Q43 農地を贈与で取得した場合
Q44 農地を相続で取得した場合
2 遺言による相続
Q45 遺言の意義
Q46 遺言の種類
Q47 遺言の効果
Q48 遺言の作成方法
Q49 公正証書遺言の作成費用
Q50 死因贈与
Q51 成年後見制度
3 遺産分割・相続放棄
Q52 農地の遺産分割
Q53 遺産分割における債務の扱い
Q54 遺産分割前の相続分の譲渡
Q55 相続放棄
第2 農業を承継する場合の税務
1 相続税の納税猶予
Q56 相続税の納税猶予の特例
Q57 特定貸付による相続税の納税猶予継続
Q58 営農困難時貸付による相続税の納税猶予継続
Q59 相続税の納税猶予の対象となる農地
Q60 相続税の納税猶予の打切り
Q61 20%以下基準(相続税)
Q62 区画整理があった場合の相続税の納税猶予
2 贈与税の納税猶予
Q63 贈与税の納税猶予の特例
Q64 特定貸付による贈与税の納税猶予継続
Q65 営農困難時貸付による贈与税の納税猶予継続
Q66 贈与税の納税猶予の対象となる農地
Q67 贈与税の納税猶予の打切り
Q68 20%以下基準(贈与税)
Q69 区画整理があった場合の贈与税の納税猶予
第3 農地を保有する場合の税務
Q70 固定資産税の概要
Q71 固定資産税の算定方法
Q72 農地の固定資産税の仕組み
Q73 固定資産税の情報開示
第4 農業所得の申告方法
Q74 農業所得の申告方法
Q75 相続で引き継いだ事業用固定資産の取得価額
Q76 減価償却資産
Q77 無償使用の土地に対する固定資産税・租税公課の範囲
Q78 必要経費に算入できる登記費用等
第5章 農業を承継しない場合の法務と税務
第1 農業を承継しない場合の法務
Q79 市街化調整区域の農地を転用する場合の利用制限
第2 農業を承継しない場合の税務
1 土地を譲渡した場合の税金の計算
Q80 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
Q81 離作料・立毛補償金
Q82 低額譲渡とみなし譲渡課税
Q83 固定資産の交換の特例
Q84 事業用資産の買換え
Q85 農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
Q86 等価交換方式による立体買換え
Q87 特定の交換分合による面整備
Q88 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地を相続時まで保有した後離農する場合
2 定期借地権方式による土地活用
Q89 定期借地権の設定と所得税課税
3 農業法人をめぐる税務
Q90 農業生産法人
Q91 農事組合法人
Q92 特定農業法人
Q93 農住組合
4 相続時精算課税制度
Q94 相続時精算課税制度
5 配偶者控除・住宅取得資金贈与
Q95 贈与税の配偶者控除
Q96 贈与税の配偶者控除(居住用不動産の範囲)
Q97 住宅取得資金贈与
Q98 住宅取得資金贈与(相続時精算課税を選択した場合)
第6章 相続・承継に伴う手続と納税
第1 相続税の申告と登記
Q99 相続開始後の申告手続スケジュール
Q100 相続の登記費用
第2 相続税の納付方法
1 相続税の納付方法
Q101 相続税の納付方法
2 延納制度
Q102 延納制度とは
3 物納制度
Q103 農地の物納
Q104 仮換地の物納
Q105 定期借地権が設定された土地の物納
Q106 超過物納
Q107 物納適格財産と不適格財産
Q108 物納の取下げ・却下
Q109 生産緑地の物納
Q110 固定資産税の減免
Q111 資産の売却と物納の選択
Q112 特定物納
Q113 物納撤回
第1 相続と贈与
1 相続・贈与の税金
2 財産の分け方
3 相続税の課税財産と非課税財産
4 財産の評価と税額計算
第2 農業の承継
1 農業・農家をめぐる現代の情勢
2 農地をめぐる諸制度
第2章 農家の相続
第1 相続税額の計算
Q1 課税価格の計算
Q2 非課税財産・債務控除・生前贈与加算
Q3 遺産が未分割の場合
Q4 相続税の総額の計算
Q5 納付税額の計算
第2 贈与税額の計算
Q6 暦年課税額の計算
Q7 贈与税の非課税財産
第3 農地の相続・贈与
Q8 農地の相続・贈与に要する手続のあらまし
Q9 農地とは何か
Q10 市街化区域と市街化調整区域
Q11 生産緑地制度
Q12 農業後継者でなくてもいい
第4 農地以外の土地の相続
Q13 相続税の小規模宅地等の適用要件の厳格化
Q14 自宅の土地の取得者を誰にするか
第5 土地以外の相続
Q15 死亡共済金を受け取った場合
第3章 財産の評価
第1 土地および土地の上に存する権利の評価
Q16 土地の評価
Q17 農地の評価
Q18 宅地比準方式による市街地農地の評価
Q19 造成費の計算
Q20 耕作権の目的となっている農地の評価
Q21 市民農園として貸し付けられている農地の評価
Q22 生産緑地の評価
Q23 広大地の評価
Q24 接道義務を満たしていない土地の評価
Q25 がけ地等を有する土地の評価
Q26 農業用施設用地の評価
Q27 セットバックを必要とする土地の評価
Q28 土地区画整理事業中の宅地の評価
Q29 造成中の宅地の評価
Q30 河川を隔てて道路がある土地の評価
Q31 市街化調整区域内の雑種地の評価
Q32 定期借地権の底地の評価
第2 家屋および構築物の評価
Q33 家屋の評価
Q34 構築物の評価
第3 株式および出資の評価
Q35 上場株式の評価
Q36 出資金の評価
Q37 公社債の評価
第4 預貯金の評価
Q38 預貯金の評価
第5 その他の財産の評価
Q39 一般動産の評価
Q40 定期金に関する権利の評価(給付事由が発生している場合)
Q41 定期金に関する権利の評価(給付事由の発生していない場合)
Q42 生命保険契約に関する権利の評価
第4章 農業を承継する場合の法務と税務
第1 農業を承継する場合の法務
1 農地法上の手続
Q43 農地を贈与で取得した場合
Q44 農地を相続で取得した場合
2 遺言による相続
Q45 遺言の意義
Q46 遺言の種類
Q47 遺言の効果
Q48 遺言の作成方法
Q49 公正証書遺言の作成費用
Q50 死因贈与
Q51 成年後見制度
3 遺産分割・相続放棄
Q52 農地の遺産分割
Q53 遺産分割における債務の扱い
Q54 遺産分割前の相続分の譲渡
Q55 相続放棄
第2 農業を承継する場合の税務
1 相続税の納税猶予
Q56 相続税の納税猶予の特例
Q57 特定貸付による相続税の納税猶予継続
Q58 営農困難時貸付による相続税の納税猶予継続
Q59 相続税の納税猶予の対象となる農地
Q60 相続税の納税猶予の打切り
Q61 20%以下基準(相続税)
Q62 区画整理があった場合の相続税の納税猶予
2 贈与税の納税猶予
Q63 贈与税の納税猶予の特例
Q64 特定貸付による贈与税の納税猶予継続
Q65 営農困難時貸付による贈与税の納税猶予継続
Q66 贈与税の納税猶予の対象となる農地
Q67 贈与税の納税猶予の打切り
Q68 20%以下基準(贈与税)
Q69 区画整理があった場合の贈与税の納税猶予
第3 農地を保有する場合の税務
Q70 固定資産税の概要
Q71 固定資産税の算定方法
Q72 農地の固定資産税の仕組み
Q73 固定資産税の情報開示
第4 農業所得の申告方法
Q74 農業所得の申告方法
Q75 相続で引き継いだ事業用固定資産の取得価額
Q76 減価償却資産
Q77 無償使用の土地に対する固定資産税・租税公課の範囲
Q78 必要経費に算入できる登記費用等
第5章 農業を承継しない場合の法務と税務
第1 農業を承継しない場合の法務
Q79 市街化調整区域の農地を転用する場合の利用制限
第2 農業を承継しない場合の税務
1 土地を譲渡した場合の税金の計算
Q80 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
Q81 離作料・立毛補償金
Q82 低額譲渡とみなし譲渡課税
Q83 固定資産の交換の特例
Q84 事業用資産の買換え
Q85 農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
Q86 等価交換方式による立体買換え
Q87 特定の交換分合による面整備
Q88 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地を相続時まで保有した後離農する場合
2 定期借地権方式による土地活用
Q89 定期借地権の設定と所得税課税
3 農業法人をめぐる税務
Q90 農業生産法人
Q91 農事組合法人
Q92 特定農業法人
Q93 農住組合
4 相続時精算課税制度
Q94 相続時精算課税制度
5 配偶者控除・住宅取得資金贈与
Q95 贈与税の配偶者控除
Q96 贈与税の配偶者控除(居住用不動産の範囲)
Q97 住宅取得資金贈与
Q98 住宅取得資金贈与(相続時精算課税を選択した場合)
第6章 相続・承継に伴う手続と納税
第1 相続税の申告と登記
Q99 相続開始後の申告手続スケジュール
Q100 相続の登記費用
第2 相続税の納付方法
1 相続税の納付方法
Q101 相続税の納付方法
2 延納制度
Q102 延納制度とは
3 物納制度
Q103 農地の物納
Q104 仮換地の物納
Q105 定期借地権が設定された土地の物納
Q106 超過物納
Q107 物納適格財産と不適格財産
Q108 物納の取下げ・却下
Q109 生産緑地の物納
Q110 固定資産税の減免
Q111 資産の売却と物納の選択
Q112 特定物納
Q113 物納撤回
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。