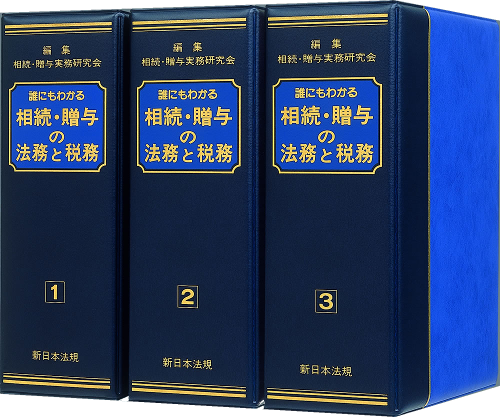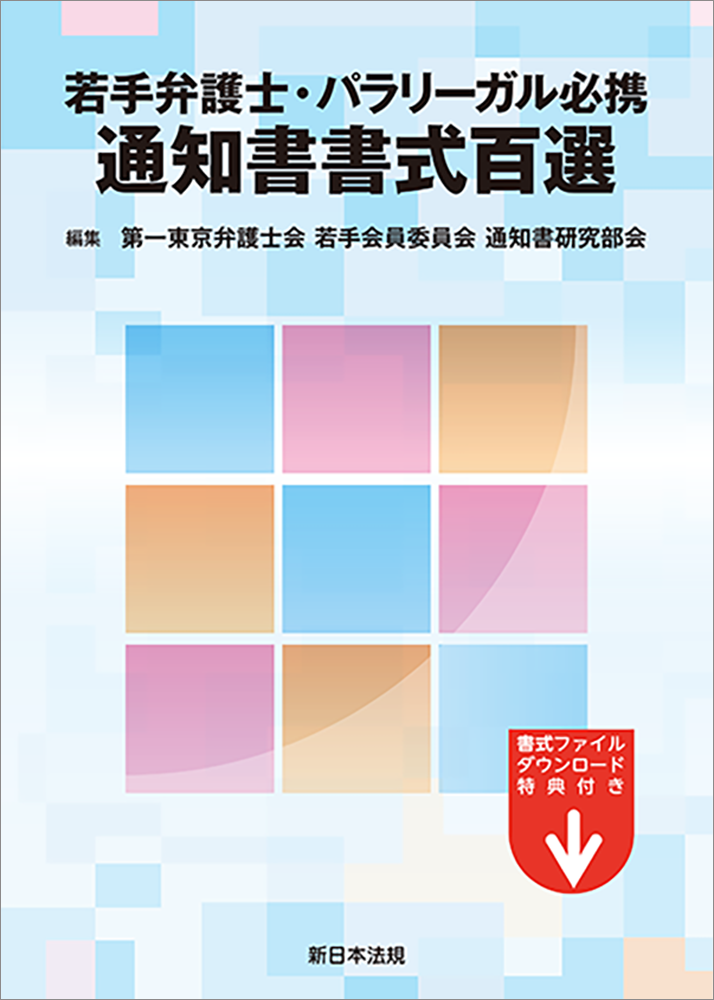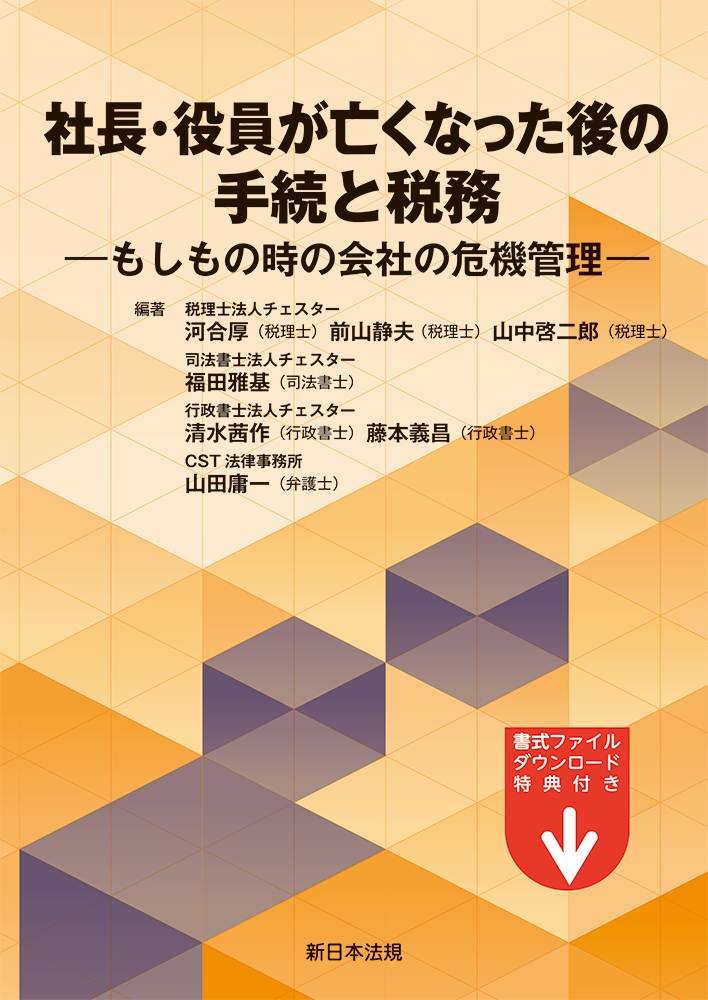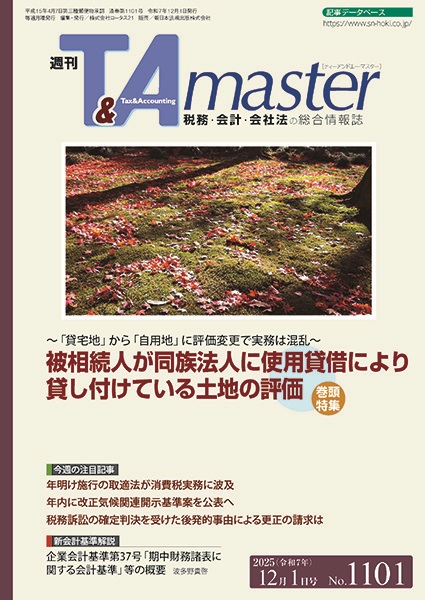概要
◆相続・贈与のすべてがわかる!
相続・贈与にかかる法律の解説から税金の計算方法や納税手続、節税対策まで収載し、法務と税務の一体化を図ったこれまでにない構成となっていますので、あらゆる問題の解決を図ることができます。
◆わかりやすく親しみやすい内容!
知りたい問題が即座にわかるQ&A方式を採用し、難解な用語を避けてなるべく平易な言葉でわかりやすく解説しています。また、随所にイラストを入れるなど、親しみやすいよう工夫された内容となっていますので、どなたにも幅広くご利用いただけます。
本書は、加除式電子版をご利用いただける書籍です。(無料)
加除式電子版閲覧サービスはこちら
商品情報
- 商品コード
- 0343
- サイズ
- B5判
- 巻数
- 全3巻・ケース付
- ページ数
- 3,348
- 発行年月
- 1993年5月
目次
平成30年民法(相続法)改正等のあらまし
相続法における配偶者の居住権保護の方策とは
遺産分割等に関する見直しとは
遺言制度に関する見直しとは
法務局における遺言書の保管等に関する法律とは
遺留分制度の見直しとは
相続の効力等に関する見直しとは
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料制度)とは
第1 相続税のあらまし
相続税とはどのような税金か
相続税の基礎控除とはどういうことか
相続税がかかる遺産の額はどのくらいからか
相続税の納税義務者(個人)は
財産の種類ごとの所在の判定のしかたは
相続税の納税義務者(個人以外)は
町内会に財産を遺贈した場合は課税されるか
相続時精算課税制度とはなにか
相続税と贈与税の相互の関連性とは
贈与税とはどのような税金か
贈与税がかかるのはどのような場合か
みなし贈与にはどんなものがあるか
負担付贈与とはなにか
第2 相続人と相続分
1 相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と相続の順位は
戸籍証明書等の広域交付制度とは
法定相続情報証明制度とは
同時死亡の推定とは
内縁の妻は相続できるか
重婚的内縁関係にある者も労働基準法施行規則42条1項の内縁の妻にあたるか
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合の財産分与はどうなるか
内縁の妻は借家権を相続できるか
内縁の配偶者の居住権は
再婚した場合は相続権を失うか
子供のない妻は亡き夫に代わって義父の財産を相続できるか
離婚訴訟中に死亡した妻の財産を夫が相続できるか(推定相続人の廃除)
胎児は相続できるか
後妻の連れ子は相続できるか
人工授精で生まれた子は相続できるか
卵子提供により生まれた子は相続できるか
同性パートナーに相続させることができるか
認知とはどのようなことか
血縁上の父子関係のないことを知りながらなされた認知について、認知者自身が認知の無効を主張できるか
庶子出生の届出とは
死後認知はできるか
夫の死後、冷凍精子を体外受精して生まれた子は死後認知されるか
認知されていない非嫡出子が父子関係存在確認の訴えを提起することはできるか
女性への性別変更の審判が確定した生物学上の父に対し生殖補助医療により生まれた子は認知請求することができるか
人事訴訟の補助参加人の上訴期間は
二重資格の相続人とはどのような者をいうか
事実上の養子に相続権はあるか
戸籍上嫡出子とされている子(藁の上からの養子)は相続できるか
子との間に生物学上の父子関係が認められない場合であっても嫡出の推定を受けるか
養子は実父母に対しても相続権をもつか
遺産相続が目的である養子縁組は有効か
推定相続人から廃除することを目的とした死後離縁は認められるか
養子縁組無効確認の訴えを提起できる者の範囲は
戸籍の記載がない場合にも相続権はあるか
非嫡出子に相続権はあるか
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が憲法に反する場合とは
里子は里親の財産を相続できるか(特別養子)
養父母にも相続権はあるか
代襲相続人とはどのような者をいうか
養子の子に代襲相続権はあるか
もともと被相続人の傍系卑属(従姪)であった、養子縁組により被相続人と兄弟姉妹になった者の当該養子縁組前に生まれた子は、被相続人の代襲相続人になることができるか
おいやめいにも相続権はあるか
相続人になれない人とはどのような人か
遺言書を隠してしまった者でも相続人になれるのか
不当な利益を目的とせずに遺言書を破棄した者も相続欠格者となるか
相続欠格事由のある者について、被相続人がその相続人資格を回復させることができるか(欠格の宥恕)
相続欠格事由の存否に争いがあるような場合に、相続人の地位の存否を確認する訴訟を提起することができるか
共同相続人間の相続人の地位不存在確認の訴えは、共同相続人全員が訴訟当事者とならなければならないか
自己の相続分を全部譲渡した共同相続人の遺産確認の訴えにおける当事者適格は
いったん廃除した相続人にも相続させることはできるか(推定相続人廃除の取消)
遺産分割後に相続人廃除の申立てが棄却された相続人は、遺産分割の請求ができるか
勘当された子の相続権はどうなるか
相続させたくない人がいる場合はどうするか
推定相続人の廃除事由である「著しい非行」とはどのようなものか
相続廃除の取消に一定の条件を付けるには
相続人廃除の審判手続中に死亡した被廃除者の審判手続上の地位は承継されるか
相続人兼遺言執行者が被相続人の養子との間で遺留分に関する合意をしながら、その養子を推定相続人から廃除することはできるか
相続人に行方不明者がいる場合はどうするか
本人が死亡した場合、後見人は本人の残債務について支払わなければならないか
成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)とは
相続の開始とは
相続人がいない場合はどうなるか
所有者が死亡し、倒壊の危険がある隣の空き家の管理はどうすればよいか
相続財産管理人選任の請求ができる場合とは
相続財産管理人は相続財産に軽微な変更を加えることはできるか
死後事務委任契約の受任者は相続財産清算人選任の申立てができるか
取得時効の完成後に相続財産清算人が選任された場合、時効完成猶予の効力が認められるか
身寄りのない者から遺産全部の遺贈を受けた場合の手続は
相続人のいない借地権は消滅するのか
相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することはできるか
特別縁故者とはどのような者をいうか
相続放棄をした相続人が特別縁故者として相続財産の分与を受けることができるか
相続人でない人が被相続人の世話をしていた場合は
死後認知の訴えが提起されている場合に、特別縁故者は相続財産の分与を受けることができるか
不動産の共有者の1人が相続人なく死亡したときであっても、その特別縁故者は相続財産の分与を主張できるか
特別縁故者の相続人は相続財産分与の申立てができるか
過去の一時期の縁故によって特別縁故者と認められるか
被相続人の死後における特別の縁故は認められるか
被相続人の生存中にその財産を不当利得した者は特別縁故者となれるか
被相続人の遺言書を偽造した者でも特別縁故者として相続財産の分与を受けることができるか
相続人なく死亡した日本に居住する外国人の特別縁故者は
成年後見人は特別縁故者となれるか
介護付入居施設に入所中に死亡した者の遺産について、同施設は特別縁故者となり得るか
雇い主も特別縁故者と認められるか
特別縁故者への財産分与の審判後に新たに相続財産が見つかったときは
地方公共団体も特別縁故者となり得るか
被相続人が外国人である場合では
遺産分割の国際裁判管轄は
2 相続分
(1) 法定相続分と指定相続分
相続分の算定はどのようにするか
非嫡出子の法定相続分の取扱いは
非嫡出子の相続分にかかる最高裁決定による遡及効の取扱いは
相続により権利を承継した場合における対抗要件の要否
法定相続分と指定相続分はどちらが優先するか
長期間放置した遺産分割における具体的相続分の主張(特別受益・寄与分の主張)の取扱いは
遺言で相続分の指定がされている場合でも、相続債権者は法定相続分に応じて権利行使できるか
遺産分割が未了のままとなっている相続財産である振替株式を、相続人の債権者は差し押さえることができるか
相続資格が重複している人の相続分は
代襲相続人がいる場合の相続分は
相続分の一部を譲渡することはできるか
遺産分割協議をする前に相続人の1人が勝手に抵当権を設定することは許されるか
不動産の相続分を無断で譲渡され第三者への所有権移転登記が経由された場合、その相続分の所有を当該第三者に主張できるか
相続回復請求権とはどのような権利か
相続回復請求権は相続されるか
相続回復請求権と取得時効の関係
被相続人の実子でないのに実子として出生届がなされ、実子として養育されてきた者は被相続人の遺産を相続できるか
(2) 特別受益者と相続分
特別受益とはなにか
第三者の受益に伴う特別受益の取扱いは
特別受益の範囲は
相続人の居住の利益は特別受益にあたるか
教育費は特別受益にあたるか
死亡保険金請求権は特別受益ないしこれに準じるものとして持戻しの対象となるか
相続人が被相続人から土地の使用貸借権の設定を受けることは特別受益となるか
被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合は、持戻しの対象となるか
推定相続人でない者が被相続人から贈与を受けた後に代襲相続人になった場合、その贈与は特別受益に当たるか
配偶者を通じて、間接的に経済的利益を受けている場合は、特別受益として持戻しの対象となるか
養子縁組前に贈与された財産の相続財産への持戻しは
特別受益者の相続分の算定はどのようにするか
生前贈与に対する持戻免除とはなにか
生前贈与に対する持戻免除の意思表示はどのようにするか
配偶者に対する自宅の生前贈与は特別受益にあたるか
配偶者居住権は特別受益にあたるか
特別受益となる遺贈に対する持戻免除の意思表示は遺言でなされなければならないか
超過特別受益者がいる場合の相続分の算定はどのようにするか
特別受益額が具体的相続分を超過するとき、その超過分は寄与分から差し引かれるか
相続が開始して遺産分割が完了しない間に第二次相続が開始した場合において第二次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否は
特別受益に関して当事者間の合意がある場合の取扱いは
「相続させる」趣旨の遺言による特定の遺産承継は特別受益となるか
譲り受けた法定相続分の遺産は特別受益に当たるか
(3) 寄与分
寄与分とはなにか
被相続人の資産を運用したことによる資産の増加は、寄与分として認められるか
被相続人の扶養は寄与分と認められるか
相続開始後に遺産の維持・管理にあたった相続人の寄与は寄与分として認められるか
寄与分を受けることができるのはどのような者か
寄与者が廃除された者である場合、その寄与分はどう取り扱われるか
寄与分はどのように算定されるか
相続人全員に同等の寄与が認められる場合の取扱いは
共同相続人の遺留分を侵害する寄与分は認められるか(寄与分と遺留分の関係)
相続人になる以前の寄与分はどうなるか
相続人の配偶者の寄与を相続人の寄与として評価することはできるか
相続人の配偶者の寄与分は認められるか
遺言で相続分の指定がされた場合の寄与分はどうなるか
寄与分を遺言で定めることはできるか
寄与分は相続されるか
相続の放棄は寄与として認められるか
相続分の譲渡にともない寄与分も譲渡されるか
生前贈与や遺贈がある場合の寄与分の算定はどのようにするか
被相続人経営の会社への援助が寄与分として認められるか
寄与分を取得した場合の相続税の課税関係はどうなるか
特別の寄与とはなにか
法定相続分等のない相続人が遺留分侵害額請求を行使した場合、特別寄与料は負担するか
遺産分割未了のまま第2次相続が開始した場合、第2次相続についての登記を省略した所有権移転登記申請は認められるか
順次の相続が生じた場合においてなされた中間省略登記が実体関係と異なるときの登記の是正方法は
第3 相続の承認と放棄・財産分離
1 相続の承認と放棄
相続の単純承認とはどのようなことか
相続人が相続放棄の申述受理後、被相続人の遺品を持ち帰った行為は「相続財産の隠匿」に当たるか
被相続人の預金を解約し墓石購入費に充てた行為は「相続財産の処分」に当たるか
相続開始後、相続放棄の手続をする前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立ててその取立金を収受領得する行為は「相続財産の処分」に当たるか
相続財産である株式の株主権の行使および不動産の転貸料の受取人の変更は「相続財産の処分」にあたるか
相続の限定承認とはどのようなことか
限定承認者は相続債権者の調査をする義務があるか
限定承認者が不当に一部の相続債権者に弁済した場合はどのような責任を負うか
限定承認において、条件付債権等に当たらない債権につき裁判所が選任した鑑定人が債権額を鑑定した場合、当事者はこれに拘束されるか
限定承認の場合の相続財産清算人の地位・権限は
相続人が限定承認した場合、被相続人の債権者は相続財産に対して強制執行できるか
限定承認を取り消すことはできるか
相続の放棄はどのようにするか
相続させる旨の遺言を放棄することはできるか
相続を放棄した者は、相続財産についてどのような保存義務を負うか
相続人全員が相続を放棄した場合、遺産の管理等はどうなるか
自らも相続人である後見人が被後見人の相続の放棄をすることはできるか
相続人が遺産は何もないと誤信したことにより、相続放棄することなく熟慮期間を徒過してしまった場合、相続放棄はもはやできないか
熟慮期間の経過後に限定承認の却下がされたときも相続放棄をすることができるか
未成年の相続人の熟慮期間の起算点は
災害時における熟慮期間は
相続の放棄や限定承認はいつ意思表示すればよいのか
相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合、その相続人はどのような手続をすればよいか
相続人の1人が相続放棄した場合の相続分の算定はどうなるか
一次相続を放棄した場合の再転相続はどうなるか
二重資格の相続人が相続放棄をするには
相続放棄を取り消すことはできるか
相続放棄の錯誤取消しの主張は認められるか
相続放棄と登記
限定承認した相続人は死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗できるか
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為の効力はどうなるか
無権代理人が本人を共同相続した場合の無権代理行為の効力は
破産手続開始決定前の相続について開始決定後に破産者がなした単純承認または相続放棄の効力は
2 財産分離
相続人が多額の債務を負担していて財産を相続すると被相続人に対する債権者の債務の弁済ができなくなる場合にはどうしたらよいか
財産分離された相続財産を人手に渡さないことはできるか
第4 遺産分割
1 遺産の範囲
祭祀財産はどのように扱うのか
遺産から葬儀費用を支出することは認められるか
包括遺贈の遺言が存在する場合、その受遺者が祭祀承継者となるのか
成年被後見人を祭祀承継者に指定できるか
遺骨は誰に帰属するか
勲章は相続財産となるか
墓地は相続財産になるか
持分会社の社員の地位の相続は
譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求とは、どのような制度か
雇用契約上の地位は相続されるか
保険金受取人が死亡保険金支払請求権を放棄した場合はどうなるか
生命保険契約において受取人が「法定相続人」とされていた場合、相続放棄した法定相続人も保険金を受領することができるか
生命保険金は遺産となるか
生命保険の保険金受取人とその相続人となるべき者が同時に死亡した場合に保険金を受け取ることができる者は
死亡保険金の受取人を変更する行為は遺贈または贈与にあたるか
相続預貯金は遺産分割の対象か
定額郵便貯金債権についての払戻しは
自動継続定期預金の払戻しはできるか
賃借権は相続できるか
改良住宅の使用権は承継できるか
特許権や著作権などは相続できるか
労災保険から支給される遺族補償年金は遺産となるか
遺族補償年金と損害賠償請求権との損益相殺的な調整
未払いとなっている扶養料請求権は相続の対象となるか
生活保護受給権は相続の対象となるか
居宅介護サービス費の支給を受ける権利は相続の対象となるか
離縁請求権は相続の対象となるか
連帯債務の相続はどうなるか
担保権の設定された土地が相続により共有になった場合、弁済による代位の割合を定める「頭数」はどうなるか
身元保証債務は相続されるのか
根抵当債務者が死亡した場合の相続はどうなるか
包括根保証人が死亡した場合の相続はどうなるか
退職金は遺産の範囲に含まれるか
銀行の貸金庫を開けるにはどうすればよいか
預金者の共同相続人の1人による預金口座の取引経過明細の開示請求は認められるか
受遺者以外の法定相続人は預金取引開示請求ができるか
相続人は預金契約解約後に取引経過の開示請求を金融機関に求めることはできるか
預金者の相続人による印鑑届書の開示請求は認められるか
相続開始後の家賃収入は遺産となるのか
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、共同相続人の1人は自己の相続分を超えて取得時効を援用できるか
被相続人の占有が他主占有であっても、相続人の自主占有による時効取得が認められるか
共同相続人の1人による相続財産の占有に取得時効が認められるか
被相続人と同居してきた相続人が相続開始後も当該建物を占有していることは不当利得に当たるか
被相続人と同居してきた相続人が相続開始後も当該建物に住むことができるか
配偶者居住権はどのような場合に取得できるのか
配偶者居住権と登記
配偶者居住権は譲渡できるか
配偶者居住権が設定されている建物の修繕費は誰が負担するのか
配偶者居住権を活用した後継ぎ遺贈型の不動産承継とは
配偶者短期居住権の制度趣旨と成立要件は
配偶者短期居住権が存続している間の配偶者の権利義務および第三者対抗要件は
配偶者短期居住権の消滅原因および終了後の法律関係は
売り主としての義務は引き継がなければならないか
株主代表訴訟中に死亡した取締役の責任は
罰金や追徴金は相続人が引き継がなければならないか
当座勘定取引契約は相続するか
口座振替契約は預金者の死亡によりどうなるか
財産分与の調停中に死亡した者の相続人は分与請求を承継できるか
ジョイント・アカウント預金は相続財産になるか
暗号資産は相続されるか
SNSのアカウントを相続できるか
破産者の相続人は免責を申し立てることができるか
遺産の範囲に争いのある場合の解決方法は
被相続人の子の名義の有価証券は相続財産になるか
遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟か
遺産の分割を禁止することはできるか
損害賠償請求権は遺産分割の対象となるか
1の2 分割協議
分割協議はどのように行うか
相続開始前に遺産分割協議を行った場合はどうなるか
法定相続分と異なる分割協議は有効か
相続分のないことの証明書の効力は
「相続分のないことの証明書」の作成・交付は相続分の譲渡・放棄にあたるか
数代前の相続登記がされている土地を相続した場合どうすればよいか
相続人の1人が行方不明のときはどうするか
相続人の1人が所在不明の場合に所在不明相続人の共有持分を取得できるか
相続人の1人が所在不明の場合に所在不明相続人の共有持分を含めて譲渡できるか
所在不明の相続人がいる場合に所有者不明土地管理制度を活用できるか
相続人が遠隔地にいる場合の遺産分割はどのようにするか
胎児がいるときの遺産分割協議はどのようにするか
親権者が子に代わって分割協議ができるか
未成年者に親権者がいない場合の遺産分割はどのようにするか
相続人の債権者は遺産分割の代位請求をおこせるか
遺産分割と登記の対抗関係は
扶養義務の債務不履行を理由に遺産分割協議をやり直すことはできるか
協議で定めたことが実行されないときはどうするか
分割協議をやり直すことはできるか
遺産分割審判後に、その財産は遺産ではないとの民事判決が確定した場合、審判の効力はどうなるか
遺産分割協議中に当事者が死亡したときは
相続人の1人が精神病の場合、遺産分割調停はどうすればよいか
共同相続人の一部を除外して行った遺産分割の効力は
一旦成立した遺産分割協議が後に確定判決で無効とされた場合において、当該分割協議に基づいて賃貸不動産を取得した相続人がその無効と判断される原因事実を知っていた場合、当該相続人は悪意の占有者にあたるか
相続人中に成年後見人と成年被後見人とがいる場合の遺産分割協議はどのように行うか
相続人の中に任意後見契約を締結している者がいる場合、遺産分割手続はどのように行えばよいか
分割禁止の遺産がある場合にはどうするか
相続分の譲受人は分割協議に参加できるか
農地を分割するにはどうすればよいか
相続分の譲渡に伴う農地の権利移転には農地法の許可が必要か
相続による農地の細分化を防ぐにはどのような方法があるか
遺言で相続人が定められている財産についても遺産分割の対象とすることができるか
遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効か
遺産分割協議の対象とならなかった定期預金債権の特定遺贈の効力は
ゴルフ会員権を相続する場合どうすればよいか
遺産分割協議書の真否を争うことはできるか
遺産分割協議後に相続人の1人が認知症であったことが判明したとき遺産分割協議はどうなるか
遺産分割協議書無効による分割代償金返還請求権の消滅時効の起算点は
遺産分割協議は詐害行為取消権行使の対象となるか
遺産分割協議によって共同相続人の1人が法定相続分を超える価額の遺産を取得した場合、破産管財人による否認権行使の対象となるか
遺産分割協議により取得した遺産に国税徴収法の「第二次納税義務」が発生するか
不在者財産管理人による遺産分割協議成立後に不在者が現れた場合の遺産分割協議の効力は
行政書士の関与により成立した遺産分割協議は有効か
特別代理人によってなされた遺産分割の内容が本人の法定相続分を侵害する内容であったことを理由に当該遺産分割は無効とならないか
遺産分割のやり直しその他の理由により相続人間で相続税の過多・過少負担が生じた場合に、過多負担となった相続人が過少負担となった相続人に対して不当利得返還請求でその不均衡の是正を図ることの是非は
相続登記の義務化とは
相続により取得した土地を国庫に帰属させることができるか
相続土地国庫帰属制度の処分に対する不服申立ての手続は
相続をした土地が国庫に帰属した後に、責任を負うことがあるか
相続により取得した隣接する2筆以上の土地に関する負担金算定額の特例とは
2 分割の方法
遺産分割にはどのような方法があるか
一団の土地を形成する複数の共有不動産について現物分割の請求があった場合の分割方法にはどのようなものがあるか
共同相続人の1人が遺産の現状を変更した場合、他の共同相続人は原状回復請求ができるか
遺産分割前に処分された財産は遺産分割の対象となるか
相続人の1人が、被相続人の預金通帳と届出印を持参して金融機関から預金の払戻しを受けた場合に、他の相続人が取り得る手段は
相続人の1人が、被相続人の生前および死後に預金口座から無断で出金したことに対し、不当利得返還請求権を行使する場合の権利割合はどうなるか
被相続人から払戻権限を与えられていた相続人の1人が、相続発生前に被相続人名義の預金を自らの預金に振り替えていた場合に他の相続人がとりうる手段は
預金債権の本人以外の者に対する払戻しが弁済として有効である場合に金融機関は遺留分権利者に対して過誤払いを防止すべきか
仮差押えされている物件は換価できるか
共有とする分割方法とは
遺産相続により共有となった財産を分割するために、共有物分割の訴えによることができるか
共有持分について相続が発生した場合の共有関係解消の方法は
使用権を設定する分割方法とは
代償財産の提供による分割方法とは
代償分割の債務不履行を理由に遺産分割の協議を解除できるか
分割の協議が成立しない場合は
遺産分割の審判に対する不服の申立てはいつまでにしなければならないか
相続預貯金につき遺産分割前に1人の相続人が払戻しを受けることは可能か
簡易生命保険の保険金の共同相続人は単独で自己の相続分に応じた支払いを求めることができるか
個人向け国債について相続分に応じた代金の請求はできるか
投資信託について相続分に応じた解約金を請求できるか
共同相続人の1人が自己の相続分に相当する投資信託受益権の金額の支払を請求することの可否は
境界紛争があり訴訟が係属中の土地は、どのように遺産分割手続を進めたらよいか
具体的相続分や特別受益の確認を求める訴えはできるか
遺産の一部分割は認められるか
遺産分割協議後に発見された遺産の分割は
適正な遺産分割のためには遺産評価の基準時をいつにすればよいか
死後被認知者の価額支払請求はどうするか
相続開始後に新たに子と推定された者の価額支払請求権
障害者である共同相続人の1人に扶養分として法定相続分を超える遺産を分けることができるか
相続財産中に同族会社(非公開会社)の株式が含まれている場合、遺産分割に当たってどのようなことに注意すればよいか
第5 遺言と遺留分
1 遺言の方式と効力
どのようなことを遺言できるか
遺言書で臓器提供の意思表示をすることができるか
親権者の一方が子に財産を遺贈する場合、その財産について他方の親権者の管理権を奪い、管理人を指定することができるか
「相続させる」と「遺贈する」とではどう異なるのか
遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させるには
相続させる旨の遺言と登記
相続させる旨の遺言による相続に代襲相続は認められるか
「相続させる」旨の遺言に負担付遺贈の規定は適用されるか
自筆証書遺言、秘密証書遺言の記載内容はどのように解釈されるか
「財産をすべて任せる」旨の遺言は包括遺贈と認められるか
遺言執行者に受遺者の選定を委託した遺言は有効か
住所のみが表示された不動産の遺贈は土地建物を目的としたものと解することができるか
共同で遺言をすることはできるか
遺言のしかたにはどのような方法があるか
エンディングノートの法的効力は
自筆証書遺言の作り方と加除訂正の方法は
自筆証書遺言における財産目録の作成方法は
自書によらない財産目録に署名押印がされていない自筆証書遺言は有効か
他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言は有効か
自筆証書遺言の有効性の判断における動画の実質的証拠力は
自筆証書遺言の加除訂正について、要式が欠けていても有効となることがあるか
日付・署名捺印の後に付記されている自筆証書遺言は無効か
自筆証書遺言の「署名・押印」の場所は
花押が書かれた自筆証書遺言の効力は
郵便はがきに書かれた文書は遺言として有効か
遺言が成立した日と相違する日付の自筆証書遺言は有効か
複数の筆跡鑑定が結論を異にする場合の自筆証書遺言の効力は
ICレコーダーやパソコンによって遺言することができるか
公正証書遺言書のデジタル化とは
法務局における自筆証書遺言の保管制度とは
遺言者は保管された遺言書の閲覧、撤回、変更ができるか
遺言書が法務局に保管されている場合の相続人の手続は
保管していた遺言書はどうするか
自筆証書遺言が複数ある場合の検認手続の範囲は
公正証書によって遺言をするには
通訳を介して公正証書遺言を作成できるか
口がきけない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
耳が聞こえない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
目が見えない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
未成年者が遺言することはできるか
認知症患者の遺言には効力があるか
病により意識が低下した状態で作成された公正証書遺言の効力は
遺言能力が否定された遺言作成に関与した信託銀行の責任は
被後見人が後見人の利益となるべき遺言をした場合の効力は
証人は公正証書遺言に終始立ち会うことが必要か
証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言の効力は
遺言者が自己の氏名とは異なった署名をした公正証書遺言の効力は
公正証書遺言における遺言者の口授とは
秘密証書方式による遺言の方法は
ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題および本文を入力・印字した者は遺言書の筆者であると言えるか
公正証書遺言および秘密証書遺言の証人の欠格事由は
危急時にはどのような方法で遺言をすればよいか
危急時遺言における遺言者の口授とは
危急時遺言が失効となるときとは
家庭裁判所による危急時遺言の確認時に裁判所が得るべき心証の程度は
外国にいる日本人が遺言書を作成するときに注意することは
隔絶地にいる者が遺言をする方法は
遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力は
遺言で生命保険金の受取人を変更できるか
生命保険の契約者の地位または受取人の地位を遺言により処分することができるか
遺言者の死亡前または同時に受遺者が死亡した場合は
遺言を撤回するにはどうするか
文書全体に斜線が引かれた自筆証書遺言の効力はどうなるか
相続開始前に遺言者本人によって解約された定期預金の払戻金が、遺言書記載の「遺言者名義の預貯金債権」に該当するか
遺言書中の相続等の対象とされた「現金」に預金は含まれるか
遺言を撤回する遺言をさらに別の遺言で撤回した場合、当初の遺言の効力は復活するか
離婚前にされた前妻への遺言の効力は
老後の扶養を前提にした養子縁組とともになされた遺言は、その後の協議離縁により撤回したものとみなされるか
不動産を遺贈する旨の遺言は、当該不動産を売却するための専任媒介契約の締結により撤回したものとみなされるか
同時死亡を前提とした遺言の効力は
遺言書本文が封入された封筒の裏面に停止条件が記載されていた遺言の効力は
複数の推定相続人のうちの一部の者が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言の執行はどのように行うか
遺言執行者と相続人が対立した場合はどうするか
遺言執行者がいる場合の特定遺贈は
遺言執行者による相続預金の払戻しの可否は
遺留分のない相続人に対する遺言内容通知義務の有無
遺言執行者による遺言の執行を妨げる処分行為の効力は
遺言執行者がいる場合の相続財産の処分は
清算型遺贈における不動産登記は
遺言執行者がいる場合の相続人による相続預金の払戻しの可否は
遺留分権利者は、遺言執行者が指定されている場合であっても相続人を債務者として遺産の処分禁止の仮処分の申立てができるか
遺言執行費用は誰が負担すればよいか
遺言執行者は相続財産から葬儀費用を支出できるか
遺言執行者の報酬はどのようにして決められるか
審判で決定された遺言執行者の報酬について不服申立てはできないか
遺言執行者の遺言執行状況の報告義務違反および相続財産目録交付義務違反について損害賠償を請求することができるか
遺言執行者の申立手続および解任事由
遺言執行者による執行途中の報酬受領と解任
遺言の無効を訴えることはできるか
遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺言無効確認の訴えは認められるか
特別縁故者に遺言無効確認の訴えの利益はあるか
前訴判決と矛盾する遺言の有効確認の訴えは認められるか
遺言信託とはどんなことか
遺言による公益信託とは
遺言代用信託とは
遺言信託、遺言代用信託における受益者連続型信託の活用とは
信託条項に「遺産分割協議で定める」とする条項は有効か
遺産分割の後で遺言が出てきたときにはどうするか
死亡後における事務処理を依頼する準委任契約と遺言の効力
遺言書を作成した上で専門家と死後事務委任契約を締結する際の注意点
遺言でデジタル情報の相続先や処理方法を定めることができるか
電子データ、NFTを相続するには
2 遺贈・死因贈与
遺贈・死因贈与とはなにか
死因贈与執行者には遺言執行者に関する規定が準用されるか
無効な遺言書が死因贈与契約を証する書面と認められるのはどのような場合か
贈与者よりも受贈者が先に死亡した場合の死因贈与の効力は
遺言により死因贈与契約は撤回できるか
遺贈寄付を選択するにはどうすればよいか
不倫の相手方に対する包括遺贈は公序良俗に反するか
死因贈与を原因とする銀行預金の譲渡はできるか
特定受遺者が遺贈を承認・放棄するには
負担付遺贈を放棄することはできるか
包括遺贈の放棄はどのようにすればよいか
複数の包括遺贈の一つが放棄された場合に、他の包括受遺者に帰属するか
被相続人が同一不動産をある相続人に贈与した後ほかの相続人にも遺贈した場合に、受贈者は登記をしなければ受遺者に対抗することができないか
遺贈の目的物が相続開始前に遺言者の成年後見人によって売却されたために相続財産に属さない場合の物上代位の可否は
相続人ではない負担付遺贈の受益者は受遺者に対して負担の履行を請求できるか
負担付特定財産承継遺言の取消しの可否は
ペットに関する遺言についての留意点
3 遺留分
遺留分とはなにか
遺留分の割合はどうなっているか
遺留分算定の基礎となる財産は
遺留分侵害額の算定方法は
侵害された遺留分を取り戻すには
遺留分侵害目的の養子縁組は効力があるか
認知症の人のために遺留分を確保するためには、どうすればよいか
相続開始前の贈与に対する遺留分侵害額請求を受贈者は取得時効を援用して拒むことができるか
養子縁組前の贈与に対する遺留分侵害額請求権はどうなるか
遺留分侵害額請求権は代位行使できるか
遺産分割協議の申入れに遺留分侵害額請求の意思表示が含まれるとされるのはどんな場合か
遺留分侵害額請求権を行使されたらどのように対応すればよいか
遺留分侵害額の請求をされた受遺者がすぐに金銭を用意できない場合はどうすればよいか
遺留分侵害額請求の順序はどうなっているか
複数の遺贈がある場合の遺留分侵害額請求の方法は
複数の贈与がある場合の遺留分侵害額請求の順序は
遺贈や贈与が相続人に対してされた場合の遺留分侵害額の算定方法は
相続人の1人に全財産を相続させるには
親が遺留分の放棄をしている場合に代襲相続できるか
遺留分の放棄を取り消すことができるか
遺留分の事前放棄の合意がなされたにもかかわらず遺留分侵害額請求をすることは認められるか
遺留分の算定において控除すべき被相続人の「債務」に保証債務は含まれるか
遺留分侵害額の算定にあたり、遺留分権利者が承継した相続債務の額を加算できるか
包括遺贈の遺言がある場合に遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分侵害額に加算できるか
遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点はいつと考えるべきか
相続の開始から10年を経過した後に、遺留分侵害額請求権を行使できるか
長年音信不通であった者からの遺留分侵害額請求は認められるか
4 遺留分の特例
中小企業経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例とは
遺留分に関する民法の特例を受けるための要件とは
遺留分に関する民法の特例の「除外合意」・「固定合意」とは
「除外合意」・「固定合意」の手続は
「除外合意」・「固定合意」の効力は
第6 課税財産と非課税財産
1 課税財産
相続税が課税される財産にはどのようなものがあるか
みなし相続財産とはどのようなものか
損害賠償請求権の相続は可能か、また相続税が課税されるか
被相続人が払った所得税等にかかる過納金の還付請求権は課税財産となるか
生命保険金受取人をたんに「相続人」と記載した場合は相続財産となるか
生命保険契約のケースごとの死亡保険金(一時金)に関する課税関係は
生命保険契約のケースごとの死亡保険金(年金払)に関する課税関係は
生命保険契約のケースごとの満期保険金に関する課税関係は
人身傷害補償保険金にかかる相続税および贈与税の課税関係は
保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の相続税の課税関係は
退職手当金や功労金に該当するかどうかの判定基準は
生命保険契約に関する権利にかかる税金は
相続人が小規模企業共済金を受け取った場合の相続税はどうなるか
特別縁故者が相続財産の分与を受けたときにかかる相続税は
特別寄与者が寄与料の支払を受けた場合にかかる相続税は
共有持分の変更をした場合、相続税・贈与税はどうなるのか
不動産の名義変更をした場合、贈与税は課税されるか
遺贈・死因贈与に対する課税はどのようになされるか
公益法人等への遺贈の課税関係は
特定一般社団法人等に対する相続税の課税制度とは
代償財産を提供された場合の登記手続と課税関係は
遺留分侵害額請求により取得した金員の課税価格への算入すべき価額は
親族の債務を弁済した場合でも贈与税はかかるか
募集株式の付与を受けると贈与税がかかるか
離婚による財産分与でも贈与税が課税されるか
等価交換方式で売買契約中の土地にかかる相続税はどうなるか
下宿する大学生に一括贈与した生活費や教育費は課税されるか
ゴルフ会員権を相続税評価額で売買した場合、課税されるか
相続人が外国に居住している場合の相続税の課税はどうなるか
海外在住者が海外財産を相続した場合、どのような場合に課税されるか
遺留分侵害額請求にもとづく判決と異なる内容の相続財産の分配を行った場合、課税はどうなるか
相続や贈与により取得した暗号資産は、相続税・贈与税の課税対象になるか。また、課税対象になった場合には、どのように評価するのか
配偶者居住権についての相続税・贈与税の課税関係はどうなるか
相続開始時点で売買契約中であった土地は相続税が課税されるか
2 非課税財産
相続税が課税されない財産にはどのようなものがあるか
弔慰金と退職手当金を区別する意味は
墓地、仏壇などを生前に取得したときは
高度の公益事業者に該当する具体的な要件は
私立幼稚園の教育用財産についての非課税要件は
生命保険金の非課税限度額は
心身障害者共済制度にもとづく給付金に相続税は課税されるか
建物更生共済契約にかかる相続税等の課税関係は
死亡退職手当金などの非課税限度額は
未支給年金を受け取った場合は、相続税の課税財産となるか
相続財産などを公益法人に寄附した場合の非課税制度とは
寄附した相続財産を公益法人等が売却した場合は
相続財産などを公益法人設立のために寄附した場合は
相続財産を特定非営利活動法人に贈与した場合は
建築協力金の債務控除の額はどうなるか
不動産信託についての相続税・贈与税は
特定公益信託に支出した相続財産は非課税となるか
公益事業を行う法人への遺贈につき非課税と認められる要件は
遺贈の非課税要件たる「税負担の不当減少がないこと」とは
公益法人等が遺贈財産を譲渡した場合は
相続税法66条と租税特別措置法40条関係の規定の差異は
相続開始時に支払期限の来ていない家賃等は課税されるか
やむを得ない理由により、他人名義で家屋を取得した場合の課税は
就労等のため日本に居住する外国人の国外財産への相続税の課税は
3 債務控除
債務控除とはなにか
被相続人の死亡後に確定した所得税額の債務控除はできるか
借金は債務控除の対象になるか
連帯債務・保証債務は控除できるか
葬式費用で控除できるもの・できないもの
告別式を2回行った場合、いずれも葬式費用として控除できるか
葬儀等の参列者に渡した商品券の購入費用は葬式費用として控除できるか
被相続人が加害者である場合の損害賠償金は債務控除できるか
被相続人の生存中に相続人が負担した医療費は債務控除できるか
遺言執行費用は債務控除できるか
合名会社の無限責任社員が死亡した場合、会社の債務について債務控除できるか
被相続人が生命保険付住宅ローンで家屋を取得していた場合、課税関係はどうなるか
固定資産税、市町村民税は債務控除できるか
被相続人の事業を継承した相続人が従業員に支払った退職金は相続債務か
外国に居住する相続人が負担した葬式費用は控除できないか
特別寄与料を制限納税義務者へ支払った場合、債務控除できるか
第7 相続・贈与税の計算
1 計算方法
相続税の計算はどのようにするか
相続税の総額の計算はどのようにするか
相続税の課税価格の算定時期は、相続開始時か遺産分割時か
遺産にかかる基礎控除額の計算はどのようにするか
各相続人の相続税額の算出方法は
非嫡出子の相続分に対する最高裁違憲決定と今後の相続税の取扱いは
法定相続人に含められない養子とは
相続税が2割加算される場合とは
未分割遺産の課税はどうするか
株式の信用取引による空売り中に相続が開始した場合はどうなるか
相続開始前7年以内の贈与は
贈与税の計算はどのようにするのか
負担付贈与の場合の課税価格の計算は
平成27年以降に直系尊属から財産の贈与を受けた場合の贈与税(暦年課税)の計算はどうなるか
令和4年1月1日において18歳または19歳である場合の贈与税の計算はどうなるか
贈与税の除斥期間が過ぎた後に贈与税の申告内容に誤りが判明した場合、相続財産への加算対象額はどうなるか
限定承認した場合の相続税と譲渡所得税はどうなるか
配偶者居住権等を消滅(譲渡)した場合の譲渡所得の計算は
相続等により取得した信託終了時の残余財産を譲渡する場合の譲渡所得の計算は
遺贈に対して遺留分侵害額の金額が確定した場合の相続税の計算は
贈与に対して遺留分侵害額の金額が確定した場合の贈与税・相続税の計算は
2 税額控除
贈与税額控除とはなにか
配偶者の税額軽減とはなにか
未成年者控除とはなにか
成年年齢の引下げによる未成年者控除額の計算はどうなるか
障害者控除とはなにか
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用は
障害者控除の控除不足額を控除することができる扶養義務者とは
相次相続控除とはなにか
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用は
外国税額控除とはなにか
相続税の災害減免措置とはどのようなことか
災害等により被害を受けた場合の相続税・贈与税の免除や緩和されるなどの税制上の措置とは
特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価は
特定居住用宅地にかかる評価額の軽減の特例とはなにか
特定事業用宅地にかかる評価額の軽減の特例とはなにか
不動産貸付事業用の敷地は特定事業用宅地に該当するか
特定計画山林にかかる評価額の軽減の特例とは
第8 相続・贈与税の申告と納付
1 申 告
相続税申告の手続はどうするか
相続税申告におけるマイナンバー制度とは
相続税申告における法定相続情報証明制度とは
相続税の申告書の提出期限はいつか
申告期限までに申告しなかった場合はどうするか
相続財産が分割されていないときの申告は
過少申告や過大申告があったときはどうするか
過少申告や無申告でも加算税が課されない「正当な理由」とは
遺産分割による申告に課税負担の錯誤があった場合に更正の請求はできるか
遺留分侵害請求による更正の請求を行う場合の提出期限は
胎児がいる場合の相続税の申告期限は
所得税の準確定申告とは
相続税申告における時効は
相続税の更正処分に不服のある場合はどうしたらよいか
贈与税の申告・納付における財産取得時期の判定は
区分所有権について建物と敷地利用権とを分けて贈与することは可能か
停止条件付遺贈の場合の申告はどうするか
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の課税はどうなるか
相続税の脱税犯とされるのはどんな場合か
重加算税が課税されるのはどんな場合か
申告漏れ等、相続手続に伴う税理士の責任は
外国国籍を取得した相続人が日本国籍を失っていないと誤信して行った相続税の申告について過少申告加算税等が課せられた場合に税理士に損害賠償責任が認められるか
国外転出(贈与・相続)時課税とは
新型コロナウイルス感染症による相続税の申告期限の延長はできるか
配偶者居住権の設定が申告期限後になった場合の相続税の申告はどうするか
2 納 付
相続税の納付はどのようにするか
相続税や贈与税の窓口納付以外の納付手続にはどのようなものがあるか
相続税納付における連帯納付の義務とは
相続税の延納とはなにか、利子税はどうなるか
延納はどのようにするか、担保の提供はどうなるか
延納期間の延長や変更はできるか
延納申請と物納申請との変更はできるか
相続税の延滞税はどのように計算されるか
延納の担保に提供している物件の売却や建替えはできるか
相続税の物納とはなにか
農地や山林は物納が認められるか
マンションやアパートは物納が認められるか
相続税の物納にあてることができる美術品とは
取引相場のない株式に係る株券は物納できるか
暗号資産は物納できるか
物納申請の撤回はどのようにするか
物納できない財産にはどのようなものがあるか
相続税額を超える価額の財産による物納はできるのか
未分割の遺産の相続税申告と物納は
物納が有利な場合とは
贈与税納付における延納制度とは
一画地の土地を分割し、分割後の土地を物納する場合の収納価額は
第9 相続財産の評価
1 不動産の評価
宅地の評価はどのようにするか
倍率方式による宅地の評価方法とは
路線価方式による宅地の評価方法とは
路線価方式による不整形地などの補正計算とは
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価はどのようにするか
私道の用に供されている宅地の評価は
路線価の付されていない私道に接する宅地の評価は
大規模工場用地の評価はどのようにするか
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例とは
小規模宅地等の特例において二世帯住宅の場合はどうなるか
小規模宅地等の特例において被相続人が老人ホームに入居していた場合はどうなるか
小規模宅地等の特例を受けた者が空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けることはできるか
不動産貸付けにかかる小規模宅地の特例とは
庭先部分を相続した場合、小規模宅地等の特例は適用できるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋の敷地を相続人が共有で相続した場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋とその敷地が被相続人と配偶者の共有となっていた場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋の敷地が他人からの借地である場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
相続開始の年に被相続人から宅地の贈与を受けていた場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺留分侵害額の請求により宅地を取得した場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
法人所有建物の建替え中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
土地区画整理事業中の宅地の評価は
造成中の宅地の評価はどのようにするか
「地積規模の大きな宅地の評価」はどのようにするか
広大地の評価はどのようにするか
農業用施設用地の評価はどのようにするか
区分地上権の評価はどのようにするか
利用制限のある宅地の評価はどのようにするか
借地権の評価はどのようにするか
地上権等(借地・区分地上権を除く)の評価はどうするか
容積率の異なる地域にわたる宅地の評価は
余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価は
セットバックを必要とする土地の評価はどのようにするか
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価はどのようにするか
一つの土地に借地権・区分地上権等の権利が複相している土地の評価はどうするのか
定期借地権等の評価はどのようにするか
定期借地権等の目的となっている宅地の評価はどのようにするか
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価はどのようにするか
他人に貸している宅地の評価はどのようにするか
貸家の建っている土地の評価はどのようにするか
抵当権が設定されている土地の評価はどうするか
宅地の評価にあたって評価減とは
一体利用の宅地の中に赤道(国有地)が存する場合の評価は
単独取得地と共有取得地が隣接している場合の評価はどのようにするか
駐車場の評価はどうするのか
土壌汚染地の評価はどのようにするか
埋蔵文化財包蔵地の評価はどのようにするか
生物多様性維持協定が締結されている土地の評価はどのようにするか
家屋の評価はどのようにするか
家屋の附属設備などの評価はどのようにするか
他人に貸している家屋の評価はどのようにするか
重要文化財に指定されている家屋およびその敷地の評価はどうするのか
マンションを相続した場合の評価(賃貸・分譲)方法は
相続開始時に賃貸マンションに一部空き部屋がある場合のその敷地等の評価は
高層マンション(いわゆるタワマン)節税の評価はどうなるか
居住用マンションの区分所有財産はどのように評価するか
農地の評価はどのようにするか
市街化区域内の農地の評価はどうするか
貸農地の評価はどのようにするか
都市市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価方法は
農地法の許可を受けないで他人に貸し付けている農地の評価はどうなるか
認定事業計画に基づき貸し付けられている農地の評価はどうなるか
耕作権、永小作権などの評価はどのようにするか
占用権の評価はどのようにするか
山林の評価はどのようにするか
貸し付けられている山林の評価はどうするか
果樹園などの評価はどのようにするか
鉱泉地の評価はどのようにするか
立木の評価はどのようにするか
雑種地の評価はどのようにするか
遊園地等の用に供されている土地の評価はどのようになるか
市民緑地の用地として貸し付けられている土地の評価はどうするか
無償で貸し付けられている幼稚園の園舎敷地と運動場用地の評価は
ゴルフ場用地として貸し付けている土地の評価はどうするか
土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の貸宅地の評価はどうなるか
デューデリジェンスにもとづいて算定される不動産の鑑定評価を相続税の財産評価で採用できるか
相続開始後における不動産売買契約の解除と相続財産の評価は
財産評価基本通達により算定した評価額が時価を上回る場合は
東日本大震災により被害を受けた場合、相続や贈与により取得した土地や非上場株式の評価額はどうなるか
2 動産・株式などの評価
上場株式の評価はどのようにするか
上場株式の評価の特則とは
気配相場のある株式の評価はどのようにするか
取引相場のない株式の評価方法は
会社の規模と評価方式の判定はどのようにするか
類似業種比準価額方式による評価方法とは
兼業会社の会社規模の判定方法は
評価会社の事業が該当する業種目の判定は
類似業種比準価額方式における比準3要素が「零」である場合の評価は
相続開始の直前に評価会社が合併した場合の類似業種比準価額の計算は
純資産価額方式による評価方法とは
中会社の株式評価はどのようにするか
配当還元価額方式による評価方法とは
株式等保有特定会社の株式の評価方法は
S1+S2とはなにか
土地保有特定会社の株式の評価方法は
種類株式の評価方法は
遺留分に関する民法の特例の固定合意における株式の「相当な価額」とは
「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」とは
株式に関する権利の評価は
ストックオプションの評価はどのようにするか
上場新株予約権の評価はどのようにするのか
医療法人に対する出資の評価はどのようにするか
公社債などの評価はどのようにするか
ディスカウント債の評価方法は
個人向け国債の評価はどのようにするのか
抵当証券の評価はどのようにするか
不動産投資信託証券の評価はどのようにするか
開業後3年未満の会社の株式の評価方法は
開業前、休業中または清算中の会社の株式の評価方法は
預貯金の評価はどのようにするか
外貨建てによる財産の邦貨換算はどうするか
生命保険契約に関する権利の評価はどのようにするか
定期年金に関する権利の評価はどのようにするか
相続開始時点で年金の種類等が決められていない保険契約の「年金受給権」の評価はどのようにするか
ゴルフ会員権の評価はどのようにするか
営業権の評価はどのようにするか
絵や骨とう品、競走馬などの評価はどのようにするか
ペットの評価はどのようにするか
棚卸商品の評価はどうするのか
著作権の評価はどのようにするか
未収獲農産物の評価はどのようにするのか
船舶の評価はどのようにするか
無利息債務の評価はどのようにするか
配偶者居住権の評価はどのようにするか
第10 相続・贈与税対策
養子をとった場合の相続税は
生前贈与の節税効果は
公正証書による贈与の課税時期はいつか
相続時精算課税制度のメリット・デメリットは
生前贈与において暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するべきか
孫が相続時精算課税適用者である場合、相続税額の加算の規定は適用されるか
法人の事業承継の場合の「相続時精算課税適用者の特例」とは
個人版事業承継税制と「相続時精算課税」の特例との併用適用は
相続時精算課税にかかる土地または建物の価額特例とは
災害により被害を受けた場合、精算課税の災害特例や災害減免法による減免措置の重複適用はどうなるか
特定贈与者が死亡した場合、精算課税の災害特例はどうなるか
災害発生日前に相続時精算課税適用者が死亡している場合、精算課税の災害特例に係る継続所有要件の判定はどうなるか
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税および相続税の取扱いはどうなるか
相続時精算課税選択届出書を提出した後に贈与税の期限後申告書を提出することとなった場合、相続時精算課税の適用はどうなるか
相続時精算課税適用者が特定贈与者より前に死亡した場合、相続時精算課税にかかる権利または義務の承継はどうなるか
贈与の節税分岐点とはなにか
贈与税が課税されない財産にはなにがあるか
不動産贈与は現金贈与よりトクか
負担付贈与を有利に行うためには
子供名義で預金を積み立てたときは
親子間で土地の使用貸借をして受領した駐車場収益における課税関係はどうなるか
孫に対する財産分与の効果は
教育資金の一括贈与の非課税措置とは
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは
配偶者控除はどれだけ認められているか
特定障害者のための贈与税の優遇措置とは
配偶者控除の効果的な活用方法は
贈与を受けた配偶者が年の途中で死亡した場合でも配偶者控除が受けられるか
共稼ぎ夫婦が住宅を購入する場合は
相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の特例とは
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは
住宅取得等資金の贈与を受けた後に、海外転勤となった場合の住宅資金等の贈与税の非課税特例の適用は
連年で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例の適用は
親の土地に子が家を建てるときは
子供へ土地や家屋の貸付をする方法は
親の借地上に子が家を建てるときは
親の家屋の底地を子が買い取るときは
山林についての相続税の納税猶予制度とは
親名義の建物に子が増築した場合は
空き地にアパートや貸しビルを建設することは
借入金で不動産を購入することは
土地や建物の等価交換と相続税対策
事業用資産の買換えと相続税への影響およびその効果
相続などを考慮した居住用財産の買換えは
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは
相続財産を売却した場合の譲渡所得の取得費加算の特例とは
相続開始時点で売買契約中であった土地の譲渡所得について相続税額の取得費加算の特例の適用はどうなるか
相続時までの土地の値上がり益に対する課税は相続税と所得税の二重課税となるか
優良住宅地等の譲渡の特例とは
賃貸用の国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の特例計算とは
個人商店を法人成りさせることは
適格請求書発行事業者の事業を相続する場合の手続は
法人の事業承継問題にどう取り組むか
非上場株式等についての相続税の納税猶予制度(一般措置)とは
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度(一般措置)とは
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予・免除(特例措置)とは
非上場株式等の納税猶予制度(一般措置)における資産保有型会社等の該当判断は
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(一般措置)を受けるための手続は
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予および免除(特例措置)を受けるための手続は
相続に伴う遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)がされた場合の贈与税の納税猶予制度の取扱いは
非上場株式等についての相続税の納税猶予と小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例の併用は
非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税・納税猶予の特例(一般措置)とは
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)とは
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けるための手続は
自社株対策のポイントはなにか
自社株の評価額を引き下げるにはどうすればよいか
従業員持株制度を発足することは
自社株を生前贈与する場合の方法は
自社株の親子間売買において注意する点は
相続等により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例とは
信託の終了に伴い取得した非上場会社の株式を発行会社に譲渡した場合の特例とは
株式を相続する際にはどのような点に注意すればよいか
株式を共同相続した場合、株主権の行使はどうするか
株券を紛失してしまった場合の相続は
医業継続にかかる相続税の納税猶予制度とは
医業継続にかかる贈与税の納税猶予制度とは
医療法人の出資者全員が出資持分を同時に放棄し、持分のない医療法人に移行した場合の課税関係はどうなるか
医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例とは
農地についての相続税の納税猶予制度とは
相続税の納税猶予を適用している特例農地に太陽光パネルの設置を目的とした区分地上権を設定した場合の納税猶予の特例の継続は可能か
相続税の納税猶予の適用を受けている場合の特定貸付農地等の特例とは
特定生産緑地制度等の創設により納税猶予の対象となる特例農地等の範囲はどうなるか
相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例とは
農地についての贈与税の納税猶予制度とは
旧特定農業生産法人に使用貸借による権利の設定をした場合の贈与税の納税猶予の継続の特例とは
農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合の納税猶予の特例は
相続税対策のため変額保険契約を結ぶときに注意することは
保険契約者(保険料負担者)以外の者が保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合の課税関係はどうなるか
特定の美術品についての相続税の納税猶予制度とは
附録
○民法(抄)(明29法89)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平20法33)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令(平20政245)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平21経産令22)
○相続税法(昭25法73)
○相続税法基本通達(昭34直資10)
○財産評価基本通達(昭39直資56、直審(資)17)
○平成25年分の基準年利率
○平成26年分の基準年利率
○平成27年分の基準年利率
○平成28年分の基準年利率
索引
○事項索引
相続法における配偶者の居住権保護の方策とは
遺産分割等に関する見直しとは
遺言制度に関する見直しとは
法務局における遺言書の保管等に関する法律とは
遺留分制度の見直しとは
相続の効力等に関する見直しとは
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別寄与料制度)とは
第1 相続税のあらまし
相続税とはどのような税金か
相続税の基礎控除とはどういうことか
相続税がかかる遺産の額はどのくらいからか
相続税の納税義務者(個人)は
財産の種類ごとの所在の判定のしかたは
相続税の納税義務者(個人以外)は
町内会に財産を遺贈した場合は課税されるか
相続時精算課税制度とはなにか
相続税と贈与税の相互の関連性とは
贈与税とはどのような税金か
贈与税がかかるのはどのような場合か
みなし贈与にはどんなものがあるか
負担付贈与とはなにか
第2 相続人と相続分
1 相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と相続の順位は
戸籍証明書等の広域交付制度とは
法定相続情報証明制度とは
同時死亡の推定とは
内縁の妻は相続できるか
重婚的内縁関係にある者も労働基準法施行規則42条1項の内縁の妻にあたるか
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合の財産分与はどうなるか
内縁の妻は借家権を相続できるか
内縁の配偶者の居住権は
再婚した場合は相続権を失うか
子供のない妻は亡き夫に代わって義父の財産を相続できるか
離婚訴訟中に死亡した妻の財産を夫が相続できるか(推定相続人の廃除)
胎児は相続できるか
後妻の連れ子は相続できるか
人工授精で生まれた子は相続できるか
卵子提供により生まれた子は相続できるか
同性パートナーに相続させることができるか
認知とはどのようなことか
血縁上の父子関係のないことを知りながらなされた認知について、認知者自身が認知の無効を主張できるか
庶子出生の届出とは
死後認知はできるか
夫の死後、冷凍精子を体外受精して生まれた子は死後認知されるか
認知されていない非嫡出子が父子関係存在確認の訴えを提起することはできるか
女性への性別変更の審判が確定した生物学上の父に対し生殖補助医療により生まれた子は認知請求することができるか
人事訴訟の補助参加人の上訴期間は
二重資格の相続人とはどのような者をいうか
事実上の養子に相続権はあるか
戸籍上嫡出子とされている子(藁の上からの養子)は相続できるか
子との間に生物学上の父子関係が認められない場合であっても嫡出の推定を受けるか
養子は実父母に対しても相続権をもつか
遺産相続が目的である養子縁組は有効か
推定相続人から廃除することを目的とした死後離縁は認められるか
養子縁組無効確認の訴えを提起できる者の範囲は
戸籍の記載がない場合にも相続権はあるか
非嫡出子に相続権はあるか
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が憲法に反する場合とは
里子は里親の財産を相続できるか(特別養子)
養父母にも相続権はあるか
代襲相続人とはどのような者をいうか
養子の子に代襲相続権はあるか
もともと被相続人の傍系卑属(従姪)であった、養子縁組により被相続人と兄弟姉妹になった者の当該養子縁組前に生まれた子は、被相続人の代襲相続人になることができるか
おいやめいにも相続権はあるか
相続人になれない人とはどのような人か
遺言書を隠してしまった者でも相続人になれるのか
不当な利益を目的とせずに遺言書を破棄した者も相続欠格者となるか
相続欠格事由のある者について、被相続人がその相続人資格を回復させることができるか(欠格の宥恕)
相続欠格事由の存否に争いがあるような場合に、相続人の地位の存否を確認する訴訟を提起することができるか
共同相続人間の相続人の地位不存在確認の訴えは、共同相続人全員が訴訟当事者とならなければならないか
自己の相続分を全部譲渡した共同相続人の遺産確認の訴えにおける当事者適格は
いったん廃除した相続人にも相続させることはできるか(推定相続人廃除の取消)
遺産分割後に相続人廃除の申立てが棄却された相続人は、遺産分割の請求ができるか
勘当された子の相続権はどうなるか
相続させたくない人がいる場合はどうするか
推定相続人の廃除事由である「著しい非行」とはどのようなものか
相続廃除の取消に一定の条件を付けるには
相続人廃除の審判手続中に死亡した被廃除者の審判手続上の地位は承継されるか
相続人兼遺言執行者が被相続人の養子との間で遺留分に関する合意をしながら、その養子を推定相続人から廃除することはできるか
相続人に行方不明者がいる場合はどうするか
本人が死亡した場合、後見人は本人の残債務について支払わなければならないか
成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)とは
相続の開始とは
相続人がいない場合はどうなるか
所有者が死亡し、倒壊の危険がある隣の空き家の管理はどうすればよいか
相続財産管理人選任の請求ができる場合とは
相続財産管理人は相続財産に軽微な変更を加えることはできるか
死後事務委任契約の受任者は相続財産清算人選任の申立てができるか
取得時効の完成後に相続財産清算人が選任された場合、時効完成猶予の効力が認められるか
身寄りのない者から遺産全部の遺贈を受けた場合の手続は
相続人のいない借地権は消滅するのか
相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することはできるか
特別縁故者とはどのような者をいうか
相続放棄をした相続人が特別縁故者として相続財産の分与を受けることができるか
相続人でない人が被相続人の世話をしていた場合は
死後認知の訴えが提起されている場合に、特別縁故者は相続財産の分与を受けることができるか
不動産の共有者の1人が相続人なく死亡したときであっても、その特別縁故者は相続財産の分与を主張できるか
特別縁故者の相続人は相続財産分与の申立てができるか
過去の一時期の縁故によって特別縁故者と認められるか
被相続人の死後における特別の縁故は認められるか
被相続人の生存中にその財産を不当利得した者は特別縁故者となれるか
被相続人の遺言書を偽造した者でも特別縁故者として相続財産の分与を受けることができるか
相続人なく死亡した日本に居住する外国人の特別縁故者は
成年後見人は特別縁故者となれるか
介護付入居施設に入所中に死亡した者の遺産について、同施設は特別縁故者となり得るか
雇い主も特別縁故者と認められるか
特別縁故者への財産分与の審判後に新たに相続財産が見つかったときは
地方公共団体も特別縁故者となり得るか
被相続人が外国人である場合では
遺産分割の国際裁判管轄は
2 相続分
(1) 法定相続分と指定相続分
相続分の算定はどのようにするか
非嫡出子の法定相続分の取扱いは
非嫡出子の相続分にかかる最高裁決定による遡及効の取扱いは
相続により権利を承継した場合における対抗要件の要否
法定相続分と指定相続分はどちらが優先するか
長期間放置した遺産分割における具体的相続分の主張(特別受益・寄与分の主張)の取扱いは
遺言で相続分の指定がされている場合でも、相続債権者は法定相続分に応じて権利行使できるか
遺産分割が未了のままとなっている相続財産である振替株式を、相続人の債権者は差し押さえることができるか
相続資格が重複している人の相続分は
代襲相続人がいる場合の相続分は
相続分の一部を譲渡することはできるか
遺産分割協議をする前に相続人の1人が勝手に抵当権を設定することは許されるか
不動産の相続分を無断で譲渡され第三者への所有権移転登記が経由された場合、その相続分の所有を当該第三者に主張できるか
相続回復請求権とはどのような権利か
相続回復請求権は相続されるか
相続回復請求権と取得時効の関係
被相続人の実子でないのに実子として出生届がなされ、実子として養育されてきた者は被相続人の遺産を相続できるか
(2) 特別受益者と相続分
特別受益とはなにか
第三者の受益に伴う特別受益の取扱いは
特別受益の範囲は
相続人の居住の利益は特別受益にあたるか
教育費は特別受益にあたるか
死亡保険金請求権は特別受益ないしこれに準じるものとして持戻しの対象となるか
相続人が被相続人から土地の使用貸借権の設定を受けることは特別受益となるか
被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合は、持戻しの対象となるか
推定相続人でない者が被相続人から贈与を受けた後に代襲相続人になった場合、その贈与は特別受益に当たるか
配偶者を通じて、間接的に経済的利益を受けている場合は、特別受益として持戻しの対象となるか
養子縁組前に贈与された財産の相続財産への持戻しは
特別受益者の相続分の算定はどのようにするか
生前贈与に対する持戻免除とはなにか
生前贈与に対する持戻免除の意思表示はどのようにするか
配偶者に対する自宅の生前贈与は特別受益にあたるか
配偶者居住権は特別受益にあたるか
特別受益となる遺贈に対する持戻免除の意思表示は遺言でなされなければならないか
超過特別受益者がいる場合の相続分の算定はどのようにするか
特別受益額が具体的相続分を超過するとき、その超過分は寄与分から差し引かれるか
相続が開始して遺産分割が完了しない間に第二次相続が開始した場合において第二次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否は
特別受益に関して当事者間の合意がある場合の取扱いは
「相続させる」趣旨の遺言による特定の遺産承継は特別受益となるか
譲り受けた法定相続分の遺産は特別受益に当たるか
(3) 寄与分
寄与分とはなにか
被相続人の資産を運用したことによる資産の増加は、寄与分として認められるか
被相続人の扶養は寄与分と認められるか
相続開始後に遺産の維持・管理にあたった相続人の寄与は寄与分として認められるか
寄与分を受けることができるのはどのような者か
寄与者が廃除された者である場合、その寄与分はどう取り扱われるか
寄与分はどのように算定されるか
相続人全員に同等の寄与が認められる場合の取扱いは
共同相続人の遺留分を侵害する寄与分は認められるか(寄与分と遺留分の関係)
相続人になる以前の寄与分はどうなるか
相続人の配偶者の寄与を相続人の寄与として評価することはできるか
相続人の配偶者の寄与分は認められるか
遺言で相続分の指定がされた場合の寄与分はどうなるか
寄与分を遺言で定めることはできるか
寄与分は相続されるか
相続の放棄は寄与として認められるか
相続分の譲渡にともない寄与分も譲渡されるか
生前贈与や遺贈がある場合の寄与分の算定はどのようにするか
被相続人経営の会社への援助が寄与分として認められるか
寄与分を取得した場合の相続税の課税関係はどうなるか
特別の寄与とはなにか
法定相続分等のない相続人が遺留分侵害額請求を行使した場合、特別寄与料は負担するか
遺産分割未了のまま第2次相続が開始した場合、第2次相続についての登記を省略した所有権移転登記申請は認められるか
順次の相続が生じた場合においてなされた中間省略登記が実体関係と異なるときの登記の是正方法は
第3 相続の承認と放棄・財産分離
1 相続の承認と放棄
相続の単純承認とはどのようなことか
相続人が相続放棄の申述受理後、被相続人の遺品を持ち帰った行為は「相続財産の隠匿」に当たるか
被相続人の預金を解約し墓石購入費に充てた行為は「相続財産の処分」に当たるか
相続開始後、相続放棄の手続をする前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立ててその取立金を収受領得する行為は「相続財産の処分」に当たるか
相続財産である株式の株主権の行使および不動産の転貸料の受取人の変更は「相続財産の処分」にあたるか
相続の限定承認とはどのようなことか
限定承認者は相続債権者の調査をする義務があるか
限定承認者が不当に一部の相続債権者に弁済した場合はどのような責任を負うか
限定承認において、条件付債権等に当たらない債権につき裁判所が選任した鑑定人が債権額を鑑定した場合、当事者はこれに拘束されるか
限定承認の場合の相続財産清算人の地位・権限は
相続人が限定承認した場合、被相続人の債権者は相続財産に対して強制執行できるか
限定承認を取り消すことはできるか
相続の放棄はどのようにするか
相続させる旨の遺言を放棄することはできるか
相続を放棄した者は、相続財産についてどのような保存義務を負うか
相続人全員が相続を放棄した場合、遺産の管理等はどうなるか
自らも相続人である後見人が被後見人の相続の放棄をすることはできるか
相続人が遺産は何もないと誤信したことにより、相続放棄することなく熟慮期間を徒過してしまった場合、相続放棄はもはやできないか
熟慮期間の経過後に限定承認の却下がされたときも相続放棄をすることができるか
未成年の相続人の熟慮期間の起算点は
災害時における熟慮期間は
相続の放棄や限定承認はいつ意思表示すればよいのか
相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合、その相続人はどのような手続をすればよいか
相続人の1人が相続放棄した場合の相続分の算定はどうなるか
一次相続を放棄した場合の再転相続はどうなるか
二重資格の相続人が相続放棄をするには
相続放棄を取り消すことはできるか
相続放棄の錯誤取消しの主張は認められるか
相続放棄と登記
限定承認した相続人は死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗できるか
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為の効力はどうなるか
無権代理人が本人を共同相続した場合の無権代理行為の効力は
破産手続開始決定前の相続について開始決定後に破産者がなした単純承認または相続放棄の効力は
2 財産分離
相続人が多額の債務を負担していて財産を相続すると被相続人に対する債権者の債務の弁済ができなくなる場合にはどうしたらよいか
財産分離された相続財産を人手に渡さないことはできるか
第4 遺産分割
1 遺産の範囲
祭祀財産はどのように扱うのか
遺産から葬儀費用を支出することは認められるか
包括遺贈の遺言が存在する場合、その受遺者が祭祀承継者となるのか
成年被後見人を祭祀承継者に指定できるか
遺骨は誰に帰属するか
勲章は相続財産となるか
墓地は相続財産になるか
持分会社の社員の地位の相続は
譲渡制限株式の相続人に対する売渡請求とは、どのような制度か
雇用契約上の地位は相続されるか
保険金受取人が死亡保険金支払請求権を放棄した場合はどうなるか
生命保険契約において受取人が「法定相続人」とされていた場合、相続放棄した法定相続人も保険金を受領することができるか
生命保険金は遺産となるか
生命保険の保険金受取人とその相続人となるべき者が同時に死亡した場合に保険金を受け取ることができる者は
死亡保険金の受取人を変更する行為は遺贈または贈与にあたるか
相続預貯金は遺産分割の対象か
定額郵便貯金債権についての払戻しは
自動継続定期預金の払戻しはできるか
賃借権は相続できるか
改良住宅の使用権は承継できるか
特許権や著作権などは相続できるか
労災保険から支給される遺族補償年金は遺産となるか
遺族補償年金と損害賠償請求権との損益相殺的な調整
未払いとなっている扶養料請求権は相続の対象となるか
生活保護受給権は相続の対象となるか
居宅介護サービス費の支給を受ける権利は相続の対象となるか
離縁請求権は相続の対象となるか
連帯債務の相続はどうなるか
担保権の設定された土地が相続により共有になった場合、弁済による代位の割合を定める「頭数」はどうなるか
身元保証債務は相続されるのか
根抵当債務者が死亡した場合の相続はどうなるか
包括根保証人が死亡した場合の相続はどうなるか
退職金は遺産の範囲に含まれるか
銀行の貸金庫を開けるにはどうすればよいか
預金者の共同相続人の1人による預金口座の取引経過明細の開示請求は認められるか
受遺者以外の法定相続人は預金取引開示請求ができるか
相続人は預金契約解約後に取引経過の開示請求を金融機関に求めることはできるか
預金者の相続人による印鑑届書の開示請求は認められるか
相続開始後の家賃収入は遺産となるのか
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、共同相続人の1人は自己の相続分を超えて取得時効を援用できるか
被相続人の占有が他主占有であっても、相続人の自主占有による時効取得が認められるか
共同相続人の1人による相続財産の占有に取得時効が認められるか
被相続人と同居してきた相続人が相続開始後も当該建物を占有していることは不当利得に当たるか
被相続人と同居してきた相続人が相続開始後も当該建物に住むことができるか
配偶者居住権はどのような場合に取得できるのか
配偶者居住権と登記
配偶者居住権は譲渡できるか
配偶者居住権が設定されている建物の修繕費は誰が負担するのか
配偶者居住権を活用した後継ぎ遺贈型の不動産承継とは
配偶者短期居住権の制度趣旨と成立要件は
配偶者短期居住権が存続している間の配偶者の権利義務および第三者対抗要件は
配偶者短期居住権の消滅原因および終了後の法律関係は
売り主としての義務は引き継がなければならないか
株主代表訴訟中に死亡した取締役の責任は
罰金や追徴金は相続人が引き継がなければならないか
当座勘定取引契約は相続するか
口座振替契約は預金者の死亡によりどうなるか
財産分与の調停中に死亡した者の相続人は分与請求を承継できるか
ジョイント・アカウント預金は相続財産になるか
暗号資産は相続されるか
SNSのアカウントを相続できるか
破産者の相続人は免責を申し立てることができるか
遺産の範囲に争いのある場合の解決方法は
被相続人の子の名義の有価証券は相続財産になるか
遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟か
遺産の分割を禁止することはできるか
損害賠償請求権は遺産分割の対象となるか
1の2 分割協議
分割協議はどのように行うか
相続開始前に遺産分割協議を行った場合はどうなるか
法定相続分と異なる分割協議は有効か
相続分のないことの証明書の効力は
「相続分のないことの証明書」の作成・交付は相続分の譲渡・放棄にあたるか
数代前の相続登記がされている土地を相続した場合どうすればよいか
相続人の1人が行方不明のときはどうするか
相続人の1人が所在不明の場合に所在不明相続人の共有持分を取得できるか
相続人の1人が所在不明の場合に所在不明相続人の共有持分を含めて譲渡できるか
所在不明の相続人がいる場合に所有者不明土地管理制度を活用できるか
相続人が遠隔地にいる場合の遺産分割はどのようにするか
胎児がいるときの遺産分割協議はどのようにするか
親権者が子に代わって分割協議ができるか
未成年者に親権者がいない場合の遺産分割はどのようにするか
相続人の債権者は遺産分割の代位請求をおこせるか
遺産分割と登記の対抗関係は
扶養義務の債務不履行を理由に遺産分割協議をやり直すことはできるか
協議で定めたことが実行されないときはどうするか
分割協議をやり直すことはできるか
遺産分割審判後に、その財産は遺産ではないとの民事判決が確定した場合、審判の効力はどうなるか
遺産分割協議中に当事者が死亡したときは
相続人の1人が精神病の場合、遺産分割調停はどうすればよいか
共同相続人の一部を除外して行った遺産分割の効力は
一旦成立した遺産分割協議が後に確定判決で無効とされた場合において、当該分割協議に基づいて賃貸不動産を取得した相続人がその無効と判断される原因事実を知っていた場合、当該相続人は悪意の占有者にあたるか
相続人中に成年後見人と成年被後見人とがいる場合の遺産分割協議はどのように行うか
相続人の中に任意後見契約を締結している者がいる場合、遺産分割手続はどのように行えばよいか
分割禁止の遺産がある場合にはどうするか
相続分の譲受人は分割協議に参加できるか
農地を分割するにはどうすればよいか
相続分の譲渡に伴う農地の権利移転には農地法の許可が必要か
相続による農地の細分化を防ぐにはどのような方法があるか
遺言で相続人が定められている財産についても遺産分割の対象とすることができるか
遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効か
遺産分割協議の対象とならなかった定期預金債権の特定遺贈の効力は
ゴルフ会員権を相続する場合どうすればよいか
遺産分割協議書の真否を争うことはできるか
遺産分割協議後に相続人の1人が認知症であったことが判明したとき遺産分割協議はどうなるか
遺産分割協議書無効による分割代償金返還請求権の消滅時効の起算点は
遺産分割協議は詐害行為取消権行使の対象となるか
遺産分割協議によって共同相続人の1人が法定相続分を超える価額の遺産を取得した場合、破産管財人による否認権行使の対象となるか
遺産分割協議により取得した遺産に国税徴収法の「第二次納税義務」が発生するか
不在者財産管理人による遺産分割協議成立後に不在者が現れた場合の遺産分割協議の効力は
行政書士の関与により成立した遺産分割協議は有効か
特別代理人によってなされた遺産分割の内容が本人の法定相続分を侵害する内容であったことを理由に当該遺産分割は無効とならないか
遺産分割のやり直しその他の理由により相続人間で相続税の過多・過少負担が生じた場合に、過多負担となった相続人が過少負担となった相続人に対して不当利得返還請求でその不均衡の是正を図ることの是非は
相続登記の義務化とは
相続により取得した土地を国庫に帰属させることができるか
相続土地国庫帰属制度の処分に対する不服申立ての手続は
相続をした土地が国庫に帰属した後に、責任を負うことがあるか
相続により取得した隣接する2筆以上の土地に関する負担金算定額の特例とは
2 分割の方法
遺産分割にはどのような方法があるか
一団の土地を形成する複数の共有不動産について現物分割の請求があった場合の分割方法にはどのようなものがあるか
共同相続人の1人が遺産の現状を変更した場合、他の共同相続人は原状回復請求ができるか
遺産分割前に処分された財産は遺産分割の対象となるか
相続人の1人が、被相続人の預金通帳と届出印を持参して金融機関から預金の払戻しを受けた場合に、他の相続人が取り得る手段は
相続人の1人が、被相続人の生前および死後に預金口座から無断で出金したことに対し、不当利得返還請求権を行使する場合の権利割合はどうなるか
被相続人から払戻権限を与えられていた相続人の1人が、相続発生前に被相続人名義の預金を自らの預金に振り替えていた場合に他の相続人がとりうる手段は
預金債権の本人以外の者に対する払戻しが弁済として有効である場合に金融機関は遺留分権利者に対して過誤払いを防止すべきか
仮差押えされている物件は換価できるか
共有とする分割方法とは
遺産相続により共有となった財産を分割するために、共有物分割の訴えによることができるか
共有持分について相続が発生した場合の共有関係解消の方法は
使用権を設定する分割方法とは
代償財産の提供による分割方法とは
代償分割の債務不履行を理由に遺産分割の協議を解除できるか
分割の協議が成立しない場合は
遺産分割の審判に対する不服の申立てはいつまでにしなければならないか
相続預貯金につき遺産分割前に1人の相続人が払戻しを受けることは可能か
簡易生命保険の保険金の共同相続人は単独で自己の相続分に応じた支払いを求めることができるか
個人向け国債について相続分に応じた代金の請求はできるか
投資信託について相続分に応じた解約金を請求できるか
共同相続人の1人が自己の相続分に相当する投資信託受益権の金額の支払を請求することの可否は
境界紛争があり訴訟が係属中の土地は、どのように遺産分割手続を進めたらよいか
具体的相続分や特別受益の確認を求める訴えはできるか
遺産の一部分割は認められるか
遺産分割協議後に発見された遺産の分割は
適正な遺産分割のためには遺産評価の基準時をいつにすればよいか
死後被認知者の価額支払請求はどうするか
相続開始後に新たに子と推定された者の価額支払請求権
障害者である共同相続人の1人に扶養分として法定相続分を超える遺産を分けることができるか
相続財産中に同族会社(非公開会社)の株式が含まれている場合、遺産分割に当たってどのようなことに注意すればよいか
第5 遺言と遺留分
1 遺言の方式と効力
どのようなことを遺言できるか
遺言書で臓器提供の意思表示をすることができるか
親権者の一方が子に財産を遺贈する場合、その財産について他方の親権者の管理権を奪い、管理人を指定することができるか
「相続させる」と「遺贈する」とではどう異なるのか
遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させるには
相続させる旨の遺言と登記
相続させる旨の遺言による相続に代襲相続は認められるか
「相続させる」旨の遺言に負担付遺贈の規定は適用されるか
自筆証書遺言、秘密証書遺言の記載内容はどのように解釈されるか
「財産をすべて任せる」旨の遺言は包括遺贈と認められるか
遺言執行者に受遺者の選定を委託した遺言は有効か
住所のみが表示された不動産の遺贈は土地建物を目的としたものと解することができるか
共同で遺言をすることはできるか
遺言のしかたにはどのような方法があるか
エンディングノートの法的効力は
自筆証書遺言の作り方と加除訂正の方法は
自筆証書遺言における財産目録の作成方法は
自書によらない財産目録に署名押印がされていない自筆証書遺言は有効か
他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言は有効か
自筆証書遺言の有効性の判断における動画の実質的証拠力は
自筆証書遺言の加除訂正について、要式が欠けていても有効となることがあるか
日付・署名捺印の後に付記されている自筆証書遺言は無効か
自筆証書遺言の「署名・押印」の場所は
花押が書かれた自筆証書遺言の効力は
郵便はがきに書かれた文書は遺言として有効か
遺言が成立した日と相違する日付の自筆証書遺言は有効か
複数の筆跡鑑定が結論を異にする場合の自筆証書遺言の効力は
ICレコーダーやパソコンによって遺言することができるか
公正証書遺言書のデジタル化とは
法務局における自筆証書遺言の保管制度とは
遺言者は保管された遺言書の閲覧、撤回、変更ができるか
遺言書が法務局に保管されている場合の相続人の手続は
保管していた遺言書はどうするか
自筆証書遺言が複数ある場合の検認手続の範囲は
公正証書によって遺言をするには
通訳を介して公正証書遺言を作成できるか
口がきけない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
耳が聞こえない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
目が見えない場合は、どのようにしたら遺言ができるか
未成年者が遺言することはできるか
認知症患者の遺言には効力があるか
病により意識が低下した状態で作成された公正証書遺言の効力は
遺言能力が否定された遺言作成に関与した信託銀行の責任は
被後見人が後見人の利益となるべき遺言をした場合の効力は
証人は公正証書遺言に終始立ち会うことが必要か
証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言の効力は
遺言者が自己の氏名とは異なった署名をした公正証書遺言の効力は
公正証書遺言における遺言者の口授とは
秘密証書方式による遺言の方法は
ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題および本文を入力・印字した者は遺言書の筆者であると言えるか
公正証書遺言および秘密証書遺言の証人の欠格事由は
危急時にはどのような方法で遺言をすればよいか
危急時遺言における遺言者の口授とは
危急時遺言が失効となるときとは
家庭裁判所による危急時遺言の確認時に裁判所が得るべき心証の程度は
外国にいる日本人が遺言書を作成するときに注意することは
隔絶地にいる者が遺言をする方法は
遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力は
遺言で生命保険金の受取人を変更できるか
生命保険の契約者の地位または受取人の地位を遺言により処分することができるか
遺言者の死亡前または同時に受遺者が死亡した場合は
遺言を撤回するにはどうするか
文書全体に斜線が引かれた自筆証書遺言の効力はどうなるか
相続開始前に遺言者本人によって解約された定期預金の払戻金が、遺言書記載の「遺言者名義の預貯金債権」に該当するか
遺言書中の相続等の対象とされた「現金」に預金は含まれるか
遺言を撤回する遺言をさらに別の遺言で撤回した場合、当初の遺言の効力は復活するか
離婚前にされた前妻への遺言の効力は
老後の扶養を前提にした養子縁組とともになされた遺言は、その後の協議離縁により撤回したものとみなされるか
不動産を遺贈する旨の遺言は、当該不動産を売却するための専任媒介契約の締結により撤回したものとみなされるか
同時死亡を前提とした遺言の効力は
遺言書本文が封入された封筒の裏面に停止条件が記載されていた遺言の効力は
複数の推定相続人のうちの一部の者が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力は
遺言の執行はどのように行うか
遺言執行者と相続人が対立した場合はどうするか
遺言執行者がいる場合の特定遺贈は
遺言執行者による相続預金の払戻しの可否は
遺留分のない相続人に対する遺言内容通知義務の有無
遺言執行者による遺言の執行を妨げる処分行為の効力は
遺言執行者がいる場合の相続財産の処分は
清算型遺贈における不動産登記は
遺言執行者がいる場合の相続人による相続預金の払戻しの可否は
遺留分権利者は、遺言執行者が指定されている場合であっても相続人を債務者として遺産の処分禁止の仮処分の申立てができるか
遺言執行費用は誰が負担すればよいか
遺言執行者は相続財産から葬儀費用を支出できるか
遺言執行者の報酬はどのようにして決められるか
審判で決定された遺言執行者の報酬について不服申立てはできないか
遺言執行者の遺言執行状況の報告義務違反および相続財産目録交付義務違反について損害賠償を請求することができるか
遺言執行者の申立手続および解任事由
遺言執行者による執行途中の報酬受領と解任
遺言の無効を訴えることはできるか
遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺言無効確認の訴えは認められるか
特別縁故者に遺言無効確認の訴えの利益はあるか
前訴判決と矛盾する遺言の有効確認の訴えは認められるか
遺言信託とはどんなことか
遺言による公益信託とは
遺言代用信託とは
遺言信託、遺言代用信託における受益者連続型信託の活用とは
信託条項に「遺産分割協議で定める」とする条項は有効か
遺産分割の後で遺言が出てきたときにはどうするか
死亡後における事務処理を依頼する準委任契約と遺言の効力
遺言書を作成した上で専門家と死後事務委任契約を締結する際の注意点
遺言でデジタル情報の相続先や処理方法を定めることができるか
電子データ、NFTを相続するには
2 遺贈・死因贈与
遺贈・死因贈与とはなにか
死因贈与執行者には遺言執行者に関する規定が準用されるか
無効な遺言書が死因贈与契約を証する書面と認められるのはどのような場合か
贈与者よりも受贈者が先に死亡した場合の死因贈与の効力は
遺言により死因贈与契約は撤回できるか
遺贈寄付を選択するにはどうすればよいか
不倫の相手方に対する包括遺贈は公序良俗に反するか
死因贈与を原因とする銀行預金の譲渡はできるか
特定受遺者が遺贈を承認・放棄するには
負担付遺贈を放棄することはできるか
包括遺贈の放棄はどのようにすればよいか
複数の包括遺贈の一つが放棄された場合に、他の包括受遺者に帰属するか
被相続人が同一不動産をある相続人に贈与した後ほかの相続人にも遺贈した場合に、受贈者は登記をしなければ受遺者に対抗することができないか
遺贈の目的物が相続開始前に遺言者の成年後見人によって売却されたために相続財産に属さない場合の物上代位の可否は
相続人ではない負担付遺贈の受益者は受遺者に対して負担の履行を請求できるか
負担付特定財産承継遺言の取消しの可否は
ペットに関する遺言についての留意点
3 遺留分
遺留分とはなにか
遺留分の割合はどうなっているか
遺留分算定の基礎となる財産は
遺留分侵害額の算定方法は
侵害された遺留分を取り戻すには
遺留分侵害目的の養子縁組は効力があるか
認知症の人のために遺留分を確保するためには、どうすればよいか
相続開始前の贈与に対する遺留分侵害額請求を受贈者は取得時効を援用して拒むことができるか
養子縁組前の贈与に対する遺留分侵害額請求権はどうなるか
遺留分侵害額請求権は代位行使できるか
遺産分割協議の申入れに遺留分侵害額請求の意思表示が含まれるとされるのはどんな場合か
遺留分侵害額請求権を行使されたらどのように対応すればよいか
遺留分侵害額の請求をされた受遺者がすぐに金銭を用意できない場合はどうすればよいか
遺留分侵害額請求の順序はどうなっているか
複数の遺贈がある場合の遺留分侵害額請求の方法は
複数の贈与がある場合の遺留分侵害額請求の順序は
遺贈や贈与が相続人に対してされた場合の遺留分侵害額の算定方法は
相続人の1人に全財産を相続させるには
親が遺留分の放棄をしている場合に代襲相続できるか
遺留分の放棄を取り消すことができるか
遺留分の事前放棄の合意がなされたにもかかわらず遺留分侵害額請求をすることは認められるか
遺留分の算定において控除すべき被相続人の「債務」に保証債務は含まれるか
遺留分侵害額の算定にあたり、遺留分権利者が承継した相続債務の額を加算できるか
包括遺贈の遺言がある場合に遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分侵害額に加算できるか
遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点はいつと考えるべきか
相続の開始から10年を経過した後に、遺留分侵害額請求権を行使できるか
長年音信不通であった者からの遺留分侵害額請求は認められるか
4 遺留分の特例
中小企業経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例とは
遺留分に関する民法の特例を受けるための要件とは
遺留分に関する民法の特例の「除外合意」・「固定合意」とは
「除外合意」・「固定合意」の手続は
「除外合意」・「固定合意」の効力は
第6 課税財産と非課税財産
1 課税財産
相続税が課税される財産にはどのようなものがあるか
みなし相続財産とはどのようなものか
損害賠償請求権の相続は可能か、また相続税が課税されるか
被相続人が払った所得税等にかかる過納金の還付請求権は課税財産となるか
生命保険金受取人をたんに「相続人」と記載した場合は相続財産となるか
生命保険契約のケースごとの死亡保険金(一時金)に関する課税関係は
生命保険契約のケースごとの死亡保険金(年金払)に関する課税関係は
生命保険契約のケースごとの満期保険金に関する課税関係は
人身傷害補償保険金にかかる相続税および贈与税の課税関係は
保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の相続税の課税関係は
退職手当金や功労金に該当するかどうかの判定基準は
生命保険契約に関する権利にかかる税金は
相続人が小規模企業共済金を受け取った場合の相続税はどうなるか
特別縁故者が相続財産の分与を受けたときにかかる相続税は
特別寄与者が寄与料の支払を受けた場合にかかる相続税は
共有持分の変更をした場合、相続税・贈与税はどうなるのか
不動産の名義変更をした場合、贈与税は課税されるか
遺贈・死因贈与に対する課税はどのようになされるか
公益法人等への遺贈の課税関係は
特定一般社団法人等に対する相続税の課税制度とは
代償財産を提供された場合の登記手続と課税関係は
遺留分侵害額請求により取得した金員の課税価格への算入すべき価額は
親族の債務を弁済した場合でも贈与税はかかるか
募集株式の付与を受けると贈与税がかかるか
離婚による財産分与でも贈与税が課税されるか
等価交換方式で売買契約中の土地にかかる相続税はどうなるか
下宿する大学生に一括贈与した生活費や教育費は課税されるか
ゴルフ会員権を相続税評価額で売買した場合、課税されるか
相続人が外国に居住している場合の相続税の課税はどうなるか
海外在住者が海外財産を相続した場合、どのような場合に課税されるか
遺留分侵害額請求にもとづく判決と異なる内容の相続財産の分配を行った場合、課税はどうなるか
相続や贈与により取得した暗号資産は、相続税・贈与税の課税対象になるか。また、課税対象になった場合には、どのように評価するのか
配偶者居住権についての相続税・贈与税の課税関係はどうなるか
相続開始時点で売買契約中であった土地は相続税が課税されるか
2 非課税財産
相続税が課税されない財産にはどのようなものがあるか
弔慰金と退職手当金を区別する意味は
墓地、仏壇などを生前に取得したときは
高度の公益事業者に該当する具体的な要件は
私立幼稚園の教育用財産についての非課税要件は
生命保険金の非課税限度額は
心身障害者共済制度にもとづく給付金に相続税は課税されるか
建物更生共済契約にかかる相続税等の課税関係は
死亡退職手当金などの非課税限度額は
未支給年金を受け取った場合は、相続税の課税財産となるか
相続財産などを公益法人に寄附した場合の非課税制度とは
寄附した相続財産を公益法人等が売却した場合は
相続財産などを公益法人設立のために寄附した場合は
相続財産を特定非営利活動法人に贈与した場合は
建築協力金の債務控除の額はどうなるか
不動産信託についての相続税・贈与税は
特定公益信託に支出した相続財産は非課税となるか
公益事業を行う法人への遺贈につき非課税と認められる要件は
遺贈の非課税要件たる「税負担の不当減少がないこと」とは
公益法人等が遺贈財産を譲渡した場合は
相続税法66条と租税特別措置法40条関係の規定の差異は
相続開始時に支払期限の来ていない家賃等は課税されるか
やむを得ない理由により、他人名義で家屋を取得した場合の課税は
就労等のため日本に居住する外国人の国外財産への相続税の課税は
3 債務控除
債務控除とはなにか
被相続人の死亡後に確定した所得税額の債務控除はできるか
借金は債務控除の対象になるか
連帯債務・保証債務は控除できるか
葬式費用で控除できるもの・できないもの
告別式を2回行った場合、いずれも葬式費用として控除できるか
葬儀等の参列者に渡した商品券の購入費用は葬式費用として控除できるか
被相続人が加害者である場合の損害賠償金は債務控除できるか
被相続人の生存中に相続人が負担した医療費は債務控除できるか
遺言執行費用は債務控除できるか
合名会社の無限責任社員が死亡した場合、会社の債務について債務控除できるか
被相続人が生命保険付住宅ローンで家屋を取得していた場合、課税関係はどうなるか
固定資産税、市町村民税は債務控除できるか
被相続人の事業を継承した相続人が従業員に支払った退職金は相続債務か
外国に居住する相続人が負担した葬式費用は控除できないか
特別寄与料を制限納税義務者へ支払った場合、債務控除できるか
第7 相続・贈与税の計算
1 計算方法
相続税の計算はどのようにするか
相続税の総額の計算はどのようにするか
相続税の課税価格の算定時期は、相続開始時か遺産分割時か
遺産にかかる基礎控除額の計算はどのようにするか
各相続人の相続税額の算出方法は
非嫡出子の相続分に対する最高裁違憲決定と今後の相続税の取扱いは
法定相続人に含められない養子とは
相続税が2割加算される場合とは
未分割遺産の課税はどうするか
株式の信用取引による空売り中に相続が開始した場合はどうなるか
相続開始前7年以内の贈与は
贈与税の計算はどのようにするのか
負担付贈与の場合の課税価格の計算は
平成27年以降に直系尊属から財産の贈与を受けた場合の贈与税(暦年課税)の計算はどうなるか
令和4年1月1日において18歳または19歳である場合の贈与税の計算はどうなるか
贈与税の除斥期間が過ぎた後に贈与税の申告内容に誤りが判明した場合、相続財産への加算対象額はどうなるか
限定承認した場合の相続税と譲渡所得税はどうなるか
配偶者居住権等を消滅(譲渡)した場合の譲渡所得の計算は
相続等により取得した信託終了時の残余財産を譲渡する場合の譲渡所得の計算は
遺贈に対して遺留分侵害額の金額が確定した場合の相続税の計算は
贈与に対して遺留分侵害額の金額が確定した場合の贈与税・相続税の計算は
2 税額控除
贈与税額控除とはなにか
配偶者の税額軽減とはなにか
未成年者控除とはなにか
成年年齢の引下げによる未成年者控除額の計算はどうなるか
障害者控除とはなにか
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用は
障害者控除の控除不足額を控除することができる扶養義務者とは
相次相続控除とはなにか
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用は
外国税額控除とはなにか
相続税の災害減免措置とはどのようなことか
災害等により被害を受けた場合の相続税・贈与税の免除や緩和されるなどの税制上の措置とは
特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価は
特定居住用宅地にかかる評価額の軽減の特例とはなにか
特定事業用宅地にかかる評価額の軽減の特例とはなにか
不動産貸付事業用の敷地は特定事業用宅地に該当するか
特定計画山林にかかる評価額の軽減の特例とは
第8 相続・贈与税の申告と納付
1 申 告
相続税申告の手続はどうするか
相続税申告におけるマイナンバー制度とは
相続税申告における法定相続情報証明制度とは
相続税の申告書の提出期限はいつか
申告期限までに申告しなかった場合はどうするか
相続財産が分割されていないときの申告は
過少申告や過大申告があったときはどうするか
過少申告や無申告でも加算税が課されない「正当な理由」とは
遺産分割による申告に課税負担の錯誤があった場合に更正の請求はできるか
遺留分侵害請求による更正の請求を行う場合の提出期限は
胎児がいる場合の相続税の申告期限は
所得税の準確定申告とは
相続税申告における時効は
相続税の更正処分に不服のある場合はどうしたらよいか
贈与税の申告・納付における財産取得時期の判定は
区分所有権について建物と敷地利用権とを分けて贈与することは可能か
停止条件付遺贈の場合の申告はどうするか
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の課税はどうなるか
相続税の脱税犯とされるのはどんな場合か
重加算税が課税されるのはどんな場合か
申告漏れ等、相続手続に伴う税理士の責任は
外国国籍を取得した相続人が日本国籍を失っていないと誤信して行った相続税の申告について過少申告加算税等が課せられた場合に税理士に損害賠償責任が認められるか
国外転出(贈与・相続)時課税とは
新型コロナウイルス感染症による相続税の申告期限の延長はできるか
配偶者居住権の設定が申告期限後になった場合の相続税の申告はどうするか
2 納 付
相続税の納付はどのようにするか
相続税や贈与税の窓口納付以外の納付手続にはどのようなものがあるか
相続税納付における連帯納付の義務とは
相続税の延納とはなにか、利子税はどうなるか
延納はどのようにするか、担保の提供はどうなるか
延納期間の延長や変更はできるか
延納申請と物納申請との変更はできるか
相続税の延滞税はどのように計算されるか
延納の担保に提供している物件の売却や建替えはできるか
相続税の物納とはなにか
農地や山林は物納が認められるか
マンションやアパートは物納が認められるか
相続税の物納にあてることができる美術品とは
取引相場のない株式に係る株券は物納できるか
暗号資産は物納できるか
物納申請の撤回はどのようにするか
物納できない財産にはどのようなものがあるか
相続税額を超える価額の財産による物納はできるのか
未分割の遺産の相続税申告と物納は
物納が有利な場合とは
贈与税納付における延納制度とは
一画地の土地を分割し、分割後の土地を物納する場合の収納価額は
第9 相続財産の評価
1 不動産の評価
宅地の評価はどのようにするか
倍率方式による宅地の評価方法とは
路線価方式による宅地の評価方法とは
路線価方式による不整形地などの補正計算とは
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価はどのようにするか
私道の用に供されている宅地の評価は
路線価の付されていない私道に接する宅地の評価は
大規模工場用地の評価はどのようにするか
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例とは
小規模宅地等の特例において二世帯住宅の場合はどうなるか
小規模宅地等の特例において被相続人が老人ホームに入居していた場合はどうなるか
小規模宅地等の特例を受けた者が空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けることはできるか
不動産貸付けにかかる小規模宅地の特例とは
庭先部分を相続した場合、小規模宅地等の特例は適用できるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋の敷地を相続人が共有で相続した場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋とその敷地が被相続人と配偶者の共有となっていた場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺産分割により配偶者居住権が設定された家屋の敷地が他人からの借地である場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
相続開始の年に被相続人から宅地の贈与を受けていた場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
遺留分侵害額の請求により宅地を取得した場合、小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
法人所有建物の建替え中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用はどうなるか
土地区画整理事業中の宅地の評価は
造成中の宅地の評価はどのようにするか
「地積規模の大きな宅地の評価」はどのようにするか
広大地の評価はどのようにするか
農業用施設用地の評価はどのようにするか
区分地上権の評価はどのようにするか
利用制限のある宅地の評価はどのようにするか
借地権の評価はどのようにするか
地上権等(借地・区分地上権を除く)の評価はどうするか
容積率の異なる地域にわたる宅地の評価は
余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価は
セットバックを必要とする土地の評価はどのようにするか
都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価はどのようにするか
一つの土地に借地権・区分地上権等の権利が複相している土地の評価はどうするのか
定期借地権等の評価はどのようにするか
定期借地権等の目的となっている宅地の評価はどのようにするか
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価はどのようにするか
他人に貸している宅地の評価はどのようにするか
貸家の建っている土地の評価はどのようにするか
抵当権が設定されている土地の評価はどうするか
宅地の評価にあたって評価減とは
一体利用の宅地の中に赤道(国有地)が存する場合の評価は
単独取得地と共有取得地が隣接している場合の評価はどのようにするか
駐車場の評価はどうするのか
土壌汚染地の評価はどのようにするか
埋蔵文化財包蔵地の評価はどのようにするか
生物多様性維持協定が締結されている土地の評価はどのようにするか
家屋の評価はどのようにするか
家屋の附属設備などの評価はどのようにするか
他人に貸している家屋の評価はどのようにするか
重要文化財に指定されている家屋およびその敷地の評価はどうするのか
マンションを相続した場合の評価(賃貸・分譲)方法は
相続開始時に賃貸マンションに一部空き部屋がある場合のその敷地等の評価は
高層マンション(いわゆるタワマン)節税の評価はどうなるか
居住用マンションの区分所有財産はどのように評価するか
農地の評価はどのようにするか
市街化区域内の農地の評価はどうするか
貸農地の評価はどのようにするか
都市市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価方法は
農地法の許可を受けないで他人に貸し付けている農地の評価はどうなるか
認定事業計画に基づき貸し付けられている農地の評価はどうなるか
耕作権、永小作権などの評価はどのようにするか
占用権の評価はどのようにするか
山林の評価はどのようにするか
貸し付けられている山林の評価はどうするか
果樹園などの評価はどのようにするか
鉱泉地の評価はどのようにするか
立木の評価はどのようにするか
雑種地の評価はどのようにするか
遊園地等の用に供されている土地の評価はどのようになるか
市民緑地の用地として貸し付けられている土地の評価はどうするか
無償で貸し付けられている幼稚園の園舎敷地と運動場用地の評価は
ゴルフ場用地として貸し付けている土地の評価はどうするか
土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の貸宅地の評価はどうなるか
デューデリジェンスにもとづいて算定される不動産の鑑定評価を相続税の財産評価で採用できるか
相続開始後における不動産売買契約の解除と相続財産の評価は
財産評価基本通達により算定した評価額が時価を上回る場合は
東日本大震災により被害を受けた場合、相続や贈与により取得した土地や非上場株式の評価額はどうなるか
2 動産・株式などの評価
上場株式の評価はどのようにするか
上場株式の評価の特則とは
気配相場のある株式の評価はどのようにするか
取引相場のない株式の評価方法は
会社の規模と評価方式の判定はどのようにするか
類似業種比準価額方式による評価方法とは
兼業会社の会社規模の判定方法は
評価会社の事業が該当する業種目の判定は
類似業種比準価額方式における比準3要素が「零」である場合の評価は
相続開始の直前に評価会社が合併した場合の類似業種比準価額の計算は
純資産価額方式による評価方法とは
中会社の株式評価はどのようにするか
配当還元価額方式による評価方法とは
株式等保有特定会社の株式の評価方法は
S1+S2とはなにか
土地保有特定会社の株式の評価方法は
種類株式の評価方法は
遺留分に関する民法の特例の固定合意における株式の「相当な価額」とは
「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」とは
株式に関する権利の評価は
ストックオプションの評価はどのようにするか
上場新株予約権の評価はどのようにするのか
医療法人に対する出資の評価はどのようにするか
公社債などの評価はどのようにするか
ディスカウント債の評価方法は
個人向け国債の評価はどのようにするのか
抵当証券の評価はどのようにするか
不動産投資信託証券の評価はどのようにするか
開業後3年未満の会社の株式の評価方法は
開業前、休業中または清算中の会社の株式の評価方法は
預貯金の評価はどのようにするか
外貨建てによる財産の邦貨換算はどうするか
生命保険契約に関する権利の評価はどのようにするか
定期年金に関する権利の評価はどのようにするか
相続開始時点で年金の種類等が決められていない保険契約の「年金受給権」の評価はどのようにするか
ゴルフ会員権の評価はどのようにするか
営業権の評価はどのようにするか
絵や骨とう品、競走馬などの評価はどのようにするか
ペットの評価はどのようにするか
棚卸商品の評価はどうするのか
著作権の評価はどのようにするか
未収獲農産物の評価はどのようにするのか
船舶の評価はどのようにするか
無利息債務の評価はどのようにするか
配偶者居住権の評価はどのようにするか
第10 相続・贈与税対策
養子をとった場合の相続税は
生前贈与の節税効果は
公正証書による贈与の課税時期はいつか
相続時精算課税制度のメリット・デメリットは
生前贈与において暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するべきか
孫が相続時精算課税適用者である場合、相続税額の加算の規定は適用されるか
法人の事業承継の場合の「相続時精算課税適用者の特例」とは
個人版事業承継税制と「相続時精算課税」の特例との併用適用は
相続時精算課税にかかる土地または建物の価額特例とは
災害により被害を受けた場合、精算課税の災害特例や災害減免法による減免措置の重複適用はどうなるか
特定贈与者が死亡した場合、精算課税の災害特例はどうなるか
災害発生日前に相続時精算課税適用者が死亡している場合、精算課税の災害特例に係る継続所有要件の判定はどうなるか
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税および相続税の取扱いはどうなるか
相続時精算課税選択届出書を提出した後に贈与税の期限後申告書を提出することとなった場合、相続時精算課税の適用はどうなるか
相続時精算課税適用者が特定贈与者より前に死亡した場合、相続時精算課税にかかる権利または義務の承継はどうなるか
贈与の節税分岐点とはなにか
贈与税が課税されない財産にはなにがあるか
不動産贈与は現金贈与よりトクか
負担付贈与を有利に行うためには
子供名義で預金を積み立てたときは
親子間で土地の使用貸借をして受領した駐車場収益における課税関係はどうなるか
孫に対する財産分与の効果は
教育資金の一括贈与の非課税措置とは
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは
配偶者控除はどれだけ認められているか
特定障害者のための贈与税の優遇措置とは
配偶者控除の効果的な活用方法は
贈与を受けた配偶者が年の途中で死亡した場合でも配偶者控除が受けられるか
共稼ぎ夫婦が住宅を購入する場合は
相続時精算課税制度の住宅取得資金の贈与の特例とは
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは
住宅取得等資金の贈与を受けた後に、海外転勤となった場合の住宅資金等の贈与税の非課税特例の適用は
連年で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例の適用は
親の土地に子が家を建てるときは
子供へ土地や家屋の貸付をする方法は
親の借地上に子が家を建てるときは
親の家屋の底地を子が買い取るときは
山林についての相続税の納税猶予制度とは
親名義の建物に子が増築した場合は
空き地にアパートや貸しビルを建設することは
借入金で不動産を購入することは
土地や建物の等価交換と相続税対策
事業用資産の買換えと相続税への影響およびその効果
相続などを考慮した居住用財産の買換えは
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは
相続財産を売却した場合の譲渡所得の取得費加算の特例とは
相続開始時点で売買契約中であった土地の譲渡所得について相続税額の取得費加算の特例の適用はどうなるか
相続時までの土地の値上がり益に対する課税は相続税と所得税の二重課税となるか
優良住宅地等の譲渡の特例とは
賃貸用の国外中古建物を譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の特例計算とは
個人商店を法人成りさせることは
適格請求書発行事業者の事業を相続する場合の手続は
法人の事業承継問題にどう取り組むか
非上場株式等についての相続税の納税猶予制度(一般措置)とは
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度(一般措置)とは
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予・免除(特例措置)とは
非上場株式等の納税猶予制度(一般措置)における資産保有型会社等の該当判断は
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(一般措置)を受けるための手続は
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予および免除(特例措置)を受けるための手続は
相続に伴う遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)がされた場合の贈与税の納税猶予制度の取扱いは
非上場株式等についての相続税の納税猶予と小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例の併用は
非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税・納税猶予の特例(一般措置)とは
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)とは
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けるための手続は
自社株対策のポイントはなにか
自社株の評価額を引き下げるにはどうすればよいか
従業員持株制度を発足することは
自社株を生前贈与する場合の方法は
自社株の親子間売買において注意する点は
相続等により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例とは
信託の終了に伴い取得した非上場会社の株式を発行会社に譲渡した場合の特例とは
株式を相続する際にはどのような点に注意すればよいか
株式を共同相続した場合、株主権の行使はどうするか
株券を紛失してしまった場合の相続は
医業継続にかかる相続税の納税猶予制度とは
医業継続にかかる贈与税の納税猶予制度とは
医療法人の出資者全員が出資持分を同時に放棄し、持分のない医療法人に移行した場合の課税関係はどうなるか
医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例とは
農地についての相続税の納税猶予制度とは
相続税の納税猶予を適用している特例農地に太陽光パネルの設置を目的とした区分地上権を設定した場合の納税猶予の特例の継続は可能か
相続税の納税猶予の適用を受けている場合の特定貸付農地等の特例とは
特定生産緑地制度等の創設により納税猶予の対象となる特例農地等の範囲はどうなるか
相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例とは
農地についての贈与税の納税猶予制度とは
旧特定農業生産法人に使用貸借による権利の設定をした場合の贈与税の納税猶予の継続の特例とは
農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合の納税猶予の特例は
相続税対策のため変額保険契約を結ぶときに注意することは
保険契約者(保険料負担者)以外の者が保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合の課税関係はどうなるか
特定の美術品についての相続税の納税猶予制度とは
附録
○民法(抄)(明29法89)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平20法33)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令(平20政245)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平21経産令22)
○相続税法(昭25法73)
○相続税法基本通達(昭34直資10)
○財産評価基本通達(昭39直資56、直審(資)17)
○平成25年分の基準年利率
○平成26年分の基準年利率
○平成27年分の基準年利率
○平成28年分の基準年利率
索引
○事項索引
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。