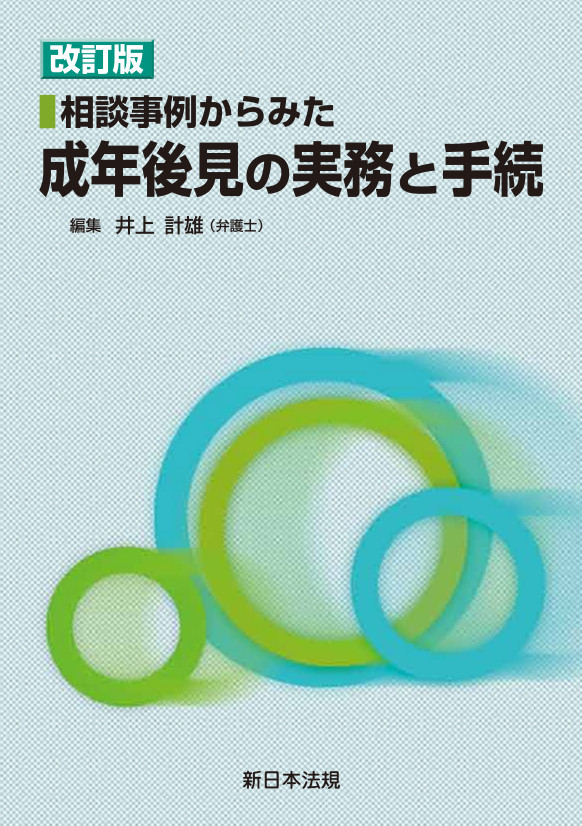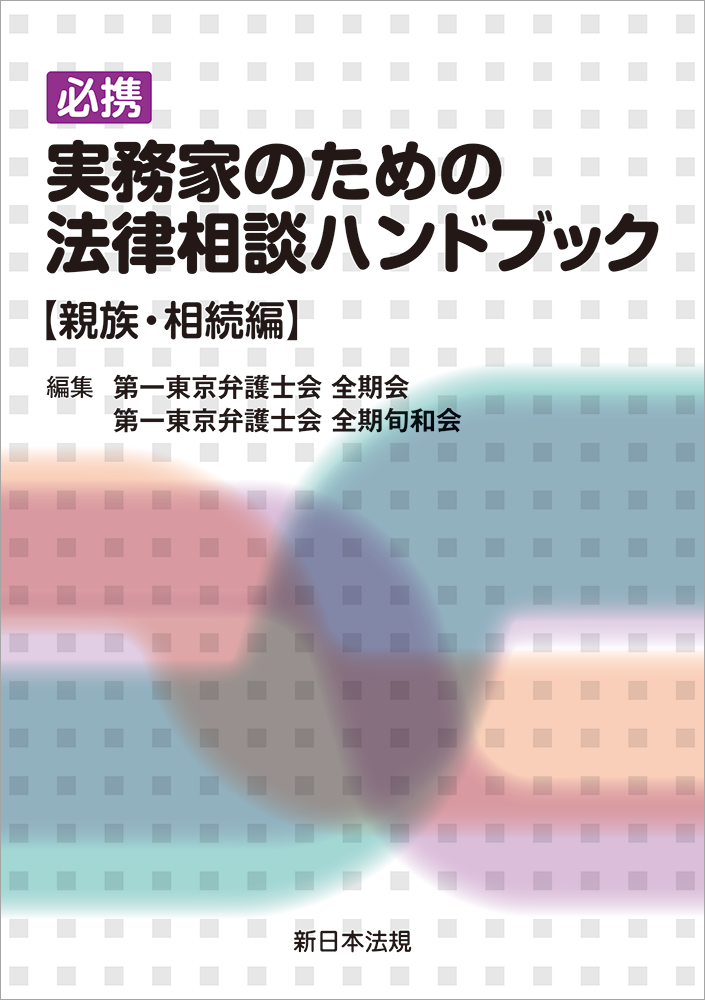概要
具体的な相談事例をもとにした実践的な内容!
《改訂版の特色》
・平成25年1月施行「家事事件手続法」に対応
・市民後見人に関する相談事例など、新たに13件の相談事例を登載
◆判断能力が不十分な人の日常生活や財産管理をフォローするために必要な【法定後見】【任意後見】【財産管理委任契約】【日常生活自立支援事業】の4つの制度について、各制度の概要から利用方法、具体的な実務上の問題までわかりやすく解説しています。
◆弁護士等の専門家をはじめ、「市民後見人」必携の書です。
◆実際に寄せられた具体的な相談事例98件をもとに、制度利用者の判断能力の程度や生活状況など諸事情を考慮した現実的な対応方法を解説しています。
どのような場合に、どのような制度を、どのように利用すべきかがわかります。
◆成年後見に関する各種申立書をはじめ、本人や後見人の候補者に関する照会書、診断書、鑑定書など、実務に役立つ書式を記載例入りで掲載しています。
商品情報
- 商品コード
- 50804
- ISBN
- 978-4-7882-7666-6
- JAN
- 9784788276666/1923032050005
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 510
- 発行年月
- 2012年12月
目次
1 法定後見の概要
1 法定後見にはどのようなものがあるか
2 浪費者に法定後見制度を利用できるか
3 法定後見を利用すべき場合とはどいういう場合か
4 未成年者でも成年後見等の対象にするべき場合は
5 親亡き後についてはどう対処すべきか
6 成年後見人等の代理権とは
7 成年後見人の同意権・取消権とは
8 利益相反とはどのような場合か
9 成年後見人の代理権の範囲は
10 成年後見等の開始によるデメリットは
2 申立て
11 精神上の障害とはどのようなものがあるか
12 本人による成年後見開始審判の申立ては可能か
13 内縁の妻以外に身寄りがないときは誰が申立てをしたらよいか
14 成年後見人が本人に代わって本人の親族の成年後見申立てをすることができるか
15 申立書に書くべきことは何か
16 申立てに必要な書類は何か
17 成年被後見人の身上や財産等がわからない場合に、どのように対応したらよいか
18 診断書はどのようにして入手したらよいか。診断書が用意できない場合はどうしたらよいか
19 申立てに際して、どれくらいの申立費用が必要か
20 申立費用は誰が負担すべきか
21 費用が負担できない場合はどうしたらよいか
22 市町村長が申立てをする場合とは
23 市町村長が申立てをする場合の注意は
24 後見開始等の申立ては取り下げることができるか
3 審理等
25 調査官の調査はどのようなものか
26 鑑定はどのように行われるか
27 申立類型と鑑定結果が異なった場合はどうなるか
28 身寄りのない人の成年後見人等の選任はどうなるか
29 どのような場合に不服申立てができるか
30 緊急に財産の管理が必要な場合はどうするか
31 緊急に本人の行為を制限する必要がある場合はどうするか
4 成年後見人等の実務
(1)選任直後にすべき事務
32 後見人はどのように本人の自己決定を尊重すればいいのか
33 市民後見人の特性と役割とは
34 後見人等はどこまで事実行為をする必要があるか
35 成年後見人は選任直後にどのようなことを行うか
36 成年後見人の財産目録の作成は、どのように行うか
(2)財産管理事務
37 財産管理事務とはどのようなものか
38 預貯金の管理についてどのような問題があるか
39 新規口座を開設する場合は
40 貸金庫の利用はできるか
41 成年被後見人の居住用不動産を処分できるか
42 後見人等が医療機関等から保証人になるように頼まれたときは、どうすればよいか
(3)身上監護事務
43 身上監護について成年後見人はどこまでしなければならないか
44 医療機関から医療同意を求められた場合、どのように対処すればよいか
45 入院治療を嫌がる成年被後見人にはどのように対応したらよいか
(4) その他の事務
46 成年後見人等は、家庭裁判所にどのような報告をしなければならないか
47 成年後見人は、成年被後見人死亡後、家庭裁判所に何か報告する義務はあるか
48 成年後見人等には報酬を受け取る権利があるか
49 本人死亡による後見終了後の報酬はどのようにして受け取ればよいか
50 保佐事務の中で新たに代理権を取得するには、どのようにしたらよいか
51 成年後見人等はどのような法的責任を負っているのか
52 虐待に対し成年後見人はどのように対応すべきか
53 成年後見人として親族とはどのように関わるべきか
(5)本人死亡後の処理
54 成年被後見人の死亡後の成年後見人の義務は何か
55 身寄りのない成年被後見人の葬儀はどうするか
56 成年被後見人の病院代等の支払いはどうするか
57 相続人がいない場合の財産の引継ぎはどうするか
58 所在不明の相続人がいる場合の財産の引継ぎはどうするか
59 相続人間の話し合いが決まらない場合の財産の引継ぎはどうするか
60 相続人が所在不明の場合の賃貸不動産等の保守管理は誰が行うか
61 死後事務を委任することはできるか
(6)保佐人・補助人・後見監督人
62 補助人・保佐人が事務を行うにあたり、本人の意思と対立が生じた場合、どのように対応すべきか
63 保佐人・補助人に財産管理権はあるか。あるとすればその範囲はどのようにして定められるか
64 被補助人が消費者被害に遭った場合、補助人はどのように対応すべきか。また、被害を予防するためにはどうすべきか
65 法定後見監督人はどのような職務を行うか
66 後見監督事務の遂行における後見事務の不適切事案にはどのようなものがあるか。後見監督人はそれらの事案についてどのように対応すべきか
67 後見制度支援信託とはどういうものか
■第2章 任意後見
1 任意後見の概要
68 任意後見とはどのような制度か。どういう場合に利用できるか
69 任意後見制度を利用する場合の費用はどのくらいかかるか
70 任意後見受任者が、本人の判断能力が低下しているのに後見監督人の選任申立てを怠っているときどうすればよいか
71 任意後見契約が締結されている場合でも、法定後見が開始されるか
2 契約締結
72 任意後見契約にはどのような内容を盛り込めばよいか。盛り込めない事項は何があるか
73 任意後見契約を締結するにはどうしたらよいか。注意すべき点はどこか
74 任意後見契約の締結後、任意後見受任者として何をしなければならないか
3 任意後見人の実務
75 任意後見監督人の選任申立ての手続は、どのようにすればよいか
76 任意後見人の職務とはどのようなものか
77 任意後見人として消費者被害にどう対応すればよいか
78 任意後見人はいつ、誰に報告をしなければならないか
4 任意後見監督人の実務
79 任意後見監督人は初期にどのような事務を行うのか
80 任意後見監督人の具体的職務はどのようなものか
81 任意後見監督人は任意後見人に対してどのような指導を行えばよいか
■第3章 財産管理委任契約
1 財産管理委任契約の概要
82 財産管理委任契約とはどういうものか。どのような利点があるか
83 財産管理委任契約と他の制度を併用することはできるか
84 財産管理委任契約を引き受けてくれるのは誰か
2 契約締結
85 財産管理委任契約にはどのような内容を盛り込むことができるか
86 財産管理委任契約を締結する場合の手続と留意点は何か
3 財産管理人の実務
87 財産管理人はどのようなことができるか。また、しなければならないか
88 財産管理委任契約には、どの程度の費用がかかるか
■第4章 日常生活自立支援事業
1 日常生活自立支援事業の概要
89 日常生活自立支援事業とはどのような制度か
2 契約締結
90 日常生活自立支援事業の内容にはどのようなものが含まれるか
91 日常生活自立支援事業の契約をするためにはどの程度の能力が必要か
92 契約を締結するにはどうすればよいか。費用はどの程度かかるか
3 実施機関の実務
93 日常生活自立支援事業の実施機関として行うべき業務はどのようなものか
94 契約者が消費者被害にあった場合、事業者が相手方と交渉し取り消すことができるか
4 契約の終了
95 契約が終了する場合はどのような場合か。また、終了する場合の処理として何が必要か
96 利用者の死亡により契約が終了した場合、どのようなことに留意すべきか
5 成年後見制度との関係
97 日常生活自立支援事業と成年後見制度の関係はどうなっているか
98 契約者の判断能力が低下して成年後見制度を活用することになった場合、日常生活自立支援事業は利用することができるか
参考書式
〈大阪家庭裁判所の書式例〉
○申立書類チェックリスト
○後見等開始申立書
○診断書
○鑑定についてのおたずね
○本人に関する照会書
○代理行為目録
○同意行為目録
○親族関係図
○財産目録
○収支目録
○候補者に関する照会書
○陳述書
○同意書
〈東京家庭裁判所の書式例〉
○後見開始申立書
〈共通、その他の参考書式例〉
○登記されていないことの証明申請書1(本人が申請する場合)
○登記されていないことの証明申請書2(代理人が申請する場合)
○鑑定書の記載例(認知症・後見開始の審判の場合)
○鑑定書(成年後見用・要点式)
○審判前の保全処分申立書
○居住用不動産処分許可申立書
○成年後見人に対する報酬付与審判申立書
〈任意後見用の書式例〉
○代理権目録(附録第1号様式)
○代理権目録(附録第2号様式)
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。