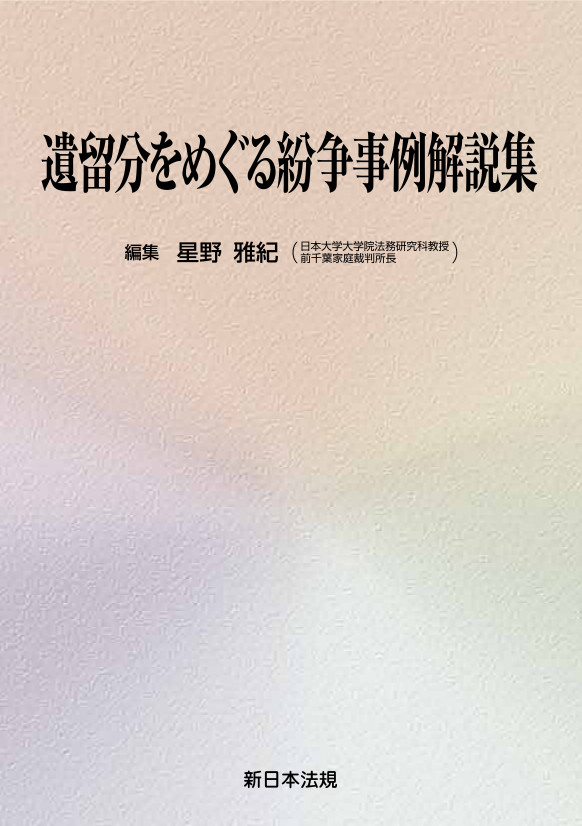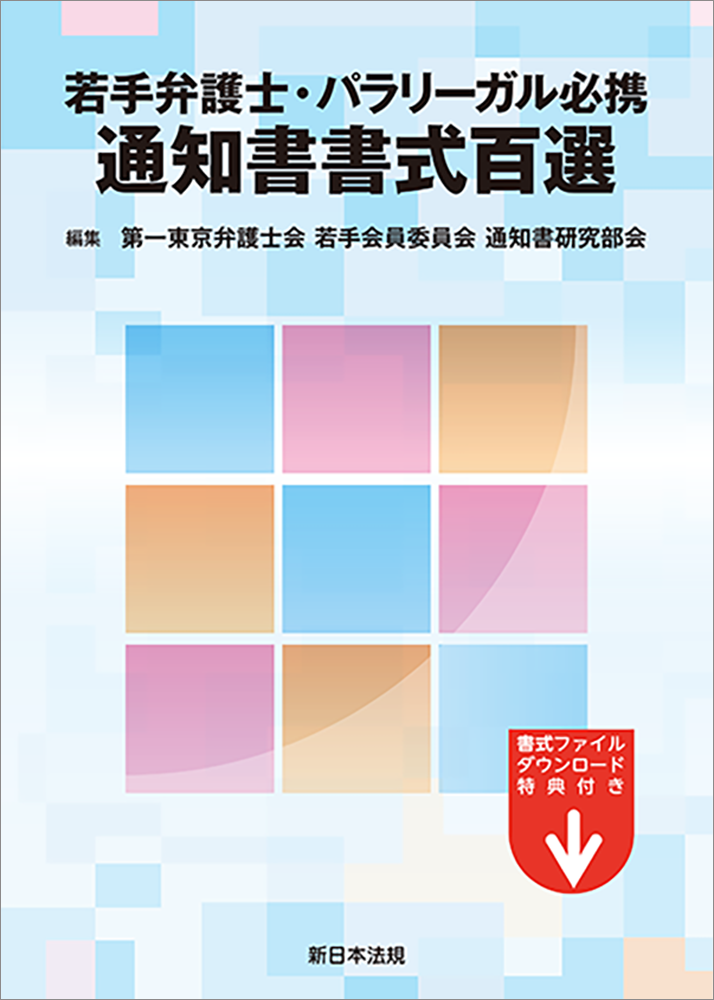- 相続・遺言
- 単行本
遺留分をめぐる紛争事例解説集
編集/星野雅紀(日本大学大学院法務研究科教授・前千葉家庭裁判所長)
概要
遺留分について争われた94の裁判例を解説!
◆実務の指針となる紛争事例を収載
遺留分をめぐって争われた多数の裁判例の中から、実務の指針となる事例を取り上げ、わかりやすく解説しています。
◆複雑な関係を整理・検討
各事例では、【事案の概要】【当事者の主張】【裁判所の判断】等により、複雑な当事者の関係、紛争の経緯をわかりやすく示すとともに、【コメント】にて実務的な観点からの考察を加えています。
商品情報
- 商品コード
- 81260002
- ISBN
- 978-4-7882-7486-0
- ページ数
- 498
- 発行年月
- 2009年3月
目次
■序 章
概 説
○相続開始前に遺留分を侵害されたとして不動産仮登記を求めることの可否
○遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記申請の可否
■第1章 遺留分
概 説
第1 遺言と遺留分
○家督相続開始前相続人以外の者に対してした被相続人の全財産の贈与について公序良俗違反を理由に無効を求めることの可否
○被相続人が相続人の一人に対してした全財産の遺贈について公序良俗違反を理由に無効を求めることの可否
○女戸主がした財産留保について家督相続人の遺留分を害することを理由に無効を求めることの可否
○遺言者の財産全部の包括遺贈について、遺留分権利者が受遺者に対し減殺請求権を行使して所有権移転登記手続を求めることの可否
○特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合の遺留分減殺請求訴訟において、(1)遺言執行者を被告とすること、及び、(2)相続人の譲受人に対して遺留分減殺を求めることの可否
○全部相続させる趣旨の遺言がされた場合、法定相続分に応じて分割された相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
第2 遺留分の財産の範囲
○相続開始1年前の贈与のうち、遺留分算定の基礎となる財産に参入すべき「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与(民法1030条後段)の意義
○「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与(民法1030条後段)に該当するか否かの具体的判断要素
○停止条件付贈与契約の場合の「1年前」(民法1030条)の標準時
○受給権者ないし受取人が固有の権利として取得する死亡退職手当、遺族年金及び生命保険金の特別受益該当性
○相続人の一人を受取人と指定した保険金請求権を遺留分算定の基礎とすること及び遺留分減殺請求の対象とすることの可否
○民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象(民法1030条の定める要件を満たすことの要否)
第3 財産の評価・算定方法
○遺留分侵害の有無の算定時期と算定方法
○負担付贈与と遺留分減殺請求権
○相続人が被相続人から贈与された金銭についての特別受益額の算定方法
○共同相続人の一部の相続放棄と他の共同相続人の遺留分
○被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
第4 遺留分と特別受益
○被相続人が設立し経営していた会社からの相続人に対する死亡弔慰金の支払は特別受益に当たるか
○被相続人を被保険者とする生命保険契約において、保険金受取人が「相続人」と指定されていたときに、相続人が取得した生命保険金は特別受益財産に当たるか
○遺留分の基礎財産の算定における、特別受益についての持戻し免除の意思表示の効力
○自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と、民法1031条に規定する遺贈又は贈与との該当性
第5 遺留分と寄与分
○遺留分減殺請求訴訟において、寄与分を抗弁として請求することの可否
○寄与分を定めるに当たって、他の相続人の遺留分について考慮しないことの可否
第6 遺留分と債務
○遺留分の侵害額を算定するに当たって遺留分額から控除すべき「債務」に被相続人の保証債務を含めることの可否
■第2章 遺留分の減殺(遺留分減殺請求権)
概 説
第1 遺留分減殺請求権の当事者
○遺留分減殺請求権の性質
○受贈者が目的物についての他の受贈者の持分を他の受贈者の持分放棄によって取得した場合に、遺留分権利者が民法1040条1項ただし書に基づき当該受贈者に対しその善意悪意にかかわらず遺留分減殺請求をすることの可否
○自己の遺留分の範囲内で贈与又は遺贈を受けている受贈者又は受遺者に対する遺留分減殺請求の可否
○不動産を相続人の一人に相続させ、遺言執行者を指定した遺言がある場合、他の相続人が遺留分減殺による所有権一部移転登記手続を求める訴訟を提起する際の被告
○包括遺贈の減殺請求の相手方
○遺留分減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否及び同請求権の消滅時効期間の起算点
○遺留分減殺請求後に受遺者が目的物を第三者に譲渡した場合に遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償の請求をすることの可否
○遺留分権利者が受遺者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合に受遺者が価額弁償をして損害賠償義務を免れることの可否
第2 遺留分減殺請求権の行使
○遺贈の目的物が複数ある場合における減殺請求権行使の方法
○相続人に対する遺贈と民法1034条の「目的の価額」の趣旨
○複数の贈与がある場合の減殺の方法
○同一人に対する贈与、遺贈の目的物が複数存在する場合の遺留分権利者の選択権の有無
○遺贈、死因贈与及び生前贈与がある場合の減殺の順序
○遺贈より前に贈与の減殺をすることの可否
○贈与の時期を異にする数個の贈与財産に対する遺留分減殺請求権の行使方法
○受遺者への生前贈与の否認と遺留分減殺の意思表示
○遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立てと遺留分減殺の意思表示
○遺産分割協議の申入れと遺留分減殺の意思表示
○被相続人の生前、相続人間で遺留分の放棄について合意している場合に遺留分減殺請求権の行使が権利濫用となる場合(1)
○被相続人の生前、相続人間で遺留分の放棄について合意している場合に遺留分減殺請求権の行使が権利濫用となる場合(2)
○遺留分減殺請求権の行使により遺留分権利者に帰属する権利の性質(1)
○遺留分減殺請求権の行使により遺留分権利者に帰属する権利の性質(2)
第3 遺留分減殺請求権の消滅
○遺留分減殺請求権の行使の結果生じた目的物の返還請求権等と民法1042条所定の消滅時効
○(1)民法1042条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時の意義
(2)遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張している時と減殺すべき贈与があったことを知ったと推認される場合
○相続人の一人に遺贈をする旨の遺言書の存在を知った他の相続人が訴訟で同遺言の効力を争っていた場合と遺留分減殺請求権の短期時効の起算点
○遺留分権利者が遺贈の無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかった場合における遺留分減殺請求権の消滅時効の開始時期
○(1)受贈者に対する遺留分減殺請求がなされた後に転得行為があった場合、転得者に対し重ねて減殺請求をすることの許否(消極)
(2)贈与の目的物を転得した者に対する遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点
○遺留分減殺請求権の行使と時効中断の関係
○遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者へのその目的物についての権利の帰属
○共同相続人の一部の間で土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告がその土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否
第4 遺留分減殺請求に関する手続
(1) 訴訟手続
○共有物分割と遺産分割を審判手続の中で併せて行うことの可否
○遺留分減殺請求訴訟における自己の取得分を増大させるため、遺産分割の申立てがされていないにもかかわらず、寄与分を定める処分の申立てをすることの可否
○遺産分割審判における遺留分減殺請求権行使の事実及びその効果を主張することの可否
○日本民法と相続分等の割合が異なる他国民法を適用することの可否
○価額弁償の抗弁が提出されていない場合に、遺留分権利者から価額弁償を請求することの可否
○遺留分減殺の抗弁に対し、原告が価額弁償の再抗弁を主張した場合に、弁償額の弁済をするか又はその提供を条件として請求を認容することの可否
○遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において、受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合の判決主文(1)
○遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において、受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合の判決主文(2)
(2) 保全処分等
○遺言無効の訴えの本案性について
○遺留分減殺請求による土地共有持分の返還請求権を被保全権利とする処分禁止仮処分と特別事情による取消し
○遺留分減殺請求に基づく共有持分移転の仮登記仮処分を求める場合の疎明内容
(3) 債権者代位
○遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
○遺留分減殺請求権に対して債権差押えをすることの可否
■第3章 価額による弁償
概 説
○遺留分権利者が受贈者又は受贈者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
○特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
○遺留分減殺の訴えの判決確定後に民法1041条に定める価額弁償を行うことの可否
○受贈者が目的物を第三者に処分した後に遺留分減殺請求がなされた場合の価額弁償の基準時
○遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
○価額弁償請求訴訟における弁償金に対する遅延損害金の起算点
○遺留分権利者が、遺留分減殺によって取得した遺贈の目的物の所有権等を失い、価額弁償請求権を確定的に取得する時期
■第4章 遺留分の放棄
概 説
○(1)遺産分割協議の申入れと遺留分減殺の意思表示の関係
(2)留置期間満了で返戻された内容証明郵便による遺留分減殺の意思表示の到達
○推定相続人廃除審判に対する即時抗告中に遺留分放棄が認められた場合の廃除審判の可否
○将来、履行が確実といえない贈与契約による遺留分の認否
○遺留分放棄の許可審判と非訟事件手続法19条1項の準用によるその取消しの認否
○遺留分放棄許可審判取消しの申立ての可否
○遺留分放棄許可審判の取消しが許されるための要件
○遺留分放棄の許可取消しの申立てに基づく審判に対する不服申立ての可否
■第5章 その他
第1 遺留分と登記
○遺贈に係る不動産につき遺留分減殺請求権行使の結果、共有権者となった者から、当該不動産の第三取得者に対する登記の全部抹消請求の可否
○被相続人が遺産である不動産を相続人の一人に包括遺贈した場合、他の相続人は、遺留分減殺請求権の行使の結果、当該不動産について遺留分割合による共有持分の移転登記手続を請求することの可否
○遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することの可否
○不動産を単独相続した相続人が法定相続登記を単独相続登記に更正登記手続することを求めたのに対し、他の相続人が遺留分減殺請求権を行使したことを抗弁として主張することの可否
第2 遺留分と税務
○法人に対する遺贈を目的としてされた遺留分減殺請求につき価額弁償がされた場合における所得税法59条1項のみなし譲渡課税の成否
○遺贈を受けた法人が価額弁償により遺留分減殺請求に伴う現物返還を免れた場合における価額弁償額の損金算入時期
○遺留分減殺請求に係る訴訟が係属していた場合における租税特別措置法39条1項所定の期間の起算点
○遺留分減殺義務者から価額弁償を受けた場合における相続税法34条1項の相続税連帯納付義務
第3 その他
○韓国民法の遺留分制度における贈与、特別受益等の解釈
○遺留分減殺請求事件を受任した弁護士が期待された職務の遂行を怠ったとして慰謝料の支払を命じられた事例
○弁護士である遺言執行者が遺留分減殺請求事件の代理人となることと弁護士倫理(当時)
※ 内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
概 説
○相続開始前に遺留分を侵害されたとして不動産仮登記を求めることの可否
○遺留分減殺を登記原因とする所有権移転登記申請の可否
■第1章 遺留分
概 説
第1 遺言と遺留分
○家督相続開始前相続人以外の者に対してした被相続人の全財産の贈与について公序良俗違反を理由に無効を求めることの可否
○被相続人が相続人の一人に対してした全財産の遺贈について公序良俗違反を理由に無効を求めることの可否
○女戸主がした財産留保について家督相続人の遺留分を害することを理由に無効を求めることの可否
○遺言者の財産全部の包括遺贈について、遺留分権利者が受遺者に対し減殺請求権を行使して所有権移転登記手続を求めることの可否
○特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合の遺留分減殺請求訴訟において、(1)遺言執行者を被告とすること、及び、(2)相続人の譲受人に対して遺留分減殺を求めることの可否
○全部相続させる趣旨の遺言がされた場合、法定相続分に応じて分割された相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
第2 遺留分の財産の範囲
○相続開始1年前の贈与のうち、遺留分算定の基礎となる財産に参入すべき「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与(民法1030条後段)の意義
○「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与(民法1030条後段)に該当するか否かの具体的判断要素
○停止条件付贈与契約の場合の「1年前」(民法1030条)の標準時
○受給権者ないし受取人が固有の権利として取得する死亡退職手当、遺族年金及び生命保険金の特別受益該当性
○相続人の一人を受取人と指定した保険金請求権を遺留分算定の基礎とすること及び遺留分減殺請求の対象とすることの可否
○民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象(民法1030条の定める要件を満たすことの要否)
第3 財産の評価・算定方法
○遺留分侵害の有無の算定時期と算定方法
○負担付贈与と遺留分減殺請求権
○相続人が被相続人から贈与された金銭についての特別受益額の算定方法
○共同相続人の一部の相続放棄と他の共同相続人の遺留分
○被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
第4 遺留分と特別受益
○被相続人が設立し経営していた会社からの相続人に対する死亡弔慰金の支払は特別受益に当たるか
○被相続人を被保険者とする生命保険契約において、保険金受取人が「相続人」と指定されていたときに、相続人が取得した生命保険金は特別受益財産に当たるか
○遺留分の基礎財産の算定における、特別受益についての持戻し免除の意思表示の効力
○自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と、民法1031条に規定する遺贈又は贈与との該当性
第5 遺留分と寄与分
○遺留分減殺請求訴訟において、寄与分を抗弁として請求することの可否
○寄与分を定めるに当たって、他の相続人の遺留分について考慮しないことの可否
第6 遺留分と債務
○遺留分の侵害額を算定するに当たって遺留分額から控除すべき「債務」に被相続人の保証債務を含めることの可否
■第2章 遺留分の減殺(遺留分減殺請求権)
概 説
第1 遺留分減殺請求権の当事者
○遺留分減殺請求権の性質
○受贈者が目的物についての他の受贈者の持分を他の受贈者の持分放棄によって取得した場合に、遺留分権利者が民法1040条1項ただし書に基づき当該受贈者に対しその善意悪意にかかわらず遺留分減殺請求をすることの可否
○自己の遺留分の範囲内で贈与又は遺贈を受けている受贈者又は受遺者に対する遺留分減殺請求の可否
○不動産を相続人の一人に相続させ、遺言執行者を指定した遺言がある場合、他の相続人が遺留分減殺による所有権一部移転登記手続を求める訴訟を提起する際の被告
○包括遺贈の減殺請求の相手方
○遺留分減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否及び同請求権の消滅時効期間の起算点
○遺留分減殺請求後に受遺者が目的物を第三者に譲渡した場合に遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償の請求をすることの可否
○遺留分権利者が受遺者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した場合に受遺者が価額弁償をして損害賠償義務を免れることの可否
第2 遺留分減殺請求権の行使
○遺贈の目的物が複数ある場合における減殺請求権行使の方法
○相続人に対する遺贈と民法1034条の「目的の価額」の趣旨
○複数の贈与がある場合の減殺の方法
○同一人に対する贈与、遺贈の目的物が複数存在する場合の遺留分権利者の選択権の有無
○遺贈、死因贈与及び生前贈与がある場合の減殺の順序
○遺贈より前に贈与の減殺をすることの可否
○贈与の時期を異にする数個の贈与財産に対する遺留分減殺請求権の行使方法
○受遺者への生前贈与の否認と遺留分減殺の意思表示
○遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立てと遺留分減殺の意思表示
○遺産分割協議の申入れと遺留分減殺の意思表示
○被相続人の生前、相続人間で遺留分の放棄について合意している場合に遺留分減殺請求権の行使が権利濫用となる場合(1)
○被相続人の生前、相続人間で遺留分の放棄について合意している場合に遺留分減殺請求権の行使が権利濫用となる場合(2)
○遺留分減殺請求権の行使により遺留分権利者に帰属する権利の性質(1)
○遺留分減殺請求権の行使により遺留分権利者に帰属する権利の性質(2)
第3 遺留分減殺請求権の消滅
○遺留分減殺請求権の行使の結果生じた目的物の返還請求権等と民法1042条所定の消滅時効
○(1)民法1042条にいう減殺すべき贈与があったことを知った時の意義
(2)遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張している時と減殺すべき贈与があったことを知ったと推認される場合
○相続人の一人に遺贈をする旨の遺言書の存在を知った他の相続人が訴訟で同遺言の効力を争っていた場合と遺留分減殺請求権の短期時効の起算点
○遺留分権利者が遺贈の無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかった場合における遺留分減殺請求権の消滅時効の開始時期
○(1)受贈者に対する遺留分減殺請求がなされた後に転得行為があった場合、転得者に対し重ねて減殺請求をすることの許否(消極)
(2)贈与の目的物を転得した者に対する遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点
○遺留分減殺請求権の行使と時効中断の関係
○遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者へのその目的物についての権利の帰属
○共同相続人の一部の間で土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告がその土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否
第4 遺留分減殺請求に関する手続
(1) 訴訟手続
○共有物分割と遺産分割を審判手続の中で併せて行うことの可否
○遺留分減殺請求訴訟における自己の取得分を増大させるため、遺産分割の申立てがされていないにもかかわらず、寄与分を定める処分の申立てをすることの可否
○遺産分割審判における遺留分減殺請求権行使の事実及びその効果を主張することの可否
○日本民法と相続分等の割合が異なる他国民法を適用することの可否
○価額弁償の抗弁が提出されていない場合に、遺留分権利者から価額弁償を請求することの可否
○遺留分減殺の抗弁に対し、原告が価額弁償の再抗弁を主張した場合に、弁償額の弁済をするか又はその提供を条件として請求を認容することの可否
○遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において、受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合の判決主文(1)
○遺留分権利者からの不動産持分移転登記手続請求訴訟において、受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合の判決主文(2)
(2) 保全処分等
○遺言無効の訴えの本案性について
○遺留分減殺請求による土地共有持分の返還請求権を被保全権利とする処分禁止仮処分と特別事情による取消し
○遺留分減殺請求に基づく共有持分移転の仮登記仮処分を求める場合の疎明内容
(3) 債権者代位
○遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
○遺留分減殺請求権に対して債権差押えをすることの可否
■第3章 価額による弁償
概 説
○遺留分権利者が受贈者又は受贈者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
○特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義
○遺留分減殺の訴えの判決確定後に民法1041条に定める価額弁償を行うことの可否
○受贈者が目的物を第三者に処分した後に遺留分減殺請求がなされた場合の価額弁償の基準時
○遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
○価額弁償請求訴訟における弁償金に対する遅延損害金の起算点
○遺留分権利者が、遺留分減殺によって取得した遺贈の目的物の所有権等を失い、価額弁償請求権を確定的に取得する時期
■第4章 遺留分の放棄
概 説
○(1)遺産分割協議の申入れと遺留分減殺の意思表示の関係
(2)留置期間満了で返戻された内容証明郵便による遺留分減殺の意思表示の到達
○推定相続人廃除審判に対する即時抗告中に遺留分放棄が認められた場合の廃除審判の可否
○将来、履行が確実といえない贈与契約による遺留分の認否
○遺留分放棄の許可審判と非訟事件手続法19条1項の準用によるその取消しの認否
○遺留分放棄許可審判取消しの申立ての可否
○遺留分放棄許可審判の取消しが許されるための要件
○遺留分放棄の許可取消しの申立てに基づく審判に対する不服申立ての可否
■第5章 その他
第1 遺留分と登記
○遺贈に係る不動産につき遺留分減殺請求権行使の結果、共有権者となった者から、当該不動産の第三取得者に対する登記の全部抹消請求の可否
○被相続人が遺産である不動産を相続人の一人に包括遺贈した場合、他の相続人は、遺留分減殺請求権の行使の結果、当該不動産について遺留分割合による共有持分の移転登記手続を請求することの可否
○遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することの可否
○不動産を単独相続した相続人が法定相続登記を単独相続登記に更正登記手続することを求めたのに対し、他の相続人が遺留分減殺請求権を行使したことを抗弁として主張することの可否
第2 遺留分と税務
○法人に対する遺贈を目的としてされた遺留分減殺請求につき価額弁償がされた場合における所得税法59条1項のみなし譲渡課税の成否
○遺贈を受けた法人が価額弁償により遺留分減殺請求に伴う現物返還を免れた場合における価額弁償額の損金算入時期
○遺留分減殺請求に係る訴訟が係属していた場合における租税特別措置法39条1項所定の期間の起算点
○遺留分減殺義務者から価額弁償を受けた場合における相続税法34条1項の相続税連帯納付義務
第3 その他
○韓国民法の遺留分制度における贈与、特別受益等の解釈
○遺留分減殺請求事件を受任した弁護士が期待された職務の遂行を怠ったとして慰謝料の支払を命じられた事例
○弁護士である遺言執行者が遺留分減殺請求事件の代理人となることと弁護士倫理(当時)
※ 内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。