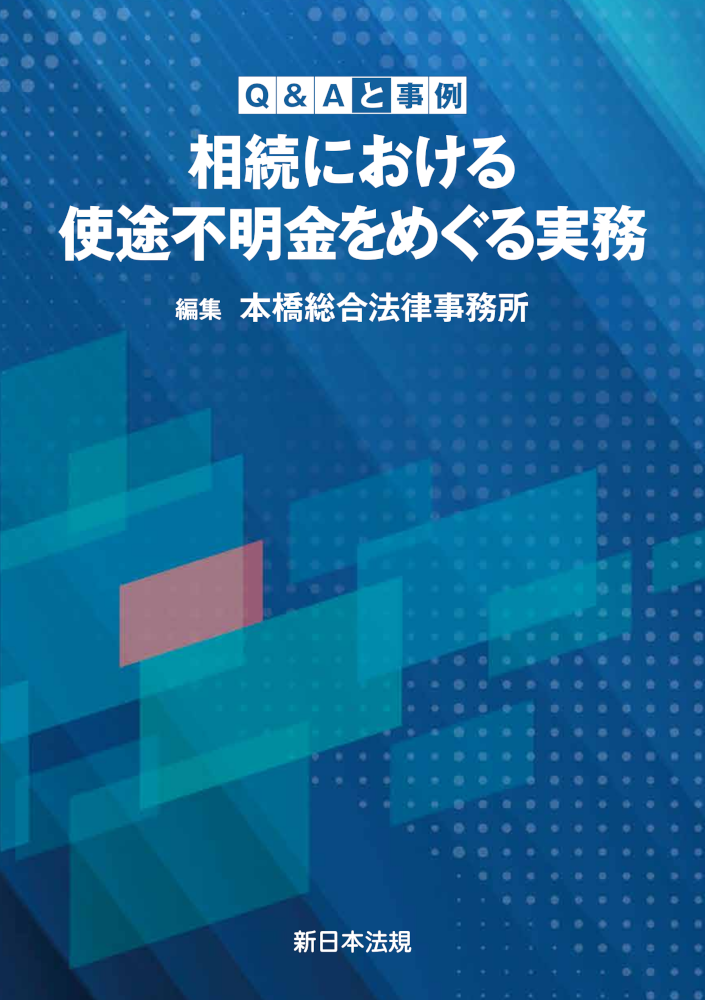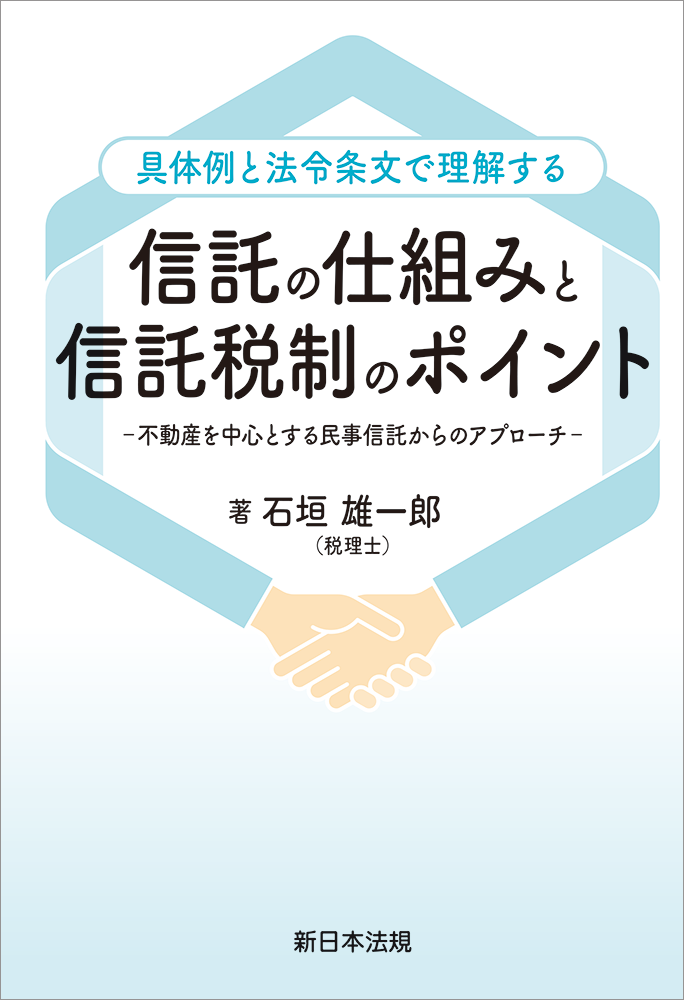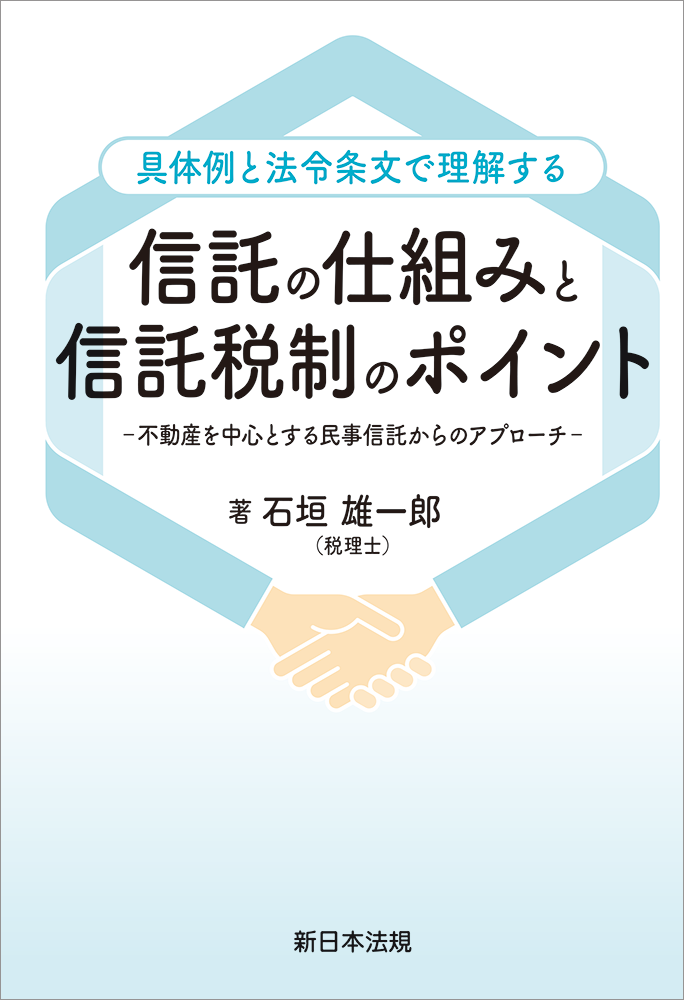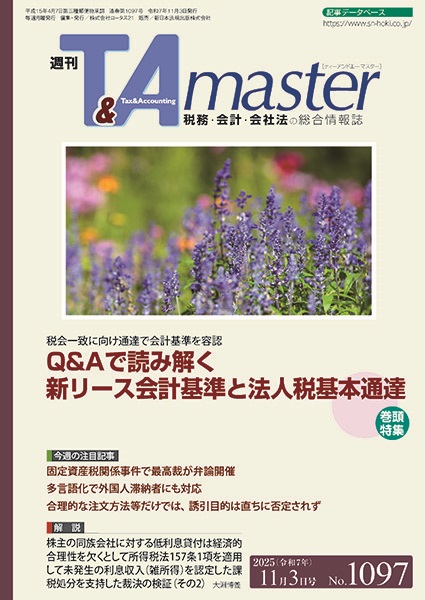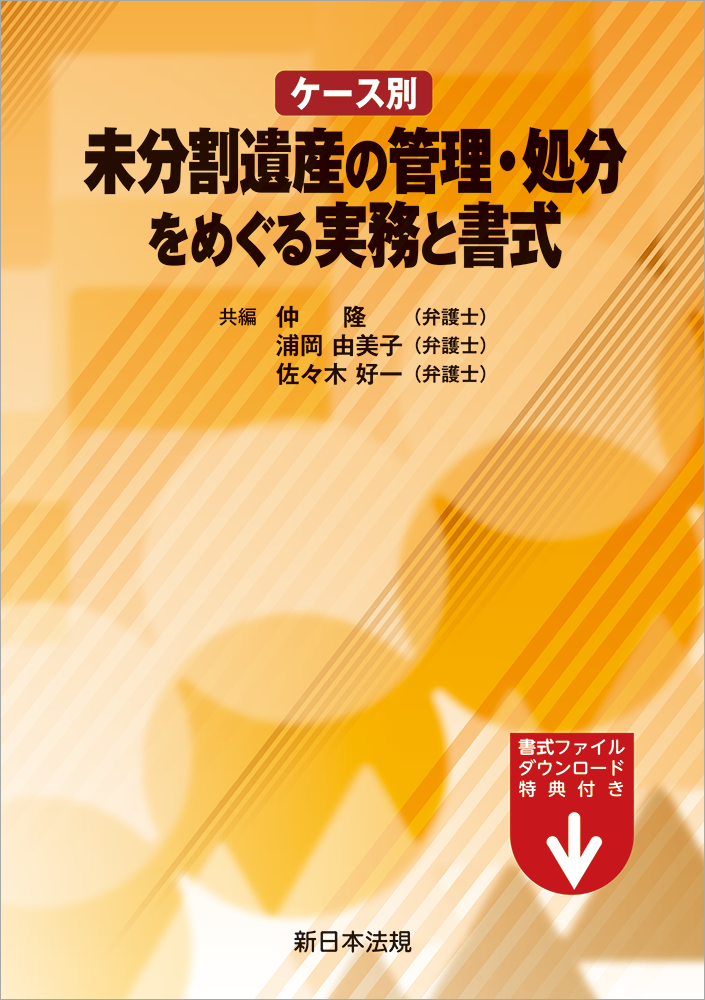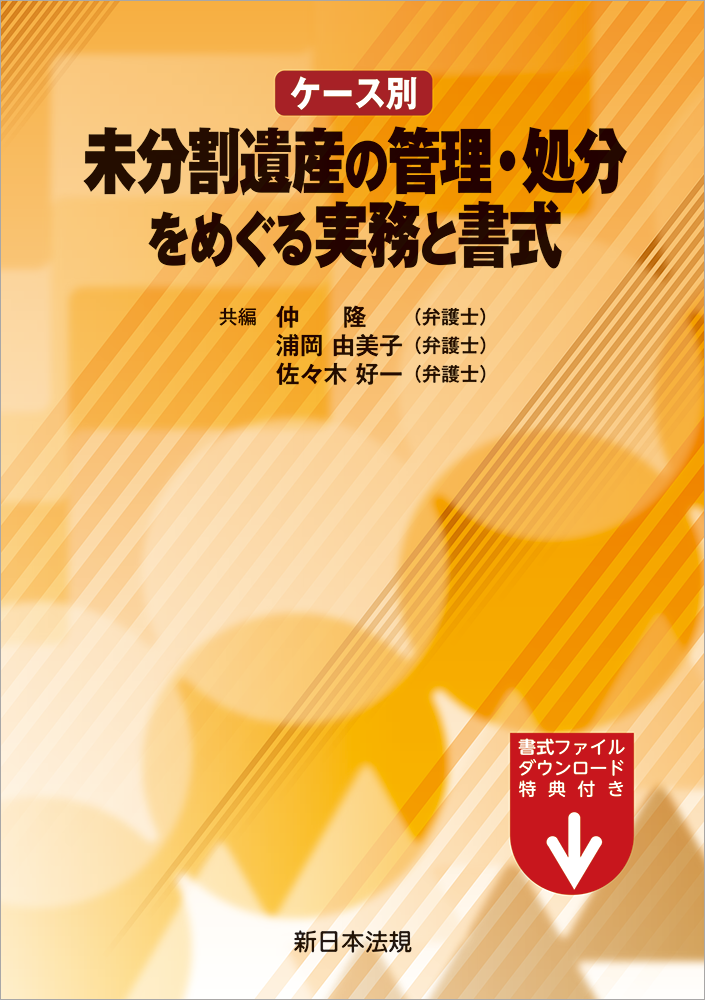- 相続・遺言
- 単行本
Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務
編集/本橋総合法律事務所
概要
「使途不明金」の法的整理を明快に!
◆使途不明金をめぐる争点と主張立証の勘所をQ&Aと事例で分かりやすく解説しています。
◆近年の裁判例の判断傾向を読み解き、実務に役立つ対応策を提示しています。
◆相続実務に精通した弁護士が、豊富な知見と経験を活かして執筆した信頼できる内容です。
商品情報
- 商品コード
- 81260536
- ISBN
- 978-4-7882-9491-2
- ページ数
- 308
- 発行年月
- 2025年5月
目次
総 論
第1 使途不明金返還請求訴訟と遺産分割の関係
第2 使途不明金返還請求訴訟と遺留分侵害額請求との関係
第3 訴訟物
第4 各訴訟物の違い
第5 被告に対する包括的な授権ないし被相続人の承諾
第6 使途不明金返還請求訴訟の主張立証の実際
第7 出金の使途の立証方法
第8 使途不明金の使途別の認定
Q&A編
第1 はじめに
Q1 使途不明金をめぐるトラブルの類型は
Q2 相続法改正による使途不明金問題への影響は
Q3 預貯金の使い込み、使途不明金に関するトラブルの解決手順は
Q4 賠償請求又は返還請求し得る相続人の範囲は
Q5 金融機関に対して払戻請求書や残高証明書等の開示請求を行う場合の手続は
Q6 弁護士会照会により取引履歴の開示請求を行う場合の手続は
Q7 相続人の預貯金口座につき金融機関に対する調査嘱託が採用されるケースとは
Q8 使途不明金の取扱いと遺言の解釈との関係は
第2 引出行為の有無
Q9 引出行為の有無が問題となるのはどのような場合か
Q10 相続人や第三者が引出行為に関与していたことが推認される間接事実とは
Q11 被相続人の引出行為を補助しただけであることを立証する際のポイントは
Q12 使途不明金返還請求訴訟の中で被告側から「贈与を受けた」という主張がなされたときのポイントは
第3 引出権限の存否
Q13 包括的な委任の有無についての判断要素は
Q14 委任契約がなくても引出権限が認められる場合とは
Q15 明確な意思表示がなくても委任契約の存在が認められる場合とは
Q16 委任時又は引出行為時の被相続人の意思能力の判断基準は
第4 引出金の使途
Q17 包括的委任で通常認められる授権の範囲は
Q18 出金者が被相続人へ引出金を渡したことを立証するための資料は
Q19 客観的な証拠がなくても被相続人のための支出があったと認められる使途とは
Q20 被相続人の生活費として相当とされる金額は
Q21 同居家族等の生活費を被相続人の預貯金から拠出することについて被相続人の意思の有無を判断するための考慮要素は
Q22 被相続人の預貯金から医師への謝礼等を支払うことの可否は
Q23 被相続人の葬儀費用を相続財産から負担することの可否は
Q24 引出金について贈与があったことを主張する場合の遺産分割上の留意点は
Q25 贈与契約書が存在しない場合の贈与の有無についての判断要素は
第5 調停・審判・訴訟の手続と留意点
Q26 使途不明金について遺産分割調停で協議することができる場合とは
Q27 相続発生後、遺産分割前に共同相続人の一人によって払い戻された金銭を遺産分割調停・審判の対象に含めることの可否は
Q28 使途不明金問題が解決する前に遺産分割審判が確定してしまいそうな場合における対応は
Q29 遺産確認請求と損害賠償・不当利得返還請求の選択のポイントは
Q30 不法行為に基づく損害賠償を請求する場合の要件事実は
Q31 遺産分割終了後に発見された通帳について使途不明金返還請求訴訟を提起することの可否は
Q32 使途不明金返還請求訴訟において遺留分の請求をする際の取扱いは
第6 税務上の取扱い
Q33 使途不明金がみなし贈与として贈与税が課税される場合とは
Q34 使途不明金が預託金や不当利得返還請求権として相続税が課せられる場合とは
Q35 使途不明金に関して正当性が認められなかった場合の相続税修正申告のポイントは
Q36 使途不明金についての相続税申告上の注意点、税務調査についての心構えや留意点とは
事例編
[1] 被相続人Aの姪である被告がA名義の預金及び精神病に罹患している(Aの子であり、後に死亡した)被相続人B名義の預金の払戻しを受け、Aの葬式代及びBの世話のための費用その他の名目で使用した場合に、Aと被告との間に預金払戻し等についての管理処分のための委任契約がされ、Aの死亡によっては同契約は終了しないとされ、また、Bとの関係では一部が事務管理による費用として認められるとされたが、A、Bとのいずれの関係においても、正当な費用支出とはいえない部分については不法行為による損害賠償義務が認められた事例(高松高判平22・8・30判時2106・52)
[2] 被相続人Aの子である被告がAの預貯金を無権限で引き出して不当に領得し自己使用したとして不法行為損害賠償等の請求がなされた事案につき、被告はAの了解を得て、Aの財産管理及び必要な支出の支払につき包括的に引き受けた等として、その請求の全部が棄却された事例(東京地判平23・8・22(平21(ワ)39197))
[3] 相続開始前に、被相続人が財産管理不能の状態において、相続人の一人が預金を払い戻し、私的財産と区分せずに一体化して保管したことにより、不法行為の成立が認められ、相続開始後に、当該相続人が行った被相続人の預金名義変更等についても不法行為の成立が認められた事例(東京地判平24・12・26(平22(ワ)12317))
[4] 相続人の一人が被相続人の財産管理をしていた際に使途不明金が生じたとして、当該相続人に対し、主位的に受任者の受取金引渡請求権、予備的に不法行為損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づく支払請求をした事案について、原告の請求の全部が認められなかった事例(東京地判平24・12・26(平23(ワ)28147))
[5] 被告と被相続人間で締結された財産管理事務処理委託契約による善管注意義務違反の債務不履行があったとして、被告に対してなされた損害賠償請求等が認められなかった事例(東京地判平25・2・4(平23(ワ)18779))
[6] 被告と亡父母との間に委任契約が成立していたとして被告に対する委任契約に基づく返還請求権が認められた事例(東京地判平26・2・14(平24(ワ)10350))
[7] 被告に対する不当利得返還請求権に基づく請求、及び、不法行為損害賠償請求権に基づく請求のいずれについても、時効消滅していることにより認められなかった事例(東京地判平26・3・6(平23(ワ)41611))
[8] 被告は、被相続人口座からの出金ルールにつき、他の相続人の了解を得たとの認識に基づき、記録を残して出金して、使用・分配しているので、不法行為に当たらないとされたが、被告による上記出金ルールに基づく出金であっても、その使途が不相当である場合には不当利得が成立するとされた事例(東京地判平26・12・3(平25(ワ)20389))
[9] 遺産分割後に不当利得返還請求、又は、不法行為損害賠償請求をすることが、遺産分割の不当な蒸し返しであって、訴権を濫用する不適法なものとはならないとされ、被告が亡Aから指示を受けてA名義の預金を引き出して、Aに渡したことが明らかとなれば、これを超えて被告にAによる当該現金の具体的使途まで明らかにする必要はないとされた事例(東京地判平28・1・14(平24(ワ)27833))
[10] 被告に対し全財産の包括遺贈がなされている場合には、被告に対する不当利得返還請求権ないし不法行為損害賠償請求権等も遺贈されたものであるが、被告が取得したそれらの請求権についても遺留分の算定の基礎となるとされた事例(東京地判平28・2・10(平24(ワ)13422))
[11] 被告の不当利得額について、民事訴訟法248条の趣旨に照らして、使途が明らかでなく支出された金額の2分の1の金額が認められた事例(東京地判平28・3・15(平26(ワ)24344))
[12] 被相続人から預金口座等の管理を委託されていた被告に対し、返還未了の委託金等の返還請求等を認めた事例(東京地判平28・7・19(平25(ワ)16409))
[13] 被相続人(母)の介護をしていた二男に対し、委任契約の終了に基づく返還債務として、預金の一部の支払を命じた事例(東京地判平29・4・14(平25(ワ)11325))
[14] 被告による被相続人口座からの引出金の返還請求が認められなかった事例(東京地判平29・6・21(平27(ワ)37184))
[15] 相続人が他の相続人に対し、被相続人(母)の預金の無断払戻金及び死亡保険金の受取人無断変更による損害金を請求し、その一部が認められた事例(東京地判平29・9・28(平27(ワ)17284))
[16] 被相続人の毎月10万円の生活費、「お小遣い」としての特別支出以外の払戻金を、使途不明金として、その返還請求を認めた事例(東京地判平29・10・6(平27(ワ)35412))
[17] 被告による被相続人口座からの引出金を、被告が生前贈与を受けた特別受益とは認められないとした事例(東京地判平30・3・23(平25(ワ)34602))
[18] 被相続人Aの子である被告が、Aの生前に、A名義の預金を払い戻した金員につき、被告がAに頼まれて、預金を引き出してAに交付した、あるいは、Aのために立替払をした部分を除いて不当利得の成立が認められた事例(東京地判平30・3・28(平28(ワ)8716))
[19] 被相続人死亡後に相続人のうちの一人が被相続人の預貯金を引き出して受領し、年金・現金も受領したことにつき、葬儀費用に充てられた部分は不当利得又は不法行為が成立しないが、一周忌法要等に充てられた部分については不法行為又は不法行為が成立するとされた事例(東京地判平30・4・24(平29(レ)864))
[20] 被相続人の長男の妻が、被相続人の預貯金を引き出した場合に、その引き出しは、被相続人の所有ないし管理する賃貸物件の管理、被相続人の所得税及び固定資産税・都市計画税の納付、被相続人の医療費の支払等の被相続人の財産に関する事務の一環として行われたものであり、被告が被相続人の意思に反して引き出しを行ったとはいえず、また、被相続人が、認知能力の低下により、これらの引き出しの必要性等につき正しく理解した上で承諾を与えることができなかったとしても、それらの支払は、いずれも被相続人の利益にかなうものであり、その引き出しについては事務管理が成立し得るため、不法行為は成立しないとされた事例(東京地判平30・11・19(平28(ワ)32476))
[21] 二男が、長女に対し、相続開始前及び相続開始後に払い戻した被相続人の預金の返還を求めた事例(東京地判平31・2・14(平29(ワ)18872))
[22] 被相続人亡Aの長男である被告が、亡Aの同意を得ずに亡Aの預金口座から払い戻した金員のうち、亡Aのために支出したと認められない金員について不当利得が成立するとされた事例(東京地判平31・3・28(平30(ワ)2515))
[23] 亡A(兄)からその生前にタンス預金783万円余を受領した被告Y2(妹)が、うち583万円余をA名義の預金口座に入金し、残りの200万円をAから贈与を受けたとして被告Y1(Y2の夫)名義の預金口座に入金した場合に、AからYらに対してなされた贈与には、精神的な疾患を抱えていたA及び高齢で要介護状態にあった同人の母親Bの生活につき、Yらが支援するという趣旨が含まれており、Yらには不当利得が成立しないとされた事例(東京地判平31・4・10(平29(ワ)43671))
[24] 被相続人が相手方相続人のために預貯金をしていた(いわゆる名義預金)として、相手方相続人がこれらを取得するにつき法律上の原因を欠くと認めることはできないとした事例(東京地判令元・10・28(平29(ワ)16899))
[25] 遺言の記載内容を踏まえると、被相続人が相手方相続人に対し、贈与する意思で多額の金員を交付したとは考え難く、相手方相続人も贈与を受けたのに税務申告を行っていないことなどから、相手方相続人が被相続人から受領した金銭は貸金であるとした事例(東京地判令元・11・7(平29(ワ)35163))
[26] 被相続人から、被相続人名義の全ての動産、不動産の管理、運営を任されていた相続人による預貯金等の引出金(総額2,655万円余)の使途について、被相続人のためのものか、当該相続人が利得しているかについて判断がなされ、合計547万円余について当該相続人の利得と認定された事例(東京地判令元・12・11(平29(ワ)30174))
[27] 長谷川式テストの結果が1点で主治医が後見相当との意見を示していた被相続人について、預貯金の引き出し等の意味内容を理解して引き出しを行った相続人に指示ないし承諾を与える能力がなかったと認定し、被相続人の有効な承諾なく引き出し等を行った(合計6,202万円余)として不法行為が成立するとした上で、被相続人のため被相続人の利益に適合する事務の管理として行われた支出(合計1,649万円余)については違法性が阻却されるとして、引き出し等の一部につき損害賠償請求を認めた事例(東京地判令2・3・10(平29(ワ)23837))
[28] 被相続人が入院したときには財産の管理、処分を委ねる旨の授権がされているものと推認し、金庫内の現金や預貯金の使途の内容が被相続人から授権された権限に照らしてこれを逸脱したものでなければあらかじめ承諾があったものと認められるとして、使途不明金主張額(2,235万円余)のうち一部の使途の金額(176万円余)につき授権の範囲を超えて費消して私的利用したと認定した事例(東京地判令2・3・23(平30(ワ)12135))
[29] 被告が被相続人の預貯金を管理する立場にあったと認められる場合には、被告の側から出金の経緯や使途に関する相応の合理的な説明を伴う具体的な反証がない限り、被告が当該出金額を法律上の原因なく利得して被相続人に損失を与えたと推認するのが相当であると判断した事例(東京地判令2・10・22(平29(ワ)20597))
[30] 「施設入居時及び入院中、土地・家屋の売買、葬儀等に関する諸費用全ての金銭管理使用について二男(被告)家族に一任する」旨の書面が作成されていたとしても、被相続人の金銭管理について包括的・全体的に被告ないし被告の家族に一任する内容までは含まれていないとして、被告が被相続人の預金を引き出した金額のうち被告の自動車購入費用などに使用した金額につき不当利得返還請求権の成立を認めた事例(東京地判令2・10・30(平30(ワ)20836))
[31] 被告が、外形上は被相続人の承諾ないし委託らしきものをとっていたとしても、それは被相続人が意思能力を欠いた状態でのものにすぎず、各医療記録・介護記録に照らせば、被告もその点は認識し得たのであるから、被告の亡A資産の支出行為につき、法的に有効な承諾ないし委託を受けていたと評価することはできないと判断した事例(東京地判令2・12・10(平29(ワ)12642))
[32] 被相続人の収入やデイサービスの費用等の引き落としのために日常的に用いられる預金口座からの引き出しについては、被告が被相続人の同意なく引き出し、これを私的に流用したと認めることはできないとする一方で、他の口座からの引き出しについては、被告が被相続人の同意を得ることなく引き出して、私的に流用したものと認めると判断した事例(東京地判令3・2・18(平30(ワ)21733))
[33] 被相続人は、認知症に罹患しており、加えて、被相続人の財産の管理は被告が行っていたことが介護認定の調査票に回答されていることから、被相続人の財産管理は被告がするようになっていたことを認め、その使途不明金のうち、総務省統計局が公表している「60歳以上の単身無職世帯及び高齢夫婦無職世帯の家計収支」を基に推定された生活費相当額、葬儀費用等については、被相続人の意思に基づく支出であったことを認めた事例(東京地判令3・4・22(平30(ワ)18727・令2(ワ)31731))
[34] 被告が被相続人の財産の独占を企図していたことを認めるに足りる的確な証拠はないことなどから、被告が本件各払戻金等を違法ないし法律上の原因なく取得(領得ないし利得)したと認めることはできないと判断した事例(東京地判令3・11・11(平30(ワ)13183))
[35] 使途不明金なるものを被告が受領したことについては何ら主張立証できていないとして、被告の不当利得又は不法行為は認められないと判断した事例(東京地判令3・12・23(平31(ワ)6118・平31(ワ)7386))
[36] 本件送金等は、全て被相続人の意思によって行われたものと認めることができると判断した事例(東京地判令4・1・18(令元(ワ)18630・令元(ワ)30603・令3(ワ)1245))
[37] 被相続人が、被告に対し、生活費の管理及び施設入所に伴い空き家となる実家の維持管理を包括的に委任しており、それに必要な費用の支出についても被告に包括的に委任していたものと推認される。また、被相続人の施設入所に際し、原告との間で、被相続人名義の預貯金の管理や実家の管理について協議し、その際、被告において手間賃として月額10万円を受け取ることが合意され、被相続人もそれを了承していたと認められるとして、法律上の原因を認めた事例(東京地判令4・3・29(令2(ワ)15148・令2(ワ)32286))
[38] 被相続人名義の口座からの出金のうち、被告が当該口座を管理していたことを認めた期間において出金された合計約1,360万円について、被告が被相続人に交付したとする供述は採用することができないとして被相続人の被告に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していたと判断した事例(東京地判令4・4・12(令元(ワ)14130))
[39] 被告が行った各引き出しについて、被相続人の意思に基づくものであったことが推認されるから、被告の利得が法律上の原因を欠くものとは認められないと判断する一方で、被告が葬儀費用等の支払に充てた部分については、葬儀費用は、葬儀の主催者である喪主が負担すべき性質のものであるから、遺産に当たる現金からこれを支出した場合、特段の事情のない限り、自己の法定相続分を超える部分については法律上の原因を欠き不当利得が成立するというべきであるとした事例(東京地判令4・4・21(令2(ワ)25492))
[40] 被相続人Aが保管していた現金について、原告本人らの供述によっても、それのみでは客観的に存在したAの現金が原告らが主張する金額6,000万円であったと認めることは困難であるとした上で、被告らが使途を説明できない1,000万円程度の金銭について、被相続人自らが、金庫の中から現金を取り出して、自己の用途に費消した可能性を否定することができないことから、被告らが前記1,000万円程度のAの金銭を不当に利得し、又は同額の財産上の損害をAに与えたとは直ちにいうことができないと判断した事例(東京地判令4・4・25(平30(ワ)36095))
[41] 被相続人名義の預金の出金者である被告が、当該出金の使途について全く説明できなかったものの、被相続人において財産管理能力を失ってはいなかったこと、そして、被相続人が預金通帳やキャッシュカードを管理していたことなどから、使途不明の預金相当額を被告が被相続人に無断で領得したものと認定することはできないと判断した事例(東京地判令4・9・28(令2(ワ)32013))
第1 使途不明金返還請求訴訟と遺産分割の関係
第2 使途不明金返還請求訴訟と遺留分侵害額請求との関係
第3 訴訟物
第4 各訴訟物の違い
第5 被告に対する包括的な授権ないし被相続人の承諾
第6 使途不明金返還請求訴訟の主張立証の実際
第7 出金の使途の立証方法
第8 使途不明金の使途別の認定
Q&A編
第1 はじめに
Q1 使途不明金をめぐるトラブルの類型は
Q2 相続法改正による使途不明金問題への影響は
Q3 預貯金の使い込み、使途不明金に関するトラブルの解決手順は
Q4 賠償請求又は返還請求し得る相続人の範囲は
Q5 金融機関に対して払戻請求書や残高証明書等の開示請求を行う場合の手続は
Q6 弁護士会照会により取引履歴の開示請求を行う場合の手続は
Q7 相続人の預貯金口座につき金融機関に対する調査嘱託が採用されるケースとは
Q8 使途不明金の取扱いと遺言の解釈との関係は
第2 引出行為の有無
Q9 引出行為の有無が問題となるのはどのような場合か
Q10 相続人や第三者が引出行為に関与していたことが推認される間接事実とは
Q11 被相続人の引出行為を補助しただけであることを立証する際のポイントは
Q12 使途不明金返還請求訴訟の中で被告側から「贈与を受けた」という主張がなされたときのポイントは
第3 引出権限の存否
Q13 包括的な委任の有無についての判断要素は
Q14 委任契約がなくても引出権限が認められる場合とは
Q15 明確な意思表示がなくても委任契約の存在が認められる場合とは
Q16 委任時又は引出行為時の被相続人の意思能力の判断基準は
第4 引出金の使途
Q17 包括的委任で通常認められる授権の範囲は
Q18 出金者が被相続人へ引出金を渡したことを立証するための資料は
Q19 客観的な証拠がなくても被相続人のための支出があったと認められる使途とは
Q20 被相続人の生活費として相当とされる金額は
Q21 同居家族等の生活費を被相続人の預貯金から拠出することについて被相続人の意思の有無を判断するための考慮要素は
Q22 被相続人の預貯金から医師への謝礼等を支払うことの可否は
Q23 被相続人の葬儀費用を相続財産から負担することの可否は
Q24 引出金について贈与があったことを主張する場合の遺産分割上の留意点は
Q25 贈与契約書が存在しない場合の贈与の有無についての判断要素は
第5 調停・審判・訴訟の手続と留意点
Q26 使途不明金について遺産分割調停で協議することができる場合とは
Q27 相続発生後、遺産分割前に共同相続人の一人によって払い戻された金銭を遺産分割調停・審判の対象に含めることの可否は
Q28 使途不明金問題が解決する前に遺産分割審判が確定してしまいそうな場合における対応は
Q29 遺産確認請求と損害賠償・不当利得返還請求の選択のポイントは
Q30 不法行為に基づく損害賠償を請求する場合の要件事実は
Q31 遺産分割終了後に発見された通帳について使途不明金返還請求訴訟を提起することの可否は
Q32 使途不明金返還請求訴訟において遺留分の請求をする際の取扱いは
第6 税務上の取扱い
Q33 使途不明金がみなし贈与として贈与税が課税される場合とは
Q34 使途不明金が預託金や不当利得返還請求権として相続税が課せられる場合とは
Q35 使途不明金に関して正当性が認められなかった場合の相続税修正申告のポイントは
Q36 使途不明金についての相続税申告上の注意点、税務調査についての心構えや留意点とは
事例編
[1] 被相続人Aの姪である被告がA名義の預金及び精神病に罹患している(Aの子であり、後に死亡した)被相続人B名義の預金の払戻しを受け、Aの葬式代及びBの世話のための費用その他の名目で使用した場合に、Aと被告との間に預金払戻し等についての管理処分のための委任契約がされ、Aの死亡によっては同契約は終了しないとされ、また、Bとの関係では一部が事務管理による費用として認められるとされたが、A、Bとのいずれの関係においても、正当な費用支出とはいえない部分については不法行為による損害賠償義務が認められた事例(高松高判平22・8・30判時2106・52)
[2] 被相続人Aの子である被告がAの預貯金を無権限で引き出して不当に領得し自己使用したとして不法行為損害賠償等の請求がなされた事案につき、被告はAの了解を得て、Aの財産管理及び必要な支出の支払につき包括的に引き受けた等として、その請求の全部が棄却された事例(東京地判平23・8・22(平21(ワ)39197))
[3] 相続開始前に、被相続人が財産管理不能の状態において、相続人の一人が預金を払い戻し、私的財産と区分せずに一体化して保管したことにより、不法行為の成立が認められ、相続開始後に、当該相続人が行った被相続人の預金名義変更等についても不法行為の成立が認められた事例(東京地判平24・12・26(平22(ワ)12317))
[4] 相続人の一人が被相続人の財産管理をしていた際に使途不明金が生じたとして、当該相続人に対し、主位的に受任者の受取金引渡請求権、予備的に不法行為損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づく支払請求をした事案について、原告の請求の全部が認められなかった事例(東京地判平24・12・26(平23(ワ)28147))
[5] 被告と被相続人間で締結された財産管理事務処理委託契約による善管注意義務違反の債務不履行があったとして、被告に対してなされた損害賠償請求等が認められなかった事例(東京地判平25・2・4(平23(ワ)18779))
[6] 被告と亡父母との間に委任契約が成立していたとして被告に対する委任契約に基づく返還請求権が認められた事例(東京地判平26・2・14(平24(ワ)10350))
[7] 被告に対する不当利得返還請求権に基づく請求、及び、不法行為損害賠償請求権に基づく請求のいずれについても、時効消滅していることにより認められなかった事例(東京地判平26・3・6(平23(ワ)41611))
[8] 被告は、被相続人口座からの出金ルールにつき、他の相続人の了解を得たとの認識に基づき、記録を残して出金して、使用・分配しているので、不法行為に当たらないとされたが、被告による上記出金ルールに基づく出金であっても、その使途が不相当である場合には不当利得が成立するとされた事例(東京地判平26・12・3(平25(ワ)20389))
[9] 遺産分割後に不当利得返還請求、又は、不法行為損害賠償請求をすることが、遺産分割の不当な蒸し返しであって、訴権を濫用する不適法なものとはならないとされ、被告が亡Aから指示を受けてA名義の預金を引き出して、Aに渡したことが明らかとなれば、これを超えて被告にAによる当該現金の具体的使途まで明らかにする必要はないとされた事例(東京地判平28・1・14(平24(ワ)27833))
[10] 被告に対し全財産の包括遺贈がなされている場合には、被告に対する不当利得返還請求権ないし不法行為損害賠償請求権等も遺贈されたものであるが、被告が取得したそれらの請求権についても遺留分の算定の基礎となるとされた事例(東京地判平28・2・10(平24(ワ)13422))
[11] 被告の不当利得額について、民事訴訟法248条の趣旨に照らして、使途が明らかでなく支出された金額の2分の1の金額が認められた事例(東京地判平28・3・15(平26(ワ)24344))
[12] 被相続人から預金口座等の管理を委託されていた被告に対し、返還未了の委託金等の返還請求等を認めた事例(東京地判平28・7・19(平25(ワ)16409))
[13] 被相続人(母)の介護をしていた二男に対し、委任契約の終了に基づく返還債務として、預金の一部の支払を命じた事例(東京地判平29・4・14(平25(ワ)11325))
[14] 被告による被相続人口座からの引出金の返還請求が認められなかった事例(東京地判平29・6・21(平27(ワ)37184))
[15] 相続人が他の相続人に対し、被相続人(母)の預金の無断払戻金及び死亡保険金の受取人無断変更による損害金を請求し、その一部が認められた事例(東京地判平29・9・28(平27(ワ)17284))
[16] 被相続人の毎月10万円の生活費、「お小遣い」としての特別支出以外の払戻金を、使途不明金として、その返還請求を認めた事例(東京地判平29・10・6(平27(ワ)35412))
[17] 被告による被相続人口座からの引出金を、被告が生前贈与を受けた特別受益とは認められないとした事例(東京地判平30・3・23(平25(ワ)34602))
[18] 被相続人Aの子である被告が、Aの生前に、A名義の預金を払い戻した金員につき、被告がAに頼まれて、預金を引き出してAに交付した、あるいは、Aのために立替払をした部分を除いて不当利得の成立が認められた事例(東京地判平30・3・28(平28(ワ)8716))
[19] 被相続人死亡後に相続人のうちの一人が被相続人の預貯金を引き出して受領し、年金・現金も受領したことにつき、葬儀費用に充てられた部分は不当利得又は不法行為が成立しないが、一周忌法要等に充てられた部分については不法行為又は不法行為が成立するとされた事例(東京地判平30・4・24(平29(レ)864))
[20] 被相続人の長男の妻が、被相続人の預貯金を引き出した場合に、その引き出しは、被相続人の所有ないし管理する賃貸物件の管理、被相続人の所得税及び固定資産税・都市計画税の納付、被相続人の医療費の支払等の被相続人の財産に関する事務の一環として行われたものであり、被告が被相続人の意思に反して引き出しを行ったとはいえず、また、被相続人が、認知能力の低下により、これらの引き出しの必要性等につき正しく理解した上で承諾を与えることができなかったとしても、それらの支払は、いずれも被相続人の利益にかなうものであり、その引き出しについては事務管理が成立し得るため、不法行為は成立しないとされた事例(東京地判平30・11・19(平28(ワ)32476))
[21] 二男が、長女に対し、相続開始前及び相続開始後に払い戻した被相続人の預金の返還を求めた事例(東京地判平31・2・14(平29(ワ)18872))
[22] 被相続人亡Aの長男である被告が、亡Aの同意を得ずに亡Aの預金口座から払い戻した金員のうち、亡Aのために支出したと認められない金員について不当利得が成立するとされた事例(東京地判平31・3・28(平30(ワ)2515))
[23] 亡A(兄)からその生前にタンス預金783万円余を受領した被告Y2(妹)が、うち583万円余をA名義の預金口座に入金し、残りの200万円をAから贈与を受けたとして被告Y1(Y2の夫)名義の預金口座に入金した場合に、AからYらに対してなされた贈与には、精神的な疾患を抱えていたA及び高齢で要介護状態にあった同人の母親Bの生活につき、Yらが支援するという趣旨が含まれており、Yらには不当利得が成立しないとされた事例(東京地判平31・4・10(平29(ワ)43671))
[24] 被相続人が相手方相続人のために預貯金をしていた(いわゆる名義預金)として、相手方相続人がこれらを取得するにつき法律上の原因を欠くと認めることはできないとした事例(東京地判令元・10・28(平29(ワ)16899))
[25] 遺言の記載内容を踏まえると、被相続人が相手方相続人に対し、贈与する意思で多額の金員を交付したとは考え難く、相手方相続人も贈与を受けたのに税務申告を行っていないことなどから、相手方相続人が被相続人から受領した金銭は貸金であるとした事例(東京地判令元・11・7(平29(ワ)35163))
[26] 被相続人から、被相続人名義の全ての動産、不動産の管理、運営を任されていた相続人による預貯金等の引出金(総額2,655万円余)の使途について、被相続人のためのものか、当該相続人が利得しているかについて判断がなされ、合計547万円余について当該相続人の利得と認定された事例(東京地判令元・12・11(平29(ワ)30174))
[27] 長谷川式テストの結果が1点で主治医が後見相当との意見を示していた被相続人について、預貯金の引き出し等の意味内容を理解して引き出しを行った相続人に指示ないし承諾を与える能力がなかったと認定し、被相続人の有効な承諾なく引き出し等を行った(合計6,202万円余)として不法行為が成立するとした上で、被相続人のため被相続人の利益に適合する事務の管理として行われた支出(合計1,649万円余)については違法性が阻却されるとして、引き出し等の一部につき損害賠償請求を認めた事例(東京地判令2・3・10(平29(ワ)23837))
[28] 被相続人が入院したときには財産の管理、処分を委ねる旨の授権がされているものと推認し、金庫内の現金や預貯金の使途の内容が被相続人から授権された権限に照らしてこれを逸脱したものでなければあらかじめ承諾があったものと認められるとして、使途不明金主張額(2,235万円余)のうち一部の使途の金額(176万円余)につき授権の範囲を超えて費消して私的利用したと認定した事例(東京地判令2・3・23(平30(ワ)12135))
[29] 被告が被相続人の預貯金を管理する立場にあったと認められる場合には、被告の側から出金の経緯や使途に関する相応の合理的な説明を伴う具体的な反証がない限り、被告が当該出金額を法律上の原因なく利得して被相続人に損失を与えたと推認するのが相当であると判断した事例(東京地判令2・10・22(平29(ワ)20597))
[30] 「施設入居時及び入院中、土地・家屋の売買、葬儀等に関する諸費用全ての金銭管理使用について二男(被告)家族に一任する」旨の書面が作成されていたとしても、被相続人の金銭管理について包括的・全体的に被告ないし被告の家族に一任する内容までは含まれていないとして、被告が被相続人の預金を引き出した金額のうち被告の自動車購入費用などに使用した金額につき不当利得返還請求権の成立を認めた事例(東京地判令2・10・30(平30(ワ)20836))
[31] 被告が、外形上は被相続人の承諾ないし委託らしきものをとっていたとしても、それは被相続人が意思能力を欠いた状態でのものにすぎず、各医療記録・介護記録に照らせば、被告もその点は認識し得たのであるから、被告の亡A資産の支出行為につき、法的に有効な承諾ないし委託を受けていたと評価することはできないと判断した事例(東京地判令2・12・10(平29(ワ)12642))
[32] 被相続人の収入やデイサービスの費用等の引き落としのために日常的に用いられる預金口座からの引き出しについては、被告が被相続人の同意なく引き出し、これを私的に流用したと認めることはできないとする一方で、他の口座からの引き出しについては、被告が被相続人の同意を得ることなく引き出して、私的に流用したものと認めると判断した事例(東京地判令3・2・18(平30(ワ)21733))
[33] 被相続人は、認知症に罹患しており、加えて、被相続人の財産の管理は被告が行っていたことが介護認定の調査票に回答されていることから、被相続人の財産管理は被告がするようになっていたことを認め、その使途不明金のうち、総務省統計局が公表している「60歳以上の単身無職世帯及び高齢夫婦無職世帯の家計収支」を基に推定された生活費相当額、葬儀費用等については、被相続人の意思に基づく支出であったことを認めた事例(東京地判令3・4・22(平30(ワ)18727・令2(ワ)31731))
[34] 被告が被相続人の財産の独占を企図していたことを認めるに足りる的確な証拠はないことなどから、被告が本件各払戻金等を違法ないし法律上の原因なく取得(領得ないし利得)したと認めることはできないと判断した事例(東京地判令3・11・11(平30(ワ)13183))
[35] 使途不明金なるものを被告が受領したことについては何ら主張立証できていないとして、被告の不当利得又は不法行為は認められないと判断した事例(東京地判令3・12・23(平31(ワ)6118・平31(ワ)7386))
[36] 本件送金等は、全て被相続人の意思によって行われたものと認めることができると判断した事例(東京地判令4・1・18(令元(ワ)18630・令元(ワ)30603・令3(ワ)1245))
[37] 被相続人が、被告に対し、生活費の管理及び施設入所に伴い空き家となる実家の維持管理を包括的に委任しており、それに必要な費用の支出についても被告に包括的に委任していたものと推認される。また、被相続人の施設入所に際し、原告との間で、被相続人名義の預貯金の管理や実家の管理について協議し、その際、被告において手間賃として月額10万円を受け取ることが合意され、被相続人もそれを了承していたと認められるとして、法律上の原因を認めた事例(東京地判令4・3・29(令2(ワ)15148・令2(ワ)32286))
[38] 被相続人名義の口座からの出金のうち、被告が当該口座を管理していたことを認めた期間において出金された合計約1,360万円について、被告が被相続人に交付したとする供述は採用することができないとして被相続人の被告に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していたと判断した事例(東京地判令4・4・12(令元(ワ)14130))
[39] 被告が行った各引き出しについて、被相続人の意思に基づくものであったことが推認されるから、被告の利得が法律上の原因を欠くものとは認められないと判断する一方で、被告が葬儀費用等の支払に充てた部分については、葬儀費用は、葬儀の主催者である喪主が負担すべき性質のものであるから、遺産に当たる現金からこれを支出した場合、特段の事情のない限り、自己の法定相続分を超える部分については法律上の原因を欠き不当利得が成立するというべきであるとした事例(東京地判令4・4・21(令2(ワ)25492))
[40] 被相続人Aが保管していた現金について、原告本人らの供述によっても、それのみでは客観的に存在したAの現金が原告らが主張する金額6,000万円であったと認めることは困難であるとした上で、被告らが使途を説明できない1,000万円程度の金銭について、被相続人自らが、金庫の中から現金を取り出して、自己の用途に費消した可能性を否定することができないことから、被告らが前記1,000万円程度のAの金銭を不当に利得し、又は同額の財産上の損害をAに与えたとは直ちにいうことができないと判断した事例(東京地判令4・4・25(平30(ワ)36095))
[41] 被相続人名義の預金の出金者である被告が、当該出金の使途について全く説明できなかったものの、被相続人において財産管理能力を失ってはいなかったこと、そして、被相続人が預金通帳やキャッシュカードを管理していたことなどから、使途不明の預金相当額を被告が被相続人に無断で領得したものと認定することはできないと判断した事例(東京地判令4・9・28(令2(ワ)32013))
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。