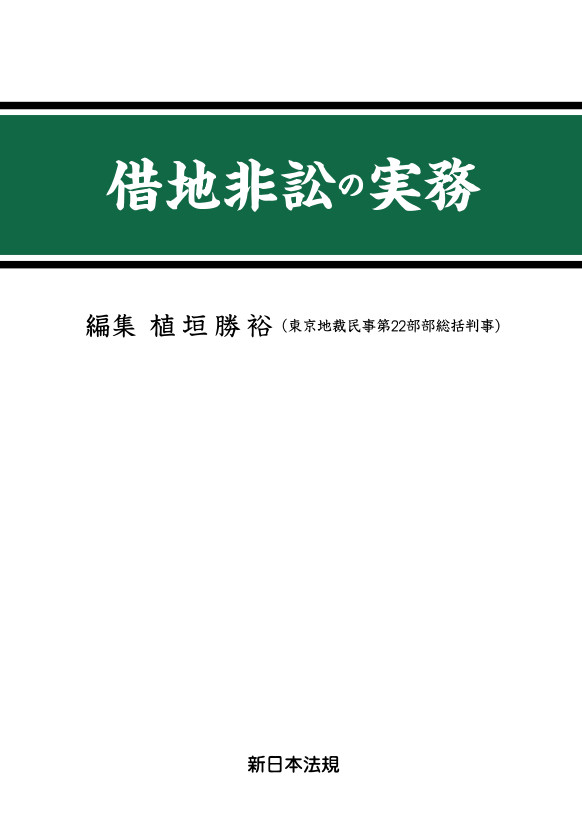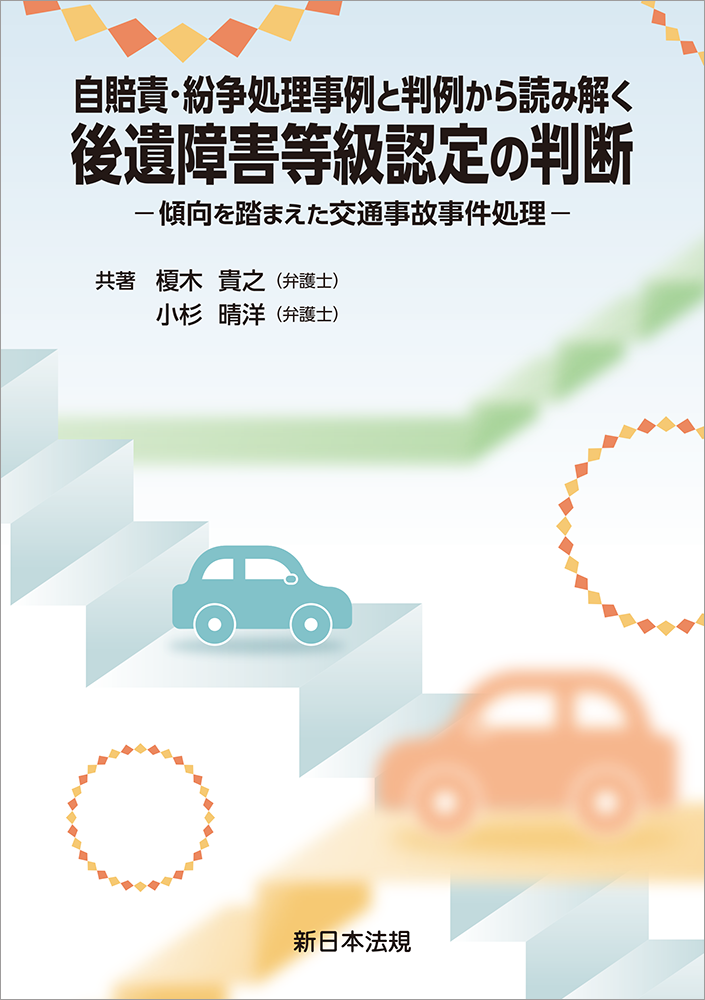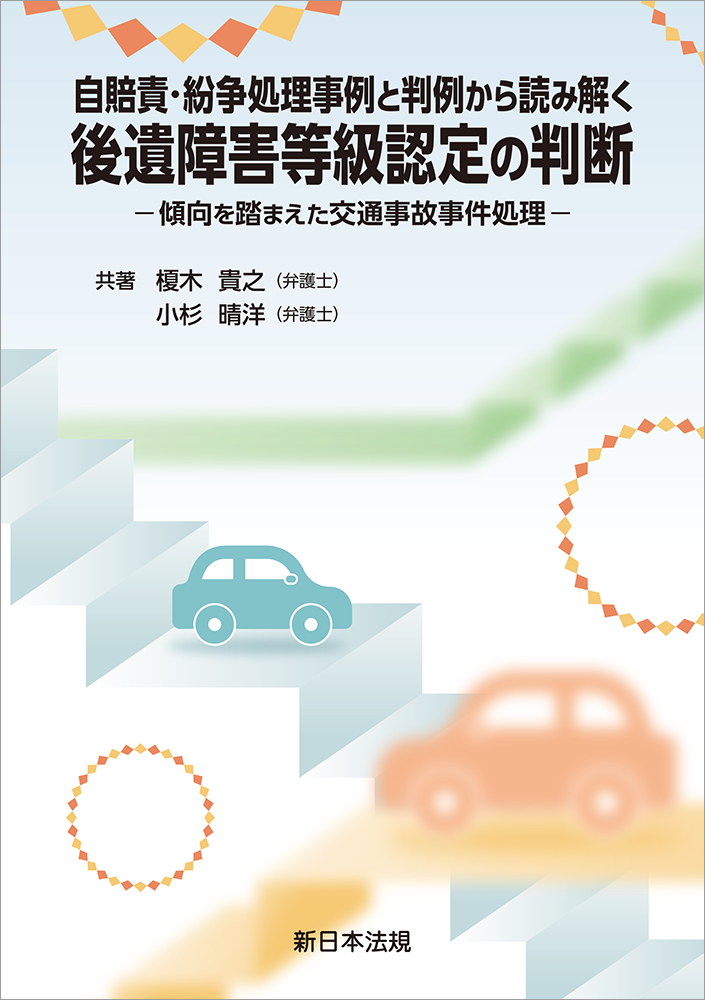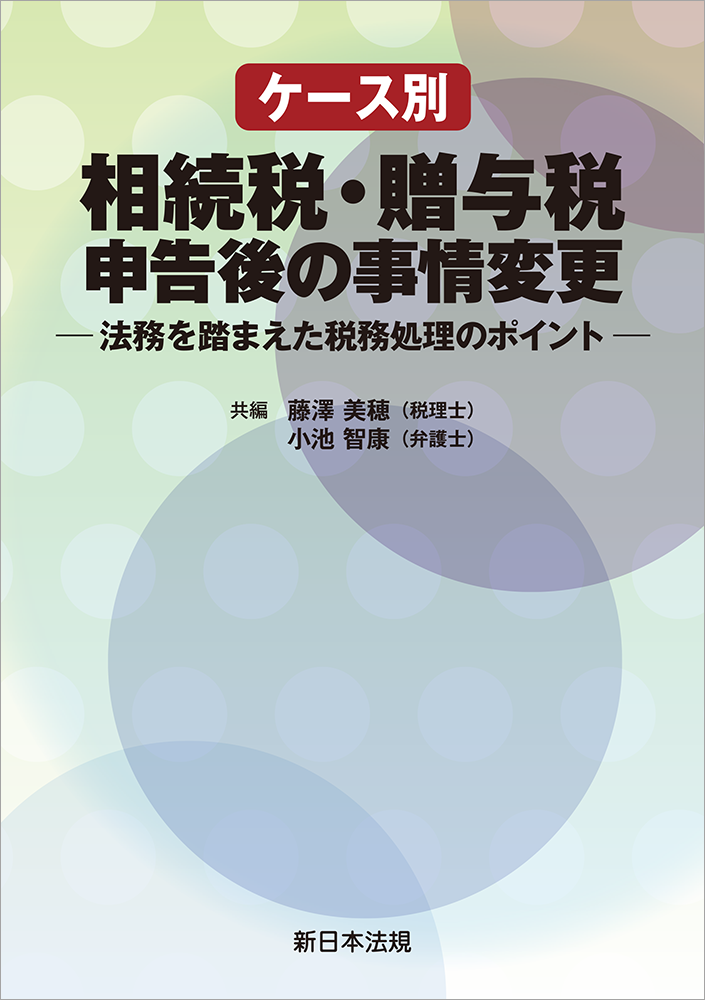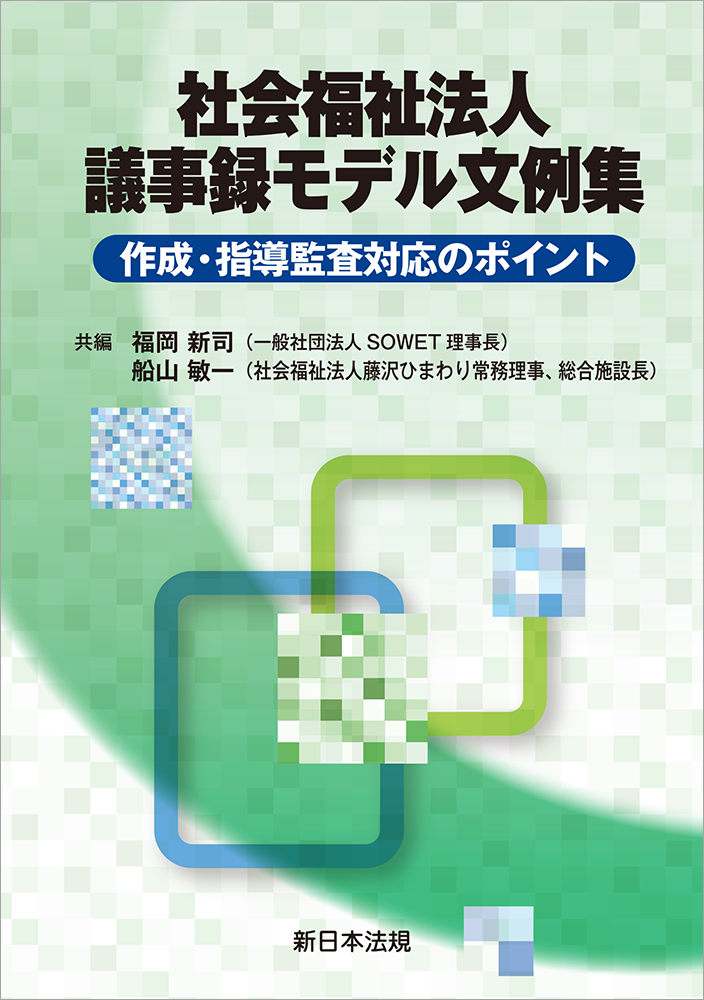概要
新しい非訟事件手続法に対応した最新版!(平成23年法律第51号)
◆借地非訟事件について、事件の類型ごとに、実務上・理論上の諸問題を判例や学説を引用しながら、詳しく解説しています。
◆各事件類型につき、主文例や和解条項例を掲げています。
◆借地非訟事件に精通した現役の裁判官、書記官が執筆しています。
商品情報
- 商品コード
- 50891
- ISBN
- 978-4-7882-7972-8
- JAN
- 9784788279728/1923032049009
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1・ケース付
- ページ数
- 496
- 発行年月
- 2015年3月
目次
第1編 総論
第1章 総説
第1節 借地非訟制度
第1 借地関係に伴う紛争と借地非訟
第2 借地非訟制度の歴史
1 戦前に設けられた制度
(1)借地借家臨時処理法
(2)防火地域内借地権処理法
2 戦後間もなく設けられた制度
(1)罹災都市借地借家臨時処理法
(2)接収不動産に関する借地借家臨時処理法
3 借地借家法改正要綱案
4 借地非訟制度の導入
5 借地借家法の制定
6 非訟事件手続法の制定及びそれに伴う借地借家法の改正
(1)総説
(2)改正の要点
(3)新旧非訟事件手続法及び借地借家法の適用関係
7 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の制定及び罹災都市借地借家臨時処理法等の廃止
(1)罹災都市借地借家臨時処理法の問題点
(2)大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の制定及び罹災都市借地借家臨時処理法の廃止
第2節 借地非訟事件の類型
第1 借地条件変更申立事件
第2 増改築許可申立事件
第3 更新後の建物再築許可申立事件
第4 賃借権譲渡・転貸許可申立事件
第5 競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第6 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第2章 借地非訟事件の手続の概要
第1節 手続の諸原則
第1 適用法規
第2 二当事者対立主義
第3 処分権主義とその制限
第4 職権探知主義
第5 口頭主義と書面主義、直接主義と間接主義
第6 公開主義と非公開主義
第2節 裁判所
第1 管轄
第2 裁判所の構成
第3 専門委員
第4 鑑定委員会
1 制度の趣旨
2 構成
3 鑑定委員の身分
4 鑑定委員会の職務活動
第3節 当事者等
第1 当事者
1 借地非訟における当事者
2 申立人と相手方
第2 当事者能力
第3 手続行為能力
第4 当事者適格
1 事件類型からみた当事者適格
2 土地所有者と契約書上の賃貸人が異なる場合
3 契約当事者が複数の場合の当事者適格
(1)問題の所在
(2)借地権者側の事情
ア 実体法上の性質の観点から
イ 手続上の必要性の観点から
ウ 結論
(3)借地権設定者側の事情
ア 実体法上の性質の観点から
イ 手続上の必要性の観点から
ウ 結論
(4)借地非訟の裁判の効力からの考え方
(5)当事者の一部から事前の承諾がある場合
(6)結論
第5 参加制度
1 非訟事件手続法及び借地借家法における参加制度
2 当事者参加の参加人となり得る者
3 任意参加
(1)任意参加申出の方式と要件
(2)任意参加申出の効果
4 強制参加
(1)強制参加申立ての方式と要件
(2)強制参加申立てに対する裁判
5 脱退
6 利害関係参加
(1)借地非訟事件における利害関係参加
(2)利害関係参加の方式
(3)利害関係参加人がすることができる行為
第6 代理人・補佐人
1 借地非訟事件の手続代理人
2 法定代理人
3 委任による手続代理人
(1)委任による手続代理人の資格
(2)代理権の証明
(3)委任による手続代理人の代理権の範囲
4 法令により裁判上の行為をすることのできる手続代理人
5 代理に関する民事訴訟法の規定の準用
6 補佐人
第7 検察官の不関与
第8 受継
1 借地非訟事件の手続の事実上の中断と受継
2 受継がされる場合
3 受継の手続
第4節 申立て
第1 申立書・印紙
1 申立ての方式
2 申立書の記載事項
(1)当事者及び法定代理人
(2)申立ての趣旨
(3)申立ての原因及び申立てを理由付ける事実
(4)借地契約の内容
(5)申立て前にした当事者間の協議の概要
(6)その他
3 申立ての併合
4 添付書類
5 印紙の貼用
6 費用の予納
第2 申立ての効果
1 事件の係属
2 重複申立ての禁止
第5節 審理
第1 当事者の陳述聴取(審問)
1 概要
2 審問期日
3 当事者の陳述聴取が必要な場合
第2 証拠調べと事実の調査
1 証明の必要
2 証拠調べ
3 事実の調査
第3 申立ての変更
1 申立ての変更の意義
2 申立ての変更の要件
(1)申立ての基礎の同一性
(2)著しく手続を遅滞させないこと
3 申立ての変更の態様
(1)土地の範囲の減縮、拡張
(2)許可を受ける増改築及び再築の内容の変更
(3)賃借権譲渡許可申立事件における申立ての内容の変更
(4)異種の申立て相互間の変更
4 申立ての変更の方式
第4 手続の併合と分離
1 手続の併合
(1)手続の併合の意義
(2)手続の併合の態様
ア 客観的併合
イ 主観的併合
2 手続の分離
3 分離・併合の裁判の取消し
第5 手続の中止
1 借地非訟事件における手続の中止
2 手続を中止することができる場合
3 中止の裁判
第6 記録の閲覧等
第7 鑑定委員会の意見
1 裁判所の求意見
2 意見書の提出
(1)事実の調査
(2)決議
(3)意見を述べる方式
(4)意見についての求説明
3 意見に対する当事者の陳述
第8 最終審問期日
第6節 手続の終了
第1 裁判
1 非訟事件の裁判
2 終局決定の種類
(1)申立てを排斥する裁判
ア 不適法である場合
イ 実体上理由がないとされる場合
(2)申立てを認容する裁判
(3)一部認容の裁判
(4)付随処分
3 終局決定の手続
4 中間決定
5 終局決定の更正・取消し又は変更
(1)終局決定に法令の違反がある場合の変更決定
(2)更正決定
(3)終局決定が不当な場合の取消し又は変更
6 終局決定の脱漏
7 終局決定の効力
(1)効力の発生
(2)終局決定の効力
ア 自縛力(自己拘束力)
イ 形成力
ウ 執行力
エ 既判力
(3)裁判の効力の及ぶ主観的範囲
8 裁判の無効・失効等
(1)裁判の無効
(2)裁判の失効
(3)形成された借地契約の変更
9 終局決定以外の裁判
第2 和解と調停
1 趣旨
2 和解と調停の運用
3 和解又は調停を積極的に試みるのが相当な例
4 運用上の問題
第3 申立ての取下げ
1 要件・方式
2 取下げの効果
第7節 手続の費用
第1 申立ての手数料
第2 費用の予納
第3 手続上の救助
第4 費用の裁判
第8節 抗告
第1 終局決定に対する即時抗告
1 総論
2 抗告権者
3 抗告期間
4 抗告提起の方式と原裁判所の手続
5 抗告提起の効果
6 抗告審への事件送付と事件送付を受けた抗告裁判所の手続
7 抗告の取下げ
8 抗告審の審理
(1)審理の構造と方式
(2)抗告審と介入権の行使
(3)抗告審と鑑定委員会
9 抗告審の裁判
(1)裁判の種類
(2)不利益変更禁止の原則と附帯抗告の可否
第2 終局決定以外の裁判に対する即時抗告
第3 再抗告
第4 特別抗告
第5 許可抗告
第6 再審
第2編 各論
第1章 建物の構造等に関する借地条件変更申立事件
第1節 総説
第1 借地条件変更裁判制度の創設
第2 堅固建物・非堅固建物の区別
第3 借地法と借地借家法における借地条件変更の裁判の対象
1 借地法の下における借地条件変更裁判の対象
2 借地借家法の下における借地条件変更裁判の対象の拡張
3 借地借家法施行前に設定された借地権についての借地条件変更の手続規定
第2節 要件
第1 総説
第2 形式的要件
1 当事者
(1)通常の場合
(2)転借地権の場合の特則
(3)当事者が複数の場合
2 借地権
(1)借地権の存在
(2)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件
(1)「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件」の意義
ア 「建物の種類、構造、規模又は用途」の意義と不動産登記法制の規定との関係
イ 「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件」の具体的な内容について
ウ 借地上の建物に関するその他の制限
(2)借地上の建物の種類、構造、規模又は用途を制限する特約の効力
(3)建物の種類、構造、規模又は用途を制限する特約の非訟手続上の意義
5 事前協議の不調
6 他の申立てとの関係
(1)賃借権譲渡許可申立てとの関係
(2)増改築許可申立てとの関係
ア 建物の構造、規模を制限する旨の借地条件変更の申立てと増改築許可申立ての関係
イ 建物の種類、用途を制限する旨の借地条件変更の申立てと増改築許可申立てとの関係
(3)建物再築許可申立てとの関係
7 その他の問題
(1)建築予定建物の具体的特定の要否
(2)建物の現存等の要否
第3 実質的要件
1 借地条件変更の相当性
(1)はじめに
(2)事情変更の意義
(3)法令による土地利用の規制の変更による事情の変更
(4)付近の土地の利用状況の変化による事情の変更
(5)その他の事情の変更
(6)借地条件変更の相当性
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)はじめに
(2)借地権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 借地権の残存期間の認定
ウ 建物の朽廃が近い場合
(3)土地の状況
(4)借地に関する従前の経過
(5)その他一切の事情
ア 跨り建物、共同ビル及び分譲マンションの築造を目的とする借地条件の変更
イ 借地条件変更の認容決定後の予定建物の変更について
第3節 付随処分
第1 概観
1 付随処分について
2 鑑定委員会の意見の聴取
第2 財産上の給付
1 総説
2 財産上の給付の根拠と給付額の算定
(1)財産上の給付の理論的根拠
(2)堅固建物所有目的への借地条件変更の場合の財産上の給付の取扱い
ア 原則的な取扱い
イ 増改築許可の裁判に対する財産上の給付との関係
ウ 借地条件変更と増改築許可を両方とも認容する場合における財産上の給付の定め方
エ 借地期間延長の付随処分の有無との関係
(3)堅固建物所有目的への変更以外の場合の財産上の給付の取扱い
(4)更新料支払の有無の考慮
第3 その他の借地条件の変更
1 存続期間の延長
(1)借地借家法施行前に設定された借地権の場合
(2)借地借家法施行後に設定された借地権等の場合
2 賃料の改定
(1)非堅固建物所有目的から堅固建物所有目的に借地条件を変更する場合の取扱い
(2)上記(1)以外の借地条件を変更する場合の取扱い
(3)賃料減額の是非
(4)賃料額の算定方法
(5)賃料改定の始期
第4 その他相当の処分
第4節 主文例や和解条項例
第2章 増改築許可申立事件
第1節 総論
第1 増改築許可の制度
第2 増改築許可の裁判制度の創設
第3 制度の特質
第2節 要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
(3)当事者複数の場合
(4)跨り建物の場合
(5)転借地関係
2 借地権
(1)借地権の存在
(2)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 増改築制限特約の存在
(1)増改築制限特約の存在
ア 増改築制限特約の意義
イ 借地法下の増改築制限特約
ウ 借地借家法下の増改築制限特約
(2)増改築制限特約の効力
(3)増改築制限特約の非訟手続上の意義
5 増改築の予定
(1)増改築の意義
ア 意義
イ 借地条件変更の合意がある場合
ウ 更地への新築
(2)増改築の予定と内容の特定
6 事前協議の不調
7 他の申立てとの関係
(1) 借地条件変更申立てとの関係
(2) 賃借権譲渡許可申立てとの関係
(3) 更新後の建物再築許可申立てとの関係
第3 実質的要件
1 土地の通常の利用上相当であるかどうか
(1) 建築基準法違反との関係
(2) 日照権侵害との関係
2 借地に関する諸事情の考慮
(1) 借地権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 建物の朽廃が近い場合
(2) 土地の状況
(3) 借地に関する従前の経過
(4) その他一切の事情
ア その他一切の事情とは
イ いわゆる跨り建物について
ウ いわゆる共同ビルについて
エ いわゆる分譲マンションについて
第3節 付随処分
第1 総説
第2 財産上の給付
1 理論的根拠
(1)総説
(2)更新料支払の有無の考慮
2 具体的算定
第3 その他の借地条件の変更
1 他の借地条件
2 賃料の改定
3 存続期間の延長
第4 その他相当の処分
1 態様
2 具体例
第4節 主文例や和解条項例
第3章 借地契約更新後の建物再築許可申立事件
第1節 総論
第1 借地契約更新後の建物再築許可制度の創設
第2 制度の趣旨
第2節 要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
(3)当事者複数の場合
2 借地借家法施行後に設定された借地権の存在
3 申立てが建物の築造前であること
4 借地契約更新後の建物再築
5 残存期間を超えて存続すべき建物の築造
(1)残存期間を超えて存続すべき建物
(2)新たに築造する場合
6 借地権設定者が地上権の消滅請求又は土地賃貸借の解約申入れをすることができない旨の定めがないこと
7 借地権設定者の承諾の不存在
8 他の申立てとの関係
(1)借地条件変更申立てとの関係
(2)増改築許可申立てとの関係
第3 実質的要件
1 やむを得ない事情
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)建物の状況
(2)建物の滅失に至った事情
(3)借地に関する従前の経過
(4)土地の使用を必要とする事情
(5)その他一切の事情
第3節 付随処分
第1 総説
第2 存続期間の延長
第3 財産上の給付
1 財産上の給付の根拠
2 給付額の算定
第4 その他の借地条件の変更
1 賃料の改定
2 建物の種類・構造・規模・用途を制限する旨の借地条件の変更
第5 その他相当の処分
第4節 主文例や和解条項例
第4章 賃借権譲渡・転貸許可申立事件及び競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第1節 賃借権譲渡・転貸許可申立ての要件
第1 総説
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
2 賃借権の存在
(1)建物所有を目的とする地上権の場合
(2)建物所有を目的とする土地賃借権
(3)賃借権の存否について争いがある場合
(4)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 借地上の建物の存在
5 借地上の建物の譲渡に伴って敷地の賃借権の譲渡又は転貸をしようとする場合であること
6 債権担保のための建物譲渡
(1)譲渡担保の場合
(2)買戻特約付売買の場合
(3)仮登記担保契約の場合
7 借地権設定者の承諾の不存在
8 他の申立てとの関係
(1)借地条件変更・増改築許可・建物再築許可との関係
(2)競公売に伴う賃借権譲受許可との関係
第3 実質的要件
1 借地権設定者に不利となるおそれのないこと
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)賃借権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 建物の朽廃が近い場合
(2)借地に関する従前の経過
(3)賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情
(4)その他一切の事情
第2節 競公売に伴う賃借権譲受許可申立ての要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
2 申立ての時期
3 借地の一部についての申立て
4 競売又は公売によって建物を取得するのに伴う土地賃借権の譲受け
(1)競売・公売の意義
(2)土地賃借権の譲受け
第3節 賃借権譲渡・転貸許可申立事件及び競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件の裁判における付随処分
第1 総説
1 はじめに
2 賃借権譲渡・転貸許可の裁判における付随処分
3 競公売に伴う賃借権譲受許可の裁判における付随処分
第2 財産上の給付
1 総説
2 財産上の給付の根拠
3 実務における財産上の給付額の算定
(1)原則的取扱い
(2)定率化された給付割合と異なる扱いをすべき場合
(3)財産上の給付額の算定の基礎とすべき借地権価格
第3 借地条件の変更その他
1 総説
2 存続期間の延長
3 賃料の改定
4 敷金の交付
第4節 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第1 総説
第2 介入権申立ての要件
1 形式的要件
(1)賃借権譲渡・転貸許可申立て又は競公売に伴う賃借権譲受許可の申立ての存在
(2)当事者
ア 借地関係が転貸借であって、転賃借権を譲渡又は再転貸しようとして許可申立てがされた場合
イ 借地が共有である場合
ウ 跨り建物の問題
(3)申立ての時期
(4)借地の一部についての申立て
2 裁量的棄却
(1)裁量的棄却の可否
(2)借地権者と譲受予定者との間に特殊な関係がある場合
(3)借地権設定者において相当の対価を支払うことができないおそれがある場合
(4)その他
第3 介入権の申立てを認容する裁判の効果
1 総説
2 当事者の義務
(1)第三者が建物を占有している場合
(2)建物に抵当権等の担保権設定の登記のある場合や所有権移転に関する仮登記のある場合
(3)当事者が義務の履行を怠った場合
3 賃借権譲渡許可申立て等の失効
第4 相当の対価の算定
1 建物及び土地賃借権の価格
2 借家権価格等の控除
3 対象建物に不法占拠者がいる場合
4 いわゆる名義書換料相当額の控除
5 まとめ
第5節 主文例や和解条項例
第1 賃借権譲渡許可申立事件
第2 競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第3 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第5章 各種申立書
○建物の構造等に関する借地条件変更申立書、増改築許可申立書
○増改築許可申立書
○借地契約更新後の建物再築許可申立書
○土地賃借権譲渡・土地転貸許可申立書
○競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立書
参考資料
○鑑定委員規則(昭和42年3月23日最高裁判所規則第4号)
○借地非訟事件の申立書様式について(昭和42年6月2日最高裁民二第492号(訟い―二)地方裁判所長あて民事局長通知)
○借地非訟事件の申立手数料の額の算定の基礎となる借地権の目的の土地の価額の算定基準について(昭和42年4月14日最高裁民二第334号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
○土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日最高裁民二第79号高等裁判所長官、地方裁判所長(東京を除く。)あて民事局長通知)
○競・公売に関する証明書の交付について(昭和42年5月8日最高裁民二第390号地方裁判所長あて民事局長通知)
○防火地域等の指定に関する証明書の交付について(昭和42年6月16日最高裁民二第542号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
○鑑定委員となるべき者の選任について(平成4年7月8日最高裁民二第190号地方裁判所長あて事務総長通達)
○鑑定委員に対する日当等の支給について(平成4年7月8日最高裁民二第193号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長、総務局長、経理局長通達)
○鑑定委員会の構成およびその運営について(昭和42年2月27日最高裁民二第199号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
事項索引
第1章 総説
第1節 借地非訟制度
第1 借地関係に伴う紛争と借地非訟
第2 借地非訟制度の歴史
1 戦前に設けられた制度
(1)借地借家臨時処理法
(2)防火地域内借地権処理法
2 戦後間もなく設けられた制度
(1)罹災都市借地借家臨時処理法
(2)接収不動産に関する借地借家臨時処理法
3 借地借家法改正要綱案
4 借地非訟制度の導入
5 借地借家法の制定
6 非訟事件手続法の制定及びそれに伴う借地借家法の改正
(1)総説
(2)改正の要点
(3)新旧非訟事件手続法及び借地借家法の適用関係
7 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の制定及び罹災都市借地借家臨時処理法等の廃止
(1)罹災都市借地借家臨時処理法の問題点
(2)大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の制定及び罹災都市借地借家臨時処理法の廃止
第2節 借地非訟事件の類型
第1 借地条件変更申立事件
第2 増改築許可申立事件
第3 更新後の建物再築許可申立事件
第4 賃借権譲渡・転貸許可申立事件
第5 競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第6 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第2章 借地非訟事件の手続の概要
第1節 手続の諸原則
第1 適用法規
第2 二当事者対立主義
第3 処分権主義とその制限
第4 職権探知主義
第5 口頭主義と書面主義、直接主義と間接主義
第6 公開主義と非公開主義
第2節 裁判所
第1 管轄
第2 裁判所の構成
第3 専門委員
第4 鑑定委員会
1 制度の趣旨
2 構成
3 鑑定委員の身分
4 鑑定委員会の職務活動
第3節 当事者等
第1 当事者
1 借地非訟における当事者
2 申立人と相手方
第2 当事者能力
第3 手続行為能力
第4 当事者適格
1 事件類型からみた当事者適格
2 土地所有者と契約書上の賃貸人が異なる場合
3 契約当事者が複数の場合の当事者適格
(1)問題の所在
(2)借地権者側の事情
ア 実体法上の性質の観点から
イ 手続上の必要性の観点から
ウ 結論
(3)借地権設定者側の事情
ア 実体法上の性質の観点から
イ 手続上の必要性の観点から
ウ 結論
(4)借地非訟の裁判の効力からの考え方
(5)当事者の一部から事前の承諾がある場合
(6)結論
第5 参加制度
1 非訟事件手続法及び借地借家法における参加制度
2 当事者参加の参加人となり得る者
3 任意参加
(1)任意参加申出の方式と要件
(2)任意参加申出の効果
4 強制参加
(1)強制参加申立ての方式と要件
(2)強制参加申立てに対する裁判
5 脱退
6 利害関係参加
(1)借地非訟事件における利害関係参加
(2)利害関係参加の方式
(3)利害関係参加人がすることができる行為
第6 代理人・補佐人
1 借地非訟事件の手続代理人
2 法定代理人
3 委任による手続代理人
(1)委任による手続代理人の資格
(2)代理権の証明
(3)委任による手続代理人の代理権の範囲
4 法令により裁判上の行為をすることのできる手続代理人
5 代理に関する民事訴訟法の規定の準用
6 補佐人
第7 検察官の不関与
第8 受継
1 借地非訟事件の手続の事実上の中断と受継
2 受継がされる場合
3 受継の手続
第4節 申立て
第1 申立書・印紙
1 申立ての方式
2 申立書の記載事項
(1)当事者及び法定代理人
(2)申立ての趣旨
(3)申立ての原因及び申立てを理由付ける事実
(4)借地契約の内容
(5)申立て前にした当事者間の協議の概要
(6)その他
3 申立ての併合
4 添付書類
5 印紙の貼用
6 費用の予納
第2 申立ての効果
1 事件の係属
2 重複申立ての禁止
第5節 審理
第1 当事者の陳述聴取(審問)
1 概要
2 審問期日
3 当事者の陳述聴取が必要な場合
第2 証拠調べと事実の調査
1 証明の必要
2 証拠調べ
3 事実の調査
第3 申立ての変更
1 申立ての変更の意義
2 申立ての変更の要件
(1)申立ての基礎の同一性
(2)著しく手続を遅滞させないこと
3 申立ての変更の態様
(1)土地の範囲の減縮、拡張
(2)許可を受ける増改築及び再築の内容の変更
(3)賃借権譲渡許可申立事件における申立ての内容の変更
(4)異種の申立て相互間の変更
4 申立ての変更の方式
第4 手続の併合と分離
1 手続の併合
(1)手続の併合の意義
(2)手続の併合の態様
ア 客観的併合
イ 主観的併合
2 手続の分離
3 分離・併合の裁判の取消し
第5 手続の中止
1 借地非訟事件における手続の中止
2 手続を中止することができる場合
3 中止の裁判
第6 記録の閲覧等
第7 鑑定委員会の意見
1 裁判所の求意見
2 意見書の提出
(1)事実の調査
(2)決議
(3)意見を述べる方式
(4)意見についての求説明
3 意見に対する当事者の陳述
第8 最終審問期日
第6節 手続の終了
第1 裁判
1 非訟事件の裁判
2 終局決定の種類
(1)申立てを排斥する裁判
ア 不適法である場合
イ 実体上理由がないとされる場合
(2)申立てを認容する裁判
(3)一部認容の裁判
(4)付随処分
3 終局決定の手続
4 中間決定
5 終局決定の更正・取消し又は変更
(1)終局決定に法令の違反がある場合の変更決定
(2)更正決定
(3)終局決定が不当な場合の取消し又は変更
6 終局決定の脱漏
7 終局決定の効力
(1)効力の発生
(2)終局決定の効力
ア 自縛力(自己拘束力)
イ 形成力
ウ 執行力
エ 既判力
(3)裁判の効力の及ぶ主観的範囲
8 裁判の無効・失効等
(1)裁判の無効
(2)裁判の失効
(3)形成された借地契約の変更
9 終局決定以外の裁判
第2 和解と調停
1 趣旨
2 和解と調停の運用
3 和解又は調停を積極的に試みるのが相当な例
4 運用上の問題
第3 申立ての取下げ
1 要件・方式
2 取下げの効果
第7節 手続の費用
第1 申立ての手数料
第2 費用の予納
第3 手続上の救助
第4 費用の裁判
第8節 抗告
第1 終局決定に対する即時抗告
1 総論
2 抗告権者
3 抗告期間
4 抗告提起の方式と原裁判所の手続
5 抗告提起の効果
6 抗告審への事件送付と事件送付を受けた抗告裁判所の手続
7 抗告の取下げ
8 抗告審の審理
(1)審理の構造と方式
(2)抗告審と介入権の行使
(3)抗告審と鑑定委員会
9 抗告審の裁判
(1)裁判の種類
(2)不利益変更禁止の原則と附帯抗告の可否
第2 終局決定以外の裁判に対する即時抗告
第3 再抗告
第4 特別抗告
第5 許可抗告
第6 再審
第2編 各論
第1章 建物の構造等に関する借地条件変更申立事件
第1節 総説
第1 借地条件変更裁判制度の創設
第2 堅固建物・非堅固建物の区別
第3 借地法と借地借家法における借地条件変更の裁判の対象
1 借地法の下における借地条件変更裁判の対象
2 借地借家法の下における借地条件変更裁判の対象の拡張
3 借地借家法施行前に設定された借地権についての借地条件変更の手続規定
第2節 要件
第1 総説
第2 形式的要件
1 当事者
(1)通常の場合
(2)転借地権の場合の特則
(3)当事者が複数の場合
2 借地権
(1)借地権の存在
(2)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件
(1)「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件」の意義
ア 「建物の種類、構造、規模又は用途」の意義と不動産登記法制の規定との関係
イ 「建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件」の具体的な内容について
ウ 借地上の建物に関するその他の制限
(2)借地上の建物の種類、構造、規模又は用途を制限する特約の効力
(3)建物の種類、構造、規模又は用途を制限する特約の非訟手続上の意義
5 事前協議の不調
6 他の申立てとの関係
(1)賃借権譲渡許可申立てとの関係
(2)増改築許可申立てとの関係
ア 建物の構造、規模を制限する旨の借地条件変更の申立てと増改築許可申立ての関係
イ 建物の種類、用途を制限する旨の借地条件変更の申立てと増改築許可申立てとの関係
(3)建物再築許可申立てとの関係
7 その他の問題
(1)建築予定建物の具体的特定の要否
(2)建物の現存等の要否
第3 実質的要件
1 借地条件変更の相当性
(1)はじめに
(2)事情変更の意義
(3)法令による土地利用の規制の変更による事情の変更
(4)付近の土地の利用状況の変化による事情の変更
(5)その他の事情の変更
(6)借地条件変更の相当性
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)はじめに
(2)借地権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 借地権の残存期間の認定
ウ 建物の朽廃が近い場合
(3)土地の状況
(4)借地に関する従前の経過
(5)その他一切の事情
ア 跨り建物、共同ビル及び分譲マンションの築造を目的とする借地条件の変更
イ 借地条件変更の認容決定後の予定建物の変更について
第3節 付随処分
第1 概観
1 付随処分について
2 鑑定委員会の意見の聴取
第2 財産上の給付
1 総説
2 財産上の給付の根拠と給付額の算定
(1)財産上の給付の理論的根拠
(2)堅固建物所有目的への借地条件変更の場合の財産上の給付の取扱い
ア 原則的な取扱い
イ 増改築許可の裁判に対する財産上の給付との関係
ウ 借地条件変更と増改築許可を両方とも認容する場合における財産上の給付の定め方
エ 借地期間延長の付随処分の有無との関係
(3)堅固建物所有目的への変更以外の場合の財産上の給付の取扱い
(4)更新料支払の有無の考慮
第3 その他の借地条件の変更
1 存続期間の延長
(1)借地借家法施行前に設定された借地権の場合
(2)借地借家法施行後に設定された借地権等の場合
2 賃料の改定
(1)非堅固建物所有目的から堅固建物所有目的に借地条件を変更する場合の取扱い
(2)上記(1)以外の借地条件を変更する場合の取扱い
(3)賃料減額の是非
(4)賃料額の算定方法
(5)賃料改定の始期
第4 その他相当の処分
第4節 主文例や和解条項例
第2章 増改築許可申立事件
第1節 総論
第1 増改築許可の制度
第2 増改築許可の裁判制度の創設
第3 制度の特質
第2節 要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
(3)当事者複数の場合
(4)跨り建物の場合
(5)転借地関係
2 借地権
(1)借地権の存在
(2)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 増改築制限特約の存在
(1)増改築制限特約の存在
ア 増改築制限特約の意義
イ 借地法下の増改築制限特約
ウ 借地借家法下の増改築制限特約
(2)増改築制限特約の効力
(3)増改築制限特約の非訟手続上の意義
5 増改築の予定
(1)増改築の意義
ア 意義
イ 借地条件変更の合意がある場合
ウ 更地への新築
(2)増改築の予定と内容の特定
6 事前協議の不調
7 他の申立てとの関係
(1) 借地条件変更申立てとの関係
(2) 賃借権譲渡許可申立てとの関係
(3) 更新後の建物再築許可申立てとの関係
第3 実質的要件
1 土地の通常の利用上相当であるかどうか
(1) 建築基準法違反との関係
(2) 日照権侵害との関係
2 借地に関する諸事情の考慮
(1) 借地権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 建物の朽廃が近い場合
(2) 土地の状況
(3) 借地に関する従前の経過
(4) その他一切の事情
ア その他一切の事情とは
イ いわゆる跨り建物について
ウ いわゆる共同ビルについて
エ いわゆる分譲マンションについて
第3節 付随処分
第1 総説
第2 財産上の給付
1 理論的根拠
(1)総説
(2)更新料支払の有無の考慮
2 具体的算定
第3 その他の借地条件の変更
1 他の借地条件
2 賃料の改定
3 存続期間の延長
第4 その他相当の処分
1 態様
2 具体例
第4節 主文例や和解条項例
第3章 借地契約更新後の建物再築許可申立事件
第1節 総論
第1 借地契約更新後の建物再築許可制度の創設
第2 制度の趣旨
第2節 要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
(3)当事者複数の場合
2 借地借家法施行後に設定された借地権の存在
3 申立てが建物の築造前であること
4 借地契約更新後の建物再築
5 残存期間を超えて存続すべき建物の築造
(1)残存期間を超えて存続すべき建物
(2)新たに築造する場合
6 借地権設定者が地上権の消滅請求又は土地賃貸借の解約申入れをすることができない旨の定めがないこと
7 借地権設定者の承諾の不存在
8 他の申立てとの関係
(1)借地条件変更申立てとの関係
(2)増改築許可申立てとの関係
第3 実質的要件
1 やむを得ない事情
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)建物の状況
(2)建物の滅失に至った事情
(3)借地に関する従前の経過
(4)土地の使用を必要とする事情
(5)その他一切の事情
第3節 付随処分
第1 総説
第2 存続期間の延長
第3 財産上の給付
1 財産上の給付の根拠
2 給付額の算定
第4 その他の借地条件の変更
1 賃料の改定
2 建物の種類・構造・規模・用途を制限する旨の借地条件の変更
第5 その他相当の処分
第4節 主文例や和解条項例
第4章 賃借権譲渡・転貸許可申立事件及び競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第1節 賃借権譲渡・転貸許可申立ての要件
第1 総説
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
2 賃借権の存在
(1)建物所有を目的とする地上権の場合
(2)建物所有を目的とする土地賃借権
(3)賃借権の存否について争いがある場合
(4)借地の一部についての申立て
3 申立ての時期
4 借地上の建物の存在
5 借地上の建物の譲渡に伴って敷地の賃借権の譲渡又は転貸をしようとする場合であること
6 債権担保のための建物譲渡
(1)譲渡担保の場合
(2)買戻特約付売買の場合
(3)仮登記担保契約の場合
7 借地権設定者の承諾の不存在
8 他の申立てとの関係
(1)借地条件変更・増改築許可・建物再築許可との関係
(2)競公売に伴う賃借権譲受許可との関係
第3 実質的要件
1 借地権設定者に不利となるおそれのないこと
2 借地に関する諸事情の考慮
(1)賃借権の残存期間
ア 残存期間が短い場合
イ 建物の朽廃が近い場合
(2)借地に関する従前の経過
(3)賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情
(4)その他一切の事情
第2節 競公売に伴う賃借権譲受許可申立ての要件
第1 総論
第2 形式的要件
1 当事者
(1)申立人
(2)相手方
2 申立ての時期
3 借地の一部についての申立て
4 競売又は公売によって建物を取得するのに伴う土地賃借権の譲受け
(1)競売・公売の意義
(2)土地賃借権の譲受け
第3節 賃借権譲渡・転貸許可申立事件及び競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件の裁判における付随処分
第1 総説
1 はじめに
2 賃借権譲渡・転貸許可の裁判における付随処分
3 競公売に伴う賃借権譲受許可の裁判における付随処分
第2 財産上の給付
1 総説
2 財産上の給付の根拠
3 実務における財産上の給付額の算定
(1)原則的取扱い
(2)定率化された給付割合と異なる扱いをすべき場合
(3)財産上の給付額の算定の基礎とすべき借地権価格
第3 借地条件の変更その他
1 総説
2 存続期間の延長
3 賃料の改定
4 敷金の交付
第4節 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第1 総説
第2 介入権申立ての要件
1 形式的要件
(1)賃借権譲渡・転貸許可申立て又は競公売に伴う賃借権譲受許可の申立ての存在
(2)当事者
ア 借地関係が転貸借であって、転賃借権を譲渡又は再転貸しようとして許可申立てがされた場合
イ 借地が共有である場合
ウ 跨り建物の問題
(3)申立ての時期
(4)借地の一部についての申立て
2 裁量的棄却
(1)裁量的棄却の可否
(2)借地権者と譲受予定者との間に特殊な関係がある場合
(3)借地権設定者において相当の対価を支払うことができないおそれがある場合
(4)その他
第3 介入権の申立てを認容する裁判の効果
1 総説
2 当事者の義務
(1)第三者が建物を占有している場合
(2)建物に抵当権等の担保権設定の登記のある場合や所有権移転に関する仮登記のある場合
(3)当事者が義務の履行を怠った場合
3 賃借権譲渡許可申立て等の失効
第4 相当の対価の算定
1 建物及び土地賃借権の価格
2 借家権価格等の控除
3 対象建物に不法占拠者がいる場合
4 いわゆる名義書換料相当額の控除
5 まとめ
第5節 主文例や和解条項例
第1 賃借権譲渡許可申立事件
第2 競公売に伴う賃借権譲受許可申立事件
第3 建物及び賃借権譲受申立事件(介入権申立事件)
第5章 各種申立書
○建物の構造等に関する借地条件変更申立書、増改築許可申立書
○増改築許可申立書
○借地契約更新後の建物再築許可申立書
○土地賃借権譲渡・土地転貸許可申立書
○競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立書
参考資料
○鑑定委員規則(昭和42年3月23日最高裁判所規則第4号)
○借地非訟事件の申立書様式について(昭和42年6月2日最高裁民二第492号(訟い―二)地方裁判所長あて民事局長通知)
○借地非訟事件の申立手数料の額の算定の基礎となる借地権の目的の土地の価額の算定基準について(昭和42年4月14日最高裁民二第334号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
○土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日最高裁民二第79号高等裁判所長官、地方裁判所長(東京を除く。)あて民事局長通知)
○競・公売に関する証明書の交付について(昭和42年5月8日最高裁民二第390号地方裁判所長あて民事局長通知)
○防火地域等の指定に関する証明書の交付について(昭和42年6月16日最高裁民二第542号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
○鑑定委員となるべき者の選任について(平成4年7月8日最高裁民二第190号地方裁判所長あて事務総長通達)
○鑑定委員に対する日当等の支給について(平成4年7月8日最高裁民二第193号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長、総務局長、経理局長通達)
○鑑定委員会の構成およびその運営について(昭和42年2月27日最高裁民二第199号高等裁判所長官、地方裁判所長あて民事局長通知)
事項索引
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。