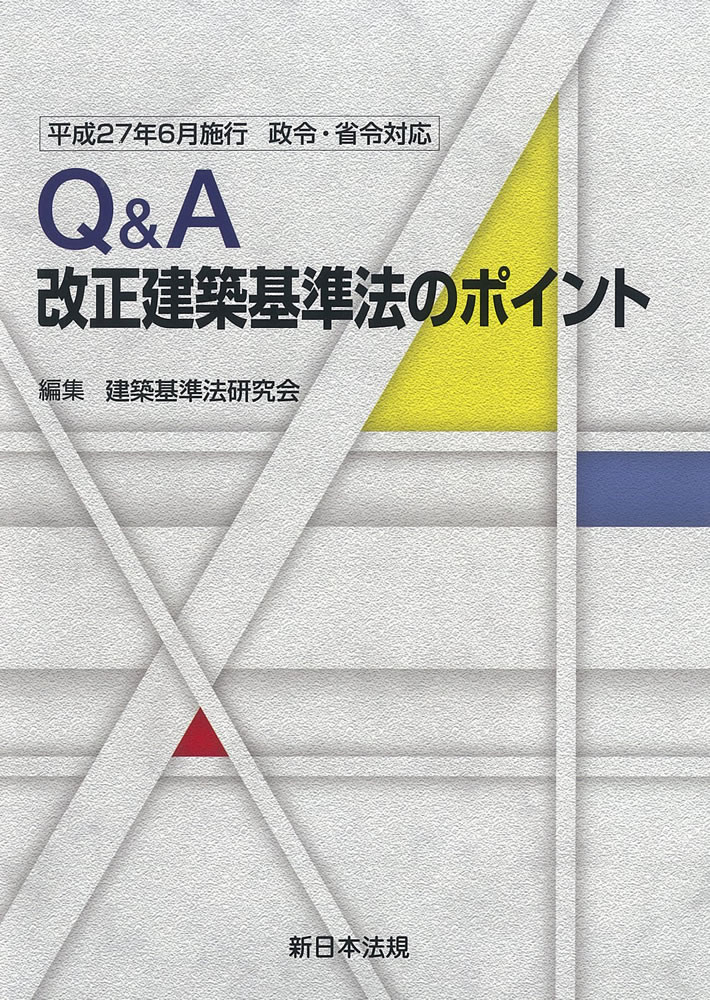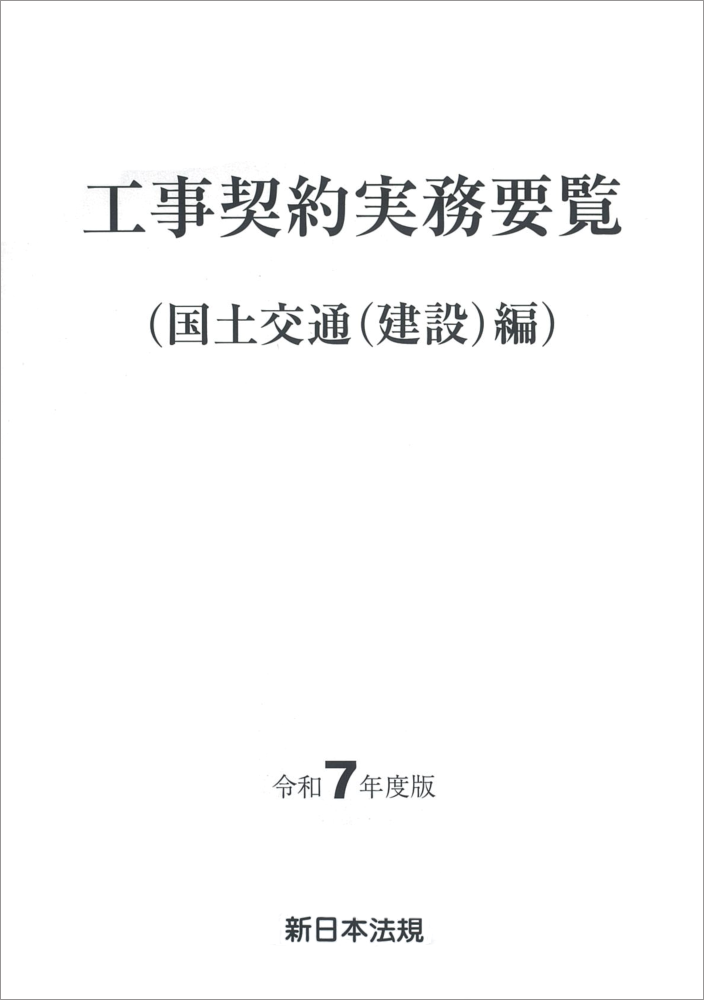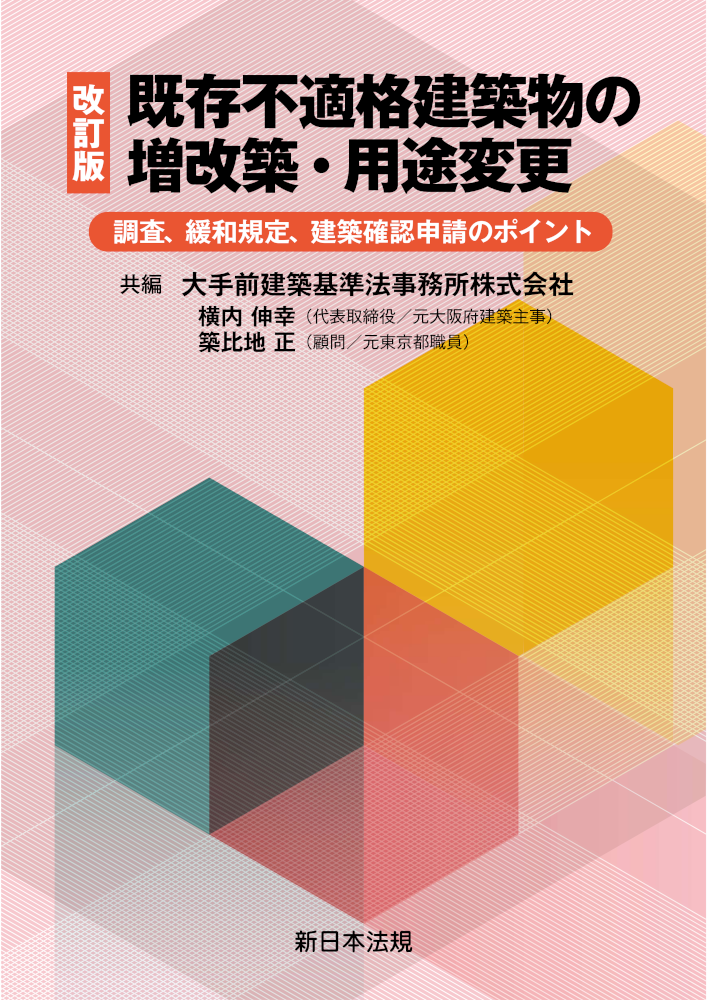概要
改正内容がよくわかる!
◆改正の要点をQ&A形式でわかりやすく解説しています。
◆建築基準法・同施行令・同施行規則の改正部分を明示した資料や関係告示、技術的助言を登載しています。
<改正の主なポイント>
1 構造計算適合性判定制度の見直し
2 指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設
3 構造耐力に関する規定の整備
4 木造建築関連基準の見直し
5 新技術の円滑な導入に向けた仕組みの創設
6 容積率制限の合理化
7 定期調査・検査報告制度の強化
8 建築物の事故等に対する調査体制の強化
商品情報
- 商品コード
- 50904
- ISBN
- 978-4-7882-8045-8
- JAN
- 9784788280458/1923032021005
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1
- ページ数
- 332
- 発行年月
- 2015年7月
目次
Q&A
第1 総論
Q1 今回の法改正の背景・経緯は何ですか。
Q2 今回の法改正全体の概要を教えてください。
第2 構造計算適合性判定制度の見直し
Q3 構造計算適合性判定制度の見直しの具体的な改正内容は何ですか。(法第6条の3)
Q4 構造計算適合性判定制度の手続を見直すとどのようなメリットがあるのですか。(法第6条の3)
Q5 なぜ建築確認と構造計算適合性判定のワンストップ化をしなかったのですか。(法第6条の3)
Q6 申請者側の要望である1機関指定の問題が解消されないのではないですか。(法第18条の2、第4章の2第3節)
Q7 申請者は2機関に申請することになり、手続が煩雑になりませんか。(法第6条の3)
Q8 別々の機関で審査をすると、審査に不整合は生じませんか。(法第6条の3)
Q9 適合判定通知書が建築主事又は指定確認検査機関に提出された後に、確認の申請書等に補正等が行われた場合の手続はどうなりますか。(法第6条の3)
Q10 構造計算適合性判定制度を見直すことにより安全性が損なわれることはないのですか。(法第6条の3)
Q11 構造計算適合性判定の対象外になるのは、どのようなケースですか。(令第9条の3)
Q12 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等は、どのような資格を持つ人ですか。(規則第3条の13)
Q13 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等が審査を行う機関等であるかどうかは、どうすればわかりますか。(規則第3条の13)
Q14 特定増改築構造計算を構造計算適合性判定の対象とする理由は何ですか。(法第6条の3、第86条の7)
Q15 建築主事等は、許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことはできますか。(規則第3条の13)
Q16 構造計算適合性判定員を登録制にする理由は何ですか。(法第4章の3第2節)
Q17 構造計算適合判定資格者検定とはどのような検定ですか。(法第5条の4、第5条の5)
Q18 現行の構造計算適合性判定員についても構造計算適合判定資格者検定を受ける必要がありますか。(改正法附則第3条)
Q19 増改築を行う建築物に係る申請図書及び書類の合理化により、どのようなメリットがあるのでしょうか。(規則第1条の3)
Q20 今回の改正により、全体計画認定の場合にも構造計算適合性判定が必要となったのでしょうか。(規則第10条の23)
第3 指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設
Q21 指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設の具体的な内容は何ですか。(法第7条の6)
Q22 特定行政庁のみが行っていた建築物の仮使用の判断を、今回の改正により、指定確認検査機関でもできるようにする趣旨は何ですか。(法第7条の6)
Q23 どのような判断基準で仮使用の認定がなされるのですか。(法第7条の6)
Q24 民間の指定確認検査機関に仮使用の認定事務を任せて消防との連携を図ることができますか。(法第7条の6)
第4 構造耐力に関する規定の整備
Q25 構造耐力に関する規定の整備の具体的な改正内容は何ですか。(法第20条)
第5 木造建築関連基準の見直し
Q26 木造建築関連基準の見直しの具体的な改正内容は何ですか。(法第21条、第27条)
Q27 学校以外の建築物は、木造3階建ての建築物に関する規制緩和の対象にならないのですか。(法第27条)
Q28 延べ面積3,000m2を超える木造建築物に関する規制緩和の内容は何ですか。(法第21条)
Q29 今回の改正で、木造3階建ての学校等の建築が可能となりましたが、建築物への木造利用は促進されますか。(法第27条)
Q30 学校を木造で建築する際の支援措置はありますか。(法第27条)
Q31 法第27条第1項に規定する「特殊建築物の主要構造部の構造方法」とは何ですか。(法第27条)
Q32 法第21条に規定されている壁等は、壁や防火設備で区画する壁等のみが告示で定められていますが、床で区画する場合も建築可能ですか。(法第21条)
Q33 法第27条第1項の「外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるもの」として令第110条の2第2号に規定する「国土交通大臣が定めるもの」は、何ですか。(法第27条)
Q34 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備について、求める性能を屋外から屋内への遮炎性能のみとしたのはなぜですか。(法第27条)
Q35 従前の耐火建築物・準耐火建築物と、改正後の「特定避難時間倒壊等防止建築物」・「耐火構造建築物」とはどのような関係にあるのですか。(法第27条)
Q36 木造3階建ての学校に関して、令第110条で定められている特定避難時間は、具体的に何時間という数値が告示において示されるのでしょうか。(法第27条)
Q37 建築確認における「特定避難時間」の取扱いはどうなるのですか。(法第27条)
第6 新技術の円滑な導入に向けた仕組み
Q38 新技術の円滑な導入に向けた仕組みの具体的な改正内容は何ですか。(法第38条)
Q39 平成10年に建築基準の性能規定化をしたのに、なぜ新たな大臣認定制度を創設するのですか。(法第38条)
Q40 平成10年の法改正で旧法第38条は廃止されていますが、旧法第38条認定を受けていた建築物を増築等しようとするときには、新法第38条認定(特殊構造方法等認定)を受けることになりますか。(法第38条)
Q41 新法第38条の認定を受けた構造方法等について、仕様を変更しようとするときは、どのような対応が必要ですか。(法第38条)
第7 容積率制限等の合理化
Q42 容積率制限等の合理化の具体的な改正内容は何ですか。(※エレベーターに関する部分は平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q43 エレベーターの床面積を容積率に不算入とすることにより、どのような効果がありますか。(※平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q44 エスカレーターは容積率不算入の対象にはなりませんか。(※平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q45 「老人ホーム等」の対象施設は具体的に何ですか。(法第52条)
Q46 なぜ病院や店舗、事務所は対象とならないのですか。(法第52条)
第8 定期報告制度の強化(公布の日から2年以内施行)
Q47 定期報告制度の具体的な改正内容は何ですか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条)
Q48 定期報告の対象として国が法令で定めるのは、具体的にどのような建築物ですか。また、調査・検査の内容はどう変わるのですか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条)
Q49 定期報告を行う者に必要な資格はありますか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条、第12条の2、第12条の3)
第9 建築物の事故等に対する調査体制強化
Q50 建築物の事故等に対する調査体制強化の具体的な改正内容は何ですか。(法第15条の2)
Q51 国による調査は何を目的に行うのですか。(法第15条の2)
Q52 国による事故等の調査は、どのような場合に行われるのですか。(法第15条の2)
Q53 製造者等に対する調査は、どのような場合に行われるのですか。(法第15条の2)
Q54 国が自ら必要な調査を行えることとなりますが、消費者庁との役割分担はどのようになっているのですか。(法第15条の2)
Q55 特定行政庁による調査対象を拡大する理由は何ですか。(法第12条)
Q56 特定行政庁による調査権限との関係性は何ですか。(法第15条の2)
第10 その他所要の改正事項
Q57 「移転」に関する改正の具体的な内容は何ですか。(法第3条、第86条の7)
Q58 大臣認定制度に係る認定建築材料等を引き渡した者に対する罰則の創設の具体的な内容は何ですか。(法第98条、第99条、第101条)
Q59 その他の罰則の改正に関する具体的な内容は何ですか。(法第99条)
第11 様式記入例
Q60 平成27年6月1日以降の第二号様式の記載方法はどうなりますか。
Q61 構造上分離している建築物の第二号様式、第四面と第六面の記載方法はどうなりますか。
資料
1 建築基準法(抄)(昭和25年法律第201号)
○平成27年6月1日までの施行分
○公布後2年以内施行分
2 建築基準法施行令(抄)(昭和25年政令第338号)
3 建築基準法施行規則(抄)(昭和25年建設省令第40号)
4 関係告示
○構造計算基準に適合する部分の計画を定める件(平成27年国土交通省告示第180号)
○確認審査等に関する指針(抄)(平成19年国土交通省告示第835号)
○建築基準法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成27年国土交通省告示第247号)
○建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件(抄)(昭和55年建設省告示第1791号)
○建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成27年国土交通省告示第189号)
○建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(抄)(平成19年国土交通省告示第1274号)
○建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)
○準耐火構造の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1358号)
○主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第253号)
○建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1377号)
○防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1360号)
○防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第257号)
○ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第254号)
○壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成27年国土交通省告示第249号)
○壁等の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第250号)
○特定防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1369号)
5 技術的助言
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日国住指第555号・国住街第39号)
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日国住指第558号・国住街第40号)
第1 総論
Q1 今回の法改正の背景・経緯は何ですか。
Q2 今回の法改正全体の概要を教えてください。
第2 構造計算適合性判定制度の見直し
Q3 構造計算適合性判定制度の見直しの具体的な改正内容は何ですか。(法第6条の3)
Q4 構造計算適合性判定制度の手続を見直すとどのようなメリットがあるのですか。(法第6条の3)
Q5 なぜ建築確認と構造計算適合性判定のワンストップ化をしなかったのですか。(法第6条の3)
Q6 申請者側の要望である1機関指定の問題が解消されないのではないですか。(法第18条の2、第4章の2第3節)
Q7 申請者は2機関に申請することになり、手続が煩雑になりませんか。(法第6条の3)
Q8 別々の機関で審査をすると、審査に不整合は生じませんか。(法第6条の3)
Q9 適合判定通知書が建築主事又は指定確認検査機関に提出された後に、確認の申請書等に補正等が行われた場合の手続はどうなりますか。(法第6条の3)
Q10 構造計算適合性判定制度を見直すことにより安全性が損なわれることはないのですか。(法第6条の3)
Q11 構造計算適合性判定の対象外になるのは、どのようなケースですか。(令第9条の3)
Q12 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等は、どのような資格を持つ人ですか。(規則第3条の13)
Q13 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等が審査を行う機関等であるかどうかは、どうすればわかりますか。(規則第3条の13)
Q14 特定増改築構造計算を構造計算適合性判定の対象とする理由は何ですか。(法第6条の3、第86条の7)
Q15 建築主事等は、許容応力度等計算(ルート2)の審査を行うことはできますか。(規則第3条の13)
Q16 構造計算適合性判定員を登録制にする理由は何ですか。(法第4章の3第2節)
Q17 構造計算適合判定資格者検定とはどのような検定ですか。(法第5条の4、第5条の5)
Q18 現行の構造計算適合性判定員についても構造計算適合判定資格者検定を受ける必要がありますか。(改正法附則第3条)
Q19 増改築を行う建築物に係る申請図書及び書類の合理化により、どのようなメリットがあるのでしょうか。(規則第1条の3)
Q20 今回の改正により、全体計画認定の場合にも構造計算適合性判定が必要となったのでしょうか。(規則第10条の23)
第3 指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設
Q21 指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設の具体的な内容は何ですか。(法第7条の6)
Q22 特定行政庁のみが行っていた建築物の仮使用の判断を、今回の改正により、指定確認検査機関でもできるようにする趣旨は何ですか。(法第7条の6)
Q23 どのような判断基準で仮使用の認定がなされるのですか。(法第7条の6)
Q24 民間の指定確認検査機関に仮使用の認定事務を任せて消防との連携を図ることができますか。(法第7条の6)
第4 構造耐力に関する規定の整備
Q25 構造耐力に関する規定の整備の具体的な改正内容は何ですか。(法第20条)
第5 木造建築関連基準の見直し
Q26 木造建築関連基準の見直しの具体的な改正内容は何ですか。(法第21条、第27条)
Q27 学校以外の建築物は、木造3階建ての建築物に関する規制緩和の対象にならないのですか。(法第27条)
Q28 延べ面積3,000m2を超える木造建築物に関する規制緩和の内容は何ですか。(法第21条)
Q29 今回の改正で、木造3階建ての学校等の建築が可能となりましたが、建築物への木造利用は促進されますか。(法第27条)
Q30 学校を木造で建築する際の支援措置はありますか。(法第27条)
Q31 法第27条第1項に規定する「特殊建築物の主要構造部の構造方法」とは何ですか。(法第27条)
Q32 法第21条に規定されている壁等は、壁や防火設備で区画する壁等のみが告示で定められていますが、床で区画する場合も建築可能ですか。(法第21条)
Q33 法第27条第1項の「外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるもの」として令第110条の2第2号に規定する「国土交通大臣が定めるもの」は、何ですか。(法第27条)
Q34 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備について、求める性能を屋外から屋内への遮炎性能のみとしたのはなぜですか。(法第27条)
Q35 従前の耐火建築物・準耐火建築物と、改正後の「特定避難時間倒壊等防止建築物」・「耐火構造建築物」とはどのような関係にあるのですか。(法第27条)
Q36 木造3階建ての学校に関して、令第110条で定められている特定避難時間は、具体的に何時間という数値が告示において示されるのでしょうか。(法第27条)
Q37 建築確認における「特定避難時間」の取扱いはどうなるのですか。(法第27条)
第6 新技術の円滑な導入に向けた仕組み
Q38 新技術の円滑な導入に向けた仕組みの具体的な改正内容は何ですか。(法第38条)
Q39 平成10年に建築基準の性能規定化をしたのに、なぜ新たな大臣認定制度を創設するのですか。(法第38条)
Q40 平成10年の法改正で旧法第38条は廃止されていますが、旧法第38条認定を受けていた建築物を増築等しようとするときには、新法第38条認定(特殊構造方法等認定)を受けることになりますか。(法第38条)
Q41 新法第38条の認定を受けた構造方法等について、仕様を変更しようとするときは、どのような対応が必要ですか。(法第38条)
第7 容積率制限等の合理化
Q42 容積率制限等の合理化の具体的な改正内容は何ですか。(※エレベーターに関する部分は平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q43 エレベーターの床面積を容積率に不算入とすることにより、どのような効果がありますか。(※平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q44 エスカレーターは容積率不算入の対象にはなりませんか。(※平成26年7月1日施行)(法第52条)
Q45 「老人ホーム等」の対象施設は具体的に何ですか。(法第52条)
Q46 なぜ病院や店舗、事務所は対象とならないのですか。(法第52条)
第8 定期報告制度の強化(公布の日から2年以内施行)
Q47 定期報告制度の具体的な改正内容は何ですか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条)
Q48 定期報告の対象として国が法令で定めるのは、具体的にどのような建築物ですか。また、調査・検査の内容はどう変わるのですか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条)
Q49 定期報告を行う者に必要な資格はありますか。(※公布の日から2年以内施行)(法第12条、第12条の2、第12条の3)
第9 建築物の事故等に対する調査体制強化
Q50 建築物の事故等に対する調査体制強化の具体的な改正内容は何ですか。(法第15条の2)
Q51 国による調査は何を目的に行うのですか。(法第15条の2)
Q52 国による事故等の調査は、どのような場合に行われるのですか。(法第15条の2)
Q53 製造者等に対する調査は、どのような場合に行われるのですか。(法第15条の2)
Q54 国が自ら必要な調査を行えることとなりますが、消費者庁との役割分担はどのようになっているのですか。(法第15条の2)
Q55 特定行政庁による調査対象を拡大する理由は何ですか。(法第12条)
Q56 特定行政庁による調査権限との関係性は何ですか。(法第15条の2)
第10 その他所要の改正事項
Q57 「移転」に関する改正の具体的な内容は何ですか。(法第3条、第86条の7)
Q58 大臣認定制度に係る認定建築材料等を引き渡した者に対する罰則の創設の具体的な内容は何ですか。(法第98条、第99条、第101条)
Q59 その他の罰則の改正に関する具体的な内容は何ですか。(法第99条)
第11 様式記入例
Q60 平成27年6月1日以降の第二号様式の記載方法はどうなりますか。
Q61 構造上分離している建築物の第二号様式、第四面と第六面の記載方法はどうなりますか。
資料
1 建築基準法(抄)(昭和25年法律第201号)
○平成27年6月1日までの施行分
○公布後2年以内施行分
2 建築基準法施行令(抄)(昭和25年政令第338号)
3 建築基準法施行規則(抄)(昭和25年建設省令第40号)
4 関係告示
○構造計算基準に適合する部分の計画を定める件(平成27年国土交通省告示第180号)
○確認審査等に関する指針(抄)(平成19年国土交通省告示第835号)
○建築基準法第7条の6第1項第2号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成27年国土交通省告示第247号)
○建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件(抄)(昭和55年建設省告示第1791号)
○建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成27年国土交通省告示第189号)
○建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(抄)(平成19年国土交通省告示第1274号)
○建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)
○準耐火構造の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1358号)
○主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第253号)
○建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1377号)
○防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1360号)
○防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第257号)
○ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第254号)
○壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成27年国土交通省告示第249号)
○壁等の構造方法を定める件(平成27年国土交通省告示第250号)
○特定防火設備の構造方法を定める件(抄)(平成12年建設省告示第1369号)
5 技術的助言
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日国住指第555号・国住街第39号)
○建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成27年5月27日国住指第558号・国住街第40号)
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。