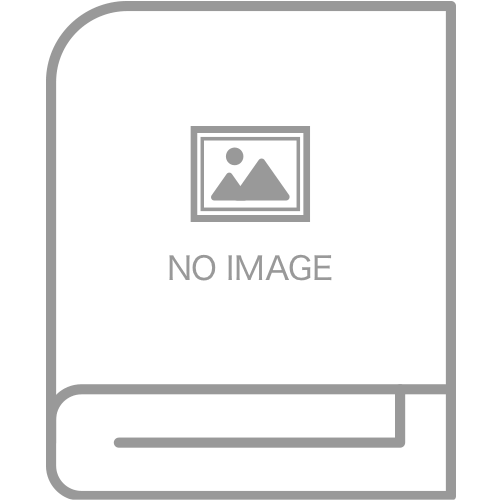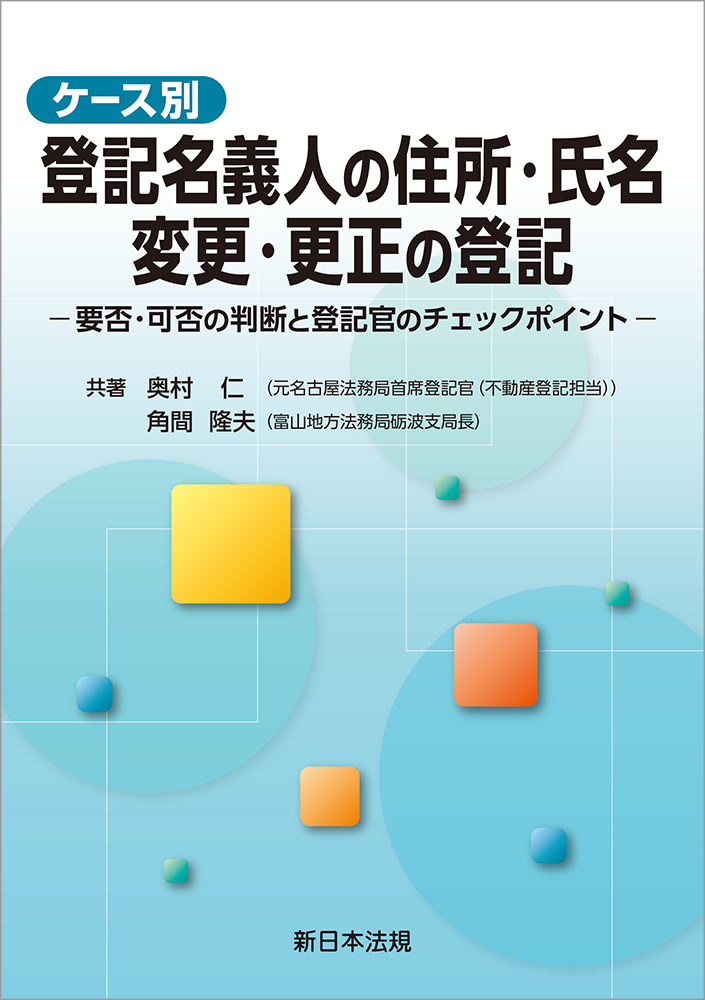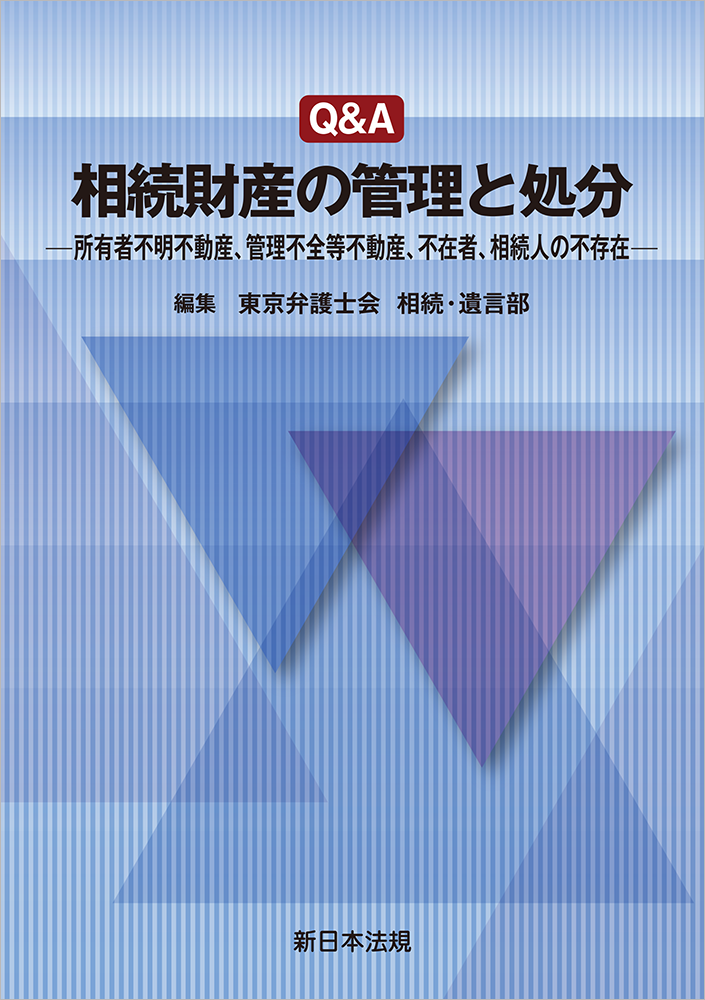概要
自主的紛争解決手続の最新手引書!
ADR基本法に対応した最新版!
◆裁判外紛争解決手続(ADR)、訴訟上の和解、訴え提起前の和解、和解に代わる決定、民事調停について、手続と問題点を実務的観点から解説。
◆各種の弁論調書・和解調書・申請書・申立書・申立調書などの作成に便利な文例書式を数多く登載。
◆さらに、合意後に作成する和解・調停条項の具体的な記載例を登載し、調書作成上の注意事項も説明。
商品情報
- 商品コード
- 5527
- ISBN
- 978-4-7882-6042-9
- JAN
- 9784788260429/1923032057004
- サイズ
- A5判
- 巻数
- 1・ケース付
- ページ数
- 940
- 発行年月
- 2007年6月
目次
序 章 裁判外紛争解決手続(ADR)
第1 概 説
第2 司法制度改革審議会のADR改革意見書
1 ADRの拡充・活性化の意義
2 ADRに関する関係機関等の連携強化
3 ADRに関する共通的な制度基盤の整備
第3 ADR基本法の制定
1 法律の制定
2 法律の目的
3 法律の基本理念
(1)4つの理念
(2)法による紛争の解決
(3)専門的な知見
4 法律の内容
5 認証手続利用の場合の優遇特例
6 ADRと認証制度
第4 ADRの基礎理論
1 裁判ADR協同主義論
2 ADR類型論
(1)ADR基本法3段階論
(2)強制的紛争解決手続(裁判)と任意的紛争解決手続(ADR)
3 ADR目的論
4 ADR特質論
5 ADR機能論
6 ADRモデル論
第5 ADRの現状
1 全体的な傾向
2 公害等調整委員会
3 建設工事紛争審査会
4 労働委員会・紛争調整委員会・労働審判
5 独立行政法人国民生活センター・都道府県消費生活センター
6 (財)交通事故紛争処理センター
7 第二東京弁護士会仲裁センター
8 (財)日本クレジットカウンセリング協会
9 (社)全国貸金業協会連合会苦情処理委員会
第6 ADRの技法
1 交渉学の説く技法論
2 レビン氏の説く調停技法論
3 草野判事流和解技術論
4 大澤恒夫教授の法的対話論
5 廣田尚久教授の紛争解決技術論
第7 和解・調停運用上の問題点
1 司法型ADRとしての和解・調停の問題点
2 訴え提起前の和解の運営上の問題点
3 訴訟上の和解の運営上の問題点
4 民事調停の運営上の問題点
第1章 訴訟上の和解
第1 意 義
第2 訴訟上の和解の性質
第3 訴訟上の和解の成立要件
1 概 説
2 和解の当事者
3 和解能力
4 法定代理権
5 訴訟代理権
6 司法書士の簡裁代理権制度の創設
7 和解の対象となり得ない事件
8 訴訟事件の係属
9 裁判所外の和解(いわゆる現地和解)
10 当事者の互譲
11 「争い」のあることの要否
第4 訴訟上の和解の手続
1 和解の試み
(1)弁論準備手続における和解
(2)裁判所等が定める和解条項
(3)裁判所等が定める和解条項の制度について共同の申立てによるものとした理由
(4)受命裁判官及び受託裁判官が定める和解条項
(5)裁判所等が定める和解条項の申立てについての取下げ
(6)裁判所に出頭することが困難な当事者に対する和解条項案の提示
(7)和解条項案の書面による受諾
(8)提出された受諾書面に条件が付せられている場合の取扱い
(9)受諾書面を提出した当事者本人の真意の確認
(10)第三者の関与
(11)和解の調書記載及び受諾書面の提出者への通知
2 専門委員制度と調査官制度の活用
(1)専門委員制度の目的
(2)専門委員の地位等
(3)専門委員の除斥・忌避
(4)専門委員の手続関与決定
(5)受命裁判官・受託裁判官の手続での専門委員関与
(6)裁判所調査官制度の活用
3 和解の成立
4 和解が調った旨の通知
5 和解調書の作成
(1)和解の調書記載
(2)調書の読聞けと閲覧の廃止、調書の記載に対する異議申立て
(3)和解調書の記載事項
ア 概 説
イ 和解調書の記載様式
書式例(1)和解調書
ウ 和解条項の告知
エ 和解調書の実質的記載事項についての問題点
6 和解調書正本の送達申請
書式例(2)和解調書正本送達申請書
(3)調書正本送達(謄本・抄本の交付)申請書
7 訴訟上の和解の効力
8 和解調書の更正
(1) 更正決定
書式例(4)和解調書更正決定の申立書
(2)更正の対象とならない事項
(3)更正の対象となる事項
(4)更正の認定に必要な資料
(5)更正の機関
(6)更正の方法
第5 和解の効力を争う手続
1 概 説
2 和解無効確認の訴え
書式例(5)和解無効確認請求の訴状
3 請求異議の訴え
書式例(6)請求異議の訴え
(7)強制執行停止決定申立書
第2章 訴え提起前の和解
第1 概 説
第2 訴え提起前の和解の性質
第3 民事上の争いの存在
第4 訴え提起前の和解の申立て
1 管 轄
書式例(8)管轄合意書
2 申立ての方式
書式例(9)訴え提起前の和解申立書
(10)訴え提起前の和解申立調書
3 申立書の記載事項とその問題点
(1)当事者
(2)法定代理人、代表者
(3)訴訟代理人
書式例(11)訴訟代理人許可申請書
(4)事件の表示
(5)請求の趣旨
(6)請求の原因
(7)争いの実情
(8)請求の趣旨,原因,争いの実情の表示がないか,又はそれが明確でない申立て
(9)和解条項案
(10)申立書の付属書類
4 訴訟係属中の訴え提起前の和解の申立ての許否
5 申立ての効果
(1)実体法上の効果
(2)訴訟法上の効果
第5 和解申立後の手続
1 受理に伴う手続
(1)申立書の審査
(2)申立ての要件,方式に違背した申立てに対する処理
2 和解事件の移送
書式例(12)移送決定書
3 和解申立ての却下
4 和解申立ての取下げ
5 和解期日の指定,呼出
(1)期日指定
(2)期日の呼出
6 和解期日における手続
書式例(13)当事者双方が任意に出頭し,口頭で和解の申立てをしたときの和解期日調書
7 和解手続の中断と受継
書式例(14)解手続受継の申立書
8 期日の結果
(1)和解期日の続行又は延期
(2)和解の不成立
(3)当事者の不出頭による和解不成立の擬制
(4)和解の成立
(5)和解調書
書式例(15)和解調書
(16)和解調書
(6)和解調書の効力
(7)和解調書の更正
(8)和解調書正本の送達申請
第6 民訴法264条,265条の規定を,訴え提起前の和解について適用しないこととした理由
第7 和解の効力を争う手続
第8 和解不成立と訴訟への移行
1 訴訟への移行
2 手数料の納付
3 管轄裁判所
4 和解申立てに要した費用の負担
第3章 和解に代わる決定
第1 概 説
1 和解に代わる決定の意義
2 和解に代わる決定の例
第2 和解に代わる決定の性質
第3 和解に代わる決定の要件
1 簡易裁判所の金銭支払請求訴訟であること
2 被告が事実を争わず防御方法を提出しないこと
3 裁判所が相当と認めるときであること
4 原告の意見を聴くこと
第4 可能な決定内容
1 期限の猶予
2 分割払
3 起訴後の損害金免除
第5 異議申立てによる決定の失効
1 異議申立ての方法
2 異議申立ての効力
3 期間経過による決定の発効
第4章 民事調停
第1 民事調停の意義
1 民事調停の対象
(1)家事紛争
(2)労働紛争
(3)行政紛争
2 民事調停の規範「条理」
3 民事調停の本質
(1)民事調停の任意性と判断性
(2)調停合意説
(3)調停裁判説
(4)両説の止揚・調和
4 民事調停の機能・存在理由
(1)訴訟補充的機能
(2)簡易裁判的機能
(3)取引仲介的機能
(4)事件振分け的機能
(5)法創造的機能
(6)民主主義的機能
(7)事案解明機能
(8)当事者自律的対処能力促進機能
第2 民事調停事件の種類と管轄
1 民事調停事件の種類
(1)宅地建物調停事件
(2)農事調停事件
(3)商事調停事件
(4)鉱害調停事件
(5)交通調停事件
(6)公害等調停事件
(7)特定調停事件
(8)民事一般調停事件
2 民事調停事件の管轄
(1)総 説
(2)原則的管轄(一般管轄)
(3)例外的管轄(合意管轄)
書式例(17)管轄合意書
(4)例外的管轄(特別管轄)
ア 宅地建物調停事件の特別管轄
イ 農事調停事件の特別管轄
ウ 鉱害調停事件の特別管轄
エ 交通調停事件の特別管轄
オ 公害等調停事件の特別管轄
(5)受訴裁判所の管轄
(6)管轄違いと移送・自庁処理
ア 管轄権の有無の調査
イ 管轄違いの場合の管轄裁判所への移送
ウ 土地管轄違いの場合の事物管轄裁判所への移送
エ 管轄裁判所の事物管轄裁判所への移送
書式例(18)移送申立書(上申)
オ 管轄裁判所の自庁処理
カ 特定調停における移送等の要件緩和
キ 当事者の異議なき管轄違い
ク 民事調停(訴訟)と家事調停との関連
第3 調停機関と補助機関
1 総 説
2 受調停裁判所と調停機関
(1) 受調停裁判所と調停機関
ア 受調停裁判所の構成
イ 調停機関の構成
ウ 権限の分配
(2) 調停委員会
ア 調停委員会の構成
イ 調停委員会の決議と評議
(3) 単独調停裁判官
3 裁判官
(1)裁判官のはたすべき役割
(2)裁判官の除斥・忌避・回避
ア 裁判官の除斥
イ 裁判官の忌避
ウ 裁判官の回避
4 民事調停官
(1)民事調停官制度の新設
(2)民事調停官の地位と身分
(3)民事調停官の権限
ア 受調停裁判所の指定
イ 調停に関する裁判官としての権限
ウ 調停に関する裁判所としての権限
エ 調停に関する権限外の権限
オ 裁判所書記官に対する命令権限
5 民事調停委員
(1) 民事調停委員の理想像
ア 民事調停委員の給源
イ 民事調停委員の法律知識
(2) 民事調停委員の任免
ア 民事調停委員の任命
イ 民事調停委員の解任
(3) 民事調停委員の地位
ア 民事調停委員の公務員化
イ 民事調停委員の任期
ウ 民事調停委員の報酬
エ 民事調停委員の分限
(4) 民事調停委員の除斥・忌避・回避
ア 民事調停委員の除斥
イ 民事調停委員の忌避
ウ 民事調停委員の回避
6 調停補助機関
(1) 裁判所書記官
ア 裁判所書記官の活用
イ 裁判所書記官の除斥・忌避・回避
(2) その他の補助機関
第4 調停当事者と調停関係人
1 総 説
2 調停能力と当事者適格
(1) 調停能力
書式例(19)補佐人許可申請書
(2) 調停当事者適格
3 調停代理人(代理と代表)
(1)調停手続の法定代理
(2)調停手続の任意代理
(3)本人出頭主義と出頭代理
書式例(20)代理人許可申請書
(21)委任状
(4)代理権の証明と無権代理・追認
(5)弁護士法違反の調停代理
(6)調停の代表
4 調停参加人(利害関係人の参加)
(1)調停参加の制度
(2)任意参加
書式例(22)利害関係人参加申立書
(3) 強制参加
書式例(23)利害関係人呼出申請書
(4) 参加人の地位(参加の効力)
5 当事者の交替(手続の承継)
(1)承継制度の許否
(2)承継の原因
(3)承継の手続と効果
書式例(24)調停手続受継申立書
6 多数当事者(共同調停,集合調停)
(1)共同調停の許否
(2)特定調停事件の併合
(3)代表当事者の選任と調停信託
(4)調停当事者の追加の許否
第5 民事調停の開始
1 総 説
2 民事調停の申立て
(1)調停申立ての時期
(2)地代借賃増減請求事件の調停前置主義
(3)調停申立ての方式
(4)特定調停手続の特則
(5)受付相談と(準)口頭受理
(6)調停申立書の記載事項
ア 総 説
イ 申立ての趣旨
ウ 紛争の要点
エ 申立ての年月日,裁判所の表示,申立人等の署名(記名)押印
書式例(25)調停申立書(一般調停)
(26) 調停申立書(宅地建物調停)
(27) 調停申立書(特定調停)
(7)添付書類
ア 資格証明書等(必要に応じて)
イ 証拠書類の差出し
ウ 申立書副本
(8)調停申立ての手数料
(9)調停申立ての効果
ア 調停係属
イ 時効中断
ウ 民事調停法19条の趣旨
エ その他の実体法上の効果
オ 民事調停の訴えの提起命令における本案性
(10)調停事件の受理・移送
ア 調停事件の受付
イ 事件係属の通知
ウ 補正命令
エ 事件の移送
3 職権調停
(1)総 説
(2)職権調停の要件
(3)付調停と事件処理
4 調停前の措置
(1)調停前の措置の意義
(2)調停前の措置の要件
書式例(28)調停前の措置命令申立書
(3)措置命令の内容
(4)措置命令の性質と不服申立て
(5)措置命令の効力
(6)措置違反に対する過料の裁判
(7)過料の決定の執行
5 調停開始と他の諸手続との関係
(1) 訴訟手続との関係
ア 民事訴訟と民事調停
イ 訴訟手続の中止
(2)訴え提起前の和解手続との関係
(3)督促手続との関係
(4)民事執行手続との関係
ア 民事執行と調停
イ 民事執行手続の停止
書式例(29)民事執行手続停止決定申立書
(30)担保取消決定申立書
(31)調停終了証明申請書
(32)同意書
(33)抗告権放棄書
ウ 特定調停における執行停止要件の緩和等
(5)保全手続との関係
(6)仲裁手続との関係
(7)破産手続との関係
第6 民事調停の進行
1 総 説
2 調停手続上の諸原則
(1)職権調査主義
(2)直接主義・口頭主義
(3)当事者権の保障
(4)非公開主義
3 調停手続の進行
(1) 期日の指定と変更
ア 期日の指定
イ 期日の変更
書式例(34)調停期日変更申請書
(2) 事件の関係人の呼出し
ア 「事件の関係人」の意義
イ 期日の呼出しの方法
ウ 不出頭者に対する過料の制裁
(3)期日への出頭
(4)期日実施の場所
ア 調停室における調停
イ 現地調停
(5)調停の非公開
(6)事実の調査
ア 「事実の調査」の意義
イ 調停主任による事実の調査
ウ 民事調停委員による事実の調査
エ 裁判所書記官による事実の調査
オ 他の裁判所に対する事実調査の嘱託
カ 民事調停委員による嘱託事実の調査
キ 官庁等に対する調査の嘱託
(7)証拠調べ
(8)意見の聴取
ア 事件関係人の意見の聴取
イ 専門家調停委員の意見の聴取
ウ 訴訟手続における専門家調停委員の活用
(9)手続調書と調停記録
ア 調停手続調書の作成
イ 調停記録の閲覧等
(10)調停手続の費用
ア 当事者の負担と国庫の負担
イ 当事者負担費用の国庫立替等
ウ 当事者間における費用の負担
4 調停合意への進行
(1)民事調停の手続と進め方
(2)調停にあたっての注意事項
ア 調停過程の実質
イ 事情聴取の際の注意事項
ウ 調停案の作成にあたっての注意事項
エ 説得にあたっての注意事項
5 各種調停の特別手続
(1)宅地建物調停
(2)農事調停
ア 特別管轄
イ 小作官等に対する事件受理等の通知
ウ 小作官等の意見陳述
エ 小作官等の意見聴取
オ 農業委員会の和解仲介等
カ 小作官等に対する事件終了等の通知
(3)商事調停
(4)鉱害調停
(5)交通調停
(6)公害等調停
ア 特別管轄
イ 代表当事者の選任
ウ 合意による暫定的措置の勧告
(7)特定調停
ア 特定調停法規の特則
イ 当事者の責務
ウ 文書等の提出
エ 職権調査
オ 官庁等からの意見聴取
カ 文書等不提出に対する制裁
第7 民事調停の終局
1 総 説
2 調停申立ての却下
(1)調停申立ての却下決定の許否
(2)申立ての却下決定に対する抗告の許否
3 調停申立ての取下げ
書式例(35)調停申立取下書
4 調停の拒否
(1)制度の意義
(2)調停申立ての却下との関係
(3)要 件
(4)事件の終了
(5)不服申立ての許否
(6)特定調停をしない場合
5 調停の不成立
(1)制度の意義
(2)要 件
(3)事件の終了
(4)調停の不成立と訴えの提起
(5)特定調停の特則
6 調停条項案の提示と調停条項案の書面による受諾
(1)調停委員会が提示する調停条項案
(2)調停条項案の書面による受諾
7 調停に代わる決定
(1)制度の意義
(2)要 件
ア 紛争の態様からのアプローチ
イ 調停の経過からのアプローチ
ウ 事件の性質からのアプローチ
(3) 裁 判
書式例(36)調停に代わる決定
(4)決定正本が不送達になった場合
(5)異議の申立て
書式例(37)調停に代わる決定に対する異議申立書
8 調停条項の裁定(一般)
(1)制度の意義
(2)裁定の要件
(3) 調停条項の裁定
9 調停条項の裁定(地代借賃増減請求事件)
(1)改正法の趣旨
(2)調停条項の裁定(一般)との相違点
10 調停条項の裁定(特定調停)
11 調停の成立
(1)制度の意義
(2)合意と調停
ア 合意の成立と調停の成立
イ 調停の法的性質
ウ 調停の成立と合意の撤回
(4) 調停成立調書
ア 調停成立調書の作成
イ 調停成立調書の更正決定
書式例(38) 調停調書更正決定申立書
ウ 調停成立調書の解釈
第8 調停の効力
1 総 説
2 調停の執行力
(1)債務名義の種類
(2)執行文の付与
(3)承継執行文(執行力の人的範囲)
(4)執行開始の要件
(5)請求異議の訴え
3 調停の既判力
(1) 学説の動向
ア 既判力肯定説
イ 制限的既判力説
ウ 既判力否定説
(2)判例の動向
(3)既判力の効果(作用)
4 調停の無効とその主張方法
(1) 調停の無効・取消原因
ア 実体法上・手続法上の瑕疵の存在
イ 調停の組織に関する瑕疵
ウ 調停の内容に関する瑕疵
エ 意思の形成に関する瑕疵
オ 調停の手続に関する瑕疵
(2) 調停無効の主張方法
ア 判例が認める無効主張方法
イ 学説の展開
ウ 各種手続の併存的適用
(3) 調停無効と国家賠償
5 調停の効力の時的限界
(1)事情変更の原則の適用
(2)調停における合意の解除
(3)調停で合意した契約の更新
第5章 和解・調停条項作成に関する問題
第1 概 説
第2 条項の種類とその態様
1 確認条項
2 形成条項
3 給付条項
4 附随的約款条項(附款)
(1)基本的条項
(2)附随的条項
ア 停止条件
イ 解除条件
ウ 確定期限
エ 不確定期限
オ 先給付
カ 引換給付
キ 債権者の予告
ク 代償請求
ケ 選択権の行使
コ 過怠約款
サ 失権約款
シ 解除権留保の特約条項
ス 特約条項
5 任意条項
6 清算条項
7 道義的条項
8 関連事件の処理条項
第3 和解・調停条項の具体的記載例
1 金銭債権に関する事件
例1 貸金債務について1回の履行を合意した場合の和解条項
例2 貸金債務について1回の履行を合意した場合の調停条項
例3 貸金債務について分割払を合意した場合
例4 分割支払を怠った場合の附帯の金員の加算と遅滞なく支払をした場合の債務の一部免除する旨の合意をした場合
例5 金銭債権に関する条項――定型様式
例6 貸金元本と遅延損害金債務の双方の分割支払を約した場合
例7 連帯債務の場合
例8 利害関係人が参加して連帯保証をした場合
例9 弁済期を延期し,かつ,分割払とする代わりに,担保として不動産に抵当権の設定を約した場合
例10 債務の一部に対し電話加入権を代物弁済とし,残金を分割払とした場合
例11 債務協定に関する調停条項
例12 債務協定に関する調停条項(即日金銭授受の条項)
例13 債務協定に関する調停条項(相殺契約条項を含む)
例14 債務協定に関する調停条項(債権減額契約と不履行の場合は全額支払条項)
例15 債務の一部免除の効力は期限の利益喪失により失われることを約した場合
例16 割賦販売法の指定商品を目的物件とした分割支払について未払代金を請求した場合
例17 保証人間の求償権の範囲に関し約定がなされた場合
例18 連帯債務者の1人が死亡して相続人が債務を承継し,他の連帯債務者と共に債務を負担する条項
例19 連帯債務者の1人が死亡し相続人が債務を承継した場合他の連帯債務者と共に分割支払を約した条項
例20 連帯債務者全員が死亡し各相続人が債務を承継しこれが支払を約した場合の条項
例21 売掛代金
例22 売掛代金(訴訟物以外の権利関係を加えた条項)
例23 売掛代金(継続的契約から生ずる法律関係全体を一括して存否につき確認する条項)
例24 売掛代金(和解内容として請求全部を放棄した条項)
例25 飲食代金
例26 立替金
例27 立替金(割賦販売あっせん業者)
例28 請負代金
例29 請負代金(瑕疵修補等請求権の放棄を含む)
例30 請負代金(補修工事を行う旨の条項を含む)
例31 請負代金(債権譲渡の条項を含む)
例32 預託金返還
例33 手附金返還
例34 手附金返還(売買契約不成立)
例35 保証金(営業保証金の還付請求)
例36 保証金
例37 違約金
例38 不当利得金返還
例39 損害賠償(工事方法の欠陥)
例40 損害賠償(診療行為の過失)
例41 損害賠償(身元保証契約によるもの)
例42 謝罪広告
例43 交通事故による損害賠償――定型様式
例44 交通事故による損害賠償――定型様式使用の条項
例45 交通事故による損害賠償(一括払条項・分割払条項)
例46 交通事故による損害賠償
例47 交通事故による損害賠償
例48 債務不存在確認
例49 保証債務不存在確認
例50 譲渡担保(不動産)
例51 譲渡担保(動産)
例52 譲渡担保(売買予約を含む)
2 不動産に関する事件
例53 不動産売買と登記手続に関する条項――定型様式
例54 不動産売買,所有権移転登記等
例55 不動産売買,所有権移転登記(代金完済のときに所有権が移転する特約)
例56 不動産売買,所有権移転登記(目的物件の坪数の増減により代金の増減を合意)
例57 不動産売買,所有権移転登記(目的土地の数量超過の場合)
例58 不動産売買,所有権移転登記(建物の部分的引渡し)
例59 不動産売買,所有権移転登記(債務不履行の事実による失権約款付)
例60 不動産売買,所有権移転登記(代金支払確保のため売主のために抵当権設定登記手続をする条項を含む)
例61 不動産売買,所有権移転登記(代金完済まで所有権を留保し,その間は目的不動産を賃貸する旨の条項)
例62 不動産売買,所有権移転登記(遺産分割による登記手続の条項を含む)
例63 土地の賃借人が地上建物を土地賃借権と共に土地賃貸人に売却した場合
例64 建物と借地権を,敷地所有者の承諾又は借地借家法19条の承諾に代わる裁判所の許可を条件として譲渡する場合
例65 売買予約
例66 贈 与
例67 交 換
例68 真正なる登記名義の回復
例69 所有権確認(土地の一部)
例70 所有権確認
例71 共有持分権確認,更正登記手続
例72 所有権移転登記の抹消
例73 抵当権設定登記抹消
例74 仮登記担保契約
例75 共有物分割
例76 境界確認(所有権確認)
例77 境界確認(所有権確認)
例78 境界確定の調停の申立ての結果成立した調停条項
例79 賃借権の範囲の確認
例80 通行権確認
例81 通行地役権確認
例82 隣地侵害による家屋部分の収去
例83 境界線近傍の建築についての合意
例84 民法233条1項の合意
例85 農地売買(農事調停に該当する例)
例86 農地所有権移転
例87 農地の賃貸借
例88 賃借権確認(土地)
例89 賃借権確認(建物)
例90 賃貸借条項――定型様式
例91 土地賃貸借
例92 土地賃貸借(短期間の賃貸借)
例93 土地賃貸借契約の更新
例94 建物賃貸借(賃借人からする賃貸借契約解除条項を含む)
例95 建物賃貸借(前賃貸借の解除,明渡しの執行力は更新後の賃貸借に及ぶか)
例96 建物賃貸借契約の更新
例97 部屋の賃貸借(失権約款条項を含む)
例98 一時使用のための土地賃貸借
例99 一時使用のための建物賃貸借
例100 借地権譲渡
例101 賃料増額(土地)
例102 賃料増額(建物)
例103 土地又は建物明渡し――定型様式
例104 建物明渡し
例105 建物明渡し
例106 建物明渡し
例107 建物明渡し
例108 建物明渡し
例109 権原なき建物占有者の明渡し
例110 期限付合意解約
例111 合意解除の効力を期限の到来にかからしめる条項
例112 土地明渡し,建物の買取り
例113 建物使用貸借契約解除,明渡し
例114 建物収去,土地明渡条項――定型様式
例115 建物収去,土地明渡し
例116 不法占有による建物収去,土地明渡し
例117 土地賃貸借契約解除,土地上の建物贈与契約条項
例118 地上建物の所有権放棄,土地明渡し
例119 第三者のためにする契約
3 商事調停に該当する事件
例120 約束手形金
例121 約束手形金
例122 約束手形返還請求についての条項
例123 時効消滅した約束手形債権の利得償還請求についての条項
例124 株券引渡し(代償請求)
例125 商標権
4 鉱害調停に該当する事件
例126 鉱害による賠償責任
例127 鉱害による賠償責任
5 日照,採光,通風等阻害に関する事件(公害調停に該当する事件)
例128 日照等阻害(補償による解決)
例129 日照等阻害(補償による解決)
例130 日照等阻害(一部建築工事中止)
例131 日照等阻害(補償と目隠し設置)
例132 騒音,振動(補償と騒音の防止設備)
例133 騒音,振動(補償と防音設備)
例134 騒音,振動(損害賠償)
例135 騒音,振動,大気汚染(補償と防音等の設備)
例136 大気汚染
例137 水質汚濁
6 請求異議
例138 請求異議訴訟において和解成立した場合の和解条項
例139 請求異議訴訟における請求の表示と和解条項の記載例
7 離 婚
例140 離婚,慰藉料等の請求
8 少額訴訟における和解条項
例141 少額訴訟の損害賠償金
9 特定調停事件
例142 特定調停事件
10 問題となる和解・調停条項
例143 債権者が債務全額についての債務名義を求めていたのに,これがない条項
例144 債務名義にならない条項
例145 給付の対象となる一定の金額が記載されていない条項
例146 明渡期限までに買戻しができる旨の約款と,明渡猶予期限の利益を失った場合との関係
例147 借地借家法適用の回避を目的とする疑いがある訴え提起前の和解条項
例148 建物移築に必要な替地について提供する宅地が確定されていない条項
例149 建物が存在するのに土地だけの明渡条項
例150 設置すべき目隠しの特定記載のない条項
例151 申立人の指定する者のために登記手続をするとの条項
例152 登記手続をなすべき意思の陳述が,相手方の登記手続をなすべき意思の陳述と同時履行の関係にある条項
例153 仮処分登記の抹消登記手続をするとの合意条項
例154 単に執行解放手続をするとの条項
第1 概 説
第2 司法制度改革審議会のADR改革意見書
1 ADRの拡充・活性化の意義
2 ADRに関する関係機関等の連携強化
3 ADRに関する共通的な制度基盤の整備
第3 ADR基本法の制定
1 法律の制定
2 法律の目的
3 法律の基本理念
(1)4つの理念
(2)法による紛争の解決
(3)専門的な知見
4 法律の内容
5 認証手続利用の場合の優遇特例
6 ADRと認証制度
第4 ADRの基礎理論
1 裁判ADR協同主義論
2 ADR類型論
(1)ADR基本法3段階論
(2)強制的紛争解決手続(裁判)と任意的紛争解決手続(ADR)
3 ADR目的論
4 ADR特質論
5 ADR機能論
6 ADRモデル論
第5 ADRの現状
1 全体的な傾向
2 公害等調整委員会
3 建設工事紛争審査会
4 労働委員会・紛争調整委員会・労働審判
5 独立行政法人国民生活センター・都道府県消費生活センター
6 (財)交通事故紛争処理センター
7 第二東京弁護士会仲裁センター
8 (財)日本クレジットカウンセリング協会
9 (社)全国貸金業協会連合会苦情処理委員会
第6 ADRの技法
1 交渉学の説く技法論
2 レビン氏の説く調停技法論
3 草野判事流和解技術論
4 大澤恒夫教授の法的対話論
5 廣田尚久教授の紛争解決技術論
第7 和解・調停運用上の問題点
1 司法型ADRとしての和解・調停の問題点
2 訴え提起前の和解の運営上の問題点
3 訴訟上の和解の運営上の問題点
4 民事調停の運営上の問題点
第1章 訴訟上の和解
第1 意 義
第2 訴訟上の和解の性質
第3 訴訟上の和解の成立要件
1 概 説
2 和解の当事者
3 和解能力
4 法定代理権
5 訴訟代理権
6 司法書士の簡裁代理権制度の創設
7 和解の対象となり得ない事件
8 訴訟事件の係属
9 裁判所外の和解(いわゆる現地和解)
10 当事者の互譲
11 「争い」のあることの要否
第4 訴訟上の和解の手続
1 和解の試み
(1)弁論準備手続における和解
(2)裁判所等が定める和解条項
(3)裁判所等が定める和解条項の制度について共同の申立てによるものとした理由
(4)受命裁判官及び受託裁判官が定める和解条項
(5)裁判所等が定める和解条項の申立てについての取下げ
(6)裁判所に出頭することが困難な当事者に対する和解条項案の提示
(7)和解条項案の書面による受諾
(8)提出された受諾書面に条件が付せられている場合の取扱い
(9)受諾書面を提出した当事者本人の真意の確認
(10)第三者の関与
(11)和解の調書記載及び受諾書面の提出者への通知
2 専門委員制度と調査官制度の活用
(1)専門委員制度の目的
(2)専門委員の地位等
(3)専門委員の除斥・忌避
(4)専門委員の手続関与決定
(5)受命裁判官・受託裁判官の手続での専門委員関与
(6)裁判所調査官制度の活用
3 和解の成立
4 和解が調った旨の通知
5 和解調書の作成
(1)和解の調書記載
(2)調書の読聞けと閲覧の廃止、調書の記載に対する異議申立て
(3)和解調書の記載事項
ア 概 説
イ 和解調書の記載様式
書式例(1)和解調書
ウ 和解条項の告知
エ 和解調書の実質的記載事項についての問題点
6 和解調書正本の送達申請
書式例(2)和解調書正本送達申請書
(3)調書正本送達(謄本・抄本の交付)申請書
7 訴訟上の和解の効力
8 和解調書の更正
(1) 更正決定
書式例(4)和解調書更正決定の申立書
(2)更正の対象とならない事項
(3)更正の対象となる事項
(4)更正の認定に必要な資料
(5)更正の機関
(6)更正の方法
第5 和解の効力を争う手続
1 概 説
2 和解無効確認の訴え
書式例(5)和解無効確認請求の訴状
3 請求異議の訴え
書式例(6)請求異議の訴え
(7)強制執行停止決定申立書
第2章 訴え提起前の和解
第1 概 説
第2 訴え提起前の和解の性質
第3 民事上の争いの存在
第4 訴え提起前の和解の申立て
1 管 轄
書式例(8)管轄合意書
2 申立ての方式
書式例(9)訴え提起前の和解申立書
(10)訴え提起前の和解申立調書
3 申立書の記載事項とその問題点
(1)当事者
(2)法定代理人、代表者
(3)訴訟代理人
書式例(11)訴訟代理人許可申請書
(4)事件の表示
(5)請求の趣旨
(6)請求の原因
(7)争いの実情
(8)請求の趣旨,原因,争いの実情の表示がないか,又はそれが明確でない申立て
(9)和解条項案
(10)申立書の付属書類
4 訴訟係属中の訴え提起前の和解の申立ての許否
5 申立ての効果
(1)実体法上の効果
(2)訴訟法上の効果
第5 和解申立後の手続
1 受理に伴う手続
(1)申立書の審査
(2)申立ての要件,方式に違背した申立てに対する処理
2 和解事件の移送
書式例(12)移送決定書
3 和解申立ての却下
4 和解申立ての取下げ
5 和解期日の指定,呼出
(1)期日指定
(2)期日の呼出
6 和解期日における手続
書式例(13)当事者双方が任意に出頭し,口頭で和解の申立てをしたときの和解期日調書
7 和解手続の中断と受継
書式例(14)解手続受継の申立書
8 期日の結果
(1)和解期日の続行又は延期
(2)和解の不成立
(3)当事者の不出頭による和解不成立の擬制
(4)和解の成立
(5)和解調書
書式例(15)和解調書
(16)和解調書
(6)和解調書の効力
(7)和解調書の更正
(8)和解調書正本の送達申請
第6 民訴法264条,265条の規定を,訴え提起前の和解について適用しないこととした理由
第7 和解の効力を争う手続
第8 和解不成立と訴訟への移行
1 訴訟への移行
2 手数料の納付
3 管轄裁判所
4 和解申立てに要した費用の負担
第3章 和解に代わる決定
第1 概 説
1 和解に代わる決定の意義
2 和解に代わる決定の例
第2 和解に代わる決定の性質
第3 和解に代わる決定の要件
1 簡易裁判所の金銭支払請求訴訟であること
2 被告が事実を争わず防御方法を提出しないこと
3 裁判所が相当と認めるときであること
4 原告の意見を聴くこと
第4 可能な決定内容
1 期限の猶予
2 分割払
3 起訴後の損害金免除
第5 異議申立てによる決定の失効
1 異議申立ての方法
2 異議申立ての効力
3 期間経過による決定の発効
第4章 民事調停
第1 民事調停の意義
1 民事調停の対象
(1)家事紛争
(2)労働紛争
(3)行政紛争
2 民事調停の規範「条理」
3 民事調停の本質
(1)民事調停の任意性と判断性
(2)調停合意説
(3)調停裁判説
(4)両説の止揚・調和
4 民事調停の機能・存在理由
(1)訴訟補充的機能
(2)簡易裁判的機能
(3)取引仲介的機能
(4)事件振分け的機能
(5)法創造的機能
(6)民主主義的機能
(7)事案解明機能
(8)当事者自律的対処能力促進機能
第2 民事調停事件の種類と管轄
1 民事調停事件の種類
(1)宅地建物調停事件
(2)農事調停事件
(3)商事調停事件
(4)鉱害調停事件
(5)交通調停事件
(6)公害等調停事件
(7)特定調停事件
(8)民事一般調停事件
2 民事調停事件の管轄
(1)総 説
(2)原則的管轄(一般管轄)
(3)例外的管轄(合意管轄)
書式例(17)管轄合意書
(4)例外的管轄(特別管轄)
ア 宅地建物調停事件の特別管轄
イ 農事調停事件の特別管轄
ウ 鉱害調停事件の特別管轄
エ 交通調停事件の特別管轄
オ 公害等調停事件の特別管轄
(5)受訴裁判所の管轄
(6)管轄違いと移送・自庁処理
ア 管轄権の有無の調査
イ 管轄違いの場合の管轄裁判所への移送
ウ 土地管轄違いの場合の事物管轄裁判所への移送
エ 管轄裁判所の事物管轄裁判所への移送
書式例(18)移送申立書(上申)
オ 管轄裁判所の自庁処理
カ 特定調停における移送等の要件緩和
キ 当事者の異議なき管轄違い
ク 民事調停(訴訟)と家事調停との関連
第3 調停機関と補助機関
1 総 説
2 受調停裁判所と調停機関
(1) 受調停裁判所と調停機関
ア 受調停裁判所の構成
イ 調停機関の構成
ウ 権限の分配
(2) 調停委員会
ア 調停委員会の構成
イ 調停委員会の決議と評議
(3) 単独調停裁判官
3 裁判官
(1)裁判官のはたすべき役割
(2)裁判官の除斥・忌避・回避
ア 裁判官の除斥
イ 裁判官の忌避
ウ 裁判官の回避
4 民事調停官
(1)民事調停官制度の新設
(2)民事調停官の地位と身分
(3)民事調停官の権限
ア 受調停裁判所の指定
イ 調停に関する裁判官としての権限
ウ 調停に関する裁判所としての権限
エ 調停に関する権限外の権限
オ 裁判所書記官に対する命令権限
5 民事調停委員
(1) 民事調停委員の理想像
ア 民事調停委員の給源
イ 民事調停委員の法律知識
(2) 民事調停委員の任免
ア 民事調停委員の任命
イ 民事調停委員の解任
(3) 民事調停委員の地位
ア 民事調停委員の公務員化
イ 民事調停委員の任期
ウ 民事調停委員の報酬
エ 民事調停委員の分限
(4) 民事調停委員の除斥・忌避・回避
ア 民事調停委員の除斥
イ 民事調停委員の忌避
ウ 民事調停委員の回避
6 調停補助機関
(1) 裁判所書記官
ア 裁判所書記官の活用
イ 裁判所書記官の除斥・忌避・回避
(2) その他の補助機関
第4 調停当事者と調停関係人
1 総 説
2 調停能力と当事者適格
(1) 調停能力
書式例(19)補佐人許可申請書
(2) 調停当事者適格
3 調停代理人(代理と代表)
(1)調停手続の法定代理
(2)調停手続の任意代理
(3)本人出頭主義と出頭代理
書式例(20)代理人許可申請書
(21)委任状
(4)代理権の証明と無権代理・追認
(5)弁護士法違反の調停代理
(6)調停の代表
4 調停参加人(利害関係人の参加)
(1)調停参加の制度
(2)任意参加
書式例(22)利害関係人参加申立書
(3) 強制参加
書式例(23)利害関係人呼出申請書
(4) 参加人の地位(参加の効力)
5 当事者の交替(手続の承継)
(1)承継制度の許否
(2)承継の原因
(3)承継の手続と効果
書式例(24)調停手続受継申立書
6 多数当事者(共同調停,集合調停)
(1)共同調停の許否
(2)特定調停事件の併合
(3)代表当事者の選任と調停信託
(4)調停当事者の追加の許否
第5 民事調停の開始
1 総 説
2 民事調停の申立て
(1)調停申立ての時期
(2)地代借賃増減請求事件の調停前置主義
(3)調停申立ての方式
(4)特定調停手続の特則
(5)受付相談と(準)口頭受理
(6)調停申立書の記載事項
ア 総 説
イ 申立ての趣旨
ウ 紛争の要点
エ 申立ての年月日,裁判所の表示,申立人等の署名(記名)押印
書式例(25)調停申立書(一般調停)
(26) 調停申立書(宅地建物調停)
(27) 調停申立書(特定調停)
(7)添付書類
ア 資格証明書等(必要に応じて)
イ 証拠書類の差出し
ウ 申立書副本
(8)調停申立ての手数料
(9)調停申立ての効果
ア 調停係属
イ 時効中断
ウ 民事調停法19条の趣旨
エ その他の実体法上の効果
オ 民事調停の訴えの提起命令における本案性
(10)調停事件の受理・移送
ア 調停事件の受付
イ 事件係属の通知
ウ 補正命令
エ 事件の移送
3 職権調停
(1)総 説
(2)職権調停の要件
(3)付調停と事件処理
4 調停前の措置
(1)調停前の措置の意義
(2)調停前の措置の要件
書式例(28)調停前の措置命令申立書
(3)措置命令の内容
(4)措置命令の性質と不服申立て
(5)措置命令の効力
(6)措置違反に対する過料の裁判
(7)過料の決定の執行
5 調停開始と他の諸手続との関係
(1) 訴訟手続との関係
ア 民事訴訟と民事調停
イ 訴訟手続の中止
(2)訴え提起前の和解手続との関係
(3)督促手続との関係
(4)民事執行手続との関係
ア 民事執行と調停
イ 民事執行手続の停止
書式例(29)民事執行手続停止決定申立書
(30)担保取消決定申立書
(31)調停終了証明申請書
(32)同意書
(33)抗告権放棄書
ウ 特定調停における執行停止要件の緩和等
(5)保全手続との関係
(6)仲裁手続との関係
(7)破産手続との関係
第6 民事調停の進行
1 総 説
2 調停手続上の諸原則
(1)職権調査主義
(2)直接主義・口頭主義
(3)当事者権の保障
(4)非公開主義
3 調停手続の進行
(1) 期日の指定と変更
ア 期日の指定
イ 期日の変更
書式例(34)調停期日変更申請書
(2) 事件の関係人の呼出し
ア 「事件の関係人」の意義
イ 期日の呼出しの方法
ウ 不出頭者に対する過料の制裁
(3)期日への出頭
(4)期日実施の場所
ア 調停室における調停
イ 現地調停
(5)調停の非公開
(6)事実の調査
ア 「事実の調査」の意義
イ 調停主任による事実の調査
ウ 民事調停委員による事実の調査
エ 裁判所書記官による事実の調査
オ 他の裁判所に対する事実調査の嘱託
カ 民事調停委員による嘱託事実の調査
キ 官庁等に対する調査の嘱託
(7)証拠調べ
(8)意見の聴取
ア 事件関係人の意見の聴取
イ 専門家調停委員の意見の聴取
ウ 訴訟手続における専門家調停委員の活用
(9)手続調書と調停記録
ア 調停手続調書の作成
イ 調停記録の閲覧等
(10)調停手続の費用
ア 当事者の負担と国庫の負担
イ 当事者負担費用の国庫立替等
ウ 当事者間における費用の負担
4 調停合意への進行
(1)民事調停の手続と進め方
(2)調停にあたっての注意事項
ア 調停過程の実質
イ 事情聴取の際の注意事項
ウ 調停案の作成にあたっての注意事項
エ 説得にあたっての注意事項
5 各種調停の特別手続
(1)宅地建物調停
(2)農事調停
ア 特別管轄
イ 小作官等に対する事件受理等の通知
ウ 小作官等の意見陳述
エ 小作官等の意見聴取
オ 農業委員会の和解仲介等
カ 小作官等に対する事件終了等の通知
(3)商事調停
(4)鉱害調停
(5)交通調停
(6)公害等調停
ア 特別管轄
イ 代表当事者の選任
ウ 合意による暫定的措置の勧告
(7)特定調停
ア 特定調停法規の特則
イ 当事者の責務
ウ 文書等の提出
エ 職権調査
オ 官庁等からの意見聴取
カ 文書等不提出に対する制裁
第7 民事調停の終局
1 総 説
2 調停申立ての却下
(1)調停申立ての却下決定の許否
(2)申立ての却下決定に対する抗告の許否
3 調停申立ての取下げ
書式例(35)調停申立取下書
4 調停の拒否
(1)制度の意義
(2)調停申立ての却下との関係
(3)要 件
(4)事件の終了
(5)不服申立ての許否
(6)特定調停をしない場合
5 調停の不成立
(1)制度の意義
(2)要 件
(3)事件の終了
(4)調停の不成立と訴えの提起
(5)特定調停の特則
6 調停条項案の提示と調停条項案の書面による受諾
(1)調停委員会が提示する調停条項案
(2)調停条項案の書面による受諾
7 調停に代わる決定
(1)制度の意義
(2)要 件
ア 紛争の態様からのアプローチ
イ 調停の経過からのアプローチ
ウ 事件の性質からのアプローチ
(3) 裁 判
書式例(36)調停に代わる決定
(4)決定正本が不送達になった場合
(5)異議の申立て
書式例(37)調停に代わる決定に対する異議申立書
8 調停条項の裁定(一般)
(1)制度の意義
(2)裁定の要件
(3) 調停条項の裁定
9 調停条項の裁定(地代借賃増減請求事件)
(1)改正法の趣旨
(2)調停条項の裁定(一般)との相違点
10 調停条項の裁定(特定調停)
11 調停の成立
(1)制度の意義
(2)合意と調停
ア 合意の成立と調停の成立
イ 調停の法的性質
ウ 調停の成立と合意の撤回
(4) 調停成立調書
ア 調停成立調書の作成
イ 調停成立調書の更正決定
書式例(38) 調停調書更正決定申立書
ウ 調停成立調書の解釈
第8 調停の効力
1 総 説
2 調停の執行力
(1)債務名義の種類
(2)執行文の付与
(3)承継執行文(執行力の人的範囲)
(4)執行開始の要件
(5)請求異議の訴え
3 調停の既判力
(1) 学説の動向
ア 既判力肯定説
イ 制限的既判力説
ウ 既判力否定説
(2)判例の動向
(3)既判力の効果(作用)
4 調停の無効とその主張方法
(1) 調停の無効・取消原因
ア 実体法上・手続法上の瑕疵の存在
イ 調停の組織に関する瑕疵
ウ 調停の内容に関する瑕疵
エ 意思の形成に関する瑕疵
オ 調停の手続に関する瑕疵
(2) 調停無効の主張方法
ア 判例が認める無効主張方法
イ 学説の展開
ウ 各種手続の併存的適用
(3) 調停無効と国家賠償
5 調停の効力の時的限界
(1)事情変更の原則の適用
(2)調停における合意の解除
(3)調停で合意した契約の更新
第5章 和解・調停条項作成に関する問題
第1 概 説
第2 条項の種類とその態様
1 確認条項
2 形成条項
3 給付条項
4 附随的約款条項(附款)
(1)基本的条項
(2)附随的条項
ア 停止条件
イ 解除条件
ウ 確定期限
エ 不確定期限
オ 先給付
カ 引換給付
キ 債権者の予告
ク 代償請求
ケ 選択権の行使
コ 過怠約款
サ 失権約款
シ 解除権留保の特約条項
ス 特約条項
5 任意条項
6 清算条項
7 道義的条項
8 関連事件の処理条項
第3 和解・調停条項の具体的記載例
1 金銭債権に関する事件
例1 貸金債務について1回の履行を合意した場合の和解条項
例2 貸金債務について1回の履行を合意した場合の調停条項
例3 貸金債務について分割払を合意した場合
例4 分割支払を怠った場合の附帯の金員の加算と遅滞なく支払をした場合の債務の一部免除する旨の合意をした場合
例5 金銭債権に関する条項――定型様式
例6 貸金元本と遅延損害金債務の双方の分割支払を約した場合
例7 連帯債務の場合
例8 利害関係人が参加して連帯保証をした場合
例9 弁済期を延期し,かつ,分割払とする代わりに,担保として不動産に抵当権の設定を約した場合
例10 債務の一部に対し電話加入権を代物弁済とし,残金を分割払とした場合
例11 債務協定に関する調停条項
例12 債務協定に関する調停条項(即日金銭授受の条項)
例13 債務協定に関する調停条項(相殺契約条項を含む)
例14 債務協定に関する調停条項(債権減額契約と不履行の場合は全額支払条項)
例15 債務の一部免除の効力は期限の利益喪失により失われることを約した場合
例16 割賦販売法の指定商品を目的物件とした分割支払について未払代金を請求した場合
例17 保証人間の求償権の範囲に関し約定がなされた場合
例18 連帯債務者の1人が死亡して相続人が債務を承継し,他の連帯債務者と共に債務を負担する条項
例19 連帯債務者の1人が死亡し相続人が債務を承継した場合他の連帯債務者と共に分割支払を約した条項
例20 連帯債務者全員が死亡し各相続人が債務を承継しこれが支払を約した場合の条項
例21 売掛代金
例22 売掛代金(訴訟物以外の権利関係を加えた条項)
例23 売掛代金(継続的契約から生ずる法律関係全体を一括して存否につき確認する条項)
例24 売掛代金(和解内容として請求全部を放棄した条項)
例25 飲食代金
例26 立替金
例27 立替金(割賦販売あっせん業者)
例28 請負代金
例29 請負代金(瑕疵修補等請求権の放棄を含む)
例30 請負代金(補修工事を行う旨の条項を含む)
例31 請負代金(債権譲渡の条項を含む)
例32 預託金返還
例33 手附金返還
例34 手附金返還(売買契約不成立)
例35 保証金(営業保証金の還付請求)
例36 保証金
例37 違約金
例38 不当利得金返還
例39 損害賠償(工事方法の欠陥)
例40 損害賠償(診療行為の過失)
例41 損害賠償(身元保証契約によるもの)
例42 謝罪広告
例43 交通事故による損害賠償――定型様式
例44 交通事故による損害賠償――定型様式使用の条項
例45 交通事故による損害賠償(一括払条項・分割払条項)
例46 交通事故による損害賠償
例47 交通事故による損害賠償
例48 債務不存在確認
例49 保証債務不存在確認
例50 譲渡担保(不動産)
例51 譲渡担保(動産)
例52 譲渡担保(売買予約を含む)
2 不動産に関する事件
例53 不動産売買と登記手続に関する条項――定型様式
例54 不動産売買,所有権移転登記等
例55 不動産売買,所有権移転登記(代金完済のときに所有権が移転する特約)
例56 不動産売買,所有権移転登記(目的物件の坪数の増減により代金の増減を合意)
例57 不動産売買,所有権移転登記(目的土地の数量超過の場合)
例58 不動産売買,所有権移転登記(建物の部分的引渡し)
例59 不動産売買,所有権移転登記(債務不履行の事実による失権約款付)
例60 不動産売買,所有権移転登記(代金支払確保のため売主のために抵当権設定登記手続をする条項を含む)
例61 不動産売買,所有権移転登記(代金完済まで所有権を留保し,その間は目的不動産を賃貸する旨の条項)
例62 不動産売買,所有権移転登記(遺産分割による登記手続の条項を含む)
例63 土地の賃借人が地上建物を土地賃借権と共に土地賃貸人に売却した場合
例64 建物と借地権を,敷地所有者の承諾又は借地借家法19条の承諾に代わる裁判所の許可を条件として譲渡する場合
例65 売買予約
例66 贈 与
例67 交 換
例68 真正なる登記名義の回復
例69 所有権確認(土地の一部)
例70 所有権確認
例71 共有持分権確認,更正登記手続
例72 所有権移転登記の抹消
例73 抵当権設定登記抹消
例74 仮登記担保契約
例75 共有物分割
例76 境界確認(所有権確認)
例77 境界確認(所有権確認)
例78 境界確定の調停の申立ての結果成立した調停条項
例79 賃借権の範囲の確認
例80 通行権確認
例81 通行地役権確認
例82 隣地侵害による家屋部分の収去
例83 境界線近傍の建築についての合意
例84 民法233条1項の合意
例85 農地売買(農事調停に該当する例)
例86 農地所有権移転
例87 農地の賃貸借
例88 賃借権確認(土地)
例89 賃借権確認(建物)
例90 賃貸借条項――定型様式
例91 土地賃貸借
例92 土地賃貸借(短期間の賃貸借)
例93 土地賃貸借契約の更新
例94 建物賃貸借(賃借人からする賃貸借契約解除条項を含む)
例95 建物賃貸借(前賃貸借の解除,明渡しの執行力は更新後の賃貸借に及ぶか)
例96 建物賃貸借契約の更新
例97 部屋の賃貸借(失権約款条項を含む)
例98 一時使用のための土地賃貸借
例99 一時使用のための建物賃貸借
例100 借地権譲渡
例101 賃料増額(土地)
例102 賃料増額(建物)
例103 土地又は建物明渡し――定型様式
例104 建物明渡し
例105 建物明渡し
例106 建物明渡し
例107 建物明渡し
例108 建物明渡し
例109 権原なき建物占有者の明渡し
例110 期限付合意解約
例111 合意解除の効力を期限の到来にかからしめる条項
例112 土地明渡し,建物の買取り
例113 建物使用貸借契約解除,明渡し
例114 建物収去,土地明渡条項――定型様式
例115 建物収去,土地明渡し
例116 不法占有による建物収去,土地明渡し
例117 土地賃貸借契約解除,土地上の建物贈与契約条項
例118 地上建物の所有権放棄,土地明渡し
例119 第三者のためにする契約
3 商事調停に該当する事件
例120 約束手形金
例121 約束手形金
例122 約束手形返還請求についての条項
例123 時効消滅した約束手形債権の利得償還請求についての条項
例124 株券引渡し(代償請求)
例125 商標権
4 鉱害調停に該当する事件
例126 鉱害による賠償責任
例127 鉱害による賠償責任
5 日照,採光,通風等阻害に関する事件(公害調停に該当する事件)
例128 日照等阻害(補償による解決)
例129 日照等阻害(補償による解決)
例130 日照等阻害(一部建築工事中止)
例131 日照等阻害(補償と目隠し設置)
例132 騒音,振動(補償と騒音の防止設備)
例133 騒音,振動(補償と防音設備)
例134 騒音,振動(損害賠償)
例135 騒音,振動,大気汚染(補償と防音等の設備)
例136 大気汚染
例137 水質汚濁
6 請求異議
例138 請求異議訴訟において和解成立した場合の和解条項
例139 請求異議訴訟における請求の表示と和解条項の記載例
7 離 婚
例140 離婚,慰藉料等の請求
8 少額訴訟における和解条項
例141 少額訴訟の損害賠償金
9 特定調停事件
例142 特定調停事件
10 問題となる和解・調停条項
例143 債権者が債務全額についての債務名義を求めていたのに,これがない条項
例144 債務名義にならない条項
例145 給付の対象となる一定の金額が記載されていない条項
例146 明渡期限までに買戻しができる旨の約款と,明渡猶予期限の利益を失った場合との関係
例147 借地借家法適用の回避を目的とする疑いがある訴え提起前の和解条項
例148 建物移築に必要な替地について提供する宅地が確定されていない条項
例149 建物が存在するのに土地だけの明渡条項
例150 設置すべき目隠しの特定記載のない条項
例151 申立人の指定する者のために登記手続をするとの条項
例152 登記手続をなすべき意思の陳述が,相手方の登記手続をなすべき意思の陳述と同時履行の関係にある条項
例153 仮処分登記の抹消登記手続をするとの合意条項
例154 単に執行解放手続をするとの条項
著者
加除式購読者のお客様へ
本書は加除式書籍です。
本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。
加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ
本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。
WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。
1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。
契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。
契約期間中の途中解約はできません。
契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。
ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。