解説記事2005年10月03日 【ニュース特集】 カネボウの粉飾決算事件が与える影響は?(2005年10月3日号・№132)
ニュース特集
業務停止処分となれば一時会計監査人の選任という事態も
カネボウの粉飾決算事件が与える影響は?
現在、金融庁では、カネボウの粉飾決算事件を受け、行政処分を検討中だ。今回の事件では、中央青山監査法人の社員が4名、証券取引法違反の容疑で東京地方検察庁により逮捕されているが、金融庁の行政処分は中央青山監査法人だけでなく、同法人を会計監査人としている会社にとっても対岸の火事とはいえない。仮に業務停止処分が公認会計士又は監査法人に対して行われた場合には、一時会計監査人を選任する事態にもなりかねないからだ。今回の特集では、カネボウの粉飾事件を巡る影響とその問題点についてお伝えする。
行政処分はどうなる?
カネボウの粉飾決算事件については、証券取引等監視委員会と東京地方検察庁特別捜査部が平成17年7月29日、証券取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、関係先に対する強制調査を実施。8月17日にはカネボウの元社長ら3名が東京地方検察庁に告発され、このうち2名が起訴されている。その後、9月13日、カネボウの監査を担当していた中央青山監査法人の公認会計士4名についても逮捕されている。刑事責任については、今後、行われるであろう裁判の推移を見守る必要があるが、一方、公認会計士法における行政処分については、被監査会社にとっても注目すべき事項といえる。
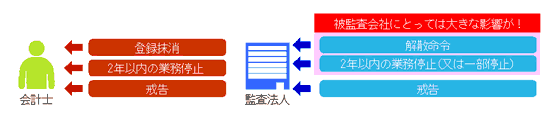
過去、業務停止は瑞穂監査法人のみ
具体的に公認会計士法による懲戒処分(公認会計士法第30条)では、重い順に①登録の抹消、②2年以内の業務停止、③戒告となる。また、監査法人に対する懲戒処分(同法第34条の21)では、①解散命令、②2年以内の業務の全部又は一部の停止、③戒告となる。
公認会計士の場合、最も重い処分が登録の抹消。この場合、公認会計士の業務を行う要件とされている公認会計士名簿の登録が抹消され、公認会計士としての身分を失うことになる。また、処分を受けた日から5年を経過しない間は、公認会計士の欠格事由(同法第4条)に該当することになり、公認会計士になることはできない。一方、監査法人については、最も重い処分が解散命令であり、次に業務停止である。過去に解散命令の処分が下された事案はなく、業務停止についても平成14年のフットワークエクスプレス株式会社の監査を行った瑞穂監査法人のみとなっている(右表参照)。
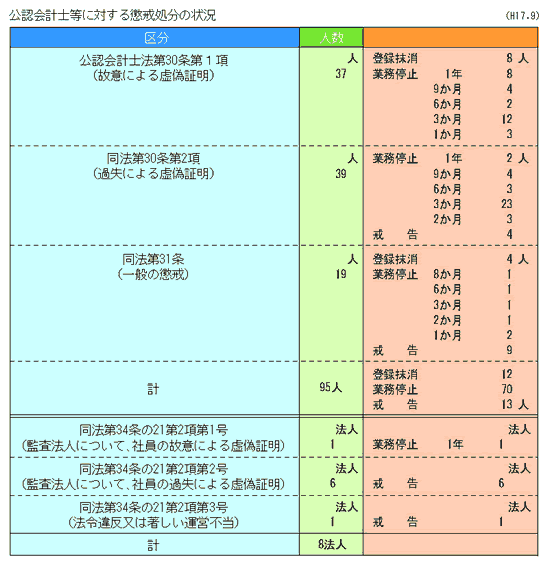
なお、金融庁では、平成16年の公認会計士法改正を受け、3月31日に「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」と題する報告書を公表している。これは、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準を明確化するもの。それによると、公認会計士による虚偽証明・不当証明について、故意の場合には、登録抹消、過失の場合には業務停止6か月が基本となる。
また、監査法人の場合には、故意の場合には業務停止3か月、過失の場合には業務停止1か月が基本となる。ただし、内部管理の態様など、個別事情等により、基本となる処分を加重又は軽減できるとしているほか、監査法人内の一部分(部門、従たる事務所など)又は一部の業務のみに問題がある場合については、監査法人全体に対してだけではなく、一部分又は一部の業務に対してのみ業務停止を行うことができるとしている。
問題の鍵は商法特例法~一部業務停止でも会計監査人の資格を失う
行政処分が行われた場合、大きな問題点として浮上してくるのが商法特例法上の規定だ。会計監査人の資格を規定している商法特例法(第4条②三、四)によれば、①公認会計士法によって業務停止処分を受け、その停止期間が経過していない者、②監査法人でその社員のうち、①の処分を受けている者があるものについては、会社の会計監査人になることができないとされている。また、会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計監査人が選任されない場合には、監査役会は、一時会計監査人を選任することとされている(同法第6条の4)。
このため、今回のカネボウ粉飾決算事件で逮捕された会計士が業務停止あるいは監査法人が業務停止を受けた場合には、被監査会社は、会計監査人を選任する必要がでてくるわけだ。
ケース別にこの問題点についてみてみることにしよう。ケース1として、公認会計士が業務停止処分とされた場合については(※監査法人の処分を戒告又は処分なしと仮定する)、前述の②のとおり、監査法人についても会計監査人の資格を失うことになる。
次にケース2として、監査法人に対して業務停止処分が行われた場合については、処分が一部業務停止にかかわらず、前述の①のとおり、会計監査人の資格を失うことになる。
ケース1については、公認会計士が処分の行われる前までに監査法人を辞めていれば、商法特例法上の規定に抵触しないことになる。このため、被監査会社にとって問題となるのはケース2ということになる。現行の商法特例法では、監査法人に業務停止が行われた場合には、「解散命令」と同様の効果を持つわけだ。
ただし、問題はこれだけにとどまらない。解散命令や業務停止は、監査法人にとっても、被監査会社にとっても影響が大きいものであるため、組織ぐるみで不正を行ったケースなどでなければ、処分を行うことが難しいのが現状のようだ。前述の瑞穂監査法人については、関与社員が故意により虚偽のある財務書類を虚偽のないものとしてそのまま監査法人の意見として監査証明を行ったことに対し、平成14年10月15日付けで金融庁長官から業務停止1年の懲戒処分が行われている(2名の関与社員については登録抹消)。瑞穂監査法人が行っていた証券取引法監査及び商法監査は26社であったが、実質、監査業務が行うことができなくなったため、その後、解散となっている。被監査会社についても一時会計監査人を選任している。ただ、瑞穂監査法人の場合は、法人の社員数など、技術的な問題があった模様で、特殊な事例とされている。
証取法上は可能だ
このため、行政処分としては、一部業務停止といった処分が視野に入ってくる。一部業務停止のケースでは、証券取引法上は監査業務が可能となるが、商法特例法上については、監査業務を行えないことになる。法律は別々のものであるため、このような事態が想定されるわけだが、実務上は、簡単なことではない。実際は、個々の監査契約によることになるが、通常は、証券取引法監査と商法監査を同時に行う契約となっている。このため、実質的には監査業務ができなくなるといったことに等しいものとなる。
金融庁では、現在、カネボウ事件に対する情報収集を行っている段階。中央青山監査法人の場合、平成17年6月30日現在、関与会社数は5,330社にのぼる(このうち、証取・商法監査は850社)。瑞穂監査法人の場合と比較して、仮に業務停止処分などが行われた場合の影響の大きさが予想される。このため、行政処分については、既存の被監査会社の影響も考慮しながら慎重に対応するとしている。今後の動向を見守る必要がありそうだ。
 中央青山監査法人が入る霞が関ビル
中央青山監査法人が入る霞が関ビル
会社法では問題点が解消に
現行の商法特例法上の第4条第2項第三号、第四号の規定は、従来から問題視されていた点だ。監査法人の業務が一部であっても停止された場合、監査法人のすべての業務が停止されてしまうためだ。このため、来年の5月施行予定の会社法では、現行の第4条第2項第三号、第四号の規定は削除されている。
会社法
(会計監査人の資格等)
第337条
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
業務停止処分となれば一時会計監査人の選任という事態も
カネボウの粉飾決算事件が与える影響は?
現在、金融庁では、カネボウの粉飾決算事件を受け、行政処分を検討中だ。今回の事件では、中央青山監査法人の社員が4名、証券取引法違反の容疑で東京地方検察庁により逮捕されているが、金融庁の行政処分は中央青山監査法人だけでなく、同法人を会計監査人としている会社にとっても対岸の火事とはいえない。仮に業務停止処分が公認会計士又は監査法人に対して行われた場合には、一時会計監査人を選任する事態にもなりかねないからだ。今回の特集では、カネボウの粉飾事件を巡る影響とその問題点についてお伝えする。
行政処分はどうなる?
カネボウの粉飾決算事件については、証券取引等監視委員会と東京地方検察庁特別捜査部が平成17年7月29日、証券取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、関係先に対する強制調査を実施。8月17日にはカネボウの元社長ら3名が東京地方検察庁に告発され、このうち2名が起訴されている。その後、9月13日、カネボウの監査を担当していた中央青山監査法人の公認会計士4名についても逮捕されている。刑事責任については、今後、行われるであろう裁判の推移を見守る必要があるが、一方、公認会計士法における行政処分については、被監査会社にとっても注目すべき事項といえる。
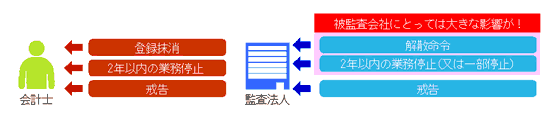
過去、業務停止は瑞穂監査法人のみ
具体的に公認会計士法による懲戒処分(公認会計士法第30条)では、重い順に①登録の抹消、②2年以内の業務停止、③戒告となる。また、監査法人に対する懲戒処分(同法第34条の21)では、①解散命令、②2年以内の業務の全部又は一部の停止、③戒告となる。
公認会計士の場合、最も重い処分が登録の抹消。この場合、公認会計士の業務を行う要件とされている公認会計士名簿の登録が抹消され、公認会計士としての身分を失うことになる。また、処分を受けた日から5年を経過しない間は、公認会計士の欠格事由(同法第4条)に該当することになり、公認会計士になることはできない。一方、監査法人については、最も重い処分が解散命令であり、次に業務停止である。過去に解散命令の処分が下された事案はなく、業務停止についても平成14年のフットワークエクスプレス株式会社の監査を行った瑞穂監査法人のみとなっている(右表参照)。
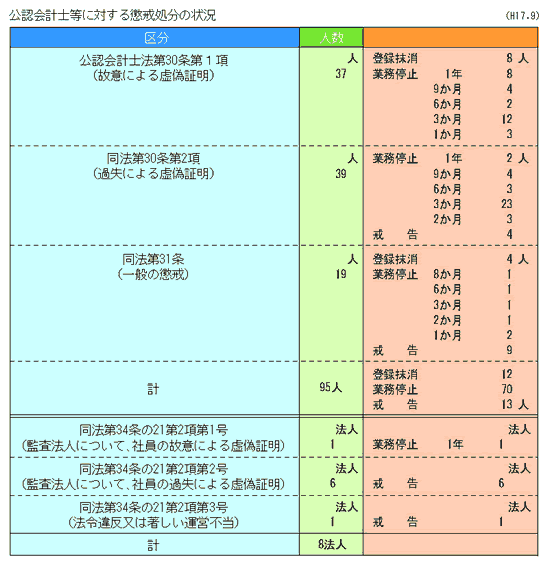
なお、金融庁では、平成16年の公認会計士法改正を受け、3月31日に「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」と題する報告書を公表している。これは、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準を明確化するもの。それによると、公認会計士による虚偽証明・不当証明について、故意の場合には、登録抹消、過失の場合には業務停止6か月が基本となる。
また、監査法人の場合には、故意の場合には業務停止3か月、過失の場合には業務停止1か月が基本となる。ただし、内部管理の態様など、個別事情等により、基本となる処分を加重又は軽減できるとしているほか、監査法人内の一部分(部門、従たる事務所など)又は一部の業務のみに問題がある場合については、監査法人全体に対してだけではなく、一部分又は一部の業務に対してのみ業務停止を行うことができるとしている。
問題の鍵は商法特例法~一部業務停止でも会計監査人の資格を失う
行政処分が行われた場合、大きな問題点として浮上してくるのが商法特例法上の規定だ。会計監査人の資格を規定している商法特例法(第4条②三、四)によれば、①公認会計士法によって業務停止処分を受け、その停止期間が経過していない者、②監査法人でその社員のうち、①の処分を受けている者があるものについては、会社の会計監査人になることができないとされている。また、会計監査人が欠けた場合、遅滞なく会計監査人が選任されない場合には、監査役会は、一時会計監査人を選任することとされている(同法第6条の4)。
このため、今回のカネボウ粉飾決算事件で逮捕された会計士が業務停止あるいは監査法人が業務停止を受けた場合には、被監査会社は、会計監査人を選任する必要がでてくるわけだ。
ケース別にこの問題点についてみてみることにしよう。ケース1として、公認会計士が業務停止処分とされた場合については(※監査法人の処分を戒告又は処分なしと仮定する)、前述の②のとおり、監査法人についても会計監査人の資格を失うことになる。
次にケース2として、監査法人に対して業務停止処分が行われた場合については、処分が一部業務停止にかかわらず、前述の①のとおり、会計監査人の資格を失うことになる。
ケース1については、公認会計士が処分の行われる前までに監査法人を辞めていれば、商法特例法上の規定に抵触しないことになる。このため、被監査会社にとって問題となるのはケース2ということになる。現行の商法特例法では、監査法人に業務停止が行われた場合には、「解散命令」と同様の効果を持つわけだ。
ただし、問題はこれだけにとどまらない。解散命令や業務停止は、監査法人にとっても、被監査会社にとっても影響が大きいものであるため、組織ぐるみで不正を行ったケースなどでなければ、処分を行うことが難しいのが現状のようだ。前述の瑞穂監査法人については、関与社員が故意により虚偽のある財務書類を虚偽のないものとしてそのまま監査法人の意見として監査証明を行ったことに対し、平成14年10月15日付けで金融庁長官から業務停止1年の懲戒処分が行われている(2名の関与社員については登録抹消)。瑞穂監査法人が行っていた証券取引法監査及び商法監査は26社であったが、実質、監査業務が行うことができなくなったため、その後、解散となっている。被監査会社についても一時会計監査人を選任している。ただ、瑞穂監査法人の場合は、法人の社員数など、技術的な問題があった模様で、特殊な事例とされている。
証取法上は可能だ
このため、行政処分としては、一部業務停止といった処分が視野に入ってくる。一部業務停止のケースでは、証券取引法上は監査業務が可能となるが、商法特例法上については、監査業務を行えないことになる。法律は別々のものであるため、このような事態が想定されるわけだが、実務上は、簡単なことではない。実際は、個々の監査契約によることになるが、通常は、証券取引法監査と商法監査を同時に行う契約となっている。このため、実質的には監査業務ができなくなるといったことに等しいものとなる。
金融庁では、現在、カネボウ事件に対する情報収集を行っている段階。中央青山監査法人の場合、平成17年6月30日現在、関与会社数は5,330社にのぼる(このうち、証取・商法監査は850社)。瑞穂監査法人の場合と比較して、仮に業務停止処分などが行われた場合の影響の大きさが予想される。このため、行政処分については、既存の被監査会社の影響も考慮しながら慎重に対応するとしている。今後の動向を見守る必要がありそうだ。
 中央青山監査法人が入る霞が関ビル
中央青山監査法人が入る霞が関ビル会社法では問題点が解消に
現行の商法特例法上の第4条第2項第三号、第四号の規定は、従来から問題視されていた点だ。監査法人の業務が一部であっても停止された場合、監査法人のすべての業務が停止されてしまうためだ。このため、来年の5月施行予定の会社法では、現行の第4条第2項第三号、第四号の規定は削除されている。
会社法
(会計監査人の資格等)
第337条
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























