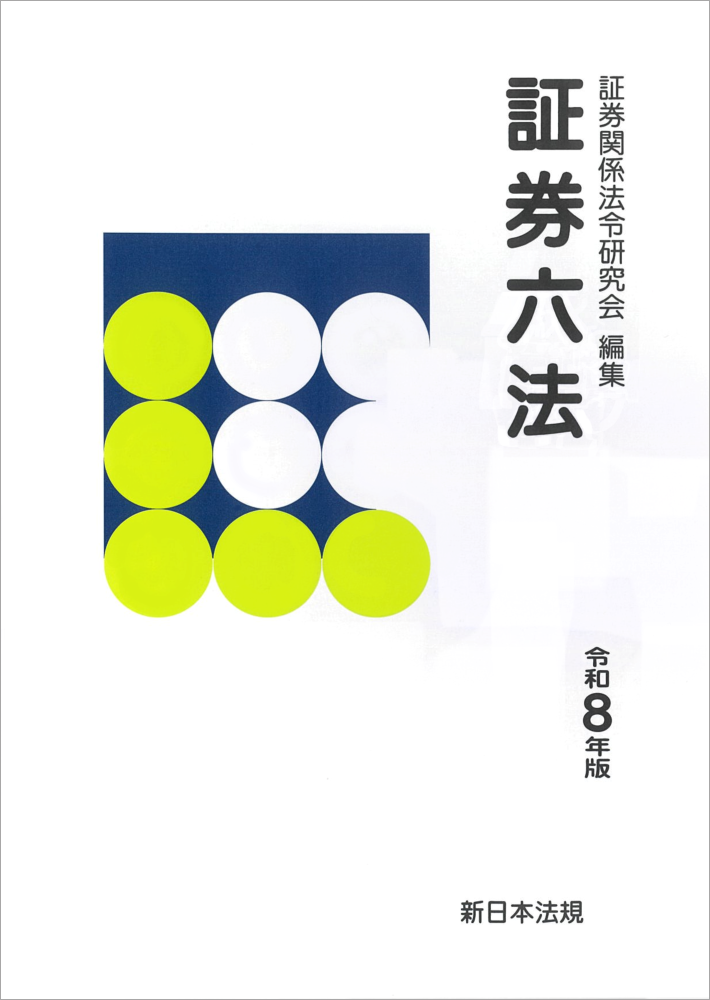解説記事2012年07月30日 【新会計基準解説】 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び同適用指針について(2012年7月30日号・№461)
新会計基準解説
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び同適用指針について
元企業会計基準委員会 研究員 熊谷 元
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成24年5月17日に企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。また本会計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本会計基準等の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 公表の経緯
平成19年8月に公表された「東京合意」(会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意)を背景に、ASBJでは、退職給付について、国際的な会計基準における見直しの議論と歩調を合わせて中長期的に取り組むこととし、平成21年1月に「退職給付会計の見直しに関する論点の整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。そして、論点整理に寄せられたコメントを分析し検討を重ねた結果、退職給付に関する会計基準等の見直しを2つのステップに分け、ステップ1においては、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、主に次を取り扱うこととした。
(1)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し
(2)退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し
(3)開示の拡充
このステップ1の成果として、平成22年3月に公開草案を公表し、広く意見を求めたところ、寄せられたコメントの中には、退職給付会計の改正は関連諸制度との調整が必要となること等を踏まえて、個別財務諸表への適用は慎重に検討すべきという意見があった。こうした中、個別財務諸表のコンバージェンスを当面どのように取り扱うべきかについて意見を聴取するために、公益財団法人財務会計基準機構(FASF)内において平成22年9月に「単体財務諸表に関する検討会議」(以下「単体検討会議」という。)が設置され、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の負債計上に係る個別財務諸表の取扱いが当該会議における論点の1つとして取り上げられて議論された。単体検討会議の報告書は平成23年4月に公表され、ASBJでは当該会議の報告書で示された方向性の考え方を十分斟酌しつつ、その後も時間をかけて慎重に検討を重ねた。本会計基準等は、このような経緯を経て、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。
なお、本会計基準等は、次の会計基準等(以下「改正前会計基準等」という。)を集約・承継しつつ、いくつかの項目について改正を行ったものである。また後述するいくつかの改正に合わせて、表現の明確化や、重複する内容については削除するなどの整理を行っている。
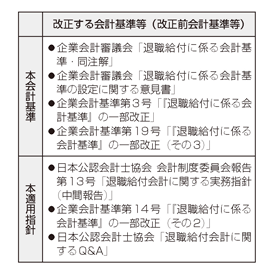
Ⅲ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し
1 連結貸借対照表上での取扱い 改正前会計基準等は、数理計算上の差異及び過去勤務費用(脚注2)を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理することとし、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用(数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち費用処理されていない部分。以下「未認識項目」という。)については連結貸借対照表に計上せず、これに対応する部分を除いた、退職給付債務と年金資産の差額(以下「積立状況を示す額」という。)を負債(又は資産)として計上することとしていた。
しかし、このように一部が除かれた積立状況を示す額を連結貸借対照表に計上する場合、積立超過のときに負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、退職給付制度に係る状況について財務諸表利用者の理解を妨げているのではないかという指摘があった(会計基準第55項)。
本会計基準等ではこうした指摘に対応するため、国際的な会計基準(同様の観点からすでに見直しが行われている。)も参考にしつつ検討を行った結果、連結貸借対照表上は、積立状況を示す額をそのまま負債(又は資産)として計上することとしている(会計基準第13項、第24項また書き及び第25項また書き)(図表1参照)。これによって、財務諸表利用者の理解可能性を高め、透明性の向上による財務報告の改善を図ることになるとしている(会計基準第49項)。
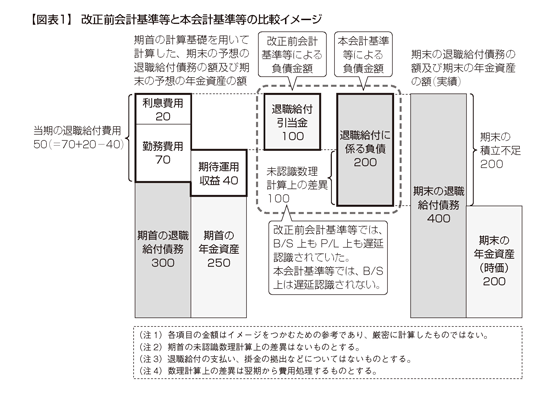
2 連結損益計算書及び連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上での取扱い 本会計基準等は、改正前会計基準等から数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法を変更しておらず、従来どおり平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理することとしている(脚注3)。したがって、数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分(未認識項目)については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、税効果を調整の上、その他の包括利益に含めて計上し、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行うこととしている(会計基準第15項)。
3 個別財務諸表における当面の取扱い 公開草案では、連結財務諸表と同様に、個別財務諸表についても、前掲1や2で示した未認識項目の処理方法を提案していたが、本会計基準等を個別財務諸表へ適用することについて慎重に検討すべきという、公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、その後、重要な論点として審議された。本論点は単体検討会議においても議論され、当該会議の報告書では、年金法制との関係の観点や分配可能額に影響を与える可能性等を踏まえ、慎重に対処し連結先行も含め何らかの激変を緩和する措置を講ずる必要があるという方向性の考え方が示された。
ASBJの審議の過程では、年金法制による規制の結果、事業再編時に合理的な方法によって資産の移換や債務の引継ぎが困難な状況が存在し、また、受給者分は事実上移換できないため、親会社の債務として扱った上で子会社の剰余金で補われる場合もあり、個別財務諸表に未認識項目を負債として認識すると、事業再編後の経営実態を必ずしも適切に表していないとの意見や、未認識項目の負債計上は会社法上の分配可能額に影響が及ぶ可能性が懸念されるという意見があった。一方、年金法制による影響の程度が明確でなく、影響範囲は負担する債務の一部に限定されるのではないかという意見や、会社法上の分配可能額は、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成された計算書類を基礎として、必要な調整を加えて計算されることとされているため、上記の懸念は会計基準の策定にあたり一義的に問題とすべきものではないという意見もあった。
ASBJでは、このように市場関係者の合意形成が十分に図られていない状況を踏まえ、今後議論を継続することとし、現時点における対応としては、未認識項目の負債計上に係る個別財務諸表の取扱いについては、当面の間、改正前会計基準(平成10年会計基準)の取扱いを継続することとしている(会計基準第39項(1)(2)及び第86項から第88項)。なお、連結財務諸表に関する変更に伴い、連結財務諸表を作成する会社については、個別財務諸表において未認識項目の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨の注記を求めることとしている(会計基準第39項(4))。
4 具体的な会計処理及び表示の方法
(1)会計処理方法 本会計基準等では、未認識項目について、次のように会計処理することとしている(適用指針第33項)。また本適用指針の[設例4-2]及び[設例5-2]も併せて参照されたい。
① 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、退職給付費用として、当期純利益を構成する項目に含めて計上する(連結財務諸表及び個別財務諸表とも共通)。
② 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理されない部分(未認識項目となる。)については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、税効果を調整の上、その他の包括利益で認識し、連結貸借対照表上、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上する。
③ 連結貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、当期に費用処理された部分について、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
従来の会計処理と比較して示したイメージが図表2であり、次の点がポイントになると考えられる。
・上記②に従い、本会計基準等によるX1年度末は、積立状況を示す額(200)が「退職給付に係る負債」となり、未認識数理計算上の差異(100)はその他の包括利益で認識され、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上される。
・本会計基準等によるX2年度及びX3年度の退職給付費用(50)及び当期純利益(△50)は、従来の会計処理と同じ結果になる。
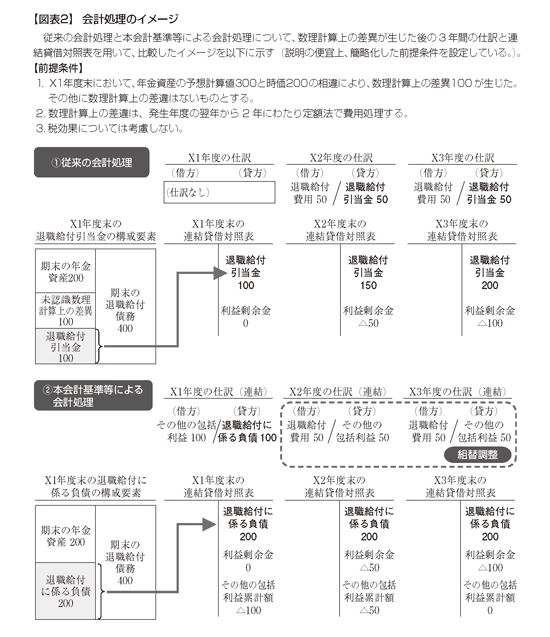
(2)表示方法 本会計基準等では、連結貸借対照表上、積立状況を示す額について、負債となる場合は「退職給付に係る負債」等の適当な科目をもって固定負債に計上し、資産となる場合は「退職給付に係る資産」等の適当な科目をもって固定資産に計上することとしている(会計基準第27項)。
改正前会計基準等では、将来の退職給付のうち当期の負担に属する額を当期の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を負債計上額としていたが、本会計基準等では、その他の包括利益を通じて認識される、未認識項目に対応する額も負債計上額に加える方法に変更したことに伴い、従来の「退職給付引当金」及び「前払年金費用」という名称を、それぞれ「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る資産」に変更している(会計基準第74項)。なお、個別財務諸表においては、当面の間、この取扱いを適用せず、従来の名称を使用することに留意が必要である(会計基準第39項(3))。
また、本会計基準等では、未認識項目について、連結貸借対照表上は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額に「退職給付に係る調整累計額」等の適当な科目をもって計上することとしている(会計基準第27項)。また、当期に発生した未認識項目並びに当期に費用処理された組替調整額については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の適当な科目をもって、一括して計上することとしている(会計基準第29項)。
(3)税効果会計の影響 税効果会計を考慮し、図表2について仕訳を用いて説明すると次のようになる(前提条件として、法定実効税率は40%であり、繰延税金資産の回収可能性に問題はないものとする。)。
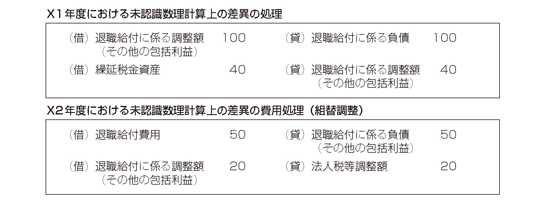 (4)適用初年度の会計処理
本会計基準等に従い、従来は連結貸借対照表で認識されていなかった未認識項目及び会計基準変更時差異の未処理額が、連結貸借対照表の純資産の部におけるその他の包括利益累計額に計上されることとなるが、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、適用初年度においては、その他の包括利益を通じることなく、その他の包括利益累計額に直接計上することとしている(会計基準第37項)。本適用指針の[設例3]に具体例があるので、当該設例も参照されたい。
(4)適用初年度の会計処理
本会計基準等に従い、従来は連結貸借対照表で認識されていなかった未認識項目及び会計基準変更時差異の未処理額が、連結貸借対照表の純資産の部におけるその他の包括利益累計額に計上されることとなるが、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、適用初年度においては、その他の包括利益を通じることなく、その他の包括利益累計額に直接計上することとしている(会計基準第37項)。本適用指針の[設例3]に具体例があるので、当該設例も参照されたい。
なお、この際に退職給付に係る負債(又は資産)の金額が変動する結果、新たに繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されることがあるが、適用時点における繰延税金資産の回収可能性を判断した上で、これに伴う税効果の影響額についても、その他の包括利益累計額に直接加減する必要がある(適用指針第69項及び第128項)。
Ⅳ 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し
1 退職給付見込額の期間帰属方法の見直し 改正前会計基準等は、退職給付見込額の期間帰属方法として期間定額基準を原則的な方法とし、支給倍率基準、ポイント基準及び給与基準については、一定の場合に当該方法の採用を容認していた(図表3参照)。
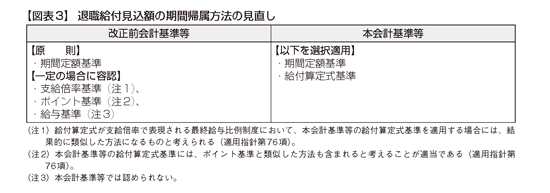
本会計基準等では、退職給付見込額(退職により見込まれる退職給付の総額)のうち期末までに発生したと認められる額は、次の①又は②のいずれかの方法を選択適用して計算することとしている(会計基準第19項)。この場合、いったん採用した方法は、原則として、継続して適用しなければならない。
②の給付算定式基準の具体的な考え方は、本適用指針の[設例2]に示されているので、当該設例も参照されたい。
本会計基準等において給付算定式基準を導入した理由としては、給付算定式基準だけを認める国際的な会計基準とのコンバージェンスを進めることが挙げられるが、国際的な会計基準において認められていない期間定額基準についても選択適用として存続させた理由は、次のようなものである(会計基準第60項から第63項)。
・我が国の退職給付会計では退職給付見込額の期間帰属方法を費用配分の方法として捉えており、直接観察できない労働サービスの費消態様に合理的な仮定を置かざるを得ないことを踏まえれば、労働サービスに係る費用配分の方法は一義的に決まらず、勤務期間を基礎とする費用配分の方法(期間定額基準)についても、これを否定する根拠は乏しい。
・給付算定式基準では、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となる場合(給付算定式に従う給付が著しく後加重である場合)、その部分について均等に生じるものとみなして補正すべきとされているが、これは、勤務期間を基礎とする配分に一定の合理性を認めていることを示唆している。
・期間定額基準は適用の明確さでより優れていると考えられる。
2 割引率の見直し 改正前会計基準等は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、退職給付の見込支払日までの平均期間を原則とするが、実務上は従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とすることができるとされていた。
本会計基準等では、時期や金額が異なる支払から構成される退職給付債務をより適切に割り引くべきと考えたことや、国際的な会計基準における考え方との整合性を図るために、割引率は退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するものでなければならないとしている。当該割引率としては、例えば、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれるとしている(適用指針第24項及び第93項)。
3 予想昇給率の見直し 改正前会計基準等は、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「確実に見込まれる」昇給等が含まれるものとされていた。
本会計基準等では、退職給付債務及び勤務費用の計算基礎の1つである予想昇給率について、確実なものだけを考慮する場合、割引率等の他の計算基礎との整合性を欠く結果になると考えられることや、国際的な会計基準では確実性までは求められていないことを勘案し、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「予想される」昇給等が含まれるものとしている(会計基準(注5)及び第57項)。
4 適用初年度の取扱い 本会計基準等を適用するにあたり、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、前掲1から3の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、期首の利益剰余金に加減する(数理計算上の差異には加減しない。)こととしている(会計基準第37項)。
なお、前掲1の期間帰属方法の選択は会計方針の変更であるため、その変更には正当な理由が必要であり、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第6項(2)の定めに従って遡及適用することになるが、本会計基準等の退職給付債務及び勤務費用の定め(会計基準第16項から第21項)の適用初年度に限っては、その適用前に期間定額基準を採用していた場合であっても、適用初年度の期首において、給付算定式基準を選択することができる(この場合、遡及適用は不要)こととしている(会計基準第38項及び第82項)。
Ⅴ 開示の拡充
本会計基準等では、財務諸表の有用性をさらに高めるよう、その拡充を求める意見が論点整理に対して多く寄せられたことや、より多くの項目を注記している国際的な会計基準とのコンバージェンスを進める観点から、国際的な会計基準で採用されているものを中心に開示項目を拡充している。具体的には、図表4を注記することとしている(会計基準第30項及び第77項並びに適用指針第52項から第60項)(脚注4)。本適用指針に参考として付した[開示例1]も参照されたい。
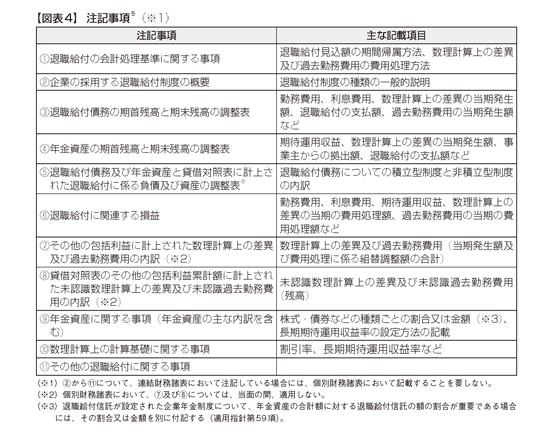
なお、適用初年度において、本会計基準等により求められる新たな注記事項について、遡及処理は行われず、過去の期間に対する財務諸表の組替えを行わない(会計基準第84項)。
Ⅵ その他の改正事項
1 複数事業主制度の会計処理 複数事業主制度のうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないケースでは、要拠出額をもって費用処理されるが、改正前会計基準等は、複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合について、このケースにあたらないものとみなしていた。本会計基準等では、一律にあたらないものとはみなさず、制度の内容を勘案して判断することとしている(適用指針第64項及び第121項)。
2 過去勤務費用の表示 新たに退職給付制度を採用したとき又は給付水準の重要な改訂を行ったときに発生する過去勤務費用について、改正前会計基準等は、これに係る当期の費用処理額が重要である場合、当該費用処理額を特別損失として計上することを認めていたが、本会計基準等では、その発生時に全額費用処理する場合などにおいて、その金額が重要であると認められるときには、当該金額を特別損益として計上できることとしている(会計基準第28項及び第75項)。
3 長期期待運用収益率の明確化 長期期待運用収益率の設定の際に考慮すべき事項は、改正前会計基準等における取扱いを引き継いでいるが、長期期待運用収益率の算定は、退職給付の支払に充てられるまでの期間等を考慮して設定することを明らかにしている(これに伴い、名称を「長期」期待運用収益率としている(会計基準第23項)。)。
なお、これは従来の考え方を改めるものではなく、取扱いの明確化にすぎないため、会計方針の変更には該当しないこととしている(適用指針第25項及び第98項)。
Ⅶ 適用時期
本会計基準等の適用時期は図表5のとおりである(会計基準第34項から第38項)。
図表5の②の変更には、新たな年金数理計算のために一定の準備期間を要するという意見があったことから適用時期を分け、関連する定めについては適用時期を遅らせることとしている(脚注7)(会計基準第80項)。
また、②の変更について、公開草案後の審議の過程では、数理計算の準備状況(適用上の判断に係る準備も含む。)等から平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用が困難となる場合も懸念されるという意見があったことを踏まえ、当該年度の期首から適用することが実務上困難な場合(脚注8)には、所定の注記を行うことを条件に、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用も認めることとしている(会計基準第85項)。
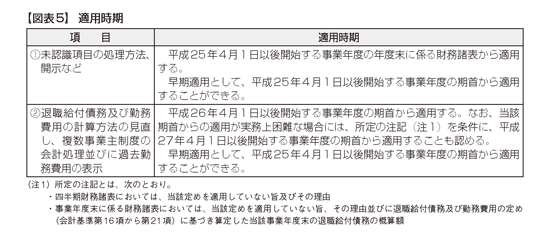
脚注
1 本会計基準等の全文については、ASBJのウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu-4/)を参照のこと。
2 改正前会計基準等における「過去勤務債務」を、本会計基準等では「過去勤務費用」という名称に改めているが、これは、年金財政計算上の「過去勤務債務」とは異なることを明瞭にするためであり、その内容の変更を意図したものではない(会計基準第52項)。
3 会計基準変更時差異の未処理額についても、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用と同様に、税効果調整後の残高を純資産の部に計上した上で、費用処理を継続することとしている(適用指針第130項)。
4 公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、本会計基準等では、公開草案で提案されていた開示項目の一部が修正されている。
5 簡便法を適用した退職給付制度がある場合には、別途の開示が求められ、会計基準第30項及び適用指針第52項から第60項の注記を要しないとされている(適用指針第62項)。ただし、連結財務諸表を作成している会社において、簡便法により会計処理している連結会社(親会社及び連結子会社)について、連結財務諸表における重要性が乏しい場合には、原則法による注記事項(適用指針第52項から第60項)に含めて開示することができるものと考えられる(適用指針第117項)。
6 注記事項は個別財務諸表にも適用される(会計基準第30項)。このため、連結財務諸表を作成していない会社においては、「退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表」で、これまでと同様に、貸借対照表に計上されない未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の期末残高が注記されることになるものと考えられる。
7 本会計基準等は適用時期が分かれているため、開示の実務において留意が必要となる場合がある。例えば、図表5の①が強制適用される年度末の財務諸表において、②を早期適用していないときは、未適用の会計基準等に関する注記(会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第12項)について、②に関連する定めが未適用であるため所定の記載が必要になるものと考えられる。
8 実務上困難な場合には、例えば、当該期首からの適用において、退職給付見込額の期間帰属方法として期間定額基準と給付算定式基準のいずれかの選択を判断するにあたり、必要な情報の整備等が完了していないケースや、選択のための中長期的な視点からの検討が整わず時間をさらに要するケースなども含まれるものと考えられる。
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び同適用指針について
元企業会計基準委員会 研究員 熊谷 元
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成24年5月17日に企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。また本会計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本会計基準等の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 公表の経緯
平成19年8月に公表された「東京合意」(会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意)を背景に、ASBJでは、退職給付について、国際的な会計基準における見直しの議論と歩調を合わせて中長期的に取り組むこととし、平成21年1月に「退職給付会計の見直しに関する論点の整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。そして、論点整理に寄せられたコメントを分析し検討を重ねた結果、退職給付に関する会計基準等の見直しを2つのステップに分け、ステップ1においては、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、主に次を取り扱うこととした。
(1)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し
(2)退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し
(3)開示の拡充
このステップ1の成果として、平成22年3月に公開草案を公表し、広く意見を求めたところ、寄せられたコメントの中には、退職給付会計の改正は関連諸制度との調整が必要となること等を踏まえて、個別財務諸表への適用は慎重に検討すべきという意見があった。こうした中、個別財務諸表のコンバージェンスを当面どのように取り扱うべきかについて意見を聴取するために、公益財団法人財務会計基準機構(FASF)内において平成22年9月に「単体財務諸表に関する検討会議」(以下「単体検討会議」という。)が設置され、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の負債計上に係る個別財務諸表の取扱いが当該会議における論点の1つとして取り上げられて議論された。単体検討会議の報告書は平成23年4月に公表され、ASBJでは当該会議の報告書で示された方向性の考え方を十分斟酌しつつ、その後も時間をかけて慎重に検討を重ねた。本会計基準等は、このような経緯を経て、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。
なお、本会計基準等は、次の会計基準等(以下「改正前会計基準等」という。)を集約・承継しつつ、いくつかの項目について改正を行ったものである。また後述するいくつかの改正に合わせて、表現の明確化や、重複する内容については削除するなどの整理を行っている。
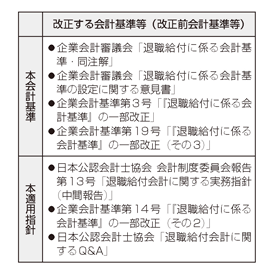
Ⅲ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し
1 連結貸借対照表上での取扱い 改正前会計基準等は、数理計算上の差異及び過去勤務費用(脚注2)を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理することとし、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用(数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち費用処理されていない部分。以下「未認識項目」という。)については連結貸借対照表に計上せず、これに対応する部分を除いた、退職給付債務と年金資産の差額(以下「積立状況を示す額」という。)を負債(又は資産)として計上することとしていた。
しかし、このように一部が除かれた積立状況を示す額を連結貸借対照表に計上する場合、積立超過のときに負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、退職給付制度に係る状況について財務諸表利用者の理解を妨げているのではないかという指摘があった(会計基準第55項)。
本会計基準等ではこうした指摘に対応するため、国際的な会計基準(同様の観点からすでに見直しが行われている。)も参考にしつつ検討を行った結果、連結貸借対照表上は、積立状況を示す額をそのまま負債(又は資産)として計上することとしている(会計基準第13項、第24項また書き及び第25項また書き)(図表1参照)。これによって、財務諸表利用者の理解可能性を高め、透明性の向上による財務報告の改善を図ることになるとしている(会計基準第49項)。
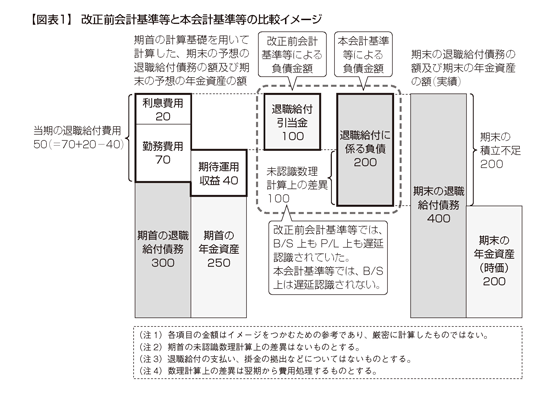
2 連結損益計算書及び連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上での取扱い 本会計基準等は、改正前会計基準等から数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法を変更しておらず、従来どおり平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理することとしている(脚注3)。したがって、数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分(未認識項目)については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、税効果を調整の上、その他の包括利益に含めて計上し、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行うこととしている(会計基準第15項)。
3 個別財務諸表における当面の取扱い 公開草案では、連結財務諸表と同様に、個別財務諸表についても、前掲1や2で示した未認識項目の処理方法を提案していたが、本会計基準等を個別財務諸表へ適用することについて慎重に検討すべきという、公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、その後、重要な論点として審議された。本論点は単体検討会議においても議論され、当該会議の報告書では、年金法制との関係の観点や分配可能額に影響を与える可能性等を踏まえ、慎重に対処し連結先行も含め何らかの激変を緩和する措置を講ずる必要があるという方向性の考え方が示された。
ASBJの審議の過程では、年金法制による規制の結果、事業再編時に合理的な方法によって資産の移換や債務の引継ぎが困難な状況が存在し、また、受給者分は事実上移換できないため、親会社の債務として扱った上で子会社の剰余金で補われる場合もあり、個別財務諸表に未認識項目を負債として認識すると、事業再編後の経営実態を必ずしも適切に表していないとの意見や、未認識項目の負債計上は会社法上の分配可能額に影響が及ぶ可能性が懸念されるという意見があった。一方、年金法制による影響の程度が明確でなく、影響範囲は負担する債務の一部に限定されるのではないかという意見や、会社法上の分配可能額は、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成された計算書類を基礎として、必要な調整を加えて計算されることとされているため、上記の懸念は会計基準の策定にあたり一義的に問題とすべきものではないという意見もあった。
ASBJでは、このように市場関係者の合意形成が十分に図られていない状況を踏まえ、今後議論を継続することとし、現時点における対応としては、未認識項目の負債計上に係る個別財務諸表の取扱いについては、当面の間、改正前会計基準(平成10年会計基準)の取扱いを継続することとしている(会計基準第39項(1)(2)及び第86項から第88項)。なお、連結財務諸表に関する変更に伴い、連結財務諸表を作成する会社については、個別財務諸表において未認識項目の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なる旨の注記を求めることとしている(会計基準第39項(4))。
4 具体的な会計処理及び表示の方法
(1)会計処理方法 本会計基準等では、未認識項目について、次のように会計処理することとしている(適用指針第33項)。また本適用指針の[設例4-2]及び[設例5-2]も併せて参照されたい。
① 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、退職給付費用として、当期純利益を構成する項目に含めて計上する(連結財務諸表及び個別財務諸表とも共通)。
② 当期に発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち、当期に費用処理されない部分(未認識項目となる。)については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、税効果を調整の上、その他の包括利益で認識し、連結貸借対照表上、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上する。
③ 連結貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上されている未認識項目のうち、当期に費用処理された部分について、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
従来の会計処理と比較して示したイメージが図表2であり、次の点がポイントになると考えられる。
・上記②に従い、本会計基準等によるX1年度末は、積立状況を示す額(200)が「退職給付に係る負債」となり、未認識数理計算上の差異(100)はその他の包括利益で認識され、純資産の部のその他の包括利益累計額に計上される。
・本会計基準等によるX2年度及びX3年度の退職給付費用(50)及び当期純利益(△50)は、従来の会計処理と同じ結果になる。
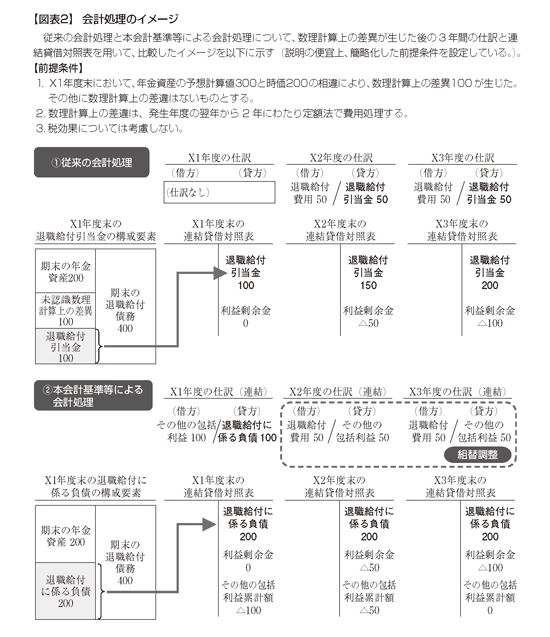
(2)表示方法 本会計基準等では、連結貸借対照表上、積立状況を示す額について、負債となる場合は「退職給付に係る負債」等の適当な科目をもって固定負債に計上し、資産となる場合は「退職給付に係る資産」等の適当な科目をもって固定資産に計上することとしている(会計基準第27項)。
改正前会計基準等では、将来の退職給付のうち当期の負担に属する額を当期の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を負債計上額としていたが、本会計基準等では、その他の包括利益を通じて認識される、未認識項目に対応する額も負債計上額に加える方法に変更したことに伴い、従来の「退職給付引当金」及び「前払年金費用」という名称を、それぞれ「退職給付に係る負債」及び「退職給付に係る資産」に変更している(会計基準第74項)。なお、個別財務諸表においては、当面の間、この取扱いを適用せず、従来の名称を使用することに留意が必要である(会計基準第39項(3))。
また、本会計基準等では、未認識項目について、連結貸借対照表上は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額に「退職給付に係る調整累計額」等の適当な科目をもって計上することとしている(会計基準第27項)。また、当期に発生した未認識項目並びに当期に費用処理された組替調整額については、連結包括利益計算書(又は連結損益及び包括利益計算書)上、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の適当な科目をもって、一括して計上することとしている(会計基準第29項)。
(3)税効果会計の影響 税効果会計を考慮し、図表2について仕訳を用いて説明すると次のようになる(前提条件として、法定実効税率は40%であり、繰延税金資産の回収可能性に問題はないものとする。)。
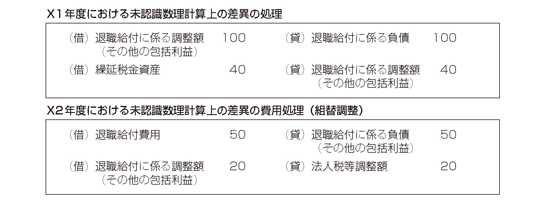 (4)適用初年度の会計処理
本会計基準等に従い、従来は連結貸借対照表で認識されていなかった未認識項目及び会計基準変更時差異の未処理額が、連結貸借対照表の純資産の部におけるその他の包括利益累計額に計上されることとなるが、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、適用初年度においては、その他の包括利益を通じることなく、その他の包括利益累計額に直接計上することとしている(会計基準第37項)。本適用指針の[設例3]に具体例があるので、当該設例も参照されたい。
(4)適用初年度の会計処理
本会計基準等に従い、従来は連結貸借対照表で認識されていなかった未認識項目及び会計基準変更時差異の未処理額が、連結貸借対照表の純資産の部におけるその他の包括利益累計額に計上されることとなるが、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、適用初年度においては、その他の包括利益を通じることなく、その他の包括利益累計額に直接計上することとしている(会計基準第37項)。本適用指針の[設例3]に具体例があるので、当該設例も参照されたい。なお、この際に退職給付に係る負債(又は資産)の金額が変動する結果、新たに繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されることがあるが、適用時点における繰延税金資産の回収可能性を判断した上で、これに伴う税効果の影響額についても、その他の包括利益累計額に直接加減する必要がある(適用指針第69項及び第128項)。
Ⅳ 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し
1 退職給付見込額の期間帰属方法の見直し 改正前会計基準等は、退職給付見込額の期間帰属方法として期間定額基準を原則的な方法とし、支給倍率基準、ポイント基準及び給与基準については、一定の場合に当該方法の採用を容認していた(図表3参照)。
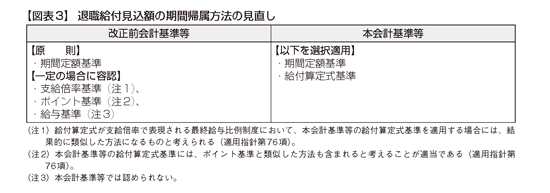
本会計基準等では、退職給付見込額(退職により見込まれる退職給付の総額)のうち期末までに発生したと認められる額は、次の①又は②のいずれかの方法を選択適用して計算することとしている(会計基準第19項)。この場合、いったん採用した方法は、原則として、継続して適用しなければならない。
| ① 期間定額基準(退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法) ② 給付算定式基準(退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法) なお、②の方法による場合、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となるとき(著しく後加重)には、当該期間の給付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない。 |
本会計基準等において給付算定式基準を導入した理由としては、給付算定式基準だけを認める国際的な会計基準とのコンバージェンスを進めることが挙げられるが、国際的な会計基準において認められていない期間定額基準についても選択適用として存続させた理由は、次のようなものである(会計基準第60項から第63項)。
・我が国の退職給付会計では退職給付見込額の期間帰属方法を費用配分の方法として捉えており、直接観察できない労働サービスの費消態様に合理的な仮定を置かざるを得ないことを踏まえれば、労働サービスに係る費用配分の方法は一義的に決まらず、勤務期間を基礎とする費用配分の方法(期間定額基準)についても、これを否定する根拠は乏しい。
・給付算定式基準では、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となる場合(給付算定式に従う給付が著しく後加重である場合)、その部分について均等に生じるものとみなして補正すべきとされているが、これは、勤務期間を基礎とする配分に一定の合理性を認めていることを示唆している。
・期間定額基準は適用の明確さでより優れていると考えられる。
2 割引率の見直し 改正前会計基準等は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、退職給付の見込支払日までの平均期間を原則とするが、実務上は従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とすることができるとされていた。
本会計基準等では、時期や金額が異なる支払から構成される退職給付債務をより適切に割り引くべきと考えたことや、国際的な会計基準における考え方との整合性を図るために、割引率は退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するものでなければならないとしている。当該割引率としては、例えば、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれるとしている(適用指針第24項及び第93項)。
3 予想昇給率の見直し 改正前会計基準等は、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「確実に見込まれる」昇給等が含まれるものとされていた。
本会計基準等では、退職給付債務及び勤務費用の計算基礎の1つである予想昇給率について、確実なものだけを考慮する場合、割引率等の他の計算基礎との整合性を欠く結果になると考えられることや、国際的な会計基準では確実性までは求められていないことを勘案し、退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「予想される」昇給等が含まれるものとしている(会計基準(注5)及び第57項)。
4 適用初年度の取扱い 本会計基準等を適用するにあたり、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しないこととし、前掲1から3の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、期首の利益剰余金に加減する(数理計算上の差異には加減しない。)こととしている(会計基準第37項)。
なお、前掲1の期間帰属方法の選択は会計方針の変更であるため、その変更には正当な理由が必要であり、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第6項(2)の定めに従って遡及適用することになるが、本会計基準等の退職給付債務及び勤務費用の定め(会計基準第16項から第21項)の適用初年度に限っては、その適用前に期間定額基準を採用していた場合であっても、適用初年度の期首において、給付算定式基準を選択することができる(この場合、遡及適用は不要)こととしている(会計基準第38項及び第82項)。
Ⅴ 開示の拡充
本会計基準等では、財務諸表の有用性をさらに高めるよう、その拡充を求める意見が論点整理に対して多く寄せられたことや、より多くの項目を注記している国際的な会計基準とのコンバージェンスを進める観点から、国際的な会計基準で採用されているものを中心に開示項目を拡充している。具体的には、図表4を注記することとしている(会計基準第30項及び第77項並びに適用指針第52項から第60項)(脚注4)。本適用指針に参考として付した[開示例1]も参照されたい。
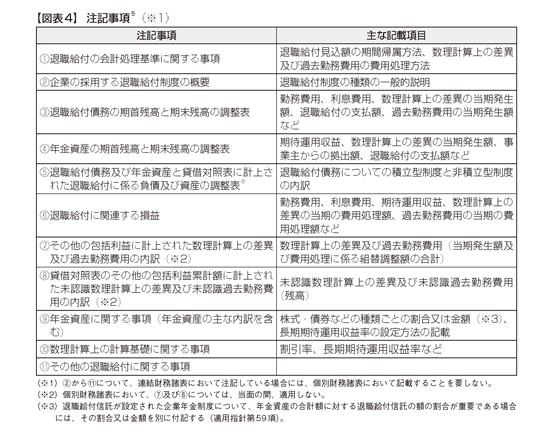
なお、適用初年度において、本会計基準等により求められる新たな注記事項について、遡及処理は行われず、過去の期間に対する財務諸表の組替えを行わない(会計基準第84項)。
Ⅵ その他の改正事項
1 複数事業主制度の会計処理 複数事業主制度のうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないケースでは、要拠出額をもって費用処理されるが、改正前会計基準等は、複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合について、このケースにあたらないものとみなしていた。本会計基準等では、一律にあたらないものとはみなさず、制度の内容を勘案して判断することとしている(適用指針第64項及び第121項)。
2 過去勤務費用の表示 新たに退職給付制度を採用したとき又は給付水準の重要な改訂を行ったときに発生する過去勤務費用について、改正前会計基準等は、これに係る当期の費用処理額が重要である場合、当該費用処理額を特別損失として計上することを認めていたが、本会計基準等では、その発生時に全額費用処理する場合などにおいて、その金額が重要であると認められるときには、当該金額を特別損益として計上できることとしている(会計基準第28項及び第75項)。
3 長期期待運用収益率の明確化 長期期待運用収益率の設定の際に考慮すべき事項は、改正前会計基準等における取扱いを引き継いでいるが、長期期待運用収益率の算定は、退職給付の支払に充てられるまでの期間等を考慮して設定することを明らかにしている(これに伴い、名称を「長期」期待運用収益率としている(会計基準第23項)。)。
なお、これは従来の考え方を改めるものではなく、取扱いの明確化にすぎないため、会計方針の変更には該当しないこととしている(適用指針第25項及び第98項)。
Ⅶ 適用時期
本会計基準等の適用時期は図表5のとおりである(会計基準第34項から第38項)。
図表5の②の変更には、新たな年金数理計算のために一定の準備期間を要するという意見があったことから適用時期を分け、関連する定めについては適用時期を遅らせることとしている(脚注7)(会計基準第80項)。
また、②の変更について、公開草案後の審議の過程では、数理計算の準備状況(適用上の判断に係る準備も含む。)等から平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用が困難となる場合も懸念されるという意見があったことを踏まえ、当該年度の期首から適用することが実務上困難な場合(脚注8)には、所定の注記を行うことを条件に、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用も認めることとしている(会計基準第85項)。
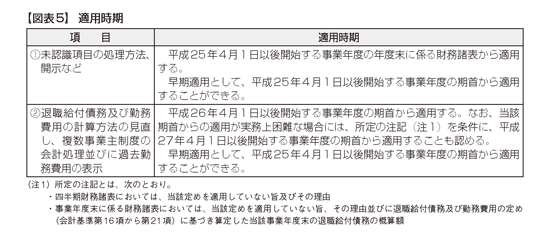
脚注
1 本会計基準等の全文については、ASBJのウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu-4/)を参照のこと。
2 改正前会計基準等における「過去勤務債務」を、本会計基準等では「過去勤務費用」という名称に改めているが、これは、年金財政計算上の「過去勤務債務」とは異なることを明瞭にするためであり、その内容の変更を意図したものではない(会計基準第52項)。
3 会計基準変更時差異の未処理額についても、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用と同様に、税効果調整後の残高を純資産の部に計上した上で、費用処理を継続することとしている(適用指針第130項)。
4 公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、本会計基準等では、公開草案で提案されていた開示項目の一部が修正されている。
5 簡便法を適用した退職給付制度がある場合には、別途の開示が求められ、会計基準第30項及び適用指針第52項から第60項の注記を要しないとされている(適用指針第62項)。ただし、連結財務諸表を作成している会社において、簡便法により会計処理している連結会社(親会社及び連結子会社)について、連結財務諸表における重要性が乏しい場合には、原則法による注記事項(適用指針第52項から第60項)に含めて開示することができるものと考えられる(適用指針第117項)。
6 注記事項は個別財務諸表にも適用される(会計基準第30項)。このため、連結財務諸表を作成していない会社においては、「退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表」で、これまでと同様に、貸借対照表に計上されない未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の期末残高が注記されることになるものと考えられる。
7 本会計基準等は適用時期が分かれているため、開示の実務において留意が必要となる場合がある。例えば、図表5の①が強制適用される年度末の財務諸表において、②を早期適用していないときは、未適用の会計基準等に関する注記(会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第12項)について、②に関連する定めが未適用であるため所定の記載が必要になるものと考えられる。
8 実務上困難な場合には、例えば、当該期首からの適用において、退職給付見込額の期間帰属方法として期間定額基準と給付算定式基準のいずれかの選択を判断するにあたり、必要な情報の整備等が完了していないケースや、選択のための中長期的な視点からの検討が整わず時間をさらに要するケースなども含まれるものと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -