解説記事2021年12月13日 未公開判決事例紹介 総会決議取消し判決前なら株主を前提に訴えの提起可(2021年12月13日号・№910)
未公開判決事例紹介
総会決議取消し判決前なら株主を前提に訴えの提起可
東京地裁、会社が元株主に損害賠償請求も棄却
本誌890号40頁で紹介した損害賠償請求事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する。
○株主の地位を失ったにも関わらず16件の計算書類閲覧謄写請求事件などを提起したとして、会社(原告)が元株主(被告)に対して弁護士費用等の支払いを求めた損害賠償請求事件。東京地裁(鈴木昭洋裁判長)は令和3年2月24日、会社の請求をすべて棄却する判決を下した(平成29年(ワ)第41630号)。東京地裁は、16件の被告の訴えの提起等は株主総会決議の不存在確認等を求める被告の訴えを棄却する判決がすべて確定した前であると指摘。被告が原告の株主であることを前提に訴えを提起等しても、法律的根拠を欠くものと評価できないとした。
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、1994万5588円及びこれに対する平成29年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が被告に対し、被告が原告の株主の地位を喪失したことを知りながら原告に対し別紙事件一覧表記載の訴えの提起、会社非訟事件及び仮処分の申立てを行い、さらにこれらの事件の手続遂行や不服申立てをしたこと(以下「本件訴え提起等」という。)により損害を被ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、応訴のために要した弁護士費用1834万5588円及び慰謝料160万円の合計1994万5588円並びにこれに対する平成29年9月20日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲証拠等により容易に認められる。)
(1)当事者
ア 原告は、電子機器・部品その他の物品の販売等を目的とする株式会社である(甲1)。
イ 被告は、平成25年7月22日時点で原告の株式3万5600株を保有する株主であった者であり、その後、同株式100株を第三者に譲渡し、平成28年7月26日時点で同株式3万5500株を保有していた(甲4〜7、29、30)。
(2)平成25年に原告が実施したスクイズアウトの経過
ア 原告は、平成25年6月28日、いわゆるスクイズアウト(少数株主の排除)を目的として、定時株主総会及び種類株主総会を開催し、これらの株主総会において、A種種類株式の発行に係る定款変更をする旨の決議、全ての原告普通株式に全部取得条項を付する定款変更をする旨の決議、原告が同年7月22日をもって全部取得条項付種類株式を全て取得し対価として株式1株につきA種種類株式101万分の1株を株主に交付する旨の決議をした(甲2、4〜7、29、30)。
イ 被告を含む一部の株主は、平成25年7月19日、原告に対し、上記種類株主総会決議の取消し等を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。同裁判所は、平成26年4月17日、同株主総会の議決権行使に係る基準日を設定する旨の公告をしなかったことが会社法124条3項に違反するとして、同決議を取り消す旨の判決をした。これに対し、被告ら及び原告がそれぞれ控訴し、東京高等裁判所は、平成27年3月12日、上記各控訴をいずれも棄却する判決をした。さらに、原告及び被告がそれぞれ上告及び上告受理申立てをし、最高裁判所は、平成28年4月7日、上記各上告を棄却するとともに、いずれも上告審として受理しない決定をした。これにより、上記第1審判決が確定し、上記種類株主総会決議は効力を喪失した。(甲4〜7)
(3)本件各決議
ア 原告は、平成28年6月18日、再びスクイズアウトを目的として、株主に対し、臨時株主総会及び普通株式の株主を構成員とする種類株主総会の招集通知をし、同年7月26日を効力発生日とする普通株式とA種種類株式のそれぞれにつき125万株を1株に併合する株式併合(以下「本件株式併合」という。)を行う旨の議案を記載した書面を送付した。これに対し、被告は、同年6月30日、原告に対し、上記議案に反対する旨を通知する内容証明郵便を送付したが、原告は、同年7月4日、上記各株主総会を開催し、本件株式併合を行う旨をそれぞれ決議した(以下「本件各決議」という。)。(甲9〜11)
イ これに対し、被告は、平成28年7月23日、原告に対し、会社法182条の4第1項に基づき被告が保有する原告株式を公正な価格により買い取ることを請求した(甲12。以下「本件買取請求」という。)。
(4)本件各決議に対する被告の不存在確認訴訟等
ア 被告は、原告に対し、本件各決議は不存在であるから本件株式併合及び本件買取請求は効力を生じないとして、被告が原告株式3万5500株を有する株主であることの確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。同裁判所は、平成29年3月28日、本件各決議が不存在であると評価すべき著しい瑕疵は認められず、本件株式併合及び本件買取請求はいずれも効力を生じており、被告は全ての原告株式を喪失したとして、被告の請求を棄却する判決をした(同裁判所平成28年(ワ)第11783号)。これに対し、被告が控訴したが、東京高等裁判所は、平成29年10月18日、上記控訴を棄却する判決をした(同裁判所平成29年(ネ)第2151号)。さらに、被告が上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁判所は、平成30年4月26日、上記上告を棄却するとともに、上告審として受理しない決定をし(同裁判所平成30年(オ)第167号及び同平成36年(受)第207号)、これにより上記第1審判決が確定した。(甲8、29、30、40)
イ 被告は、平成28年9月28日、原告に対し、主位的に本件各決議が存在しないことの確認等、予備的に本件各決議が無効であることの確認又は本件各決議の取消し等をそれぞれ求める訴えを東京地方裁判所に提起したが、同裁判所は、平成30年12月20日、被告の請求をいずれも棄却する判決をした(同裁判所平成28年(ワ)第33458号)。これに対し、被告が控訴し、東京高等裁判所は、令和元年12月4日、上記控訴を棄却する判決をした(同裁判所平成31年(ネ)第521号)。さらに、被告が上告及び上告受理申立てをし、最高裁判所は、令和2年10月29日、上記上告を棄却するとともに、上告審として受理しない決定をし(同裁判所令和2年(オ)第734号、同令和2年(受)第931号)、これにより上記第1審判決が確定した。(甲61、62、88)
(5)本件訴え提起等
被告は、別紙事件一覧表の1から16までのとおり、平成28年10月11日から平成29年8月24日にかけて、原告に対し、被告が原告の株主であることを前提として、3件の訴えの提起並びに5件の会社非訟事件及び8件の仮処分事件の申立て(本件訴え提起等)をした(甲13〜28。以下、別紙事件一覧表の各事件をいうときは、「本件事件1」のようにいう。)。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1)本件訴え提起等が不法行為を構成するか
(原告)
ア 被告は、本件株式併合の効力発生日である平成28年7月26日の到来により原告の株主の地位を喪失したにもかかわらず、同日以降、原告の株主であることを前提として本件訴え提起等をした。
被告は、本件株式併合に対し本件買取請求や株式の価格決定申立てをしたほか、本件株式併合の差止めを求める被告の仮処分命令申立て(東京地方裁判所平成28年(ヨ)第20096号)が平成28年7月25日に却下されたことからすれば、被告は、スクイズアウトの結果原告の株主の地位を喪失したことを知りつつ、あえて本件訴え提起等をしたものというべきである。また、本件訴え提起等の審理における、本件各決議が不存在である旨の被告の主張が失当であることは明白であるし、本件各決議は、これを取り消す判決が確定するまでは有効なものである。したがって、本件訴え提起等は、いずれも原告に対する不法行為を構成する。
イ 東京地方裁判所は、平成29年3月28日、被告が原告に対し株主権の確認を求めた訴えにつき、本件株式併合及び本件買取請求により被告が全ての原告株式を喪失した旨の判決をし、東京高等裁判所は、同年10月18日、これに対する被告の控訴を棄却する判決をした。本件訴え提起等の一部は、上記各判決の後に行われたものであり、これらが不法行為に該当することは明らかである。
ウ 被告は、平成29年3月31日時点の株主名簿に係る閲覧謄写仮処分命令申立て(本件事件9)が同年6月26日に却下されたにもかかわらず、同年8月17日、最新の株主名簿に係る閲覧謄写仮処分命令申立て(同11)をし、平成28年7月14日にした仮取締役兼仮代表取締役の選任申立てが却下されたにもかかわらず、平成29年1月20日、再び同申立て(同4)をした。また、被告は、平成28年4月13日に訴訟提起した計算書類・有価証券報告書・半期報告書等閲覧謄写請求事件において、平成26年3月期から平成28年3月期までの計算書類を既に保有していたことを前提として訴えを一部取り下げ、同裁判所は、被告が閲覧謄写を求める有価証券報告書及び半期報告書がいずれも会社法上の閲覧謄写の対象に該当しない旨の判断を示したにもかかわらず、平成29年2月9日、上記各書類の閲覧謄写を求める仮処分申立て(同7)をした。
これらは、原告に応訴の負担を課して損害を与える意図をもって、重複する申立てをするものであり、原告に対する不法行為を構成する。
(被告)
否認し、争う。
ア 被告は他の原告株主であるK(以下「K」という。)から詳細な資料に基づき本件各決議が不存在である旨の説明を受けており、現在も原告の株主であると信じている。また、本件訴え提起等をした各時点において、被告が提起した本件各決議の不存在確認等の訴えに係る判決は確定しておらず、いずれにしても同訴えは、被告が保有する原告株式4万4400株のうち3万5500株についてのみ判断するものにすぎない。また、本件訴え提起等のほぼ全てが確定していないことからすると、原告は、被告に対し不法行為責任を追及できる状態ではない。仮に、被告が原告の株主でないとされた場合であっても、本件各事件のほぼ全てにおいて、原告の債権者である旨も併せて主張しているから、本件訴え提起等が違法であるとされる理由はない。万が一、本件訴え提起等につき不法行為責任が生じるとしても、これを負うのは手続を主導したKであって、被告ではない。
イ 被告が原告の指摘する有価証券報告書又は計算書類の閲覧謄写を求める仮処分申立てをしたのは、単なる思い違いによるものであり、原告に損害を与える意図はない。
ウ 非訟事件又は仮処分事件は、訴訟とは明確に区別される手続であり、対立構造をとらないものも含まれるから、これらは不当「訴訟」ではない。また、非訟事件や仮処分事件は即時性が求められ、不十分な資料、調査及び情報量に基づく申立てをせざるを得ず、申立て自体が不法行為とされると、非訟事件や仮処分事件の制度自体が無意味になり相当でない。
(2)損害の有無及びその金額
(原告)
被告の不法行為により、原告には以下のとおり損害が発生した。
ア 弁護士費用 1834万5588円
原告は、同訴訟代理人に対し、弁護士費用として、訴訟事件又は非訟事件につき1件当たり着手金49万円、成功報酬98万円、仮処分事件につき1件当たり着手金32万6666円、成功報酬32万6666円との基準により算定される金額を支払った。本件訴え提起等のうち、訴訟事件と会社非訟事件は合計8件、仮処分事件は合計8件であるから、着手金の総額は少なくとも705万5994円、成功報酬の総額は少なくとも1128万9594円であり、これらの合計は1834万5588円である。
イ 慰謝料160万円
原告は、本件訴え提起等に対する応訴を強いられたものであり、これにより生じた精神的損害を填補するための慰謝料は1件当たり10万円、合計で160万円を下らない。
(被告)
争う。
ア 原告は、弁護士代理人を選任せずに訴訟追行をすることも可能であったから、弁護士費用を損害と評価するのは相当でない。また、原告が弁護士を代理人として選任した事実は明らかでないし、原告が主張する弁護士費用は、その根拠が不明であるほか、日本弁護士連合会の報酬規程(平成16年以前のもの)に基づく金額とかけ離れた高額なものである。
イ 原告は法人であり、精神的な損害は生じ得ないから、慰謝料を請求することはできない。また、慰謝料請求権は一身専属的な権利であるから、原告が商号を変更した時点で全て消滅したものである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件訴え提起等が不法行為を構成するか)について
(1)原告は、被告が本件株式併合の効力発生により原告の株主の地位を喪失したにもかかわらず本件訴え提起等をしたことは原告に対する不法行為を構成する旨主張する。
ところで、訴えの提起が違法となるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁参照)。
また、非訟事件若しくは仮処分の申立てについても、申立人の権利行使が最大限尊重されるべきである一方、相手方が手続に応じる場合に負担が生じる点は訴え提起の場合と同様である。そうすると、上記各申立てが違法となるのは、申立人の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、申立人が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて申立てをしたなど、非訟事件又は仮処分の申立てが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。
以上を前提に検討すると、前提事実(4)のとおり、本件各決議の不存在確認等を求める被告の各訴えを棄却する判決が全て確定したのは令和2年10月29日であり、本件訴え提起等は、いずれも同判決の確定日よりも前にされたものであると認められる。被告は、本件各決議の取消しが認められれば原告の株主としての地位を有することになるのであり、少なくとも、被告が本件各決議の瑕疵を主張してその効力を争っていた上記事件の判決が確定するより前の時点においては、被告が原告の株主であることを前提として訴訟を提起し、非訟事件若しくは仮処分事件を申立て、これらの手続を遂行し又は不服申立てを行ったとしても、これが事実的、法律的根拠を欠くものであると評価することはできない。原告は、本件各決議を取り消す旨の判決が確定するまでは同決議は有効であるとも主張するが、この点が上記結論を左右するものではない。
以上からすれば、本件訴え提起等が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとは認められず、原告に対する不法行為を構成するものとは認められない。
(2)原告は、①株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立て(本件事件9)が却下された後に再び同申立て(同11)をしたこと、②仮役員の選任申立てが却下された後に再び同申立て(同4)をしたこと、③被告が平成26年3月期から平成28年3月期までの計算書類を既に保有していたことを前提としてその閲覧謄写請求を取り下げ、裁判所が有価証券報告書及び半期報告書がいずれも会社法上の閲覧謄写の対象に該当しない旨の判断を示した後に、上記各書類の閲覧謄写を求める仮処分申立て(同7)をしたことがそれぞれ原告に対し重複する申立てをするものであり、不法行為を構成する旨主張する。
しかし、上記①については、本件事件9の申立ての対象が平成29年3月31日時点の株主名簿であるのに対し、同11の申立ての対象が最新の株主名簿とされていることからすると、閲覧の対象が同一であるとはいえず、また同種の申立てをしたことが不法行為を構成するということはできない。また、上記②及び③についても、証拠(甲8、16、18、20)及び弁論の全趣旨によれば、原告と被告の間には、平成28年から平成29年にかけて70件に及ぶ多数の訴訟事件や非訟事件が係属していたと認められるところ、Kと連名で申立てがされた本件事件4及び7の各申立てについては、被告自身、Kの指示を受けて申立てをしたものであって、重複していると分かって申し立てたものはない旨供述する(被告7頁、34頁)ことからしても、被告が重複するものであることを認識しつつあえて申立てに至ったと認めるには至らない。
以上からすれば、被告が権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであると知りながら、あえて上記各申立てをし、これが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものであるとまでは認められず、したがって、上記各申立てが原告に対する不法行為を構成するとする原告の主張は採用することができない。
2 以上によれば、争点(2)(損害の有無及びその金額)について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。
なお、被告は、原告代表者を原告の代表取締役に選任する取締役会決議は無効であり、同代表者による原告訴訟代理人に対する本件訴訟に係る訴訟委任も無効であるから、本件訴えは不適法である旨主張するが、原告代表者が原告の代表権を有しないことを認めるに足りる証拠はなく、同主張は採用することができない。
3 結論
したがって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第25部
裁判長裁判官 鈴木昭洋
裁判官 森 優介
裁判官 窓岩亮佑
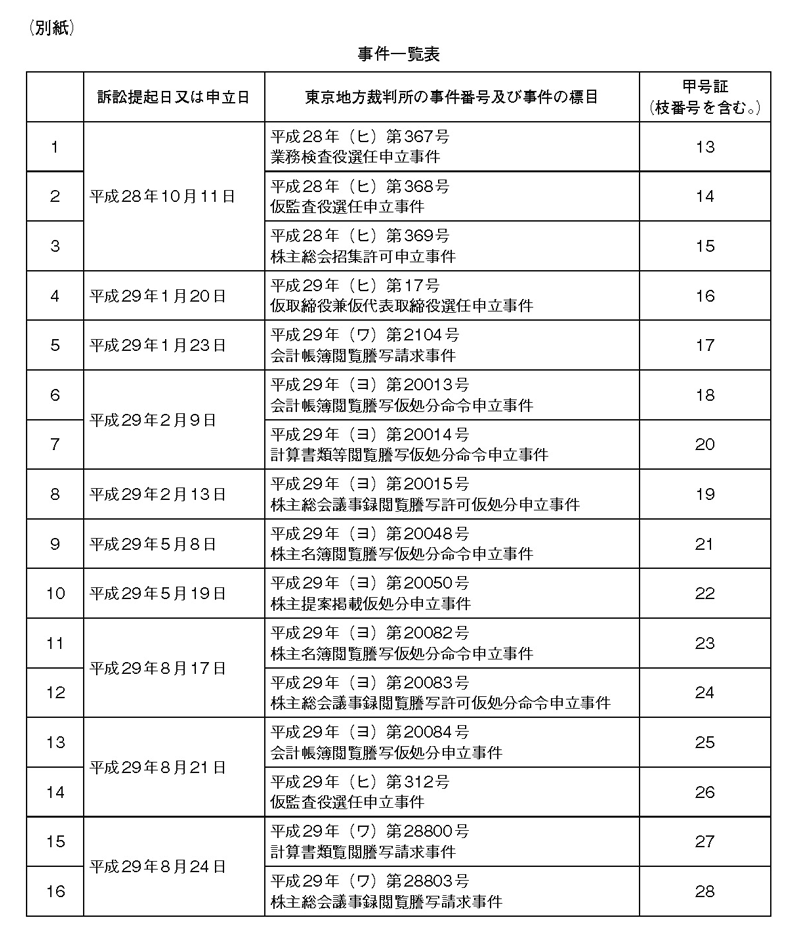
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















