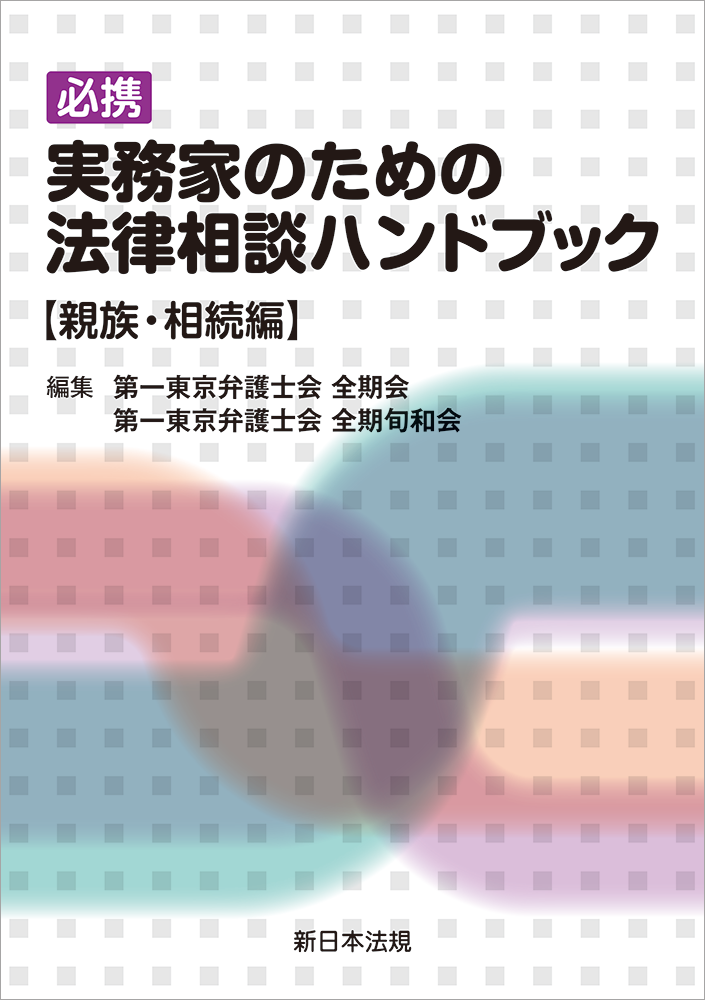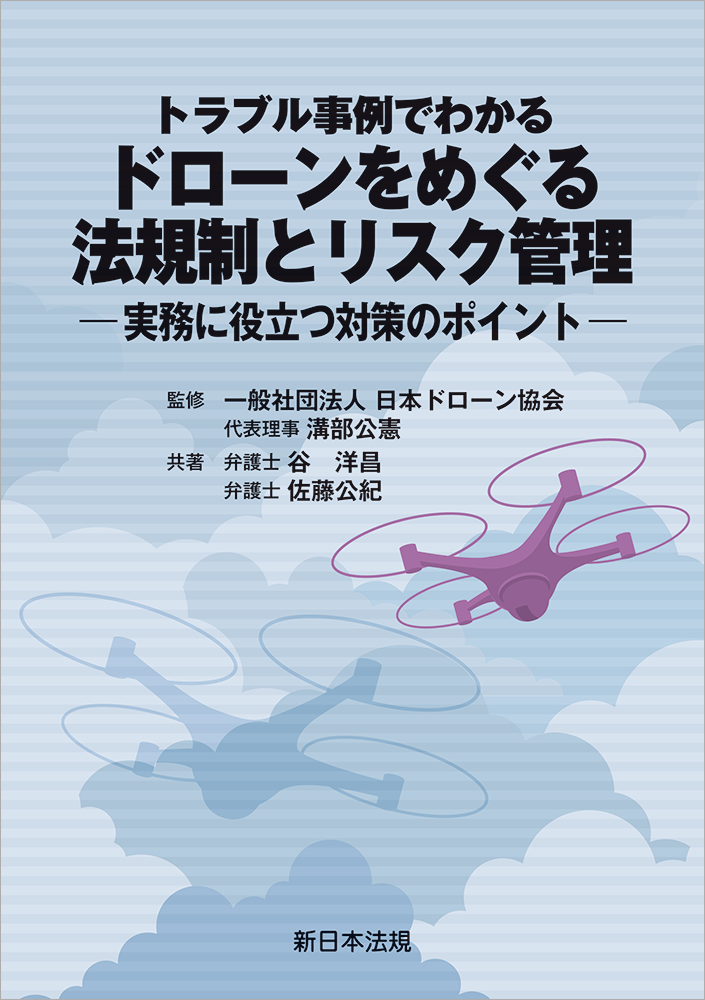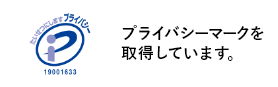解説記事2025年11月17日 ニュース特集 相続税の申告期限に間に合わず、税理士損害賠償責任事件に発展(2025年11月17日号・№1099)
ニュース特集
委任契約に基づき履行割合に応じた報酬の請求可
相続税の申告期限に間に合わず、税理士損害賠償責任事件に発展
長らく税理士業務を行っていれば、誰しも税理士損害賠償のリスクがないとはいえず、不運にもクライアントから訴えられるケースがある。本特集では、クライアントから訴えられた2件の税理士損害賠償請求事件を紹介する。1件目は、相続税の法定申告期限内に申告できなかったというものだが、税理士法人が委任契約を締結する際に、申告期限に間に合わない旨を説明していたことで原告の請求は棄却されている。また、2件目は、税務調査の結果、青色申告の承認取消処分等が行われることになったが、調査の際に税理士法人の説明不足があったとして訴訟に至ったもの。原告の請求は棄却されているが、クライアントである原告の対応もさることながら税理士法人側の調査時及びその後の対応にも疑問符がつくものとなっている。
委任契約は法定申告期限までに間に合わない可能性を前提に締結
1件目は、相続税の法定申告期限内に申告手続が完了しなかったため、相続人であり、かつ、クライアントでもある原告から税理士法人(被告)が訴えられた事件である(令和7年7月17日判決、令和6年(ワ)第9056号、令和6年(ワ)第18329号)。相続税申告手続の委任契約がいつ成立したかが争点となっている。
原告は、税理士法人(被告)との間で、相続税申告手続の委任契約をし、被告には委任契約に基づき相続税の法定申告期限内に相続税申告手続を完了すべき善管注意義務があったにもかかわらず、これを怠って手続を完了させなかったため、他の税理士に委任し相続税申告手続を行わざるを得なくなり、加えて無申告加算税及び延滞税の支払いを余儀なくされたと主張し、税理士法人に対し、不法行為に基づき2,300万円余りの損害賠償請求を行ったものである。一方、税理士法人側は、原告の所得税の申告を完了したにもかかわらず、所得税申告委任契約に基づく報酬11万円を支払っておらず、また、相続税申告書の最終稿を作成して原告に交付したにもかかわらず、原告が一方的に委任契約を解除したため、既履行分の報酬として400万円の支払い(合計411万円)を求めている。
原告は、令和4年11月初旬頃に被相続人の相続税申告手続を依頼し、被告の税理士法人代表者はこれを快諾したとするが、税理士法人側は、委任契約が成立したのは令和5年1月21日と主張(表1参照)。なお、法定申告期限は令和5年3月10日であった。
【表1】当事者の主な主張
| 原告(クライアント) | 被告(税理士法人) |
| 原告は、令和4年11月初旬頃、被告代表者に対し、直接、亡母の相続財産についての相続税申告手続を依頼し、被告はこれを快諾した。原告は、被告代表者の指示により除籍謄本等を取得しているが、これらの発行日は令和4年11月28日となっている。したがって、被告には、法定申告期限までには十分な時間的余裕があったのであり、被告は亡母の各種税務顧問として亡母の財産状況を熟知しており、被相続人が原告のみであって遺産分割も不要という状況だったのであるから、被告において相続税申告のための各種検討に特に時間を要するはずがなく、税務申告の依頼を行うに当たって、法定申告期限の徒過を許容することなどあり得ないから、被告は、委任契約において、法定申告期限までに確定申告を終える善管注意義務を負っていた。 | 被告代表者は、令和5年1月5日、原告から亡母の相続財産に係る相続税の申告について相談を受け、亡母の除籍謄本を渡された。被告代表者は、原告に対し、被告の顧問先の法人税・所得税の確定申告に関する業務が繁忙期に入ることや亡母の相続財産の大きさからすると相当な業務量が見込まれるため、被告が受任した場合に法定申告期限に間に合わせることは困難である旨説明し、別の会計事務所に依頼することを含めてどのように対応するのか検討してほしいと説明したが、被告に依頼すると明言しなかった。その後、1月21日に面談し、改めて、この時点で相続税申告の依頼を受けても法定申告期限に間に合わせるのは困難だが、最善を尽くす旨説明するとともに、申告期限を徒過した場合の説明などを行い、原告はこれらを理解した上で被告に依頼した。 |
東京地方裁判所(大野元春裁判官)は、原告と被告代表者との間のショートメッセージのやり取りを見ても、令和4年11月頃に亡母の相続税の問題について話題に上っている形跡はなく、面談自体もないと指摘。また、被告は、亡母との間で各種税務顧問として所得税の確定申告等を行っていたのであり、これによって把握できる亡母の資産規模からして、相続税申告のために必要な書類が戸籍関係や銀行の残高証明だけでは到底足りないことは被告において明らかであったといえるとし、委任契約が令和4年11月頃に成立しているのであれば、被告が原告に対し、必要書類について、その内容から書面で具体的な指示をするはずであるが、そのような指示がされている形跡はないとした。
原告は、亡母の戸籍関係の書類を令和4年11月に取得していることを委任契約が同月に締結されたことの根拠としているが、裁判所は、相続税の申告に当たって、被相続人の相続人が誰であるかを確認するために戸籍関係書類が必要であるのは当然であるから、戸籍関係書類を取得していることをもって委任契約が同月に締結された根拠ということはできないとした。
したがって、裁判所は、委任契約は法定申告期限までに間に合わない可能性が高いことを前提に締結されたというべきであるから、被告の税理士法人が委任契約に基づき法定申告期限内に相続税の申告を完了すべき義務を負っていたとは認められないとの判断を示した。
申告書の最終案を作成、契約の7割を履行
本件では、反訴として税理士法人が原告に対して既履行分の報酬等の支払いを請求している。裁判所は、委任契約が履行の中途で終了した場合、委任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるとされており(民法648条3項2号)、本件委任契約は、原告の解除によって終了しているから、税理士法人は委任契約に基づく履行の割合に応じた報酬を請求することができるとした。
本件では、被告代表者が令和5年5月28日に原告にメールで送付した相続税申告書の最終案は、現実に申告手続を行った別の税理士事務所が作成した申告書とほぼ同内容のものであったと認められることから、被告は、同日までに亡母の相続に関する相続税申告書を完成させていたということができるとした。もっとも、税理士法上、税理士の業務には税務書類の作成や税務相談以外に、税務申告等の代理や代行を行う税務代理があり、本件委任契約は税務代理をその内容とするものということができると指摘。相続税申告書の作成は、相続財産の調査や検討を必要とするものであるから、申告書の作成が税務代理の履行を兼ねているというべきであるものの、税務代理で予定されている業務として、税務官公署に対してする主張や陳述を行うことの代理が含まれているのであるから、相続税申告書の完成をもって委任契約がすべて履行されているとみることはできないとの見解を示した。
本件では、亡母の所有不動産についての大規模修繕工事の件など、当初の申告書案がそのまま税務署において認められるか不明な部分があったというべきことなどからすれば、被告に対する委任契約の履行割合は7割(270万円)を相当として認めると判断した。
税務調査に応じない場合の不利益の説明義務はあるが
2件目に紹介する事件は、税務調査により、青色申告の承認取消処分等が行われることになったが、調査の際に税理士法人(被告)の説明不足があったとしてクライアントから訴えられたもの(令和7年7月31日判決、令和3年(ワ)第28057号)。本件では、原告の請求が棄却されているが、税理士法人側の主張が全面的に認められたものでもない。原告自身が帳簿書類等を提示しない場合の不利益を十分に認識していながら、税務署に提示することを自ら拒否していたものとされたものであり、税理士法人側の調査時及びその後の対応に疑問符がつく事案となっている。
具体的には、原告が税務調査を受けた際、被告の税理士法人の説明義務違反により、帳簿書類等の提示をせず、修正申告しなかった結果、青色申告の承認の取消処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分等を受け、事業の縮小を余儀されなくされたと主張し、税理士法人及び同法人の社員らに対し、債務不履行に基づき6,600万円余りの損害賠償を求めたものである。
原告は、税理士法人は原告に対し、事前通知のない税務調査が違法になる要件、調査が違法と認められる可能性の程度、調査が違法な無予告調査と認められなかった場合になお帳簿書類等を提示しないことによる不利益、今後改めて事前通知を経た税務調査がなされた場合の準備等について説明をする義務を負っていたと主張(説明義務違反①)。また、被告の代表社員は、消費税等の修正申告を行わなければ各処分が下されることを予見できたのであるから、税理士法人は原告に対して修正申告の必要性等を説明する義務を負っていたとした(説明義務違反②)。一方、税理士法人は、税務調査は事前通知が原則であり、本件調査は例外要件(通則法74条の10)を充足しない可能性があり、例外要件を充足するかは被告法人が確認するが、今後無予告調査の要件充足性が確認されるか、改めて事前通知を経た税務調査がなされればこれに応じる必要があり、税務調査自体を拒否することはできないことを説明し、原告も理解していたと主張した。
なお、税務調査の一連の経緯は表2のとおりである。
【表2】税務調査の一連の経緯
| ・令和元年8月27日、税務署職員は原告代表者の自宅に臨場し、税務調査に協力するように要請(事前通知なし)。これに対し、原告代表者は、調査への協力の意向を示しつつ、税理士法人の事務員に電話連絡。事務員が事前通知のない調査への協力を渋ったため、税務署職員は税理士法人の代表社員への連絡を求め、代表社員に対し、調査への協力を求めた。 ・同年8月28日、税務署職員は税理士法人の事務員に電話し、原告の帳簿書類等の提示を求めたが、事務員は無予告調査の理由を開示するまでは調査に協力できないと伝えた。同日、税務署職員は、原告代表者に電話をし、帳簿書類等の提示を求めたところ、原告代表者はすべて税理士法人に預けている旨を回答したため、税理士法人代表社員に連絡し、帳簿書類等の提示を依頼。しかし、税務署職員が翌日に税理士法人の事務所に臨場するも代表社員は不在で、その後も連絡がなかった。 ・同年8月30日、税務署職員は原告代表者に電話をし、税理士法人から帳簿書類等の提示がないこと、このままでは法人税の青色申告の承認が取り消され、消費税の仕入税額控除が認められなくなる旨を説明した。 ・税務署職員は、その後も税理士法人代表社員に連絡を取ろうとしたが、連絡が取れなかったため、同年12月11日、原告代表者に電話をし、再度、帳簿書類等の提示がない場合には、青色申告の承認が取り消され、消費税の仕入税額控除が認められなくなる旨を説明し、税理士法人の代表社員にも書面を送付した。 ・同年12月19日、税理士法人代表社員は、税務署職員に対し、書面に対する抗議を行うとともに、調査が事前通知なく実施されたことの理由を開示するよう求めた。 ・(その後も税務署職員は電話や書面を送付するなどしたが)令和2年6月2日、税務署職員は税理士法人代表社員に対し、電話で調査の結果を説明するとともに、修正申告の意向を確認したが、修正申告をしない旨を述べたため、6月18日付で本件各処分が行われた。 |
原告は不利益について認識
東京地方裁判所(知野明裁判長)は、適法な税務調査を拒否して帳簿書類等を提示しない場合、刑事罰(通則法128条)、青色申告の承認の取消し(法人税法127条1項1号、同法126条1項)、仕入税額控除の否認(消費税法30条7項、同条1項)といった不利益が生じるおそれがあるところ、被告税理士法人の代表社員で税理士である被告Hは、不利益が生じるおそれがあることを認識していたと認められ、原告から税務署への確定申告を含む決算業務を受任していた被告法人は、原告に対し、適法な税務調査に応じない場合の不利益について説明する義務を負っていたといえるとした。
しかし、原告代表者は、税務職員から何度も直接の電話ないし書面送付により、帳簿書類等の提示が求められ、提示がない場合には青色申告の承認取消事由に該当し、仕入税額控除が適用されなくなる旨通知されていたのであるから、帳簿書類等を提示しない場合の不利益を十分に認識していたと認められると指摘。自らの意思で帳簿書類等を提示しなかったと結論付けた。
また、税理士法人の代表社員の被告Hは、原告に対して、調査に基づく修正申告の必要性について説明していないと供述しており、被告税理士法人が説明義務②に違反したと認められる余地があるとしたが、原告は、帳簿書類等を提示しない場合の不利益を十分に認識していながら、税務署に対し、帳簿書類等を提示することを自ら拒否していたものであり、仮に被告税理士法人から調査に基づく修正申告の必要性について説明を受けたとしても、修正申告には応じなかったものと推認することができるとし、被告税理士法人の説明義務違反によるものとは認められないと判断した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -