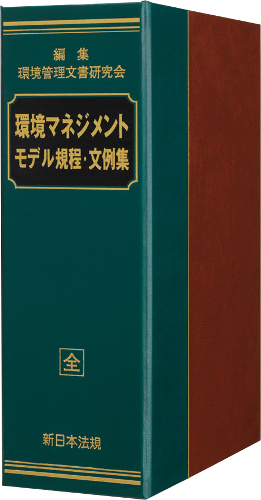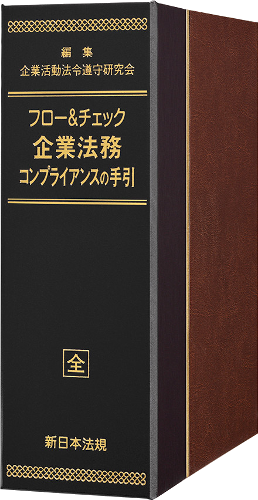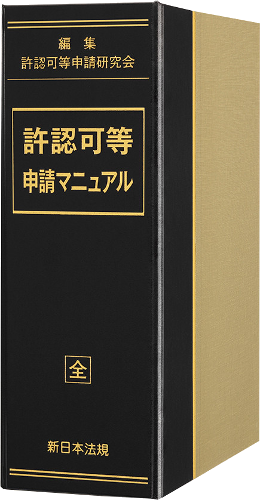PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正(令和4年6月1日法律第60号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年6月24日(政令第237号)において令和4年7月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年06月01日
- 施行日 令和4年07月01日
環境省
平成10年法律第117号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年06月01日
- 施行日 令和4年07月01日
環境省
平成10年法律第117号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二三七号)(環境省)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六〇号)の施行期日は、令和四年七月一日とすることとした。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)(環境省)
1 地方公共団体に対する財政上の措置等
国は、都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとすることとした。(第一九条第三項関係)
2 機構の目的
株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とすることとした。(第三六条の二関係)
3 総則
機構は、環境大臣の認可により、一を限って設立される株式会社とし、政府は、常時、機構が発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならないこととした。(第三六条の三及び第三六条の四関係)
4 脱炭素化委員会
機構に脱炭素化委員会を置くとともに、同委員会は取締役である委員三人以上七人以内で組織し、対象事業活動の支援(以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容の決定等を行うこととした。(第三六条の一六~第三六条の一八関係)
5 業務
㈠ 業務の範囲
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務等を営むものとすることとした。(第三六条の二三関係)
⑴ 対象事業者(対象事業活動支援の対象となった事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
⑵ 対象事業者に対する基金の拠出
⑶ 対象事業者に対する資金の貸付け
⑷ 対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
⑸ 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
⑹ 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
⑺ 対象事業者のためにする有価証券の募集又は私募
⑻ 対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣
㈡ 支援基準
環境大臣は、機構が対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」という。)を定めるものとすることとし、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならないこととした。(第三六条の二四関係)
㈢ 支援決定
機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならず、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならないこととした。(第三六条の二五関係)
6 国の援助等
環境大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととし、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととした。(第三六条の二八関係)
7 財務及び会計
機構は、毎事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならないこととし、機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととしたほか、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができること等とした。(第三六条の三〇~第三六条の三三関係)
8 監督
機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督することとし、環境大臣は、3の認可等をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこと等とした。(第三六条の三四~第三六条の三七関係)
9 解散等
機構は、5の㈠に掲げる業務の完了により解散することとした。(第三六条の三八関係)
10 罰則
罰則について、所要の規定を整備することとした。(第六六条~第七〇条、第七四条及び第七六条関係)
11 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六〇号)の施行期日は、令和四年七月一日とすることとした。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)(環境省)
1 地方公共団体に対する財政上の措置等
国は、都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとすることとした。(第一九条第三項関係)
2 機構の目的
株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とすることとした。(第三六条の二関係)
3 総則
機構は、環境大臣の認可により、一を限って設立される株式会社とし、政府は、常時、機構が発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならないこととした。(第三六条の三及び第三六条の四関係)
4 脱炭素化委員会
機構に脱炭素化委員会を置くとともに、同委員会は取締役である委員三人以上七人以内で組織し、対象事業活動の支援(以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容の決定等を行うこととした。(第三六条の一六~第三六条の一八関係)
5 業務
㈠ 業務の範囲
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務等を営むものとすることとした。(第三六条の二三関係)
⑴ 対象事業者(対象事業活動支援の対象となった事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
⑵ 対象事業者に対する基金の拠出
⑶ 対象事業者に対する資金の貸付け
⑷ 対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
⑸ 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
⑹ 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
⑺ 対象事業者のためにする有価証券の募集又は私募
⑻ 対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣
㈡ 支援基準
環境大臣は、機構が対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」という。)を定めるものとすることとし、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣に協議しなければならないこととした。(第三六条の二四関係)
㈢ 支援決定
機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならず、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならないこととした。(第三六条の二五関係)
6 国の援助等
環境大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととし、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととした。(第三六条の二八関係)
7 財務及び会計
機構は、毎事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならないこととし、機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととしたほか、政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができること等とした。(第三六条の三〇~第三六条の三三関係)
8 監督
機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督することとし、環境大臣は、3の認可等をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこと等とした。(第三六条の三四~第三六条の三七関係)
9 解散等
機構は、5の㈠に掲げる業務の完了により解散することとした。(第三六条の三八関係)
10 罰則
罰則について、所要の規定を整備することとした。(第六六条~第七〇条、第七四条及び第七六条関係)
11 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -