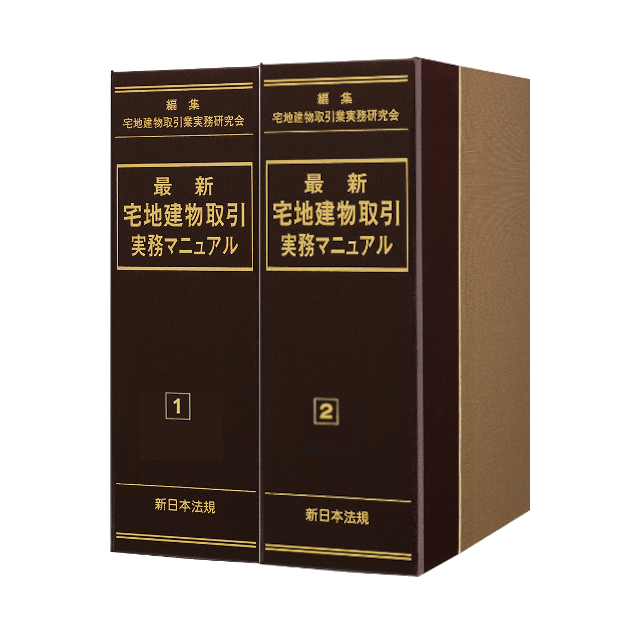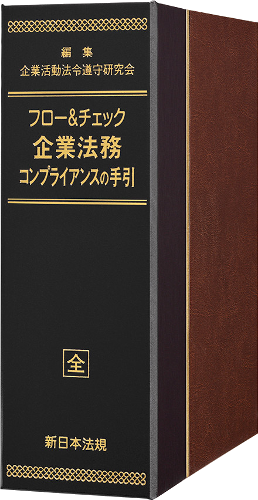PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正(令和7年6月13日法律第67号〔附則第11条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 未定
経済産業省
平成11年法律第136号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 未定
経済産業省
平成11年法律第136号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(法律第六七号)(経済産業省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者について早期での円滑な事業再生を促すことにより、当該事業者がその事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で経営資源を有効に活用してその事業活動を活性化できるようにすることが重要であることに鑑み、当該事業者の事業再生の実施のため、公正かつ中立な第三者が関与して金融機関等であるその債権者の一定の割合以上の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた当該債権者の決議により、当該債権者に対する当該事業者の債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等に関し必要な事項を定め、もって当該事業者の円滑な事業再生の実施を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
⑴ この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいうものとすることとした。
イ 預金保険法第二条第一項に規定する金融機関
ロ 銀行法第四条第一項の免許を受けた同法第一〇条第二項第八号に規定する外国銀行
ハ 農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合
ニ 保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二二三条第一項に規定する免許特定法人
ホ 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
ヘ 政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる経済産業省令で定める特殊法人等
ト イからヘまでに掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者として経済産業省令で定める者
チ 地方公共団体
リ 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社その他債権の譲受けに関する業務を行う事業者として経済産業省令で定める者(第二条第一項関係)
⑵ この法律において「貸付債権等」とは、貸付債権その他信用の供与に基づく債権として経済産業省令で定めるもの(⑴のリに掲げる者が有するものにあっては、⑴のイからチまでに掲げる者が有していたものを⑴のリに掲げる者が譲り受けた場合のものに限る。)をいうものとすることとした。(第二条第二項関係)
⑶ この法律において「対象債権」とは、2の㈠の⑴の確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)に対して当該確認の時に金融機関等が有する当該確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等及び当該貸付債権等に係る次に掲げる権利をいうものとすることとした。
イ 当該確認後の利息の請求権
ロ 当該確認後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(第二条第三項関係)
⑷ この法律において「対象債権者」とは、対象債権を有する者であって、2の㈠の⑵の規定による通知を受けた者をいうものとすることとした。(第二条第四項関係)
2 対象債権者の権利の変更に関する手続
㈠ 指定確認調査機関の確認等
⑴ 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、その事業再生を図るため、㈡の⑴の対象債権者集会における㈡の⑴に規定する権利変更議案の決議(以下「権利変更決議」という。)により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、当該権利の変更について、申請書に当該権利の変更に関する概要を記載した書面及び当該貸付債権等の一覧表(以下「権利変更概要書等」という。)を添付して、これらを3の㈠の⑴の規定による指定を受けた者(以下「指定確認調査機関」という。)に提出し、その申請が一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないものとするなど、指定確認調査機関の確認に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第三条第一項~第六項関係)
⑵ 指定確認調査機関は、⑴の確認をしたときは、その旨を対象債権を有する者に通知しなければならないものとすることとした。(第三条第七項関係)
⑶ 指定確認調査機関は、一定の要件に該当する場合には、⑴の確認を取り消さなければならないものとするなど、変更の確認等及び確認の取消しに関する手続について所要の規定を設けることとした。(第四条及び第五条関係)
⑷ 指定確認調査機関は、⑴の確認後、速やかに、全ての対象債権者に対し、㈡の⑴に規定する権利変更議案につき㈡の⑺に規定する議決権者の全ての同意が得られ、当該権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間、対象債権の回収その他経済産業省令で定める債権者としての権利の行使をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならないものとするなど、一時停止の要請等について所要の規定を設けることとした。(第六条関係)
⑸ 裁判所は、⑴の確認があった場合において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、確認事業者の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができるものとするなど、強制執行等の中止命令等について所要の規定を設けることとした。(第七条関係)
⑹ 裁判所は、⑴の確認があった場合において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権(対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。)を有する者に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、その担保権の実行手続の中止を命ずることができるものとするなど、担保権の実行手続の中止命令について所要の規定を設けることとした。(第八条関係)
⑺ 権利変更決議の認可の決定があったときは、⑸の規定により中止した手続は、その効力を失うものとすることとした。(第九条関係)
㈡ 対象債権者集会及び権利変更決議の認可
⑴ 対象債権者集会は、対象債権者の権利(対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。)の変更に関する議案(以下「権利変更議案」という。)について決議をすることができるものとするなど、対象債権者集会の構成及び権限について所要の規定を設けることとした。(第一〇条及び第一一条関係)
⑵ 確認事業者は、権利変更議案において、権利変更概要書等に基づき、対象債権者の権利の全部又は一部を変更する条項を定めなければならないものとするなど、権利変更議案について所要の規定を設けることとした。(第一二条及び第一三条関係)
⑶ 確認事業者は、㈠の⑴の確認後六月以内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画(以下「早期事業再生計画」という。)を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならないものとするなど、早期事業再生計画について所要の規定を設けることとした。(第一四条関係)
⑷ 指定確認調査機関は、⑶の規定による提出を受けたときは、権利変更議案及び早期事業再生計画等が一定の要件に該当するものであることについて調査を行わなければならないものとするなど、指定確認調査機関の調査について所要の規定を設けることとした。(第一五条関係)
⑸ 対象債権者集会を招集するには、確認事業者は、対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに、対象債権者及び指定確認調査機関に対して、その通知を発しなければならないものとするなど、対象債権者集会の招集等について所要の規定を設けることとした。(第一六条関係)
⑹ 確認事業者は、⑸の通知(権利変更議案を決議するための対象債権者集会に係るものに限る。)に際しては、対象債権者に対し、権利変更議案の内容を記載した書面、早期事業再生計画、⑷の調査の結果を記載した書面その他議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「対象債権者集会書類」という。)及び対象債権者が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならないものとするなど、対象債権者集会書類及び議決権行使書面の交付等について所要の規定を設けることとした。(第一七条及び第一八条関係)
⑺ 対象債権者集会において権利変更議案を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。)の議決権の総額の四分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならないものとするなど、対象債権者の議決権及び対象債権者集会の決議等について所要の規定を設けることとした。(第一九条~第二五条関係)
⑻ 権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、確認事業者は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならないものとするなど、権利変更決議の認可の申立て及び裁判所による権利変更決議の認可又は不認可の決定に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第二六条及び第二七条関係)
⑼ 権利変更決議の認可の決定があったときは、対象債権者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更されるものとするなど、権利変更決議の効力について所要の規定を設けることとした。(第二八条関係)
⑽ 権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときは、⑼の規定にかかわらず、権利変更決議はその効力を生じ、対象債権者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更されるものとするなど、議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力について所要の規定を設けることとした。(第二九条関係)
㈢ 雑則
⑴ 2の規定による非訟事件(以下「対象債権者集会決議関連事件」という。)は、確認事業者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄するものとするなど、対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続について所要の規定を設けることとした。(第三〇条~第四三条関係)
⑵ 仮登記担保契約に関する法律第四条第一項(同法第二〇条において準用する場合を含む。)に規定する担保仮登記(同法第一四条(同法第二〇条において準用する場合を含む。)に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、2の規定の適用については、抵当権とみなすものとするなど、担保仮登記の取扱いについて所要の規定を設けることとした。(第四四条関係)
⑶ 2に定めるもののほか、対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続に関し必要な事項は最高裁判所規則で、その他2に定める手続に関し必要な事項は経済産業省令で、それぞれ定めるものとすることとした。(第四五条関係)
3 指定確認調査機関
㈠ 総則
⑴ 経済産業大臣は、一定の要件に該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務(2に定める手続(対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続を除く。以下「対象債権者集会手続」という。)に係る2の規定による業務及び4の規定による業務並びにこれらに付随する業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができるものとするなど、指定確認調査機関の指定に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第四六条及び第四七条関係)
⑵ 指定確認調査機関の確認調査員若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとするなど、指定確認調査機関の秘密保持義務等について所要の規定を設けることとした。(第四八条関係)
㈡ 業務
指定確認調査機関は、2の㈠の⑴の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しなければならないものとするなど、指定確認調査機関の業務等について所要の規定を設けることとした。(第四九条~第五四条関係)
㈢ 監督
指定確認調査機関の監督等について所要の規定を設けることとした。(第五五条~第六三条関係)
4 確認事業者に係る特例
㈠ 調停機関に関する特例
確認事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について対象債権者集会手続が実施されていた場合における調停機関に関する特例を設けることとした。(第六四条関係)
㈡ 監督委員に関する特例
再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る事業者について対象債権者集会手続が実施されていたときは、裁判所は、民事再生法第五四条第一項の処分をする場合には、確認調査員が当該対象債権者集会手続に係る対象債権者集会関連業務に従事していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする特例を設けるものとするなど、再生手続及び更生手続における監督委員に関する特例を設けることとした。(第六五条及び第六六条関係)
㈢ 社債権者集会に関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該確認事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができるものとするなど、社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第六七条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の規定により指定確認調査機関が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七三二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該確認事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七三三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとするなど、社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例を設けることとした。(第六八条関係)
㈣ 資金の借入れに関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、当該確認を受けた時から権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間における当該確認事業者の資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができるものとするなど、資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第六九条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした確認事業者の再生手続において、当該確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法第一六三条第一項の再生計画案をいう。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第一五五条第一項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとするなど、資金の借入れに関する再生手続及び更生手続の特例を設けることとした。(第七〇条及び第七一条関係)
㈤ 債権の弁済に関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権が一定の要件に該当することの確認を求めることができるものとするなど、債権に関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第七二条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の要件に該当することの確認を受けた債権(以下「確認債権」という。)に係る債務を負担した確認事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三〇条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が⑴の要件に該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとするなど、債権の弁済に関する再生手続及び更生手続の特例を設けることとした。(第七三条~第七八条関係)
㈥ 破産手続等に係る指定確認調査機関の意見
指定確認調査機関は、確認事業者についての破産手続等において、当該破産手続等における一定の裁判に係る事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体に対し、その求めに応じて、意見を述べることができるものとすることとした。(第七九条関係)
5 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第八〇条~第九二条関係)
6 附則
㈠ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
㈡ 経過措置等について所要の規定を設けることとした。(附則第三条~第一〇条関係)
㈢ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一一条及び第一二条関係)
7 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 総則
㈠ 目的
この法律は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者について早期での円滑な事業再生を促すことにより、当該事業者がその事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で経営資源を有効に活用してその事業活動を活性化できるようにすることが重要であることに鑑み、当該事業者の事業再生の実施のため、公正かつ中立な第三者が関与して金融機関等であるその債権者の一定の割合以上の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた当該債権者の決議により、当該債権者に対する当該事業者の債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等に関し必要な事項を定め、もって当該事業者の円滑な事業再生の実施を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
⑴ この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいうものとすることとした。
イ 預金保険法第二条第一項に規定する金融機関
ロ 銀行法第四条第一項の免許を受けた同法第一〇条第二項第八号に規定する外国銀行
ハ 農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合
ニ 保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二二三条第一項に規定する免許特定法人
ホ 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者
ヘ 政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる経済産業省令で定める特殊法人等
ト イからヘまでに掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務で信用の供与に係るものを行う事業者として経済産業省令で定める者
チ 地方公共団体
リ 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社その他債権の譲受けに関する業務を行う事業者として経済産業省令で定める者(第二条第一項関係)
⑵ この法律において「貸付債権等」とは、貸付債権その他信用の供与に基づく債権として経済産業省令で定めるもの(⑴のリに掲げる者が有するものにあっては、⑴のイからチまでに掲げる者が有していたものを⑴のリに掲げる者が譲り受けた場合のものに限る。)をいうものとすることとした。(第二条第二項関係)
⑶ この法律において「対象債権」とは、2の㈠の⑴の確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)に対して当該確認の時に金融機関等が有する当該確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等及び当該貸付債権等に係る次に掲げる権利をいうものとすることとした。
イ 当該確認後の利息の請求権
ロ 当該確認後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(第二条第三項関係)
⑷ この法律において「対象債権者」とは、対象債権を有する者であって、2の㈠の⑵の規定による通知を受けた者をいうものとすることとした。(第二条第四項関係)
2 対象債権者の権利の変更に関する手続
㈠ 指定確認調査機関の確認等
⑴ 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、その事業再生を図るため、㈡の⑴の対象債権者集会における㈡の⑴に規定する権利変更議案の決議(以下「権利変更決議」という。)により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、当該権利の変更について、申請書に当該権利の変更に関する概要を記載した書面及び当該貸付債権等の一覧表(以下「権利変更概要書等」という。)を添付して、これらを3の㈠の⑴の規定による指定を受けた者(以下「指定確認調査機関」という。)に提出し、その申請が一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないものとするなど、指定確認調査機関の確認に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第三条第一項~第六項関係)
⑵ 指定確認調査機関は、⑴の確認をしたときは、その旨を対象債権を有する者に通知しなければならないものとすることとした。(第三条第七項関係)
⑶ 指定確認調査機関は、一定の要件に該当する場合には、⑴の確認を取り消さなければならないものとするなど、変更の確認等及び確認の取消しに関する手続について所要の規定を設けることとした。(第四条及び第五条関係)
⑷ 指定確認調査機関は、⑴の確認後、速やかに、全ての対象債権者に対し、㈡の⑴に規定する権利変更議案につき㈡の⑺に規定する議決権者の全ての同意が得られ、当該権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間、対象債権の回収その他経済産業省令で定める債権者としての権利の行使をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならないものとするなど、一時停止の要請等について所要の規定を設けることとした。(第六条関係)
⑸ 裁判所は、⑴の確認があった場合において、必要があると認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、対象債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は対象債権を被担保債権とする留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売の手続で、確認事業者の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができるものとするなど、強制執行等の中止命令等について所要の規定を設けることとした。(第七条関係)
⑹ 裁判所は、⑴の確認があった場合において、対象債権者の一般の利益に適合し、かつ、確認事業者の財産につき存する担保権(対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。)を有する者に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、確認事業者又は対象債権者の申立てにより、相当の期間を定めて、その担保権の実行手続の中止を命ずることができるものとするなど、担保権の実行手続の中止命令について所要の規定を設けることとした。(第八条関係)
⑺ 権利変更決議の認可の決定があったときは、⑸の規定により中止した手続は、その効力を失うものとすることとした。(第九条関係)
㈡ 対象債権者集会及び権利変更決議の認可
⑴ 対象債権者集会は、対象債権者の権利(対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。以下同じ。)の変更に関する議案(以下「権利変更議案」という。)について決議をすることができるものとするなど、対象債権者集会の構成及び権限について所要の規定を設けることとした。(第一〇条及び第一一条関係)
⑵ 確認事業者は、権利変更議案において、権利変更概要書等に基づき、対象債権者の権利の全部又は一部を変更する条項を定めなければならないものとするなど、権利変更議案について所要の規定を設けることとした。(第一二条及び第一三条関係)
⑶ 確認事業者は、㈠の⑴の確認後六月以内に、権利変更概要書等に基づき、確認事業者の早期での事業再生に関する計画(以下「早期事業再生計画」という。)を作成し、権利変更議案の内容を記載した書面と共に指定確認調査機関に提出しなければならないものとするなど、早期事業再生計画について所要の規定を設けることとした。(第一四条関係)
⑷ 指定確認調査機関は、⑶の規定による提出を受けたときは、権利変更議案及び早期事業再生計画等が一定の要件に該当するものであることについて調査を行わなければならないものとするなど、指定確認調査機関の調査について所要の規定を設けることとした。(第一五条関係)
⑸ 対象債権者集会を招集するには、確認事業者は、対象債権者集会の日の経済産業省令で定める日数前までに、対象債権者及び指定確認調査機関に対して、その通知を発しなければならないものとするなど、対象債権者集会の招集等について所要の規定を設けることとした。(第一六条関係)
⑹ 確認事業者は、⑸の通知(権利変更議案を決議するための対象債権者集会に係るものに限る。)に際しては、対象債権者に対し、権利変更議案の内容を記載した書面、早期事業再生計画、⑷の調査の結果を記載した書面その他議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「対象債権者集会書類」という。)及び対象債権者が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならないものとするなど、対象債権者集会書類及び議決権行使書面の交付等について所要の規定を設けることとした。(第一七条及び第一八条関係)
⑺ 対象債権者集会において権利変更議案を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。)の議決権の総額の四分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならないものとするなど、対象債権者の議決権及び対象債権者集会の決議等について所要の規定を設けることとした。(第一九条~第二五条関係)
⑻ 権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、確認事業者は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならないものとするなど、権利変更決議の認可の申立て及び裁判所による権利変更決議の認可又は不認可の決定に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第二六条及び第二七条関係)
⑼ 権利変更決議の認可の決定があったときは、対象債権者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更されるものとするなど、権利変更決議の効力について所要の規定を設けることとした。(第二八条関係)
⑽ 権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときは、⑼の規定にかかわらず、権利変更決議はその効力を生じ、対象債権者の権利は、権利変更決議の内容に従い、変更されるものとするなど、議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力について所要の規定を設けることとした。(第二九条関係)
㈢ 雑則
⑴ 2の規定による非訟事件(以下「対象債権者集会決議関連事件」という。)は、確認事業者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄するものとするなど、対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続について所要の規定を設けることとした。(第三〇条~第四三条関係)
⑵ 仮登記担保契約に関する法律第四条第一項(同法第二〇条において準用する場合を含む。)に規定する担保仮登記(同法第一四条(同法第二〇条において準用する場合を含む。)に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、2の規定の適用については、抵当権とみなすものとするなど、担保仮登記の取扱いについて所要の規定を設けることとした。(第四四条関係)
⑶ 2に定めるもののほか、対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続に関し必要な事項は最高裁判所規則で、その他2に定める手続に関し必要な事項は経済産業省令で、それぞれ定めるものとすることとした。(第四五条関係)
3 指定確認調査機関
㈠ 総則
⑴ 経済産業大臣は、一定の要件に該当すると認められる者を、その申請により、対象債権者集会関連業務(2に定める手続(対象債権者集会決議関連事件に関する裁判手続を除く。以下「対象債権者集会手続」という。)に係る2の規定による業務及び4の規定による業務並びにこれらに付随する業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができるものとするなど、指定確認調査機関の指定に関する手続について所要の規定を設けることとした。(第四六条及び第四七条関係)
⑵ 指定確認調査機関の確認調査員若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、対象債権者集会関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとするなど、指定確認調査機関の秘密保持義務等について所要の規定を設けることとした。(第四八条関係)
㈡ 業務
指定確認調査機関は、2の㈠の⑴の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しなければならないものとするなど、指定確認調査機関の業務等について所要の規定を設けることとした。(第四九条~第五四条関係)
㈢ 監督
指定確認調査機関の監督等について所要の規定を設けることとした。(第五五条~第六三条関係)
4 確認事業者に係る特例
㈠ 調停機関に関する特例
確認事業者が特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二条第二項に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第三条第二項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について対象債権者集会手続が実施されていた場合における調停機関に関する特例を設けることとした。(第六四条関係)
㈡ 監督委員に関する特例
再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る事業者について対象債権者集会手続が実施されていたときは、裁判所は、民事再生法第五四条第一項の処分をする場合には、確認調査員が当該対象債権者集会手続に係る対象債権者集会関連業務に従事していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする特例を設けるものとするなど、再生手続及び更生手続における監督委員に関する特例を設けることとした。(第六五条及び第六六条関係)
㈢ 社債権者集会に関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該確認事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができるものとするなど、社債の金額の減額に関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第六七条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の規定により指定確認調査機関が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第七三二条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該確認事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第七三三条第四号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとするなど、社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例を設けることとした。(第六八条関係)
㈣ 資金の借入れに関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、当該確認を受けた時から権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間における当該確認事業者の資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができるものとするなど、資金の借入れに関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第六九条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の基準に適合するものであることの確認を受けた資金の借入れをした確認事業者の再生手続において、当該確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案(民事再生法第一六三条第一項の再生計画案をいう。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが当該確認事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第一五五条第一項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとするなど、資金の借入れに関する再生手続及び更生手続の特例を設けることとした。(第七〇条及び第七一条関係)
㈤ 債権の弁済に関する特例
⑴ 確認事業者は、当該確認事業者に関し2の㈠の⑴の確認をした指定確認調査機関に対し、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間の原因に基づいて生じた債権が一定の要件に該当することの確認を求めることができるものとするなど、債権に関する指定確認調査機関の確認について所要の規定を設けることとした。(第七二条関係)
⑵ 裁判所は、⑴の要件に該当することの確認を受けた債権(以下「確認債権」という。)に係る債務を負担した確認事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三〇条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が⑴の要件に該当することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとするなど、債権の弁済に関する再生手続及び更生手続の特例を設けることとした。(第七三条~第七八条関係)
㈥ 破産手続等に係る指定確認調査機関の意見
指定確認調査機関は、確認事業者についての破産手続等において、当該破産手続等における一定の裁判に係る事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体に対し、その求めに応じて、意見を述べることができるものとすることとした。(第七九条関係)
5 罰則
罰則について所要の規定を設けることとした。(第八〇条~第九二条関係)
6 附則
㈠ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
㈡ 経過措置等について所要の規定を設けることとした。(附則第三条~第一〇条関係)
㈢ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一一条及び第一二条関係)
7 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -