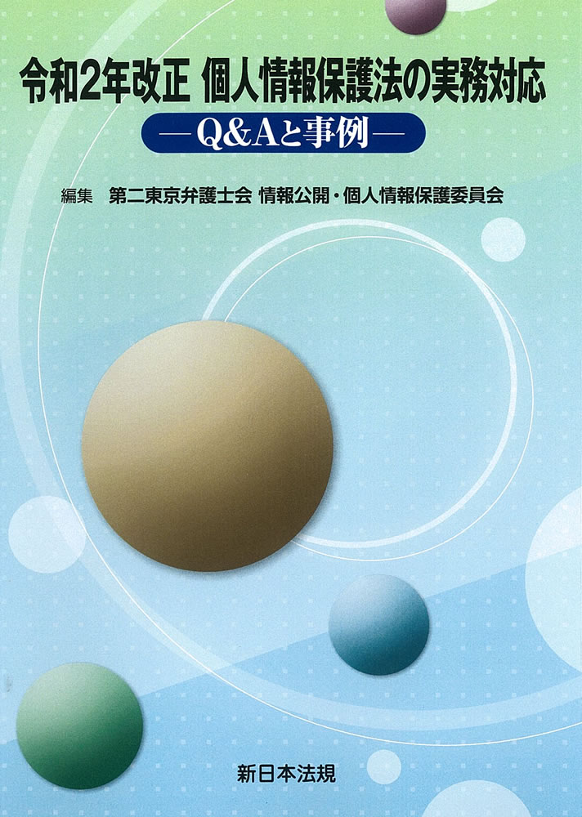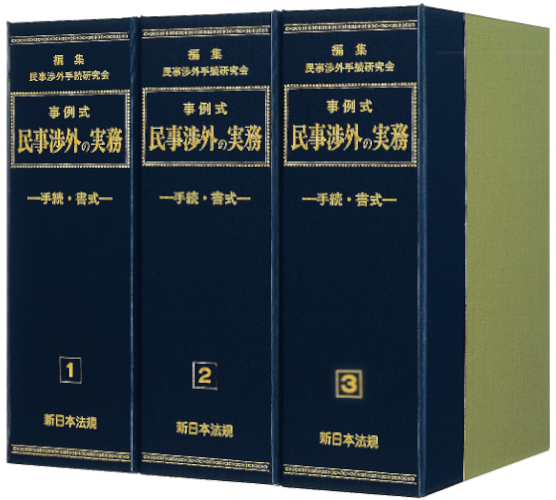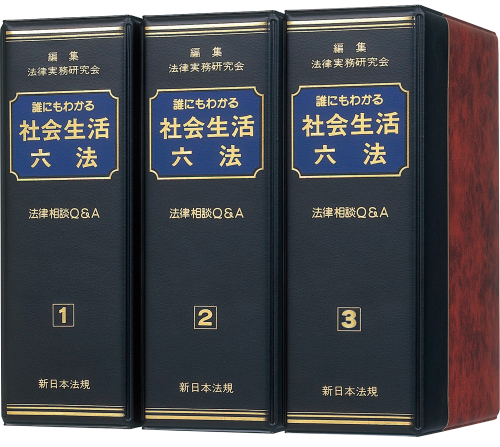PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
住民基本台帳法の一部改正(令和6年6月21日法律第60号〔附則第32条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和7年10月1日(政令第340号)において令和9年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和9年04月01日
法務省
昭和42年法律第81号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和9年04月01日
法務省
昭和42年法律第81号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三百四十号)(法務省)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行期日は、令和九年四月一日とする。
◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)(法務省・厚生労働省)
一 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係
1 特定技能の在留資格に係る基本方針の案を作成するとき、又は分野別運用方針を定めるときは、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならないこととした。(第二条の三第四項及び第二条の四第三項関係)
2 一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施は、登録支援機関以外の者に委託してはならないこととした。(第一九条の二二第二項関係)
3 永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消し等に関する規定の整備
(一) 永住許可の要件として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記することとした。(第二二条第二項関係)
(二) 永住者の在留資格をもって在留する者が、入管法に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと等を在留資格の取消事由として整備することとした。(第二二条の四第一項第八号及び第九号関係)
(三) 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、(二)の事由により在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、他の在留資格への変更を許可することとした。(第二二条の六関係)
(四) 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって在留資格取消事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとした。(第六二条の二関係)
4 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。)からの相談に応じ、援助を行う業務等を行うものとすることとした。(第六九条の二の二関係)
5 外国人に不法就労活動をさせるなどした者について、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第七三条の二関係)
6 別表第一の整備
(一) 企業内転勤の項の下欄に第二号を加え、企業内転勤(同号に係るものに限る。)の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の企業内転勤の項関係)
(二) 技能実習の項を育成就労の項に改め、育成就労の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の育成就労の項関係)
(三) 家族滞在の項の下欄に必要な整備を行うこととした。(別表第一の四の表の家族滞在の項関係)
二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正関係
1 法律の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めるとともに、育成就労産業分野(以下この1及び6において「分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成すること、分野における人材を確保することを法律の目的とすることとした。(題名及び第一条関係)
2 育成就労の適正な実施等に関する基本方針及び分野別運用方針の策定をすることとした。(第七条及び第七条の二関係)
3 育成就労計画に関する規定の整備
(一) 育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条及び第九条関係)
(二) 労働者派遣等の形態により行う監理型育成就労を行わせるものである場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条第二項及び第九条第二項関係)
(三) 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、育成就労実施者の変更を希望する旨を、育成就労実施者、監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申し出ることができること等とした。(第八条の二関係)
(四) 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に(三)に関する事務を行わせることができることとした。(第八条の三関係)
(五) (三)の申出をした育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、機構において職業紹介その他の援助等を行い、監理支援機関において連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第八条の四関係)
(六) (三)の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の五及び第九条の二関係)
(七) 育成就労認定が取り消されたこと等により育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の六及び第九条の三関係)
(八) 認定の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第一〇条関係)
(九) 個別育成就労産業分野を所管する行政機関の長は、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定の停止の措置を求め、又は停止の措置がとられた場合における再開の措置を求めることができることとした。(第一二条の二関係)
(一〇) 育成就労外国人が新たに認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となった場合における従前の育成就労計画の認定は、原則として新たに認定を受けた育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失うこととした。(第一八条関係)
4 監理支援機関に関する規定の整備
(一) 監理支援機関の許可の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第二三条及び第二五条関係)
(二) 許可の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第二六条関係)
(三) 監理支援機関が監理型育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法の特例に関する規定を整備することとした。(第二七条第一項関係)
(四) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年を下らない政令で定める期間等とすることとした。(第三一条第一項関係)
(五) 監理支援機関は、3(五)等の必要な措置を適切に行わなければならないこととした。(第三九条第三項関係)
(六) 監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、監理支援機関の業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならないこととした。(第三九条第五項関係)
5 分野別協議会及び地域協議会に関する規定を整備することとした。(第五四条及び第五六条関係)
6 機構に関する規定の整備
(一) 機構は、分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成をすること、分野における人材の確保に寄与することを目的とすることとした。(第五七条関係)
(二) 機構の業務に関する規定を整備することとした。(第八七条関係)
(三) 機構が育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法等の特例に関する規定を設けることとした。(第八七条の二関係)
(四) 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局は、3(五)等の業務が円滑に行われるよう、連携を図り、機構は、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、必要な情報の提供を行わなければならないこととした。(第一〇六条関係)
7 所要の罰則規定を設けることとした。(第一〇八条~第一一三条関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行期日は、令和九年四月一日とする。
◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(法律第六〇号)(法務省・厚生労働省)
一 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係
1 特定技能の在留資格に係る基本方針の案を作成するとき、又は分野別運用方針を定めるときは、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならないこととした。(第二条の三第四項及び第二条の四第三項関係)
2 一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施は、登録支援機関以外の者に委託してはならないこととした。(第一九条の二二第二項関係)
3 永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消し等に関する規定の整備
(一) 永住許可の要件として、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記することとした。(第二二条第二項関係)
(二) 永住者の在留資格をもって在留する者が、入管法に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと等を在留資格の取消事由として整備することとした。(第二二条の四第一項第八号及び第九号関係)
(三) 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、(二)の事由により在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、他の在留資格への変更を許可することとした。(第二二条の六関係)
(四) 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって在留資格取消事由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとした。(第六二条の二関係)
4 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、特定技能外国人(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。)からの相談に応じ、援助を行う業務等を行うものとすることとした。(第六九条の二の二関係)
5 外国人に不法就労活動をさせるなどした者について、五年以下の拘禁刑若しくは五〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとした。(第七三条の二関係)
6 別表第一の整備
(一) 企業内転勤の項の下欄に第二号を加え、企業内転勤(同号に係るものに限る。)の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の企業内転勤の項関係)
(二) 技能実習の項を育成就労の項に改め、育成就労の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動を定めることとした。(別表第一の二の表の育成就労の項関係)
(三) 家族滞在の項の下欄に必要な整備を行うこととした。(別表第一の四の表の家族滞在の項関係)
二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正関係
1 法律の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めるとともに、育成就労産業分野(以下この1及び6において「分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成すること、分野における人材を確保することを法律の目的とすることとした。(題名及び第一条関係)
2 育成就労の適正な実施等に関する基本方針及び分野別運用方針の策定をすることとした。(第七条及び第七条の二関係)
3 育成就労計画に関する規定の整備
(一) 育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条及び第九条関係)
(二) 労働者派遣等の形態により行う監理型育成就労を行わせるものである場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条第二項及び第九条第二項関係)
(三) 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、育成就労実施者の変更を希望する旨を、育成就労実施者、監理支援機関又は出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申し出ることができること等とした。(第八条の二関係)
(四) 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に(三)に関する事務を行わせることができることとした。(第八条の三関係)
(五) (三)の申出をした育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、機構において職業紹介その他の援助等を行い、監理支援機関において連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第八条の四関係)
(六) (三)の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の五及び第九条の二関係)
(七) 育成就労認定が取り消されたこと等により育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合の育成就労計画の認定の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第八条の六及び第九条の三関係)
(八) 認定の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第一〇条関係)
(九) 個別育成就労産業分野を所管する行政機関の長は、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定の停止の措置を求め、又は停止の措置がとられた場合における再開の措置を求めることができることとした。(第一二条の二関係)
(一〇) 育成就労外国人が新たに認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となった場合における従前の育成就労計画の認定は、原則として新たに認定を受けた育成就労計画に定められた育成就労の開始日に、その効力を失うこととした。(第一八条関係)
4 監理支援機関に関する規定の整備
(一) 監理支援機関の許可の申請及び基準に関する規定を整備することとした。(第二三条及び第二五条関係)
(二) 許可の欠格事由に関する規定を整備することとした。(第二六条関係)
(三) 監理支援機関が監理型育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法の特例に関する規定を整備することとした。(第二七条第一項関係)
(四) 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年を下らない政令で定める期間等とすることとした。(第三一条第一項関係)
(五) 監理支援機関は、3(五)等の必要な措置を適切に行わなければならないこととした。(第三九条第三項関係)
(六) 監理支援機関は、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、監理支援機関の業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならないこととした。(第三九条第五項関係)
5 分野別協議会及び地域協議会に関する規定を整備することとした。(第五四条及び第五六条関係)
6 機構に関する規定の整備
(一) 機構は、分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成をすること、分野における人材の確保に寄与することを目的とすることとした。(第五七条関係)
(二) 機構の業務に関する規定を整備することとした。(第八七条関係)
(三) 機構が育成就労に係る職業紹介事業を行う場合における職業安定法等の特例に関する規定を設けることとした。(第八七条の二関係)
(四) 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局は、3(五)等の業務が円滑に行われるよう、連携を図り、機構は、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、必要な情報の提供を行わなければならないこととした。(第一〇六条関係)
7 所要の罰則規定を設けることとした。(第一〇八条~第一一三条関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -