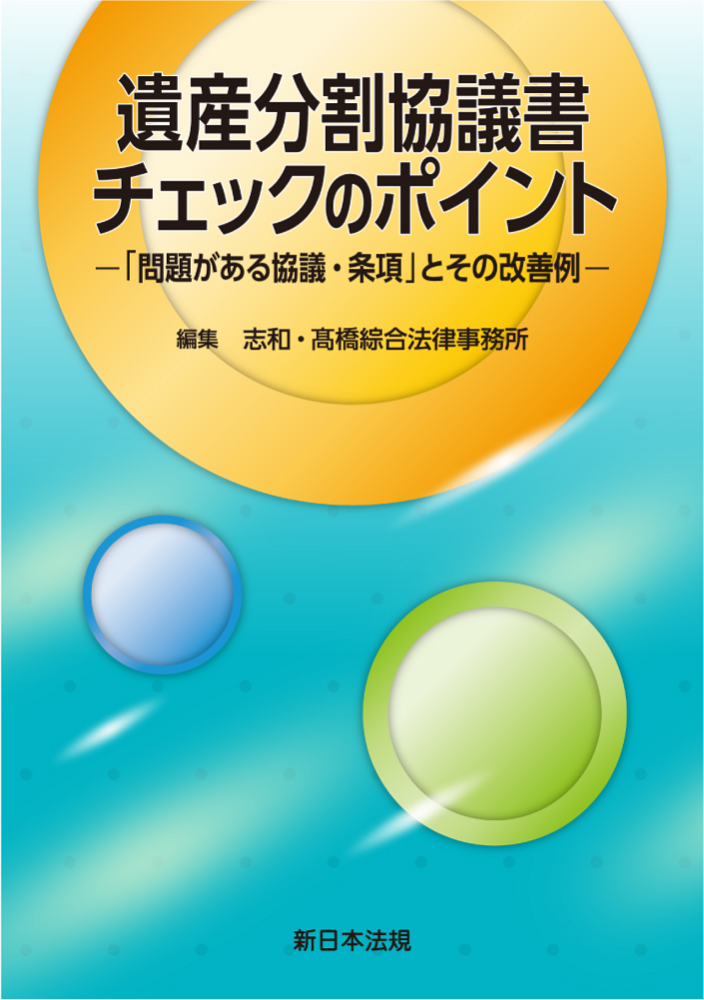資料1998年10月21日 【裁決事例】 相続税法第34条第2項の連帯納付義務には補充性は認められず、また、連帯納付義務者に対する差押処分は、財産の選択を誤った国税徴収法第49条に反するものとはいえないとされた事例(不動産の差押処分/棄却)
(平10.10.21裁決、裁決事例集No.56 435頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
原処分庁は、平成6年3月24日に死亡したE(以下「被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)開始に係る相続税について、共同相続人であるG及びH(以下「Gら」という。)の別表1に記載する滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、共同相続人9人全員に対し相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の規定による連帯納付義務額について、国税通則法(以下「通則法」という。)第37条《督促》第1項の規定に基づき督促をした。
次いで原処分庁は、督促後10日を経過しても本件滞納国税が完納されなかったため、平成9年11月14日付で本件相続の相続財産で未分割の別表2に記載する不動産(以下「本件差押物件」という。)について、共同相続人各人の法定相続分に応じて差押処分をした。
共同相続人の一人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の持分についてされた当該差押処分(以下「本件差押処分」という。)を不服として平成10年1月14日に異議申立てをしたところ、異議審理庁が同年4月3日付で棄却の異議決定をしたので、同年5月1日にその全部の取消しを求めて審査請求をした。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法、不当であるから、その全部の取消しを求める。
イ Gらは、相続税の納税資金として、相続財産の中からそれぞれ約239,000,000円を相続財産管理人を通じて受領しており、さらに固有資産としてP市T町1番10所在の土地及びその土地上の建物のほか5筆の土地を保有していることから、本件滞納国税の納税資金ないし納税資金調達能力を有しているにもかかわらず、原処分庁は、本来の納税義務者であるGらに対して強制的な徴税の執行を行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対して本件差押処分を行ったことは、違法、不当である。
ロ 仮に上記イの主張が認められないとしても、原処分庁は、差押物件の選択を誤っている。
すなわち、本件差押物件は、被相続人が生前からY株式会社(以下「Y社」という。)に賃貸し、Y社はこれを貸駐車場として事業の用に供しており、当該物件が公売されると一般顧客とY社の間の賃貸借関係について複雑な法律問題が発生し、かつ、Y社の経営に極めて大きな影響を与えることとなる。
他方、未分割の相続財産としてP市Q町15番7所在の土地(以下「A土地」という。)及び同番9所在の土地(以下「B土地」といい、A土地と併せて「Q町の物件」という。)が存在し、当該物件は本件滞納国税を大幅に上回る価値がある上、賃借権などの法律上の負担もなく換価も容易であることから、請求人は差押物件としてQ町の物件を選択するよう原処分庁に要望していた。
しかしながら、原処分庁がこの要望に耳を傾けず、敢えて本件差押処分を行ったことは、裁量権の著しい濫用である。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 請求人は、Gらの財産から優先して差押えをすべきであると主張するが、同一の被相続人から相続により取得した財産に係る相続税については、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、各相続人は互いに連帯して納付する義務があり(相続税法第34条)、また、相続人の一人に対し又は同時若しくは順次にすべての相続人に対して滞納処分ができる(通則法第8条《国税の連帯納付義務についての民法の準用》の規定により民法第432条準用)ことから、他の相続人の資力等は抗弁の対象にならない。
したがって、請求人には連帯納付義務があるところ、Gらの相続税が完納されなかったため、連帯納付義務額に係る督促処分を経て本件差押処分を行ったものである。
ロ また、請求人は、差押物件の選択が誤っていると主張するが、Q町の物件は被相続人が自宅として利用していた土地部分の一画であり、しかも、請求人を含む他の相続人所有の不動産と共に強固な塀で囲まれ一体化されている。
一方、本件差押物件は、Y社に賃貸され青空駐車場として利用されているが、同物件上には建築物はなく、また、不動産登記簿上においても抵当権及び賃借権等の権利の設定はされていないことから、Q町の物件よりも本件差押物件の方が換価が容易であると判断して本件差押処分を行ったものであり、差押財産の選択は適切である。
3 判断
本件審査請求の争点は、本来の納税義務者に対する徴税の執行が連帯納付義務者に対する滞納処分の前提要件となるか否か及び差押財産の選択の適否にあるので、以下審理する。
(1)請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によると、次の事実が認められる。
イ 不動産登記簿によると、本件差押物件上には、抵当権等の土地に関する権利の設定はされていない。
ロ 本件相続開始に係る相続税の申告書による本件差押物件の価額は、自用地としての価額から賃借権の価額として5パーセント相当額を減算している。
ハ Q町の物件は、請求人、共同相続人であるJ及びK(以下、請求人及びJと併せて「請求人ら」という。)の固有の土地と共に周囲を塀で囲まれており、当該塀は、道路に面した部分が約4メートル、南側の隣接地との境界部分が約10メートルの高さでいずれも強固なものである。
なお、Q町の物件の実測平面図によると、A土地及びB土地双方ともに建物が建築されている。
(2)請求人は、当審判所に対し次のとおり答述している。
イ 本件差押物件の賃貸料は、被相続人の生前からY社との間において定められているが、契約書等は取り交わされていない。
ロ 請求人が代表取締役であるY社は、本件差押物件のうち、P市R町2丁目204番ないし206番所在の土地については約50パーセントを株式会社X(以下「X社」という。)にショッピングセンター駐車場用地として賃貸し、当該土地の残りの部分と同市W町1丁目319番1及び468番11所在の土地については一般顧客に月極駐車場として賃貸している。
なお、Y社とX社及び一般顧客との間において保証金等の授受はない。
ハ 本件差押物件はいずれも青空駐車場であり、建物及び設備等は建築されていない。
ニ A土地上には被相続人名義の建物が存し請求人が居住している。また、B土地上には、Jの居宅が存している。
なお、K所有の土地上には同人の居宅が存している。
(3)ところで、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、相続人が二人以上いる場合に各相続人に対し、自ら負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに、他の相続人の相続税の納税義務について、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として連帯して納付する責任を負担させているもので、これは、相続税の徴収の確保を図るために相互に各相続人に課した特別の責任であると解される。そして、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、各相続人の固有の相続税の納税義務が確定すれば、国税の徴収に当たる所轄庁は直ちに連帯納付義務者に対して徴収手続を行うことができると解され、本来の納税義務についての履行責任を連帯納付義務者に補充的に負わせるものではない。
このことは、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第32条《第二次納税義務の通則》に規定する第二次納税義務者又は通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する保証人から国税を徴収する要件として、徴収法第33条《無限責任社員の第二次納税義務》ないし第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》及び第41条《人格のない社団等に係る第二次納税義務》並びに通則法第52条《担保の処分》において、本来の納税義務者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められる場合に限り、補充的に第二次納税義務者又は保証人から徴収する旨規定しているが、連帯納付義務者に対してはこのような規定がないことからも明らかである。
また、通則法第8条において、連帯納付義務における民法の規定を準用しているところ、民法第432条では履行の順位を定めていないのであるから、差押時における各納税義務者の資力の多寡が差押順位に影響を及ぼすものではない。
以上のことから、本来の納税義務者に対する徴税の執行が連帯納付義務者に対する滞納処分の前提要件ではなく、Gらに対する強制的な徴税の執行を行うことなくされたとして本件差押処分を違法、不当とする請求人の主張には理由がない。
(4)次に、差押財産の選択について、以下、検討する。
イ 差押財産の選択については、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》、同法第75条《一般の差押禁止財産》、同法第76条《給与の差押禁止》、同法第77条《社会保険制度に基づく給付の差押禁止》及び同法第78条《条件付差押禁止財産》等の規定により差押えが禁止されている財産があるほか、同法第49条《差押財産の選択に当っての第三者の権利の尊重》の規定により、徴収職員は滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならないとされているが、明文上の規定がない事項については、専ら徴収職員の合理的な裁量にゆだねられているものと解されている。
なお、第三者が有する権利を害さないように努めなければならないとは、差押えに当たって滞納者の全財産を調査して、その中から第三者の権利の対象となっていない財産を差し押さえることまでを要求するものではなく、例えば、徴収職員が差押えに当たって通常の調査をした結果、差し押さえ得る財産が二つあることが判明した場合において、一方には抵当権が設定されており、他方は第三者の権利の対象となっていない場合で、かつ、この財産により滞納国税の額を満足させることができる場合は、後者を差し押さえなければならないとの趣旨であると解される。
ロ ところで、Q町の物件は、前記(1)のハ及び(2)のニのとおり請求人らの固有の土地と共に周囲を強固な塀で囲まれており、しかも、同物件上には建物が建築され居住の用に供されていることから、当該物件を公売するとした場合、法定地上権等の新たな権利関係が発生することもあり、その利用状況及び権利関係を勘案すると相当な換価の困難性が見込まれる。
一方、本件差押物件は、前記(1)のロ及び(2)のイからY社が賃借権を有すると認められるものの、前記(1)のイ並びに(2)のロ及びハのとおり、いわゆる青空駐車場として利用されているものであり、抵当権等の土地に関する権利の設定はない。
また、Y社とX社及び一般顧客の間において保証金の授受はない上、駐車場の利用権はその土地自体に及ぼす権利ではないので、複雑な法律上の問題が発生するということは認められない。
ハ 以上のことから、原処分庁が本件差押物件の方が換価が容易であるとして行った原処分には合理性があり、Q町の物件を選択しなかった本件差押処分は裁量権の著しい濫用であるとする請求人の主張は、採用することができない。
(5)原処分のその他の部分については請求人は争わず、当審判所の調査によってもこれを不相当とする理由は認められない。
別表1 滞納国税の明細
(単位:円)
滞納者 税目 納 期 限 本 税 延 滞 税
G 相続税 平成6年11月24日 438,874,900 法律による金額
H 相続税 平成6年11月24日 438,874,900 法律による金額
別表2 差押物件の明細
(単位:平方メートル)
所 在 地 地目 地 積
S市R町2丁目204番 宅地 640.59
S市R町2丁目205番 宅地 462.08
S市R町2丁目206番 宅地 1,354.87
S市W町1丁目319番1 宅地 436.36
S市W町1丁目468番11 宅地 290.38
上記のうち各共同相続人の持ち分 9分の1
《裁決書(抄)》
1 事実
原処分庁は、平成6年3月24日に死亡したE(以下「被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)開始に係る相続税について、共同相続人であるG及びH(以下「Gら」という。)の別表1に記載する滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)を徴収するため、共同相続人9人全員に対し相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の規定による連帯納付義務額について、国税通則法(以下「通則法」という。)第37条《督促》第1項の規定に基づき督促をした。
次いで原処分庁は、督促後10日を経過しても本件滞納国税が完納されなかったため、平成9年11月14日付で本件相続の相続財産で未分割の別表2に記載する不動産(以下「本件差押物件」という。)について、共同相続人各人の法定相続分に応じて差押処分をした。
共同相続人の一人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の持分についてされた当該差押処分(以下「本件差押処分」という。)を不服として平成10年1月14日に異議申立てをしたところ、異議審理庁が同年4月3日付で棄却の異議決定をしたので、同年5月1日にその全部の取消しを求めて審査請求をした。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法、不当であるから、その全部の取消しを求める。
イ Gらは、相続税の納税資金として、相続財産の中からそれぞれ約239,000,000円を相続財産管理人を通じて受領しており、さらに固有資産としてP市T町1番10所在の土地及びその土地上の建物のほか5筆の土地を保有していることから、本件滞納国税の納税資金ないし納税資金調達能力を有しているにもかかわらず、原処分庁は、本来の納税義務者であるGらに対して強制的な徴税の執行を行うことなく、自己の相続税を完納した請求人に対して本件差押処分を行ったことは、違法、不当である。
ロ 仮に上記イの主張が認められないとしても、原処分庁は、差押物件の選択を誤っている。
すなわち、本件差押物件は、被相続人が生前からY株式会社(以下「Y社」という。)に賃貸し、Y社はこれを貸駐車場として事業の用に供しており、当該物件が公売されると一般顧客とY社の間の賃貸借関係について複雑な法律問題が発生し、かつ、Y社の経営に極めて大きな影響を与えることとなる。
他方、未分割の相続財産としてP市Q町15番7所在の土地(以下「A土地」という。)及び同番9所在の土地(以下「B土地」といい、A土地と併せて「Q町の物件」という。)が存在し、当該物件は本件滞納国税を大幅に上回る価値がある上、賃借権などの法律上の負担もなく換価も容易であることから、請求人は差押物件としてQ町の物件を選択するよう原処分庁に要望していた。
しかしながら、原処分庁がこの要望に耳を傾けず、敢えて本件差押処分を行ったことは、裁量権の著しい濫用である。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 請求人は、Gらの財産から優先して差押えをすべきであると主張するが、同一の被相続人から相続により取得した財産に係る相続税については、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、各相続人は互いに連帯して納付する義務があり(相続税法第34条)、また、相続人の一人に対し又は同時若しくは順次にすべての相続人に対して滞納処分ができる(通則法第8条《国税の連帯納付義務についての民法の準用》の規定により民法第432条準用)ことから、他の相続人の資力等は抗弁の対象にならない。
したがって、請求人には連帯納付義務があるところ、Gらの相続税が完納されなかったため、連帯納付義務額に係る督促処分を経て本件差押処分を行ったものである。
ロ また、請求人は、差押物件の選択が誤っていると主張するが、Q町の物件は被相続人が自宅として利用していた土地部分の一画であり、しかも、請求人を含む他の相続人所有の不動産と共に強固な塀で囲まれ一体化されている。
一方、本件差押物件は、Y社に賃貸され青空駐車場として利用されているが、同物件上には建築物はなく、また、不動産登記簿上においても抵当権及び賃借権等の権利の設定はされていないことから、Q町の物件よりも本件差押物件の方が換価が容易であると判断して本件差押処分を行ったものであり、差押財産の選択は適切である。
3 判断
本件審査請求の争点は、本来の納税義務者に対する徴税の執行が連帯納付義務者に対する滞納処分の前提要件となるか否か及び差押財産の選択の適否にあるので、以下審理する。
(1)請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によると、次の事実が認められる。
イ 不動産登記簿によると、本件差押物件上には、抵当権等の土地に関する権利の設定はされていない。
ロ 本件相続開始に係る相続税の申告書による本件差押物件の価額は、自用地としての価額から賃借権の価額として5パーセント相当額を減算している。
ハ Q町の物件は、請求人、共同相続人であるJ及びK(以下、請求人及びJと併せて「請求人ら」という。)の固有の土地と共に周囲を塀で囲まれており、当該塀は、道路に面した部分が約4メートル、南側の隣接地との境界部分が約10メートルの高さでいずれも強固なものである。
なお、Q町の物件の実測平面図によると、A土地及びB土地双方ともに建物が建築されている。
(2)請求人は、当審判所に対し次のとおり答述している。
イ 本件差押物件の賃貸料は、被相続人の生前からY社との間において定められているが、契約書等は取り交わされていない。
ロ 請求人が代表取締役であるY社は、本件差押物件のうち、P市R町2丁目204番ないし206番所在の土地については約50パーセントを株式会社X(以下「X社」という。)にショッピングセンター駐車場用地として賃貸し、当該土地の残りの部分と同市W町1丁目319番1及び468番11所在の土地については一般顧客に月極駐車場として賃貸している。
なお、Y社とX社及び一般顧客との間において保証金等の授受はない。
ハ 本件差押物件はいずれも青空駐車場であり、建物及び設備等は建築されていない。
ニ A土地上には被相続人名義の建物が存し請求人が居住している。また、B土地上には、Jの居宅が存している。
なお、K所有の土地上には同人の居宅が存している。
(3)ところで、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務は、相続人が二人以上いる場合に各相続人に対し、自ら負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに、他の相続人の相続税の納税義務について、当該相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として連帯して納付する責任を負担させているもので、これは、相続税の徴収の確保を図るために相互に各相続人に課した特別の責任であると解される。そして、その義務履行の前提条件をなす連帯納付義務の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではなく、各相続人の固有の相続税の納税義務が確定すれば、国税の徴収に当たる所轄庁は直ちに連帯納付義務者に対して徴収手続を行うことができると解され、本来の納税義務についての履行責任を連帯納付義務者に補充的に負わせるものではない。
このことは、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第32条《第二次納税義務の通則》に規定する第二次納税義務者又は通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する保証人から国税を徴収する要件として、徴収法第33条《無限責任社員の第二次納税義務》ないし第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》及び第41条《人格のない社団等に係る第二次納税義務》並びに通則法第52条《担保の処分》において、本来の納税義務者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められる場合に限り、補充的に第二次納税義務者又は保証人から徴収する旨規定しているが、連帯納付義務者に対してはこのような規定がないことからも明らかである。
また、通則法第8条において、連帯納付義務における民法の規定を準用しているところ、民法第432条では履行の順位を定めていないのであるから、差押時における各納税義務者の資力の多寡が差押順位に影響を及ぼすものではない。
以上のことから、本来の納税義務者に対する徴税の執行が連帯納付義務者に対する滞納処分の前提要件ではなく、Gらに対する強制的な徴税の執行を行うことなくされたとして本件差押処分を違法、不当とする請求人の主張には理由がない。
(4)次に、差押財産の選択について、以下、検討する。
イ 差押財産の選択については、徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》、同法第75条《一般の差押禁止財産》、同法第76条《給与の差押禁止》、同法第77条《社会保険制度に基づく給付の差押禁止》及び同法第78条《条件付差押禁止財産》等の規定により差押えが禁止されている財産があるほか、同法第49条《差押財産の選択に当っての第三者の権利の尊重》の規定により、徴収職員は滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならないとされているが、明文上の規定がない事項については、専ら徴収職員の合理的な裁量にゆだねられているものと解されている。
なお、第三者が有する権利を害さないように努めなければならないとは、差押えに当たって滞納者の全財産を調査して、その中から第三者の権利の対象となっていない財産を差し押さえることまでを要求するものではなく、例えば、徴収職員が差押えに当たって通常の調査をした結果、差し押さえ得る財産が二つあることが判明した場合において、一方には抵当権が設定されており、他方は第三者の権利の対象となっていない場合で、かつ、この財産により滞納国税の額を満足させることができる場合は、後者を差し押さえなければならないとの趣旨であると解される。
ロ ところで、Q町の物件は、前記(1)のハ及び(2)のニのとおり請求人らの固有の土地と共に周囲を強固な塀で囲まれており、しかも、同物件上には建物が建築され居住の用に供されていることから、当該物件を公売するとした場合、法定地上権等の新たな権利関係が発生することもあり、その利用状況及び権利関係を勘案すると相当な換価の困難性が見込まれる。
一方、本件差押物件は、前記(1)のロ及び(2)のイからY社が賃借権を有すると認められるものの、前記(1)のイ並びに(2)のロ及びハのとおり、いわゆる青空駐車場として利用されているものであり、抵当権等の土地に関する権利の設定はない。
また、Y社とX社及び一般顧客の間において保証金の授受はない上、駐車場の利用権はその土地自体に及ぼす権利ではないので、複雑な法律上の問題が発生するということは認められない。
ハ 以上のことから、原処分庁が本件差押物件の方が換価が容易であるとして行った原処分には合理性があり、Q町の物件を選択しなかった本件差押処分は裁量権の著しい濫用であるとする請求人の主張は、採用することができない。
(5)原処分のその他の部分については請求人は争わず、当審判所の調査によってもこれを不相当とする理由は認められない。
別表1 滞納国税の明細
(単位:円)
滞納者 税目 納 期 限 本 税 延 滞 税
G 相続税 平成6年11月24日 438,874,900 法律による金額
H 相続税 平成6年11月24日 438,874,900 法律による金額
別表2 差押物件の明細
(単位:平方メートル)
所 在 地 地目 地 積
S市R町2丁目204番 宅地 640.59
S市R町2丁目205番 宅地 462.08
S市R町2丁目206番 宅地 1,354.87
S市W町1丁目319番1 宅地 436.36
S市W町1丁目468番11 宅地 290.38
上記のうち各共同相続人の持ち分 9分の1
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.