解説記事2003年02月03日 【実務解説】 新株予約権、ストック・オプションの実務対応 第1回 新株予約権、ストック・オプションの概要(2003年2月3日号・№5)
実務解説
新株予約権、ストック・オプションの実務対応
公認会計士・税理士 棟田裕幸
第1回 新株予約権、ストック・オプションの概要
1. はじめに
平成14年4月施行の商法改正により、新株予約権が登場しました。新株予約権とは、新株予約権の発行時にあらかじめ定めた価額で会社の株式を会社から取得することのできる権利をいいます。
従来から新株引受権やストック・オプションは存在し、実務界でも使われてきましたが、これらとどのように異なるのか、またどのように進化したのでしょうか。
新株予約権について、その全体像、その本質的な意味合いを明らかにした上で、税務がどのように対応しているのか、会計処理はどのようにするのか等を、課題を含めて解明して行きたいと思います。
とかくわかりにくい新株予約権ですが、図解や設例を使い、よりビジュアルなものにして行きたいと思っております。
解説は4回シリーズで進めることとし、各回の内容は次の通りといたします。
第1回の今回は、改正商法で登場した新株予約権とは、従来の新株予約権やストック・オプションとどう違うのか、どのような使い道があるのか、またどうすれば発行できるのか等について次の流れで解説します。
1.はじめに
2.新株予約権、ストック・オプションとは
3.新株予約権と新株引受権との違い
4.ストック・オプション制度の改正前と改正後との違い
5.新株予約権の発行手続
6.新株予約権、ストック・オプションの様々な使い道
7.課題
第2回は、新株予約権の発行・行使・消滅・譲渡・相続そして取得株式の譲渡という各段階において課税関係の発生が考えられますが、これがどうなるのかを解説します。
第3回では、行使時の課税所得区分につき、所得税基本通達の考え方と、このたび注目されているストック・オプション課税判決について、その内容を解説し検討して行きます。
第4回は、会計処理と今後の課題について解説いたします。
2. 新株予約権、ストック・オプションとは
平成14年4月施行の商法改正により、新株予約権が登場しました。新株予約権とは、新株予約権の発行時にあらかじめ定められた価額で会社の株式を会社から取得することのできる権利をいい、これを表象するものが新株予約権証券であり、これは有価証券となります。この新株予約権証券を所有する者は、将来この会社の株価がどんなに上昇してもあらかじめ定められた価額で取得できる特典を有しています。逆に将来この会社の株価が下落し、あらかじめ定められた価額よりも低くなってしまった場合には、もはやこの権利を行使せず権利を放棄することとなるでしょう。
このように新株予約権は、将来株価が上昇する場合にはプラチナペーパーにもなりますが、逆に将来の株価の下落により単なる紙切れになるというリスクも有しています。この意味でこれは株式の取得に関する選択権(コール・オプション、すなわち買う権利)の性格を有したものといえます。
改正前の商法は、このような株式のコール・オプションの存在は認めていたものの、その価値を全面的に認めていたわけではありませんでした。しかし改正商法は、そのオプションの権利としての価値を認知いたしました。そこでオプションの単独発行(通常は有償発行となります)も認めることとなりました。このように新株予約権には、オプション権としての有価証券の地位が与えられることとなりました。
なお、新株予約権が無償で発行される場合がありますが、その典型がストック・オプションといわれるものです。
このように新株予約権とは、会社に株式の取得を要求することのできる権利であり、これを有するものが、会社に対してこの権利を行使した場合、会社はその者に対して、新株を発行しまたはこれに代えて当該会社の所有する自己株式を移転する義務を負うこととなります(商法280条の191)。
その発行関係を図示すると次のようになります。
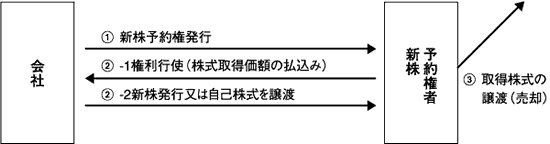
ここに、新株予約権の発行においては、原則として新株予約権の時価を算定し、取得者はその価額を会社に払込んで新株予約権という有価証券を取得します。これを無償にて発行するものが、新株予約権の有利発行の典型であるストック・オプションということになります。
この新株予約権には次の2つのものがあります。
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
新株予約権の単独発行の場合を例にとり、その流れを見てみます。
<設例>
1新株予約権の発行時 株式の時価50
新株予約権の時価10
権利行使価額を50と設定
2新株予約権の権利行使時(権利行使により株式を取得)
行使価額50を払込む
株式時価200
3取得株式の譲渡 株式時価250で譲渡
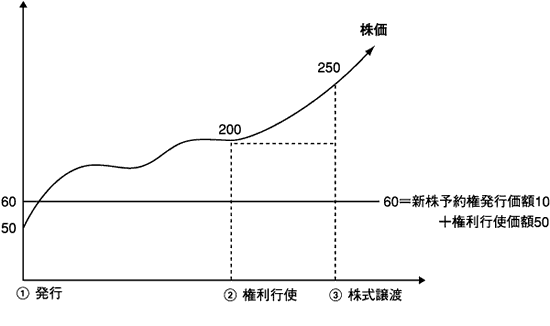
このように新株予約権を発行するとその後、権利行使による株式取得、取得株式の譲渡(売却)という各段階が生じます。
この例では、新株予約権の発行に際して、新株予約権自体の時価10を算定し、新株予約権を取得する者は、この10を会社に払込み、新株予約権という有価証券を取得しています。そして権利行使時には、その権利行使価額50を会社に払込みます。このように新株予約権の権利行使により株式取得をする場合のその取得価額は、これらの合計額となります。
前述したように新商法のもとでは、新株予約権というオプション自体に価値が認知されたため、その取得は有価証券の取得に該当することとなりました。したがって、その取得は当然に有償で行なうことが原則的な取得形態となります。ここが商法上も税務上も気をつけなければならない重要なポイントとなります。
すなわち、商法上はこの新株予約権を無償で第三者に発行することとなれば(すなわちストック・オプションの場合)、それは既存株主以外の者への有利発行となります。また、税務上もこのような無償での有利発行が行なわれると、その取得者に経済的利益が発生したと考えられ、課税が発生する余地が生じます。
なお、上記の1~3各段階のほかに、権利行使をせずに何らかの理由で、新株予約権が消滅する場合(期限徒過による消滅又は発行時に定めた消却事由の該当による消却の場合等)があり、また、新株予約権自体を譲渡するという場合もあります。さらには新株予約権の相続も考えられます。そこで、ここに新株予約権の発行後に考えられるパターンを整理してみます。
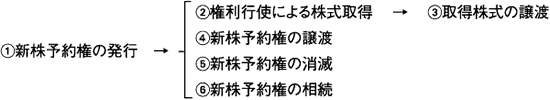
この1~4各段階において、経済的利益が発生するとその時に課税が生じる余地が発生します。また、5新株予約権を取得した者に相続が発生すると、相続税の問題が発生します。これらについては、第2回で解説します。
3. 新株予約権と新株引受権との違い
用語の使い方になりますが、重要なので解説しておきます。
旧商法では「新株引受権」がありました。改正商法では「新株予約権」及び「新株引受権」が並存しています。各々どのようなもので、何が変わったのか以下にまとめます。
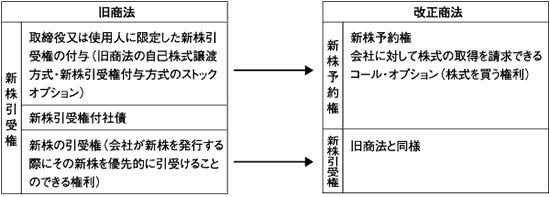
すなわち、旧商法のストック・オプションの付与は自己株式譲渡方式と新株引受権付与方式でしたが、改正商法は両社を統合して、ストック・オプションを新株予約権の有利発行としてまとめました。また旧商法ではストック・オプション以外の新株引受権は、新株引受権付社債又は転換社債に付してしか発行できなかったが、改正商法では新株予約権の単独発行(有償による通常発行)も可能となりました。これは、オプションの公正価値の算定が可能となったことも要因としてあげられます。
なお、現在の新株予約権のその種類毎の変化をまとめたものが以下のものです。
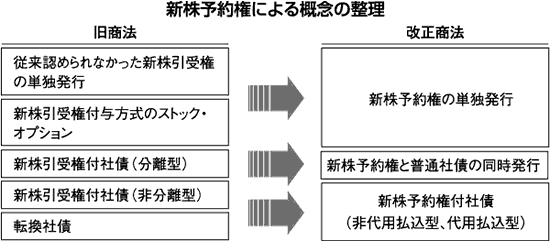
4. ストック・オプション制度の改正前と改正後との違い
ここでは、ストック・オプションに限定して、商法の改正前と改正後とのその違いについて見ていきます。
近年、インセンティブプランとしてのストック・オプションの必要性が高まりましたが、商法上以前はストック・オプションの考え方がありませんでした。そこで平成7年以降、本来は資金調達手段であるはずの分離型新株引受権付社債を利用した擬似ストック・オプションというものの付与が実務界では行なわれていました。
その後平成9年の商法改正により、商法上のストック・オプションとしての自己株式譲渡方式のストック・オプション及び新株引受権付与方式のストック・オプションが導入されました。しかしこれらは、個々の付与対象者の氏名につき株主総会決議が必要とされ、また、付与対象者の範囲(取締役又は使用人に限定)、行使期間(10年)及び付与できる株式数(発行済み株式総数の1/10)等、数々の制限があったことから、実務界では、より制約の少ない擬似ストック・オプションが依然として発行されていました。
このため、ストック・オプション制度をより活用しやすく実効性のあるものとすべく、改善が求められ、結局平成14年4月施行改正商法にて、従前のものと比較して以下のようなものに進化するに至りました。
1付与可能な株式数制限を撤廃
従来の発行済株式総数の1/10を超えない範囲としていた付与株式数の制限を撤廃した。
2権利行使期間の制限を撤廃
権利行使期間を株主総会付与決議日から10年以内としていた制限を撤廃した。
3付与対象者の制限を撤廃
付与対象者を、会社の取締役・使用人に限定していた制限を撤廃した。これにより付与対象者は、監査役、パートタイマー、他社からの出向社員、派遣社員、外部コンサルタント、弁護士、税理士、公認会計士、取引先、子会社・関連会社の取締役等への付与も可能となりました。
4付与対象者の氏名、付与決議の種類・数についての株主総会決議が不要
ストック・オプションの付与は、新株予約権の有利発行の一形態として、総会の特別決議が必要ですが、総会決議において、付与対象者の氏名や各人ごとの付与株式数を決議する必要はないとの解釈が採られています。但し、事後開示として営業報告書への記載は要します(商法施行規則84条111号)。
5行使時の株式選択が自由
新株予約権が行使されたときに新株予約権者に渡す株式を、新株を発行するか、会社が有する自己株式(金庫株)を移転するかをあらかじめ決めずに、会社がその行使時に選択できるようになりました。
5. 新株予約権の発行手続
新株予約権の発行は、取締役会決議で行なえることとなりましたが、有利発行の場合(ストック・オプションの発行は有利発行に該当する)は、株主総会の特別決議を必要とします。新株予約権の商法上の発行手続フローは次のようになります。
下記は新株予約権の発行手続フローで、新株予約権を単独で発行する場合を想定しています。すなわち、新株予約権を時価で評価してこれを有償にて発行する場合(通常発行)と、無償にて有利発行する場合のその典型としてのストック・オプションの場合とが考えられます。
このほかに、新株予約権付社債の発行の場合もありますが、その発行手続フローは、下記とほとんど同様です。
なお、下記の発行手続の中に「3有価証券通知書、有価証券届出書の提出」がありますが、これは、証券取引法上提出が求められるもので、要件に該当すると届出義務が生じます。気をつけなければならないので、第4回で解説する予定です。
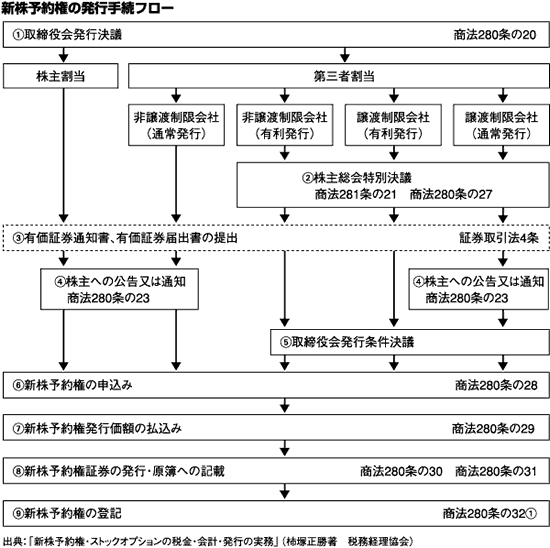
6. 新株予約権、ストック・オプションの様々な使い道
新株予約権、その無償取得としてのストック・オプションは、実務界ではすでに様々な活用が行なわれています。現に日本証券業協会の調べによると、平成14年4月~11月の8ヶ月間における全国上場企業による国内での新株予約権発行は、388件、金額(行使された場合の金額)で538,207百万円に上りました。また、昨年6月の株主総会では、約420社が新株予約権を使ったストック・オプションの付与を決議しています(以上、平成15年1月17日付、日経朝刊より)。
様々な使い道をここに解説いたします。
(1)インセンティブ・プランとしての活用
通常ストック・オプションとして、会社の取締役又は使用人等を対象に付与するもので、選ばれたものにその貢献度合い又は期待度合いに応じて付与することにより、より一層の貢献意欲・帰属意識・勤労意識の増進を図ろうとするものです。
商法改正により、前述のように取締役や使用人のほかに、子会社・関連会社の取締役、さらには取引先等外部者にも付与できるようになり、これら外部者の協力を得やすい環境を作ることができるようになりました。
(2)株式上場の資本政策における活用
まずは商法上の持株比率と株主の支配権(株主総会における支配権)との関係を示します。
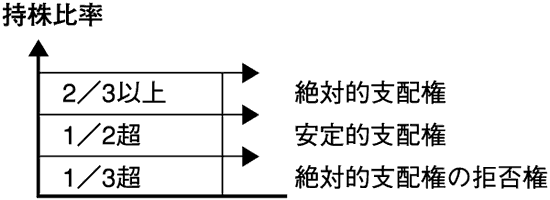
商法上、株主は議決権ある株式の2/3以上を所有すれば、株式会社の絶対的支配権を持つことができます。
逆に、1/3超を第三者に所有されると、この絶対的支配権が拒否される可能性が生じます。
議決権の1/2超の所有により、役員の選任決議等の株主総会の普通決議ができ、安定的支配が可能となります。
株式上場の資本政策では、上場により一般投資家が多数介入しますが、会社オーナーを中心とした安定株主の比率が1/2超、望ましくは2/3超あれば、その後も安定的な支配権の下に経営が行なわれることとなるため、事前にこのための対策をいたします。
株式上場のために、ベンチャーキャピタルや一般投資家の資本参加は受けたいが、一定の持株比率を確保することが必要な場合は、安定株主である社長、役員等に上場前の早い段階で新株予約権を発行しておくことにより持株比率の希薄化を防止することができます。例えば以下の例のように、ベンチャーキャピタルの第三者割当増資の引受けにより、持株比率が大きく崩れる場合にこれが活用できます。
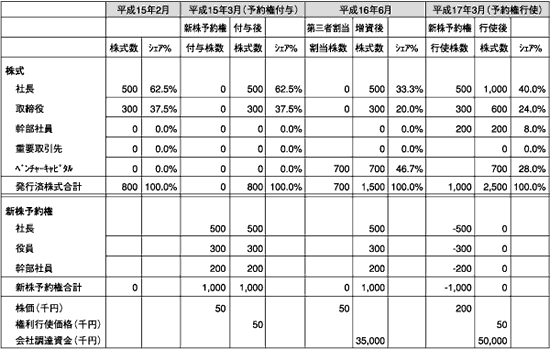
このように、新株予約権を株価が低いうち(5万円)に発行しておくと、その後ベンチャーキャピタル等の資本参加により、社長等安定株主の持株比率が低くなったとしても、その後の株価上昇(20万円)に影響されない低い価格での権利行使価格により株式が取得でき、安定株主比率を復活させることができます。
(3)M&Aにおける活用
実務界では、西友のウォルマートによる買収が、次のように新株予約権をうまく使った段階的資本参加として行なわれております。
平成14年5月31日に西友はウォルマートを対象にした3種の新株予約権を無償にて発行し、この新株予約権の行使期間を3段階(それぞれ平成14年12月27日、17年12月28日、19年12月28日)に分けました。すなわち、第1回新株予約権を行使するとウォルマートの議決権比率は1/3となり、第2回の行使により1/2、第3回までを行使すると2/3超となるというものです。このスキームは、ウォルマートに買収予約権を与えたものでありますが、同時に、権利行使期間の段階的設定は、資本参加者にそのリスクを軽減する効果を与えたものといえます。
(4)敵対的買収の防衛としての活用
第三者がTOB(株式の公開買付)手続を開始した場合に、第三者が一定割合(例えば1/3超)の株式を取得した場合等を行使条件として、経営陣や取引先に新株予約権を発行するというものです。この場合、新株予約権に譲渡制限を付けること、行使条件や消却事由も制限を置くべきことに注意すべきです。
(5)資金調達における活用
日本政策投資銀行は、新規事業の資金融資の方法として「新株予約権付融資」を実行したと発表しました。報道によると、融資先が発行する新株予約権を確保する代わりに、融資金利を軽減するとのことです(日経平成14年5月24日朝刊)。このように、新株予約権をファイナンスの条件を有利にするための甘味料として利用することも考えられます。
(6)事業承継における活用
特定した事業承継者に新株予約権を大きく付与しておけば、事業承継者の資金工面がつき次第、過半数までの株式を所有するよう権利を確保しておくことができます。権利行使の期限の制約はなく、また権利行使により発行する株式数は、譲渡制限のある会社は授権株数の制約もない(商法166条4但し書)ので、事業承継者の年齢、資金状況等を勘案した上で、新株予約権の付与内容を設定することができます。
7. 課題
以上述べた通り、新株予約権、ストック・オプションは、実効性のあるものとして制度上改善がなされ、実務界でも広く活用されてきています。
しかし、このような新株予約権ではありますが、実務上次のような課題もあります。
(1)新株予約権の評価方法
新株予約権は株式のコール・オプションのひとつですので、ブラック=ショールズ・モデルにより公正な発行価額を算定することが可能です。しかし、これに基づき評価を行なうと、実際にはかなり高額な評価となることが多いようで、実務上対応できるのか課題が残ります。また、未公開株式の評価についてもこのモデルが適用されるべきなのかについても課題があろうかとも思われます。これらについては第4回で解説します。
(2)取得者側・発行者側の各課税関係
これについては、第2回、第3回にて解説します。
(3)会計処理
とりわけストック・オプションの会計処理について、現在検討が行なわれているところです。これについては、第4回で解説します。
(次号第2回へ続く)
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会元委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
新株予約権、ストック・オプションの実務対応
公認会計士・税理士 棟田裕幸
第1回 新株予約権、ストック・オプションの概要
1. はじめに
平成14年4月施行の商法改正により、新株予約権が登場しました。新株予約権とは、新株予約権の発行時にあらかじめ定めた価額で会社の株式を会社から取得することのできる権利をいいます。
従来から新株引受権やストック・オプションは存在し、実務界でも使われてきましたが、これらとどのように異なるのか、またどのように進化したのでしょうか。
新株予約権について、その全体像、その本質的な意味合いを明らかにした上で、税務がどのように対応しているのか、会計処理はどのようにするのか等を、課題を含めて解明して行きたいと思います。
とかくわかりにくい新株予約権ですが、図解や設例を使い、よりビジュアルなものにして行きたいと思っております。
解説は4回シリーズで進めることとし、各回の内容は次の通りといたします。
第1回の今回は、改正商法で登場した新株予約権とは、従来の新株予約権やストック・オプションとどう違うのか、どのような使い道があるのか、またどうすれば発行できるのか等について次の流れで解説します。
1.はじめに
2.新株予約権、ストック・オプションとは
3.新株予約権と新株引受権との違い
4.ストック・オプション制度の改正前と改正後との違い
5.新株予約権の発行手続
6.新株予約権、ストック・オプションの様々な使い道
7.課題
第2回は、新株予約権の発行・行使・消滅・譲渡・相続そして取得株式の譲渡という各段階において課税関係の発生が考えられますが、これがどうなるのかを解説します。
第3回では、行使時の課税所得区分につき、所得税基本通達の考え方と、このたび注目されているストック・オプション課税判決について、その内容を解説し検討して行きます。
第4回は、会計処理と今後の課題について解説いたします。
2. 新株予約権、ストック・オプションとは
平成14年4月施行の商法改正により、新株予約権が登場しました。新株予約権とは、新株予約権の発行時にあらかじめ定められた価額で会社の株式を会社から取得することのできる権利をいい、これを表象するものが新株予約権証券であり、これは有価証券となります。この新株予約権証券を所有する者は、将来この会社の株価がどんなに上昇してもあらかじめ定められた価額で取得できる特典を有しています。逆に将来この会社の株価が下落し、あらかじめ定められた価額よりも低くなってしまった場合には、もはやこの権利を行使せず権利を放棄することとなるでしょう。
このように新株予約権は、将来株価が上昇する場合にはプラチナペーパーにもなりますが、逆に将来の株価の下落により単なる紙切れになるというリスクも有しています。この意味でこれは株式の取得に関する選択権(コール・オプション、すなわち買う権利)の性格を有したものといえます。
改正前の商法は、このような株式のコール・オプションの存在は認めていたものの、その価値を全面的に認めていたわけではありませんでした。しかし改正商法は、そのオプションの権利としての価値を認知いたしました。そこでオプションの単独発行(通常は有償発行となります)も認めることとなりました。このように新株予約権には、オプション権としての有価証券の地位が与えられることとなりました。
なお、新株予約権が無償で発行される場合がありますが、その典型がストック・オプションといわれるものです。
このように新株予約権とは、会社に株式の取得を要求することのできる権利であり、これを有するものが、会社に対してこの権利を行使した場合、会社はその者に対して、新株を発行しまたはこれに代えて当該会社の所有する自己株式を移転する義務を負うこととなります(商法280条の191)。
その発行関係を図示すると次のようになります。
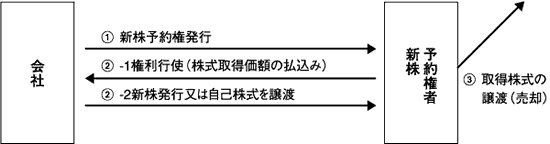
ここに、新株予約権の発行においては、原則として新株予約権の時価を算定し、取得者はその価額を会社に払込んで新株予約権という有価証券を取得します。これを無償にて発行するものが、新株予約権の有利発行の典型であるストック・オプションということになります。
この新株予約権には次の2つのものがあります。
--------------------------------------------------------------------------------
| 新株予約権の単独発行 通常発行(有償発行のもの) 有利発行(第三者割当の無償発行であるストック・オプションが典型例) 新株予約権付社債(社債付で発行するもの) 新株予約権+社債・・・・・(従来の分離型新株引受権付社債) 新株予約権付社債・・・・・代用払込型(従来の転換社債) の他(従来の非分離型新株引受権付社債) 上記は各々、株主割当と第三者割当とがあります。 |
--------------------------------------------------------------------------------
新株予約権の単独発行の場合を例にとり、その流れを見てみます。
<設例>
1新株予約権の発行時 株式の時価50
新株予約権の時価10
権利行使価額を50と設定
2新株予約権の権利行使時(権利行使により株式を取得)
行使価額50を払込む
株式時価200
3取得株式の譲渡 株式時価250で譲渡
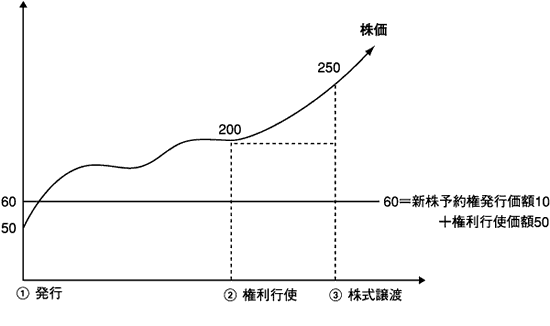
このように新株予約権を発行するとその後、権利行使による株式取得、取得株式の譲渡(売却)という各段階が生じます。
この例では、新株予約権の発行に際して、新株予約権自体の時価10を算定し、新株予約権を取得する者は、この10を会社に払込み、新株予約権という有価証券を取得しています。そして権利行使時には、その権利行使価額50を会社に払込みます。このように新株予約権の権利行使により株式取得をする場合のその取得価額は、これらの合計額となります。
前述したように新商法のもとでは、新株予約権というオプション自体に価値が認知されたため、その取得は有価証券の取得に該当することとなりました。したがって、その取得は当然に有償で行なうことが原則的な取得形態となります。ここが商法上も税務上も気をつけなければならない重要なポイントとなります。
すなわち、商法上はこの新株予約権を無償で第三者に発行することとなれば(すなわちストック・オプションの場合)、それは既存株主以外の者への有利発行となります。また、税務上もこのような無償での有利発行が行なわれると、その取得者に経済的利益が発生したと考えられ、課税が発生する余地が生じます。
なお、上記の1~3各段階のほかに、権利行使をせずに何らかの理由で、新株予約権が消滅する場合(期限徒過による消滅又は発行時に定めた消却事由の該当による消却の場合等)があり、また、新株予約権自体を譲渡するという場合もあります。さらには新株予約権の相続も考えられます。そこで、ここに新株予約権の発行後に考えられるパターンを整理してみます。
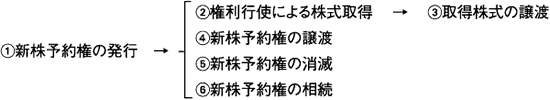
この1~4各段階において、経済的利益が発生するとその時に課税が生じる余地が発生します。また、5新株予約権を取得した者に相続が発生すると、相続税の問題が発生します。これらについては、第2回で解説します。
3. 新株予約権と新株引受権との違い
用語の使い方になりますが、重要なので解説しておきます。
旧商法では「新株引受権」がありました。改正商法では「新株予約権」及び「新株引受権」が並存しています。各々どのようなもので、何が変わったのか以下にまとめます。
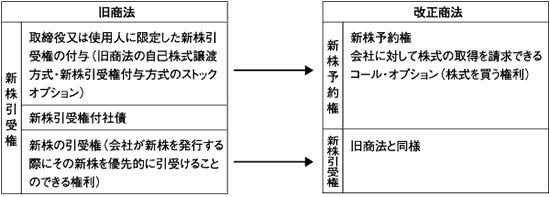
すなわち、旧商法のストック・オプションの付与は自己株式譲渡方式と新株引受権付与方式でしたが、改正商法は両社を統合して、ストック・オプションを新株予約権の有利発行としてまとめました。また旧商法ではストック・オプション以外の新株引受権は、新株引受権付社債又は転換社債に付してしか発行できなかったが、改正商法では新株予約権の単独発行(有償による通常発行)も可能となりました。これは、オプションの公正価値の算定が可能となったことも要因としてあげられます。
なお、現在の新株予約権のその種類毎の変化をまとめたものが以下のものです。
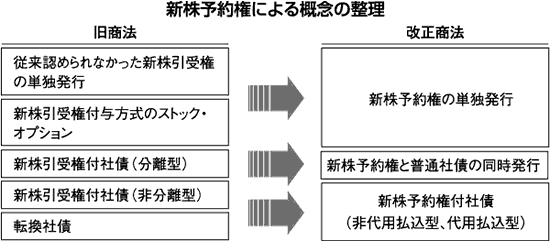
4. ストック・オプション制度の改正前と改正後との違い
ここでは、ストック・オプションに限定して、商法の改正前と改正後とのその違いについて見ていきます。
近年、インセンティブプランとしてのストック・オプションの必要性が高まりましたが、商法上以前はストック・オプションの考え方がありませんでした。そこで平成7年以降、本来は資金調達手段であるはずの分離型新株引受権付社債を利用した擬似ストック・オプションというものの付与が実務界では行なわれていました。
その後平成9年の商法改正により、商法上のストック・オプションとしての自己株式譲渡方式のストック・オプション及び新株引受権付与方式のストック・オプションが導入されました。しかしこれらは、個々の付与対象者の氏名につき株主総会決議が必要とされ、また、付与対象者の範囲(取締役又は使用人に限定)、行使期間(10年)及び付与できる株式数(発行済み株式総数の1/10)等、数々の制限があったことから、実務界では、より制約の少ない擬似ストック・オプションが依然として発行されていました。
このため、ストック・オプション制度をより活用しやすく実効性のあるものとすべく、改善が求められ、結局平成14年4月施行改正商法にて、従前のものと比較して以下のようなものに進化するに至りました。
1付与可能な株式数制限を撤廃
従来の発行済株式総数の1/10を超えない範囲としていた付与株式数の制限を撤廃した。
2権利行使期間の制限を撤廃
権利行使期間を株主総会付与決議日から10年以内としていた制限を撤廃した。
3付与対象者の制限を撤廃
付与対象者を、会社の取締役・使用人に限定していた制限を撤廃した。これにより付与対象者は、監査役、パートタイマー、他社からの出向社員、派遣社員、外部コンサルタント、弁護士、税理士、公認会計士、取引先、子会社・関連会社の取締役等への付与も可能となりました。
4付与対象者の氏名、付与決議の種類・数についての株主総会決議が不要
ストック・オプションの付与は、新株予約権の有利発行の一形態として、総会の特別決議が必要ですが、総会決議において、付与対象者の氏名や各人ごとの付与株式数を決議する必要はないとの解釈が採られています。但し、事後開示として営業報告書への記載は要します(商法施行規則84条111号)。
5行使時の株式選択が自由
新株予約権が行使されたときに新株予約権者に渡す株式を、新株を発行するか、会社が有する自己株式(金庫株)を移転するかをあらかじめ決めずに、会社がその行使時に選択できるようになりました。
5. 新株予約権の発行手続
新株予約権の発行は、取締役会決議で行なえることとなりましたが、有利発行の場合(ストック・オプションの発行は有利発行に該当する)は、株主総会の特別決議を必要とします。新株予約権の商法上の発行手続フローは次のようになります。
下記は新株予約権の発行手続フローで、新株予約権を単独で発行する場合を想定しています。すなわち、新株予約権を時価で評価してこれを有償にて発行する場合(通常発行)と、無償にて有利発行する場合のその典型としてのストック・オプションの場合とが考えられます。
このほかに、新株予約権付社債の発行の場合もありますが、その発行手続フローは、下記とほとんど同様です。
なお、下記の発行手続の中に「3有価証券通知書、有価証券届出書の提出」がありますが、これは、証券取引法上提出が求められるもので、要件に該当すると届出義務が生じます。気をつけなければならないので、第4回で解説する予定です。
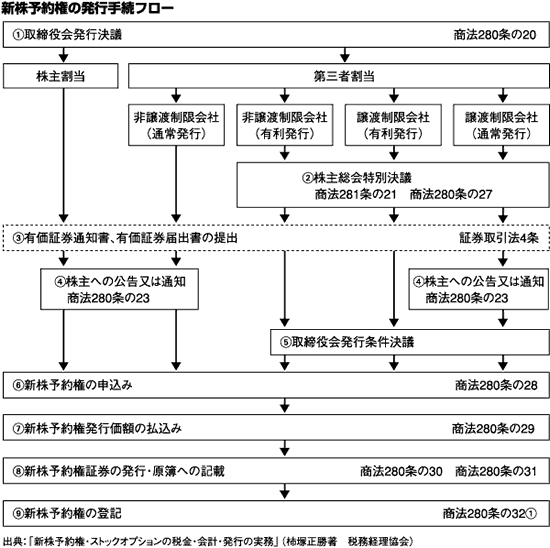
6. 新株予約権、ストック・オプションの様々な使い道
新株予約権、その無償取得としてのストック・オプションは、実務界ではすでに様々な活用が行なわれています。現に日本証券業協会の調べによると、平成14年4月~11月の8ヶ月間における全国上場企業による国内での新株予約権発行は、388件、金額(行使された場合の金額)で538,207百万円に上りました。また、昨年6月の株主総会では、約420社が新株予約権を使ったストック・オプションの付与を決議しています(以上、平成15年1月17日付、日経朝刊より)。
様々な使い道をここに解説いたします。
(1)インセンティブ・プランとしての活用
通常ストック・オプションとして、会社の取締役又は使用人等を対象に付与するもので、選ばれたものにその貢献度合い又は期待度合いに応じて付与することにより、より一層の貢献意欲・帰属意識・勤労意識の増進を図ろうとするものです。
商法改正により、前述のように取締役や使用人のほかに、子会社・関連会社の取締役、さらには取引先等外部者にも付与できるようになり、これら外部者の協力を得やすい環境を作ることができるようになりました。
(2)株式上場の資本政策における活用
まずは商法上の持株比率と株主の支配権(株主総会における支配権)との関係を示します。
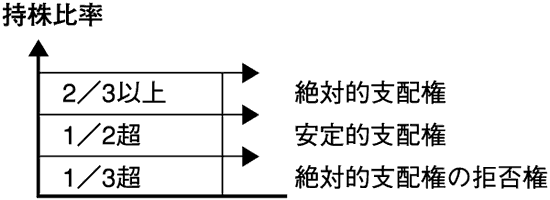
商法上、株主は議決権ある株式の2/3以上を所有すれば、株式会社の絶対的支配権を持つことができます。
逆に、1/3超を第三者に所有されると、この絶対的支配権が拒否される可能性が生じます。
議決権の1/2超の所有により、役員の選任決議等の株主総会の普通決議ができ、安定的支配が可能となります。
株式上場の資本政策では、上場により一般投資家が多数介入しますが、会社オーナーを中心とした安定株主の比率が1/2超、望ましくは2/3超あれば、その後も安定的な支配権の下に経営が行なわれることとなるため、事前にこのための対策をいたします。
株式上場のために、ベンチャーキャピタルや一般投資家の資本参加は受けたいが、一定の持株比率を確保することが必要な場合は、安定株主である社長、役員等に上場前の早い段階で新株予約権を発行しておくことにより持株比率の希薄化を防止することができます。例えば以下の例のように、ベンチャーキャピタルの第三者割当増資の引受けにより、持株比率が大きく崩れる場合にこれが活用できます。
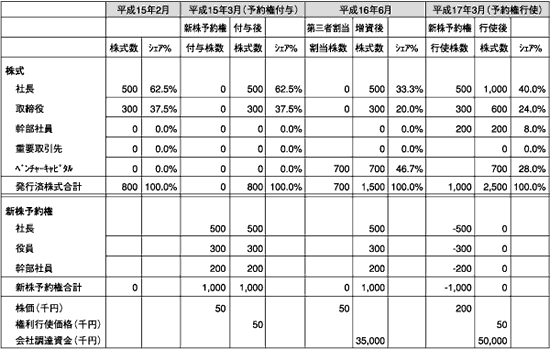
このように、新株予約権を株価が低いうち(5万円)に発行しておくと、その後ベンチャーキャピタル等の資本参加により、社長等安定株主の持株比率が低くなったとしても、その後の株価上昇(20万円)に影響されない低い価格での権利行使価格により株式が取得でき、安定株主比率を復活させることができます。
(3)M&Aにおける活用
実務界では、西友のウォルマートによる買収が、次のように新株予約権をうまく使った段階的資本参加として行なわれております。
平成14年5月31日に西友はウォルマートを対象にした3種の新株予約権を無償にて発行し、この新株予約権の行使期間を3段階(それぞれ平成14年12月27日、17年12月28日、19年12月28日)に分けました。すなわち、第1回新株予約権を行使するとウォルマートの議決権比率は1/3となり、第2回の行使により1/2、第3回までを行使すると2/3超となるというものです。このスキームは、ウォルマートに買収予約権を与えたものでありますが、同時に、権利行使期間の段階的設定は、資本参加者にそのリスクを軽減する効果を与えたものといえます。
(4)敵対的買収の防衛としての活用
第三者がTOB(株式の公開買付)手続を開始した場合に、第三者が一定割合(例えば1/3超)の株式を取得した場合等を行使条件として、経営陣や取引先に新株予約権を発行するというものです。この場合、新株予約権に譲渡制限を付けること、行使条件や消却事由も制限を置くべきことに注意すべきです。
(5)資金調達における活用
日本政策投資銀行は、新規事業の資金融資の方法として「新株予約権付融資」を実行したと発表しました。報道によると、融資先が発行する新株予約権を確保する代わりに、融資金利を軽減するとのことです(日経平成14年5月24日朝刊)。このように、新株予約権をファイナンスの条件を有利にするための甘味料として利用することも考えられます。
(6)事業承継における活用
特定した事業承継者に新株予約権を大きく付与しておけば、事業承継者の資金工面がつき次第、過半数までの株式を所有するよう権利を確保しておくことができます。権利行使の期限の制約はなく、また権利行使により発行する株式数は、譲渡制限のある会社は授権株数の制約もない(商法166条4但し書)ので、事業承継者の年齢、資金状況等を勘案した上で、新株予約権の付与内容を設定することができます。
7. 課題
以上述べた通り、新株予約権、ストック・オプションは、実効性のあるものとして制度上改善がなされ、実務界でも広く活用されてきています。
しかし、このような新株予約権ではありますが、実務上次のような課題もあります。
(1)新株予約権の評価方法
新株予約権は株式のコール・オプションのひとつですので、ブラック=ショールズ・モデルにより公正な発行価額を算定することが可能です。しかし、これに基づき評価を行なうと、実際にはかなり高額な評価となることが多いようで、実務上対応できるのか課題が残ります。また、未公開株式の評価についてもこのモデルが適用されるべきなのかについても課題があろうかとも思われます。これらについては第4回で解説します。
(2)取得者側・発行者側の各課税関係
これについては、第2回、第3回にて解説します。
(3)会計処理
とりわけストック・オプションの会計処理について、現在検討が行なわれているところです。これについては、第4回で解説します。
(次号第2回へ続く)
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会元委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























