解説記事2003年02月10日 【実務解説】 新株予約権、ストック・オプションの実務対応 第2回 新株予約権、ストック・オプションの税務(その1)(2003年2月10日号・№6)
実務解説
新株予約権、ストック・オプションの実務対応
公認会計士・税理士 棟田裕幸
第2回 新株予約権、ストック・オプションの税務(その1)
はじめに
前回は、新株予約権とその有利発行の一形態であるストック・オプションについて、それらがどのようなものなのかその概要、発行手続そして実務上の活用について解説いたしました。
前回解説したように、新株予約権はコール・オプションすなわち株式を買う権利であり、改正商法上コール・オプションとしてその価値が認知されました。これは、その公正価値がブラック=ショールズ・モデルのようなオプションの経済的価値の評価モデルにより測定可能となったことが大きな要因となっています。
発行会社側及び取得者側ではその発行がなされた後、何らかの経済的利益が発生した場合には課税が生じます。今回は、新株予約権及びストック・オプションの1発行、2権利行使、3取得株式の譲渡、4新株予約権自体の譲渡、5消滅そして6相続の各場合における税務関係について、次の順序で解説いたします。
1.新株引受権、ストック・オプションの発行者側の税務
2.新株引受権、ストック・オプションの取得者側の税務
(1)いつ課税されるのか
(2)取得ケース別の課税関係
1)新株予約権の適正価額による有償取得の場合
2)新株予約権の有利発行である無償取得(ストック・オプション)の場合
-1 譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
-2 税制適格要件を満たした譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
-3 譲渡可能で市場等で売買される新株予約権を無償取得した場合
3)新株予約権の有償取得だが有利発行になる場合
(3)新株予約権、ストック・オプション自体を譲渡した場合の課税関係
(4)新株予約権、ストック・オプションの消滅の課税関係
(5)新株予約権、ストック・オプションの相続税課税
(6)まとめ
(6)では、これら課税関係を表にまとめます。
1. 新株予約権の取得会社者側の税務
新株予約権を発行した会社は、新株予約権の払込金額を負債(仮勘定)に計上します。
この権利が行使された場合、計上された負債金額と権利行使による払込み金額との合計額が株式発行価額となるため、これを資本金(及び資本準備金)に振り替えます。このような取引は資本取引に該当し、損益の発生はないため、税務上も課税所得は発生いたしません。
一方、新株予約権が消滅した場合には、負債に計上された金額は、新株予約権取崩益として利益に計上されます。税務上、当該取崩益は益金に計上するものと考えられます。
2. 新株予約権の取得者側の税務
(1)いつ課税されるのか
新株予約権は税法上有価証券として取り扱われます(所得税法2条117号、法人税法2条121号)。新株予約権を会社が発行した場合、取得者には取得後の以下各段階において経済的利益の発生する場合が生じ、この場合に課税が発生します。所得税法36条2は、経済的利益を享受した時の価額をもって課税が生ずる旨規定しています。
1新株予約権の取得
取得者は、新株予約権を有償又は無償にて取得します。とりわけ無償取得であるストック・オプションの場合、この時点で経済的利益が発生していると考えられます。新株予約権の発行時には時価が算定されることとなるため、ここに課税の余地は確かに生じます。しかし、ストック・オプションは付与者を特定しており固有性が強いことから通常譲渡禁止しているケースが多いと思われます。このような譲渡禁止のものは、取得してもその時に換金性はなく経済的利益を享受したとはいい難く未実現の利益を受けたにすぎないと考えられます。したがってこの場合、権利行使により株式を取得して、ここではじめて利益を享受(実現)したと考え、課税が発生するものと考えられます。
なお、今後譲渡可能で市場等で売買されるストック・オプションが登場するかもしれません。その場合にはその取得時に経済的利益が発生したとして、取得時の課税が生ずることとなるでしょう。
2権利行使
その後、会社の株価が上昇すると、新株予約権者はその買う権利を行使するでしょう。権利行使による株式取得は、株価がどんなに上昇してもあらかじめ定められた価額により取得できるため、一見ここに経済的利益が発生するようにも思われます。
しかしそもそも新株予約権は、このような特典を価値としたもので、これを適正な時価で有償取得した者には、その特典である権利を行使しても、そこには特段の利益の享受はないものと考えられます。
したがって新株予約権を適正価額で有償した場合の権利行使には課税は発生いたしません。
しかし新株予約権を無償で取得するストック・オプションの場合には、これが譲渡禁止のものならば1で述べた通り取得時は非課税ですが、権利行使時はその経済的利益が実現したものとして課税が発生いたします。この所得課税区分については次回第3回で解説します。
3取得株式の譲渡
株式を取得した者は、取得した株式を譲渡(売却)して株価差益を得る事ができます。ここに経済的利益が発生し、課税が生じます。
4新株予約権自体の譲渡
新株予約権それ自体を譲渡する場合があります。この場合にも譲渡差益が生じていれば、ここに経済的利益が発生し、譲渡益課税が生じます。
5消滅
権利行使をせずに、何らかの理由により新株予約権が消滅する場合があります。あらかじめ定められた権利行使価額よりも株価が下落してしまい、権利行使されないままに放棄される場合、又は発行時に定めた消滅事由の該当による消滅の場合等が考えられます。この場合に発行会社から払戻しを受け、新株予約権の取得価額と会社からの払戻し額との差額に利益が生じていれば、経済的利益の発生として譲渡益課税が生じます。
6相続
新株予約権の所有者に相続が発生した場合、新株予約権は有価証券であるため、ここにその評価額に対して相続税が発生します。
このように1~5において経済的利益の発生があった場合、ここに課税の発生の余地が生じます。6においては相続税の課税が生じます。
以下、次の設例をもとに、新株予約権の取得ケース別に経済的利益の発生を検討し、課税の問題を検討して行きたいと思います。
<設例>
1新株予約権の発行 株式の時価50
新株予約権の時価10
新株予約権の権利行使価
額を50と設定
2新株予約権の権利行使(権利行使による株式取得)
行使価額50
この時の株式時価200
3取得株式の譲渡 この時の株式時価250に
て株式を譲渡
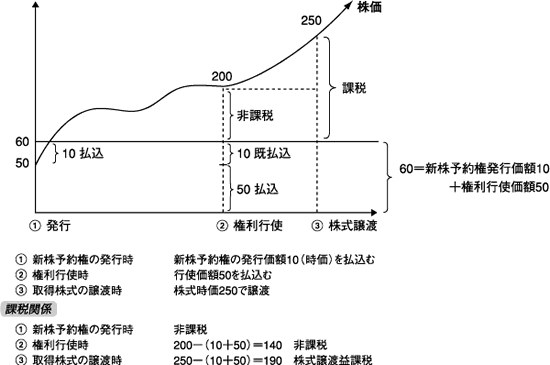
(2)取得ケース別の課税関係
1)新株予約権の適正価額による有償取得の場合
新株予約権を単独発行し、これを適正な価額で有償取得した場合です。
1新株予約権の発行時:非課税
新株予約権は税法上も有価証券として扱われます。したがって第三者割当の新株予約権の発行でもそれが適正な時価で取得されている(通常発行されている)限り通常の有価証券の取得であり、そこには何ら経済的利益の発生はなく、課税の問題は発生しません。
株主割当発行の場合は、既存株主に平等に割当が行なわれるため、例え無償発行でも課税の問題は生じません。
なお、新株予約権をその時価よりも低い価額で取得した場合(例えば時価10の新株予約権を6で取得)には、時価と取得価額との差額(10-6=4)は、経済的利益として取得時(発行時)に課税の余地が生じます(所基通36-15(1))。
2権利行使時:200-(10+50)=140 非課税
新株予約権の通常発行の場合及び株主割当発行の場合、税法上何ら課税の規定はありません。繰り返しますが、これは新株予約権を適正な価額にて有償取得した者は、将来どんなに株価が上昇しても、あらかじめ定められた行使価額で行使できる権利(特典)を有した有価証券を取得したもので、この権利を行使してもそこには特段の経済的利益は発生していないと考えられるからです。
このように権利行使時に課税が生じない場合には、次の算式が該当していると考えられます。
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
これがもし逆の不等号ならば、新株予約権発行時の株価以下の払込みしか行なわれないこととなり、結局は当初の時価以下の取得になり、経済的利益が生じていると考えられます。
なお、「新株予約権の行使により取得した株式の取得価額」の算定は、所基通48-6の2は次のようにそれらの合計額であると定めています。
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
3取得株式の譲渡時:250-(10+50)=190 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。
非上場株式は、税率は26%(所得税20%、住民税6%)。上場株式等は平成15年改正で20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられましたが、平成15年から5年間に限り10%(所得税7%、住民税3%)、ただしこれらの引下げは、証券会社等を通じての譲渡にのみ適用があり、上場株式等を相対で譲渡した場合は26%(所得税20%、住民税6%)となります。
2)新株予約権の有利発行である無償取得(ストック・オプション)の場合
ストック・オプションの課税関係について検討いたします。
2)-1 譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
1新株予約権発行時:非課税
2権利行使時:200-(0+50)=150 課税
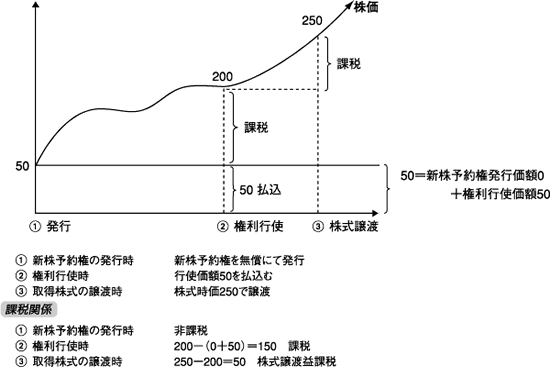
新株予約権はコール・オプションとしての価値を有するため適正な時価が付されます。したがって、その新株予約権を無償取得した場合には、取得者にはその時点で経済的利益が発生するため、所得税法36条2に基づき、その時に課税されると考えられるふしがあります。
しかし、平成14年税制改正により所得税法施行令84条3号に「商法280条の211(新株予約権の有利発行の決議)に基づき発行された新株予約権」に関する規定が加えられました。この規定はストック・オプションについて、課税される時期を権利行使時と定め、収入金額を「権利行使時の株価-(新株予約権の取得価額+行使払込額)」と定めました。これはすなわち、有利発行による新株予約権を与えられた場合の経済的利益は、従来の商法上のいわゆるストック・オプション(新株引受権付与方式又は自己株式譲渡方式)と同じく、権利行使時に発生しこの時に課税されるとしたものであります。これは同規定が、譲渡禁止のもので、権利行使によらなければ利益を享受できない有利発行による新株予約権に係る経済的利益を想定しているからと考えられます。譲渡禁止ならば、新株予約権の取得時にはこれを換金できる手段はないので、経済的利益はあるものの未実現と考え、課税の問題は生じないと考えられます。そしてこの権利行使時に、未実現の経済的利益が実現したものとして、この時に課税が発生するとものと考えられます。
このように、所得税法施行令84条3号は、譲渡禁止のストック・オプションを規定しています。しかし今後、譲渡が禁止されず市場等で売買される新株予約権が出てくることも考えられます。その場合には、その発行時において新株予約権の時価と取得価額との差額は経済的利益として顕在化しているため、所得税法36条2の規定により発行時に当然に課税すべきものとなります。これについては2)-3で解説します。
3取得株式の譲渡時:250-200=50 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。税率は、前述のとおりです。
2)-2 税制適格要件を満たした譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
措置法29条の2に規定する税制適格ストック・オプションについての課税関係は次のとおりです。
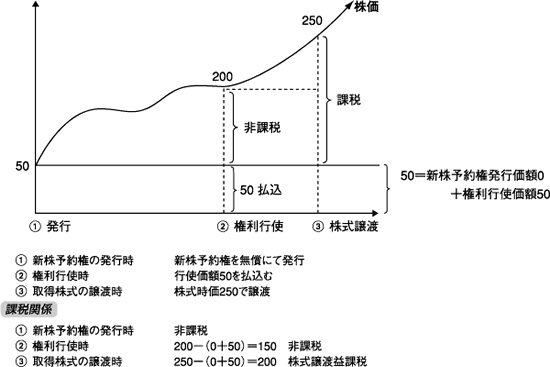
1新株予約権発行時:非課税
譲渡禁止のストック・オプションの場合と同様です。
2権利行使時:200-(0+50)=150非課税
措置法29の2に規定する一定の条件のあるストック・オプションについては、権利行使時の経済的利益に対する課税を非課税とします。
3取得株式の譲渡時:250-(0+50)=200 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。税率は、前述のとおりです。
ここに税制適格ストック・オプションとなるためには、所定の要件を満たす必要があります。付与対象者は一定規模以上の大口株主及びその親族等ではない、会社及び子会社の取締役又は使用人たる個人に限定され、その適用要件は次のとおりです。
・権利行使は付与決議から2年を経過した日から10年を経過するまでに行なうこと。
・権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと。
・権利行使価額は、付与契約締結時の時価以上であること。
・当該新株予約権に譲渡禁止規定が付されていること。
・権利行使による新株発行又は株式譲渡が付与決議事項に違反しないこと。
・権利行使により取得した株式が証券会社等に保管委託されること。
2)-3 譲渡可能で市場等で売買される新株予約権を無償取得した場合
現在はあまりないとは思われますが、今後、譲渡が禁止されず、市場等で売買される新株予約権が登場することも考えられます。その場合の経済的利益の発生とその課税関係は以下のとおりです。
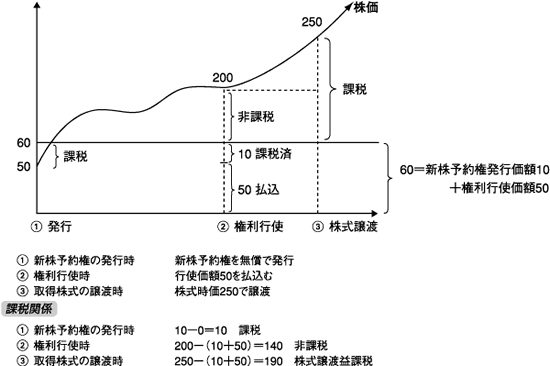
この場合は、その発行時に新株予約権の時価と取得価額(0)との差額は経済的利益として顕在化していることから、所得税法36条2の規定により発行時に課税されることとなります。
1新株予約権発行時:10-0=10 課税
有利発行による新株予約権の発行時の時価と発行価額との差額について、経済的利益が実現していることから課税が生じます(所得税法362、所基通36-36)。
2権利行使時:200-(10+50)=140 非課税
新株予約権発行時に経済的利益が実現して課税されるため、権利行使時には経済的利益の発生はなく、課税はありません。
3取得株式の譲渡時:250-(10+50)=190 株式譲渡益課税
譲渡した株式の取得価額は、権利行使直前の新株予約権の取得価額と権利行使価額との合計額となります(所基通48-6の2)。
ここに新株予約権の取得価額はゼロですが、その発行時に10が課税されているため10で取得したものとします。
また、株式譲渡金額とこの取得価額との差額は、株式譲渡益として申告分離で課税されます。
3)新株予約権の有償取得だが有利発行になる場合
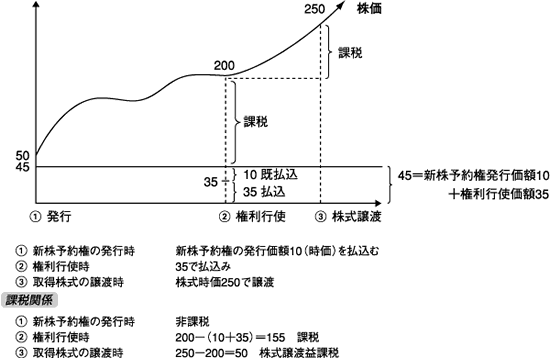
1新株予約権発行時:非課税
これは、譲渡禁止の新株予約権をその時価である10で取得しているが、権利行使を行使価額50よりも低い価額で行ない、新株予約権の行使による取得株式の発行価額(新株予約権の取得価額10+権利行使による株式払込価額35=合計額45)が新株予約権発行時の株価50に満たないという場合が考えられます。なお、ここでは譲渡禁止を想定しているため、新株予約権発行時は経済的利益が未実現であり課税はありません。
2権利行使時:200-(10+35)=155 課税
新株予約権の権利行使により経済的利益が確定するため、権利行使時に課税が発生します。
3取得株式の譲渡時:250-200=50 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離課税されます。税率は、前述のとおりです。
(3)新株予約権、ストック・オプション自体を譲渡した場合の課税関係
新株予約権は有価証券であるため、新株予約権そのものを譲渡した場合、有価証券の譲渡損益として取扱われます。租税特別措置法上、新株予約権は株式等に該当し、譲渡損益についての所得税は、他の所得とは区別して申告分離課税となります。譲渡損益の税率は、株式譲渡益の税率と同様。
なお、譲渡禁止のストック・オプション、とりわけ税制適格ストック・オプションの場合は、新株予約権の発行条件として譲渡を禁止しているため、譲渡はありえません。
(4)新株予約権、ストック・オプションの消滅の課税関係
期限徒過や発行時に定めた消滅要件に該当した場合に新株予約権は消滅します。この場合、消滅要件により新株予約権は有償又は無償にて消滅します。取得者が個人ならば、有償の場合は有価証券の譲渡損益となります(措置法37条の104)。無償の場合は、取得価額分の損失となります。
(5)新株予約権、ストック・オプションの相続税課税
新株予約権を所有する者が死亡した場合、新株予約権は有価証券であるため、その評価額に対して相続財産として相続人に相続税が課せられます。この場合、財産評価基本通達190(新株引受権の評価)の類推適用として次の評価が行なわれます。
新株予約権の評価額=(株式の時価-新株1株につき払込むべき金額)×新株予約権による発行価額
なお、所有者の死亡により新株予約権が消滅するケースの場合は相続財産とはなりません。
(6)まとめ
以上、新株予約権、ストック・オプションの課税関係を解説しましたが、発行からその後の各段階における課税関係を表でまとめると次のとおりとなります。
以上、今回は新株予約権の取得者側の課税関係を解説しました。次回は税務編その2として新株予約権、ストック・オプションの取得者側の権利行使時課税の所得課税区分について、所得税基本通達の考え方とともに、今話題のストック・オプション課税判決の考え方について検討いたします。
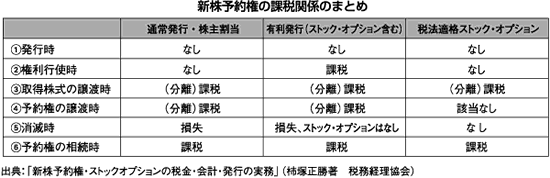
参考文献:
「新株予約権・ストックオプションの税金・会計・発行の実務」(柿塚正勝著 税務経理協会)
「商法改正による新株予約権の所得税法上の取扱い」(石井敏彦著 大蔵財務協会)
(次号第3回へ続く)
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会元委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
新株予約権、ストック・オプションの実務対応
公認会計士・税理士 棟田裕幸
第2回 新株予約権、ストック・オプションの税務(その1)
はじめに
前回は、新株予約権とその有利発行の一形態であるストック・オプションについて、それらがどのようなものなのかその概要、発行手続そして実務上の活用について解説いたしました。
前回解説したように、新株予約権はコール・オプションすなわち株式を買う権利であり、改正商法上コール・オプションとしてその価値が認知されました。これは、その公正価値がブラック=ショールズ・モデルのようなオプションの経済的価値の評価モデルにより測定可能となったことが大きな要因となっています。
発行会社側及び取得者側ではその発行がなされた後、何らかの経済的利益が発生した場合には課税が生じます。今回は、新株予約権及びストック・オプションの1発行、2権利行使、3取得株式の譲渡、4新株予約権自体の譲渡、5消滅そして6相続の各場合における税務関係について、次の順序で解説いたします。
1.新株引受権、ストック・オプションの発行者側の税務
2.新株引受権、ストック・オプションの取得者側の税務
(1)いつ課税されるのか
(2)取得ケース別の課税関係
1)新株予約権の適正価額による有償取得の場合
2)新株予約権の有利発行である無償取得(ストック・オプション)の場合
-1 譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
-2 税制適格要件を満たした譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
-3 譲渡可能で市場等で売買される新株予約権を無償取得した場合
3)新株予約権の有償取得だが有利発行になる場合
(3)新株予約権、ストック・オプション自体を譲渡した場合の課税関係
(4)新株予約権、ストック・オプションの消滅の課税関係
(5)新株予約権、ストック・オプションの相続税課税
(6)まとめ
(6)では、これら課税関係を表にまとめます。
1. 新株予約権の取得会社者側の税務
新株予約権を発行した会社は、新株予約権の払込金額を負債(仮勘定)に計上します。
この権利が行使された場合、計上された負債金額と権利行使による払込み金額との合計額が株式発行価額となるため、これを資本金(及び資本準備金)に振り替えます。このような取引は資本取引に該当し、損益の発生はないため、税務上も課税所得は発生いたしません。
一方、新株予約権が消滅した場合には、負債に計上された金額は、新株予約権取崩益として利益に計上されます。税務上、当該取崩益は益金に計上するものと考えられます。
2. 新株予約権の取得者側の税務
(1)いつ課税されるのか
新株予約権は税法上有価証券として取り扱われます(所得税法2条117号、法人税法2条121号)。新株予約権を会社が発行した場合、取得者には取得後の以下各段階において経済的利益の発生する場合が生じ、この場合に課税が発生します。所得税法36条2は、経済的利益を享受した時の価額をもって課税が生ずる旨規定しています。
1新株予約権の取得
取得者は、新株予約権を有償又は無償にて取得します。とりわけ無償取得であるストック・オプションの場合、この時点で経済的利益が発生していると考えられます。新株予約権の発行時には時価が算定されることとなるため、ここに課税の余地は確かに生じます。しかし、ストック・オプションは付与者を特定しており固有性が強いことから通常譲渡禁止しているケースが多いと思われます。このような譲渡禁止のものは、取得してもその時に換金性はなく経済的利益を享受したとはいい難く未実現の利益を受けたにすぎないと考えられます。したがってこの場合、権利行使により株式を取得して、ここではじめて利益を享受(実現)したと考え、課税が発生するものと考えられます。
なお、今後譲渡可能で市場等で売買されるストック・オプションが登場するかもしれません。その場合にはその取得時に経済的利益が発生したとして、取得時の課税が生ずることとなるでしょう。
2権利行使
その後、会社の株価が上昇すると、新株予約権者はその買う権利を行使するでしょう。権利行使による株式取得は、株価がどんなに上昇してもあらかじめ定められた価額により取得できるため、一見ここに経済的利益が発生するようにも思われます。
しかしそもそも新株予約権は、このような特典を価値としたもので、これを適正な時価で有償取得した者には、その特典である権利を行使しても、そこには特段の利益の享受はないものと考えられます。
したがって新株予約権を適正価額で有償した場合の権利行使には課税は発生いたしません。
しかし新株予約権を無償で取得するストック・オプションの場合には、これが譲渡禁止のものならば1で述べた通り取得時は非課税ですが、権利行使時はその経済的利益が実現したものとして課税が発生いたします。この所得課税区分については次回第3回で解説します。
3取得株式の譲渡
株式を取得した者は、取得した株式を譲渡(売却)して株価差益を得る事ができます。ここに経済的利益が発生し、課税が生じます。
4新株予約権自体の譲渡
新株予約権それ自体を譲渡する場合があります。この場合にも譲渡差益が生じていれば、ここに経済的利益が発生し、譲渡益課税が生じます。
5消滅
権利行使をせずに、何らかの理由により新株予約権が消滅する場合があります。あらかじめ定められた権利行使価額よりも株価が下落してしまい、権利行使されないままに放棄される場合、又は発行時に定めた消滅事由の該当による消滅の場合等が考えられます。この場合に発行会社から払戻しを受け、新株予約権の取得価額と会社からの払戻し額との差額に利益が生じていれば、経済的利益の発生として譲渡益課税が生じます。
6相続
新株予約権の所有者に相続が発生した場合、新株予約権は有価証券であるため、ここにその評価額に対して相続税が発生します。
このように1~5において経済的利益の発生があった場合、ここに課税の発生の余地が生じます。6においては相続税の課税が生じます。
以下、次の設例をもとに、新株予約権の取得ケース別に経済的利益の発生を検討し、課税の問題を検討して行きたいと思います。
<設例>
1新株予約権の発行 株式の時価50
新株予約権の時価10
新株予約権の権利行使価
額を50と設定
2新株予約権の権利行使(権利行使による株式取得)
行使価額50
この時の株式時価200
3取得株式の譲渡 この時の株式時価250に
て株式を譲渡
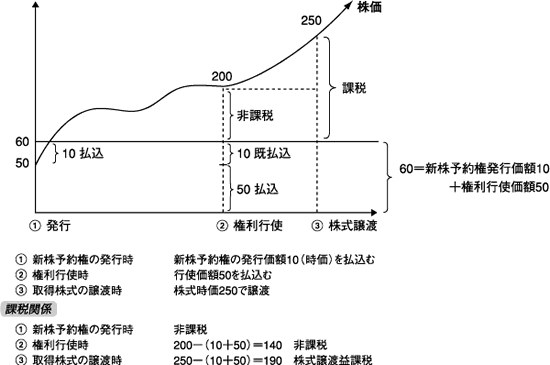
(2)取得ケース別の課税関係
1)新株予約権の適正価額による有償取得の場合
新株予約権を単独発行し、これを適正な価額で有償取得した場合です。
1新株予約権の発行時:非課税
新株予約権は税法上も有価証券として扱われます。したがって第三者割当の新株予約権の発行でもそれが適正な時価で取得されている(通常発行されている)限り通常の有価証券の取得であり、そこには何ら経済的利益の発生はなく、課税の問題は発生しません。
株主割当発行の場合は、既存株主に平等に割当が行なわれるため、例え無償発行でも課税の問題は生じません。
なお、新株予約権をその時価よりも低い価額で取得した場合(例えば時価10の新株予約権を6で取得)には、時価と取得価額との差額(10-6=4)は、経済的利益として取得時(発行時)に課税の余地が生じます(所基通36-15(1))。
2権利行使時:200-(10+50)=140 非課税
新株予約権の通常発行の場合及び株主割当発行の場合、税法上何ら課税の規定はありません。繰り返しますが、これは新株予約権を適正な価額にて有償取得した者は、将来どんなに株価が上昇しても、あらかじめ定められた行使価額で行使できる権利(特典)を有した有価証券を取得したもので、この権利を行使してもそこには特段の経済的利益は発生していないと考えられるからです。
このように権利行使時に課税が生じない場合には、次の算式が該当していると考えられます。
--------------------------------------------------------------------------------
| |
これがもし逆の不等号ならば、新株予約権発行時の株価以下の払込みしか行なわれないこととなり、結局は当初の時価以下の取得になり、経済的利益が生じていると考えられます。
なお、「新株予約権の行使により取得した株式の取得価額」の算定は、所基通48-6の2は次のようにそれらの合計額であると定めています。
--------------------------------------------------------------------------------
| |
3取得株式の譲渡時:250-(10+50)=190 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。
非上場株式は、税率は26%(所得税20%、住民税6%)。上場株式等は平成15年改正で20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられましたが、平成15年から5年間に限り10%(所得税7%、住民税3%)、ただしこれらの引下げは、証券会社等を通じての譲渡にのみ適用があり、上場株式等を相対で譲渡した場合は26%(所得税20%、住民税6%)となります。
2)新株予約権の有利発行である無償取得(ストック・オプション)の場合
ストック・オプションの課税関係について検討いたします。
2)-1 譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
1新株予約権発行時:非課税
2権利行使時:200-(0+50)=150 課税
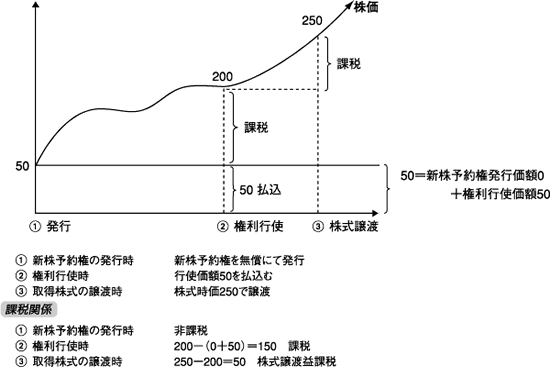
新株予約権はコール・オプションとしての価値を有するため適正な時価が付されます。したがって、その新株予約権を無償取得した場合には、取得者にはその時点で経済的利益が発生するため、所得税法36条2に基づき、その時に課税されると考えられるふしがあります。
しかし、平成14年税制改正により所得税法施行令84条3号に「商法280条の211(新株予約権の有利発行の決議)に基づき発行された新株予約権」に関する規定が加えられました。この規定はストック・オプションについて、課税される時期を権利行使時と定め、収入金額を「権利行使時の株価-(新株予約権の取得価額+行使払込額)」と定めました。これはすなわち、有利発行による新株予約権を与えられた場合の経済的利益は、従来の商法上のいわゆるストック・オプション(新株引受権付与方式又は自己株式譲渡方式)と同じく、権利行使時に発生しこの時に課税されるとしたものであります。これは同規定が、譲渡禁止のもので、権利行使によらなければ利益を享受できない有利発行による新株予約権に係る経済的利益を想定しているからと考えられます。譲渡禁止ならば、新株予約権の取得時にはこれを換金できる手段はないので、経済的利益はあるものの未実現と考え、課税の問題は生じないと考えられます。そしてこの権利行使時に、未実現の経済的利益が実現したものとして、この時に課税が発生するとものと考えられます。
このように、所得税法施行令84条3号は、譲渡禁止のストック・オプションを規定しています。しかし今後、譲渡が禁止されず市場等で売買される新株予約権が出てくることも考えられます。その場合には、その発行時において新株予約権の時価と取得価額との差額は経済的利益として顕在化しているため、所得税法36条2の規定により発行時に当然に課税すべきものとなります。これについては2)-3で解説します。
3取得株式の譲渡時:250-200=50 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。税率は、前述のとおりです。
2)-2 税制適格要件を満たした譲渡禁止の新株予約権を無償取得した場合
措置法29条の2に規定する税制適格ストック・オプションについての課税関係は次のとおりです。
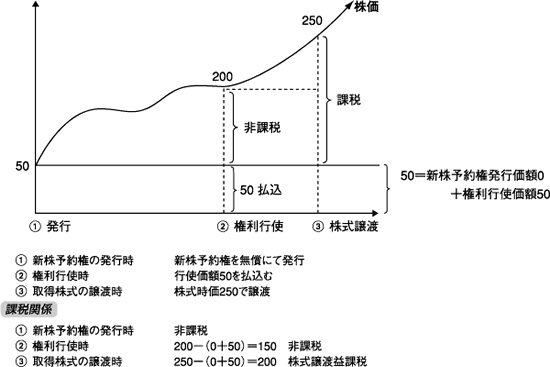
1新株予約権発行時:非課税
譲渡禁止のストック・オプションの場合と同様です。
2権利行使時:200-(0+50)=150非課税
措置法29の2に規定する一定の条件のあるストック・オプションについては、権利行使時の経済的利益に対する課税を非課税とします。
3取得株式の譲渡時:250-(0+50)=200 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離で課税されます。税率は、前述のとおりです。
ここに税制適格ストック・オプションとなるためには、所定の要件を満たす必要があります。付与対象者は一定規模以上の大口株主及びその親族等ではない、会社及び子会社の取締役又は使用人たる個人に限定され、その適用要件は次のとおりです。
・権利行使は付与決議から2年を経過した日から10年を経過するまでに行なうこと。
・権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと。
・権利行使価額は、付与契約締結時の時価以上であること。
・当該新株予約権に譲渡禁止規定が付されていること。
・権利行使による新株発行又は株式譲渡が付与決議事項に違反しないこと。
・権利行使により取得した株式が証券会社等に保管委託されること。
2)-3 譲渡可能で市場等で売買される新株予約権を無償取得した場合
現在はあまりないとは思われますが、今後、譲渡が禁止されず、市場等で売買される新株予約権が登場することも考えられます。その場合の経済的利益の発生とその課税関係は以下のとおりです。
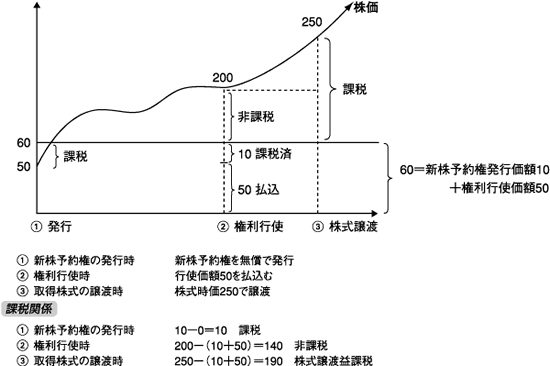
この場合は、その発行時に新株予約権の時価と取得価額(0)との差額は経済的利益として顕在化していることから、所得税法36条2の規定により発行時に課税されることとなります。
1新株予約権発行時:10-0=10 課税
有利発行による新株予約権の発行時の時価と発行価額との差額について、経済的利益が実現していることから課税が生じます(所得税法362、所基通36-36)。
2権利行使時:200-(10+50)=140 非課税
新株予約権発行時に経済的利益が実現して課税されるため、権利行使時には経済的利益の発生はなく、課税はありません。
3取得株式の譲渡時:250-(10+50)=190 株式譲渡益課税
譲渡した株式の取得価額は、権利行使直前の新株予約権の取得価額と権利行使価額との合計額となります(所基通48-6の2)。
ここに新株予約権の取得価額はゼロですが、その発行時に10が課税されているため10で取得したものとします。
また、株式譲渡金額とこの取得価額との差額は、株式譲渡益として申告分離で課税されます。
3)新株予約権の有償取得だが有利発行になる場合
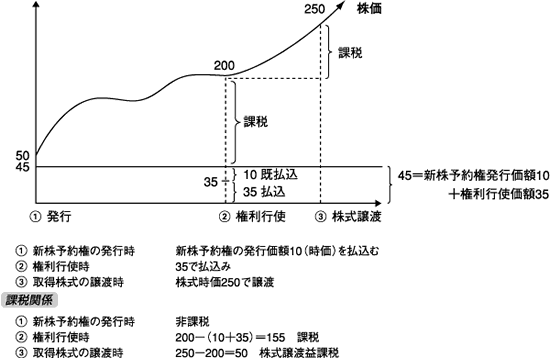
1新株予約権発行時:非課税
これは、譲渡禁止の新株予約権をその時価である10で取得しているが、権利行使を行使価額50よりも低い価額で行ない、新株予約権の行使による取得株式の発行価額(新株予約権の取得価額10+権利行使による株式払込価額35=合計額45)が新株予約権発行時の株価50に満たないという場合が考えられます。なお、ここでは譲渡禁止を想定しているため、新株予約権発行時は経済的利益が未実現であり課税はありません。
2権利行使時:200-(10+35)=155 課税
新株予約権の権利行使により経済的利益が確定するため、権利行使時に課税が発生します。
3取得株式の譲渡時:250-200=50 株式譲渡益課税
譲渡益が生じている場合は、株式譲渡益課税として申告分離課税されます。税率は、前述のとおりです。
(3)新株予約権、ストック・オプション自体を譲渡した場合の課税関係
新株予約権は有価証券であるため、新株予約権そのものを譲渡した場合、有価証券の譲渡損益として取扱われます。租税特別措置法上、新株予約権は株式等に該当し、譲渡損益についての所得税は、他の所得とは区別して申告分離課税となります。譲渡損益の税率は、株式譲渡益の税率と同様。
なお、譲渡禁止のストック・オプション、とりわけ税制適格ストック・オプションの場合は、新株予約権の発行条件として譲渡を禁止しているため、譲渡はありえません。
(4)新株予約権、ストック・オプションの消滅の課税関係
期限徒過や発行時に定めた消滅要件に該当した場合に新株予約権は消滅します。この場合、消滅要件により新株予約権は有償又は無償にて消滅します。取得者が個人ならば、有償の場合は有価証券の譲渡損益となります(措置法37条の104)。無償の場合は、取得価額分の損失となります。
(5)新株予約権、ストック・オプションの相続税課税
新株予約権を所有する者が死亡した場合、新株予約権は有価証券であるため、その評価額に対して相続財産として相続人に相続税が課せられます。この場合、財産評価基本通達190(新株引受権の評価)の類推適用として次の評価が行なわれます。
新株予約権の評価額=(株式の時価-新株1株につき払込むべき金額)×新株予約権による発行価額
なお、所有者の死亡により新株予約権が消滅するケースの場合は相続財産とはなりません。
(6)まとめ
以上、新株予約権、ストック・オプションの課税関係を解説しましたが、発行からその後の各段階における課税関係を表でまとめると次のとおりとなります。
以上、今回は新株予約権の取得者側の課税関係を解説しました。次回は税務編その2として新株予約権、ストック・オプションの取得者側の権利行使時課税の所得課税区分について、所得税基本通達の考え方とともに、今話題のストック・オプション課税判決の考え方について検討いたします。
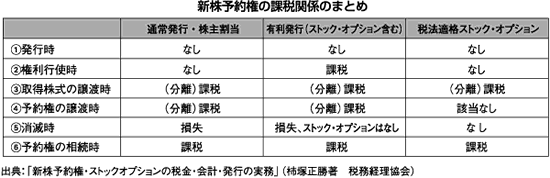
参考文献:
「新株予約権・ストックオプションの税金・会計・発行の実務」(柿塚正勝著 税務経理協会)
「商法改正による新株予約権の所得税法上の取扱い」(石井敏彦著 大蔵財務協会)
(次号第3回へ続く)
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京実務補習所運営委員会元委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















