解説記事2003年09月15日 【実務解説】 事業承継税制の改正(3)小規模宅地等に係る課税価格の特例(措置法69条の4)(2003年9月15日号・№035)
実務解説
事業承継税制の改正(3)小規模宅地等に係る課税価格の特例(措置法69条の4)
税理士 竹内陽一
公認会計士 長谷川敏也
ポイント
1. 特定同族会社事業用宅地等(80%評価減)特例が拡充されました。
2. 相続時精算課税度が創設されましたが、「小規模宅地等の減額特例」には影響はなく、一方相続時精算課税制度の選択適用を受ける特定受贈同族会社株式等は相続時に「特定事業用資産についての評価減特例」対象として取り扱われます。
3. 小規模宅地等の減額特例で面積限度まで余裕がある場合に、自社株軽減特例が余裕分の割合で適用することができるようになりました。また、いずれを優先的に適用しなければならない旨の規定はありませんので、逆に自社株軽減特例の適用を優先して、その限度までの余裕分を小規模宅地等の減額特例が適用できます。
1. 相続時精算課税と小規模宅地等の減額特例
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続の間で資産移転時期の選択に対して税制の中立性を確保する趣旨のものであり、この趣旨からは小規模宅地等の減額特例を生前贈与時に適用することが制度本来のあり方かもしれません。
しかし、相続時精算課税制度はその取得原因が「贈与」であり、また相続時精算課税制度はその財産に制限がありませんが、措置法69条の4は特段の改正がありませんので、残念ながら贈与時に小規模宅地等の減額特例の適用はありません(措通69-4-1)。したがって、相続時精算課税制度により生前贈与された宅地は、相続時に小規模宅地等の減額特例は適用できませんので、親が引き続き所有していたほうが有利である場合にはその宅地等は贈与計画から除くべきでしょう。
一方、「特定事業用資産についての特例」(いわゆる自社株軽減特例)では生前贈与した特定事業用資産であっても、相続時に「特定事業用資産についての評価減特例」対象として取り扱われます。
2. 特定同族会社事業用宅地等(80%評価減)の改正
(1) 改正のポイント
小規模宅地等の減額特例のうち、「特定同族会社事業用宅地等」の80%評価減の特例が拡充されました。従来の要件のうち、「被相続人および生計を一にする親族の出資割合が50%以上」という要件は、実務上厳しいものであり、生計を別にする親族に生前に出資を大幅に譲渡(贈与)してしまうと、この「特定同族会社事業用宅地等」の80%減額特例が活用できませんでした。そこで、都心で事業を経営している中小企業オーナーの事業承継対策では、相続開始の時にどのような出資割合になるかまで考慮していたところです。この制限が、今般の改正によって大きく緩和されています。
(2)同族法人の要件の拡充
特定同族会社事業用宅地の特例を受けることができる同族法人の要件が、「相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式等の総数がその法人の発行済み株式総数の10分の5を超える法人」に改められました。
この結果、特定同族会社事業用宅地に該当する範囲が拡大され、事業承継対策がより行いやすくなりました(措69の4③四)。
ここで、政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者をいいます。
一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 被相続人の使用人
三 被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五 次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が有する他の法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が有する他の法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の法人
(3)議決権に制限のある株式がある場合
なお、これらの規定の適用に当たっては、議決権に制限のある株式・出資は含まないものとし、具体的には、相続開始の時において、商法第222条第4項に規定する議決権制限株式で議決権を行使すべき事項の全部について議決権を有しないもの、同法第241条第2項(自己株式)又は第3項(4分の1超を保有されている会社が保有する会社の株式を持っている(相互持合)場合)の規定により議決権を有しないものとされる株式その他の議決権のない株式等はカウントからはずされます(措令40の2⑩、措規則23の2)。
(4)特定同族会社事業用宅地の特例判定のまとめ
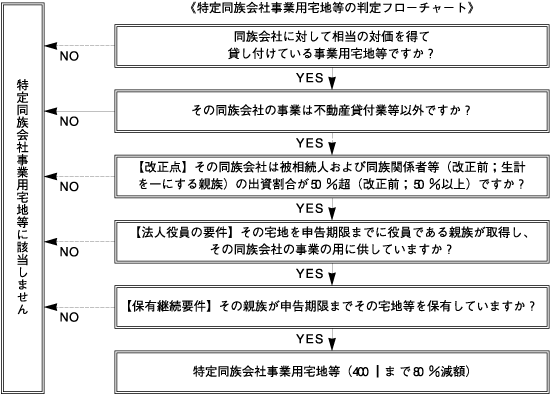
3. 小規模宅地等の減額特例と特定事業用資産の特例の併用
(1)小規模宅地等の減額特例と特定事業用資産の特例の併用規定
小規模宅地等または特定同族会社株式等、そして特定受贈同族会社株式等については相続税の課税価格の計算の特例を受けることができる土地等の面積または価額について、一定の制限がありますが、納税者の選択した面積または価額について余裕がある場合、特例の併用ができることになりました。
すなわち措置法69条の5第7項は「小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計が400平方メートル未満である場合には、選択特定事業用資産の価額に400平方メートルから当該面積の合計を控除したものの400平方メートルに占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、同項の規定を適用する。」とあります。
このことを算式で表現すると以下のようになります(措通69の5-25)。
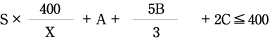
S:3億円以下の範囲で選択した自社株
X:3億円又は2/3枠が3億円以下の場合の2/3枠相当額として選択できる上限額
S、Xの単位:1億円
A、B、Cの単位:平方メートル
A:特定事業用宅地
B:特定居住用宅地
C:A、B以外の小規模宅地
この結果、分割協議において限度内において相続人Aは小規模宅地等の特例、相続人Bは特定事業用資産の特例の適用を受けることができます。また、もっとも納税額が有利になるように減額特例を活用することもできます。
(2)特例適用における有利計算
自社株軽減特例について、平成15年改正で、小規模宅地等の減額特例と自社株軽減特例について、併用不可から併用可に変わり、同時に適用会社が改正前時価総額10億円、上限1/3から、改正後20億円、2/3と大きく変わったため、改正後において、精算課税贈与時から相続迄の各年において、自社株総額が4.5億円以上20億円未満のときは、自社株特例減額の3,000万円がフルに活用できることとなりました。
小規模宅地等の減額特例において、特定事業用宅地(=A)、特定居住用宅地(=B)、その他の宅地(=C)とすると、A、B、Cの評価減の金額が面積換算ベースの400㎡で自社株特例の減額である3,000万円となる土地の単価は、
A=93,750円、
B=156,250円、
C=300,000円
になります。したがって、 Xが上限の3億円のときは、これらの土地単価以下であれば自社株軽減特例を優先したほうが有利です。たとえば特定事業用宅地(=A)が800㎡(@90,000円)であって特定居住用宅地(=B)、その他の宅地(=C)がない場合には
単価90,000円×上限400㎡×80%=28,800千円<自社株軽減額30,000千円
となり、自社株軽減特例を優先したほうが有利です。
この単価以上の相続土地が、
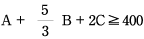 のときは、
のときは、
小規模宅地等の減額特例が有利ですが、
この単価以上の土地で、
面積が
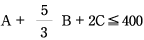 のときは、
のときは、
常に併用することが考えられます。
事業承継税制の改正(3)小規模宅地等に係る課税価格の特例(措置法69条の4)
税理士 竹内陽一
公認会計士 長谷川敏也
ポイント
1. 特定同族会社事業用宅地等(80%評価減)特例が拡充されました。
2. 相続時精算課税度が創設されましたが、「小規模宅地等の減額特例」には影響はなく、一方相続時精算課税制度の選択適用を受ける特定受贈同族会社株式等は相続時に「特定事業用資産についての評価減特例」対象として取り扱われます。
3. 小規模宅地等の減額特例で面積限度まで余裕がある場合に、自社株軽減特例が余裕分の割合で適用することができるようになりました。また、いずれを優先的に適用しなければならない旨の規定はありませんので、逆に自社株軽減特例の適用を優先して、その限度までの余裕分を小規模宅地等の減額特例が適用できます。
1. 相続時精算課税と小規模宅地等の減額特例
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続の間で資産移転時期の選択に対して税制の中立性を確保する趣旨のものであり、この趣旨からは小規模宅地等の減額特例を生前贈与時に適用することが制度本来のあり方かもしれません。
しかし、相続時精算課税制度はその取得原因が「贈与」であり、また相続時精算課税制度はその財産に制限がありませんが、措置法69条の4は特段の改正がありませんので、残念ながら贈与時に小規模宅地等の減額特例の適用はありません(措通69-4-1)。したがって、相続時精算課税制度により生前贈与された宅地は、相続時に小規模宅地等の減額特例は適用できませんので、親が引き続き所有していたほうが有利である場合にはその宅地等は贈与計画から除くべきでしょう。
一方、「特定事業用資産についての特例」(いわゆる自社株軽減特例)では生前贈与した特定事業用資産であっても、相続時に「特定事業用資産についての評価減特例」対象として取り扱われます。
2. 特定同族会社事業用宅地等(80%評価減)の改正
(1) 改正のポイント
小規模宅地等の減額特例のうち、「特定同族会社事業用宅地等」の80%評価減の特例が拡充されました。従来の要件のうち、「被相続人および生計を一にする親族の出資割合が50%以上」という要件は、実務上厳しいものであり、生計を別にする親族に生前に出資を大幅に譲渡(贈与)してしまうと、この「特定同族会社事業用宅地等」の80%減額特例が活用できませんでした。そこで、都心で事業を経営している中小企業オーナーの事業承継対策では、相続開始の時にどのような出資割合になるかまで考慮していたところです。この制限が、今般の改正によって大きく緩和されています。
(2)同族法人の要件の拡充
特定同族会社事業用宅地の特例を受けることができる同族法人の要件が、「相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式等の総数がその法人の発行済み株式総数の10分の5を超える法人」に改められました。
この結果、特定同族会社事業用宅地に該当する範囲が拡大され、事業承継対策がより行いやすくなりました(措69の4③四)。
ここで、政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者をいいます。
一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 被相続人の使用人
三 被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五 次に掲げる法人
イ 被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該法人の発行済株式の総数又は出資金額(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該法人
ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が有する他の法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の法人
ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が有する他の法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合における当該他の法人
(3)議決権に制限のある株式がある場合
なお、これらの規定の適用に当たっては、議決権に制限のある株式・出資は含まないものとし、具体的には、相続開始の時において、商法第222条第4項に規定する議決権制限株式で議決権を行使すべき事項の全部について議決権を有しないもの、同法第241条第2項(自己株式)又は第3項(4分の1超を保有されている会社が保有する会社の株式を持っている(相互持合)場合)の規定により議決権を有しないものとされる株式その他の議決権のない株式等はカウントからはずされます(措令40の2⑩、措規則23の2)。
(4)特定同族会社事業用宅地の特例判定のまとめ
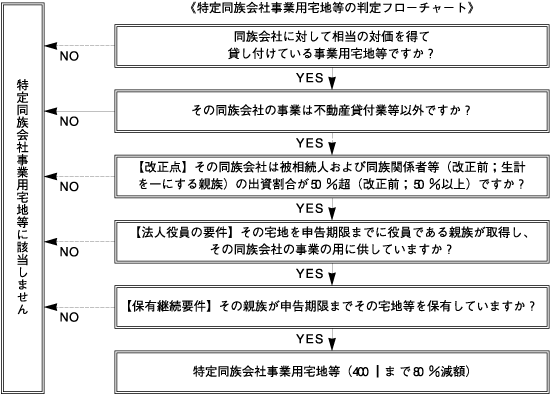
3. 小規模宅地等の減額特例と特定事業用資産の特例の併用
(1)小規模宅地等の減額特例と特定事業用資産の特例の併用規定
小規模宅地等または特定同族会社株式等、そして特定受贈同族会社株式等については相続税の課税価格の計算の特例を受けることができる土地等の面積または価額について、一定の制限がありますが、納税者の選択した面積または価額について余裕がある場合、特例の併用ができることになりました。
すなわち措置法69条の5第7項は「小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計が400平方メートル未満である場合には、選択特定事業用資産の価額に400平方メートルから当該面積の合計を控除したものの400平方メートルに占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、同項の規定を適用する。」とあります。
このことを算式で表現すると以下のようになります(措通69の5-25)。
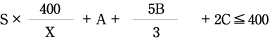
S:3億円以下の範囲で選択した自社株
X:3億円又は2/3枠が3億円以下の場合の2/3枠相当額として選択できる上限額
S、Xの単位:1億円
A、B、Cの単位:平方メートル
A:特定事業用宅地
B:特定居住用宅地
C:A、B以外の小規模宅地
この結果、分割協議において限度内において相続人Aは小規模宅地等の特例、相続人Bは特定事業用資産の特例の適用を受けることができます。また、もっとも納税額が有利になるように減額特例を活用することもできます。
(2)特例適用における有利計算
自社株軽減特例について、平成15年改正で、小規模宅地等の減額特例と自社株軽減特例について、併用不可から併用可に変わり、同時に適用会社が改正前時価総額10億円、上限1/3から、改正後20億円、2/3と大きく変わったため、改正後において、精算課税贈与時から相続迄の各年において、自社株総額が4.5億円以上20億円未満のときは、自社株特例減額の3,000万円がフルに活用できることとなりました。
小規模宅地等の減額特例において、特定事業用宅地(=A)、特定居住用宅地(=B)、その他の宅地(=C)とすると、A、B、Cの評価減の金額が面積換算ベースの400㎡で自社株特例の減額である3,000万円となる土地の単価は、
A=93,750円、
B=156,250円、
C=300,000円
になります。したがって、 Xが上限の3億円のときは、これらの土地単価以下であれば自社株軽減特例を優先したほうが有利です。たとえば特定事業用宅地(=A)が800㎡(@90,000円)であって特定居住用宅地(=B)、その他の宅地(=C)がない場合には
単価90,000円×上限400㎡×80%=28,800千円<自社株軽減額30,000千円
となり、自社株軽減特例を優先したほうが有利です。
この単価以上の相続土地が、
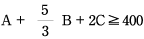 のときは、
のときは、小規模宅地等の減額特例が有利ですが、
この単価以上の土地で、
面積が
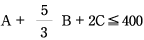 のときは、
のときは、常に併用することが考えられます。
| | ||
| | | |
| Aの土地 | 93,750円 | 62,500円 |
| Bの土地 | 156,250円 | 104,167円 |
| Cの土地 | 300,000円 | 200,000円 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















