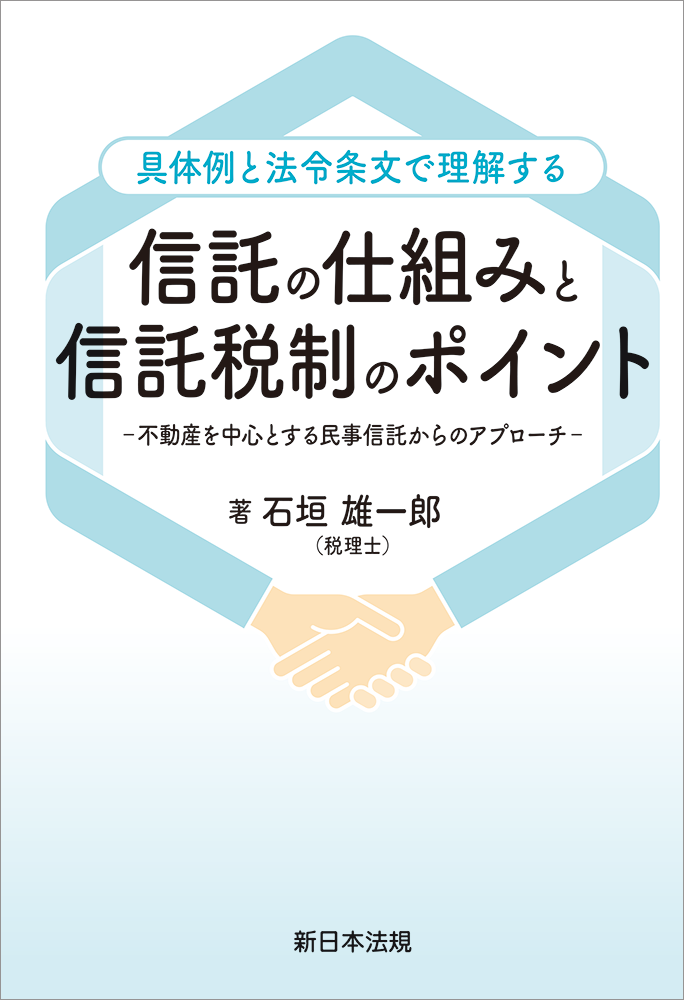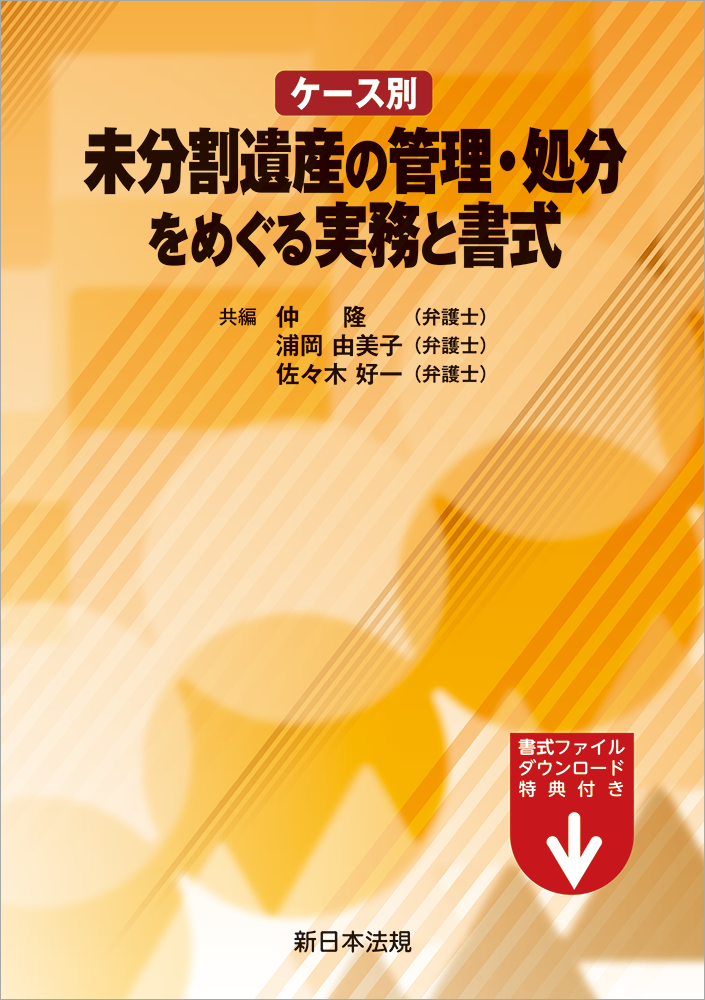解説記事2004年05月03日 【ニュース特集】 わかりやすい!日米新租税条約の改正点(2004年5月3日号・№065)
ニュース特集
知らなきゃ損!世界の最先端を行く画期的な租税条約
わかりやすい!日米新租税条約の改正点
昨年11月に調印された日米新租税条約は、特許使用料や配当など源泉徴収分の減免規定が今年7月1日から、源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては来年1月1日以降に開始する各事業年度の所得から適用されます。財務省は、この日米新租税条約を新たな「国際標準」と位置づけており、今後、この条約ポリシーを英仏独など欧州主要国、中国やアジア各国との租税条約に反映させたい考えです。
今回は、投資交流促進のための「1.投資所得(配当、利子、使用料)に関する源泉地国課税の大幅軽減」、課税年度終了時から7年以内に調査を開始しない場合にはその処分を行うことができない「2.移転価格課税の期間制限」、所定の要件を満たした居住者に対してのみ条約の特典を付与する「3.特典制限条項の導入」を取り上げ、わかりやすく解説します。
1.投資所得(配当、利子、使用料)に関する源泉地国課税の大幅軽減
日米間における投資交流の一層の促進を図るため、配当、利子、使用料に関する源泉地国における課税が大幅に軽減されました。
租税条約による投資交流促進(イメージ)
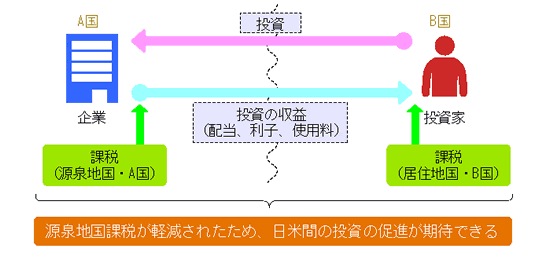
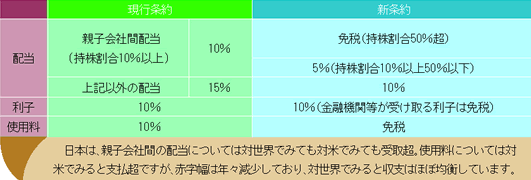
【配当】
新条約では、持株割合50%超の会社からの配当については免税、持株割合10%以上50%以下の会社からの配当については源泉徴収税率を5%、それ以外の配当は、10%に軽減されました。これにより、日本から米国へ進出している子会社(約3,600社)のうち9割以上が免税の対象となります。大幅な資本輸入国である米国が、免税とする範囲を持株割合50%超のケースにまで譲歩したのは初めてのことです。
【利子】
利子に対する源泉徴収税率は現行条約・新条約いずれも10%ですが、金融機関等が受け取る利子は免税とされました。金融機関等とは、銀行、保険、登録を受けた証券会社のこと。これ以外にも、直前の三課税年度においてバランスシート上の負債の50%を超える部分が金融市場における債券の発行又は有利子預金からなっていること、かつ、資産の50%を超える部分が非関連者に対する貸付である場合には、受取利子が免税となります。
【使用料】
特許権等の使用料(ロイヤリティ)については、現行は10%の源泉徴収税を課していましたが、新条約では一律免税となりました。免税にした理由は、①米国企業あるいは欧州企業からの対日投資促進を図るため、②アジア諸国と使用料に対する源泉税率を引き下げるための交渉を行っていくため、とされています。前述したとおり、使用料は対米でみると支払超ですが、ここ5年で急速に支払超額が縮小してきており、将来的には税収の観点から日本が有利となることが予想されます。
OECDモデル条約(※)では、配当は資本関係が10%以上の親子間で5%、その他の配当は15%、利子は日米と同様に10%、使用料は免税になっています。
2.移転価格課税
移転価格課税の期間制限が導入されたことに加え、OECD移転価格ガイドラインの遵守が明記されました。

移転価格課税とは、互いの国の子会社との取引を利用した所得の国外移転を防止するため、その取引を通常の取引価格(独立企業間価格)に引き直して課税する制度です。日本の移転価格課税の更正期間制限は法定申告期限等から6年以内(除斥期間)(措法66条の4⑯)とされていますが、米国ではこれまで、移転価格課税の処分を行う期間制限が設けられていませんでした。しかし、日本企業からしてみると、いつまでも租税法上の安定的な地位が得られない上、帳簿を保存しておく等の実務的な負担もあり、改善が望まれていました。
今回の規定で、両国とも、課税年度終了時から7年以内に調査を開始しない場合にはその処分を行うことができないこととされました。ただし、 IRS(米国内国歳入庁)が調査に一旦着手すれば、調査が終了するまでは調査を受けなければならず、調査開始時点が1つのメルクマールになっています。また、不正に租税を免れた場合、定められた期間内に調査を開始することができないことが当該企業の作為もしくは不作為に帰せられる場合には適用されません。
米国は、この制度を懲罰的に使い、多くの日系企業に巨額の課税をしていましたが、遡及期間が限られることで日系企業が過年度を対象とした巨額の課税処分を受ける懸念が薄れ、米国での事業展開がしやすくなります。
3.租税回避の防止のための特典制限条項の導入
現行条約では、居住者であれば条約の特典が付与されていましたが、新条約においては投資所得に対する源泉地国課税が大幅に軽減されることから、第三国居住者による条約の濫用を防止するため、所定の要件を満たした居住者に対してのみ条約の特典を付与することとされました。
特典制限条項の適用(イメージ)
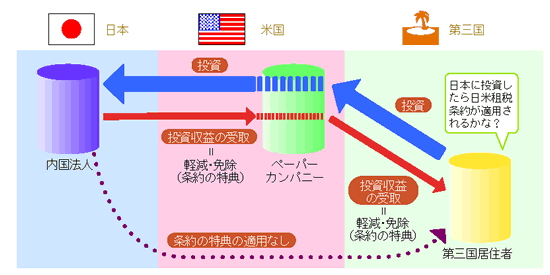
右頁の「特典を与えるかどうかの3つの基準」をご覧ください。一番目の適格者基準は、まず者としての適格性を判断するための基準です。この適格者基準を満たしている場合は、その者がどういう取引をしても基本的には日米条約上の恩典が与えられることになります。一定の公開会社というのは、公開されていても休眠会社であってはならないという趣旨で、直前の課税年度中に株の取引が発行済株式の6%以上ないといけないと規定(議定書第11項)されています。
二番目の能動的事業活動基準は、適格者基準に当てはまらない場合であっても、ある所得がこの基準を満たしていれば、その所得に対して条約の恩典が与えられるという基準です。この場合の「能動的」の定義に関しては、IRSがケースバイケースで判断することとしているようです。新条約上は、第22条第2項(a)に、「当該居住者が自己の勘定のために投資を行い、又は管理する活動」は能動的ではない可能性があると規定されています(銀行、保険会社、証券会社を除く)。
三番目の権限ある当局の認定は、適格者基準や能動的事業活動基準を満たしていない場合であっても、個別に国税当局が濫用のおそれはないと認定した場合に、特典を与えられることとされています。
形式的には米国の居住者であっても、実は第三国にこの米国居住者の実質的な所有者がいて、それが米国のペーパーカンパニー(※)をコントロールしているというような場合には、この米国居住者に対するリターンに対しては、当初から日米条約上の恩典は与えるべきではないというのが基本的な考えです。
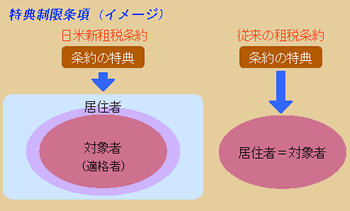
特典を与えるかどうかの3つの基準
【1.適格者基準】
● 個人、国、一定の公開会社、一定の公益法人、一定の年金基金
● その他の法人又は団体(次のいずれの要件も満たす場合)
・居住地国の適格者によって支配されていること
・第三国居住者に対して一定以上の所得移転が行われていないこと
【2.能動的事業活動基準】
● 次の3つの要件を満たす者
・居住地国で営業、事業の活動に能動的に従事していること
・その取得する所得が上記営業又は事業の活動に関連、付随しているものであること
・条約の特典に関する要件を満たしていること
<上記の者で、相手国内にPE(※)を有するもの>
・上記の要件に加えて、相手国内で行う営業又は事業の活動から所得を得る場合は、自らが居住地国で行うその営業又は事業の活動が実質的なものであること
【3.権限のある当局の認定】
●上記1.の者に該当せず、かつ、上記2.の特典を受ける権利を有しないもので、権限のある当局により認定を受けたもの
日米経済と国際租税戦略
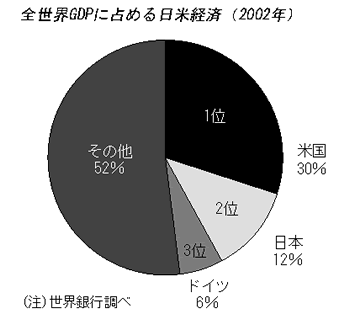
世界1位、2位の経済大国である日米間の経済交流は、既に、成熟した関係だ。配当や使用料の源泉地国課税を免税にしても日米両国との税収の「損得」に大差がなく、経済交流の促進が期待できることが、踏み込んだ条約改正につながったものと思われる。
また、今回の日米租税条約は、対アジア、対欧州など、今後の日本と他国との租税条約のモデルと位置づけられるものだ。アジア各国と使用料免税などを盛り込んだ租税条約ができれば、日本企業の経済戦略がより有利になることは必至だからだ。この時期に日本が日米租税条約の改正を行った背景には、平成15年度税制改革で手当てされたIT投資減税、研究開発税制の整備に引き続き、国際租税の面からも日米間の直接投資を促進することで、日本経済の活性化を図ろうという意図がある。この戦略は同時に、米国以外の他の国との租税条約に、財務省が「国際標準」と意気込む今回の租税条約が展開されてこそ、意味を持つものになるといえるのだ。他国との条約改定交渉が早期に開始されることが期待される。
用語解説
OECDモデル条約:OECD(経済協力開発機構)が定めた二国間の課税に関して二重課税の排除や共通の課税ルール等、各国租税条約の範となるべきもの。
ペーパーカンパニー:登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社のこと。
PE:Permanent Establishment(恒久的施設)の略。営業又は事業活動を行うための支店等のこと。
知らなきゃ損!世界の最先端を行く画期的な租税条約
わかりやすい!日米新租税条約の改正点
昨年11月に調印された日米新租税条約は、特許使用料や配当など源泉徴収分の減免規定が今年7月1日から、源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては来年1月1日以降に開始する各事業年度の所得から適用されます。財務省は、この日米新租税条約を新たな「国際標準」と位置づけており、今後、この条約ポリシーを英仏独など欧州主要国、中国やアジア各国との租税条約に反映させたい考えです。
今回は、投資交流促進のための「1.投資所得(配当、利子、使用料)に関する源泉地国課税の大幅軽減」、課税年度終了時から7年以内に調査を開始しない場合にはその処分を行うことができない「2.移転価格課税の期間制限」、所定の要件を満たした居住者に対してのみ条約の特典を付与する「3.特典制限条項の導入」を取り上げ、わかりやすく解説します。
1.投資所得(配当、利子、使用料)に関する源泉地国課税の大幅軽減
日米間における投資交流の一層の促進を図るため、配当、利子、使用料に関する源泉地国における課税が大幅に軽減されました。
租税条約による投資交流促進(イメージ)
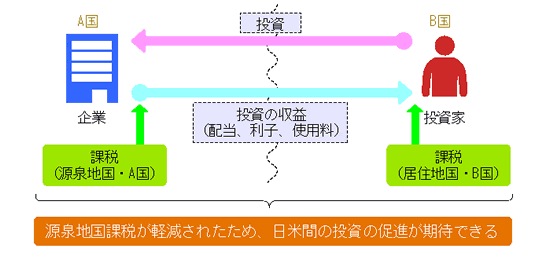
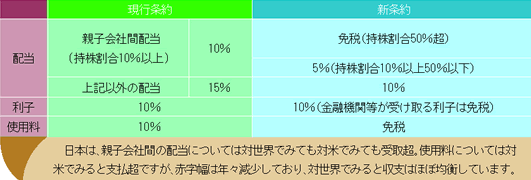
【配当】
新条約では、持株割合50%超の会社からの配当については免税、持株割合10%以上50%以下の会社からの配当については源泉徴収税率を5%、それ以外の配当は、10%に軽減されました。これにより、日本から米国へ進出している子会社(約3,600社)のうち9割以上が免税の対象となります。大幅な資本輸入国である米国が、免税とする範囲を持株割合50%超のケースにまで譲歩したのは初めてのことです。
【利子】
利子に対する源泉徴収税率は現行条約・新条約いずれも10%ですが、金融機関等が受け取る利子は免税とされました。金融機関等とは、銀行、保険、登録を受けた証券会社のこと。これ以外にも、直前の三課税年度においてバランスシート上の負債の50%を超える部分が金融市場における債券の発行又は有利子預金からなっていること、かつ、資産の50%を超える部分が非関連者に対する貸付である場合には、受取利子が免税となります。
【使用料】
特許権等の使用料(ロイヤリティ)については、現行は10%の源泉徴収税を課していましたが、新条約では一律免税となりました。免税にした理由は、①米国企業あるいは欧州企業からの対日投資促進を図るため、②アジア諸国と使用料に対する源泉税率を引き下げるための交渉を行っていくため、とされています。前述したとおり、使用料は対米でみると支払超ですが、ここ5年で急速に支払超額が縮小してきており、将来的には税収の観点から日本が有利となることが予想されます。
OECDモデル条約(※)では、配当は資本関係が10%以上の親子間で5%、その他の配当は15%、利子は日米と同様に10%、使用料は免税になっています。
2.移転価格課税
移転価格課税の期間制限が導入されたことに加え、OECD移転価格ガイドラインの遵守が明記されました。

移転価格課税とは、互いの国の子会社との取引を利用した所得の国外移転を防止するため、その取引を通常の取引価格(独立企業間価格)に引き直して課税する制度です。日本の移転価格課税の更正期間制限は法定申告期限等から6年以内(除斥期間)(措法66条の4⑯)とされていますが、米国ではこれまで、移転価格課税の処分を行う期間制限が設けられていませんでした。しかし、日本企業からしてみると、いつまでも租税法上の安定的な地位が得られない上、帳簿を保存しておく等の実務的な負担もあり、改善が望まれていました。
今回の規定で、両国とも、課税年度終了時から7年以内に調査を開始しない場合にはその処分を行うことができないこととされました。ただし、 IRS(米国内国歳入庁)が調査に一旦着手すれば、調査が終了するまでは調査を受けなければならず、調査開始時点が1つのメルクマールになっています。また、不正に租税を免れた場合、定められた期間内に調査を開始することができないことが当該企業の作為もしくは不作為に帰せられる場合には適用されません。
米国は、この制度を懲罰的に使い、多くの日系企業に巨額の課税をしていましたが、遡及期間が限られることで日系企業が過年度を対象とした巨額の課税処分を受ける懸念が薄れ、米国での事業展開がしやすくなります。
3.租税回避の防止のための特典制限条項の導入
現行条約では、居住者であれば条約の特典が付与されていましたが、新条約においては投資所得に対する源泉地国課税が大幅に軽減されることから、第三国居住者による条約の濫用を防止するため、所定の要件を満たした居住者に対してのみ条約の特典を付与することとされました。
特典制限条項の適用(イメージ)
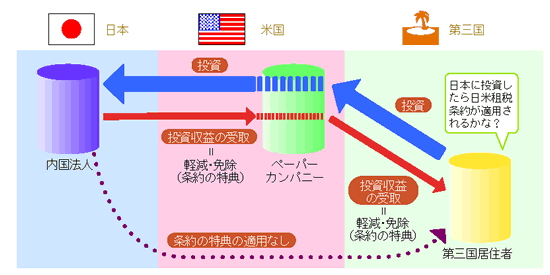
右頁の「特典を与えるかどうかの3つの基準」をご覧ください。一番目の適格者基準は、まず者としての適格性を判断するための基準です。この適格者基準を満たしている場合は、その者がどういう取引をしても基本的には日米条約上の恩典が与えられることになります。一定の公開会社というのは、公開されていても休眠会社であってはならないという趣旨で、直前の課税年度中に株の取引が発行済株式の6%以上ないといけないと規定(議定書第11項)されています。
二番目の能動的事業活動基準は、適格者基準に当てはまらない場合であっても、ある所得がこの基準を満たしていれば、その所得に対して条約の恩典が与えられるという基準です。この場合の「能動的」の定義に関しては、IRSがケースバイケースで判断することとしているようです。新条約上は、第22条第2項(a)に、「当該居住者が自己の勘定のために投資を行い、又は管理する活動」は能動的ではない可能性があると規定されています(銀行、保険会社、証券会社を除く)。
三番目の権限ある当局の認定は、適格者基準や能動的事業活動基準を満たしていない場合であっても、個別に国税当局が濫用のおそれはないと認定した場合に、特典を与えられることとされています。
形式的には米国の居住者であっても、実は第三国にこの米国居住者の実質的な所有者がいて、それが米国のペーパーカンパニー(※)をコントロールしているというような場合には、この米国居住者に対するリターンに対しては、当初から日米条約上の恩典は与えるべきではないというのが基本的な考えです。
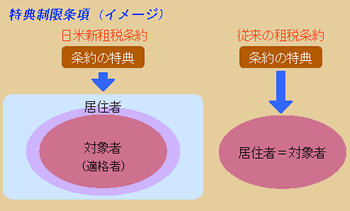
特典を与えるかどうかの3つの基準
【1.適格者基準】
● 個人、国、一定の公開会社、一定の公益法人、一定の年金基金
● その他の法人又は団体(次のいずれの要件も満たす場合)
・居住地国の適格者によって支配されていること
・第三国居住者に対して一定以上の所得移転が行われていないこと
【2.能動的事業活動基準】
● 次の3つの要件を満たす者
・居住地国で営業、事業の活動に能動的に従事していること
・その取得する所得が上記営業又は事業の活動に関連、付随しているものであること
・条約の特典に関する要件を満たしていること
<上記の者で、相手国内にPE(※)を有するもの>
・上記の要件に加えて、相手国内で行う営業又は事業の活動から所得を得る場合は、自らが居住地国で行うその営業又は事業の活動が実質的なものであること
【3.権限のある当局の認定】
●上記1.の者に該当せず、かつ、上記2.の特典を受ける権利を有しないもので、権限のある当局により認定を受けたもの
日米経済と国際租税戦略
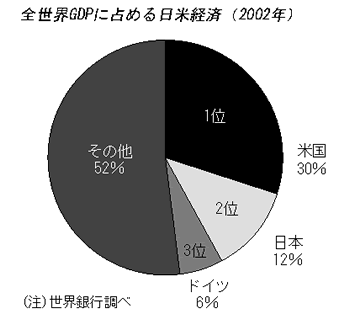
世界1位、2位の経済大国である日米間の経済交流は、既に、成熟した関係だ。配当や使用料の源泉地国課税を免税にしても日米両国との税収の「損得」に大差がなく、経済交流の促進が期待できることが、踏み込んだ条約改正につながったものと思われる。
また、今回の日米租税条約は、対アジア、対欧州など、今後の日本と他国との租税条約のモデルと位置づけられるものだ。アジア各国と使用料免税などを盛り込んだ租税条約ができれば、日本企業の経済戦略がより有利になることは必至だからだ。この時期に日本が日米租税条約の改正を行った背景には、平成15年度税制改革で手当てされたIT投資減税、研究開発税制の整備に引き続き、国際租税の面からも日米間の直接投資を促進することで、日本経済の活性化を図ろうという意図がある。この戦略は同時に、米国以外の他の国との租税条約に、財務省が「国際標準」と意気込む今回の租税条約が展開されてこそ、意味を持つものになるといえるのだ。他国との条約改定交渉が早期に開始されることが期待される。
用語解説
OECDモデル条約:OECD(経済協力開発機構)が定めた二国間の課税に関して二重課税の排除や共通の課税ルール等、各国租税条約の範となるべきもの。
ペーパーカンパニー:登記書類の上で存在するだけで、事業所や従業員を有しない実体のない会社のこと。
PE:Permanent Establishment(恒久的施設)の略。営業又は事業活動を行うための支店等のこと。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -