解説記事2004年11月29日 【最新判決研究】 修正申告時の隠ぺい・仮装行為と重加算税賦課の当否(2004年11月29日号・№092)
修正申告時の隠ぺい・仮装行為と重加算税賦課の当否
東京地裁平成13年(行ウ)第157号 平成16年1月30日判決
東京高裁平成16年(行コ)第63号 平成16年7月21日判決
品川 芳宣
筑波大学大学院教授
一、事実
(1)X(原告、控訴人)及び乙(Xの母、甲の妻)は、平成7年12月12日死亡した甲(Xの父)を相続(以下「本件相続」という。)した。また、丙(当時検事正)は、Xの夫である(Xと丙を併せて、以下「Xら」という。)。
Xは、平成8年7月15日、Y(被告、被控訴人)税務署長に対し、本件相続に係る相続税を申告(以下「本件当初申告」という。)し、申告書(以下「本件当初申告書」という。)に相続財産の価額を3億5927万円余と記載した。
乙は、昭和60年頃から同人名義でN銀行S支店との間で割引興業債券の取引を行っていたが、平成7年12月当時、その額面総額が2億6000万円(以下「本件ワリコー」という。)であった。
Yの担当係官は、本件相続に係る相続税の調査を開始し、平成9年12月22日、本件ワリコー及び乙名義の定期預金等について、Xに対してメモを渡し、それらの存在と原資について確認を求め、前記乙名義の定期預金の一部が甲の相続財産に該当する旨説明した。
(2)これを受けて、Xは、平成10年2月16日、Yに対し、前記定期預金のうち9200万円が甲の相続財産に当たるとする修正申告書(以下「本件第1次修正申告書」という。)を提出した(以下「第1次修正申告」という。)。
Yの担当係官は、更に調査を行い、Xらに対し、本件ワリコーも甲の相続財産に含まれるか否かについて確認を求めた。これを受けて、Xは、平成10年5月27日、Yに対し、本件ワリコーを甲の相続財産に加える旨の修正申告書(以下「本件第2次修正申告書」という。)を提出した(以下「本件第2次修正申告」という。)。本件第2次修正申告書に記載された相続財産の価額は、7億1025万円余である。
Yは、平成10年6月30日、Xに対し、重加算税の額を3786万円余とする賦課決定処分(以下「本件処分」という。)をした。Xは、本件処分を不服として、不服申立ての前置を経て、本訴を提起した。
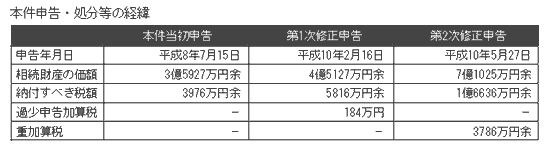
二、争点と当事者の主張
1 争点
(1)Xが、本件当初申告について、相続税の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づき本件当初申告書を提出したか否か。
(2)法定申告期限の経過後にされた修正申告についても、国税通則法(以下「通則法」という。)68条1項の適用があるか否か。
(3)Xが、本件第1次修正申告について、相続税の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づき本件第1次修正申告書を提出したか否か。
2 Xの主張
(1)Xは、そもそも本件当初申告において、本件ワリコーを含む相続財産を隠ぺい又は仮装したことはない。このことは、以下のとおりの事情から裏付けられる。
Xは、父、夫ともに検察官という遵法精神の高い生活環境にあったものであり、脱税が刑事罰を伴う重罪であること、また、Xが脱税した場合、その発覚によって甲の名誉はおろか、当時検事正であった丙がその地位を失う可能性が高いことを十分認識していたのであるから、かかる危険性を顧慮することなくXが脱税を図るとは考えられない。
本件ワリコーは、額面2億6000万円という金額であり、本件当初申告における申告額の約7割にものぼる金額であり、検察官の家庭に育ち検察官の妻であるXがかかる巨額の脱税をするのは不自然であり、むしろ、このような事情は、Xが本件ワリコーの存在を認識していなかったことを裏付けるものである。そして、Xは、本件当初申告に際し、乙は、本件ワリコーを自己の財産と認識していたため、Xに対して本件ワリコーが相続財産であると告知することはなく、そのため、Xは、本件ワリコーの存在すら認識しておらず、その認識の機会もなかった。
(2)修正申告は、申告義務のない任意の申告にすぎないから、通則法68条1項の適用はなく、したがって、本件第1次修正申告については、重加算税を課すことはできない。
通則法68条1項に定める重加算税賦課制度は、申告納税制度のもとにおいて、不正な申告に対し重い制裁を課して上記制度を守ろうとするものであり、申告義務ないし納付義務違反があり、その違反の態様が隠ぺい又は仮装を伴うときに、過少申告加算税、無申告加算税ないし不納付加算税を課すのに代えて重く課するという制度である。そうすると、通則法19条に規定する修正申告書は、原則として、提出を義務付けられていない任意的な申告書にすぎず、納税者において修正すべき事実を発見してもこれを申告すべき義務は存在しないのであるから、前述した重加算税の制度趣旨に照らせば、修正申告について重加算税を課すことはできず、同項にいう「納税申告書」には「修正申告書」は含まれないと解すべきである。
(3)仮に、修正申告についても通則法68条1項の適用を受けるとしても、本件においては、本件第1次修正申告について、仮装又は隠ぺいの事実は存在しない。
前記のとおり、Xは、乙より依頼を受けて本件ワリコーの償還、購入を行ったにすぎず、本件ワリコーは当初より乙の財産であって、相続財産ではないと考えていたことから、Yの担当係官からの質問に対しても本件ワリコーが相続財産ではないことを前提とする対応を取っていた。
そして、平成10年2月5日になって、Y税務署のI副署長から丙に電話があり、調査の結果、乙名義の定期預金9200万円についで甲の預金が原資であることを確認できたこと、また、これにより調査が終了したので上記定期預金について修正申告するよう申入れがあったが、本件ワリコーについては何の言及もなかった。
以上のとおり、Xは、Yの調査結果に基づくとする修正申告の慫慂に応じて本件第1次修正申告を行ったにすぎず、Yの主張するように、本件ワリコーについて修正申告の対象から除外し、隠ぺい又は仮装する意図は持っていなかったものであり、また、そもそも、Yらの慫慂に基づいてなされた修正申告については、通則法68条1項を適用する余地はないというべきである。
(4)Y税務署の副署長が本件第1次修正申告書の提出の際に「これで終わりです。」と述べたこともこれを裏付けるものである。このような事情があるにもかかわらず、本件ワリコーの隠ぺいに基づき本件第1次修正申告書を提出したとして重加算税を賦課するのは、信義則に反する。
3 Yの主張
(1)本件ワリコーは、甲の死亡時点において額面総額2億6000万円と極めて多額に上るものであり、本件当初申告書に記載された甲の相続財産の価額の合計額の7割を超える金額であるところ、①乙の専従者給与では到底形成できないものであるうえ、②昭和62年5月から平成7年6月までの期間において、甲名義の預金から多額の金員が出金されていること、③本件ワリコーの担当支店であったK銀行S支店における取引カードの顧客名も甲となっていたことからすると、本件ワリコーが甲の資産から形成されたことは明らかであって、これらの事実からすれば、乙も本件ワリコーが相続財産に当たることを認識していたものということができる。
そして、Xは、相続時において、甲と乙の一人娘であり、本件当初申告当時、一緒に同居するなどからみて、Xも本件ワリコーが甲の相続財産であることを認識していたとみるのが自然である。
(2)Xの過少申告行為は、単に真実の相続財産の価額よりも少ない価額を記載した納税申告書であることを認識しながらこれを提出したというにとどまらず、本件ワリコーが無記名債券で、かつ、現物取引であって調査解明に困難が伴う状況を利用し、これを隠ぺいしようという確定的な意図の下に申告額の7割以上にも及ぶ多額の相続財産を除外することにより、課税価格をことさら過少に記載した内容虚偽の本件当初申告書を提出したものであり、本件当初申告書の提出後においても、本件ワリコーの存在を隠匿し続けるため、煩雑な方法で償還、購入を繰り返すという手続を行うとともに、税務調査に対しては一貫してその存在を否定し続けるなどして、本件ワリコーを隠ぺいする態度、行動をできる限り貫こうとしたものであるから、これらの行為は、隠ぺい又は仮装に当たる。
(3)過少申告加算税、無申告加算税に代えて、重加算税という重い加算税が課されるのは、法定申告期限内に適正な申告をしなかっただけにとどまらず(これに対する行政上の制裁としては、過少申告加算税・無申告加算税が課される。)、不正手段を用いた申告をした点に求められるというべきであるから、かかる悪質な申告が行われた以上は、これに対して重い行政上の制裁を課し、厳しくこれを取り締まる必要があるというべきである。そうすると、重加算税の対象となる納税申告は、期限内申告に限らず、修正申告、期限後申告も含まれるというべきであって、申告書の提出義務があるかどうかは、重加算税の適用には関わりがないというべきである。
三、判決要旨
請求棄却。
1 本件当初申告における隠ぺい・仮装の有無
(1)乙が甲の生前から本件ワリコーの取引を行っていたことについては当事者間に争いがないことから、乙において、本件当初申告の際、本件ワリコーが自己の財産であると認識していたか否かの点を検討する。
この点につき、Xは、乙は本件ワリコーが自己の財産であると認識していたと主張する。
しかし、前記認定事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば、①昭和62年5月から平成7年6月までの期間において、本件ワリコーの基になったワリコーが1億5000万円増加しているところ、同期間において甲名義の預金から多額の金員が出金されていること、②本件ワリコーの担当支店であったK銀行S支店における取引カードの顧客名は、甲となっていたこと、③乙は、不服審査手続において、本件ワリコーは自分の父からの贈与と自己の専従者給与から形成取得したと答述しているが、贈与の点についてはこれを認めるに足りる証拠はなく、また、額面総額2億6000万円という本件ワリコーの金額に照らして、その原資が乙の専従者給与のみでは到底蓄積できるものとは考えられないことからすると、本件ワリコーが甲の資産から形成されたことは明らかである。
そして、乙は、本件ワリコーにつき甲の生前から平成9年5月ころまで自ら乗換手続を行っていたものであり、乙は、本件当初申告に先立って、本件ワリコーが相続財産であることについて認識していたものと認められる。
(2)次いで、Xが本件当初申告の際、本件ワリコーが相続財産に属することについて認識していたかどうかにつき検討する。
この点については、Xにおいて、甲の生前、本件ワリコーが甲の財産に属することについて予め認識していたと認めるに足りる証拠はない。
ちなみに、Xは、乙と親子の関係にあり、平成6年3月16日から現在に至るまで、自宅を住所とする住民登録を行い、少なくとも、平成6年3月ころから平成7年11月ころまでの間、一月の半分程度は上記自宅に居住していたことが認められるが、これらの事実だけでは、その間に、乙より教示されるなどして、本件ワリコーの存在を認識したと推認することはできない。
確かに、Xは、多額のワリコーをK銀行の各本支店の窓口に持参し、その一部を償還し、現金化したうえで当該現金とともに別の本支店の窓口に赴き、新たにワリコーを購入するとともに、別途、多額のワリコーを償還して現金化するということを繰り返し行っていたものであり、単に乗換えの趣旨であれば、このように、わざわざ多額の現金及びワリコーを所持しながらK銀行の各本支店を行き来する必要性は乏しいといわざるを得ない。
しかし、Xが上記の償還等の行為を行った時期は、本件当初申告から約1年後のことである。そして、仮に、本件当初申告の際、Xが本件ワリコーの存在を認識しており、またこれを隠ぺいする意図を有していたならば、乙と相談するなどして早期に本件ワリコーについて上記のような手段による償還等を行ってしかるべきであるにもかかわらず、そのような形跡は窺われず、かえって、乙は、平成9年5月までは、従前どおり、担当者を自宅に呼んで乗換手続を行っていたものである。
これらのことからすれば、Xが上記の償還等の行為を行っていることをもって、Xが本件当初申告時において本件ワリコーの存在を認識していたと推認することはできない。
2 修正申告にも通則法68条1項の適用があるか。
(1)重加算税制度は、申告納税制度の下において、納税者に適正な申告をさせるべく、納付すべき税額の計算の基礎となる事実について隠ぺい又は仮装するという不正手段を用い、これに基づいて申告等がされたときに、当該申告を行った者に対して過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするところにあるものと解される(最高裁判所第二小法廷平成7年4月28日判決)。
(2)通則法68条1項にいう「納税申告書」とは、申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により、課税標準等及び税額等の事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいうところ(同法2・六)、修正申告書(同法19条③)も「納税申告書」に該当することは、同法の上記規定に照らして明らかであり、同法68条1項の文理上、通常の期限内申告と修正申告を別異に解すべき理由はない。
そして、修正申告も、納税義務を負う税額を確定させる行為であり、その際に隠ぺい又は仮装したところに基づいて過少申告が行われた場合には、その制度の基礎が害されることとなることは、期限内申告と同様であるから、実質的にみても、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって悪質な納税義務違反の発生を防止すべき必要性が存することは異ならない。
したがって、通則法68条1項にいう「納税申告書」には、同法19条3項所定の修正申告書も含まれるというべきであって、納税義務者が、その国税の課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて修正申告書を提出していたときは、その納税者に対して重加算税を課することができると解するのが相当である。
(3)また、Xは、通則法15条2項13号は、重加算税の納税義務の成立時期を「法定申告期限の経過の時」と規定していることからすれば、重加算税を賦課するためには、隠ぺい又は仮装と評価すべき行為が本件当初申告時に存在することが必要であると主張する。
しかし、通則法15条2項は、昭和37年の通則法の制定に当たり、納税義務は成立しているが納付すべき税額が確定していない税額の徴収手続として繰上保全差押制度(通則法38条③)が創設されたことに伴い、国税の納税義務の成立時期を明確にする趣旨から、主として繰上請求の観点からみて必要な範囲において、同法15条2項各号又は通則法施行令5条に、各税目ごとの成立時期が規定されたものであると解すべきである。
このことは、同法65条1項及び68条1項の規定に照らしても明らかである。
すなわち、同法15条2項13号は、過少申告加算税についても、その納税義務の成立時期を「法定申告期限の経過の時」と定めている。しかし、仮に、Xが主張するように、同法15条2項13号に基づいて、法定申告期限の経過の時までに加算税の課税要件が充足される必要があると解するとすれば、この場合、法定申告期限の経過時においては、過少申告加算税の課税要件は常に充たされていないのであるから、過少申告加算税を課することはできないことになるが、同法65条1項は、「期限内申告書が提出された場合」には、「期限後申告がされた場合において、次条第1項ただし書の規定の適用があるときを含む。」としており、同法68条1項が、同法65条1項の規定に該当する場合のうち、同法65条5項の規定の適用がある場合を除く外は、重加算税を賦課する対象とする旨を規定していることに照らしても、Xの上記主張のとおり解釈することは困難であるといわざるを得ない。
3 本件第一次申告における隠ぺい・仮装の有無
(1)前記認定事実と証拠及び弁論の全趣旨によれば、①本件ワリコーは額面総額2億6000万円と多額なものであって、その原資は、乙の専従者給与等では到底形成できるものではなかったこと、②Xは、乙が従来行っていた乗換手続の方法によるのではなく、本件ワリコーについて、平成9年7月11日に1000万円、同年9月18日に4000万円、同月19日に2000万円、同年10月9日に3000万円と合計1億円にも上るワリコーを自ら償還、購入しており、その方法も、いずれも債券をいったん現金化したうえで、新たに債券を購入するという複雑なものであり、そのなかでも特に同年9月18日、同月19日及び10月9日については、1000万円以上の現金を所持して各支店を回って償還及び購入の手続を行っていること、③このような方法でのXの償還及び購入の手続は、税務調査の通告があった同年10月22日以降行われておらず、再度行われたのは、本件第1次修正申告がされた後であること、④ワリコーは、無記名債券であり、一般に、これが現物で取引されている場合には、当該債券の真実の所有者を特定することが困難であり、乗換えの場合は、旧債券と新債券の連続性が取引記録上確認できるのに対し、旧債券をいったん現金に償還したうえで新債券を購入する場合は、取引記録などから旧債券と新債券との連続性を確認して真実の所有者を把握することは容易でないことが、それぞれ認められる。
これらの事実に照らせば、Xの上記②の行為、すなわちXが行った本件ワリコーについての償還、購入手続は、X自身が本件ワリコーが甲の相続財産であることを認識していたことを前提としなければ、その行動を合理的に説明することができないものというべきであり、Xは、遅くとも、同一の日に本件ワリコーの償還手続と購入手続をそれぞれ別々の店舗において行った平成9年9月頃には、本件ワリコーが甲の相続財産に属することを認識していたことが推認できるというべきである。
以上認定した事実によれば、Xは、平成9年9月頃には、本件ワリコーが相続財産であることを認識し、かつ、その存在が発覚しないように、その頃から、前記に記載したような煩雑な償還及び購入の手続をあえて行い、同年12月に行われたYの税務調査の中で本件ワリコーの存在について何度も確認を求められたにもかかわらず、乙とともに本件ワリコーの存在を否定して、本件ワリコーを除外した本件第1次修正申告書を提出したものであり、かかるXの行為は、相続税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいしたものと認められる。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。
(1)前記認定事実によれば、平成9年9月までにXが償還と購入を行ったワリコーは7000万円(同年10月分も含めると1億円)にとどまるものの、Xがこのように多額のワリコーの償還と購入を依頼されれば、それがどのようにして取得されたものか、総額がどの程度のものかなどにつき、親子間で話が出るのが通常であると考えられ、上記依頼を受けたワリコーが乙管理に係るものの全部である旨を乙から告げられたなど特段の事情を認めるに足りる証拠がない以上、Xは、償還を頼まれたもの以外にも相続財産に属する管理に係るワリコーがあることを認識していたものと推認することができる。したがって、Xは、その総額についての正確な認識がなかったとしても、平成9年9月の時点において、これら乙管理に係る一群のワリコーの全部(本件ワリコー)を隠ぺいしたものと認定することができる。
(2)通則法68条1項の文理上は修正申告書も「納税申告書」に含まれること、修正申告は期限内申告と同様に納税義務を確定させる行為であり、修正申告には申告の義務がないとしても、申告納税制度維持の観点から修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があること、通則法15条2項13号が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時と定めたのは、実質的には、通則法38条3項の繰上保全差押との関係で納税義務の成立時期を明確にする趣旨にすぎず、この規定からX主張のような重加算税の賦課要件を読み取ることはできないことなどは、原判決に説示するとおりである。したがって、通則法68条1項の「納税申告書」には修正申告書も含まれるものと解すべきである。
Xは、本件のように当初申告後に隠ぺい、仮装行為があった場合について、その後修正申告書を提出しなければ重加算税を課することができないのに、その後申告義務のない修正申告書を提出したときには重加算税が課税されるのは、不公平であるから、修正申告書は通則法68条1項の納税申告書には該当しないと主張する。しかしながら、そのような解釈は前記のとおり文理に反する上、実質的にも修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があることは多言を要しないところであって、到底採用の限りではない。Xのように、当初申告前には隠ぺい、仮装行為がなく、申告後に初めてこれが行われたが、その後は過少申告がされなかったという場合、本件のように後に隠ぺい、仮装行為が発覚して追加課税がされたケースにおいては、隠ぺい、仮装行為を行った者は、税務当局に対しては何ら不正な働きかけをしていないのであるから、納税義務違反の悪質性は過少申告行為を行った者と比較して低いと評価することも可能であろう。そうであれば、Xの主張するような不公平はないともいえるが、いずれにしても、上記のような事態はまれであって、そのような例との比較において文理上も実体上も十分な根拠のある重加算税の課税を否定するのは本末転倒というほかない。
(3)Xは、本件第1次修正申告書を提出する4箇月前の平成9年9月から乙管理に係る一群のワリコーが甲の相続財産に属することを認織していたのであるから、平成10年2月の本件第1次修正申告において、預金のみならず本件ワリコーも申告すべきであった(本件ワリコーの総額の調査に若干の時間を要するとしても、少なくとも、その旨をYの担当官に告げた上で、申告の準備に入り、数週間のうちに追加修正申告をすべきであった。)。それにもかかわらず、Xは、本件第1次修正申告前から、本件ワリコーについて追加の修正申告をする意思を持たないまま、前記認定したとおり、修正申告前の平成9年7月から10月にかけて、さらには修正申告後の平成10年2月から5月にかけて、本件ワリコーの隠ぺいのため、償還と購入の行為を行っていたものである。
このようなX側の事情を考慮すると、仮に、本件第1次修正申告書の提出の際にYの担当官がこれで終わりですという趣旨の発言をしたとしても、それを信用したXを信義則を適用して保獲するまでの事情があるということはできない。
五、解説
はじめに
本件は、検察幹部一家の脱税事件として社会的に注目された事件であるが、重加算税の賦課要件の充足において重要な論点を有している。
すなわち、本件各判決の認定事実によると、Xは、本件相続に係る本件当初申告段階(法定申告期限経過時)では、過少申告について隠ぺい・仮装をしなかったのであるが、その後の第1次修正申告段階における過少申告において隠ぺい・仮装をしたというものである。
かくして、重加算税の賦課要件につき、通則法68条1項が「・・・・その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」と規定し、同法15条2項13号が過少申告加算税に代える重加算税の納税義務の成立の時を「法定申告期限の経過の時」と規定していることに照らし、本件のような場合に、重加算税の賦課要件を充足するか否かが問題視されていた。
もっとも、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為に対する重加算税の賦課決定については、従前においてもその適法性を容認する裁判例が多かったが、その理由付けについて本件各判決とは大きな差異が認められる。そのため、本件各判決は、重加算税の賦課要件について重要な判断を示した先例となるものであるが、その当否について検討を要する。
1 重加算税の賦課要件
(1)通則法68条1項は、「第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(<略>)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、<略>過少申告加算税に代え、<略>重加算税を課する。」と規定している。
このように、過少申告加算税に代えて重加算税が課されるには、①過少申告加算税の賦課要件を充足していること、②納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したこと及び③その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたこと、が要件とされる。
また、通則法68条1項による重加算税は、法定申告期限の経過の時に納税義務が成立するものと定められている(通則法15②一三)。
他方、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、<略>」(通則法70⑤)た場合には、更正決定等の期間制限が、3年又は5年から7年に延長される(同前)。更に、「国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、<略>た国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。」(通則法73③)と定められている。
そして、これらの場合における「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、」とは、各税法の 脱罪の構成要件と同じとなっている(所法238①、法法159①、相法68①、消法64①等参照)。
(2)かくして、以上の各規定から、過少申告加算税に代えて課される重加算税の賦課要件については、①隠ぺい・仮装の意義、②納税者がその隠ぺい・仮装を行うに当たって税を免れようとする意思すなわち故意(認識)が明らかにされている必要があるか否か、③隠ぺい・仮装を行った者(行為者)が納税者本人に限定されるのか、限定されないとした場合のその範囲、④無記帳、不申告、虚偽申告、つまみ申告等のように積極的(外形的)な不正行為を伴わない行為が隠ぺい・仮装行為といえるか否か、⑤法定申告期限後の税務調査時等における虚偽答弁、虚偽資料の提出等が賦課要件を充足し得るか、⑥
脱罪が問われることとなる場合又は更正決定等の期間制限(除斥期間)が延長されること等となる場合の「偽りその他不正の行為により税を免れる」との関係(異同)はどうなるのか、等が問題とされる(注1)。
これらの各問題点については、多くの裁判例で争われてきており(注2)、本件においては、特に、前記⑤の問題点が争われることとなったものである。また、それに関連して、通則法68条1項にいう「・・・・基づき納税申告書を提出していたとき」の「納税申告書」に本件第1次修正申告書のような法定申告期限経過後に提出される修正申告書が含まれるか否かが問題とされている。
(3)なお、前述の重加算税の賦課要件の問題点の解明に当たっては、「国税通則法68条に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各重加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によって行なわれた場合に、行政機関の手続により違反者に課せられるもので、これによってかかる方法による納税義務違反の発生を防止し、もって徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべきである(注3)」とされる重加算税の性質(注4)に照らして論じる必要がある。
2 「納税申告書」の意義・範囲
(1)本件においては、本件各判決の認定事実によると、Xは、本件相続に係る本件当初申告においては過少申告について隠ぺい又は仮装したわけではなく、その後の第1次修正申告において隠ぺい又は仮装したというものである。そのため、まず、通則法68条1項にいう「・・・・基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するか否かが問題とされた。
この点について、一審判決は、「通則法68条1項にいう「納税申告書」とは、申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により、課税標準等及び税額等の事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいうところ(同法2条6号)、修正申告書(同法19条3項)も「納税申告書」に該当することは、同法の上記規定に照らして明らかであり、同法68条1項の文理上、通常の期限内申告と修正申告を別異に解すべき理由はない。」と判示し、「・・・・その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて修正申告書を提出していたときは、その納税者に対して重加算税を課することができると解するのが相当である。」と判示している。
また、控訴審判決も、「通則法68条1項の文理上は修正申告書も、「納税申告書」に含まれること、修正申告は期限内申告と同様に納税義務を確定させる行為であり、修正申告には申告の義務がないとしても、申告納税制度維持の観点から修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があること、<略>したがって、通則法68条1項の「納税申告書」には修正申告書も含まれるものと解すべきである。」と判示している。
(2)確かに、通則法2条6号が「納税申告書」とは、「申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、<略>」と定義しているものであるから、通則法68条1項にいう「納税申告書」には、文理上修正申告書も含まれることになる。また、重加算税は、前述のように、申告秩序維持のための行政制裁であるという性質を有するものであるから、修正申告の段階における悪質な納税義務違反を重加算税賦課の対象とすることも、法の予定しているとも解される。
(3)しかしながら、このような解釈論には、若干の違和感が残る。けだし、通則法68条1項に定める重加算税は、過少申告加算税に代えて課されるところ、過少申告加算税は、「期限内申告書(<略>)が提出された場合(<略>)において、修正申告書の提出又は更正があったとき」(通則法65①)に課されるものである。そして、通則法68条1項は、「第65条第1項(<略>)の規定に該当する場合(<略>)において、<略>その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に重加算税を課する旨定めている。
然すれば、通則法68条1項に定める「納税申告書」は、期限内申告書を予定していることは明らかである。もちろん、「納税申告書」それ自体には、前述のように、修正申告書も含まれることになろうが、通則法68条1項によって重加算税を課す場合には、法定申告期限後の修正申告書の提出を予定していないものと考えられる。
もっとも、本件のような場合に、重加算税を課すこと自体は、法の予定しているところと考えられるのであるが、本件各判決の理由付けの方に問題があるように考えられる。本件各判決は、本件当初申告においてXが隠ぺい・仮装行為としていないという認定の下に、本件第1次修正申告書が通則法68条1項に定める「納税申告書」に含まれるとする理由を導いているが、そこに問題がある。本件においては、認定事実によれば、本件当初申告においてXが隠ぺい・仮装行為をしていなくとも、Xの母親である乙は、本件ワリコーが甲の相続財産に含まれることを認識していたことが容易に推認し得る。
そうであれば、通則法68条1項に定める「納税者」の範囲を従前の裁判例(注5)のように弾力的に解釈すれば、乙の行為をXの行為と同視(推認)することも可能であろうし、それによって、本件処分を適法とすることも可能であると考えられる(もっとも、この点は、本件各判決とも否定している。)。また、その方が、後述する重加算税の納税義務の成立の時期との関係において斉合性を維持し得るもとのと考えられる。
3 隠ぺい・仮装の時期と納税義務の成立
(1)本件において最も重視すべき問題は、前述の納税義務成立との関係上、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することになるか否かである。
従前の裁判例では、隠ぺい・仮装行為の存否の判断は確定申告時(法定申告期限)を基準とすべきとするのが支配的である(注6)。また、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為については、「右確定申告時において原告が隠ぺい又は仮装の意思を有していたか否かを判定するための資料となるにすぎない。」(注7)、「右期限後の隠ぺい・仮装行為は、法定申告時における隠ぺい・仮装行為は、法定申告時における隠ぺい・仮装行為の存否を推認させる一間接事実となりうるに過ぎない。」(注8)、「これに対する課税を回避しようとする意図が当初からあったものと推認することでき、・・・・」(注9)等と解されてきた。
このように、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為を、法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の存在を判断するための「資料」、「間接事実」、「推認事項」等とする考え方は、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することを否定するものではない。
しかしながら、本件のように、法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の存在が否定されたときには、当該充足の根拠を失うことになる。
なお、従前の裁判例においても、前述の推認等とは関係なく、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為について重加算税の賦課要件の充足を肯定するものも見受けられる(注10)が、その論拠が明らかにされたとは言い難い状況にあった。
(2)このような状況の中で、本件各判決は、前述のように、本件第1次修正申告時における隠ぺい・仮装行為について、法定申告期限時の推認等とは関係なく、重加算税の賦課要件を充足するとしている。
その論拠について、一審判決は、「通則法15条2項は、昭和37年の通則法の制定に当たり、納税義務は成立しているが納付すべき税額が確定していない税額の徴収手続として繰上保全差押制度(通則法38条3項)が創設されたことに伴い、国税の納税義務の成立時期を明確にする趣旨から、主として繰上請求の観点からみて必要な範囲において、同条15条2項各号又は国税通則法施行令5条に、各税目ごとの成立時期が規定されたものであると解すべきである。」と判示している。
また、一審判決は、このことは、通則法65条1項が「期限後申告がされた場合において、次条第1項ただし書の規定の適用があるときを含む。」と規定していることからも裏付けられる、としている。
このような考え方は、控訴審判決においても支持されており、同判決は、「通則法15条2項13号が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時と定めたのは、実質的には、通則法38条3項の繰上保全差押との関係で納税義務の成立時期を明確にする趣旨にすぎず、」と判示している。
(3)このように、法定申告期限後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することの論拠が明確にされたことは、裁判例としては初めてのことであるので、極めて注目される。しかしながら、その論拠の妥当性については、依然として疑問が残る。
まず、本件各判決は、通則法が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時としたのは同法38条に定めた繰上請求との関係で定めたもので、同法68条1項の解釈とは関係がないように判示している。しかしながら、税制調査会の「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)及びその説明」(昭和36年7月、以下「通則法制定答申説明」という。)を読む限りでは、本件各判決が判示するようには理解できない。
すなわち、通則法制定答申説明では、租税債権・債務の成立に関し、「所得税については、課税標準の計算期間である1暦年が経過して所得税法の実体的規定に定める課税要件が充足されると、租税債権・債務が成立する。」(注11)と述べ、繰上請求との関係についても、「暦年が経過すると租税債権は成立しているので、これをその確定時まで待たなければならない必要は理論的にはないし、実際上の要請にもかえりみて、この繰上徴収ができる始期を暦年の終了の時までさかのぼらせることが妥当であると考えられる。」(注12)と述べているに過ぎない。
すなわち、租税債権・債務の成立と繰上請求の関係は、前者が定められたことによって後者の手続が可能となるのであって、後者のために前者が定められたわけではない。このことは、通則法15条2項に定める各税目についての納税義務の成立は、繰上請求のみならず、納税の猶予の要件(通則法46①一)、国税の更正決定等の期間制限の始期(通則法70⑤三)、保全差押(徴法159①)にも関係していることからも裏付けられる。
また、通則法の立法担当者の解説書として評価の高い「国税通則法精解」(大蔵財務協会)においても、本件各判決の判示を裏付けるような記述は見当たらない(注13)。
なお、一審判決は、通則法65条1項が期限内申告書を提出しなかった場合にも過少申告加算税が賦課されることを挙げているが、それは期限内申告書を提出できなかったことについて「正当な理由」が存する場合に限定しているのであって、そのような事実が存しない本件に敷衍できるものではないであろう。
4 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件は、法定申告期限時には隠ぺい・仮装の事実がなく、当該期限経過後の修正申告段階における隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足するかが問題とされたものである。
この問題は、従前の裁判例では、隠ぺい・仮装の事実の判断時期は原則として法定申告期限時であるとしつつも、当該期限経過の隠ぺい・仮装行為を法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の推認事項等であるとして、当該賦課処分の適法性を容認するケースが多かった。しかしながら、この場合には、法定申告期限時に明らかに隠ぺい・仮装行為の存在が否定されたときには、当該賦課処分の適法性は容認し得なくなることが考えられる。
この点、本件各判決は、重加算税の納税義務の成立時期の定めは繰上請求制度のために設けられたものとし、納税義務成立(法定申告期限経過時)後の隠ぺい・仮装行為が当然に重加算税の賦課要件を充足する旨判断した。この点においては、その当否はともかくとして、重加算税の賦課に関する解釈としては画期的なものであり、本件各判決の意義は大きい。
(2)しかしながら、本件各判決の判断については、前述のように、通則法が制定された際の立法趣旨等に照らしても、首肯し難い所がある。また、このことは、前述した関係条項の文理解釈においても、依然として問題を残している。
確かに、本件のように、本件当初申告段階から家族ぐるみで過少申告を意図していることがうかがわれ、かつ、本件第1次修正申告段階では、通則法68条1項にいう「納税者」たるXも隠ぺい・仮装行為に加担したと認められるというのであるから、申告秩序維持のための行政制裁たる重加算税を課すこと自体法が予定しているものと考えられる。
然すれば、どのような措置が考えられるかであるが、結局、関係条項の整備を図ることが最善であるように考えられる(注14)。例えば、一審判決も指摘しているように、通則法65条1項では、期限内申告書が提出されなかった場合にも過少申告加算税を課すことを例外的に定めているのであるが、このような規定を通則法68条1項に付加することも考えられる。
(注1)品川芳宣「附帯税の事例研究 第三版」(財経詳報社)261頁、286頁参照
(注2)前出(注1)287頁以下参照
(注3)最高裁昭和45年9月11日第二小法廷判決(刑集24巻10号1333頁)。同旨最高裁昭和33年4月30日大法廷判決(民集12巻6号938頁)、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申の説明」(昭和36年)第6章第2節二・三一三等参照
(注4)前出(注1)253頁参照
(注5)納税者の家族がした隠ぺい・仮装行為が当該納税者の行為と同視し得るとした裁判例としては、大阪地裁昭和36年8月10日判決(行裁例集12巻8号1608頁)、大阪地裁昭和58年5月27日判決(税資130号514頁)、大阪地裁平成元年11月14日判決(同174号618頁)、大阪地裁昭和56年2月25日判決(同116号318頁)等参照。なお、「納税者」の意義・範囲についての解釈論及び他の裁判例については、前出(注1)300頁以下参照
(注6)大阪地裁昭和29年12月24日判決(行裁例集5巻12号299頁)、大阪地裁昭和50年5月20日判決(税資81号602頁)、名古屋地裁昭和55年10月13日判決(同115号31頁)、大阪地裁平成5年4月27日判決(税資195号169頁)、宇都宮地裁平成12年8月30日判決(同248号586頁)等参照
(注7)大阪地裁昭和50年5月20日判決(税資81号602頁)
(注8)大阪地裁平成5年4月27日判決(税資195号169頁)
(注9)東京地裁昭和52年7月25日判決(税資95号124頁)
(注10)静岡地裁昭和57年1月22日判決(税資122号26頁)、名古屋地裁昭和44年5月27日判決(行裁例集20巻5・6号659頁)、東京高裁平成13年4月25日判決(平成12年(行コ)第273号)等参照
(注11)通則法制定答申説明第3章第1節1・1(1)
(注12)前出(注11)第4章第3節3・3
(注13)志場喜徳郎他共編「国税通則法精解平成16年版」(大蔵財務協会)232頁参照
(注14)前出(注1)368頁参照
品川芳宣 (しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学社会科学系教授。
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)他多数。
東京地裁平成13年(行ウ)第157号 平成16年1月30日判決
東京高裁平成16年(行コ)第63号 平成16年7月21日判決
品川 芳宣
筑波大学大学院教授
一、事実
(1)X(原告、控訴人)及び乙(Xの母、甲の妻)は、平成7年12月12日死亡した甲(Xの父)を相続(以下「本件相続」という。)した。また、丙(当時検事正)は、Xの夫である(Xと丙を併せて、以下「Xら」という。)。
Xは、平成8年7月15日、Y(被告、被控訴人)税務署長に対し、本件相続に係る相続税を申告(以下「本件当初申告」という。)し、申告書(以下「本件当初申告書」という。)に相続財産の価額を3億5927万円余と記載した。
乙は、昭和60年頃から同人名義でN銀行S支店との間で割引興業債券の取引を行っていたが、平成7年12月当時、その額面総額が2億6000万円(以下「本件ワリコー」という。)であった。
Yの担当係官は、本件相続に係る相続税の調査を開始し、平成9年12月22日、本件ワリコー及び乙名義の定期預金等について、Xに対してメモを渡し、それらの存在と原資について確認を求め、前記乙名義の定期預金の一部が甲の相続財産に該当する旨説明した。
(2)これを受けて、Xは、平成10年2月16日、Yに対し、前記定期預金のうち9200万円が甲の相続財産に当たるとする修正申告書(以下「本件第1次修正申告書」という。)を提出した(以下「第1次修正申告」という。)。
Yの担当係官は、更に調査を行い、Xらに対し、本件ワリコーも甲の相続財産に含まれるか否かについて確認を求めた。これを受けて、Xは、平成10年5月27日、Yに対し、本件ワリコーを甲の相続財産に加える旨の修正申告書(以下「本件第2次修正申告書」という。)を提出した(以下「本件第2次修正申告」という。)。本件第2次修正申告書に記載された相続財産の価額は、7億1025万円余である。
Yは、平成10年6月30日、Xに対し、重加算税の額を3786万円余とする賦課決定処分(以下「本件処分」という。)をした。Xは、本件処分を不服として、不服申立ての前置を経て、本訴を提起した。
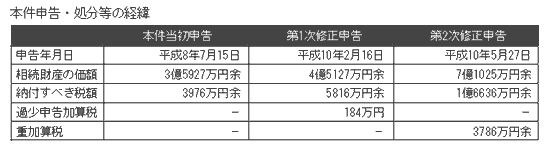
二、争点と当事者の主張
1 争点
(1)Xが、本件当初申告について、相続税の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づき本件当初申告書を提出したか否か。
(2)法定申告期限の経過後にされた修正申告についても、国税通則法(以下「通則法」という。)68条1項の適用があるか否か。
(3)Xが、本件第1次修正申告について、相続税の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づき本件第1次修正申告書を提出したか否か。
2 Xの主張
(1)Xは、そもそも本件当初申告において、本件ワリコーを含む相続財産を隠ぺい又は仮装したことはない。このことは、以下のとおりの事情から裏付けられる。
Xは、父、夫ともに検察官という遵法精神の高い生活環境にあったものであり、脱税が刑事罰を伴う重罪であること、また、Xが脱税した場合、その発覚によって甲の名誉はおろか、当時検事正であった丙がその地位を失う可能性が高いことを十分認識していたのであるから、かかる危険性を顧慮することなくXが脱税を図るとは考えられない。
本件ワリコーは、額面2億6000万円という金額であり、本件当初申告における申告額の約7割にものぼる金額であり、検察官の家庭に育ち検察官の妻であるXがかかる巨額の脱税をするのは不自然であり、むしろ、このような事情は、Xが本件ワリコーの存在を認識していなかったことを裏付けるものである。そして、Xは、本件当初申告に際し、乙は、本件ワリコーを自己の財産と認識していたため、Xに対して本件ワリコーが相続財産であると告知することはなく、そのため、Xは、本件ワリコーの存在すら認識しておらず、その認識の機会もなかった。
(2)修正申告は、申告義務のない任意の申告にすぎないから、通則法68条1項の適用はなく、したがって、本件第1次修正申告については、重加算税を課すことはできない。
通則法68条1項に定める重加算税賦課制度は、申告納税制度のもとにおいて、不正な申告に対し重い制裁を課して上記制度を守ろうとするものであり、申告義務ないし納付義務違反があり、その違反の態様が隠ぺい又は仮装を伴うときに、過少申告加算税、無申告加算税ないし不納付加算税を課すのに代えて重く課するという制度である。そうすると、通則法19条に規定する修正申告書は、原則として、提出を義務付けられていない任意的な申告書にすぎず、納税者において修正すべき事実を発見してもこれを申告すべき義務は存在しないのであるから、前述した重加算税の制度趣旨に照らせば、修正申告について重加算税を課すことはできず、同項にいう「納税申告書」には「修正申告書」は含まれないと解すべきである。
(3)仮に、修正申告についても通則法68条1項の適用を受けるとしても、本件においては、本件第1次修正申告について、仮装又は隠ぺいの事実は存在しない。
前記のとおり、Xは、乙より依頼を受けて本件ワリコーの償還、購入を行ったにすぎず、本件ワリコーは当初より乙の財産であって、相続財産ではないと考えていたことから、Yの担当係官からの質問に対しても本件ワリコーが相続財産ではないことを前提とする対応を取っていた。
そして、平成10年2月5日になって、Y税務署のI副署長から丙に電話があり、調査の結果、乙名義の定期預金9200万円についで甲の預金が原資であることを確認できたこと、また、これにより調査が終了したので上記定期預金について修正申告するよう申入れがあったが、本件ワリコーについては何の言及もなかった。
以上のとおり、Xは、Yの調査結果に基づくとする修正申告の慫慂に応じて本件第1次修正申告を行ったにすぎず、Yの主張するように、本件ワリコーについて修正申告の対象から除外し、隠ぺい又は仮装する意図は持っていなかったものであり、また、そもそも、Yらの慫慂に基づいてなされた修正申告については、通則法68条1項を適用する余地はないというべきである。
(4)Y税務署の副署長が本件第1次修正申告書の提出の際に「これで終わりです。」と述べたこともこれを裏付けるものである。このような事情があるにもかかわらず、本件ワリコーの隠ぺいに基づき本件第1次修正申告書を提出したとして重加算税を賦課するのは、信義則に反する。
3 Yの主張
(1)本件ワリコーは、甲の死亡時点において額面総額2億6000万円と極めて多額に上るものであり、本件当初申告書に記載された甲の相続財産の価額の合計額の7割を超える金額であるところ、①乙の専従者給与では到底形成できないものであるうえ、②昭和62年5月から平成7年6月までの期間において、甲名義の預金から多額の金員が出金されていること、③本件ワリコーの担当支店であったK銀行S支店における取引カードの顧客名も甲となっていたことからすると、本件ワリコーが甲の資産から形成されたことは明らかであって、これらの事実からすれば、乙も本件ワリコーが相続財産に当たることを認識していたものということができる。
そして、Xは、相続時において、甲と乙の一人娘であり、本件当初申告当時、一緒に同居するなどからみて、Xも本件ワリコーが甲の相続財産であることを認識していたとみるのが自然である。
(2)Xの過少申告行為は、単に真実の相続財産の価額よりも少ない価額を記載した納税申告書であることを認識しながらこれを提出したというにとどまらず、本件ワリコーが無記名債券で、かつ、現物取引であって調査解明に困難が伴う状況を利用し、これを隠ぺいしようという確定的な意図の下に申告額の7割以上にも及ぶ多額の相続財産を除外することにより、課税価格をことさら過少に記載した内容虚偽の本件当初申告書を提出したものであり、本件当初申告書の提出後においても、本件ワリコーの存在を隠匿し続けるため、煩雑な方法で償還、購入を繰り返すという手続を行うとともに、税務調査に対しては一貫してその存在を否定し続けるなどして、本件ワリコーを隠ぺいする態度、行動をできる限り貫こうとしたものであるから、これらの行為は、隠ぺい又は仮装に当たる。
(3)過少申告加算税、無申告加算税に代えて、重加算税という重い加算税が課されるのは、法定申告期限内に適正な申告をしなかっただけにとどまらず(これに対する行政上の制裁としては、過少申告加算税・無申告加算税が課される。)、不正手段を用いた申告をした点に求められるというべきであるから、かかる悪質な申告が行われた以上は、これに対して重い行政上の制裁を課し、厳しくこれを取り締まる必要があるというべきである。そうすると、重加算税の対象となる納税申告は、期限内申告に限らず、修正申告、期限後申告も含まれるというべきであって、申告書の提出義務があるかどうかは、重加算税の適用には関わりがないというべきである。
三、判決要旨
請求棄却。
1 本件当初申告における隠ぺい・仮装の有無
(1)乙が甲の生前から本件ワリコーの取引を行っていたことについては当事者間に争いがないことから、乙において、本件当初申告の際、本件ワリコーが自己の財産であると認識していたか否かの点を検討する。
この点につき、Xは、乙は本件ワリコーが自己の財産であると認識していたと主張する。
しかし、前記認定事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば、①昭和62年5月から平成7年6月までの期間において、本件ワリコーの基になったワリコーが1億5000万円増加しているところ、同期間において甲名義の預金から多額の金員が出金されていること、②本件ワリコーの担当支店であったK銀行S支店における取引カードの顧客名は、甲となっていたこと、③乙は、不服審査手続において、本件ワリコーは自分の父からの贈与と自己の専従者給与から形成取得したと答述しているが、贈与の点についてはこれを認めるに足りる証拠はなく、また、額面総額2億6000万円という本件ワリコーの金額に照らして、その原資が乙の専従者給与のみでは到底蓄積できるものとは考えられないことからすると、本件ワリコーが甲の資産から形成されたことは明らかである。
そして、乙は、本件ワリコーにつき甲の生前から平成9年5月ころまで自ら乗換手続を行っていたものであり、乙は、本件当初申告に先立って、本件ワリコーが相続財産であることについて認識していたものと認められる。
(2)次いで、Xが本件当初申告の際、本件ワリコーが相続財産に属することについて認識していたかどうかにつき検討する。
この点については、Xにおいて、甲の生前、本件ワリコーが甲の財産に属することについて予め認識していたと認めるに足りる証拠はない。
ちなみに、Xは、乙と親子の関係にあり、平成6年3月16日から現在に至るまで、自宅を住所とする住民登録を行い、少なくとも、平成6年3月ころから平成7年11月ころまでの間、一月の半分程度は上記自宅に居住していたことが認められるが、これらの事実だけでは、その間に、乙より教示されるなどして、本件ワリコーの存在を認識したと推認することはできない。
確かに、Xは、多額のワリコーをK銀行の各本支店の窓口に持参し、その一部を償還し、現金化したうえで当該現金とともに別の本支店の窓口に赴き、新たにワリコーを購入するとともに、別途、多額のワリコーを償還して現金化するということを繰り返し行っていたものであり、単に乗換えの趣旨であれば、このように、わざわざ多額の現金及びワリコーを所持しながらK銀行の各本支店を行き来する必要性は乏しいといわざるを得ない。
しかし、Xが上記の償還等の行為を行った時期は、本件当初申告から約1年後のことである。そして、仮に、本件当初申告の際、Xが本件ワリコーの存在を認識しており、またこれを隠ぺいする意図を有していたならば、乙と相談するなどして早期に本件ワリコーについて上記のような手段による償還等を行ってしかるべきであるにもかかわらず、そのような形跡は窺われず、かえって、乙は、平成9年5月までは、従前どおり、担当者を自宅に呼んで乗換手続を行っていたものである。
これらのことからすれば、Xが上記の償還等の行為を行っていることをもって、Xが本件当初申告時において本件ワリコーの存在を認識していたと推認することはできない。
2 修正申告にも通則法68条1項の適用があるか。
(1)重加算税制度は、申告納税制度の下において、納税者に適正な申告をさせるべく、納付すべき税額の計算の基礎となる事実について隠ぺい又は仮装するという不正手段を用い、これに基づいて申告等がされたときに、当該申告を行った者に対して過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするところにあるものと解される(最高裁判所第二小法廷平成7年4月28日判決)。
(2)通則法68条1項にいう「納税申告書」とは、申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により、課税標準等及び税額等の事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいうところ(同法2・六)、修正申告書(同法19条③)も「納税申告書」に該当することは、同法の上記規定に照らして明らかであり、同法68条1項の文理上、通常の期限内申告と修正申告を別異に解すべき理由はない。
そして、修正申告も、納税義務を負う税額を確定させる行為であり、その際に隠ぺい又は仮装したところに基づいて過少申告が行われた場合には、その制度の基礎が害されることとなることは、期限内申告と同様であるから、実質的にみても、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって悪質な納税義務違反の発生を防止すべき必要性が存することは異ならない。
したがって、通則法68条1項にいう「納税申告書」には、同法19条3項所定の修正申告書も含まれるというべきであって、納税義務者が、その国税の課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて修正申告書を提出していたときは、その納税者に対して重加算税を課することができると解するのが相当である。
(3)また、Xは、通則法15条2項13号は、重加算税の納税義務の成立時期を「法定申告期限の経過の時」と規定していることからすれば、重加算税を賦課するためには、隠ぺい又は仮装と評価すべき行為が本件当初申告時に存在することが必要であると主張する。
しかし、通則法15条2項は、昭和37年の通則法の制定に当たり、納税義務は成立しているが納付すべき税額が確定していない税額の徴収手続として繰上保全差押制度(通則法38条③)が創設されたことに伴い、国税の納税義務の成立時期を明確にする趣旨から、主として繰上請求の観点からみて必要な範囲において、同法15条2項各号又は通則法施行令5条に、各税目ごとの成立時期が規定されたものであると解すべきである。
このことは、同法65条1項及び68条1項の規定に照らしても明らかである。
すなわち、同法15条2項13号は、過少申告加算税についても、その納税義務の成立時期を「法定申告期限の経過の時」と定めている。しかし、仮に、Xが主張するように、同法15条2項13号に基づいて、法定申告期限の経過の時までに加算税の課税要件が充足される必要があると解するとすれば、この場合、法定申告期限の経過時においては、過少申告加算税の課税要件は常に充たされていないのであるから、過少申告加算税を課することはできないことになるが、同法65条1項は、「期限内申告書が提出された場合」には、「期限後申告がされた場合において、次条第1項ただし書の規定の適用があるときを含む。」としており、同法68条1項が、同法65条1項の規定に該当する場合のうち、同法65条5項の規定の適用がある場合を除く外は、重加算税を賦課する対象とする旨を規定していることに照らしても、Xの上記主張のとおり解釈することは困難であるといわざるを得ない。
3 本件第一次申告における隠ぺい・仮装の有無
(1)前記認定事実と証拠及び弁論の全趣旨によれば、①本件ワリコーは額面総額2億6000万円と多額なものであって、その原資は、乙の専従者給与等では到底形成できるものではなかったこと、②Xは、乙が従来行っていた乗換手続の方法によるのではなく、本件ワリコーについて、平成9年7月11日に1000万円、同年9月18日に4000万円、同月19日に2000万円、同年10月9日に3000万円と合計1億円にも上るワリコーを自ら償還、購入しており、その方法も、いずれも債券をいったん現金化したうえで、新たに債券を購入するという複雑なものであり、そのなかでも特に同年9月18日、同月19日及び10月9日については、1000万円以上の現金を所持して各支店を回って償還及び購入の手続を行っていること、③このような方法でのXの償還及び購入の手続は、税務調査の通告があった同年10月22日以降行われておらず、再度行われたのは、本件第1次修正申告がされた後であること、④ワリコーは、無記名債券であり、一般に、これが現物で取引されている場合には、当該債券の真実の所有者を特定することが困難であり、乗換えの場合は、旧債券と新債券の連続性が取引記録上確認できるのに対し、旧債券をいったん現金に償還したうえで新債券を購入する場合は、取引記録などから旧債券と新債券との連続性を確認して真実の所有者を把握することは容易でないことが、それぞれ認められる。
これらの事実に照らせば、Xの上記②の行為、すなわちXが行った本件ワリコーについての償還、購入手続は、X自身が本件ワリコーが甲の相続財産であることを認識していたことを前提としなければ、その行動を合理的に説明することができないものというべきであり、Xは、遅くとも、同一の日に本件ワリコーの償還手続と購入手続をそれぞれ別々の店舗において行った平成9年9月頃には、本件ワリコーが甲の相続財産に属することを認識していたことが推認できるというべきである。
以上認定した事実によれば、Xは、平成9年9月頃には、本件ワリコーが相続財産であることを認識し、かつ、その存在が発覚しないように、その頃から、前記に記載したような煩雑な償還及び購入の手続をあえて行い、同年12月に行われたYの税務調査の中で本件ワリコーの存在について何度も確認を求められたにもかかわらず、乙とともに本件ワリコーの存在を否定して、本件ワリコーを除外した本件第1次修正申告書を提出したものであり、かかるXの行為は、相続税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいしたものと認められる。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。
(1)前記認定事実によれば、平成9年9月までにXが償還と購入を行ったワリコーは7000万円(同年10月分も含めると1億円)にとどまるものの、Xがこのように多額のワリコーの償還と購入を依頼されれば、それがどのようにして取得されたものか、総額がどの程度のものかなどにつき、親子間で話が出るのが通常であると考えられ、上記依頼を受けたワリコーが乙管理に係るものの全部である旨を乙から告げられたなど特段の事情を認めるに足りる証拠がない以上、Xは、償還を頼まれたもの以外にも相続財産に属する管理に係るワリコーがあることを認識していたものと推認することができる。したがって、Xは、その総額についての正確な認識がなかったとしても、平成9年9月の時点において、これら乙管理に係る一群のワリコーの全部(本件ワリコー)を隠ぺいしたものと認定することができる。
(2)通則法68条1項の文理上は修正申告書も「納税申告書」に含まれること、修正申告は期限内申告と同様に納税義務を確定させる行為であり、修正申告には申告の義務がないとしても、申告納税制度維持の観点から修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があること、通則法15条2項13号が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時と定めたのは、実質的には、通則法38条3項の繰上保全差押との関係で納税義務の成立時期を明確にする趣旨にすぎず、この規定からX主張のような重加算税の賦課要件を読み取ることはできないことなどは、原判決に説示するとおりである。したがって、通則法68条1項の「納税申告書」には修正申告書も含まれるものと解すべきである。
Xは、本件のように当初申告後に隠ぺい、仮装行為があった場合について、その後修正申告書を提出しなければ重加算税を課することができないのに、その後申告義務のない修正申告書を提出したときには重加算税が課税されるのは、不公平であるから、修正申告書は通則法68条1項の納税申告書には該当しないと主張する。しかしながら、そのような解釈は前記のとおり文理に反する上、実質的にも修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があることは多言を要しないところであって、到底採用の限りではない。Xのように、当初申告前には隠ぺい、仮装行為がなく、申告後に初めてこれが行われたが、その後は過少申告がされなかったという場合、本件のように後に隠ぺい、仮装行為が発覚して追加課税がされたケースにおいては、隠ぺい、仮装行為を行った者は、税務当局に対しては何ら不正な働きかけをしていないのであるから、納税義務違反の悪質性は過少申告行為を行った者と比較して低いと評価することも可能であろう。そうであれば、Xの主張するような不公平はないともいえるが、いずれにしても、上記のような事態はまれであって、そのような例との比較において文理上も実体上も十分な根拠のある重加算税の課税を否定するのは本末転倒というほかない。
(3)Xは、本件第1次修正申告書を提出する4箇月前の平成9年9月から乙管理に係る一群のワリコーが甲の相続財産に属することを認織していたのであるから、平成10年2月の本件第1次修正申告において、預金のみならず本件ワリコーも申告すべきであった(本件ワリコーの総額の調査に若干の時間を要するとしても、少なくとも、その旨をYの担当官に告げた上で、申告の準備に入り、数週間のうちに追加修正申告をすべきであった。)。それにもかかわらず、Xは、本件第1次修正申告前から、本件ワリコーについて追加の修正申告をする意思を持たないまま、前記認定したとおり、修正申告前の平成9年7月から10月にかけて、さらには修正申告後の平成10年2月から5月にかけて、本件ワリコーの隠ぺいのため、償還と購入の行為を行っていたものである。
このようなX側の事情を考慮すると、仮に、本件第1次修正申告書の提出の際にYの担当官がこれで終わりですという趣旨の発言をしたとしても、それを信用したXを信義則を適用して保獲するまでの事情があるということはできない。
五、解説
はじめに
本件は、検察幹部一家の脱税事件として社会的に注目された事件であるが、重加算税の賦課要件の充足において重要な論点を有している。
すなわち、本件各判決の認定事実によると、Xは、本件相続に係る本件当初申告段階(法定申告期限経過時)では、過少申告について隠ぺい・仮装をしなかったのであるが、その後の第1次修正申告段階における過少申告において隠ぺい・仮装をしたというものである。
かくして、重加算税の賦課要件につき、通則法68条1項が「・・・・その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」と規定し、同法15条2項13号が過少申告加算税に代える重加算税の納税義務の成立の時を「法定申告期限の経過の時」と規定していることに照らし、本件のような場合に、重加算税の賦課要件を充足するか否かが問題視されていた。
もっとも、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為に対する重加算税の賦課決定については、従前においてもその適法性を容認する裁判例が多かったが、その理由付けについて本件各判決とは大きな差異が認められる。そのため、本件各判決は、重加算税の賦課要件について重要な判断を示した先例となるものであるが、その当否について検討を要する。
1 重加算税の賦課要件
(1)通則法68条1項は、「第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(<略>)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、<略>過少申告加算税に代え、<略>重加算税を課する。」と規定している。
このように、過少申告加算税に代えて重加算税が課されるには、①過少申告加算税の賦課要件を充足していること、②納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装したこと及び③その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたこと、が要件とされる。
また、通則法68条1項による重加算税は、法定申告期限の経過の時に納税義務が成立するものと定められている(通則法15②一三)。
他方、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、<略>」(通則法70⑤)た場合には、更正決定等の期間制限が、3年又は5年から7年に延長される(同前)。更に、「国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、<略>た国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。」(通則法73③)と定められている。
そして、これらの場合における「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、」とは、各税法の 脱罪の構成要件と同じとなっている(所法238①、法法159①、相法68①、消法64①等参照)。
(2)かくして、以上の各規定から、過少申告加算税に代えて課される重加算税の賦課要件については、①隠ぺい・仮装の意義、②納税者がその隠ぺい・仮装を行うに当たって税を免れようとする意思すなわち故意(認識)が明らかにされている必要があるか否か、③隠ぺい・仮装を行った者(行為者)が納税者本人に限定されるのか、限定されないとした場合のその範囲、④無記帳、不申告、虚偽申告、つまみ申告等のように積極的(外形的)な不正行為を伴わない行為が隠ぺい・仮装行為といえるか否か、⑤法定申告期限後の税務調査時等における虚偽答弁、虚偽資料の提出等が賦課要件を充足し得るか、⑥
脱罪が問われることとなる場合又は更正決定等の期間制限(除斥期間)が延長されること等となる場合の「偽りその他不正の行為により税を免れる」との関係(異同)はどうなるのか、等が問題とされる(注1)。
これらの各問題点については、多くの裁判例で争われてきており(注2)、本件においては、特に、前記⑤の問題点が争われることとなったものである。また、それに関連して、通則法68条1項にいう「・・・・基づき納税申告書を提出していたとき」の「納税申告書」に本件第1次修正申告書のような法定申告期限経過後に提出される修正申告書が含まれるか否かが問題とされている。
(3)なお、前述の重加算税の賦課要件の問題点の解明に当たっては、「国税通則法68条に規定する重加算税は、同法65条ないし67条に規定する各重加算税を課すべき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によって行なわれた場合に、行政機関の手続により違反者に課せられるもので、これによってかかる方法による納税義務違反の発生を防止し、もって徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべきである(注3)」とされる重加算税の性質(注4)に照らして論じる必要がある。
2 「納税申告書」の意義・範囲
(1)本件においては、本件各判決の認定事実によると、Xは、本件相続に係る本件当初申告においては過少申告について隠ぺい又は仮装したわけではなく、その後の第1次修正申告において隠ぺい又は仮装したというものである。そのため、まず、通則法68条1項にいう「・・・・基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するか否かが問題とされた。
この点について、一審判決は、「通則法68条1項にいう「納税申告書」とは、申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により、課税標準等及び税額等の事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいうところ(同法2条6号)、修正申告書(同法19条3項)も「納税申告書」に該当することは、同法の上記規定に照らして明らかであり、同法68条1項の文理上、通常の期限内申告と修正申告を別異に解すべき理由はない。」と判示し、「・・・・その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて修正申告書を提出していたときは、その納税者に対して重加算税を課することができると解するのが相当である。」と判示している。
また、控訴審判決も、「通則法68条1項の文理上は修正申告書も、「納税申告書」に含まれること、修正申告は期限内申告と同様に納税義務を確定させる行為であり、修正申告には申告の義務がないとしても、申告納税制度維持の観点から修正申告においても悪質な納税義務違反を抑止する必要があること、<略>したがって、通則法68条1項の「納税申告書」には修正申告書も含まれるものと解すべきである。」と判示している。
(2)確かに、通則法2条6号が「納税申告書」とは、「申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、<略>」と定義しているものであるから、通則法68条1項にいう「納税申告書」には、文理上修正申告書も含まれることになる。また、重加算税は、前述のように、申告秩序維持のための行政制裁であるという性質を有するものであるから、修正申告の段階における悪質な納税義務違反を重加算税賦課の対象とすることも、法の予定しているとも解される。
(3)しかしながら、このような解釈論には、若干の違和感が残る。けだし、通則法68条1項に定める重加算税は、過少申告加算税に代えて課されるところ、過少申告加算税は、「期限内申告書(<略>)が提出された場合(<略>)において、修正申告書の提出又は更正があったとき」(通則法65①)に課されるものである。そして、通則法68条1項は、「第65条第1項(<略>)の規定に該当する場合(<略>)において、<略>その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に重加算税を課する旨定めている。
然すれば、通則法68条1項に定める「納税申告書」は、期限内申告書を予定していることは明らかである。もちろん、「納税申告書」それ自体には、前述のように、修正申告書も含まれることになろうが、通則法68条1項によって重加算税を課す場合には、法定申告期限後の修正申告書の提出を予定していないものと考えられる。
もっとも、本件のような場合に、重加算税を課すこと自体は、法の予定しているところと考えられるのであるが、本件各判決の理由付けの方に問題があるように考えられる。本件各判決は、本件当初申告においてXが隠ぺい・仮装行為としていないという認定の下に、本件第1次修正申告書が通則法68条1項に定める「納税申告書」に含まれるとする理由を導いているが、そこに問題がある。本件においては、認定事実によれば、本件当初申告においてXが隠ぺい・仮装行為をしていなくとも、Xの母親である乙は、本件ワリコーが甲の相続財産に含まれることを認識していたことが容易に推認し得る。
そうであれば、通則法68条1項に定める「納税者」の範囲を従前の裁判例(注5)のように弾力的に解釈すれば、乙の行為をXの行為と同視(推認)することも可能であろうし、それによって、本件処分を適法とすることも可能であると考えられる(もっとも、この点は、本件各判決とも否定している。)。また、その方が、後述する重加算税の納税義務の成立の時期との関係において斉合性を維持し得るもとのと考えられる。
3 隠ぺい・仮装の時期と納税義務の成立
(1)本件において最も重視すべき問題は、前述の納税義務成立との関係上、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することになるか否かである。
従前の裁判例では、隠ぺい・仮装行為の存否の判断は確定申告時(法定申告期限)を基準とすべきとするのが支配的である(注6)。また、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為については、「右確定申告時において原告が隠ぺい又は仮装の意思を有していたか否かを判定するための資料となるにすぎない。」(注7)、「右期限後の隠ぺい・仮装行為は、法定申告時における隠ぺい・仮装行為は、法定申告時における隠ぺい・仮装行為の存否を推認させる一間接事実となりうるに過ぎない。」(注8)、「これに対する課税を回避しようとする意図が当初からあったものと推認することでき、・・・・」(注9)等と解されてきた。
このように、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為を、法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の存在を判断するための「資料」、「間接事実」、「推認事項」等とする考え方は、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することを否定するものではない。
しかしながら、本件のように、法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の存在が否定されたときには、当該充足の根拠を失うことになる。
なお、従前の裁判例においても、前述の推認等とは関係なく、法定申告期限経過後の隠ぺい・仮装行為について重加算税の賦課要件の充足を肯定するものも見受けられる(注10)が、その論拠が明らかにされたとは言い難い状況にあった。
(2)このような状況の中で、本件各判決は、前述のように、本件第1次修正申告時における隠ぺい・仮装行為について、法定申告期限時の推認等とは関係なく、重加算税の賦課要件を充足するとしている。
その論拠について、一審判決は、「通則法15条2項は、昭和37年の通則法の制定に当たり、納税義務は成立しているが納付すべき税額が確定していない税額の徴収手続として繰上保全差押制度(通則法38条3項)が創設されたことに伴い、国税の納税義務の成立時期を明確にする趣旨から、主として繰上請求の観点からみて必要な範囲において、同条15条2項各号又は国税通則法施行令5条に、各税目ごとの成立時期が規定されたものであると解すべきである。」と判示している。
また、一審判決は、このことは、通則法65条1項が「期限後申告がされた場合において、次条第1項ただし書の規定の適用があるときを含む。」と規定していることからも裏付けられる、としている。
このような考え方は、控訴審判決においても支持されており、同判決は、「通則法15条2項13号が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時と定めたのは、実質的には、通則法38条3項の繰上保全差押との関係で納税義務の成立時期を明確にする趣旨にすぎず、」と判示している。
(3)このように、法定申告期限後の隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足することの論拠が明確にされたことは、裁判例としては初めてのことであるので、極めて注目される。しかしながら、その論拠の妥当性については、依然として疑問が残る。
まず、本件各判決は、通則法が重加算税の納税義務成立時を法定申告期限経過の時としたのは同法38条に定めた繰上請求との関係で定めたもので、同法68条1項の解釈とは関係がないように判示している。しかしながら、税制調査会の「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)及びその説明」(昭和36年7月、以下「通則法制定答申説明」という。)を読む限りでは、本件各判決が判示するようには理解できない。
すなわち、通則法制定答申説明では、租税債権・債務の成立に関し、「所得税については、課税標準の計算期間である1暦年が経過して所得税法の実体的規定に定める課税要件が充足されると、租税債権・債務が成立する。」(注11)と述べ、繰上請求との関係についても、「暦年が経過すると租税債権は成立しているので、これをその確定時まで待たなければならない必要は理論的にはないし、実際上の要請にもかえりみて、この繰上徴収ができる始期を暦年の終了の時までさかのぼらせることが妥当であると考えられる。」(注12)と述べているに過ぎない。
すなわち、租税債権・債務の成立と繰上請求の関係は、前者が定められたことによって後者の手続が可能となるのであって、後者のために前者が定められたわけではない。このことは、通則法15条2項に定める各税目についての納税義務の成立は、繰上請求のみならず、納税の猶予の要件(通則法46①一)、国税の更正決定等の期間制限の始期(通則法70⑤三)、保全差押(徴法159①)にも関係していることからも裏付けられる。
また、通則法の立法担当者の解説書として評価の高い「国税通則法精解」(大蔵財務協会)においても、本件各判決の判示を裏付けるような記述は見当たらない(注13)。
なお、一審判決は、通則法65条1項が期限内申告書を提出しなかった場合にも過少申告加算税が賦課されることを挙げているが、それは期限内申告書を提出できなかったことについて「正当な理由」が存する場合に限定しているのであって、そのような事実が存しない本件に敷衍できるものではないであろう。
4 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件は、法定申告期限時には隠ぺい・仮装の事実がなく、当該期限経過後の修正申告段階における隠ぺい・仮装行為が重加算税の賦課要件を充足するかが問題とされたものである。
この問題は、従前の裁判例では、隠ぺい・仮装の事実の判断時期は原則として法定申告期限時であるとしつつも、当該期限経過の隠ぺい・仮装行為を法定申告期限時の隠ぺい・仮装行為の推認事項等であるとして、当該賦課処分の適法性を容認するケースが多かった。しかしながら、この場合には、法定申告期限時に明らかに隠ぺい・仮装行為の存在が否定されたときには、当該賦課処分の適法性は容認し得なくなることが考えられる。
この点、本件各判決は、重加算税の納税義務の成立時期の定めは繰上請求制度のために設けられたものとし、納税義務成立(法定申告期限経過時)後の隠ぺい・仮装行為が当然に重加算税の賦課要件を充足する旨判断した。この点においては、その当否はともかくとして、重加算税の賦課に関する解釈としては画期的なものであり、本件各判決の意義は大きい。
(2)しかしながら、本件各判決の判断については、前述のように、通則法が制定された際の立法趣旨等に照らしても、首肯し難い所がある。また、このことは、前述した関係条項の文理解釈においても、依然として問題を残している。
確かに、本件のように、本件当初申告段階から家族ぐるみで過少申告を意図していることがうかがわれ、かつ、本件第1次修正申告段階では、通則法68条1項にいう「納税者」たるXも隠ぺい・仮装行為に加担したと認められるというのであるから、申告秩序維持のための行政制裁たる重加算税を課すこと自体法が予定しているものと考えられる。
然すれば、どのような措置が考えられるかであるが、結局、関係条項の整備を図ることが最善であるように考えられる(注14)。例えば、一審判決も指摘しているように、通則法65条1項では、期限内申告書が提出されなかった場合にも過少申告加算税を課すことを例外的に定めているのであるが、このような規定を通則法68条1項に付加することも考えられる。
(注1)品川芳宣「附帯税の事例研究 第三版」(財経詳報社)261頁、286頁参照
(注2)前出(注1)287頁以下参照
(注3)最高裁昭和45年9月11日第二小法廷判決(刑集24巻10号1333頁)。同旨最高裁昭和33年4月30日大法廷判決(民集12巻6号938頁)、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申の説明」(昭和36年)第6章第2節二・三一三等参照
(注4)前出(注1)253頁参照
(注5)納税者の家族がした隠ぺい・仮装行為が当該納税者の行為と同視し得るとした裁判例としては、大阪地裁昭和36年8月10日判決(行裁例集12巻8号1608頁)、大阪地裁昭和58年5月27日判決(税資130号514頁)、大阪地裁平成元年11月14日判決(同174号618頁)、大阪地裁昭和56年2月25日判決(同116号318頁)等参照。なお、「納税者」の意義・範囲についての解釈論及び他の裁判例については、前出(注1)300頁以下参照
(注6)大阪地裁昭和29年12月24日判決(行裁例集5巻12号299頁)、大阪地裁昭和50年5月20日判決(税資81号602頁)、名古屋地裁昭和55年10月13日判決(同115号31頁)、大阪地裁平成5年4月27日判決(税資195号169頁)、宇都宮地裁平成12年8月30日判決(同248号586頁)等参照
(注7)大阪地裁昭和50年5月20日判決(税資81号602頁)
(注8)大阪地裁平成5年4月27日判決(税資195号169頁)
(注9)東京地裁昭和52年7月25日判決(税資95号124頁)
(注10)静岡地裁昭和57年1月22日判決(税資122号26頁)、名古屋地裁昭和44年5月27日判決(行裁例集20巻5・6号659頁)、東京高裁平成13年4月25日判決(平成12年(行コ)第273号)等参照
(注11)通則法制定答申説明第3章第1節1・1(1)
(注12)前出(注11)第4章第3節3・3
(注13)志場喜徳郎他共編「国税通則法精解平成16年版」(大蔵財務協会)232頁参照
(注14)前出(注1)368頁参照
品川芳宣 (しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学社会科学系教授。
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)他多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























