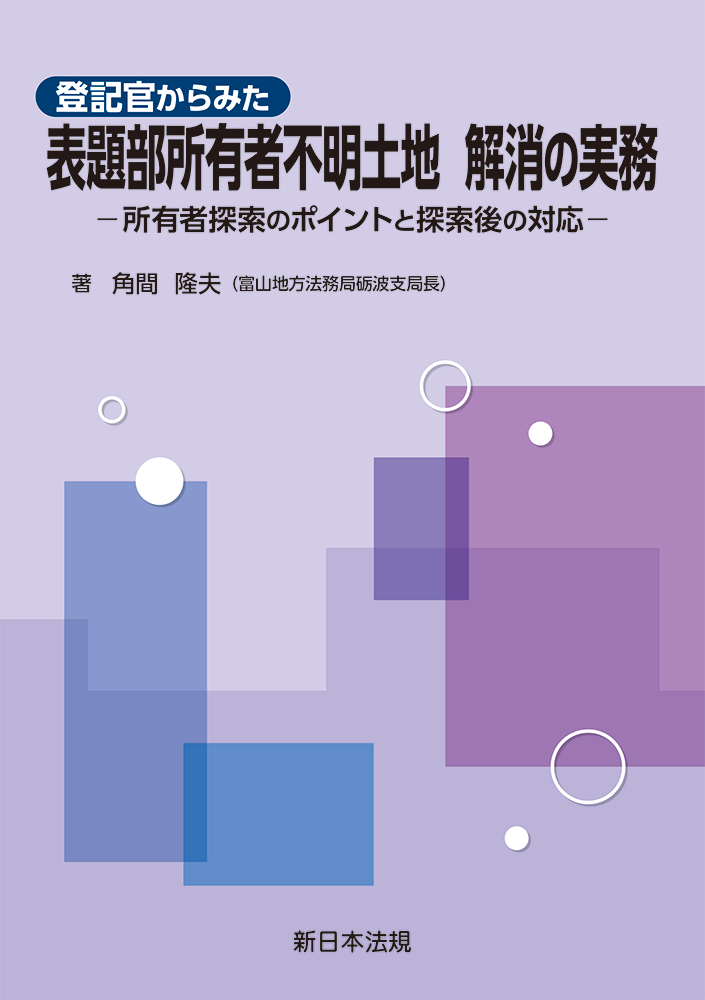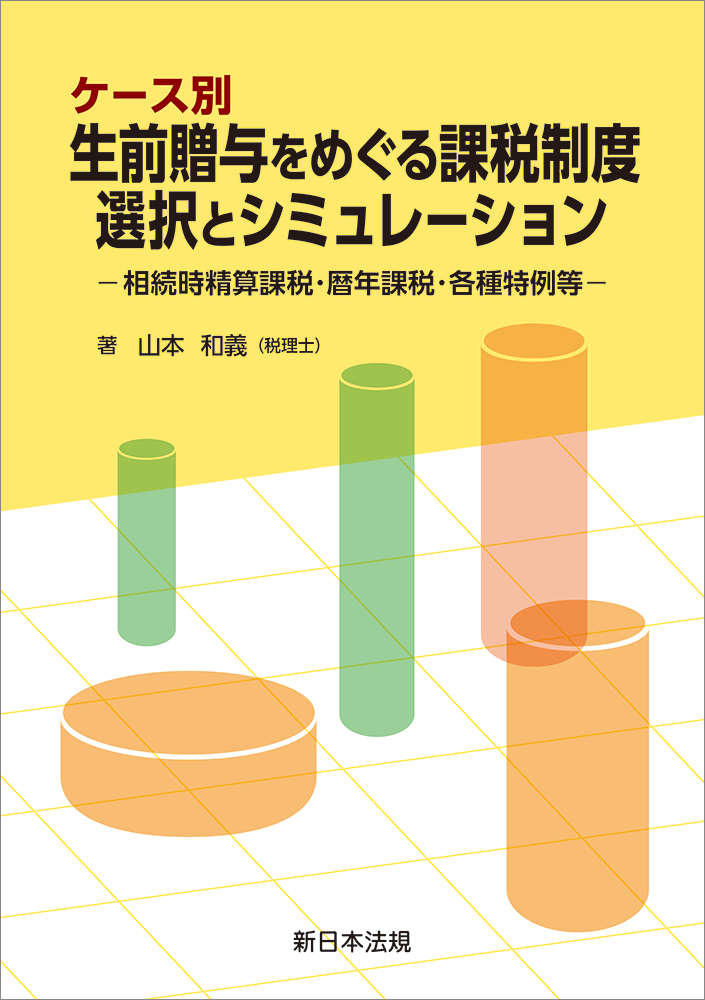資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)
(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書))
1 寄託の意義
2 寄託契約書と金銭の受取書との判別
3 依頼票(控)
4 敷金の預り証
5 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
6 取引保証金提供契約書
寄託の意義
【 照会要旨】
印紙税が課税される寄託契約について説明してください。
【 回答要旨】
印紙税で課税される寄託は、第14号文書の掲名のとおり金銭又は有価証券の寄託を課税の対象にしています。
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物(受寄物)を保管する契約で、寄託契約については、民法第657条以下に定められているところですが、同法第666条に定める消費寄託もこれに含めることにしています(基通第14号文書の1)。
消費寄託契約とは、受寄者が受寄物を消費することができ、これと同種、同等、同量の物を返還すればよい寄託で、銀行預金はその代表的なものです。
印紙税法では、先にも述べたとおり、金銭又は有価証券の寄託を課税することにしていますので、物品の寄託契約については課税されません。なお、印紙税法では、消費寄託のうち預貯金証書については、第8号文書にしています。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
寄託契約書と金銭の受取書との判別
【 照会要旨】
預金として金銭を受け入れた際に、次のような「預り証」を作成していますが、この「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)になるのでしょうか。それとも、第17号文書(金銭の受取書)に該当することになるのでしょうか。
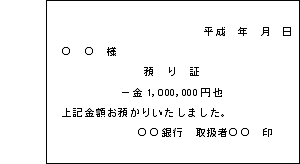
【 回答要旨】
「預り証」と称する文書には、
(1) 後日、仮領収書と同じように正式の領収書を発行することにしているために、金銭を受領したときには「預り証」としたもの
(2) 内入金、手付金等を受領した際に、「預り証」を発行するもの
(3) 得意先のために、金銭を保管することを約して「預り証」を発行するもの
等いろいろなものがありますが、「預り証」は、金銭又は有価証券の受領に際して発行されるという共通点があります。
この金銭又は有価証券の受領が、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために金銭又は有価証券を預かることとしている寄託契約により受領するものであるのか、それ以外の目的による受領なのかにより印紙税の取扱いは異なります。前者の場合には、第14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)となり、後者の場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。
印紙税法では、その文書に記載されている文言から、寄託契約であることが明らかなものは第14号文書とし、それ以外のものは第17号文書として取り扱っています。
したがって、ご質問の「預り証」は、金銭を受領した事実のみの記載で、預金として金銭を預かった旨の記載がありませんから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。 (注) 受取金額の全部又は一部が売上代金であるかが、記載事項から明らかになっていないことから、第17号の1文書になります(第17号文書定義欄1イ)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表 第17号文書定義欄1イ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
依頼票(控)
【 照会要旨】
「依頼票(控)」は、銀行の外務員が預金者から預金として金銭を受け取った場合に「依頼票」と複写で記載して、金銭の受取書として預金者に交付するものです。この「依頼票(控)」には外務員が署名押印等を一切行わないことにしていますので、課税文書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。
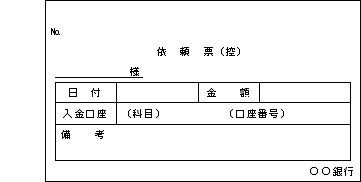
【 回答要旨】
ご質問の文書は、外務員が預金として金銭の受領事実を証明するために作成し、預金者に交付するものですから、外務員の署名、押印等が行われない場合であっても、預金科目及び口座番号の記載がありますので、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当することになります。
(注) 契約書とは、契約の成立を証すべき文書をいい、契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証するものも含まれることにしています(通則5)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
敷金の預り証
【 照会要旨】
建物賃貸借契約の締結に当たって、敷金を預かる際に預り証を作成しましたが、寄託に関する契約書(第14号文書)に該当するのでしょうか。
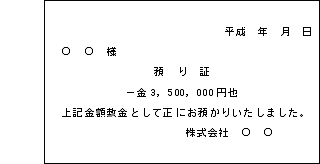
【 回答要旨】
敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。
この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通第14号文書の3)。
なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。
(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
【 照会要旨】
金融機関に対する借入金債務を指定預金口座から自動引落しの方法により支払うに当たって、「元利金等の支払いに関する念書」を作成することにしましたが、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)又はその他の課税文書に該当することになりますか。
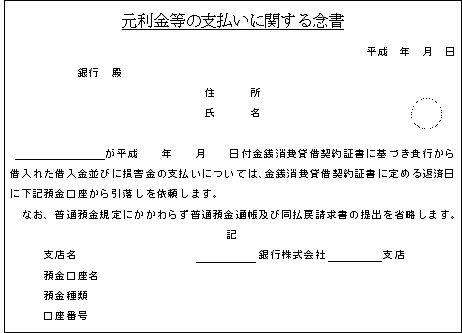
【 回答要旨】
金融機関に対する債務等を反復継続して口座振替又は口座引落しの方法で支払うことを委託する方式(いわゆる「依頼書」方式)による文書については、不課税文書として取り扱っているところですが、契約書、承諾書(念書、同意書を含みます。)等として作成されるものは、単に預金者が自己の事務処理を委託する文書とは異なり、債務の支払方法及び預金の払戻方法の特約を定めるものと認められますから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します(基通第14号文書の8)。
(注) ご質問の文書は、第1号の3文書の重要事項である支払方法を定めるものと、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)の重要事項である払戻方法を定めるものに該当し、通則3のイの規定により、第1号の3文書に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第14号文書の8、別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
取引保証金提供契約書
【 照会要旨】
当社は、商品売買の継続する取引を開始するに当たって契約の相手方から取引の保証金を預かることとし、次の「取引保証金提供契約書」を作成したいと考えますが、課税文書に該当するのでしょうか。
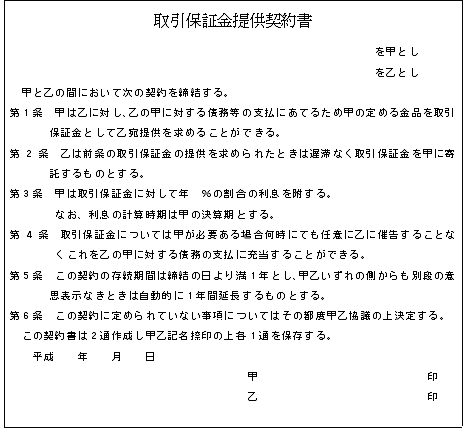
【 回答要旨】
ご質問の文書は、その文書中に「寄託」との文言の記載がありますが、取引保証金は、提供者のために保管するものではありませんから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)には該当せず、その他の課税文書にも該当しません。
なお、取引保証金提供契約書に、取引保証金受領の旨が具体的に記載された場合には、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 寄託の意義
2 寄託契約書と金銭の受取書との判別
3 依頼票(控)
4 敷金の預り証
5 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
6 取引保証金提供契約書
寄託の意義
【 照会要旨】
印紙税が課税される寄託契約について説明してください。
【 回答要旨】
印紙税で課税される寄託は、第14号文書の掲名のとおり金銭又は有価証券の寄託を課税の対象にしています。
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物(受寄物)を保管する契約で、寄託契約については、民法第657条以下に定められているところですが、同法第666条に定める消費寄託もこれに含めることにしています(基通第14号文書の1)。
消費寄託契約とは、受寄者が受寄物を消費することができ、これと同種、同等、同量の物を返還すればよい寄託で、銀行預金はその代表的なものです。
印紙税法では、先にも述べたとおり、金銭又は有価証券の寄託を課税することにしていますので、物品の寄託契約については課税されません。なお、印紙税法では、消費寄託のうち預貯金証書については、第8号文書にしています。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の1
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
寄託契約書と金銭の受取書との判別
【 照会要旨】
預金として金銭を受け入れた際に、次のような「預り証」を作成していますが、この「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)になるのでしょうか。それとも、第17号文書(金銭の受取書)に該当することになるのでしょうか。
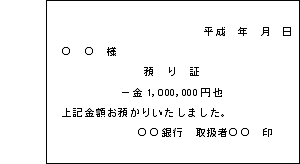
【 回答要旨】
「預り証」と称する文書には、
(1) 後日、仮領収書と同じように正式の領収書を発行することにしているために、金銭を受領したときには「預り証」としたもの
(2) 内入金、手付金等を受領した際に、「預り証」を発行するもの
(3) 得意先のために、金銭を保管することを約して「預り証」を発行するもの
等いろいろなものがありますが、「預り証」は、金銭又は有価証券の受領に際して発行されるという共通点があります。
この金銭又は有価証券の受領が、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために金銭又は有価証券を預かることとしている寄託契約により受領するものであるのか、それ以外の目的による受領なのかにより印紙税の取扱いは異なります。前者の場合には、第14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)となり、後者の場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。
印紙税法では、その文書に記載されている文言から、寄託契約であることが明らかなものは第14号文書とし、それ以外のものは第17号文書として取り扱っています。
したがって、ご質問の「預り証」は、金銭を受領した事実のみの記載で、預金として金銭を預かった旨の記載がありませんから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。 (注) 受取金額の全部又は一部が売上代金であるかが、記載事項から明らかになっていないことから、第17号の1文書になります(第17号文書定義欄1イ)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表 第17号文書定義欄1イ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
依頼票(控)
【 照会要旨】
「依頼票(控)」は、銀行の外務員が預金者から預金として金銭を受け取った場合に「依頼票」と複写で記載して、金銭の受取書として預金者に交付するものです。この「依頼票(控)」には外務員が署名押印等を一切行わないことにしていますので、課税文書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。
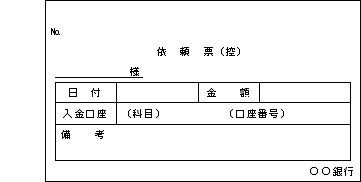
【 回答要旨】
ご質問の文書は、外務員が預金として金銭の受領事実を証明するために作成し、預金者に交付するものですから、外務員の署名、押印等が行われない場合であっても、預金科目及び口座番号の記載がありますので、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当することになります。
(注) 契約書とは、契約の成立を証すべき文書をいい、契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証するものも含まれることにしています(通則5)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
敷金の預り証
【 照会要旨】
建物賃貸借契約の締結に当たって、敷金を預かる際に預り証を作成しましたが、寄託に関する契約書(第14号文書)に該当するのでしょうか。
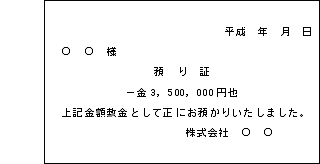
【 回答要旨】
敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。
この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通第14号文書の3)。
なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。
(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
【 照会要旨】
金融機関に対する借入金債務を指定預金口座から自動引落しの方法により支払うに当たって、「元利金等の支払いに関する念書」を作成することにしましたが、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)又はその他の課税文書に該当することになりますか。
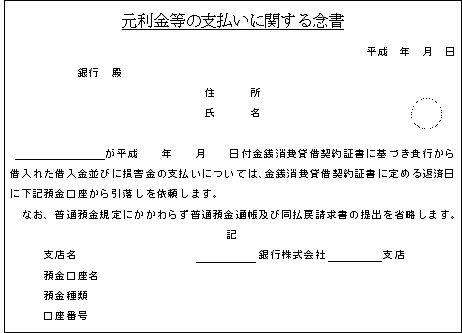
【 回答要旨】
金融機関に対する債務等を反復継続して口座振替又は口座引落しの方法で支払うことを委託する方式(いわゆる「依頼書」方式)による文書については、不課税文書として取り扱っているところですが、契約書、承諾書(念書、同意書を含みます。)等として作成されるものは、単に預金者が自己の事務処理を委託する文書とは異なり、債務の支払方法及び預金の払戻方法の特約を定めるものと認められますから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します(基通第14号文書の8)。
(注) ご質問の文書は、第1号の3文書の重要事項である支払方法を定めるものと、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)の重要事項である払戻方法を定めるものに該当し、通則3のイの規定により、第1号の3文書に該当することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第14号文書の8、別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
取引保証金提供契約書
【 照会要旨】
当社は、商品売買の継続する取引を開始するに当たって契約の相手方から取引の保証金を預かることとし、次の「取引保証金提供契約書」を作成したいと考えますが、課税文書に該当するのでしょうか。
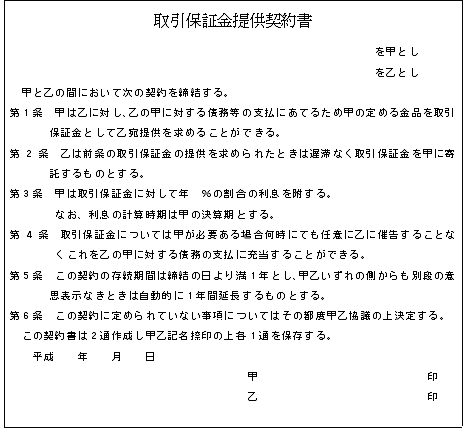
【 回答要旨】
ご質問の文書は、その文書中に「寄託」との文言の記載がありますが、取引保証金は、提供者のために保管するものではありませんから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)には該当せず、その他の課税文書にも該当しません。
なお、取引保証金提供契約書に、取引保証金受領の旨が具体的に記載された場合には、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -