解説記事2005年03月28日 【ニュース特集】 「平和事件」での「信義則違反」の検証(2005年3月28日号・№108)
ニュース特集
最高裁判所は租税訴訟での『信義則』が大きらい?!
「平和事件」での「信義則違反」の検証
最高裁判所が、租税事件について、続々と判決を下している。「平和事件」「SO訴訟」「張江訴訟」では、所法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の適用、所法28条(給与所得)の解釈、消費税法9条(小規模事業者にかかる納税義務の免除)2項に規定する「基準期間における課税売上高」の解釈というように、租税実体法の解釈・判断が主要な争点となる一方で、課税庁がそれまで行ってきた解釈・判断を一方的に変更して課税処分を行ったことへの疑問・反発が「課税処分は『信義則違反』」との納税者側の主張となって表れている。
しかし、いずれの訴訟においても、納税者の『信義則違反』の主張に対して、裁判所が前向きな対応を示したとはいい難い。なかでも、最高裁は、『信義則違反』の適用要件に厳しいハードル(下記の適用要件)を設けており、『信義則違反』が争点として取り上げられることもない。『信義則違反』の問題について、まずは「平和事件」における納税者の主張と、裁判所の判断を検証してみることにする。
信義則(信義誠実の原則)とは何か
民法1条2項は、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定している。
租税法への信義則の適用については、租税法が強行法であって、合法性の原則が支配することから、信義則の適用される余地はない、あるいは、制限されるという見解もある。しかし、納税者の立場からすれば、課税庁の見解に沿った申告を行っていたにもかかわらず、課税庁側が一方的に見解を変更して、遡って課税が行われたとすれば、そのような課税処分には当然反発することになるだろう。
私法上の大原則である信義則だが、合法性の原則が要求される租税法においては、個別的救済の法理として、極めて限定的に適用されることを理解しておく必要がある。
信義則が適用される要件については、昭和62.10.30最高裁第三小法廷判決で次のように判示しており、その後の下級審判決で引用されている。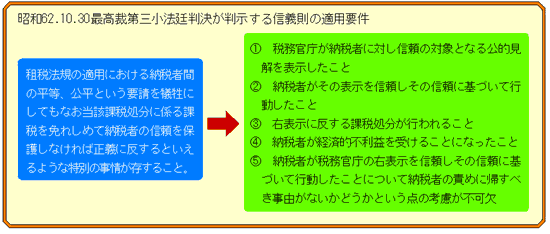
平和事件における「信義則違反」をめぐる争い
平和事件では、上告人(個人X)が自らが取締役となっていた同族会社(N社)に対して巨額(3,455億円余)の無利息貸付を行っていたことについて、被上告人(Y税務署長)が所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)を適用し、この貸付によってXに利息収入が生じたものと認定し更正処分等を行ったものである。
課税当時、課税庁の担当職員がその官職を明示して執筆した著作物(「解説書」)に、「個人が法人に無利息貸付けをしても課税上の問題は生じない」との見解が記載されていたことから、第1審でXは、以下の通り、更正処分等の信義則等違反を主張した。
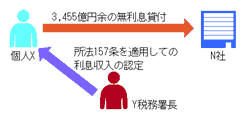
税務実務においては、長年にわたって、所得税と法人税における所得概念の相違、個人と法人との行動形態の違い等から、個人が法人に無利息貸付をしても課税上の問題は生じないものと確信されてきており、かかる税務実務の存在は、課税庁の担当職員がその官職を明示して執筆した著作物にその旨の記載があることからも明らかである。(略)
また、課税庁の担当職員の手になる前記のような著作物は、厳密には個人的な著作物であるが、執筆者の官職が明示されていること等に照らせば、課税庁において、個人から法人に対する無利息貸付けに課税されることはない旨の公の見解を表示したものと同視すべきものである。そして、本件消費貸借がかかる公の見解に等しい見解を信頼してされたものであること、その信頼が保護に値するものであることは多言を要しないから、本件各更正は信義則に反し、違法である。
Xの上記主張に対し、東京地裁は以下のような判断を示した。
昭和62.10.30最高裁第三小法廷判決にいう公的見解の表示とは、通達の公表のような場合の外、申告指導のように個別の納税者に対するものも含まれる場合があるといえるが、租税法律主義の趣旨に照らせば、私的なものであってはならず、行政活動の一環として正式にされたものでなければならないものというべきである。
(前略)各文献は、税務官庁の担当者の手になるものであり、かつ、個人から法人への無利息貸付けは一般に課税対象とはならない旨の記述がみられるものではあるが、いずれも通常想定される一般的な税務事例に即した解説書の性質を有する私的な著作物というほかなく、右にいう公的見解の表示と同視することはできないし、右いずれの記述をみても、当該無利息貸付けが経済的にみて不自然、不合理と認められるような場合を含めて常に本件規定の適用がないと述べているものとは解されない。また、その他の本件全証拠によっても、個人から法人への無利息貸付けの場合にはおよそ本件規定の適用がないとした公的見解が表示されていたものと認めることはできない。
よって、その余の点について判断するまでもなく、本件各更正が信義則の適用によって違法となる余地はない。
また、右に説示した点に加え、本件各更正に先立って、原被告が引用する無利息消費貸借事例が判例として存在していたことも併せ考えれば、本件全証拠によっても、個人の法人に対する無利息貸付けに本件規定の適用がないとの法的確信が納税者間に存在していたと認めることはできないし、原告が本件消費貸借当時において右のように信頼していたとしても、税負担の公平という本件規定の趣旨に反してまでかかる信頼を保護することはできないものというべきである。
平和事件の控訴審(東京高裁)では、前頁の第一審判決の判断を引用して、「本件各更正は、信義則及び憲法31条に照らして違法といえないものと解される。」と判示している。しかし、他方では、東京高裁は、過少申告加算税を課さない「正当な理由」についても認めなかった第一審判決を変更し、以下のように判示して「正当な理由」について容認した。
税務関係者がその編者等や発行者から判断して、その記載内容が税務当局の見解を反映したものと認識し、すなわち、税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解することは無理からぬところである。そして、(中略)控訴人の税務関係のスタッフも本件消費貸借をするに際し税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解していたことが認められ、これを単なる法解釈についての不知、誤解ということはできない。以上を総合すると、控訴人には本件各更正によって新たに納付すべき所得税があるが、過少申告加算税を課することが酷と思料される事情があり、国税通則法65条4項の正当の理由があるというべきである。(中略)また、本件各更正が信義則の適用によって違法ということができないのは前示のとおりであるが、このことと国税通則法65条4項の正当の理由に関する判断とは別のものである。
控訴審判決に対して両当事者は次のような対応を取ることになった。
1 納税者
(1)判決の理由不備(①法157条の適用について、②最高裁判例との相違について、③適用すべき利率について、④法64条1項不適用について)に基づく上告
(2)「法令の解釈に関する重要な事項についての誤り及び判例違反」に基づく上告受理申立て
2 課税庁
通則法65条4項の解釈適用に関する重要な事項についての誤りに基づく上告受理申立て
上告(上告受理申立て)の時点において、納税者側は明示的には「信義則」を争点から外すことになった。一方課税庁側は、「正当な理由」の解・釈を唯一の争点として上告受理申立てを行い、上告審として受理され、以下のような判示を受けることになった。
本件解説書はその記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない面がある。しかしながら、(中略)代表者の経営責任の観点から当該無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とする記述であるということができるから、不合理、不自然な経済的活動として本件規定(所法157条)の適用が肯定される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。そして、当時の裁判例等に照らせば、被上告人の顧問税理士等の税務担当者においても、本件貸付けに本件規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべきであったということができる。
そうすると、(中略)国税通則法65条4項にいう正当な理由があったとは認めることができない。
平和事件では、「解説書」の記載内容について、「信義則違反」を最高裁で争点として提起することもできなかったし、「信義則違反」よりも相当程度適用が緩和されているものと受け止められている「正当な理由」についても、最高裁では、認められない結果となった。
「信義則違反」については、判例が示す適用要件も納税者には厳しいものだが、最高裁で「信義則違反」を争点にして争うこと自体が(上告理由などから)困難であることが窺える。
最高裁判所は租税訴訟での『信義則』が大きらい?!
「平和事件」での「信義則違反」の検証
最高裁判所が、租税事件について、続々と判決を下している。「平和事件」「SO訴訟」「張江訴訟」では、所法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の適用、所法28条(給与所得)の解釈、消費税法9条(小規模事業者にかかる納税義務の免除)2項に規定する「基準期間における課税売上高」の解釈というように、租税実体法の解釈・判断が主要な争点となる一方で、課税庁がそれまで行ってきた解釈・判断を一方的に変更して課税処分を行ったことへの疑問・反発が「課税処分は『信義則違反』」との納税者側の主張となって表れている。
しかし、いずれの訴訟においても、納税者の『信義則違反』の主張に対して、裁判所が前向きな対応を示したとはいい難い。なかでも、最高裁は、『信義則違反』の適用要件に厳しいハードル(下記の適用要件)を設けており、『信義則違反』が争点として取り上げられることもない。『信義則違反』の問題について、まずは「平和事件」における納税者の主張と、裁判所の判断を検証してみることにする。
信義則(信義誠実の原則)とは何か
民法1条2項は、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定している。
租税法への信義則の適用については、租税法が強行法であって、合法性の原則が支配することから、信義則の適用される余地はない、あるいは、制限されるという見解もある。しかし、納税者の立場からすれば、課税庁の見解に沿った申告を行っていたにもかかわらず、課税庁側が一方的に見解を変更して、遡って課税が行われたとすれば、そのような課税処分には当然反発することになるだろう。
私法上の大原則である信義則だが、合法性の原則が要求される租税法においては、個別的救済の法理として、極めて限定的に適用されることを理解しておく必要がある。
信義則が適用される要件については、昭和62.10.30最高裁第三小法廷判決で次のように判示しており、その後の下級審判決で引用されている。
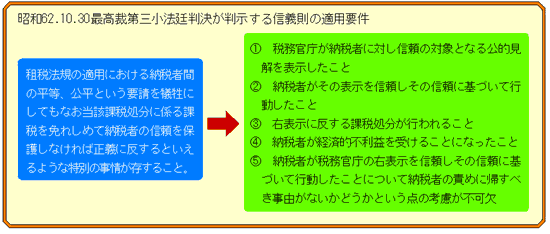
平和事件における「信義則違反」をめぐる争い
平和事件では、上告人(個人X)が自らが取締役となっていた同族会社(N社)に対して巨額(3,455億円余)の無利息貸付を行っていたことについて、被上告人(Y税務署長)が所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)を適用し、この貸付によってXに利息収入が生じたものと認定し更正処分等を行ったものである。
課税当時、課税庁の担当職員がその官職を明示して執筆した著作物(「解説書」)に、「個人が法人に無利息貸付けをしても課税上の問題は生じない」との見解が記載されていたことから、第1審でXは、以下の通り、更正処分等の信義則等違反を主張した。
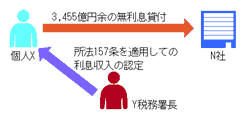
税務実務においては、長年にわたって、所得税と法人税における所得概念の相違、個人と法人との行動形態の違い等から、個人が法人に無利息貸付をしても課税上の問題は生じないものと確信されてきており、かかる税務実務の存在は、課税庁の担当職員がその官職を明示して執筆した著作物にその旨の記載があることからも明らかである。(略)
また、課税庁の担当職員の手になる前記のような著作物は、厳密には個人的な著作物であるが、執筆者の官職が明示されていること等に照らせば、課税庁において、個人から法人に対する無利息貸付けに課税されることはない旨の公の見解を表示したものと同視すべきものである。そして、本件消費貸借がかかる公の見解に等しい見解を信頼してされたものであること、その信頼が保護に値するものであることは多言を要しないから、本件各更正は信義則に反し、違法である。
Xの上記主張に対し、東京地裁は以下のような判断を示した。
昭和62.10.30最高裁第三小法廷判決にいう公的見解の表示とは、通達の公表のような場合の外、申告指導のように個別の納税者に対するものも含まれる場合があるといえるが、租税法律主義の趣旨に照らせば、私的なものであってはならず、行政活動の一環として正式にされたものでなければならないものというべきである。
(前略)各文献は、税務官庁の担当者の手になるものであり、かつ、個人から法人への無利息貸付けは一般に課税対象とはならない旨の記述がみられるものではあるが、いずれも通常想定される一般的な税務事例に即した解説書の性質を有する私的な著作物というほかなく、右にいう公的見解の表示と同視することはできないし、右いずれの記述をみても、当該無利息貸付けが経済的にみて不自然、不合理と認められるような場合を含めて常に本件規定の適用がないと述べているものとは解されない。また、その他の本件全証拠によっても、個人から法人への無利息貸付けの場合にはおよそ本件規定の適用がないとした公的見解が表示されていたものと認めることはできない。
よって、その余の点について判断するまでもなく、本件各更正が信義則の適用によって違法となる余地はない。
また、右に説示した点に加え、本件各更正に先立って、原被告が引用する無利息消費貸借事例が判例として存在していたことも併せ考えれば、本件全証拠によっても、個人の法人に対する無利息貸付けに本件規定の適用がないとの法的確信が納税者間に存在していたと認めることはできないし、原告が本件消費貸借当時において右のように信頼していたとしても、税負担の公平という本件規定の趣旨に反してまでかかる信頼を保護することはできないものというべきである。
平和事件の控訴審(東京高裁)では、前頁の第一審判決の判断を引用して、「本件各更正は、信義則及び憲法31条に照らして違法といえないものと解される。」と判示している。しかし、他方では、東京高裁は、過少申告加算税を課さない「正当な理由」についても認めなかった第一審判決を変更し、以下のように判示して「正当な理由」について容認した。
税務関係者がその編者等や発行者から判断して、その記載内容が税務当局の見解を反映したものと認識し、すなわち、税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解することは無理からぬところである。そして、(中略)控訴人の税務関係のスタッフも本件消費貸借をするに際し税務当局が個人から法人に対する無利息貸付については課税しないとの見解であると解していたことが認められ、これを単なる法解釈についての不知、誤解ということはできない。以上を総合すると、控訴人には本件各更正によって新たに納付すべき所得税があるが、過少申告加算税を課することが酷と思料される事情があり、国税通則法65条4項の正当の理由があるというべきである。(中略)また、本件各更正が信義則の適用によって違法ということができないのは前示のとおりであるが、このことと国税通則法65条4項の正当の理由に関する判断とは別のものである。
控訴審判決に対して両当事者は次のような対応を取ることになった。
1 納税者
(1)判決の理由不備(①法157条の適用について、②最高裁判例との相違について、③適用すべき利率について、④法64条1項不適用について)に基づく上告
(2)「法令の解釈に関する重要な事項についての誤り及び判例違反」に基づく上告受理申立て
2 課税庁
通則法65条4項の解釈適用に関する重要な事項についての誤りに基づく上告受理申立て
上告(上告受理申立て)の時点において、納税者側は明示的には「信義則」を争点から外すことになった。一方課税庁側は、「正当な理由」の解・釈を唯一の争点として上告受理申立てを行い、上告審として受理され、以下のような判示を受けることになった。
本件解説書はその記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない面がある。しかしながら、(中略)代表者の経営責任の観点から当該無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とする記述であるということができるから、不合理、不自然な経済的活動として本件規定(所法157条)の適用が肯定される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。そして、当時の裁判例等に照らせば、被上告人の顧問税理士等の税務担当者においても、本件貸付けに本件規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべきであったということができる。
そうすると、(中略)国税通則法65条4項にいう正当な理由があったとは認めることができない。
平和事件では、「解説書」の記載内容について、「信義則違反」を最高裁で争点として提起することもできなかったし、「信義則違反」よりも相当程度適用が緩和されているものと受け止められている「正当な理由」についても、最高裁では、認められない結果となった。
「信義則違反」については、判例が示す適用要件も納税者には厳しいものだが、最高裁で「信義則違反」を争点にして争うこと自体が(上告理由などから)困難であることが窺える。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























