資料2006年01月31日 【裁決事例】 免税期間においても課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在すると判断した事例(平成13年4月~平成14年3月課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分/棄却)
(平17.1.26裁決、裁決事例集No.69 414頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、地方公共団体である審査請求人(以下「請求人」という。)の課税仕入れに係る消費税額の控除について、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項の規定を適用した原処分について、免税事業者(消費税法第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者。以下同じ。)である課税期間(以下「免税期間」という。)においては、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額は存在しないから、補助金等の額のうち、免税期間に係る借入金等の返済に充当した額については、同項の規定を適用することはできず、原処分は違法であるとして、請求人がその一部の取消しを求めた事案であり、争点は次のとおりである。
[争点]借入金等に係る事業が行われた課税期間において免税事業者であった場合に、当該借入金等の返済のための補助金等を受けた課税期間において、消費税法第60条第4項の規定を適用することができるか否か。
(2)審査請求に至る経緯
請求人の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、審査請求(平成16年8月9日請求)に至る経緯等は、別表1のとおりである。
(3)関係法令等
関係法令等については、別紙1のとおりである。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 請求人は、平成12年3月31日に、消費税法第9条第4項に規定する「消費税課税事業者選択届出書」を原処分庁に提出した。
ロ 請求人は、本件課税期間において、免税期間に起債した地方債の償還を行っており、その償還に係る元金の内訳は、平成6年度借入分が○○○○円、平成7年度借入分が○○○○円、平成8年度借入分が○○○○円、平成9年度借入分が○○○○円、平成10年度借入分が○○○○円の合計38,550,086円である。
ハ 請求人は、本件課税期間の消費税等の額の計算において、一般会計から特別会計への繰入金○○○○円(以下「本件繰入金の額」という。)を、〔1〕特定収入の額○○○○円及び〔2〕特定収入に該当しない額○○○○円(上記ロに係る地方債の元金償還額のうち○○○○円と償還金利息○○○○円の合計額)に区分して、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を計算し、消費税等の確定申告書を提出した。
ニ 原処分庁は、本件繰入金の額、下水道加入金○○○○円及び消費税還付加算金○○○○円の合計額○○○○円(以下「本件繰入金等の額」という。)のうち、上記ロに係る地方債の元金償還に充当した額等は特定収入に該当するとして、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額が過大であるとする原処分を行った。
2 主張
当事者の主張は、別紙2のとおりである。
3 判断
(1)課税仕入れに係る消費税額
イ 消費税法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れとは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けること(当該他の者において課税資産の譲渡等に該当することとなるものに限る。)をいうものとされており、一方、課税仕入れの範囲から除外されるものとは、当該他の者において課税資産の譲渡等に該当することとなるものであっても、同法第7条第1項各号に掲げる輸出取引等に該当するもの及び同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものとされている。
ロ 請求人は、先例裁決を引用して、免税事業者においては、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額は存在しない旨主張するが、事業者の行う資産の譲受け等が、課税仕入れの範囲から除外されるものであるか否かは、消費税法第2条第1項第12号の規定により判断されるべきものであり、免税事業者が行う資産の譲受け等であることをもって、当該資産の譲受け等が課税仕入れの範囲から除外されると解されるものではない。
ハ また、消費税法第30条第1項は、同項の適用の対象となる事業者から免税事業者を除外しているが、これは、免税事業者は納税義務が免除されている一方で、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けることができない旨を規定したものであり、同項が、免税事業者においては課税仕入れに係る消費税額が存在しない旨を規定したものと解することはできない。
ニ なお、請求人が引用する先例裁決は、免税事業者が行う課税資産の譲渡等について課されるべき消費税額に相当する額が存在しないことを判断したものであって、免税事業者の行う資産の譲受け等に係る消費税額に相当する額が存在しないと判断しているものではない。
請求人の主張は、免税事業者が行う課税資産の譲渡等について課されるべき消費税額が存在しないことをもって、免税事業者における課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額の存在をも否定している点において、先例裁決の解釈を誤っているものといわざるを得ず、採用することはできない。
(2)消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
イ 消費税法第60条第4項は、同法第30条から第36条までの規定に対する課税仕入れ等の税額控除の特例であり、国や地方公共団体の特別会計等が課税仕入れ等を行った課税期間に、他会計からの繰入金、資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、消費税の還付加算金等の特定収入があった場合には、その課税期間の課税仕入れ等の税額から特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を控除し、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象としない旨を規定したものである。
ロ また、本件通達は、特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法等について定めたものであるが、借入後に法令又は交付要綱等で借入金等の返済又は償還のためにのみ使途が特定された補助金等の交付があった場合は、当該補助金等の額を、その借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額との割合で、課税仕入れ等に係る特定収入とそれ以外のものとに区分する旨を定めたものであり、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を仕入税額控除の対象としないという消費税法第60条第4項の規定の趣旨からみて、当審判所においても、この取扱いは相当であると認められる。
ハ これを本件についてみると、本件繰入金等の額のうち、平成6年度から平成10年度に係る地方債の元金償還に充当された額については、借入金等の償還に使途が特定されていることから、消費税法第60条第4項及び本件通達により、その借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合であん分して、特定収入の額を算出することになる。
ニ なお、請求人は、免税期間において消費税の仕入税額控除や還付も受けていないことから、本件課税期間において仕入控除税額の調整を行った原処分は違法である旨主張するが、免税事業者が消費税の仕入税額控除や還付を受けるためには、消費税法第9条第4項に規定する「消費税課税事業者選択届出書」を原処分庁に提出することが要件とされているところ、請求人は自らの判断で課税事業者を選択しなかったのであって、免税期間において消費税の仕入税額控除や還付を受けていたか否かが、消費税法第60条第4項の規定の適用の可否を左右するものではない。
請求人の主張は、消費税法第60条第4項の規定の適用に当たり、免税期間における課税事業者に係る選択をその前提としているものであり、採用することはできない。
(3)以上のとおり、上記争点について原処分に違法は認められず、請求人の本件課税期間に係る還付すべき税額を算出すると、別表2の「審判所認定額」欄のとおりとなり、この金額は、更正処分に係る還付すべき税額を下回るから、本件課税期間の更正処分は適法である。
(4)過少申告加算税を含む原処分のその他の部分については、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
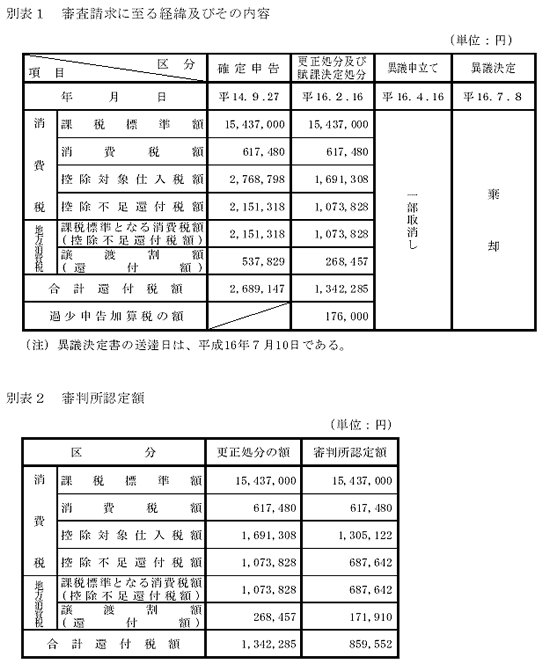
別紙1 関係法令等
1 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れについて、「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当することとなるもので、第7条《輸出免税等》第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」旨規定している。
2 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間(第2条第1項第14号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における課税売上高が3千万円以下である者については、第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」旨規定している。
3 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において課税仕入れ等を行った場合には、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を控除する。」旨規定している。
4 消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項は、「国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れ等を行う場合において、当該課税仕入れ等の日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、第30条から第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。」旨規定している。
5 消費税法基本通達(平成14年12月2日付課消1-48「消費税法基本通達の一部改正について」による改正前のもの。以下同じ。)16-2-2《国、地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法等》(4)(以下「本件通達」という。)は、「『法令又は交付要綱等』又は『予算書、予算関係書類、決算書、決算関係書類』において、借入金等の返済費又は償還費のための補助金等とされているものについては、当該補助金等の額に、当該借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん分する方法によりその使途を特定し、これらの計算過程を消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号ロに規定する文書に添付して税務署長に提出し、その文書においてその使途の特定を明らかにする。」旨定めている。
別紙2 当事者の主張
[争点]借入金等に係る事業が行われた課税期間において免税事業者であった場合に、当該借入金等の返済のための補助金等を受けた課税期間において、消費税法第60条第4項の規定を適用することができるか否か。
請求人
原処分は、次の理由により違法であるから、本件繰入金等の額のうち、地方債の償還に充当した額について消費税法第60条第4項の規定を適用し、仕入控除税額を調整した部分の取消しを求める。
なお、原処分のその他の部分については争わない。
1 課税仕入れに係る消費税の額
消費税法第9条第1項は、「消費税法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず」と規定しているように、同法第5条第1項の例外規定であり、課税要件としての納税義務者の範囲を限定するもの、すなわち、所定の要件を具備した事業者を同項に規定する納税義務者から除外すると解すべきである。
また、消費税法第30条は、事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務が免除されている事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れにつき課された消費税を控除すると規定しており、仕入税額控除は課税事業者に限られている。
したがって、免税事業者が免税期間において課税資産の譲渡等を行ったとしても納税義務は発生せず、課されるべき消費税も存在しないことから、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在しないと解すべきである。
このことは、裁決事例集(国税不服審判所版)NO.61の事例47「平成13年3月14日裁決」(以下「先例裁決」という。)において、「免税事業者が課税資産の譲渡等を行ったとしても、納税義務が発生せず、そうである以上、課されるべき消費税額等に相当する額は存在しない。」と裁決されていることからみても明らかである。
2 消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
(1)原処分庁は、本件繰入金等の額のうち、平成6年度から平成10年度において起債した地方債の償還等に充てた額があるとして、本件通達に基づき、各年度の総支出額及び課税支出額から課税支出割合を求め、課税仕入れ等に使途を特定した額を算出している。
しかしながら、請求人は、地方債を起債した当該各年度において免税事業者であり、上記1のとおり、免税事業者には課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在しないことから、地方債を起債した各課税期間の課税支出額は零円、また課税支出割合は零%であり、本件通達による補助金等の使途を特定する額はない。
(2)請求人は、地方債を起債した各課税期間は、免税事業者であったことから、仕入税額控除の適用及び消費税の還付も受けていない。
したがって、消費税法第60条第4項に規定する仕入控除税額について一定の調整を行うことは違法である。
原処分庁
原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
1 課税仕入れに係る消費税の額
課税仕入れとは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいうことから、免税事業者であるかどうかに関係なく、課税仕入れは存在するものであり、また、免税事業者は、消費税法第30条第1項本文の規定により、課税仕入れに係る消費税額の税額控除を行うことはできないが、課税仕入れに係る消費税額は存在する。
このことについては、免税事業者であった請求人に対して課税資産の譲渡等を行った事業者に課税売上及び課税売上に係る消費税額が生じることからも明らかである。
2 消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
(1)消費税法第60条第4項では、一定の割合を超える特定収入がある場合、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した残額とする旨規定されている。
また、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における収入の使途の特定については、本件通達によることとされている。
さらに、本件通達では、借入金等の返済費又は償還費のための補助金等については、当該補助金等の額に借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうち課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん分する方法により、その使途を特定する旨定められている。
これは、借入れを行った年度において、当該借入金等は特定収入に該当しないことから、その後当該借入金等の返済又は償還のために補助金等を受けた時に、当該補助金等を特定収入にすることにより、税額控除を調整する税制上の仕組みとなっているものであり、借入金等に係る事業が行われた課税期間が免税事業者であったかどうかに関係なく適用されるものである。
(2)請求人は、免税期間において仕入税額控除や還付も受けていない旨主張するが、仕入税額控除又は還付を受けていないのは、請求人がその当時課税事業者を選択しなかったことによるものであるから、このことをもって、本件繰入金等の額が特定収入に該当しないとする理由にはならない。
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、地方公共団体である審査請求人(以下「請求人」という。)の課税仕入れに係る消費税額の控除について、消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項の規定を適用した原処分について、免税事業者(消費税法第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者。以下同じ。)である課税期間(以下「免税期間」という。)においては、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額は存在しないから、補助金等の額のうち、免税期間に係る借入金等の返済に充当した額については、同項の規定を適用することはできず、原処分は違法であるとして、請求人がその一部の取消しを求めた事案であり、争点は次のとおりである。
[争点]借入金等に係る事業が行われた課税期間において免税事業者であった場合に、当該借入金等の返済のための補助金等を受けた課税期間において、消費税法第60条第4項の規定を適用することができるか否か。
(2)審査請求に至る経緯
請求人の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、審査請求(平成16年8月9日請求)に至る経緯等は、別表1のとおりである。
(3)関係法令等
関係法令等については、別紙1のとおりである。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 請求人は、平成12年3月31日に、消費税法第9条第4項に規定する「消費税課税事業者選択届出書」を原処分庁に提出した。
ロ 請求人は、本件課税期間において、免税期間に起債した地方債の償還を行っており、その償還に係る元金の内訳は、平成6年度借入分が○○○○円、平成7年度借入分が○○○○円、平成8年度借入分が○○○○円、平成9年度借入分が○○○○円、平成10年度借入分が○○○○円の合計38,550,086円である。
ハ 請求人は、本件課税期間の消費税等の額の計算において、一般会計から特別会計への繰入金○○○○円(以下「本件繰入金の額」という。)を、〔1〕特定収入の額○○○○円及び〔2〕特定収入に該当しない額○○○○円(上記ロに係る地方債の元金償還額のうち○○○○円と償還金利息○○○○円の合計額)に区分して、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を計算し、消費税等の確定申告書を提出した。
ニ 原処分庁は、本件繰入金の額、下水道加入金○○○○円及び消費税還付加算金○○○○円の合計額○○○○円(以下「本件繰入金等の額」という。)のうち、上記ロに係る地方債の元金償還に充当した額等は特定収入に該当するとして、本件課税期間の課税仕入れに係る消費税額が過大であるとする原処分を行った。
2 主張
当事者の主張は、別紙2のとおりである。
3 判断
(1)課税仕入れに係る消費税額
イ 消費税法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れとは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供を受けること(当該他の者において課税資産の譲渡等に該当することとなるものに限る。)をいうものとされており、一方、課税仕入れの範囲から除外されるものとは、当該他の者において課税資産の譲渡等に該当することとなるものであっても、同法第7条第1項各号に掲げる輸出取引等に該当するもの及び同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものとされている。
ロ 請求人は、先例裁決を引用して、免税事業者においては、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額は存在しない旨主張するが、事業者の行う資産の譲受け等が、課税仕入れの範囲から除外されるものであるか否かは、消費税法第2条第1項第12号の規定により判断されるべきものであり、免税事業者が行う資産の譲受け等であることをもって、当該資産の譲受け等が課税仕入れの範囲から除外されると解されるものではない。
ハ また、消費税法第30条第1項は、同項の適用の対象となる事業者から免税事業者を除外しているが、これは、免税事業者は納税義務が免除されている一方で、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けることができない旨を規定したものであり、同項が、免税事業者においては課税仕入れに係る消費税額が存在しない旨を規定したものと解することはできない。
ニ なお、請求人が引用する先例裁決は、免税事業者が行う課税資産の譲渡等について課されるべき消費税額に相当する額が存在しないことを判断したものであって、免税事業者の行う資産の譲受け等に係る消費税額に相当する額が存在しないと判断しているものではない。
請求人の主張は、免税事業者が行う課税資産の譲渡等について課されるべき消費税額が存在しないことをもって、免税事業者における課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税額の存在をも否定している点において、先例裁決の解釈を誤っているものといわざるを得ず、採用することはできない。
(2)消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
イ 消費税法第60条第4項は、同法第30条から第36条までの規定に対する課税仕入れ等の税額控除の特例であり、国や地方公共団体の特別会計等が課税仕入れ等を行った課税期間に、他会計からの繰入金、資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、消費税の還付加算金等の特定収入があった場合には、その課税期間の課税仕入れ等の税額から特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を控除し、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象としない旨を規定したものである。
ロ また、本件通達は、特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法等について定めたものであるが、借入後に法令又は交付要綱等で借入金等の返済又は償還のためにのみ使途が特定された補助金等の交付があった場合は、当該補助金等の額を、その借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額との割合で、課税仕入れ等に係る特定収入とそれ以外のものとに区分する旨を定めたものであり、特定収入に見合う課税仕入れ等の税額を仕入税額控除の対象としないという消費税法第60条第4項の規定の趣旨からみて、当審判所においても、この取扱いは相当であると認められる。
ハ これを本件についてみると、本件繰入金等の額のうち、平成6年度から平成10年度に係る地方債の元金償還に充当された額については、借入金等の償還に使途が特定されていることから、消費税法第60条第4項及び本件通達により、その借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合であん分して、特定収入の額を算出することになる。
ニ なお、請求人は、免税期間において消費税の仕入税額控除や還付も受けていないことから、本件課税期間において仕入控除税額の調整を行った原処分は違法である旨主張するが、免税事業者が消費税の仕入税額控除や還付を受けるためには、消費税法第9条第4項に規定する「消費税課税事業者選択届出書」を原処分庁に提出することが要件とされているところ、請求人は自らの判断で課税事業者を選択しなかったのであって、免税期間において消費税の仕入税額控除や還付を受けていたか否かが、消費税法第60条第4項の規定の適用の可否を左右するものではない。
請求人の主張は、消費税法第60条第4項の規定の適用に当たり、免税期間における課税事業者に係る選択をその前提としているものであり、採用することはできない。
(3)以上のとおり、上記争点について原処分に違法は認められず、請求人の本件課税期間に係る還付すべき税額を算出すると、別表2の「審判所認定額」欄のとおりとなり、この金額は、更正処分に係る還付すべき税額を下回るから、本件課税期間の更正処分は適法である。
(4)過少申告加算税を含む原処分のその他の部分については、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
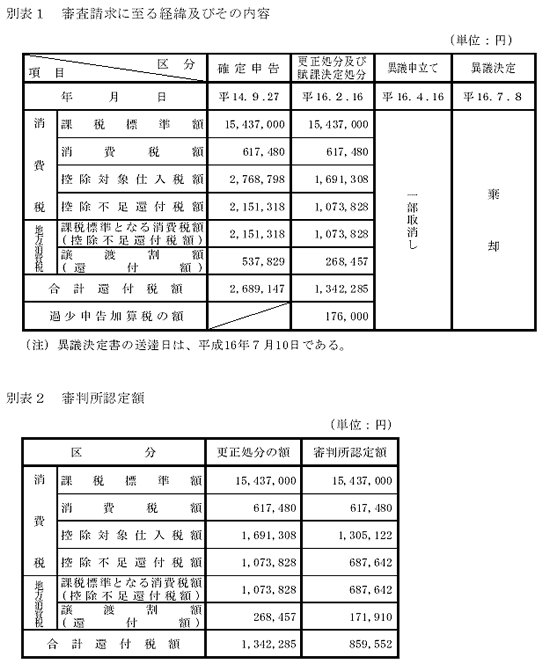
別紙1 関係法令等
1 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、課税仕入れについて、「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当することとなるもので、第7条《輸出免税等》第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」旨規定している。
2 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間(第2条第1項第14号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における課税売上高が3千万円以下である者については、第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」旨規定している。
3 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において課税仕入れ等を行った場合には、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を控除する。」旨規定している。
4 消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項は、「国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れ等を行う場合において、当該課税仕入れ等の日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、第30条から第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。」旨規定している。
5 消費税法基本通達(平成14年12月2日付課消1-48「消費税法基本通達の一部改正について」による改正前のもの。以下同じ。)16-2-2《国、地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法等》(4)(以下「本件通達」という。)は、「『法令又は交付要綱等』又は『予算書、予算関係書類、決算書、決算関係書類』において、借入金等の返済費又は償還費のための補助金等とされているものについては、当該補助金等の額に、当該借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん分する方法によりその使途を特定し、これらの計算過程を消費税法施行令第75条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》第1項第6号ロに規定する文書に添付して税務署長に提出し、その文書においてその使途の特定を明らかにする。」旨定めている。
別紙2 当事者の主張
[争点]借入金等に係る事業が行われた課税期間において免税事業者であった場合に、当該借入金等の返済のための補助金等を受けた課税期間において、消費税法第60条第4項の規定を適用することができるか否か。
請求人
原処分は、次の理由により違法であるから、本件繰入金等の額のうち、地方債の償還に充当した額について消費税法第60条第4項の規定を適用し、仕入控除税額を調整した部分の取消しを求める。
なお、原処分のその他の部分については争わない。
1 課税仕入れに係る消費税の額
消費税法第9条第1項は、「消費税法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず」と規定しているように、同法第5条第1項の例外規定であり、課税要件としての納税義務者の範囲を限定するもの、すなわち、所定の要件を具備した事業者を同項に規定する納税義務者から除外すると解すべきである。
また、消費税法第30条は、事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務が免除されている事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れにつき課された消費税を控除すると規定しており、仕入税額控除は課税事業者に限られている。
したがって、免税事業者が免税期間において課税資産の譲渡等を行ったとしても納税義務は発生せず、課されるべき消費税も存在しないことから、課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在しないと解すべきである。
このことは、裁決事例集(国税不服審判所版)NO.61の事例47「平成13年3月14日裁決」(以下「先例裁決」という。)において、「免税事業者が課税資産の譲渡等を行ったとしても、納税義務が発生せず、そうである以上、課されるべき消費税額等に相当する額は存在しない。」と裁決されていることからみても明らかである。
2 消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
(1)原処分庁は、本件繰入金等の額のうち、平成6年度から平成10年度において起債した地方債の償還等に充てた額があるとして、本件通達に基づき、各年度の総支出額及び課税支出額から課税支出割合を求め、課税仕入れ等に使途を特定した額を算出している。
しかしながら、請求人は、地方債を起債した当該各年度において免税事業者であり、上記1のとおり、免税事業者には課税仕入れ及び課税仕入れに係る消費税は存在しないことから、地方債を起債した各課税期間の課税支出額は零円、また課税支出割合は零%であり、本件通達による補助金等の使途を特定する額はない。
(2)請求人は、地方債を起債した各課税期間は、免税事業者であったことから、仕入税額控除の適用及び消費税の還付も受けていない。
したがって、消費税法第60条第4項に規定する仕入控除税額について一定の調整を行うことは違法である。
原処分庁
原処分は、次の理由により適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
1 課税仕入れに係る消費税の額
課税仕入れとは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいうことから、免税事業者であるかどうかに関係なく、課税仕入れは存在するものであり、また、免税事業者は、消費税法第30条第1項本文の規定により、課税仕入れに係る消費税額の税額控除を行うことはできないが、課税仕入れに係る消費税額は存在する。
このことについては、免税事業者であった請求人に対して課税資産の譲渡等を行った事業者に課税売上及び課税売上に係る消費税額が生じることからも明らかである。
2 消費税法第60条第4項の規定に基づく仕入控除税額の特例
(1)消費税法第60条第4項では、一定の割合を超える特定収入がある場合、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した残額とする旨規定されている。
また、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における収入の使途の特定については、本件通達によることとされている。
さらに、本件通達では、借入金等の返済費又は償還費のための補助金等については、当該補助金等の額に借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出のうち課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん分する方法により、その使途を特定する旨定められている。
これは、借入れを行った年度において、当該借入金等は特定収入に該当しないことから、その後当該借入金等の返済又は償還のために補助金等を受けた時に、当該補助金等を特定収入にすることにより、税額控除を調整する税制上の仕組みとなっているものであり、借入金等に係る事業が行われた課税期間が免税事業者であったかどうかに関係なく適用されるものである。
(2)請求人は、免税期間において仕入税額控除や還付も受けていない旨主張するが、仕入税額控除又は還付を受けていないのは、請求人がその当時課税事業者を選択しなかったことによるものであるから、このことをもって、本件繰入金等の額が特定収入に該当しないとする理由にはならない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























