解説記事2007年03月19日 【「会社法関係規則による各種書類ひな型の解説」第2回】 事業報告(下)、附属明細書(事業報告関係)(2007年3月19日号・№203)
「会社法関係規則による各種書類ひな型の解説」第2回
事業報告(下)、附属明細書(事業報告関係)
(社)日本経済団体連合会経済第二本部 中村 誠
前回に続き、今回は、事業報告(下)及び附属明細書(事業報告関係)について解説する(本文の参照頁は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を表す。なお、原文は日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf)からダウンロードすることができる)。
4.会社役員に関する事項(承前)
(6)「社外役員に関する開示」
社外役員を設けた株式会社においては、新たに、社外役員に関する多くの項目にわたる開示が求められる。
まず、「他の会社の業務執行者との兼職状況」(ひな型22頁参照)については、社外役員が他の会社(外国会社を含む)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは持分会社の法人業務執行社員の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの)又は使用人である場合に、重要でないものを除き、その事実と当該他の会社との関係を記載する(記載例1参照)。例えば、当該他の会社との取引が全くない場合や当該他の会社が単なる財産管理会社に過ぎないような場合、当該他の会社が休眠会社である場合などが「重要でないもの」に該当しうる。
「他の株式会社の社外役員との兼任状況」についても、社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任している場合に、同様にその事実を記載する。
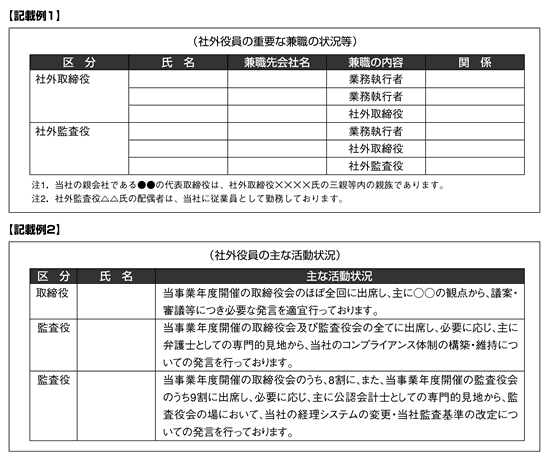
(7)「会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係」
「会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係」(ひな型22頁参照)については、社外役員が、株式会社又はその特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは持分会社の法人業務執行社員の職務を行うべき者(特定関係事業者が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの)又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを事業報告作成会社が知っているときは、重要でないものを除き、当該事実を記載する。
「知っているとき」とは、当該事項が事業報告の記載事項となっていることを前提として行われた調査の結果、知っている場合を意味する。何も調査をせずに「知っていない」と判断することはできないことは言うまでもない。
(8)「各社外役員の主な活動状況」
「各社外役員の主な活動状況」(ひな型23頁、記載例2参照)は、各社外役員ごとに取締役会及び監査役会(監査委員会)における出席・発言の状況について記載する。取締役会ごとの出欠状況まで明らかにする必要はないが、取締役会への社外役員の参加状況が明らかになるよう記載する。
発言の状況については、どのような分野についてどのような観点で発言したか等、発言の概要を記載すれば足りる。
また、社外役員の意見により会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、重要でないものを除き、その内容を記載する。ただし、企業秘密に該当する事項を記載する必要はなく、社外役員の意見によって変更されたか否かが判然としない場合には、記載する必要はない。通常の場合は開示すべき事項はないと考えられる。
会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(社外監査役の場合は、不正な業務の執行)が行われた場合、重要でないものを除き、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を記載する。不当・不正な行為がなければ、開示すべきものはない。
(9)「社外役員の報酬等の総額」「親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は子会社からの役員報酬等の総額」
「社外役員の報酬等の総額」「親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は子会社からの役員報酬等の総額」(ひな型25頁、記載例3参照)については、通常の役員報酬の記載とは別に、社外役員全体の報酬等の総額を記載する。また、社外役員のうちに、親会社又は当該親会社の子会社(親会社が会社でない場合にはその子会社に相当するものを含む)の役員を兼ねている者がいる場合には、当該兼任者が親会社又は当該親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額のうち、当該事業年度において社外役員であった期間に受けたものを記載する。
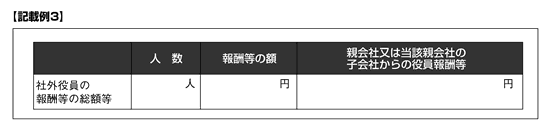
ただし、役員としての報酬等を記載すれば足り、社外役員が親会社又は当該親会社の子会社の使用人を兼ねている場合における使用人分給与を記載する必要はない。
各社外役員毎の内訳の記載はもとより、社外取締役と社外監査役が存する会社における、社外取締役と社外監査役との内訳の記載も義務付けられていない。
5.会計監査人に関する事項
(1)「当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項」
「当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項」(ひな型26頁参照)については、辞任した又は解任された会計監査人につき、次の事項を記載する。
① 氏名又は名称
② 監査役又は監査役会により会計監査人が解任されたときは、その旨及びその理由
③ 辞任又は解任について会計監査人から述べられた意見があったときは、その意見の内容
④ 辞任した者により辞任した理由が述べられるときは、その理由
ただし、会社役員と異なり、会計監査人の場合、当該事業年度中に辞任した者であれば、事業年度中の定時総会以前に辞任した又は解任されたものであっても、事業報告への記載の対象となる。
(2)「現在の業務停止処分に関する事項」
「現在の業務停止処分に関する事項」(ひな型26頁参照)については、会計監査人が現に業務停止期間中である場合に、当該業務停止処分の内容について記載する。この場合に対象となる業務停止の範囲は、監査業務に対する業務停止に限定されず、非監査業務等に対する業務停止も含まれる。
「現に」とは、事業報告の作成日を意味すると解される。
(3)「過去二年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項」
「過去二年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項」(ひな型26頁参照)については、会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合に、当該処分に係る事項のうち、事業報告作成会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項を記載する。記載の対象となる業務停止の範囲は、監査業務に対する業務停止に限定されず、非監査業務等に対する業務停止も含まれる。
「過去二年間」とは、「事業報告の作成日からさかのぼって二年間」を意味すると解される。
(4)「会計監査人の報酬等」
「会計監査人の報酬等」(ひな型26頁、記載例4参照)の関係では、以下の各事項について記載する(3・4は有価証券報告書提出大会社についてのみ)。
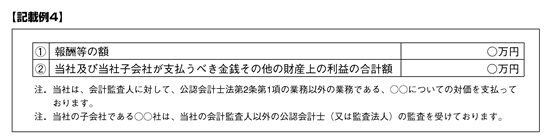
1.当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
2.会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
3.会計監査人である公認会計士又は監査法人に事業報告作成会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る)
4.事業報告作成会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人が当該事業報告作成会社の子会社(重要なものに限る)の計算関係書類(これに相当するものを含む)の監査(会社法又は証券取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む)の規定によるものに限る)をしているときは、その事実
なお、従来の営業報告書において求められていた、企業集団(事業報告作成会社及びその子会社)から受け取る財産上の利益を監査報酬とそれ以外に分けて記載することは、事業報告においては求められていない。
(5)「解任又は不再任の決定の方針」
「解任又は不再任の決定の方針」(ひな型27頁参照)については、会計監査人がどのような事態に陥った場合に、その解任又は不再任の議案を株主総会に提出するか等についての方針を定め、これを記載する。
何ら方針を定めていない場合は、その旨を記載する。
6.業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
業務の適正を確保するための体制(会社法348条3項4号、362条4項6号並びに416条1項1号ロ・ホに規定する体制)を定めている場合には、当該体制の整備に関する決定をすることが会社法上義務づけられているか否かにかかわらず、その内容の概要を記載する(ひな型27頁参照)。もちろん概要ではなく決定そのものを掲載した方が正確で分かりやすいと考えられる場合には、全文を掲載しても差し支えない。
なお、本項目についてはひな型に記載例を掲載していない。これは、本項目がすぐれて各社の実状に応じた創意工夫が求められるものであると考えられるからである。例えば、業態、規模等が全く異なる他社の体制を漫然と模倣したことが原因で、従業員の法令違反を招いた場合、しかるべき体制を構築していなかったものとして取締役の善管注意義務・忠実義務違反が問われるものと考えられる。また、単に決定して開示すれば済むものではなく、不断の見直し、充実、実践が求められる事項であることを念頭に置く必要がある。
7.株式会社の支配に関する基本方針
事業報告作成会社が当該事業報告作成会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めた場合には、①基本方針の内容、②基本方針の実現に資する取組みや不適切な者に支配されることを防止する取組み、③前記取組みが株主共同の利益を損なわない、役員の地位の維持を目的とするものではないとの取締役会の判断及び理由等を記載しなければならない(ひな型28頁参照)。これは、基本方針を定めている場合に限り記載が求められるものであり、そのような基本方針を定めていない場合は記載の必要はない。
なお、「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」とは、いわゆる買収防衛策のみを対象にしているわけではない。基本方針の内容については、特に規制はなく、定型のものがあるわけでもないため、各会社が基本方針として定めた内容をそのまま事業報告に記載すれば足りる。
Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)
会社法では、事業報告の附属明細書と計算書類の附属明細書は、別々のものとして定義された。実務上は、別々の書類として作成するのではなく、これまでどおり合冊して作成する方法もありうるが、会社法では、事業報告と計算書類とでその附属明細書を含め、監査主体が異なることが想定されている点に留意する必要がある。
事業報告の附属明細書には、「事業報告の内容を補足する重要な事項」のほか、公開会社においては、「会社役員の他の会社の業務執行者との兼務状況の明細」「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を記載する(ひな型30頁参照)。後者については、会社と、会社役員又は支配株主以外の第三者との間の取引(いわゆる間接取引)のうち、会社と会社役員又は支配株主との利益が相反するものにつき(例えば、会社役員の債務の保証を会社が行うこと)、重要でないものを除き、その明細を記載する。会社と、会社役員又は支配株主との直接取引は含まれない(計算書類における、取締役等に対する金銭債権、金銭債務それぞれの総額の注記(ひな型41頁参照)または関連当事者との取引に関する注記(ひな型44頁参照)の対象となる)。
なお、公開会社でない場合については、具体的な記載事項が定められていないが、附属明細書の作成を省略できる旨の規定は設けられておらず、「重要な事項が何ら存しない」との理由で附属明細書の作成義務を逃れることはできない。実質的にも、各社においておよそ「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないということは、通常、想定しにくいと解される。
(なかむら・まこと)
連載予定
第1回 基本方針、Ⅰ.事業報告(上)
第2回 事業報告(下)、Ⅱ.附属明細書(事業報告関係)
第3回 Ⅲ.計算書類(上)
第4回 計算書類(下)、Ⅳ.連結計算書類、Ⅴ.附属明細書(計算書類関係)、Ⅵ.決算公告要旨
第5回 Ⅶ.株主総会参考書類、Ⅷ.招集通知、Ⅸ.議決権行使書面
第6回 Ⅹ.監査報告
事業報告(下)、附属明細書(事業報告関係)
(社)日本経済団体連合会経済第二本部 中村 誠
前回に続き、今回は、事業報告(下)及び附属明細書(事業報告関係)について解説する(本文の参照頁は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を表す。なお、原文は日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf)からダウンロードすることができる)。
4.会社役員に関する事項(承前)
(6)「社外役員に関する開示」
社外役員を設けた株式会社においては、新たに、社外役員に関する多くの項目にわたる開示が求められる。
まず、「他の会社の業務執行者との兼職状況」(ひな型22頁参照)については、社外役員が他の会社(外国会社を含む)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは持分会社の法人業務執行社員の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの)又は使用人である場合に、重要でないものを除き、その事実と当該他の会社との関係を記載する(記載例1参照)。例えば、当該他の会社との取引が全くない場合や当該他の会社が単なる財産管理会社に過ぎないような場合、当該他の会社が休眠会社である場合などが「重要でないもの」に該当しうる。
「他の株式会社の社外役員との兼任状況」についても、社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任している場合に、同様にその事実を記載する。
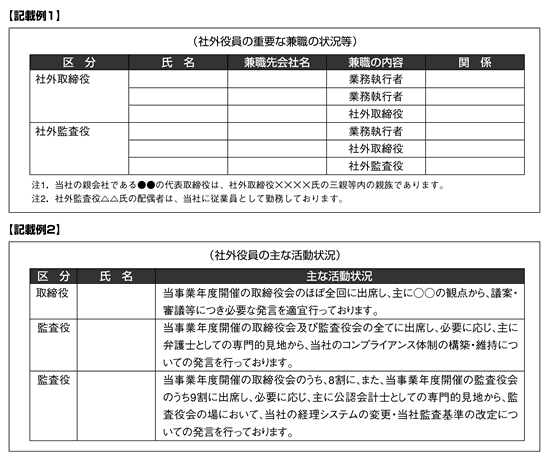
(7)「会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係」
「会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係」(ひな型22頁参照)については、社外役員が、株式会社又はその特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは持分会社の法人業務執行社員の職務を行うべき者(特定関係事業者が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの)又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを事業報告作成会社が知っているときは、重要でないものを除き、当該事実を記載する。
「知っているとき」とは、当該事項が事業報告の記載事項となっていることを前提として行われた調査の結果、知っている場合を意味する。何も調査をせずに「知っていない」と判断することはできないことは言うまでもない。
(8)「各社外役員の主な活動状況」
「各社外役員の主な活動状況」(ひな型23頁、記載例2参照)は、各社外役員ごとに取締役会及び監査役会(監査委員会)における出席・発言の状況について記載する。取締役会ごとの出欠状況まで明らかにする必要はないが、取締役会への社外役員の参加状況が明らかになるよう記載する。
発言の状況については、どのような分野についてどのような観点で発言したか等、発言の概要を記載すれば足りる。
また、社外役員の意見により会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、重要でないものを除き、その内容を記載する。ただし、企業秘密に該当する事項を記載する必要はなく、社外役員の意見によって変更されたか否かが判然としない場合には、記載する必要はない。通常の場合は開示すべき事項はないと考えられる。
会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(社外監査役の場合は、不正な業務の執行)が行われた場合、重要でないものを除き、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を記載する。不当・不正な行為がなければ、開示すべきものはない。
(9)「社外役員の報酬等の総額」「親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は子会社からの役員報酬等の総額」
「社外役員の報酬等の総額」「親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は子会社からの役員報酬等の総額」(ひな型25頁、記載例3参照)については、通常の役員報酬の記載とは別に、社外役員全体の報酬等の総額を記載する。また、社外役員のうちに、親会社又は当該親会社の子会社(親会社が会社でない場合にはその子会社に相当するものを含む)の役員を兼ねている者がいる場合には、当該兼任者が親会社又は当該親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額のうち、当該事業年度において社外役員であった期間に受けたものを記載する。
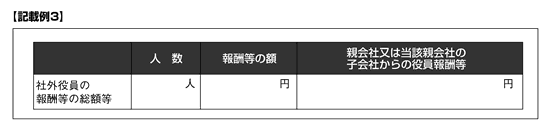
ただし、役員としての報酬等を記載すれば足り、社外役員が親会社又は当該親会社の子会社の使用人を兼ねている場合における使用人分給与を記載する必要はない。
各社外役員毎の内訳の記載はもとより、社外取締役と社外監査役が存する会社における、社外取締役と社外監査役との内訳の記載も義務付けられていない。
5.会計監査人に関する事項
(1)「当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項」
「当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項」(ひな型26頁参照)については、辞任した又は解任された会計監査人につき、次の事項を記載する。
① 氏名又は名称
② 監査役又は監査役会により会計監査人が解任されたときは、その旨及びその理由
③ 辞任又は解任について会計監査人から述べられた意見があったときは、その意見の内容
④ 辞任した者により辞任した理由が述べられるときは、その理由
ただし、会社役員と異なり、会計監査人の場合、当該事業年度中に辞任した者であれば、事業年度中の定時総会以前に辞任した又は解任されたものであっても、事業報告への記載の対象となる。
(2)「現在の業務停止処分に関する事項」
「現在の業務停止処分に関する事項」(ひな型26頁参照)については、会計監査人が現に業務停止期間中である場合に、当該業務停止処分の内容について記載する。この場合に対象となる業務停止の範囲は、監査業務に対する業務停止に限定されず、非監査業務等に対する業務停止も含まれる。
「現に」とは、事業報告の作成日を意味すると解される。
(3)「過去二年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項」
「過去二年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項」(ひな型26頁参照)については、会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合に、当該処分に係る事項のうち、事業報告作成会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項を記載する。記載の対象となる業務停止の範囲は、監査業務に対する業務停止に限定されず、非監査業務等に対する業務停止も含まれる。
「過去二年間」とは、「事業報告の作成日からさかのぼって二年間」を意味すると解される。
(4)「会計監査人の報酬等」
「会計監査人の報酬等」(ひな型26頁、記載例4参照)の関係では、以下の各事項について記載する(3・4は有価証券報告書提出大会社についてのみ)。
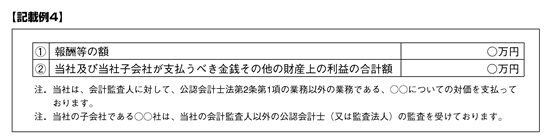
1.当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
2.会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
3.会計監査人である公認会計士又は監査法人に事業報告作成会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る)
4.事業報告作成会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人が当該事業報告作成会社の子会社(重要なものに限る)の計算関係書類(これに相当するものを含む)の監査(会社法又は証券取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む)の規定によるものに限る)をしているときは、その事実
なお、従来の営業報告書において求められていた、企業集団(事業報告作成会社及びその子会社)から受け取る財産上の利益を監査報酬とそれ以外に分けて記載することは、事業報告においては求められていない。
(5)「解任又は不再任の決定の方針」
「解任又は不再任の決定の方針」(ひな型27頁参照)については、会計監査人がどのような事態に陥った場合に、その解任又は不再任の議案を株主総会に提出するか等についての方針を定め、これを記載する。
何ら方針を定めていない場合は、その旨を記載する。
6.業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
業務の適正を確保するための体制(会社法348条3項4号、362条4項6号並びに416条1項1号ロ・ホに規定する体制)を定めている場合には、当該体制の整備に関する決定をすることが会社法上義務づけられているか否かにかかわらず、その内容の概要を記載する(ひな型27頁参照)。もちろん概要ではなく決定そのものを掲載した方が正確で分かりやすいと考えられる場合には、全文を掲載しても差し支えない。
なお、本項目についてはひな型に記載例を掲載していない。これは、本項目がすぐれて各社の実状に応じた創意工夫が求められるものであると考えられるからである。例えば、業態、規模等が全く異なる他社の体制を漫然と模倣したことが原因で、従業員の法令違反を招いた場合、しかるべき体制を構築していなかったものとして取締役の善管注意義務・忠実義務違反が問われるものと考えられる。また、単に決定して開示すれば済むものではなく、不断の見直し、充実、実践が求められる事項であることを念頭に置く必要がある。
7.株式会社の支配に関する基本方針
事業報告作成会社が当該事業報告作成会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めた場合には、①基本方針の内容、②基本方針の実現に資する取組みや不適切な者に支配されることを防止する取組み、③前記取組みが株主共同の利益を損なわない、役員の地位の維持を目的とするものではないとの取締役会の判断及び理由等を記載しなければならない(ひな型28頁参照)。これは、基本方針を定めている場合に限り記載が求められるものであり、そのような基本方針を定めていない場合は記載の必要はない。
なお、「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」とは、いわゆる買収防衛策のみを対象にしているわけではない。基本方針の内容については、特に規制はなく、定型のものがあるわけでもないため、各会社が基本方針として定めた内容をそのまま事業報告に記載すれば足りる。
Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)
会社法では、事業報告の附属明細書と計算書類の附属明細書は、別々のものとして定義された。実務上は、別々の書類として作成するのではなく、これまでどおり合冊して作成する方法もありうるが、会社法では、事業報告と計算書類とでその附属明細書を含め、監査主体が異なることが想定されている点に留意する必要がある。
事業報告の附属明細書には、「事業報告の内容を補足する重要な事項」のほか、公開会社においては、「会社役員の他の会社の業務執行者との兼務状況の明細」「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を記載する(ひな型30頁参照)。後者については、会社と、会社役員又は支配株主以外の第三者との間の取引(いわゆる間接取引)のうち、会社と会社役員又は支配株主との利益が相反するものにつき(例えば、会社役員の債務の保証を会社が行うこと)、重要でないものを除き、その明細を記載する。会社と、会社役員又は支配株主との直接取引は含まれない(計算書類における、取締役等に対する金銭債権、金銭債務それぞれの総額の注記(ひな型41頁参照)または関連当事者との取引に関する注記(ひな型44頁参照)の対象となる)。
なお、公開会社でない場合については、具体的な記載事項が定められていないが、附属明細書の作成を省略できる旨の規定は設けられておらず、「重要な事項が何ら存しない」との理由で附属明細書の作成義務を逃れることはできない。実質的にも、各社においておよそ「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないということは、通常、想定しにくいと解される。
(なかむら・まこと)
連載予定
第1回 基本方針、Ⅰ.事業報告(上)
第2回 事業報告(下)、Ⅱ.附属明細書(事業報告関係)
第3回 Ⅲ.計算書類(上)
第4回 計算書類(下)、Ⅳ.連結計算書類、Ⅴ.附属明細書(計算書類関係)、Ⅵ.決算公告要旨
第5回 Ⅶ.株主総会参考書類、Ⅷ.招集通知、Ⅸ.議決権行使書面
第6回 Ⅹ.監査報告
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























