コラム2007年06月11日 【編集部レポート】 インサイダー取引規制の認識は間違っていませんか?(2007年6月11日号・№214)
インサイダー取引規制の認識は間違っていませんか?
内部者取引管理アンケート調査結果が公表
text 編集部
東京証券取引所など、全国の証券取引所は5月31日、全国上場会社内部者取引管理アンケートの調査結果を公表した(対象は2月1日現在に上場する3,915社。このうち3,317社から回答を得た)。証券取引法の改正により、平成17年4月から課徴金制度が導入されて以来、上場会社の役職員による自社株売買等に絡むインサイダー取引が多発している(次頁表参照)。なかには、インサイダー取引とは意図せずに取引をしてしまった事例など、法的な知識の欠如によるものも見受けられている。このような状況を重くみた各証券取引所では、上場会社のインサイダー取引の未然防止体制を把握するとともに社内体制のセルフチェックを行う機会を提供する目的で、今回の調査結果をまとめたものだ。調査結果によると、情報管理体制の不備や認識の欠如といった問題が浮き彫りになっている。
子会社の解散等は重要事実に該当 調査結果によると、内部者取引管理規程を定めている上場会社は89.8%にのぼっているが、未だに規程を設けていない上場会社も5.2%(172社)あった。また、グループ会社の情報管理方法については、76.7%の上場会社が子会社情報も一元的に報告させ、企業グループをベースとした情報管理を行っているが、7.7%の上場会社は単体ベースでの情報管理を行っている結果がでている。連結対象会社がありながら単体ベースで情報管理を行っている上場会社については、連結対象会社の規模や社数がグループ全体に与える影響が少ないためといった理由を挙げているが、子会社の解散、破産手続の開始、更生手続開始の申立てなどについては、内部者取引規制上、軽微基準がなく、子会社の規模に関係なく重要事実に該当する可能性があると調査報告では指摘している。このため、連結ベースでの情報管理体制が必要であるとしている。
取締役会決議前でも重要事実に該当するケースが 重要事実となる情報を管理するタイミングとしては、取締役会等の機関決定をもって管理を開始すると回答した上場会社が40.0%と最も多かった。しかし、平成11年6月10日の最高裁判決(日本織物加工事件)では、取締役会等の正式な機関決定を経ていない状況であっても、実質的に会社の意思決定と同視されるものであれば、すでに重要事実に該当していると解されている。たとえば、大塚家具のケースでは、配当予想値の修正についての取締役会で正式に決議していなかったため、自己株式の取得を行ったが、証券取引等監視委員会では、取締役会決議の前でも重要事実に該当するとして、課徴金の納付命令を行っている。
このため、上場会社においては、経営会議、部長会、プロジェクトチーム等の社内の実質的な業務執行機関での決定段階でも重要事実に該当することがあるため、早期の情報管理が必要であると調査報告では指摘している。
役職員への啓蒙活動が必要 役職員の自社株売買の管理については、上場会社が事前に売買の可否を判断する「許可型」(74.2%)、役職員にセルフチェックを働きかける「届出型」(16.0%)、個人の自己責任に委ねる「自己リスク型」(8.5%)が挙げられ、対象範囲は全役職員としている上場会社が72.9%を占めた。いずれにせよ、法令違反を回避するためには、役職員に対する社内研修等の啓蒙活動や上場会社の規模にあった仕組みを構築することが必要になりそうだ。
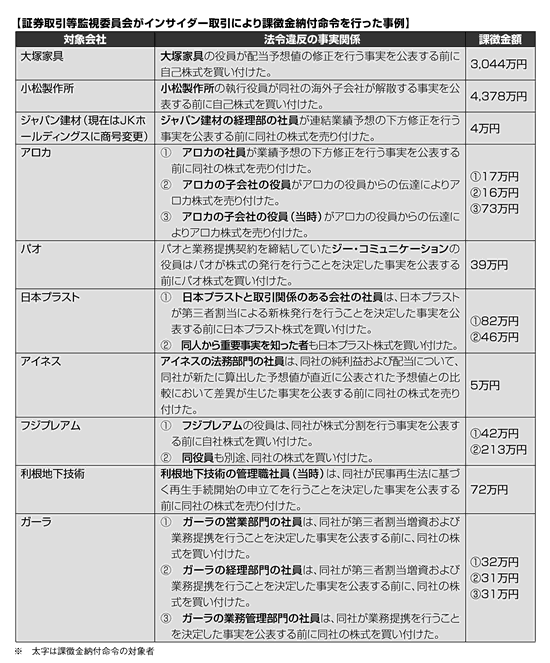
内部者取引管理アンケート調査結果が公表
text 編集部
東京証券取引所など、全国の証券取引所は5月31日、全国上場会社内部者取引管理アンケートの調査結果を公表した(対象は2月1日現在に上場する3,915社。このうち3,317社から回答を得た)。証券取引法の改正により、平成17年4月から課徴金制度が導入されて以来、上場会社の役職員による自社株売買等に絡むインサイダー取引が多発している(次頁表参照)。なかには、インサイダー取引とは意図せずに取引をしてしまった事例など、法的な知識の欠如によるものも見受けられている。このような状況を重くみた各証券取引所では、上場会社のインサイダー取引の未然防止体制を把握するとともに社内体制のセルフチェックを行う機会を提供する目的で、今回の調査結果をまとめたものだ。調査結果によると、情報管理体制の不備や認識の欠如といった問題が浮き彫りになっている。
子会社の解散等は重要事実に該当 調査結果によると、内部者取引管理規程を定めている上場会社は89.8%にのぼっているが、未だに規程を設けていない上場会社も5.2%(172社)あった。また、グループ会社の情報管理方法については、76.7%の上場会社が子会社情報も一元的に報告させ、企業グループをベースとした情報管理を行っているが、7.7%の上場会社は単体ベースでの情報管理を行っている結果がでている。連結対象会社がありながら単体ベースで情報管理を行っている上場会社については、連結対象会社の規模や社数がグループ全体に与える影響が少ないためといった理由を挙げているが、子会社の解散、破産手続の開始、更生手続開始の申立てなどについては、内部者取引規制上、軽微基準がなく、子会社の規模に関係なく重要事実に該当する可能性があると調査報告では指摘している。このため、連結ベースでの情報管理体制が必要であるとしている。
取締役会決議前でも重要事実に該当するケースが 重要事実となる情報を管理するタイミングとしては、取締役会等の機関決定をもって管理を開始すると回答した上場会社が40.0%と最も多かった。しかし、平成11年6月10日の最高裁判決(日本織物加工事件)では、取締役会等の正式な機関決定を経ていない状況であっても、実質的に会社の意思決定と同視されるものであれば、すでに重要事実に該当していると解されている。たとえば、大塚家具のケースでは、配当予想値の修正についての取締役会で正式に決議していなかったため、自己株式の取得を行ったが、証券取引等監視委員会では、取締役会決議の前でも重要事実に該当するとして、課徴金の納付命令を行っている。
このため、上場会社においては、経営会議、部長会、プロジェクトチーム等の社内の実質的な業務執行機関での決定段階でも重要事実に該当することがあるため、早期の情報管理が必要であると調査報告では指摘している。
役職員への啓蒙活動が必要 役職員の自社株売買の管理については、上場会社が事前に売買の可否を判断する「許可型」(74.2%)、役職員にセルフチェックを働きかける「届出型」(16.0%)、個人の自己責任に委ねる「自己リスク型」(8.5%)が挙げられ、対象範囲は全役職員としている上場会社が72.9%を占めた。いずれにせよ、法令違反を回避するためには、役職員に対する社内研修等の啓蒙活動や上場会社の規模にあった仕組みを構築することが必要になりそうだ。
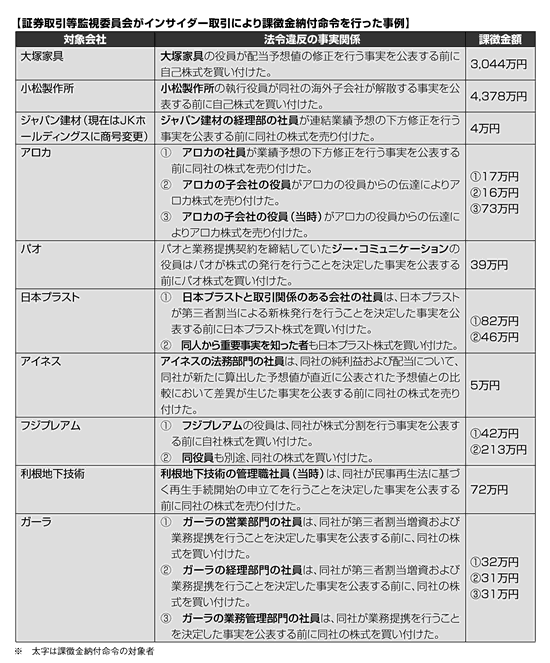
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















