コラム2007年08月06日 【SCOPE】 財務諸表監査意見と内部統制監査意見が違う!?(2007年8月6日号・№222)
投資家の混乱必至!
財務諸表監査意見と内部統制監査意見が違う!?
財務報告に係る内部統制報告書の作成および監査が平成20年4月から導入される。監査上の取扱いについては、日本公認会計士協会が7月18日に監査・保証実務委員会「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」(公開草案)を公表している(本誌221号4頁参照)。内部統制監査が導入されることによって懸念されるのが、財務諸表監査と内部統制監査の意見表明が異なる場合だ。意見表明が異なることになれば、市場に混乱を招きかねない。今回のスコープでは、果たして財務諸表監査と内部統制監査の意見表明が異なるケースがあるのか否かを検討する。
両者の監査意見が大きく異なることは想定しにくいが…… 内部統制監査報告書については、原則として、財務諸表監査における監査報告書と合わせて記載することとされており、日本公認会計士協会の公開草案では、6つのケースの内部統制監査報告書の文例が示されている(下表参照)。
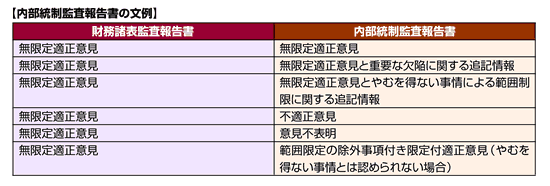
たとえば、内部統制監査において、内部統制の評価範囲、評価手続、評価結果についての経営者が行った記載に不適切なものがあり、内部統制監査報告書で無限定適正意見を表明することができない場合で、その影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示に当たるほどには重要でないと判断したときは、除外事項を付した限定付適正意見を表明することになるとされており、実務上は想定される(下表の6番目のケース)。
内部統制監査が意見不表明というケース しかし、財務諸表監査が無限定適正意見で内部統制監査が不適正意見あるいは意見不表明になるといった両者で意見表明が大きく異なるパターンは想定しにくい。内部統制監査は、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、監査計画の立案、監査証拠の入手、意見表明まで、財務諸表監査と一体となって実施されることになるからだ。
とはいっても、実務上、最も可能性のある意見表明は下表の4番目の財務諸表監査では無限定適正意見だが、内部統制監査意見では意見不表明になるケースだ。日本公認会計士協会でも現実的にあり得るとしている。
「やむを得ない事情」の場合は内部統制監査から除外するが…… 内部統制に関しては、経営者が行った評価手続に関して有効かどうかを監査人が監査することになる。しかし、経営者が「やむを得ない事情」により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった部分があれば、それを除外して内部統制が有効か否かを監査人が判断することになる。
この「やむを得ない事情」とは、日本公認会計士協会の公開草案によると、期末日直前に大型の合併等を行った場合や大規模な地震などの災害が発生した場合などが該当するとされている(下記参照)。
これらについては、期限内に内部統制評価基準に準拠した評価手続を行うことが時間的に無理だからだ。
なお、内部統制評価の責任を有する役職者や担当者の突然の異動・退職や内部統制評価の基礎となる重要な文書の不注意による滅失等、企業側に責任のある場合などについては「やむを得ない事情」には該当しないので留意したい点だ。
問題は金額的な影響が大きい場合 ただ、問題は、仮に「やむを得ない事情」に該当したとしても、財務諸表に対する金額的な影響が大きい場合には、内部統制監査の意見を表明してはならないとされている点である。
このため、財務諸表監査の意見と内部統制監査の意見が大きく異なるといった現象が生じる可能性があるわけだ。
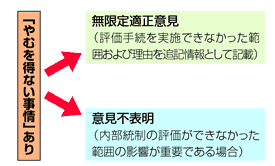
意見不表明でも即上場廃止になるわけではないが…… このようなケースでは投資家もどのように監査意見を読めばよいのか判断に迷うこともありそうだ。
東京証券取引所が4月24日に公表した上場制度総合整備プログラム2007によれば、「上場会社について、内部統制における重要な欠陥が直ちに財務諸表の虚偽記載に結びつくものではないことを踏まえ、内部統制報告書及びこれに係る監査報告書の記載内容をもって、上場廃止することは行わないものとする」という方針が示されている。これは、財務報告に係る内部統制上の問題が直ちに財務諸表自体の信頼性を毀損するものではないとの趣旨によるものだ。
このため、仮に「やむを得ない事情」による意見不表明がされたとしても、即上場廃止になるわけではない。しかし、今後、監査意見が異なることによる市場の混乱を招かないような対策が必要になってきそうだ。
やむを得ない事情に該当するケース ・期末日直前に他企業を買収または合併し、被合併会社や被買収会社の規模や事業の複雑性を考慮すると、内部統制評価には相当の準備期間が必要であり、当該年度の決算が取締役会の承認を受けるまでの期間に評価が完了しないことに合理性がある場合
・大規模なシステム変更
・大規模な地震や風水害などの災害が発生した場合
・クーデター等の政情不安により企業活動に支障をきたしている場合
財務諸表監査意見と内部統制監査意見が違う!?
財務報告に係る内部統制報告書の作成および監査が平成20年4月から導入される。監査上の取扱いについては、日本公認会計士協会が7月18日に監査・保証実務委員会「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」(公開草案)を公表している(本誌221号4頁参照)。内部統制監査が導入されることによって懸念されるのが、財務諸表監査と内部統制監査の意見表明が異なる場合だ。意見表明が異なることになれば、市場に混乱を招きかねない。今回のスコープでは、果たして財務諸表監査と内部統制監査の意見表明が異なるケースがあるのか否かを検討する。
両者の監査意見が大きく異なることは想定しにくいが…… 内部統制監査報告書については、原則として、財務諸表監査における監査報告書と合わせて記載することとされており、日本公認会計士協会の公開草案では、6つのケースの内部統制監査報告書の文例が示されている(下表参照)。
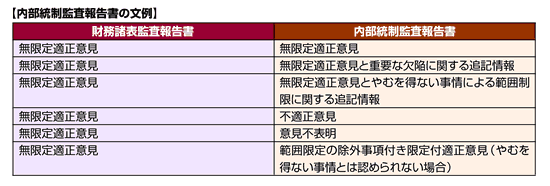
たとえば、内部統制監査において、内部統制の評価範囲、評価手続、評価結果についての経営者が行った記載に不適切なものがあり、内部統制監査報告書で無限定適正意見を表明することができない場合で、その影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示に当たるほどには重要でないと判断したときは、除外事項を付した限定付適正意見を表明することになるとされており、実務上は想定される(下表の6番目のケース)。
内部統制監査が意見不表明というケース しかし、財務諸表監査が無限定適正意見で内部統制監査が不適正意見あるいは意見不表明になるといった両者で意見表明が大きく異なるパターンは想定しにくい。内部統制監査は、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、監査計画の立案、監査証拠の入手、意見表明まで、財務諸表監査と一体となって実施されることになるからだ。
とはいっても、実務上、最も可能性のある意見表明は下表の4番目の財務諸表監査では無限定適正意見だが、内部統制監査意見では意見不表明になるケースだ。日本公認会計士協会でも現実的にあり得るとしている。
「やむを得ない事情」の場合は内部統制監査から除外するが…… 内部統制に関しては、経営者が行った評価手続に関して有効かどうかを監査人が監査することになる。しかし、経営者が「やむを得ない事情」により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった部分があれば、それを除外して内部統制が有効か否かを監査人が判断することになる。
この「やむを得ない事情」とは、日本公認会計士協会の公開草案によると、期末日直前に大型の合併等を行った場合や大規模な地震などの災害が発生した場合などが該当するとされている(下記参照)。
これらについては、期限内に内部統制評価基準に準拠した評価手続を行うことが時間的に無理だからだ。
なお、内部統制評価の責任を有する役職者や担当者の突然の異動・退職や内部統制評価の基礎となる重要な文書の不注意による滅失等、企業側に責任のある場合などについては「やむを得ない事情」には該当しないので留意したい点だ。
問題は金額的な影響が大きい場合 ただ、問題は、仮に「やむを得ない事情」に該当したとしても、財務諸表に対する金額的な影響が大きい場合には、内部統制監査の意見を表明してはならないとされている点である。
このため、財務諸表監査の意見と内部統制監査の意見が大きく異なるといった現象が生じる可能性があるわけだ。
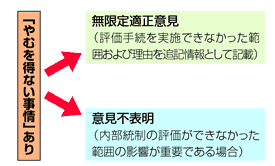
意見不表明でも即上場廃止になるわけではないが…… このようなケースでは投資家もどのように監査意見を読めばよいのか判断に迷うこともありそうだ。
東京証券取引所が4月24日に公表した上場制度総合整備プログラム2007によれば、「上場会社について、内部統制における重要な欠陥が直ちに財務諸表の虚偽記載に結びつくものではないことを踏まえ、内部統制報告書及びこれに係る監査報告書の記載内容をもって、上場廃止することは行わないものとする」という方針が示されている。これは、財務報告に係る内部統制上の問題が直ちに財務諸表自体の信頼性を毀損するものではないとの趣旨によるものだ。
このため、仮に「やむを得ない事情」による意見不表明がされたとしても、即上場廃止になるわけではない。しかし、今後、監査意見が異なることによる市場の混乱を招かないような対策が必要になってきそうだ。
やむを得ない事情に該当するケース ・期末日直前に他企業を買収または合併し、被合併会社や被買収会社の規模や事業の複雑性を考慮すると、内部統制評価には相当の準備期間が必要であり、当該年度の決算が取締役会の承認を受けるまでの期間に評価が完了しないことに合理性がある場合
・大規模なシステム変更
・大規模な地震や風水害などの災害が発生した場合
・クーデター等の政情不安により企業活動に支障をきたしている場合
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















