解説記事2007年10月01日 【最新判決研究】 国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定-武富士事件-(2007年10月1日号・№229)
最新判決研究
国外財産を贈与した場合における受贈者の「住所」の認定-武富士事件-
品川芳宣
早稲田大学大学院客員教授(専任)
筑波大学名誉教授
東京地裁平成17年(行ウ)第396号 平成19年5月23日判決
一、事実
(1)X(原告)は、父甲(平成18年8月10日死亡)及び母乙から、平成11年12月27日付の株式譲渡証書(以下「本件贈与契約書」という。)により、オランダの有限責任非公開会社であるYST社の出資口数720口(甲から560口、乙から160口、以下「本件出資」という。)を取得した(以下「本件贈与」という。)。なお、本件贈与前におけるYST社の出資総数は、800口で、甲が560口、乙が240口それぞれ所有していた。
Xは、本件贈与時には日本国内に住所を有せず、かつ、本件出資が日本国内にある財産ではない(国外財産)ということで、贈与税の申告をしていなかった。
(2)これに対し、Y税務署長は、本件贈与について、平成17年3月2日付で、Xに対し、贈与税の課税価格を1653億0603万円余、納付すべき贈与税額を1157億0290万円余とする平成11年分贈与税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の額を173億5543万円余とする賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)をした。
なお、Y税務署長は、本件出資の価額につき、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)5の定めにより、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとし、YST社の資産総額に占める株式及び出資の価額の合計額の割合が84.2%であることから、評価通達189に定める株式保有特定会社と同様に、評価通達185に定める純資産価額方式により評価することとした。
Xは、本件決定及び本件賦課決定を不服として、不服申立ての前置を経て、国(被告)に対し、本件取消請求訴訟を提起した。
二、争点と当事者の主張
1 争 点
本件贈与日(平成11年12月27日)において、Xが日本国内に住所を有していたか否か。
2 国の主張
(1)受贈者の住所がどこにあるのかは、単に住民票の記載事項により判断するのではなく、いずれが受贈者の「生活の本拠」に該当するかを、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等の客観的事実に加え、本人の居住意思・目的も考慮して、総合的に判断することとなるが、定住の意思は必ずしも常に存在するものではなく、外部から認識し難い場合が多いため、本人の主観的な意思はあくまでもその判断のための一資料として考慮するにとどまるべきである。相続税法基本通達(以下「基本通達」という。)において、相続税法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠であり、生活の本拠であるか否かは客観的事実によって判定する旨規定されているが、これは、民法上の生活の本拠についての客観説を採ることを明らかにしたにすぎず、居住者の主観面を考慮することを排除するものではない。
そして、各法域においてその目的に応じた固有の住所が存在すると解されるのであるから、贈与税に関する住所の認定に当たっても、贈与税が、贈与によって財産が移転する機会に、その財産に対して課税される租税であって、相続税の補完税としての性質を持ち、相続税のみが課税されるとした場合には、生前に財産を贈与することによって、相続税の負担を容易に回避することができることになるため、このような税負担の回避を封ずることを目的としていることが考慮されてしかるべきである。
この点について、相続税が、相続による財産の取得というかなり長期の間の偶然の一時的における事象をとらえて課税されるものであることを考えると、たまたま一時的な居住地によって課税対象財産の範囲を異にすることには問題があり、一定期間外国における勤務や外国における事業活動のため永住許可を得て外国に居住するなどの事実があっても、外国における勤務等が終わった後は日本に帰る予定である者、又は外国における勤務中も日本において家庭を持ち、社会的に定住していると認められるような者の住所は、日本にあるものとして扱われるべきであろうとされていることが参考になる。
(2)国が、本件で問題とされている平成9年6月29日(以下「日本出国日」という。)から平成12年12月17日(以下「香港出国日」という。)までの期間(以下「本件滞在期間」という。)について、Xに対し、所得税の課税処分を行わなかったことは、国がXの所得税法上の住所が国外にあったと認定したことを意味するものではない。のみならず、所得税は、年・月などをもって定期に課される期間税であるのに対し、贈与税は、課税物件が随時に生じる随時税であること、所得税は一般に暦年の終了の時に納税義務が成立するのに対し、贈与税は贈与による財産の取得の時に納税義務が成立することなど、租税としての性質や課税体系を異にするから、所得税における住所と贈与税における住所は必ずしも同一ではない。
(3)甲は、平成11年ころ、T社の将来を長男のXに委ねたいと考え、贈与者らのYST社に対する出資持分をXに贈与することとした。本件贈与の実行に至るまでには、甲及びその関係者らの間で、事前に贈与税の課税を回避するための綿密な協議が行われ、甲は、贈与税回避のためのスキームに従って、香港に渡航したものである。
もともと、甲及び乙が所有していた国内財産であるT社株式は、フランス及びオランダにおいて、極めて短期間に法人の設立や買収・増資、さらには金融機関から1000億円もの多額の借入を行うなどの様々な手法を駆使することにより、外形上、YST社の出資持分という国外財産に転換された。受贈者の国外住所化については、受贈者の滞在先として贈与税の負担のない香港を選択し、T社が2つの香港の会社を実質的に買収しXを代表者に就任させ、同人に香港居住の必要があるかのような外観を作出したほか、贈与後はXが日本に帰国することを控えるなど、甲ら及びXは、諸外国の税制を十分に研究して甲ら及びXの税負担が最小になるようにした上で、課税庁による調査が行われる可能性も念頭に置きつつ、周到な準備を行い計画的に本件贈与を実行したものである。Xが、このように贈与税を回避する目的で、香港に住所を移転したとの外形を作出するために香港に渡航したことは、もともと相続税回避を目的とする贈与税における「住所」の認定において、十分考慮されなければならない。
(4)Xは、昭和57年12月18日に、甲、乙及び実弟丙など家族とともに、杉並区内の自宅(以下「本件杉並自宅」という。)に異動しており、このころから、Xの生活の本拠は、本件杉並自宅であった。なお、Xの住民登録は、平成9年7月10日に香港に移転しているものの、平成15年1月1日には、再び本件杉並自宅に戻っている。
Xの本件滞在期間中の日本滞在日数と香港滞在日数は、香港滞在日数の割合が65.8%ではあるものの、日本滞在日数の割合が26.2%であり、本件滞在期間の間、4日に1日以上も本件杉並自宅に起居していることからも、生活の本拠が本件杉並自宅から移転していないことは明らかである。
また、本件滞在期間中、Xは、ヨーロッパ又は北米に9回渡航している。香港からヨーロッパ又は北米の主要都市に直行便があるにもかかわらず、Xは、そのうち7回はいったん東京に行ってから、ヨーロッパ又は北米に渡航しており、このことからもXの生活の本拠が本件杉並自宅であることが分かる。
Xが頻繁に帰国している事実からだけでも、Xの生活の本拠が香港に移転したとまで認定することができないというべきであり、換言すれば、Xは、日本と香港の間を何度も行き来していたにすぎない。そして、Xは、平成12年12月に失踪し、約3年間その所在も不明であった(なお、Xは、平成15年12月21日にT社に復帰している。)。
(5)T社は、香港に投資会社としてTTS社及びCH社(以下「本件香港各社」という。)を設立し、所要の費用を負担している。そして、Xは、本件香港各社の役員を務めていた。しかしながら、本件各社が然したる業績を挙げてきたわけではなく、X自身も、ベンチャーキャピタリストとしての能力があったわけでもなく、Xが平成15年にT社に復帰した際も、香港での経験が生かされたわけでもない。いずれにしても、本件香港各社の設立やXの香港滞在は、本件贈与を含む一連の行為が完了するまでの一時的なものに過ぎない。
3 Xの主張
(1)最高裁判所大法廷昭和29年10月20日判決・民集8巻10号1907頁(以下「最高裁昭和29年10月20日判決」という。)は、「およそ法令において、人の住所につき、法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのを相当とする」と明言しているが、同判決により、以下が導かれる。
① 相続税法1条の2第1項の住所は、民法21条の定める住所の意義と同様、各人の生活の本拠を指すと解される。
② 納税者個人の「生活の本拠」とは、あくまで、納税者個人の「職業の」本拠ではなく、納税者個人の「生活の」本拠であり、個人が日々生きている生活圏内の中心を意味する。就業しているか否かを問わず、すべての納税者につき住所の認定のために一律に用いられる「生活の本拠」の意義は、納税者の仕事の内容、勤務の実態に関する諸要素により左右されるべきものではあり得ない。すなわち、納税者の生活の本拠とは、通常は、納税者が、人間として、毎日、生活を営んでいる中心たる場所(通常は自宅)である。
③ 個人の生活の本拠は、主観的要素を排して、客観的事実によって認定される。基本通達1・1の2共-5も、「『住所』とは、各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。」と明定している。
(2)本件滞在期間中のXの香港での生活ぶりを概述すると、次のとおりであるから、本件贈与時のXの住所は、香港である。
① Xは、本件滞在期間中、本件香港自宅を自宅とし、同自宅で就寝、起床して朝食をとり、日中は、平日(通常午前9時から午後9時まで)及び土曜日(通常午前9時から午後6時まで)は、本件香港各会社のオフィス(ただし、平成11年1月以降。平成9年6月から平成10年12月までは、本件香港自宅の一部をオフィスとして使用していた。)に出社して、両社の代表取締役として執務し、日曜日は、自宅ですごしたり、レストラン、劇場等で友人・知人らと交際していた。
② Xは、現在まで独身である。Xは、例えば、平成11年度には、GH社から毎月8万1090~8万4600香港ドル(113万5260円ないし118万4400円相当)の給与、TTS社から毎月9010ないし9400香港ドル(12万6140円ないし13万1600円)の給与を受領しており、本件贈与時において、甲及び乙と生計を一にしているわけではない。
③ 本件滞在期間中のXの香港滞在日数は、国の主張によれば、1286日中834日(65.8%)である。そして、Xは、本件贈与日を含む課税年度につき、本件香港自宅を自宅と考えて、香港政庁に所得税を納税し、日本で所得税、地方税等を納税していない。国は、この事実について、何らとがめ立てしていない。
④ 本件香港各社は、日常的に、秘書、社員を雇用していた。このほか、両社の決算報告書の数字は、本件香港各会社が休眠会社ではなく、その常勤の代表取締役であるXも、香港で活動していたことを証明する。
(3)住所、すなわち生活の本拠は、客観的事実により判定されるべきであって、Xが租税回避の目的を有していたか否かという主観的事実は、そもそも論点ですらない。仮に、Xに贈与税の課税負担を減少させたい意思があったとしても、本件贈与のスキームによる当該意思は、単に一般に紹介され多くの資産家によって利用されていた節税行為、すなわち適法行為の意思にすぎないのであるから、租税法上非難されるべきいわれは皆無であるし、当該動機は、本件贈与日当時、Xが本件香港自宅を生活の本拠たる住所にするという居住意思があったことを裏付けるにすぎない。
三、判決要旨
請求認容(本件決定及び本件賦課決定取消)
1 認定事実
前記事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)T社は、平成8年5月、投資会社であるJ社と共同でYST投資事業組合を結成し、T社が10億円、J社が1億円をそれぞれ出資し、J社が業務執行組合員となり、国内でのベンチャー投資を始めた。同事業組合は、平成8年12月末時点で、25社に対し、4億5900万円の投資をした。
T社は、平成8年12月、J社と共同でYST2号投資事業組合を結成し、T社が28億円、J社が12億円をそれぞれ出資した。
(2)Xは、昭和40年7月9日に出生し、昭和57年12月、甲らとともに、本件杉並自宅に転居した。本件杉並自宅は、D社が所有し甲が賃借していたが、鉄筋コンクリート地下1階付2階建ての延べ床面積1999.37m2の建物で、そのうち約42m2がX個人の専用居室となっている。本件杉並自宅には、昭和57年12月以降、甲(死亡時まで)、乙及び丙(現在まで)が引き続き居住している。
Xは、昭和59年3月に都内の高校を卒業後、平成元年2月、留学のため渡米し、複数の大学で学んだ後平成6年12月に帰国した。Xは、平成5年11月30日、甲からT社の株式1001万200株の贈与を受けているところ、この贈与に係るXの贈与税の課税価格は209億6512万円余、贈与税額は146億6426万円余であった。
Xは、平成7年1月にT社に入社し、同社の都内支店の勤務を経た後、同年5月にTB支店長を経て、平成8年6月にはT社の取締役営業統轄本部長に就任し、各営業店の巡回指導やIR活動を担当した。Xは、平成9年3、4月ころ、甲が、J社のI会長とともに、投資の受入れを希望しているベンチャー起業家と面談する会議に立ち会ったことがあった。
(3)平成11年当時の相続税法のもとにおいては、贈与者が所有する財産を国外へ移転し、さらに受贈者の住所を国外に移転させた後に贈与を実行することによって、我が国の贈与税の負担を回避し、又は、いずれの国の贈与税の負担も免れるという方法が、節税方法として一般に紹介されていた。香港では、贈与税は課されていない。
甲は、平成9年2月ころ、甲と親密な関係にあったWの紹介で、M弁護士から、上記の贈与税回避手法の一般的な説明を受けた。
T社は、平成9年5月20日に開催された取締役会において、海外での事業展開を図るため、香港に海外事業統括子会社を設立することなどを決議した。その後、T社は、同年7月8日に開催された取締役会において、アジアを中心とした海外でのファイナンス業務及びベンチャーキャピタル業務の展開のための情報収集、調査、提携案件の検討並びに現地法人設立に向けた具体的な検討及び準備のため、香港駐在役員としてXを選任し、6月29日付けでXが香港に着任することを承認した。
(4)本件滞在期間中に占める香港滞在日数の割合は65.8%、日本滞在日数の割合は26.2%である。本件滞在期間中、Xは、欧州又は北米に9回渡航しているが、このうち7回はいったん東京(成田)を経由してから、欧州又は北米に渡航している。
(5)Xは、香港において、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、食器などの家財が備え付けられ、部屋の清掃やタオル、シーツの交換などホテルと同様のサービスが受けられるサービスアパートメント(本件香港居宅)に滞在することになっていたため、Xが日本出国時に香港へ携帯したのは衣類程度であった。本件香港居宅の賃貸借契約の内容は、当初、賃貸期間が平成9年7月1日から平成11年6月30日までの24か月間、賃貸料が月額7万6000香港ドル(約113万円余)、保証金が22万8000香港ドルであった。平成11年7月29日に更改された契約では、賃貸期間が平成11年7月1日から平成13年6月30日までの24か月間、賃借料が月額5万3500香港ドル(約77万円余)、保証金が16万0500香港ドルとされた。同契約は、平成11年11月30日に、借主がXからTTS社に変更された。
Xは、本件滞在期間中、月に一度は日本に帰国していたが、その際は、家族とともに、本件杉並自宅で起居していた。
(6)T社は、平成9年8月5日、消費者金融業及びベンチャーキャピタル業を営むことを目的として香港でTTS社を設立することを決議し、同年9月、TTS社の株式を買い取り、X、I・J社会長、T社海外事業部長Kがその取締役に就任した。TTS社は、3億円の増資を行い、うち2億円をT社が引き受け、1億円はJ香港社が引き受けた。
平成9年11月1日、TTS社は、T社、J香港社とともに、YST国際投資事業組合を結成した。同ファンドは、T社が10億円、TTS社が1億円、J香港社が1億円をそれぞれ出資し、主として香港、台湾その他アジア地域へのベンチャー投資を行うことを目的としていた。同ファンドは、TTS社及びJ香港社が共同業務執行組合員となり、管理報酬として、出資金総額に対してJ香港社が年率2%、TTS社が同1%を、成功報酬として、投資純益のそれぞれ10%を取得できることとされていた。
平成9年9月から平成10年12月までのTTS社の事業は、①消費者金融を含む金融業、②ベンチャーキャピタル、③上記に係る情報収集、調査、検討及び交渉、④T社の将来の海外でのファイナンス事業に係る情報収集、調査、評価並びに進出形態、進出に係る契約等の助言、⑤海外金融機関に対するT社の会社説明の代行、とされていた。
平成10年10月当時、TTS社の事務所は、J社香港社の事務所の一部を借りており、電話は設置されたものの、電話番号簿への登録はなく、ファクシミリはJ社香港社のものを使用していた。TTS社は、現地の商工会議所には加盟しておらず、常勤の役員はX1名であり、Xが現地での業務を執行しているほか従業員はおらず、会計帳簿・稟議書等はT社本社において作成されており、株主総会、取締役会は決議書を役員間で回付する方法により実施されている状況であった。
また、Xが、TTS社の事務所を訪れたのは、月2、3回程度であった。
(7)T社は、平成10年12月8日、TTS社をJ社との共同事業の運営拠点として存続させつつ、新たに全額出資子会社を設立し、ベンチャービジネスへの投資、M&A等今後の投資は新会社を中心に行っていく旨の取締役会決議をした上、香港に本店を置く休眠会社を1000香港ドルで買い取り、社名をGHインベストメント(GH社)に変更した上、30億円の増資を行い、T社が30億円と999香港ドル、Xが1香港ドル相当の株式を所有することとした。Xは、平成11年1月5日、同社の取締役に就任した。
これに伴い、香港各会社は、新たに借りた事務所と現地採用秘書を共同使用するとともに、個別に電話回線を設置することになった。現地採用秘書は、香港各会社の経費支出を逐一T社本社に報告しており、香港各会社の帳簿類は、T社で作成していた。
(8)本件香港各会社の経営状況は、次のとおりである。
① TTS社
設立日から平成10年12月末まで
当期純損失 286万余香港ドル
平成11年12月期
当期純利益 110万余香港ドル
平成12年12月期
当期純利益 54万香港ドル
② GH社
設立日から平成11年12月末まで
当期純損失 845万余香港ドル
平成12年12月期
当期純損失 5939万余香港ドル
(9)Xが香港における滞在に関連して、得意先との面談、接待、契約ないしIR活動を行った日は、平成9年10月から同12年5月までの間、延べ168日である。
また、Xは、本件滞在期間中も、月1回の割合で開催されるT社の取締役会の多くに出席しているが、報告内容の多くは、海外投資活動やT社の海外IR等の海外事業についてのものであり、それ以外の事項については、抽象的、精神論的な意見の表明がほとんどであった。
Xは、本件香港各会社から役員報酬として、平成10年には108万余香港ドル、平成11年には110万余香港ドルを受け取った。他方、Xは、本件滞在期間中、T社から、149万円余(平成11年3月期)、180万円(平成12年3月期)の役員報酬を受け取った。Xが本件香港各社及びT社から受領した役員報酬の合計額は、同時期のT社の常務取締役のうち最も報酬の高い者と近い額となっている。
なお、平成12年12月、Xが香港を出国後、TTS社等は事実上休業状態になり、TTS社株式もT社に譲渡された。
(10)平成10年の後半又は平成11年の年頭のころ、W公認会計士は、甲に面会し、以後数回にわたり、相続税・贈与税、事業承継等をテーマに税務に関するレクチャーをし、平成11年10月ころには、本件贈与の実行に関する具体的な提案をし、そのころ、Xに対しても同様の説明をした。同年12月、W公認会計士は、政府税制調査会が相続税法の納税義務者に関する規定について改正を検討しているとの情報を得て、甲に対して、同年内の本件贈与の実行を進言し、贈与を実行した場合には、Xが1年以上海外にいるようにすることなどを説明し、Xに対しても、同年内に贈与を実行する必要があることを説明した。
2 検 討
(1)住所について
法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をすべき特段の事由のない限り、住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当であり(最高裁昭和29年10月20日判決参照)、生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである(最高裁判所第三小法廷昭和35年3月22日・民集14巻4号551頁参照)。そして、一定の場所がある者の住所であるか否かは、租税法が多数人を相手方として課税を行う関係上、客観的な表象に着目して画一的に規律せざるを得ないところからして、一般的には、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定するのが相当である。これに対し、主観的な居住意思は、通常、客観的な居住の事実に具体化されているであろうから、住所の判定に無関係であるとはいえないが、かかる居住意思は必ずしも常に存在するものではなく、外部から認識し難い場合が多いため、補充的な考慮要素にとどまるものと解される。
国は、相続税の性質や課税体系の点から、外国における勤務等が終わった後に日本に帰る予定である者の住所は日本にあるものとすべきであると解しうる見解を紹介している。しかしながら、かかる見解によれば、例えば、我が国における居宅を引き払って、数年間外国に勤務し、その間に我が国に帰国せず、日本国内に生活拠点を保持しなかった場合であっても、将来日本に帰る予定があれば、国内に住所を有することになるが、このような場合にまで「住所」が国内にあるというのは、「住所」の日本語としての通常の意味内容からかけ離れるものといわざるを得ないし、国が自ら定めた基本通達1・1の2共-6にも反するものであって、上記見解は採用し難い。
(2)Xの住居について
Xは、本件滞在期間中の全日数のうち、26.2%に相当する日数は日本に滞在し、その間は本件滞在期間前の住所である本件杉並自宅に起居していたところ、Xが日本出国日に香港へ携帯したのは衣類程度であったのであるから、本件杉並自宅は従前と同様、Xの住居として使用することができる状態にあったと考えられる。
他方、Xは、本件滞在期間中、その65%余りの日数を香港で過ごし、その間は専ら本件香港自宅で起臥寝食していたものである。そして、本件香港自宅は、ホテルと同様のサービスが受けられるサービスアパートメントであるが、当初の契約では、賃貸期間を24か月とし、賃料3か月分の保証金を賃貸人に差し入れることとされており、さらに当初の賃貸期間満了時には、賃貸期間をさらに24か月延長して契約が更新されていることからみて、本件香港自宅は相当期間使用されることが予定されていたというべきであって、Xの香港滞在が一時的なものであったことを裏付けるものとはいえない。また、本件香港自宅が高額な家賃であったり、生活諸道具を持ち込んでいないことをもって、前記認定を左右するものではない。
以上によれば、本件杉並自宅と本件香港自宅は、いずれも生活の本拠としての住居たりえるものであるといえ、住居の点からXの住所が国内にあったとすることはできない。
(3)Xの職業等について
本件の事実によれば、Xの職業に着眼しても、本件滞在期間中のXの職業活動は、海外、とりわけ香港を中心としたものというべきであって、生活の本拠が国内にあったことを裏付ける要素は乏しいといわざるを得ない。国は、Xの香港における活動は、実体の伴わないものであって、香港における居住事実を作出するための作為的なものにすぎないと主張するのであるが、Xの本件滞在期間中の活動が香港を中心としたものであったことは既に詳細に認定したとおりである。そして、Xの活動が、一人前のベンチャーキャピタリストとしてのそれであるとの評価に値するものであったかどうかには疑問の余地があり、むしろ、研修ないし武者修行としての色彩があることは否定し難いとしても、研修ないし武者修行の場が香港であると認められる以上、職業生活の場が香港であることには変わりがないのであるから、いずれにせよ国の主張を採用することはできない。
(4)親族について
Xは独身であり、甲、乙ないし丙と生計を一にしていたことを認めるに足りる証拠はないから、Xが国内に生計を一にする親族を有していたとはいえない。
(5)資産の所在について
本件の事実において、金額面で比較すれば、Xの資産は国内にあるものが主であるが、香港でも生活をする上で必要な資産を有しており、本件滞在期間中の生活費等の支払も、日本国内、香港の双方の銀行口座からされているから、資産の所在から、Xの生活の本拠が本件杉並自宅にあったか否かを判断するのは困難である。
(6)居住意思その他Xの主観的事情について
① 金融機関等への住所変更届出の状況は、数の上では届出をしなかった金融機関等が多いが、住所変更手続の手間を厭ったものと考えられないわけではないし、現実に住所変更届出をした金融機関もあるのであるから、直ちにXの居住意思が本件杉並自宅所在地にあったものとは認められない。
② Xは、T社の常務取締役就任時の取締役就任承諾書及び役員宣誓書に本件杉並自宅所在地を住所として記載しているが、他方で、本件香港自宅所在地を住所として記載した書類も多数残されており、その中には、T社の有価証券報告書における大株主欄、香港の医療保険会社の加入手続書のように、書面の提出先及び性質から本件香港自宅所在地を住所として記載せざるを得ないものもある。
③ Xは、本件贈与の実行において、多額の贈与税の負担を回避しようとしてW公認会計士らの指示を受けているのは事実である。
しかしながら、前示のとおり、XはT社の海外駐在役員ないし香港各会社の代表者の地位にあって、現実にそれらの業務に従事していたものであり、かかる業務が贈与税を回避するために作出された外形にすぎないとは認められないのであるから、Xが本件滞在期間中に単に贈与税の負担を回避することのみを目的として香港に滞在していたとは認定し難い。また、Xの香港滞在の目的の1つに贈与税の負担回避があったとしても、現実にXが本件香港自宅を拠点として生活をした事実が消滅するわけではないから、Xが贈与税回避を目的としていたか否かが、本件杉並自宅所在地が生活の本拠であったか否かの点に決定的な影響を与えるとは解し難い。このように、Xの主観的事情を考慮したとしても、Xの生活の本拠が本件杉並自宅所在地であったとすることは困難である。
3 まとめ
以上のとおり、Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在し、上記住居にて起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであって、Xと甲ないしT社との関係、贈与税回避の目的その他国の指摘する諸事情を考慮してもなお、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難である。国の主張は、Xの租税回避意思を過度に強調したものであって、客観的な事実に合致するものであるとはいい難い。
四、解説
はじめに
本件は、我が国のサラ金業界の最大手であるT社の経営者夫妻が、T社の株式をオランダ法人YST社(外国法人)に保有させ、そのYST社の出資口数の大部分(総口数の90%、本件出資)を長男Xに香港で贈与(本件贈与)したのであるが、贈与税の負担を回避するためにXの住所を日本国内に存しないように工作しておいたため、本件贈与に対し我が国の贈与税が課せられるか否かが争われたものである。
また、本件は、争いの対象となる贈与税額が今までの税務訴訟における訴額の中でも最大となることや、本件のような租税回避を防止するための相続税法改正の直前において本件贈与が行われたこともあって、社会的にも大きな注目を集めたものである。
特に、本件では、サラ金業自体が専ら我が国の経済的弱者から利益を吸い上げているのであるが、その経済的弱者が社会福祉等を通じて最も恩典を受けることとなる我が国の租税(贈与税、相続税)を完全に回避しようとする(注1)冷酷な「資本の論理」が貫かれようとしているのである。それに対し、「住所」の意義の解釈等によってその「資本の論理」が打破できるかという租税法の解釈のあり方が問われるという問題が生じることになる。その問題の解決方法においては、租税回避の防止と租税法の解釈のあり方について考えさせられるところが多い。
以下、これらの問題点について、従前の事例や関連する相続税法及び所得税法上の関係条項等に照らして論じることとする。
1 「住所」と課税規定
(1)本件贈与が行われた平成11年当時の相続税法では、「この法律の施行地に住所を有するもの」は、全ての贈与により取得した財産について贈与税が課され(旧相法1の2一)、「この法律の施行地に住所を有しないもの」は、贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した時にのみ贈与税が課せられる(旧相法1の2二)ことになっていた。このように、国内に「住所」を有するか否かによって課税関係を異にするのは、相続税においても同様であった(旧相法1)。
しかしながら、このような規定では、本件のように、贈与を受ける者の住所を国外に移し、国内財産を国外財産に仕立てる方法(特に、株式等においては容易である。)によって、我が国の相続税や贈与税の負担を回避することが横行していたため、前記規定の改正の必要性が指摘されてきた。
(2)かくして、平成12年度の税制改正において、次に掲げる者が贈与税の納税義務が課せられることになった(相法1の4)。
① 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの。
② 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)。
③ 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前記②に掲げる者を除く。)。
この②のように、我が国の住所を有しなくなっても、5年間課税関係が継続することについては、相続税の場合も同様である(相法1の3三)。このような課税関係を図解すると、上図のようになる(注2)。
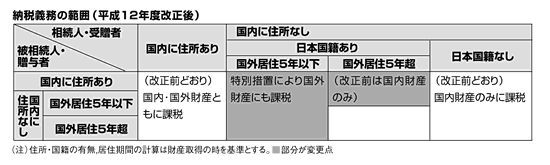
(3)このように、国内に個人の住所が存するか否かによって課税関係が異なることは、所得税法においても類似する。所得税法では、個人を居住者、非永住者及び非居住者に区分し、それぞれ納税義務の範囲を異にする(所法5)。
この場合、居住者とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」(所法2①三)をいい、非永住者とは、「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」をいい(所法2①四)、そして、非居住者とは、居住者以外の個人をいう(所法2①五)。
また、居住者と非居住者の区分については、国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しないもの及び国籍を有する者であっても、現に国外に居住し、かつ、その国に永住すると認められる者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、所定の条項が適用される(所法3①、所令13)。
なお、所得税法では、所定の場合には、国内に住所を有する者等と推定されるときがある。すなわち、国内に居住することとなった個人が、①その者が国内において継続して1年以上居住することが通常必要とする職業を有すること及び②その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があることに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定され(所令14①)、このように住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他の扶養親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定される(所令14②)。逆に、国外に居住することとなった個人が、国外において同様な事情があれば、その者は、国内に住所を有しない者と推定される(所令15)。
2 住所の意義等
(1)以上のように、個人に課税される贈与税、相続税又は所得税においては、その個人の住所が国内にあるか否かによって課税関係が大きく異なることになる。ところで、「住所」という用語については、相続税法においても又は所得税法においても、特段の定義規定を設けているわけではないので、租税法の解釈においては、いわゆる借用概念の典型であると解されている(注3)。
借用概念とは、租税法上用いられている用語のうち、他の法分野で用いられ、既に明確な意味内容を与えられている概念を意味し、他の法分野から借用しているという意味で、そのように呼称される。この点では、「住所」は、民法上、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」(民法21)と定められ、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」(民法22)と定められているところである。そして、本判決が引用する最高裁各判決において、各人の生活の本拠等が住所であると解されている。
かくして、このような借用概念の租税法上の解釈については、私法上の概念とは別意に解すべきことが租税法規の明文又はその趣旨から明らかである場合を除き、私法上におけると同じ意義に解するのが法的安定性の見地から望ましいものと解されている(注4)。
(2)ところで、「住所」の意義については、課税の取扱いにおいても、明確にされている。まず、基本通達1の3・1の4共一5では、「法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする。この場合において、同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。」と定めている。
そして、この通達に係る国税庁担当者の解説によると、①「住所」の意義については、相続税法上も民法上と同様に解するのが相当であること、②生活の本拠の判断においては、定住の意思(主観説)に拘束されず、定住という客観的事実だけで足りること、等が明らかにされている(注5)。
また、所得税基本通達2-1では、「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。(注)国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)及び第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定があることに留意する。」と定めている。
なお、この通達の趣旨についても、国税庁の担当者の解説によると、住所について民法の概念と同様であること、客観主義によって住所が判定されるべきであるとされている(注6)。
(3)次に、基本通達1の3・1の4共-6は、日本の国籍を有している者等については、その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において法施行地を離れている場合であっても、その者が、①学術、技芸の習得のため留学している者で法施行地にいる者の扶養親族となっている者及び②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内である場合をいうものとする。)であると見込まれるもの(その者の配偶その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む。)に該当する場合には、その者の住所は、法施行地にあるものとして取り扱うものとしている。
また、同通達は、「その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において法施行地を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に法施行地を離れているにすぎない者については、その者住所は法施行地にあることとなるのであるから留意する。」と定めている。
この通達に関しては、東京地裁平成17年1月28日判決(平成15年(行ウ)第518号)が、受贈者を香港に居住させる目的をもって出国させた9日後に国外財産を贈与した事案につき、前記通達に照らし、当該受贈者の住所が国内にあったものと認められるとした課税処分を適法である旨判断している(注7)。
3 本件における「住所」の認定
(1)本件においては、当初から相続税・贈与税対策として、Xが香港に居住することとし(平成9年6月)、その居住に対応してT社の関連会社を香港に設立し、Xが当該関連会社の役員を務める形式を整え、国外移住に対する租税回避防止のための相続税法改正が間近であるということで、平成11年12月27日付で、本件贈与が実行されたというものである。また、Xは、本件贈与後も約1年香港に滞在して失踪し、平成15年12月杉並の自宅に戻ってきたというものである。
結局、Xは、平成9年6月から平成12年12月まで香港に滞在(本件滞在期間)していたのであるが、その間、香港滞在日数の割合が65.8%、日本滞在日数の割合が26.2%であり、欧州又は北米に9回渡航し、7回はいったん東京(成田)を経由している。また、Xは、本件滞在期間の約3年余の間にTTS社等の関連会社で得意先との面談等を行った日は延べ168日(週に1回程度)であった。
その他、Xが香港に「住所」があったか否かの事情は、本判決において前述のように詳細に認定しているところであるが、いずれも「住所」を認定できる決定的な事情であるとも認められない。
(2)かくして、本判決は、「住所」の意義について、関係最高裁判決を引用し、「住所とは、各人に生活の本拠を指すものと解するのが相当であり、生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである」旨判示し、「一定の場所がある者の住所であるか否かは、租税法が多数人を相手方として課税を行う関係上、客観的な表象に着目して画一的に規律せざるを得ないところからして、一般的には、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定するのが相当である。」と判示している。
そして、本判決は、Xの住所が国内にあるか否かに関し、認定事実に照らし、「Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在し、上記住居にて起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであって、Xと甲ないしT社との関係、贈与税回避の目的その他国の指摘する諸事情を考慮してもなお、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難である。国の主張は、Xの租税回避意思を過度に強調したものであって、客観的な事実に合致するものであるとはいい難い。」旨判示している。
(3)以上のように、本判決は、まず、「住所」の意義について、従前の最高裁判決を踏襲し、「住所」の認定(判断)における客観説を採用(客観的事実の重視)にしつつ、Xが香港に居住するようになったのが租税回避のためであることを容認しながらも、本件贈与当時、Xの住所が日本国内にあったものとは認められないと結論付けている。
このような判断は、「住所」に関する従前の解釈論を是とし、国税庁の関係通達が「住所」の判定において客観説を採用して客観的事実(この場合、滞在日数が最重視されるものと考えられる。)を重視していることに照らし、必然的に導き出されるように考えられる。
しかしながら、前記2で述べたように、租税法における「住所」のような借用概念の解釈方法は、その趣旨から明らかである場合(特段の事情がある場合)を除き、私法上におけるものと同じ意義に解すべきこととなる。換言すれば、特段の事情があれば、租税法上の「住所」は、私法上の意義とは別異に解することが妥当する。かくして、本件のような場合には、特段の事情として何を考慮し得るかが問題となろうが、それは、租税回避を企図した種々の工作が挙げられよう。そもそも、Xの香港における本件滞在期間中に日本国内26%余しか居住しないようにしていたこと自体当該工作の現れにほかならない。
そうであれば、本件においては、「住所」の判定において、従前の解釈論や判定方法に拘泥されることなく、特段の事情を一層強く考慮する余地があるようにも考えられる。この点、本判決は、租税回避の目的等の諸事情を考慮してもなお、Xが日本国内に住所を有していたことを認定することは困難である旨判示しているのであるが、その判示では、「租税回避の目的等の諸事情が借用概念の解釈における「特段の事情」として検討されたものであるかは明らかではない。
本件においては、Xの日本と香港の滞在日数割合が26:65という大差があるから特段の事情が認められなかったのか、あるいは、40:50位に接近していたら特段の事情を容認する余地があるのか、それぞれの場合において、「特段の事情」の存否について検討を要するところである。
いずれにしても、租税法における「住所」のような借用概念の解釈(判定)方法については、従前は安易に私法上の意義と同じように解することが是とされてきたが、本件のような場合には再考の余地があるようにも考えられる。
4 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件は、我が国の資産家が、相続税又は贈与税の負担を回避するために、長男(X)を香港に居住させ、国内財産であった株式等を国外財産に仕立て(外国法人へ現物出資等)、長男に対してその国外財産を贈与し、日本の贈与税の課税を免れようとしたものである。これに対し、Y税務署長は、Xの住所が日本国内にあるものと認定して、贈与税の決定処分(本件決定)を行ったものである。
かくして、本訴においては、本件贈与当時、Xの住所がどこにあったのかが主として争われたのであるが、本判決は、前述のように、Xの香港における滞在期間中において、日本での在住割合が約26%であり、香港の在住割合が約65%であったこと(客観的事実)を重視し、本件贈与に租税回避の意図が認められるにしても、Xの住所が日本国内にあったとは認め難いとして、本件決定等を取り消している。
その取消税額が今までの税務訴訟の中で最高額であったことや、本訴の当事者が著名な我が国サラ金業界の経営者一族であり、巧妙な租税回避行為が本判決によって正当化されたこともあって、本判決は社会的に大いに注目されることになった。
(2)ところで、本件におけるXの住所の判定については、従前の借用概念に関する解釈方法、住所の解釈論、そして、国税庁の関係通達の取扱いを前提にする限りでは、本判決の結論も当然の成り行きであるようにも考えられる。
しかしながら、前述したように、従来、租税法における借用概念の解釈方法が私法上の解釈に安易に同調してきた節も見られるところである。そして、本件のように、計画的に行われた租税回避行為に対して、外形的(客観的)事実である滞在日数を重視して「住所」を判定することに疑問がないわけではない。このことは、借用概念の解釈において、特段の事情をどこまで考慮し得るかという問題を提起することになる。
いずれにしても、本判決は控訴されているようであるので、控訴審においてどのような判断が示されるかが注目されるところである。
(注1)我が国の平成11年分贈与税の総額が1,143億円であるので、本件贈与に係る贈与税額は、その総額を上回ることになる。
(注2)星野次彦『図解 日本の税制 平成19年度版』財経詳報社153頁参照。
(注3)金子宏『租税法 第12版』(弘文堂)103頁等参照。
(注4)前出(注3)103頁等参照。
(注5)香取稔編『相続税法基本通達逐条解説 改訂新版(平成18年版)』(大蔵財務協会)36頁参照。
(注6)高倉明ほか共編『所得税基本通達逐条解説 平成16年度版』(大蔵財務協会)15頁参照。
(注7)同事案においても、我が国の相続税又は贈与税の負担を回避するためのプランニングが行われ、それが実施されたのであるが、一審段階では当該目論見がはずされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















