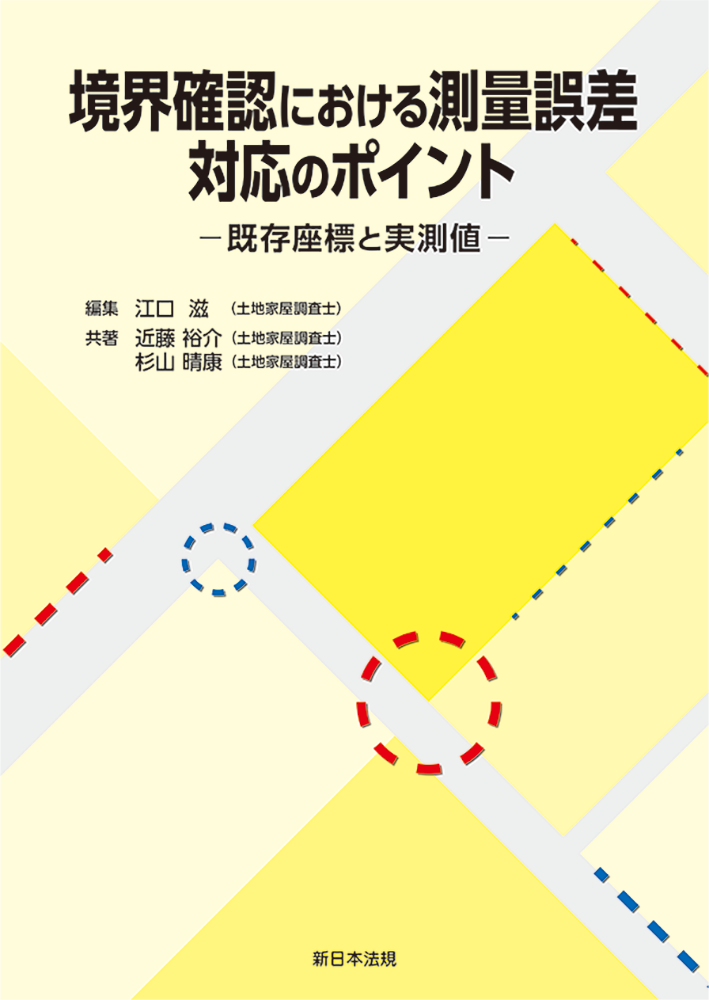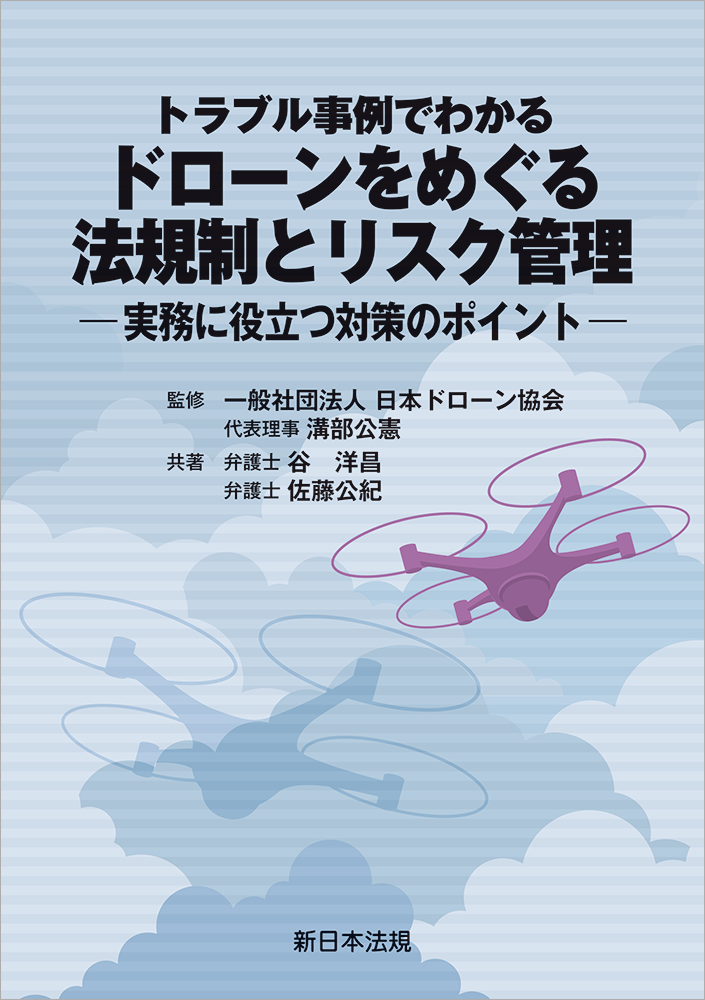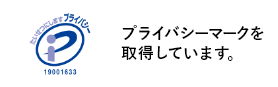解説記事2008年10月20日 【最新判決研究】 地方税法における法定外普通税の範囲―神奈川県臨時特例企業税事件―(2008年10月20日号・№279)
最新判決研究
地方税法における法定外普通税の範囲
―神奈川県臨時特例企業税事件―
品川芳宣
早稲田大学大学院教授
横浜地裁平成17年(行ウ)第55号
平成20年3月19日判決
一、事実
(1)神奈川県(被告)は、「神奈川県地方税制等研究会」(座長:神野直彦東京大学教授)の提言に基づき、神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号、同年8月1日施行。以下「本件条例」という。)を制定し、地方税法4条3項に定める法定外普通税(以下「法定外税」という。)として、神奈川県内の特定の法人に対し、臨時特例企業税(以下「本件企業税」という。)を課した。
これに対し、本件企業税の課税の対象となったX会社(原告)は、本件条例が法人事業税につき欠損金額の繰越控除を定めた地方税法の規定を潜脱して課税するものであって違法・無効であるとして、同社が同税の申告・更正等により納付した本件企業税の平成15年度分(13億1,122万円余)及び平成16年度分(6億6,341万円余)が誤納金であるとして当該金員の還付等を求める本訴を提起した。
(2)本件条例に定める本件企業税の要点は、次のとおりである。
① 納税義務者(原則)
神奈川県内に事務所又は事業所を設けて事業活動を行う法人(事業年度終了の日の資本の金額又は出資額が5億円未満の事業年度を除く。)
② 課税標準
各課税事業年度における法人の事業税の課税標準である所得の金額の計算上、繰越控除欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合における当該課税事業年度の所得の金額に相当する金額(当該金額が繰越控除欠損金額に相当する金額を超える場合は、当該繰越控除欠損金額に相当する金額)(なお、法人事業税の外形標準課税の導入を踏まえ、平成16年3月の条例改正において、課税対象となる繰越欠損金相当額を外形標準課税導入前の事業年度において生じた欠損金相当額に限定する課税標準の特例を措置。)
③ 税率
特別法人2%
普通法人 3%(法人事業税の外形標準課税の導入を踏まえ、平成16年3月の条例改正において税率を引下げ、改正後は2%。) なお、本件条例は、法人事業税における外形標準課税の導入に配慮し、平成21年3月31日限りその効力を失うこととされた。
二、争点及び当事者の主張
1 争点
本件の主たる争点は、本件条例が次の事由によって違法・無効と言えるか否かにある。
① 法人事業税の課税標準につき欠損金額の繰越控除を定めた規定を潜脱して課税するものであること。
② 法人事業税につき制限税率を定めた規定を潜脱して課税するものであること。
③ 平成15年改正前地方税法(以下「改正前地方税法」という。)72条の19の規定によらずに法人事業税の課税標準の特例を設けるものであること。
④ 担税力を有しない繰越控除欠損金に課税するものであること。
⑤ 平成15年法律第9号による地方税法改正の際に総務大臣の同意を欠くこと。
⑥ 地方税法7条の要件を満たすことなく不均一課税をするものであること。
⑦ 国民の財産権を比例原則に反して侵害するもので憲法29条に違反すること。
⑧ 租税公平主義に反し、憲法14条1項及び29条に反すること。
2 X会社の主張
(1)本件条例は、次の理由等により違法・無効である。
① 地方税法261条所定の総務大臣の同意は、法定外税の適法性を審査するものではない。
② 法定税に関する規律を潜脱する法定外税条例は、違法・無効である。
③ 法人事業税における欠損金額の繰越控除は、法律改正によらなければ変更できない。
④ 本件企業税は、実質的に法人事業税の欠損金額の繰越控除を一部遮断するもの(法人事業税の実質的変更)である。
⑤ 本件企業税は、法人事業税の課税標準につき欠損金額の繰越を定めた規定を潜脱して課税するものである。
⑥ 本件企業税は、法人事業税の制限税率を潜脱して課税するものである。
⑦ 本件企業税は、改正前地方税法72条の19の規定によらずに法人事業税の課税特例を設けるものである。
⑧ 本件企業税は、担税力を有しない繰越控除欠損金に課税するものである。
(2)本件条例が違法・無効であるから、本件企業税の課税処分等も当然に無効となり、当該課税処分等の取消しを待つまでもなく、X会社が神奈川県に対して納付した金員を誤納金として還付請求することができる。
3 神奈川県の主張
(1)本件条例は、次のような理由により、適法・有効である。
① 本件条例は、神奈川県地方税制等研究会の最終報告書を基にして、県議会の議決及び地方税法259条以下に規定する手続を経て、制定されたものである。
② 地方団体は、憲法上、いかなる租税をいかなる課税要件の下に賦課・徴収するかを自主的に決定することができる。法定外税は、このような地方団体の自治権(課税自主権)に基づいて、地方団体が設定できるものである。
③ 本件条例の新設は地方税法261条に規定する総務大臣の同意を得ている。同条の要件は、地方税法において法定外税として容認できない場合を類型化したものであり、当該法定外税が地方税法上適法かどうかを判断する分水嶺となっている。
④ 法定税である法人事業税に係る規定が法定外税の準則となるものではない。
⑤ 本件企業税は、法人事業税と同一の趣旨・目的を有するものではなく、X会社が主張するような法定税に係る規定を法定外税の準則とする潜脱論は当を得ていない。本件企業税は、少なくとも法的観点からみた場合、法人事業税における繰越欠損金の利用を妨げるという構造にはなっておらず、あくまでも当期利益に対して課税する法定外税である。
⑥ 本件企業税は、不均一課税ではなく、比例原則に違反せず、実質的公平に合致するから、租税として合理性を有する。
⑦ 本件条例が地方税法261条に規定する総務大臣の同意を得ていることについては、司法府は地方団体の裁量的判断を尊重するというのが最高裁判決の判例である。
(2)本件条例は適法・有効であるから、X会社が主張するような本件更正等に係る誤納金は存在せず、X会社の請求に理由がない。
三、判決要旨
請求棄却。
1 本件条例の適法性及び有効性
(1)憲法は、第8章「地方自治」において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」(同法92)と規定し、さらに、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」(同法94)と規定している。そして、地方団体が、地方自治の本旨に従い、国から独立した地位においてその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行していくには、その財源を自ら調達する権能、すなわち課税権を有することが必要であることからすると、地方団体の課税権は、地方自治の不可欠の要素であり、地方団体の自治権の一環として、憲法上保障されているものと解すべきである。
もっとも、地方団体の課税権が憲法上保障されたものであるとしても、憲法はその具体的内容について規定するものではないこと、地方団体はその組織及び運営に関する事項につき「法律でこれを定める」ものとされ(憲法92)、「法律の範囲内」で条例を制定することができるものとされていること(同法94)、及び、租税の賦課については国民の総合的な税負担の程度や国・地方間ないし地方団体相互間の財源の配分等の観点から国家的な調整が必要であることに照らせば、地方団体が課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収のあり方については、法律によってその準則ないし枠を定めることが予定されているものというべきである。すなわち、法律は、地方団体が課税権を行使する際の具体的準則ないし枠を設けるものであり、当該法律が地方団体の課税権を実質的に否定するものとして地方自治の本旨に反する場合は格別、地方団体の課税権は、具体的には、当該法律の規定に従って行使されなければならない。
このような観点から、地方自治法は、「普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。」(同法223)ものとしている。そして、地方税法は、「地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができる。」(同法2)として、地方団体の課税権の具体的準則を設けたものであり、その上で、「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。」(同法3①)としている。そうすると、地方団体の課税権は、地方税法が定める具体的準則の枠内において、地方団体の議会が制定する条例の定めるところによって行使されるものということができる。
(2)法定外税の課税は、その税目、課税客体、課税標準及び税率等があらかじめ法定されておらず、道府県が自己の判断においてこれらを決定できる性質のものであることからして、法定税の場合に比べ、道府県の課税権がより直接的・自主的な形で現れたものということができる。もっとも、法定税の課税も道府県の課税権の行使の一態様といえるところであるから、法定外税を法定税とどのような関係に置くか、また、法定外税をどのような要件及び手続の下に認めるかについては、道府県の課税権という概念から直ちに導かれるものではなく、法律において具体化されるべき問題というべきである。
この点、前記沿革のとおり、法定外税の新設又は変更の具体的要件及び手続については、国民の租税負担や国の経済施策への影響、地方団体の財政の健全性確保の必要性、地方団体内の税源や財政需要の存在の要請及び地方団体の自主的な課税権の重要性等の種々の要素を考慮して、その時々の法律によって定められてきたものである。そして、現行の地方税法上は、地方分権の推進の観点から、地方団体の自主的な課税権が特に尊重され、道府県において、総務大臣との同意を要する協議という比較的軽微な手続によって、法定外税の新設又は変更をすることができるものとされているところである。
ただし、前記の沿革から明らかなとおり、地方団体は、法律上、あらかじめ法定された税目を課するものとされる一方で、これに加えて法定された税目以外の税目を課することができるという形で、一定の要件及び手続の下に、法定外税の課税を認められてきたものである。そして、このような法定税と法定外税との基本的関係は、現行の地方税法上も維持されている。このような地方税法の基本的構造からすれば、地方団体の自主的な課税権を重視する現行法上も、法定外税は、法定税を補充するものとして位置付けられているものと解される。
(3)地方税法259条1項及び261条に規定する総務大臣との同意を要する協議は、上記の普通地方公共団体に対する国の関与のうち、地方自治法245条1号ニに規定する「同意」及び同条2号に規定する「協議」に該当する。地方分権推進一括法による地方税法の改正により、法定外税の新設又は変更につき、従前の許可制に代えて総務大臣との同意を要する協議制が採用されたのは、道府県の事務の処理に関する国の関与を必要最小限度のものとする観点から、国と道府県とが対等・協力の立場に立つという関係に基づき、両者が相互に誠実に協議し、その結果一定の事項について双方の意思の合致としての同意を要するものとすることによって、道府県の自主的な課税権を尊重しつつ、国の施策との整合性の確保を図ろうとしたものと解される。すなわち、国は、「国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、(略)国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ニに規定する行為(同意)を要することとすることのないようにしなければならない」ものとされているところ(地方自治法245の3④)、法定外税の新設又は変更は、特定の道府県の住民のみの租税負担を増加させ、地方団体間の物の流通に影響を及ぼすことがあり、また、その他国の経済施策の実施に影響を与える可能性があるため、国の施策との整合性を確保し、その施策の実施に著しい支障が生ずることを防ぐという観点から、法定外税の新設又は変更について、総務大臣の同意を要するものとされ、地方税法261条各号の事由が定められているものと解される。
そうすると、法定外税の新設又は変更に係る同意を要する協議制度は、国の行政機関たる総務大臣が、道府県の法定外税の新設又は変更に事前に関与することにより、異なる行政主体間において経済施策等の施策の整合性を確保するという、行政目的の下に設けられているものということができる。そして、地方税法261条各号に規定する不同意事由は、上記の関与の必要最小限度の原則(地方自治法245の3①)や同意を要する場合を限定する規定(同条④)の趣旨に照らせば、これらの不同意事由に該当しなければ同意しなければならないものとすることによって、上記行政目的の下での国の関与の態様を限定する趣旨のものということができる。すなわち、法定外税の新設又は変更に係る同意を要する協義において、総務大臣は、地方税法261条各号の事由に該当するかどうかという点に限って、国の施策との整合性の確保という行政目的の下に、検討・判断をするものということができる。
(4)地方税法は、道府県において、法定税以外の税目を起こして、法定外税を課することができるものとしているが(同法4③)、この法定外税は、道府県において原則として法定税を課すべきことを前提に、これに加えて法定税以外の税目を課する形で、法定税の課税を補充するものとして課されるものである。そして、同条2項ただし書は法定外税に触れるところはなく、法定税を課さない特別の事情と法定外税の課税自体とに直接の関係はないものと解されることからすれば、法定外税を課する場合であっても、上記のとおり道府県において法定税を法定の準則に従い課すべきことに変わりはない。
法定外税という形式を採ることにより、法定税に係る法定の準則と関わりなく課税できるとすれば、道府県は、法定外税の形式を用いることにより、法定税に係る法定の準則を回避し、いわばこれを潜脱して、実質的に当該準則に反する課税をすることも可能になりかねないが、このことが、法定税の課税の準則として詳細な規定を設け、その定めるところによって地方団体が地方税を賦課徴収することができる(地税法2)こととした地方税法の趣旨に反することは、明らかというべきである。
例えば、地方税法は、法人事業税につき、制限税率を標準税率の1.1倍(改正前)ないし1.2倍(改正後)と規定するところ、仮に、法定外税として法人事業税と課税客体及び課税標準が全く同じ租税をいかなる税率においても課することが許されるとすれば、道府県はこれにより法人事業税の制限税率の規定の適用を実質的に回避できることになるが、これが法人事業税につき制限税率を設けた地方税法の趣旨に反することは明らかである。
(5)本件企業税は、法人事業税の課税標準において欠損金額の繰越控除がされる結果、当期利益ないし受益に見合った法人事業税の負担をしていない法人に、応分の負担を求めることで、法人課税の公平化及び税収の安定化を図ろうとするものであり、法人事業税の外形標準課税の導入に準じた効果を、これが実現するまでの臨時的・特例的な措置として達成しようとするものである。本件企業税が法人事業税の外形標準課税の導入に準じた効果を意図していることは、平成15年法律第9号による地方税法の改正により法人事業税に外形標準課税が一部導入されることになったことについて、見直し報告書が、外形標準課税の導入の本来の目的からすれば不十分であるとして、法人事業税の外形標準課税の導入の程度に対応する形で税率を一部引き下げた上で本件企業税を存続させることを提言し、本件条例がこれに沿った内容に改正されたことにも示されている。また、最終報告書等において述べられているように、本件企業税の創設に当たっては、法人事業税の課税標準の特例を定めた改正前地方税法72条の19の規定を活用して法人事業税自体の欠損金額の繰越控除を遮断することが検討されたものの、その要件を満たすことが困難であるとの判断の下に、法定外税の形式が採られたものであるし、本件企業税の税率(原則3%)については、法人事業税における欠損金額の繰越控除のうち控除を否定すべき一定割合(30%)を法人事業税の税率(約10%)に掛け合わせるという方法により、算出されたものである。以上のことからすれば、本件企業税は、法定の法人事業税に代わり、これと異なる課税標準の下に、同税に相当する性質の課税をする趣旨・目的のものということができる。
(6)前記のとおり、本件企業税及びその規定の趣旨・目的は、法人事業税における欠損金額の繰越控除のうち一定割合についてその控除を実質的に遮断し、当該部分に相当する額を課税標準として法人事業税に相当する性質の課税をする効果を意図しつつ、この割合を税率の設定に反映させ、課税標準を繰越控除欠損金額に相当する当期所得額として、同性質の課税をすることにある。そして、前記のとおり、本件企業税の課税は、その規定の解釈上、欠損金額の繰越控除によって法人事業税の課税対象である所得から控除される部分の当期所得を課税対象とし、繰越控除欠損金額を課税標準として課税する効果を持つものということができ、これと税率の設定とを併せて考慮すると、上記の趣旨・目的のとおり、実質的には、法人事業税における欠損金額の繰越控除のうち一定割合についてその控除を遮断し、当該控除によって法人事業税の課税対象である所得から控除される部分の当期所得を課税対象とし、当該部分に相当する額を課税標準として、法人事業税に相当する性質の課税をする効果を持つものということができる。
(7)法人事業税の課税標準である所得の計算が法人税の課税標準である所得の計算の例によるものとされている結果、法人事業税の課税標準の計算においても、欠損金額の繰越控除が行われることとなる。このように法人事業税の課税標準の計算が法人税の課税標準の計算の例によるものとされている目的の一つは、両税の課税標準の計算を同一の方法とすることによって、徴税官庁及び納税者の便宜を図ることにあるものと解される。
しかし、租税の課税標準は、税額の基礎とするため課税客体を数値として具体化する趣旨のものであることからすれば、法人事業税の課税標準の計算につきこのような構造が採用されているのは、立法者において、単に他の課税標準を流用する便宜にとどまらず、法人税と同様の課税標準の計算方法を採ることが、法人事業税の課税客体を具体化する上においても適当であると判断したからであると解すべきである。すなわち、法人事業税の課税標準は、法人税の課税標準と同様の所得の金額とすることが適当であるとの判断の下に規定されたものであり、その所得の計算において欠損金額の繰越控除が行われることについても、法人税と同様、特定の事業年度に生じた欠損金額を以後の一定の事業年度の利益と通算することによって、法人の所得を長期的に把握し、もって法人の担税力を的確に課税に反映させることが、その趣旨・目的とするところであるというべきである。
確かに、法人事業税の租税としての趣旨・目的は、行政サービスの対価の負担という、応益原則に基づくものと解されるところである。しかし、行政サービスの対価を負担させることを租税としての趣旨・目的としつつ、具体的な課税標準の設定の段階においては、法人の担税力を考慮に入れ、その担税力に見合う限度で税負担を求めることは、租税政策上の当否はともかくとして、何ら矛盾するものではない。
(8)改正前地方税法下では、限定された要件の下で初めて、欠損金額の繰越控除を含めた法人事業税の課税標準の特例が認められていたことからすれば、当該特例の要件を満たす場合以外は常に、改正後地方税法下では、当該特例の適用外とされた法人については常に、欠損金額の繰越控除を含めた地方税法所定の法人事業税の課税標準の規定を全国一律に適用すべきものとする趣旨であると解される。
そして、特定の租税の課税標準は、その租税としての趣旨・目的に基づき、これを税額に具体的に反映させるために特定の課税客体を数値化するものである。そうすると、法人事業税についても、当該趣旨・目的に基づく当該課税客体に対する租税については、地方税法が法人事業税について定めた課税標準の規定に従って当該課税客体を数値化し、これに課税すべきとする趣旨であると解される。すなわち、法人事業税が予定するところの租税としての趣旨・目的及び課税客体に係る租税については、地方税法が法人事業税について定めた課税標準の規定に従い、その規定の目的及び効果を実現したところによって課すべきものとする趣旨であると解される。
そうすると、少なくとも、法人事業税と租税としての趣旨・目的及び課税客体が共通する法定外税の創設によって、全国一律に適用すべき法人事業税の課税標準の規定の目的及び効果が阻害されることになることは、当該課税標準の規定を定めた地方税法の趣旨に反するものといわなければならない。
上記のことは、地方税法が法人事業税につき制限税率を設けていることからも裏付けることができる。すなわち、租税の税額は基本的に課税標準と税率とによって決せられるところ、法が制限税率を設けているのは、単に税率の上限を設けるにとどまらず、一定の課税標準を前提に、これに税率を乗じて得られるところの当該租税の負担の程度に制限を設ける趣旨であると解される。そして、地方税法が法人事業税につき制限税率を設けているのは、上記の課税標準について述べたところと同様に、法人事業税が予定するところの租税としての趣旨・目的及び課税客体に係る租税につき、その租税の負担の程度に制限を設けるという趣旨であると解される。
そうすると、法人事業税と租税としての趣旨・目的及び課税客体が共通する法定外税の創設によって、法人事業税の課税標準の規定の目的及び効果が阻害されることになることは、地方税法が当該租税の負担の程度を制限するため当該課税標準を前提に制限税率を設けていることからしても、同法の趣旨に反するものというべきである。
(9)以上のとおり、本件企業税の課税は、法人事業税の課税標準である所得の計算につき欠損金額の繰越控除を定めた規定の趣旨に反し違法であるから、これを定める本件条例は違法である。
そして、地方団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ(地方自治法14①)、地方税法の定めるところによって地方税を賦課徴収することができるとされていること(同法2)に照らせば、上記のような地方税法に違反する租税を創設する条例を制定することは、地方団体の有する条例制定権を超えるものであるから、本件条例は無効というべきである。
2 本件各更正等の有効性等
本件各更正等は、本件条例に基づいてされたものであるところ、本件条例が無効であることは前記のとおりである。地方団体は、条例の定めに基づいて地方税の賦課徴収をするものであるから(地税法3①)、地方税の課税処分の根拠となった条例が無効であることは、当該課税処分につきこの上ない極めて重大な瑕疵があるというべきであって、本件各更正等には、課税要件の正に根幹に関する内容上の過誤があるというほかなく、いずれも無効である。
四、解説
はじめに
本件は、バブル経済崩壊後景気停滞が長期化する中、神奈川県が、法人事業税の大幅減収(注1)に対処するため、本件条例を制定することによって、本件企業税を所定の法人企業に課したことにつき、本件条例の効力(地方税法違反による無効性)と本件企業税の課税処分等の違法(無効)性が争われたものである。
バブル崩壊後に法人事業税を中心とする地方税の税収が大幅に落ち込んだのは、何も神奈川県だけの問題ではなく全国的な問題であったこと、また、それに対処するため東京都及び大阪府がいわゆる銀行税を創設しそれが裁判所で違法判決(注2)が下されたこともあって、本件企業税の違法性をめぐる本訴の行方が注目されていた。
また、本件企業税は、課税標準である各事業年度の所得金額の計算において繰越欠損金の控除を一部又は全部を否定するものであるだけに、法人税及び法人事業税の課税のあり方や企業課税のあり方にも影響を及ぼすものである。
更に、本件企業税は、地方税法上の新設が認められている法定外税の一つとして創設されたものであるが、法定外税については地方税法が準則法又は枠法として機能している中、法人事業税の課税標準である所得金額計算の一部を修正した課税標準を有する本件企業税が地方税法の下で容認し得るか否かが直接争われることとなった。
いずれにしても、本件は、単に地方税の一法定外税の違法性(適法性)が争われたという問題にとどまらず、地方税における法定税と法定外税との関係、繰越欠損金の控除をめぐる法人税、法人事業税等の企業課税全体のあり方、ひいては国税と地方税の関係のあり方等に種々の問題を惹起するものであると言える。
以下、それらの主要論点について、論及することとする。
1 地方税法上の法定外税と総務大臣の同意
(1)地方税法上、道府県税には、普通税及び目的税が存する(地税法4①)。そして、道府県(注3)は、普通税として、①道府県民税、②事業税、③地方消費税、④不動産取得税、⑤道府県たばこ税、⑥ゴルフ場利用税、⑦自動車税及び⑧鉱区税を課することになる(地税法4②)。また、道府県は、これら8税目の普通税のほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる(地税法4③)。この規定に基づいて課される税目が、法定外普通税と称される(本稿では、単に、法定外税と称している。)。本件企業税は、この法定外普通税である。
なお、道府県は、目的税として、①自動車取得税、②軽油引取税、③狩猟税及び④水利地益税を課する(地税法4④、⑤)ほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。この別税目の目的税は、法定外目的税と称せられる。
(2)この法定外税は、道府県が任意に新設等ができるわけではなく、所定の手続を経て総務大臣の同意を要することになっている。すなわち、道府県は、法定外税の新設又は変更(税率引下げ等所定のものを除く。)をしようとする場合には、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない(地税法259①)。
総務大臣は、前述の協議の申出を受けた場合には、その旨を財務大臣に通知しなければならない(地税法260①)。財務大臣は、その通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申出ることができる(地税法260②)。また、総務大臣は、法定外税の新設又は変更の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
更に、総務大臣は、法定外税の新設又は変更について申出を受けた場合には、当該申出に係る法定外税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない(地税法261)。
① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
③ ①及び②に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らし適当でないこと。
本件企業税は、このような地方税法上の所定の手続を経て、その新設について総務大臣の同意を得たものであるので、神奈川県としても、同税を課税し得ることになる。
(3)しかしながら、本判決は、「法定外税の新設又は変更に係る総務大臣との同意を要する協議(<略>)は、異なる行政主体間において経済施策等の施策の整合性を確保するという、行政目的の下にされるものであって、当該法定外税の適法性を審査する性質のものではないから、企業税の適法性は、総務大臣の同意の判断如何にかかわらず、本訴において別途判断されるべき問題である。」と判示して、本件条例と本件企業税が違法・無効であることを結論付けている。
確かに、本件企業税のような法定外税の適法性の判断は、最終的には司法に委ねられることになろうが、前述の地方税法259条から261条までの法律構造に照らせば、裁判所は、まず、地方税法261条に定める不同意事由の存否について判断すべきであろう。この点については、法定外税の違法性が争われた事件の先例となっている金沢地裁昭和28年11月7日判決(昭和27年(行ウ)第9号)が、地方税法261条各号該当の有無について判断しているところである。にもかかわらず、本判決は、そのような判断を一切行わず、後述のように、本件企業税と法人事業税との同一性を強調し、法人事業税の課税標準計算を違えた本件企業税を定めた本件条例を違法・無効であるとしているが、法定外税を定めた地方税法の解釈・適用上問題である。
2 本件企業税と法人事業税との関係
(1)前述したように、本件企業税は、神奈川県内に事務所又は事業所を設けて事業活動を行っている資本金5億円以上の法人に対し、各事業年度の法人事業税の課税標準である所得の金額の計算上繰越欠損金を損金の額に算しないものとして計算した金額(法人事業税の課税標準額とし重複しないように調整)を課税標準として、原則として、3%の税率によって課されるものである。このような性質を有する本件企業税については、法人事業税との関係をどう理解するかによって、法定外税としての適法性の判断にも関わることになる。
この点について、本判決は、「実質的には、法人事業税における欠損金額の繰越控除のうち一定割合についてその控除を遮断し、当該控除によって法人事業税の課税対象である所得から控除される部分の当期所得を課税対象とし、当該部分に相当する額を課税標準として、法人事業税に相当する性質の課税をする効果を持つものということができる。」と判示して、本件企業税と法人事業税の同質(同一)性を強調し、地方税法が法人事業税の課税標準の計算においてその控除を認めている繰越欠損金の控除を地方税法の改正もなく法定外税である本件企業税において否定することはできない旨判示している。
(2)しかしながら、本判決の結論では、法定税と類似している税目は法定外税として一切認められないことになるが、そのことが地方税法の関係条項の解釈上妥当であるか否かという疑問とそもそもその類似又は同質(同一)性の判断をどのように行うべきかが問題となる。
本件企業税については、行政サービスの提供を受けている法人企業に対し、応益課税の本旨に則り、当時の法人事業税における「所得」課税によって税負担を免れることの欠陥を補おうとしたものであろう。バブル崩壊後当時、法人の所得が激減していたため、本件企業税の新設は、応益課税としての機能が低下していた法人事業税とは別個に応益課税としての機能を期待したものであろう。しかも、本件企業税は、恒久的なものではなく、法人事業税の応益課税の機能が回復するまでの暫定的なものである。そして、何よりも、法人事業税と本件企業税のそれぞれの課税標準が重複しない措置が講じられている。これらの点を考慮すれば、本件企業税と法人事業税とは別個の税目としての機能を有していることになる。
更に、現行制度において数ある税目の中で、課税標準等の共通性を強調して当該税目間の同一性又は一体性を強調することも適切ではない。例えば、法人企業の「所得」を課税客体とする税目は、法人税、法人事業税及び法人住民税の3税が存するわけであるが、それらが法的に同一の税目として論じられることはない。このことは、個人の「所得」についても同様である。
3 繰越欠損金控除否定の是非
(1)前述したように、本判決は、本件企業税と法人事業税とを同一視し、法人事業税の課税標準の算定において繰越欠損金の控除が認められているにもかかわらず、本件企業税の課税標準の算定において当該控除が認められていないことを本件条例の違法事由であるとしている。すなわち、本判決は、「法人事業税と租税としての趣旨・目的及び課税客体が共通する法定外税の創設によって、全国一律に適用すべき法人事業税の課税標準の規定の目的及び効果が阻害されることになることは、当該課税標準の規定を定めた地方税法の趣旨に反する。」と判示している。
この判示は、要するに、法人事業税に類似する法定外税を創設する場合には、法人事業税の課税標準の規定の目的及び効果が阻害されないようにしなければならないこととし、本件に即していえば、繰越欠損金の控除を否定してはいけないことを意味し、かつ、法人事業税に類似する法定外税の創設を一切否定することを意味している。
(2)しかし、このような結論を導き出す本判決には、法人事業税の課税標準の算定において繰越欠損金の控除が行われていることが絶対的真理であるとの誤った認識がある。そのため、当該繰越欠損金の控除を部分的に認めないとした本件企業税の存在が地方税法上許されないものと判断したものであろう。
しかしながら、本件企業税創設当時の法人事業税は、確かに、その課税標準の算定において繰越欠損金の控除を行っていたが、それは、便宜上、法人税の課税標準(所得金額)の算定に準じていたにすぎず、事業税固有の理論に基づいているわけではなく、事業税の沿革においてもそうなってはいない。
すなわち、事業税の前身である営業税は、明治11年に創設され、その時の課税標準は業種別に定額とされ、明治29年に営業税が国税に移管し、道府県は営業税付加税を課すこととされたが、その時の課税標準は外形標準(売上金額、建物賃貸価格、従業者数等)であり、大正15年には課税標準が純益とされ、昭和25年のシャウプ税制では付加価値税として衣替えが予定されたが実施されずに事業税が施行され、昭和29年に法人事業税の課税標準が法人税の課税標準計算に合わせることとされたが、平成16年以降現行のような外形標準課税が導入されているところである(注4)。
(3)また、本件企業税新設当時の法人事業税の課税標準算定の基となっていた法人税においても、繰越欠損金の控除は一律かつ不変に行われていたわけではなく、その時々の財政状況等を反映して政策的に行われてきたに過ぎない(注5)。すなわち、我が国に法人税が導入されたのは明治32年であるが、その時には所得金額の計算上、繰越欠損金の控除は認められていなかった。その後、昭和15年になって初めて繰越欠損金の控除が認められることになったが、それも3年間であり、昭和21年には1年に短縮された。
そして、昭和25年のシャウプ税制においてその繰越期間が5年に延長されたが、その場合にも、青色申告書の提出の有無等によってその取扱いが異なることとされている。また、平成15年には、この繰越期間が7年に延長されたものの、平成18年には、特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越はできないこととされた(法法57の2)。更には、同じく期間的な「所得」を課税標準とする所得税においては、純損失等の繰越期間は、青色申告を条件に3年である(所法70、71)。
以上のような税制の沿革等を考察してみても、法人税における繰越欠損金の控除は、政策的に行われているものであって、「所得」の計算上絶対に行われなければならないことでないことが理解できる。
4 地方税法の準則法と本件企業税
(1)本件企業税のような法定外税の新設については、地方税法上無制限に認められるわけではなく、それであるからこそ、前述したような地方税法261条各号にいう総務大臣による不同意事項が定められている。また、同261条の規定のみならず、地方税法の全体の趣旨からみて、何らかの制限もあり得ることになる。それが故に、法定外税の新設においては、地方税法が準則法又は枠法として機能することになる。
そのため、本判決は、法定外税新設の適法性の最終判断は司法判断によるものとして、「地方税法は、このような立法政策的判断の結果として、法人事業税の課税標準に係る規定を置き、これが地方団体が課税権を行使する際の法定の準則となっているところ、本件条例は、地方団体の別途の政策的判断をもって、実質的に当該準則と異なる課税方法を採ろうとしたものであって、地方税法の準則法ないし枠法としての性質上、許されないものといわざるを得ない。」と判示している。
この判示においても、本件企業税と法人事業税の同一性が強調されているのであるが、そのような判断こそ問題があることは既に述べた。また、この判示の中では、本件企業税が繰越欠損金の控除を制限することが地方税法の本旨に反するとしているが、そのことの不当性についても既に述べた。
(2)もっとも、本件条例が地方税法という準則法の枠内に納まるか否かは、最終的には司法判断に委ねられるわけではあるが、それらの判断も、地方税法の関係条項を前提に総合的に判断せざるを得ないはずである。けだし、地方税法という準則法の中でいかなる法定外税の新設が認め得るかについては、絶対的な指針があるわけではなく、地方税法261条3号に、租税政策上「国の経済政策に照らして適当でないこと」が挙げられていることからも解るように、極めて政策的かつ相対的に判断せざるを得ないわけである。
この点、本判決は、法人事業税と類似する本件企業税がその課税標準の算定において繰越欠損金の控除を制限したことが準則法に反することになることが決定的事由であるかのように判示するが、その論拠が決定的でないことは既に述べた。そうであれば、原点に戻って総合的に判断するにせよ、地方税法261条に定める総務大臣の同意(判断)が一層尊重されて然るべきであるとも考えられる。
(3)また、地方税については、主要な税源について国税が課税されているため、元々税源が限られているわけであるが、その中で、地方税法は、法定税のほかに法定外税制度を認めているわけである。そのことは、地方自治の本旨に則り、地方団体に対し、積極的に新税を創設することによる税源の開拓を奨励しているものと解される。そして、その新税が全国的に容認し得るものであれば、地方税法を改正して法定税化するなり、既存の法定税を是正すればよいわけであるから、その新税そのものを否定してしまったら地方税の発展の芽を摘むことになる。その意味では、法定外税の新設については、「準則法」又は「枠法」という考え方によっていたずらに制限する必要はないものと考えられる。
このように考えると、本判決が、本件条例が地方税法という準則法に反すると判断したことは、その具体的論拠自体に前述のような問題があるほか、地方税法全体の趣旨に照らしても納得し難いことになる。
5 本判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件においては、バブル経済崩壊後において国全体の租税収入の確保が困難となっている中で、一層景気に左右され易い法人事業税を税収の中核としていた神奈川県が、それを補填するために法定外税として新設した本件企業税の課税を定めた本件条例の違法性が争われたものである。本判決は、前述したように、本件企業税と法人事業税を同一視し、法人事業税の課税標準計算において認められている繰越欠損金の控除を制限することは地方税法という準則法の下では許されないとして、本件条例と本件企業税の課税は無効である旨判断した。
このような本判決については、地方税法における法定外税新設の当否について法廷で争われることが稀有であり、それが故に当該条項をめぐる解釈論が十分に成熟しているとも認め難いこともあって、租税法(特に地方税法)の解釈論に一石を投じることとなったという点で大きな意義がある。また、神奈川県がこのような本件企業税を新設したことは、その後の法人事業税における外形標準課税の導入を促進させることになったわけでもある。その点でも、地方税制史に一石を投じたことになる。
(2)しかしながら、本判決については、前述のように幾つかの問題を残している。その中で、最大の問題は、法人税、法人事業税そして本件企業税を含めた法人所得課税において繰越欠損金の控除がどうあるべきかという問題を提起したことである。この点、本判決は、法人事業税において繰越欠損金の控除が認められていることを絶対視し、その控除を否定したことが準則法たる地方税法に反する旨判示した。しかし、そのように絶対視することこそ、繰越欠損金の控除制度を誤解しているものであることを指摘した。
また、本判決は、地方税法という準則法の枠を極めて厳しく解しているが、現在の国税と地方税の位置付け、地方税法における法定税と法定外税との関係、地方団体の財政事情が逼迫する中で税源の開拓が迫られていること、大きくは地方自治のあり方等を考慮した場合には、その判断が余りに狭量的であるようにも考えられる。
いずれにしても、本件は、控訴審で審理されているので、その結論に注目したいものである。
(注1)神奈川県の法人事業税の税収は、ピーク時の平成2年度には4,504億円(全税収比47.7%)であったが、平成12年度には1,763億円(同19.4%)となった。
(注2)東京地裁平成14年3月26日判決(判例時報1788号42頁)及び東京高裁平成15年1月30日判決(判例時報1814号44頁)。
(注3)地方税法における道府県に関する規定は、東京都にも準用される(地税法1②)。
(注4)詳細については、多田雄司『検証 外形標準課税―地方財政の現状と再構築を探る―』(税務研究会、平成12年)29頁等参照。
(注5)詳細については、吉国二郎総監修『戦後法人税制史』(税務研究会、平成8年)19頁以下参照。
品川芳宣(しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学教授。平成17年早稲田大学大学院客員教授(専任)、筑波大学名誉教授、税務大学校客員教授。弁護士
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究・増補改訂版』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)、『徹底解明相続税財産評価の理論と実践』(同)他多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -