解説記事2009年08月24日 【実務解説】 「みなし配当が生じない自己株式の取得」の税務上の取扱い(2009年8月24日号・№319)
実務解説
「みなし配当が生じない自己株式の取得」の税務上の取扱い
パートナーズ・コンサルティング 中尾 健
パートナーズ綜合税理士法人 鈴木達也
Ⅰ はじめに
平成18年の会社法の施行に伴い株主総会の普通決議によりいつでも自己株式の取得を行えるようになり(会社法155条、156条、160条、会社法施行規則27条)、同年の税制改正において、自己株式が資産ではなく資本金等の額のマイナス項目として整理された。会社が自己株式を取得した場合には、自己株式を譲渡した側で、税務上、みなし配当と譲渡損益が計上(法法24条1項4号、61条の2)されるが、その例外として、みなし配当が認識されない自己株式の取得が限定列挙されている(法令23条3項)。
今回は、みなし配当が認識されない自己株式の取得を明確化し、自己株式を取得した法人での資本金等の額の取扱いを確認していきたい。
Ⅱ みなし配当の原則的な取扱い
1 みなし配当 法人(A社)の株主等である内国法人(B社)が、その法人(A社)の自己の株式または出資の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合に、自己株式の1株当たりの金銭等の交付額が、その法人(A社)の1株当たりの資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額が配当とみなされる(法法24条1項4号)(図1・表1参照)。
つまり、この規定は株式の売却先が発行法人である場合の売主(B社)の取扱いを規定している。
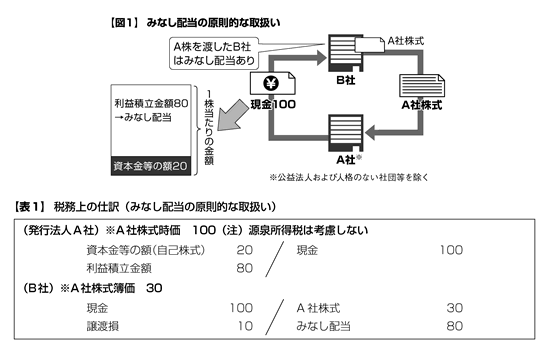
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 自己株式の取得をした法人は、次の金額に相当する資本金等の額を減算する。
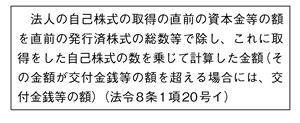
Ⅲ みなし配当の例外的な取扱い
自己株式の取得をした場合でも、その株式を譲渡した側で例外的にみなし配当が認識されないケースがある。ここでは、みなし配当が認識されない自己株式の取得のケースを概説する。
なお、詳細な説明はⅣ以降で行う。
1 みなし配当が認識されない場合 次の原因による自己株式の取得は、みなし配当は認識されず、交付金銭等の額とその株式の帳簿価額の差額は、譲渡損益として認識される。
(1)無対価による自己株式の取得 次の場合には、金銭その他の資産の交付のない自己株式の取得であることから、みなし配当は、認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
① 無償により自己株式を取得した場合
② 剰余金の配当により自己株式が交付された場合
③ 組織変更に伴い自己株式が交付された場合
(2)証券市場等での自己株式の取得 上場市場等またはPTS(私設取引システム)の利用により自己株式を取得する場合は、相対取引と異なり取引の相手方がみえず、みなし配当課税を行うことが困難であることから、みなし配当は認識されない(法令23条3項1号、2号、3号)。
(3)単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得 単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得の場合は、いずれもやむを得ない事由による自己株式の取得であるため、みなし配当は認識されない(法令23条3項9号、10号、11号)。
(4)全部取得条項付種類株式の取得等による自己株式の取得 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による自己株式の取得等で、取得対価として取得する法人の株式のみが交付され、かつ、その交付した株式の価額が取得した株式とおおむね同額である場合は、みなし配当は認識されない(法法24条3項4号括弧書)。また、これらの手続に伴い端株の買取りがあった場合も同様である(法令23条3項10号、11号)。
(5)組織再編による自己株式の取得 次の組織再編による自己株式の取得は、それぞれ次の理由によりみなし配当は認識されない。
① 事業の移転に伴う組織再編で、移転を受けた資産に自己株式が含まれている場合 事業の移転に伴う自己株式の取得であり、その移転対価の交付が利益の分配としての性格を有しているとは考えられないためである(法令23条3項4号、5号)。
② 再編の対価として自己株式が交付された場合 合併法人等が抱合株式に対して自己株式の交付を受けた場合に、その交付をした法人がその交付対価として、金銭その他の資産を受けていないことが理由となる(法法24条1項本文適用対象外)。その他、一定の組織再編による自己株式の取得の場合においてもみなし配当が認識されない(法令23条3項6号、7号)。
③ 合併に反対する被合併法人株主の買取請求に基づく買取りによる取得 反対株主からの買取りの効力発生日が合併日であること等から、効力発生日においてみなし配当の計算を行い、源泉所得税を徴収することが事実上不可能であるためである(法令23条3項8号)。
(6)個人株主からの自己株式の取得の特例 次の場合には、政策的な理由から、みなし配当は認識されない。
① 個人株主が株式公開買付(TOB)において発行法人へ自己株式を譲渡した場合
② 相続等により取得した株式を発行法人へ譲渡した場合
③ 保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
④ 強制換価手続が避けられない場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い(法令8条1項21号) 原則的には、その取得の対価の額または時価に相当する金額の資本金等の額を減算する。
ただし、次の事由により自己株式を取得したときは、直前の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算する。
① 組織再編や種類株式の取得で旧株の譲渡損益が繰り延べられるもの
② 適格組織再編による移転
Ⅳ 無対価による自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い 次に掲げる取引は、発行法人(A社)で自己株式の取得に当たるものの、相手方(B社)がその法人(A社)から「金銭その他の資産の交付を受け」ていないため、みなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
(1)無償取得 発行法人(A社)が自己株式を無償で取得した場合には、取得に伴って金銭その他の資産の交付が行われないことからみなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)(図2・表2参照)。
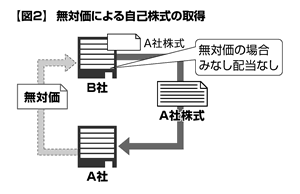
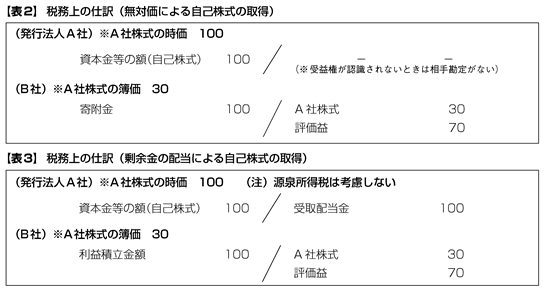
無償でA社株式を渡したB社では、A社株式の時価相当額を寄附したものとして処理する。また、無償で取得したA社では、原則として受贈益を認識する必要はないものの何らかの利益移転の目的がある場合には、受贈益を認識し課税されることもあると思われる(由比祝生編『税務相談事例集(平成19年版)』100頁(大蔵財務協会、2007年))。
(2)剰余金の配当による自己株式の取得 剰余金の配当による配当財産として自己株式の取得をした場合には、配当をした法人が金銭その他の資産の交付を受けていないことからみなし配当は認識されない。また、解散による残余財産の分配(会社法504条、505条)も会社法施行後、現物で行えることとなったため、同様の取扱いとなる(図3・表3参照)。
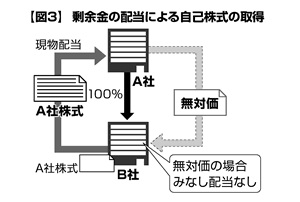
具体例としては、100%子会社が親会社株式を有する場合に、その親会社株式を現物配当する場合が考えられ、2009年3月にケンウッドが保有する親会社(JVC・ケンウッド・ホールディングス)の株式11.3%分をケンウッドからの現物配当により親会社が取得したケースがある。
なお、現物配当は、税務上、時価で譲渡したものとして扱われる。一方、会計上は企業集団内の企業に対して現物配当する場合には、適正な帳簿価額で剰余金を減額することとなる(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針10(3))。この場合には、税務調整が必要となる。
(3)組織変更に伴い交付された自己株式の取得 法人の株主または社員が、その法人の組織変更に伴う金銭等の交付として自己株式(A社株式)の交付を受けた場合には、その交付に伴いB社がA社から金銭その他の資産を受けていないことからB社ではみなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)(図4・表4参照)。
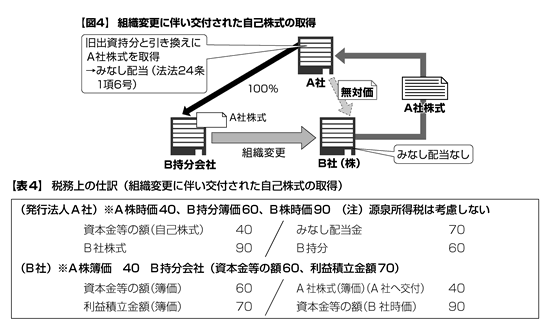
具体的には、B持分会社が既にA社株式を有しており、B株式会社への組織変更の際、社員(出資者A社)に対し、B社株式とともにA社株式を交付する場合が考えられる。
なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、法人の組織変更に伴って社員(A社)に自己株式(A社株式)を交付した法人(B社)の取扱いである。一方、その法人(B社)が新株式または新出資持分以外の金銭等を交付する場合には、その社員(A社)はみなし配当を認識する必要がある(法法24条1項6号)。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 自己株式の取得時の時価に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ、119条1項25号)。
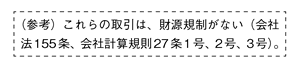
Ⅴ 証券市場等での自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い 下記の取引による自己株式の取得は、相対取引とは異なり、証券会社が仲介を行うなどにより取引の相手方がみえないため、みなし配当として課税することが事実上、困難であるとの理由から、みなし配当は認識されない(図5・表5参照)。
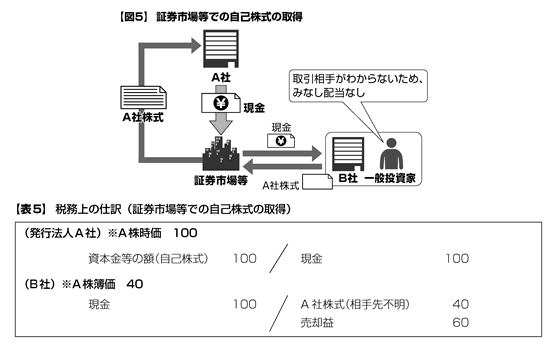
(1)上場市場における購入による取得(法令23条3項1号)
金融商品取引法2条16項に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による自己株式の取得をいう。これには、時間内取引のほか、立会外取引(ToSTNeT-2、ToSTNeT-3等)も含まれる。
一方、公開買付けによる自己株式の取得は、市場外で株式の買付け等を行う取引であることから、これに含まれない。また、グリーンシート市場は日本証券業協会が、非上場企業の株式を売買するために創設したもので、金融商品取引法上の金融商品取引所とは異なるため、これに含まれない。
(2)店頭売買登録銘柄の店頭売買による取得(法令23条3項2号)
店頭売買登録銘柄として登録された株式のその店頭売買による購入に係る自己株式の取得をいう。なお、2004年に旧株式会社ジャスダックが金融商品取引所としての認定を受けて以降、店頭売買取引は行われていない。
(3)PTS(私設取引システム)の利用による取得(法令23条3項3号)
PTS(私設取引システム)を利用した取引による自己株式の取得をいう。なおPTS取引とは、金融商品取引所を通さずに、証券会社が独自に開設したネットワーク上の私設取引所において、証券会社を仲介等として行う売買取引(夜間取引など)をいう。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号本文)。
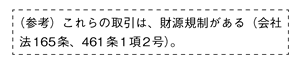
Ⅵ 単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得
1 単元未満株式および端株(後述2、3を除く)の買取り
(1)みなし配当の取扱い 次の場合の単元未満株式および端株の買取りによる自己株式の取得については、みなし配当は認識されない(法令23条3項9号)。
単元未満株式については、単元株制度において株主総会の議決権が制限されていることから、株主は発行会社へ買取請求を行うことが可能とされている(会社法189条1項、会社法192条1項)。また、端株に関しては平成17年度商法改正において端株制度が廃止されている。このように、発行法人による単元未満株式または端株の取得は、いずれもやむを得ない事情によるものであり、そのような取引にみなし配当課税を行うことは適当でない等の理由からみなし配当の対象外とされている。
① 単元未満株主からの買取請求に基づく自己株式の取得の場合(会社法192条1項)
② 株式の無償割当てにおいて、その法人の株主に無償割当てする株式に端株が生じた場合(会社法185条、234条1項3号)
③ 取得条項付新株予約権の取得事由が生じたことにより、新株予約権者に交付する株式に端株が生じた場合(会社法275条1項、234条1項4号)
④ 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により、新株予約権者に交付する株式に端数が生じた場合(会社法283条、法法61条の2第14項4号、法令23条3項11号、119条の8の2)
⑤ 株式の分割または株式の併合において、その株式の数に端株が生じた場合(会社法235条)
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号本文)。
2 全部取得条項付種類株式の端株の買取り 後述Ⅶを参照されたい。
3 組織再編により生じた端株の買取り 後述Ⅷ4を参照されたい。
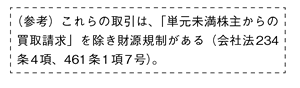
Ⅶ 全部取得条項付種類株式の取得等による自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い (1)取得対価として取得する法人の株式のみが交付される場合 次の事由により自己株式を取得した場合に、その取得対価としてその法人の株式のみが交付され、かつ、その交付した株式の価額が取得した株式とおおむね同額であるときは、みなし配当は認識されない(法法24条3項4号、61条の2第14項)(図6参照)。
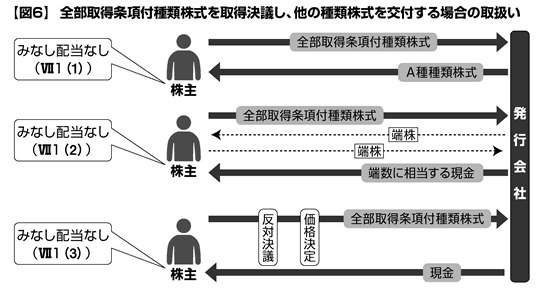
① 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による取得(法法24条3項4号、61条の2第14項3号)
② 取得条項付株式の取得事由が生じたことによる取得(法法24条3項4号、61条の2第14項2号)
③ 取得請求権付株式の請求権の行使による取得(法法24条3項4号括弧書、61条の2第14項1号)
(2)端株の買取りの場合 上記(1)に掲げる株式を取得する場合において、株主に交付する株式に端株が生じたときのその端株の買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項9号、23条3項11号、119条の8の2、会社法167条3項、170条1項、173条1項、234条1項1号、2号)(図6参照)。
(3)取得価額の決定の申立ての場合 全部取得条項付種類株式の取得決議において、その取得対価としてその株主等にその取得をする法人の株式のみが交付され、かつ、その株式の価額が取得される株式とおおむね同額である場合には、その取得価額の決定の申立てをした株主について、その株主が取得価額の決定の申立てをしなかったと仮定した場合に交付することとなる株式に端株が生じるときは、本来であれば上記(2)の規定の適用はないこととなる(図6参照)。
しかしながら、取得価額の決定の申立てをしていない株主(上記(2)の株主)の処理との平仄を合わせる理由から、その端株になると仮定される部分の買取りによる金銭の交付についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項10号)。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い
(1)Ⅶ1(1)の場合 取得する種類株式に係る種類資本金額をその種類株式と同じ種類の株式の総数で除し、これに取得をした種類株式の数を乗じて計算した金額を、その種類株式に係る種類資本金額から減算するとともに、新たに交付する株式に係る種類資本金額に加算する(法令8条5項)。
(2)Ⅶ1(2)および(3)の場合 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減少させることとなる(法令8条1項21号本文)。
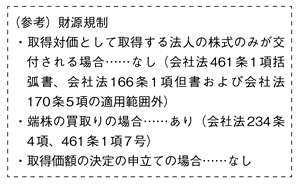
Ⅷ 組織再編による自己株式の取得
1 組織再編により移転を受けた資産に自己株式が含まれている場合
(1)みなし配当の取扱い 次の組織再編(下記①~④)により自己株式の移転を受けた場合には、事業の移転に伴い自己株式を取得しており、利益の分配としての性格を有していないため、みなし配当は認識されない(法令23条3項4号、5号)。
ただし、非適格再編において、事業が移転せず自己株式だけが移転しているような場合には、会社分割または現物出資という制度を利用しているが、その実質は自己株式の譲渡となんら変らないことから、みなし配当が認識される。
① 合併(適格非適格共通) 合併法人が適格合併または非適格合併により被合併法人から移転を受けた資産のなかに自己株式が含まれている場合(図7参照)。
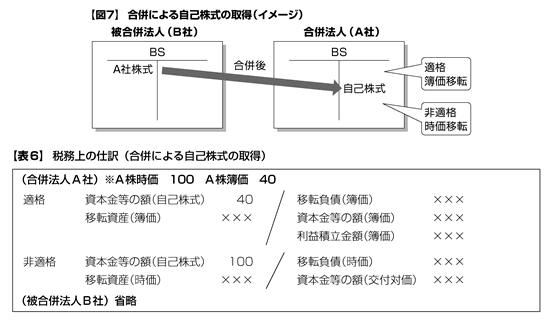
② 適格分割または適格現物出資 適格分割または適格現物出資により、分割承継法人または被現物出資法人が分割法人または現物出資法人から移転を受けた資産のなかに自己株式が含まれている場合(図8参照)。
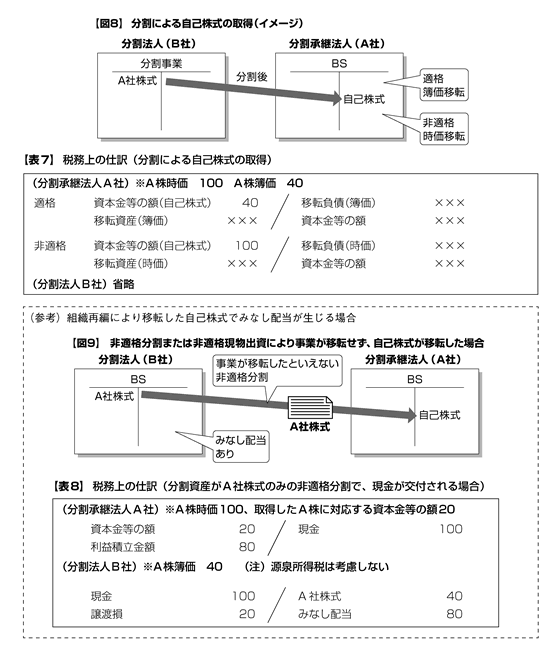
③ 非適格分割または非適格現物出資(事業が移転している場合に限る) 非適格分割または非適格現物出資の場合に、その非適格分割により事業が移転し、かつ、その事業に係る資産のなかに自己株式が含まれている場合(図8参照)。
平成18年税制改正により「事業が移転し」という要件が付け加えられた理由として、会社法における分割の定義が「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を承継させるものとなり、事業の移転を伴わない個別資産の移転も分割に含まれることとなったことによるものと解される。
④ 事業の全部譲受け 事業の全部譲受けにより取得した譲受資産のなかに自己株式が含まれていた場合。
なお、事業の一部譲受けの場合には、みなし配当が生じると解される。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い
① Ⅷ1(1)のうち適格組織再編の場合 被合併法人、分割法人または現物出資法人が移転直前に有する合併法人株式、分割承継法人株式または被現物出資法人株式の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号ロ、123条の3第4項、123条の4、123条の5)(図7・8、表6・7参照)。
② Ⅷ1(1)のうち非適格組織再編および事業の全部譲受けの場合 その自己株式の時価に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ)(図7・8、表6・7参照)。
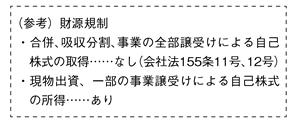
2 再編の対価として自己株式が交付された場合 合併に係る被合併法人の株主、分割型分割に係る分割法人の株主または株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が、組織再編に伴って、それぞれ旧株式と引換えに新株式の交付を受けたときの、その新株式が自己株式に該当する場合の取扱いである。
下記の(1)・(2)の組織再編について、旧株式と引換えに新株式(自己株式)のみが交付される場合には、その自己株式の取得についてはみなし配当の対象外とするとともに、資本金等の額の減少額は旧株式の帳簿価額に基づいて計算するという整理がされている。
(1)合併の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 合併の対価として自己株式が交付された場合とは、合併法人が合併の直前に被合併法人の株式(抱合株式)を有しており、合併に伴い抱合株式に合併法人株式(自己株式)が割り当てられる場合が考えられる(図10・表9参照)。この場合、その割当ての対価として被合併法人が合併法人から「金銭その他の資産の交付」を受けていないことから、その自己株式の取得についてはみなし配当が認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、合併法人(A社)に自己株式を交付した被合併法人(B社)での取扱いである。
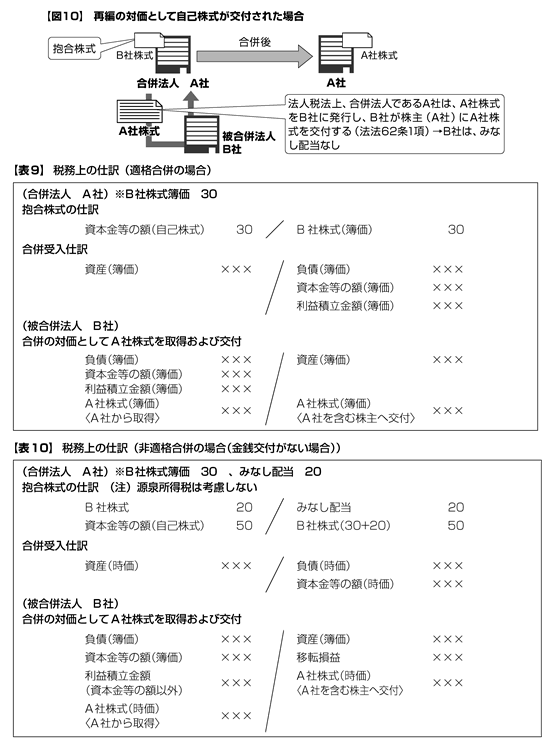
一方で、その合併が非適格合併であり、被合併法人の株主(A社)が被合併法人(B社)から資産(A社株式)の交付を受ける場合には、その被合併法人の株主(A社)は、みなし配当を認識する必要がある(法法24条1項1号)(表10参照)。
なお、合併法人が有する抱合株式については、自己株式の交付をしないこともできるが、法人税法上は、自己株式の交付があったものとみなして、みなし配当の規定が適用される(法法24条2項)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ)。
A)適格合併の場合(法令119条1項5号)
被合併法人株式の合併直前の帳簿価額に相当する金額
B)非適格合併の場合(合併対価が合併法人株式または合併親法人株式のみの場合)(法令119条1項5号)
被合併法人株式の合併直前の帳簿価額に相当する金額に、被合併法人株式の消滅についてみなし配当が生じている場合には、そのみなし配当の金額を加算した金額
C)非適格合併の場合(上記B以外で金銭等の交付がある場合)
合併法人株式の交付の時の時価に相当する金額
(2)分割型分割の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 分割型分割の対価として自己株式が交付される場合とは、次の2つが考えられる。
A)分割法人の株主が分割承継法人である場合に、分割の対価として分割承継法人株式が交付される場合(抱合株式がある場合)(図11・表11参照)
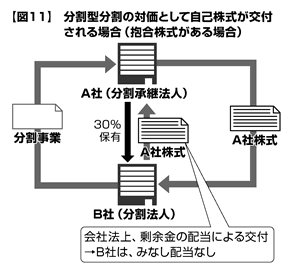
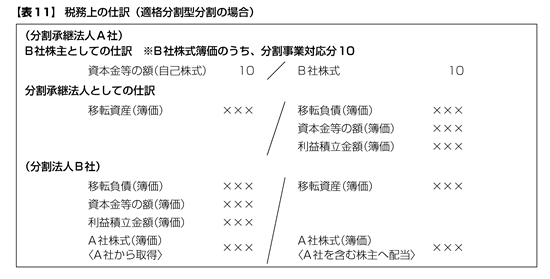
B)分割法人の株主が分割承継親法人である場合に、分割の対価として分割承継親法人株式が交付される場合(三角分割の場合)(図12・表12参照)
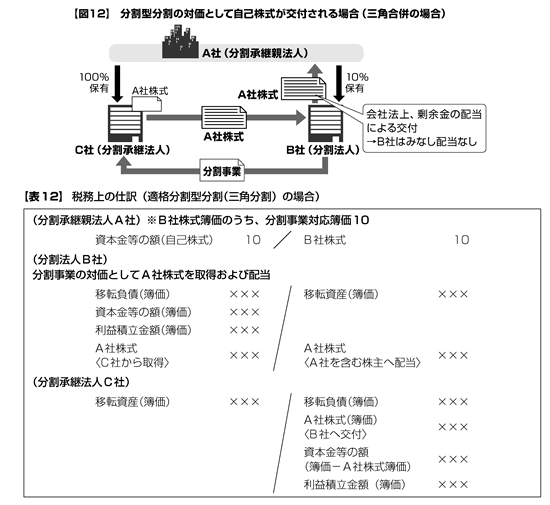
上記Aの分割型分割では、移転資産の対価として分割法人(B社)が分割承継法人(A社)から新株の交付を受け、分割法人(B社)がその分割承継法人の株式(A社株式)を剰余金の配当により分割法人の株主(A社)へ交付する。分割法人(B社)は、その交付の対価として金銭その他の資産の交付を受けないため、みなし配当が認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
一方で、その分割型分割が非適格分割型分割であり、分割法人の株主(A社)が分割法人(B社)から資産(A社株式)の交付を受ける場合には、その分割法人の株主(A社)は、みなし配当を認識する必要がある(法法24条1項2号)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ)。
A)適格分割型分割の場合(法令119条1項6号)
分割法人株式の分割直前の分割純資産対応帳簿価額に相当する金額
B)非適格分割型分割の場合(分割対価が分割承継法人株式または分割承継親法人株式のみの場合)(法令119条1項6号)
分割法人株式の分割直前の分割純資産対応帳簿価額に相当する金額に、分割法人株式の消滅についてみなし配当が生じている場合には、そのみなし配当の金額を加算した金額
C)非適格分割型分割の場合(上記B以外で金銭等の交付がある場合)
分割承継法人株式または分割承継親法人株式の交付の時の時価に相当する金額
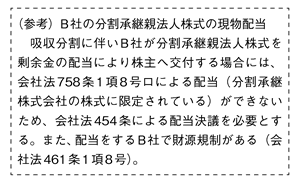
(3)適格分社型分割の場合
① みなし配当の取扱い 分社型分割の対価として自己株式が交付される場合とは、分割承継法人が分割の対価として分割法人の株式を交付する場合である(図13・表13参照)。
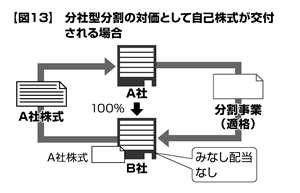
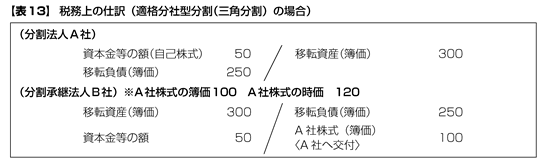
このうち、分割法人が分割承継法人の発行済株式の全部を保有する法人(分割承継親法人)であり、分割の対価として分割承継親法人株式のみが交付され、かつ、その分割が適格分社型分割である場合に限り、その自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項6号)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い その適格分社型分割により分割承継法人に移転をした資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ、119条1項7号)。
(4)株式交換の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 株式交換の対価として自己株式が交付される場合とは、株式交換完全親法人が、株式交換の対価として、株式交換完全子法人の株主の株式を交付する場合である(図14・表14参照)。
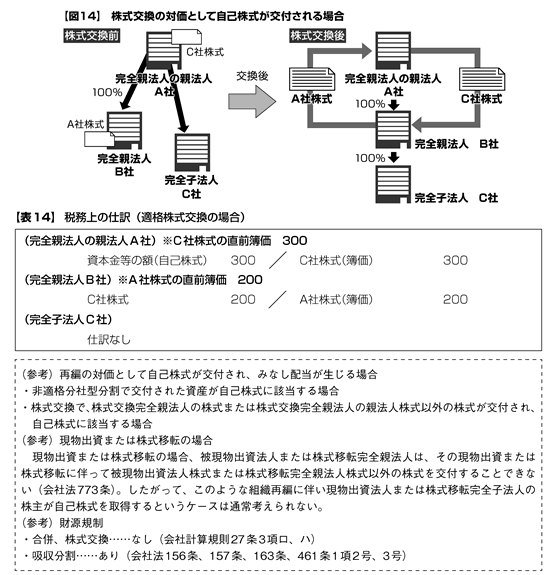
このうち、株式交換完全親法人(B社)の株式を100%保有する法人(株式交換完全親法人の親法人。A社)と株式交換完全子法人(C社)の株主(A社)が同一の法人であり、株式交換の対価として株式交換完全親法人の親法人株式(A社株式)が交付される場合(非適格株式交換であっても同様)に限り、その自己株式の取得については、みなし配当が認識されない(法令23条3項7号、法法61条の2第9項)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い その株式交換完全子法人株式のその株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ、119条1項8号)。
3 合併に反対する被合併法人株主の買取請求に基づく買取りによる取得
(1)みなし配当の取扱い 被合併法人の反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項8号)(図15・表15参照)。
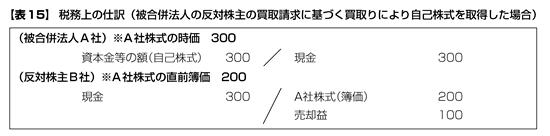
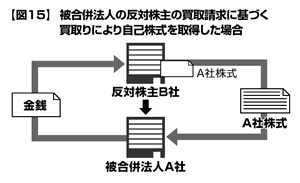 これは、会社法において、反対株主からの買取りの効力発生日は合併の効力発生日(合併日)とされていることに対して(会社法786条5項)、反対株主からの買取額の決定や支払いなどの手続は合併日後に行われること等から、効力発生日においては反対株主からの買取額は決定されておらず、したがって、みなし配当の計算を行い源泉所得税を徴収することが事実上不可能であることから、みなし配当は認識されないものとされている(財務省大臣官房文書課編『平成18年度税制改正の解説』(ファイナンス別冊)264頁(大蔵財務協会、2006年))。
これは、会社法において、反対株主からの買取りの効力発生日は合併の効力発生日(合併日)とされていることに対して(会社法786条5項)、反対株主からの買取額の決定や支払いなどの手続は合併日後に行われること等から、効力発生日においては反対株主からの買取額は決定されておらず、したがって、みなし配当の計算を行い源泉所得税を徴収することが事実上不可能であることから、みなし配当は認識されないものとされている(財務省大臣官房文書課編『平成18年度税制改正の解説』(ファイナンス別冊)264頁(大蔵財務協会、2006年))。
なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得のうち、「被合併法人」の株主のみである。「合併法人」の反対株主の買取請求に基づく買取り、その他の組織再編(分割・株式交換・株式移転)の反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得については、みなし配当が認識される。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減少させることとなる(法令8条1項21号本文)。
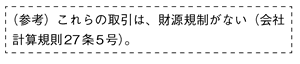
4 組織再編により生じた端株の買取り
(1)みなし配当の取扱い 次の組織再編の場合における端株の買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項9号、法基通1-4-2)。
① 吸収合併において、合併法人が被合併法人の株主に交付する合併法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項5号)
② 新設合併において、新設合併存続会社が新設合併消滅会社の株主に交付する新設合併存続会社株式に端株が生じた場合(会社法234条1項6号)
③ 株式交換において、株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株主に交付する株式交換完全親法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項7号)
④ 株式移転において、株式移転完全親法人が株式移転完全子法人の株主に交付する株式移転完全親法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項8号)
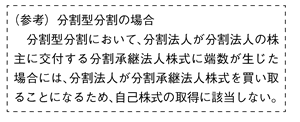
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い それぞれ取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号本文)。
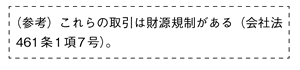
Ⅸ 個人株主の場合のみなし配当の特例
次の取引については、個人株主に限り、みなし配当を生じないとする特例が設けられている。
なお、これらは本来、みなし配当の基因となる自己株式の取得であるものを政策的にみなし配当の対象から除外しているだけであり、自己株式の取得法人においては、自己株式の1株当たりの価額が、その法人の1株当たりの資本金等の額を超えるときは、その超える部分について利益積立金額を減少させる必要がある(法令9条1項10号)。
1 個人株主の上場会社による株式公開買付け(TOB)に伴う譲渡
(1)みなし配当の取扱い 上場会社が行う株式公開買付け(TOB)により、個人株主が発行会社に株式を譲渡した場合は、市場外における相対取引であることから、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、みなし配当が上場会社のTOBに対する阻害要因とならないこと等を目的として、個人株主に限り、特例としてみなし配当の対象外とされている(措法9条の6)(表16参照)。
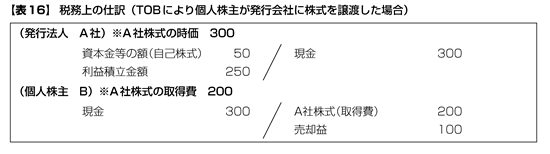
なお、法人株主については、原則どおりみなし配当の対象となるが、これは法人株主については受取配当等の益金不算入(法法23条)の適用があることから、TOBの阻害要因にならないためである。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 1株当たりの資本金等の額に、取得する自己株式の数を乗じて計算した金額(その金額が自己株式の取得について交付した金銭の額を超える場合には交付した金銭の額)だけ資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項20号)。
2 相続等により取得した株式の発行法人への譲渡
(1)みなし配当の取扱い 相続税の納税のため発行会社への自己株式の売却を容易にすることにより、第三者への売却に伴う経営権の分散を防止する観点から、特例措置が設けられた。
相続または遺贈により非上場会社の株式を取得した個人で、その相続等の納付すべき相続税額があるものが、相続に係る申告期限から3年以内に、その株式を発行法人へ譲渡した場合には、みなし配当は認識されない(措法9条の7)(表17参照)。
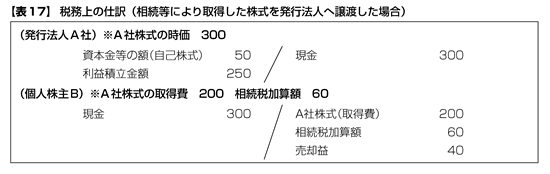
なお、あくまでこの特例の対象となるのは、相続により非上場株式を取得した個人において、納付すべき相続税が生じる場合である。納付すべき相続税が生じない場合には特例の対象にならず、原則どおりみなし配当が生じる。
また、株主においてみなし配当が生じず、譲渡所得のみが生じることから、譲渡所得の特例である取得費加算(措法39条)の適用があることに留意が必要である。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
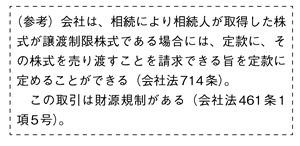
3 保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
(1)みなし配当の取扱い 個人が保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合は、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、その履行に伴い求償権の全部または一部を行使することができない場合は、譲渡所得が非課税とされる取扱いと同様、みなし配当による配当所得もなかったものとされる(所法64条2項、資産税審理研修資料東京国税局課税第一部資産課税課資産評価官「資産税関係質疑応答事例集」平成15年12月)。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
4 強制換価手続が避けられない場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
(1)みなし配当の取扱い 個人が国税通則法2条10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合は、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、この場合譲渡所得が非課税とされる取扱いと同様、みなし配当による配当所得もなかったものとされる(所法69条1項10号、所令26条、資産税審理研修資料東京国税局課税第一部資産課税課資産評価官「資産税関係質疑応答事例集」平成15年12月)。
(2)資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
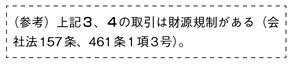
(なかお・たけし/すずき・たつや)
「みなし配当が生じない自己株式の取得」の税務上の取扱い
パートナーズ・コンサルティング 中尾 健
パートナーズ綜合税理士法人 鈴木達也
Ⅰ はじめに
平成18年の会社法の施行に伴い株主総会の普通決議によりいつでも自己株式の取得を行えるようになり(会社法155条、156条、160条、会社法施行規則27条)、同年の税制改正において、自己株式が資産ではなく資本金等の額のマイナス項目として整理された。会社が自己株式を取得した場合には、自己株式を譲渡した側で、税務上、みなし配当と譲渡損益が計上(法法24条1項4号、61条の2)されるが、その例外として、みなし配当が認識されない自己株式の取得が限定列挙されている(法令23条3項)。
今回は、みなし配当が認識されない自己株式の取得を明確化し、自己株式を取得した法人での資本金等の額の取扱いを確認していきたい。
Ⅱ みなし配当の原則的な取扱い
1 みなし配当 法人(A社)の株主等である内国法人(B社)が、その法人(A社)の自己の株式または出資の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合に、自己株式の1株当たりの金銭等の交付額が、その法人(A社)の1株当たりの資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額が配当とみなされる(法法24条1項4号)(図1・表1参照)。
つまり、この規定は株式の売却先が発行法人である場合の売主(B社)の取扱いを規定している。
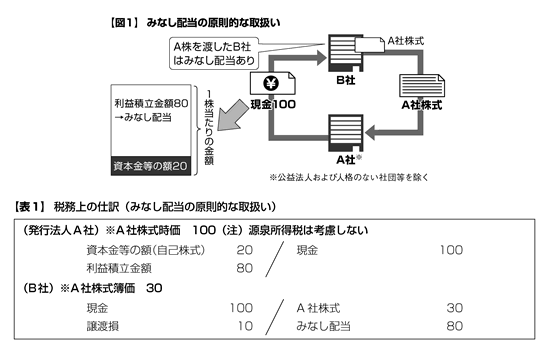
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 自己株式の取得をした法人は、次の金額に相当する資本金等の額を減算する。
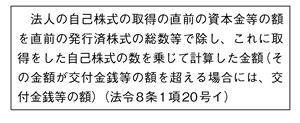
Ⅲ みなし配当の例外的な取扱い
自己株式の取得をした場合でも、その株式を譲渡した側で例外的にみなし配当が認識されないケースがある。ここでは、みなし配当が認識されない自己株式の取得のケースを概説する。
なお、詳細な説明はⅣ以降で行う。
1 みなし配当が認識されない場合 次の原因による自己株式の取得は、みなし配当は認識されず、交付金銭等の額とその株式の帳簿価額の差額は、譲渡損益として認識される。
(1)無対価による自己株式の取得 次の場合には、金銭その他の資産の交付のない自己株式の取得であることから、みなし配当は、認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
① 無償により自己株式を取得した場合
② 剰余金の配当により自己株式が交付された場合
③ 組織変更に伴い自己株式が交付された場合
(2)証券市場等での自己株式の取得 上場市場等またはPTS(私設取引システム)の利用により自己株式を取得する場合は、相対取引と異なり取引の相手方がみえず、みなし配当課税を行うことが困難であることから、みなし配当は認識されない(法令23条3項1号、2号、3号)。
(3)単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得 単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得の場合は、いずれもやむを得ない事由による自己株式の取得であるため、みなし配当は認識されない(法令23条3項9号、10号、11号)。
(4)全部取得条項付種類株式の取得等による自己株式の取得 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による自己株式の取得等で、取得対価として取得する法人の株式のみが交付され、かつ、その交付した株式の価額が取得した株式とおおむね同額である場合は、みなし配当は認識されない(法法24条3項4号括弧書)。また、これらの手続に伴い端株の買取りがあった場合も同様である(法令23条3項10号、11号)。
(5)組織再編による自己株式の取得 次の組織再編による自己株式の取得は、それぞれ次の理由によりみなし配当は認識されない。
① 事業の移転に伴う組織再編で、移転を受けた資産に自己株式が含まれている場合 事業の移転に伴う自己株式の取得であり、その移転対価の交付が利益の分配としての性格を有しているとは考えられないためである(法令23条3項4号、5号)。
② 再編の対価として自己株式が交付された場合 合併法人等が抱合株式に対して自己株式の交付を受けた場合に、その交付をした法人がその交付対価として、金銭その他の資産を受けていないことが理由となる(法法24条1項本文適用対象外)。その他、一定の組織再編による自己株式の取得の場合においてもみなし配当が認識されない(法令23条3項6号、7号)。
③ 合併に反対する被合併法人株主の買取請求に基づく買取りによる取得 反対株主からの買取りの効力発生日が合併日であること等から、効力発生日においてみなし配当の計算を行い、源泉所得税を徴収することが事実上不可能であるためである(法令23条3項8号)。
(6)個人株主からの自己株式の取得の特例 次の場合には、政策的な理由から、みなし配当は認識されない。
① 個人株主が株式公開買付(TOB)において発行法人へ自己株式を譲渡した場合
② 相続等により取得した株式を発行法人へ譲渡した場合
③ 保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
④ 強制換価手続が避けられない場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い(法令8条1項21号) 原則的には、その取得の対価の額または時価に相当する金額の資本金等の額を減算する。
ただし、次の事由により自己株式を取得したときは、直前の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算する。
① 組織再編や種類株式の取得で旧株の譲渡損益が繰り延べられるもの
② 適格組織再編による移転
Ⅳ 無対価による自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い 次に掲げる取引は、発行法人(A社)で自己株式の取得に当たるものの、相手方(B社)がその法人(A社)から「金銭その他の資産の交付を受け」ていないため、みなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
(1)無償取得 発行法人(A社)が自己株式を無償で取得した場合には、取得に伴って金銭その他の資産の交付が行われないことからみなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)(図2・表2参照)。
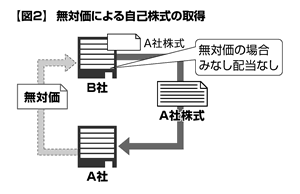
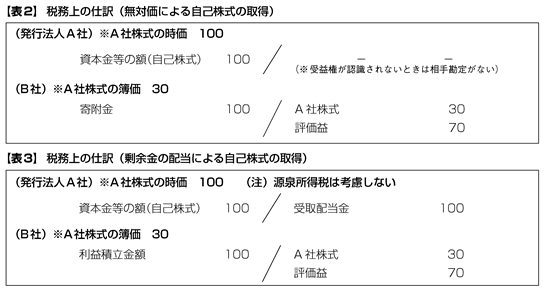
無償でA社株式を渡したB社では、A社株式の時価相当額を寄附したものとして処理する。また、無償で取得したA社では、原則として受贈益を認識する必要はないものの何らかの利益移転の目的がある場合には、受贈益を認識し課税されることもあると思われる(由比祝生編『税務相談事例集(平成19年版)』100頁(大蔵財務協会、2007年))。
(2)剰余金の配当による自己株式の取得 剰余金の配当による配当財産として自己株式の取得をした場合には、配当をした法人が金銭その他の資産の交付を受けていないことからみなし配当は認識されない。また、解散による残余財産の分配(会社法504条、505条)も会社法施行後、現物で行えることとなったため、同様の取扱いとなる(図3・表3参照)。
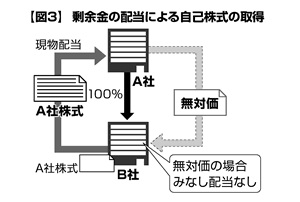
具体例としては、100%子会社が親会社株式を有する場合に、その親会社株式を現物配当する場合が考えられ、2009年3月にケンウッドが保有する親会社(JVC・ケンウッド・ホールディングス)の株式11.3%分をケンウッドからの現物配当により親会社が取得したケースがある。
なお、現物配当は、税務上、時価で譲渡したものとして扱われる。一方、会計上は企業集団内の企業に対して現物配当する場合には、適正な帳簿価額で剰余金を減額することとなる(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針10(3))。この場合には、税務調整が必要となる。
(3)組織変更に伴い交付された自己株式の取得 法人の株主または社員が、その法人の組織変更に伴う金銭等の交付として自己株式(A社株式)の交付を受けた場合には、その交付に伴いB社がA社から金銭その他の資産を受けていないことからB社ではみなし配当は認識されない(法法24条1項本文適用対象外)(図4・表4参照)。
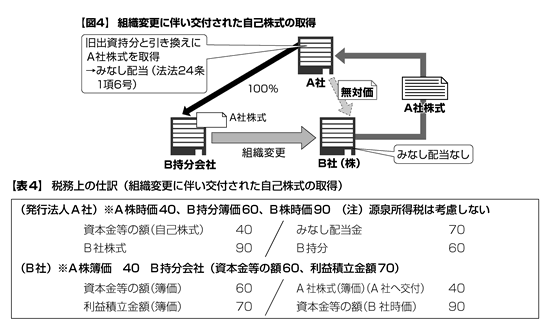
具体的には、B持分会社が既にA社株式を有しており、B株式会社への組織変更の際、社員(出資者A社)に対し、B社株式とともにA社株式を交付する場合が考えられる。
なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、法人の組織変更に伴って社員(A社)に自己株式(A社株式)を交付した法人(B社)の取扱いである。一方、その法人(B社)が新株式または新出資持分以外の金銭等を交付する場合には、その社員(A社)はみなし配当を認識する必要がある(法法24条1項6号)。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 自己株式の取得時の時価に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ、119条1項25号)。
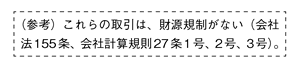
Ⅴ 証券市場等での自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い 下記の取引による自己株式の取得は、相対取引とは異なり、証券会社が仲介を行うなどにより取引の相手方がみえないため、みなし配当として課税することが事実上、困難であるとの理由から、みなし配当は認識されない(図5・表5参照)。
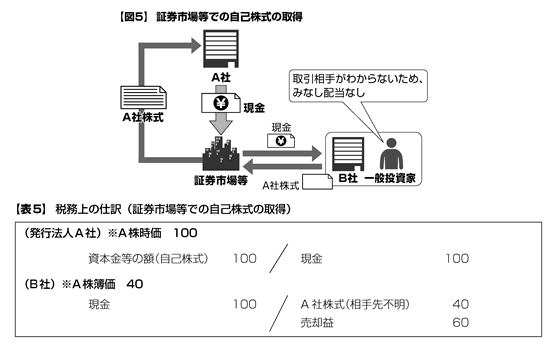
(1)上場市場における購入による取得(法令23条3項1号)
金融商品取引法2条16項に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による自己株式の取得をいう。これには、時間内取引のほか、立会外取引(ToSTNeT-2、ToSTNeT-3等)も含まれる。
一方、公開買付けによる自己株式の取得は、市場外で株式の買付け等を行う取引であることから、これに含まれない。また、グリーンシート市場は日本証券業協会が、非上場企業の株式を売買するために創設したもので、金融商品取引法上の金融商品取引所とは異なるため、これに含まれない。
(2)店頭売買登録銘柄の店頭売買による取得(法令23条3項2号)
店頭売買登録銘柄として登録された株式のその店頭売買による購入に係る自己株式の取得をいう。なお、2004年に旧株式会社ジャスダックが金融商品取引所としての認定を受けて以降、店頭売買取引は行われていない。
(3)PTS(私設取引システム)の利用による取得(法令23条3項3号)
PTS(私設取引システム)を利用した取引による自己株式の取得をいう。なおPTS取引とは、金融商品取引所を通さずに、証券会社が独自に開設したネットワーク上の私設取引所において、証券会社を仲介等として行う売買取引(夜間取引など)をいう。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号本文)。
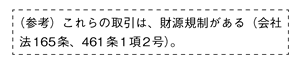
Ⅵ 単元未満株式・端株の買取りによる自己株式の取得
1 単元未満株式および端株(後述2、3を除く)の買取り
(1)みなし配当の取扱い 次の場合の単元未満株式および端株の買取りによる自己株式の取得については、みなし配当は認識されない(法令23条3項9号)。
単元未満株式については、単元株制度において株主総会の議決権が制限されていることから、株主は発行会社へ買取請求を行うことが可能とされている(会社法189条1項、会社法192条1項)。また、端株に関しては平成17年度商法改正において端株制度が廃止されている。このように、発行法人による単元未満株式または端株の取得は、いずれもやむを得ない事情によるものであり、そのような取引にみなし配当課税を行うことは適当でない等の理由からみなし配当の対象外とされている。
① 単元未満株主からの買取請求に基づく自己株式の取得の場合(会社法192条1項)
② 株式の無償割当てにおいて、その法人の株主に無償割当てする株式に端株が生じた場合(会社法185条、234条1項3号)
③ 取得条項付新株予約権の取得事由が生じたことにより、新株予約権者に交付する株式に端株が生じた場合(会社法275条1項、234条1項4号)
④ 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により、新株予約権者に交付する株式に端数が生じた場合(会社法283条、法法61条の2第14項4号、法令23条3項11号、119条の8の2)
⑤ 株式の分割または株式の併合において、その株式の数に端株が生じた場合(会社法235条)
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号本文)。
2 全部取得条項付種類株式の端株の買取り 後述Ⅶを参照されたい。
3 組織再編により生じた端株の買取り 後述Ⅷ4を参照されたい。
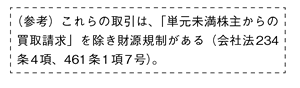
Ⅶ 全部取得条項付種類株式の取得等による自己株式の取得
1 みなし配当の取扱い (1)取得対価として取得する法人の株式のみが交付される場合 次の事由により自己株式を取得した場合に、その取得対価としてその法人の株式のみが交付され、かつ、その交付した株式の価額が取得した株式とおおむね同額であるときは、みなし配当は認識されない(法法24条3項4号、61条の2第14項)(図6参照)。
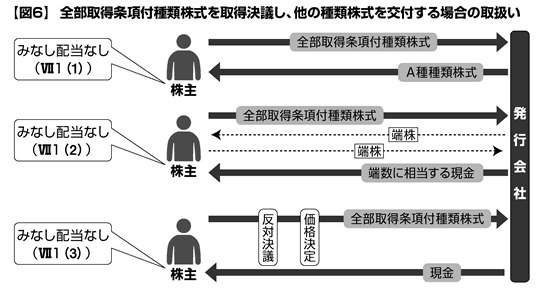
① 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による取得(法法24条3項4号、61条の2第14項3号)
② 取得条項付株式の取得事由が生じたことによる取得(法法24条3項4号、61条の2第14項2号)
③ 取得請求権付株式の請求権の行使による取得(法法24条3項4号括弧書、61条の2第14項1号)
(2)端株の買取りの場合 上記(1)に掲げる株式を取得する場合において、株主に交付する株式に端株が生じたときのその端株の買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項9号、23条3項11号、119条の8の2、会社法167条3項、170条1項、173条1項、234条1項1号、2号)(図6参照)。
(3)取得価額の決定の申立ての場合 全部取得条項付種類株式の取得決議において、その取得対価としてその株主等にその取得をする法人の株式のみが交付され、かつ、その株式の価額が取得される株式とおおむね同額である場合には、その取得価額の決定の申立てをした株主について、その株主が取得価額の決定の申立てをしなかったと仮定した場合に交付することとなる株式に端株が生じるときは、本来であれば上記(2)の規定の適用はないこととなる(図6参照)。
しかしながら、取得価額の決定の申立てをしていない株主(上記(2)の株主)の処理との平仄を合わせる理由から、その端株になると仮定される部分の買取りによる金銭の交付についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項10号)。
2 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い
(1)Ⅶ1(1)の場合 取得する種類株式に係る種類資本金額をその種類株式と同じ種類の株式の総数で除し、これに取得をした種類株式の数を乗じて計算した金額を、その種類株式に係る種類資本金額から減算するとともに、新たに交付する株式に係る種類資本金額に加算する(法令8条5項)。
(2)Ⅶ1(2)および(3)の場合 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減少させることとなる(法令8条1項21号本文)。
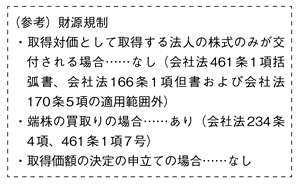
Ⅷ 組織再編による自己株式の取得
1 組織再編により移転を受けた資産に自己株式が含まれている場合
(1)みなし配当の取扱い 次の組織再編(下記①~④)により自己株式の移転を受けた場合には、事業の移転に伴い自己株式を取得しており、利益の分配としての性格を有していないため、みなし配当は認識されない(法令23条3項4号、5号)。
ただし、非適格再編において、事業が移転せず自己株式だけが移転しているような場合には、会社分割または現物出資という制度を利用しているが、その実質は自己株式の譲渡となんら変らないことから、みなし配当が認識される。
① 合併(適格非適格共通) 合併法人が適格合併または非適格合併により被合併法人から移転を受けた資産のなかに自己株式が含まれている場合(図7参照)。
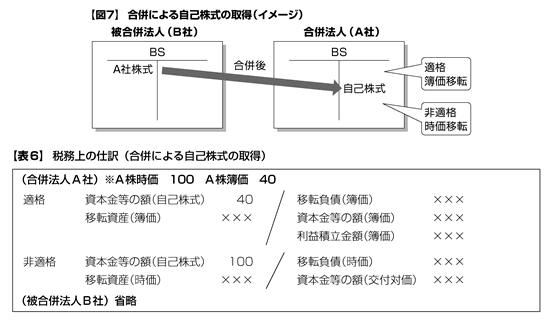
② 適格分割または適格現物出資 適格分割または適格現物出資により、分割承継法人または被現物出資法人が分割法人または現物出資法人から移転を受けた資産のなかに自己株式が含まれている場合(図8参照)。
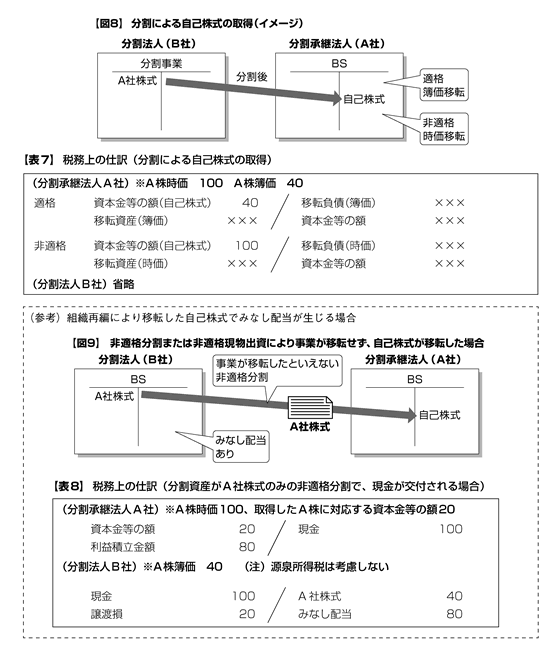
③ 非適格分割または非適格現物出資(事業が移転している場合に限る) 非適格分割または非適格現物出資の場合に、その非適格分割により事業が移転し、かつ、その事業に係る資産のなかに自己株式が含まれている場合(図8参照)。
平成18年税制改正により「事業が移転し」という要件が付け加えられた理由として、会社法における分割の定義が「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を承継させるものとなり、事業の移転を伴わない個別資産の移転も分割に含まれることとなったことによるものと解される。
④ 事業の全部譲受け 事業の全部譲受けにより取得した譲受資産のなかに自己株式が含まれていた場合。
なお、事業の一部譲受けの場合には、みなし配当が生じると解される。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い
① Ⅷ1(1)のうち適格組織再編の場合 被合併法人、分割法人または現物出資法人が移転直前に有する合併法人株式、分割承継法人株式または被現物出資法人株式の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号ロ、123条の3第4項、123条の4、123条の5)(図7・8、表6・7参照)。
② Ⅷ1(1)のうち非適格組織再編および事業の全部譲受けの場合 その自己株式の時価に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ)(図7・8、表6・7参照)。
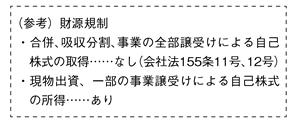
2 再編の対価として自己株式が交付された場合 合併に係る被合併法人の株主、分割型分割に係る分割法人の株主または株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が、組織再編に伴って、それぞれ旧株式と引換えに新株式の交付を受けたときの、その新株式が自己株式に該当する場合の取扱いである。
下記の(1)・(2)の組織再編について、旧株式と引換えに新株式(自己株式)のみが交付される場合には、その自己株式の取得についてはみなし配当の対象外とするとともに、資本金等の額の減少額は旧株式の帳簿価額に基づいて計算するという整理がされている。
(1)合併の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 合併の対価として自己株式が交付された場合とは、合併法人が合併の直前に被合併法人の株式(抱合株式)を有しており、合併に伴い抱合株式に合併法人株式(自己株式)が割り当てられる場合が考えられる(図10・表9参照)。この場合、その割当ての対価として被合併法人が合併法人から「金銭その他の資産の交付」を受けていないことから、その自己株式の取得についてはみなし配当が認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、合併法人(A社)に自己株式を交付した被合併法人(B社)での取扱いである。
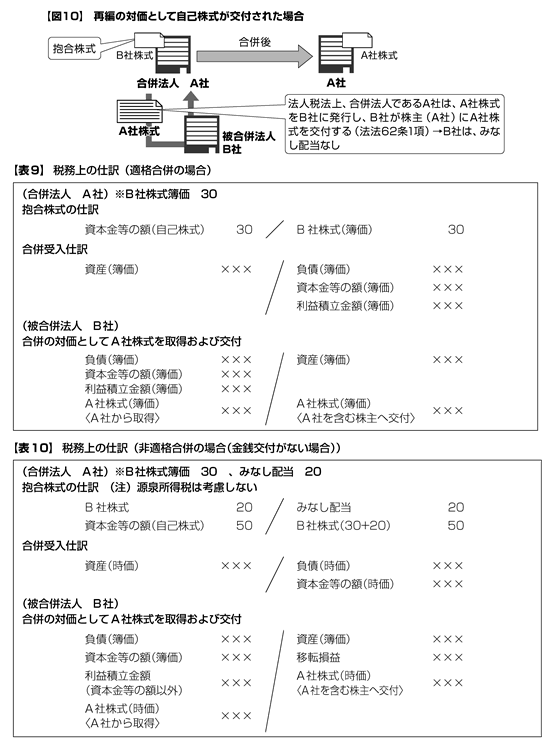
一方で、その合併が非適格合併であり、被合併法人の株主(A社)が被合併法人(B社)から資産(A社株式)の交付を受ける場合には、その被合併法人の株主(A社)は、みなし配当を認識する必要がある(法法24条1項1号)(表10参照)。
なお、合併法人が有する抱合株式については、自己株式の交付をしないこともできるが、法人税法上は、自己株式の交付があったものとみなして、みなし配当の規定が適用される(法法24条2項)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ)。
A)適格合併の場合(法令119条1項5号)
被合併法人株式の合併直前の帳簿価額に相当する金額
B)非適格合併の場合(合併対価が合併法人株式または合併親法人株式のみの場合)(法令119条1項5号)
被合併法人株式の合併直前の帳簿価額に相当する金額に、被合併法人株式の消滅についてみなし配当が生じている場合には、そのみなし配当の金額を加算した金額
C)非適格合併の場合(上記B以外で金銭等の交付がある場合)
合併法人株式の交付の時の時価に相当する金額
(2)分割型分割の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 分割型分割の対価として自己株式が交付される場合とは、次の2つが考えられる。
A)分割法人の株主が分割承継法人である場合に、分割の対価として分割承継法人株式が交付される場合(抱合株式がある場合)(図11・表11参照)
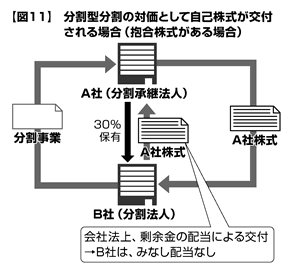
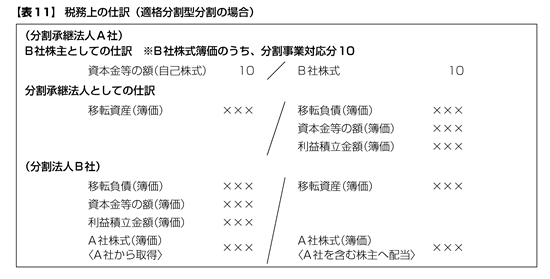
B)分割法人の株主が分割承継親法人である場合に、分割の対価として分割承継親法人株式が交付される場合(三角分割の場合)(図12・表12参照)
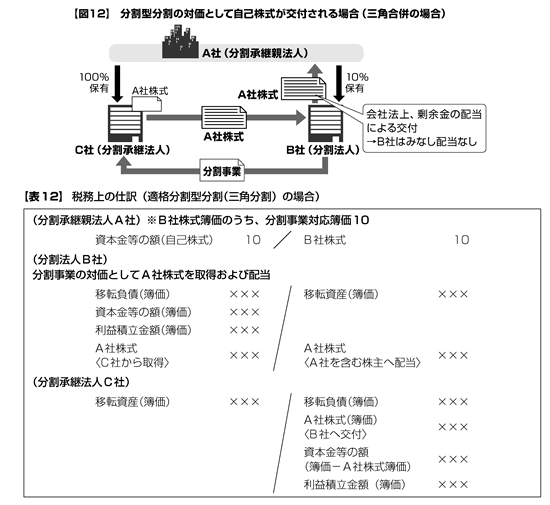
上記Aの分割型分割では、移転資産の対価として分割法人(B社)が分割承継法人(A社)から新株の交付を受け、分割法人(B社)がその分割承継法人の株式(A社株式)を剰余金の配当により分割法人の株主(A社)へ交付する。分割法人(B社)は、その交付の対価として金銭その他の資産の交付を受けないため、みなし配当が認識されない(法法24条1項本文適用対象外)。
一方で、その分割型分割が非適格分割型分割であり、分割法人の株主(A社)が分割法人(B社)から資産(A社株式)の交付を受ける場合には、その分割法人の株主(A社)は、みなし配当を認識する必要がある(法法24条1項2号)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める金額の資本金等の額を減算する(法令8条1項21号イ)。
A)適格分割型分割の場合(法令119条1項6号)
分割法人株式の分割直前の分割純資産対応帳簿価額に相当する金額
B)非適格分割型分割の場合(分割対価が分割承継法人株式または分割承継親法人株式のみの場合)(法令119条1項6号)
分割法人株式の分割直前の分割純資産対応帳簿価額に相当する金額に、分割法人株式の消滅についてみなし配当が生じている場合には、そのみなし配当の金額を加算した金額
C)非適格分割型分割の場合(上記B以外で金銭等の交付がある場合)
分割承継法人株式または分割承継親法人株式の交付の時の時価に相当する金額
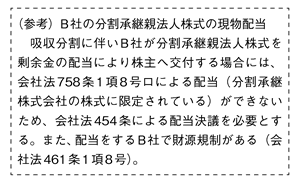
(3)適格分社型分割の場合
① みなし配当の取扱い 分社型分割の対価として自己株式が交付される場合とは、分割承継法人が分割の対価として分割法人の株式を交付する場合である(図13・表13参照)。
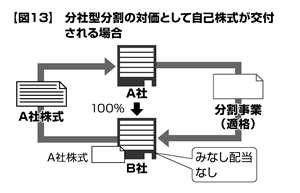
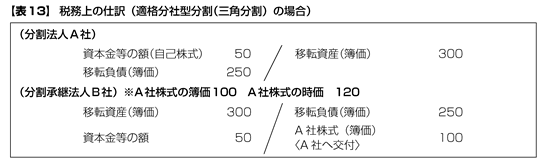
このうち、分割法人が分割承継法人の発行済株式の全部を保有する法人(分割承継親法人)であり、分割の対価として分割承継親法人株式のみが交付され、かつ、その分割が適格分社型分割である場合に限り、その自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項6号)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い その適格分社型分割により分割承継法人に移転をした資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ、119条1項7号)。
(4)株式交換の場合(適格非適格共通)
① みなし配当の取扱い 株式交換の対価として自己株式が交付される場合とは、株式交換完全親法人が、株式交換の対価として、株式交換完全子法人の株主の株式を交付する場合である(図14・表14参照)。
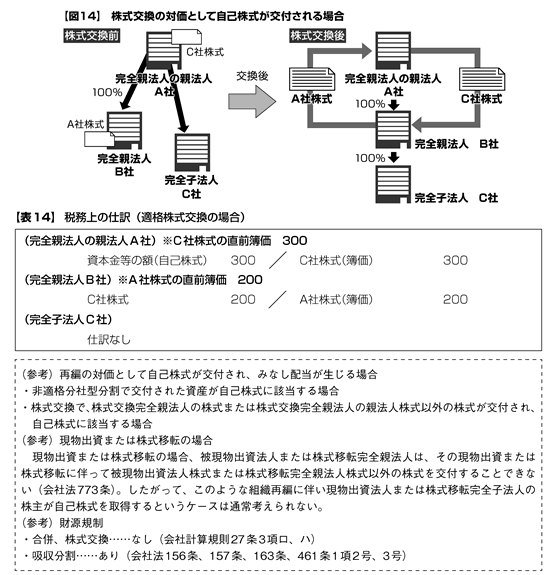
このうち、株式交換完全親法人(B社)の株式を100%保有する法人(株式交換完全親法人の親法人。A社)と株式交換完全子法人(C社)の株主(A社)が同一の法人であり、株式交換の対価として株式交換完全親法人の親法人株式(A社株式)が交付される場合(非適格株式交換であっても同様)に限り、その自己株式の取得については、みなし配当が認識されない(法令23条3項7号、法法61条の2第9項)。
② 自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い その株式交換完全子法人株式のその株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号イ、119条1項8号)。
3 合併に反対する被合併法人株主の買取請求に基づく買取りによる取得
(1)みなし配当の取扱い 被合併法人の反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項8号)(図15・表15参照)。
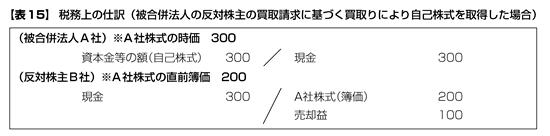
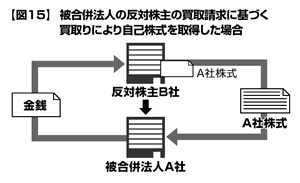 これは、会社法において、反対株主からの買取りの効力発生日は合併の効力発生日(合併日)とされていることに対して(会社法786条5項)、反対株主からの買取額の決定や支払いなどの手続は合併日後に行われること等から、効力発生日においては反対株主からの買取額は決定されておらず、したがって、みなし配当の計算を行い源泉所得税を徴収することが事実上不可能であることから、みなし配当は認識されないものとされている(財務省大臣官房文書課編『平成18年度税制改正の解説』(ファイナンス別冊)264頁(大蔵財務協会、2006年))。
これは、会社法において、反対株主からの買取りの効力発生日は合併の効力発生日(合併日)とされていることに対して(会社法786条5項)、反対株主からの買取額の決定や支払いなどの手続は合併日後に行われること等から、効力発生日においては反対株主からの買取額は決定されておらず、したがって、みなし配当の計算を行い源泉所得税を徴収することが事実上不可能であることから、みなし配当は認識されないものとされている(財務省大臣官房文書課編『平成18年度税制改正の解説』(ファイナンス別冊)264頁(大蔵財務協会、2006年))。なお、ここでみなし配当が認識されないとされるのは、反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得のうち、「被合併法人」の株主のみである。「合併法人」の反対株主の買取請求に基づく買取り、その他の組織再編(分割・株式交換・株式移転)の反対株主の買取請求に基づく買取りによる自己株式の取得については、みなし配当が認識される。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減少させることとなる(法令8条1項21号本文)。
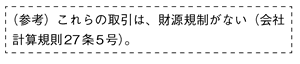
4 組織再編により生じた端株の買取り
(1)みなし配当の取扱い 次の組織再編の場合における端株の買取りによる自己株式の取得についてはみなし配当は認識されない(法令23条3項9号、法基通1-4-2)。
① 吸収合併において、合併法人が被合併法人の株主に交付する合併法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項5号)
② 新設合併において、新設合併存続会社が新設合併消滅会社の株主に交付する新設合併存続会社株式に端株が生じた場合(会社法234条1項6号)
③ 株式交換において、株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株主に交付する株式交換完全親法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項7号)
④ 株式移転において、株式移転完全親法人が株式移転完全子法人の株主に交付する株式移転完全親法人株式に端株が生じた場合(会社法234条1項8号)
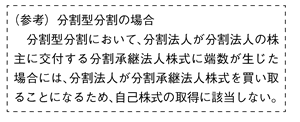
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い それぞれ取得対価の額に相当する金額の資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項21号本文)。
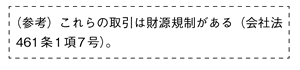
Ⅸ 個人株主の場合のみなし配当の特例
次の取引については、個人株主に限り、みなし配当を生じないとする特例が設けられている。
なお、これらは本来、みなし配当の基因となる自己株式の取得であるものを政策的にみなし配当の対象から除外しているだけであり、自己株式の取得法人においては、自己株式の1株当たりの価額が、その法人の1株当たりの資本金等の額を超えるときは、その超える部分について利益積立金額を減少させる必要がある(法令9条1項10号)。
1 個人株主の上場会社による株式公開買付け(TOB)に伴う譲渡
(1)みなし配当の取扱い 上場会社が行う株式公開買付け(TOB)により、個人株主が発行会社に株式を譲渡した場合は、市場外における相対取引であることから、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、みなし配当が上場会社のTOBに対する阻害要因とならないこと等を目的として、個人株主に限り、特例としてみなし配当の対象外とされている(措法9条の6)(表16参照)。
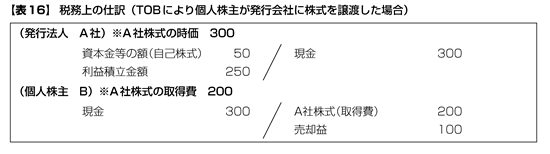
なお、法人株主については、原則どおりみなし配当の対象となるが、これは法人株主については受取配当等の益金不算入(法法23条)の適用があることから、TOBの阻害要因にならないためである。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 1株当たりの資本金等の額に、取得する自己株式の数を乗じて計算した金額(その金額が自己株式の取得について交付した金銭の額を超える場合には交付した金銭の額)だけ資本金等の額を減算することとなる(法令8条1項20号)。
2 相続等により取得した株式の発行法人への譲渡
(1)みなし配当の取扱い 相続税の納税のため発行会社への自己株式の売却を容易にすることにより、第三者への売却に伴う経営権の分散を防止する観点から、特例措置が設けられた。
相続または遺贈により非上場会社の株式を取得した個人で、その相続等の納付すべき相続税額があるものが、相続に係る申告期限から3年以内に、その株式を発行法人へ譲渡した場合には、みなし配当は認識されない(措法9条の7)(表17参照)。
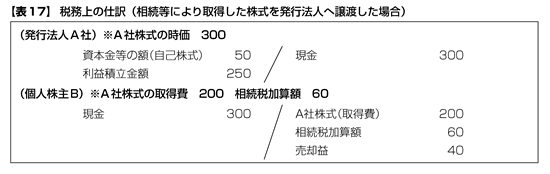
なお、あくまでこの特例の対象となるのは、相続により非上場株式を取得した個人において、納付すべき相続税が生じる場合である。納付すべき相続税が生じない場合には特例の対象にならず、原則どおりみなし配当が生じる。
また、株主においてみなし配当が生じず、譲渡所得のみが生じることから、譲渡所得の特例である取得費加算(措法39条)の適用があることに留意が必要である。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
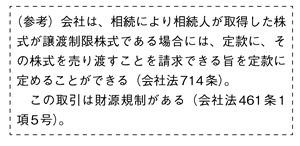
3 保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
(1)みなし配当の取扱い 個人が保証債務を履行するために発行法人へ自己株式を譲渡した場合は、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、その履行に伴い求償権の全部または一部を行使することができない場合は、譲渡所得が非課税とされる取扱いと同様、みなし配当による配当所得もなかったものとされる(所法64条2項、資産税審理研修資料東京国税局課税第一部資産課税課資産評価官「資産税関係質疑応答事例集」平成15年12月)。
(2)自己株式を取得した法人の資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
4 強制換価手続が避けられない場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合
(1)みなし配当の取扱い 個人が国税通則法2条10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合に債務の弁済に充てるために発行法人へ自己株式を譲渡した場合は、原則としてみなし配当の対象となる。しかし、この場合譲渡所得が非課税とされる取扱いと同様、みなし配当による配当所得もなかったものとされる(所法69条1項10号、所令26条、資産税審理研修資料東京国税局課税第一部資産課税課資産評価官「資産税関係質疑応答事例集」平成15年12月)。
(2)資本金等の額の取扱い 上記1(2)と同様である。
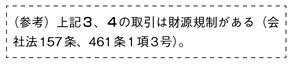
(なかお・たけし/すずき・たつや)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























