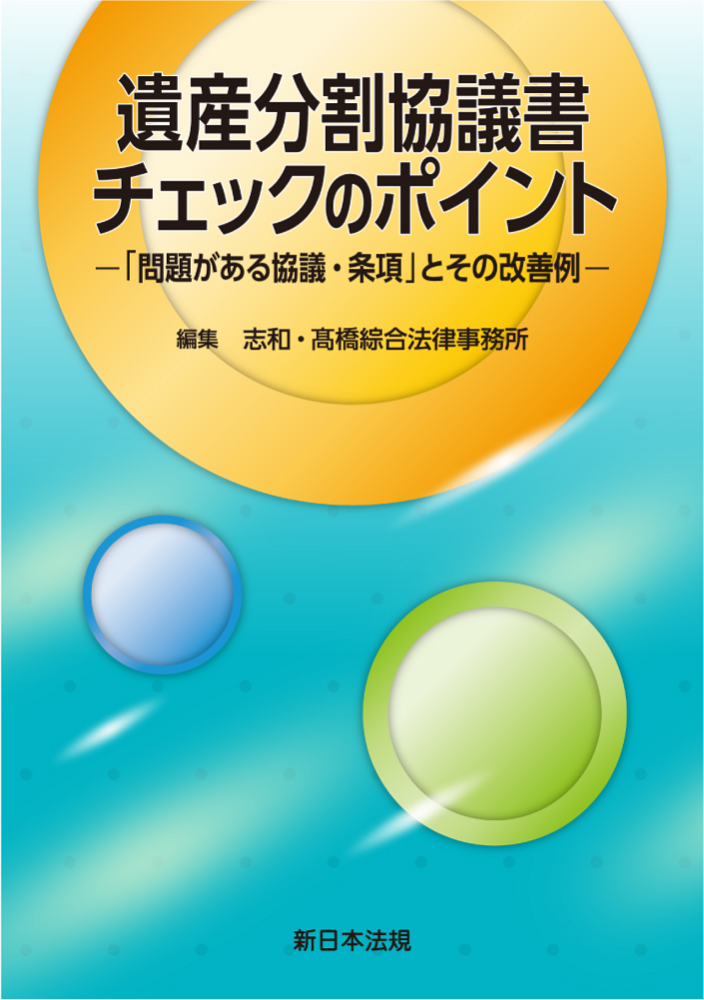コラム2009年10月05日 【SCOPE】 財務諸表の表示の論点整理へのコメントと今後の方向性(2009年10月5日号・№324)
ASBJ、平成21年中に会計基準案を公表へ
財務諸表の表示の論点整理へのコメントと今後の方向性
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月25日、財務諸表表示専門委員会を開催し、9月7日まで意見募集を行っていた「財務諸表の表示に関する論点の整理」(石原宏司・本誌319号13頁参照)に対するコメントについて検討した。包括利益の表示については、現行と同様の当期純利益との併存を前提に、導入する意見が大勢を占めている。今回のスコープでは寄せられたコメントとその後のASBJ事務局の検討方針を紹介する(表参照)。
なお、同委員会では、包括利益の表示や非継続事業等を含む財務諸表の表示に関する会計基準案を今年中に公表し、平成22年3月頃までに正式決定する予定だ。
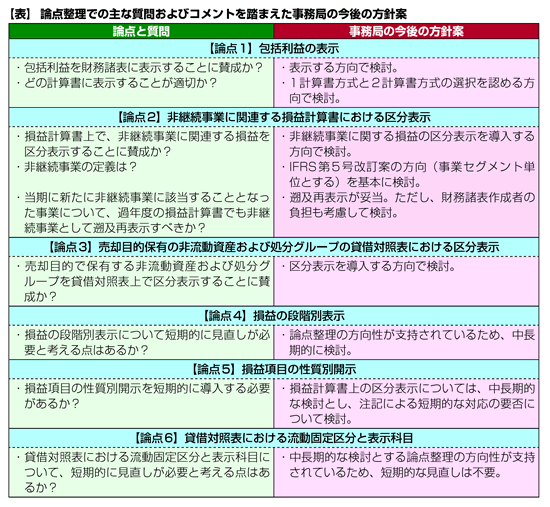
2計算書方式を支持する意見が多数も1計算書方式の選択も可 まず、論点1となる包括利益の表示については、日本公認会計士協会、日本証券アナリスト協会、全国銀行協会など、当期純利益との併存を前提として、包括利益の表示を導入するという論点整理の基本的方向性を支持する意見が大勢を占めている。
また、包括利益を表示する際の計算書については、日本貿易会、日本経済団体連合会、日本公認会計士協会など、2つの計算書(当期純利益の内訳を表示する第1の計算書と、当期純利益から始めてその他の包括利益の内訳を表示する第2の計算書)で表示する第2計算書方式を支持する意見が多かった。
ただし、企業会計基準委員会の事務局では、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準が1計算書方式(単一の包括利益計算書で表示)に1本化する可能性があることなどを考慮し、両者の選択を認める方向で検討するとしている。
非継続事業に関する損益の区分表示を導入する方向 論点2の非継続事業(いわゆる廃止事業)に関連する損益の損益計算書における区分表示については、日本貿易会、日本公認会計士協会など、その開示に賛成する意見が多かった。国際的な比較可能性を高めるだけでなく、投資家の将来予測に資する情報の提供からも必要などとする賛成意見が寄せられている。
事務局でも非継続事業に関する損益の区分表示を導入する方向で検討するとしている。
非継続事業の定義については、論点整理の42項で示されたとおり、IFRS第5号改訂案の方向(事業セグメントを単位とする)を基本とすることに賛成する意見が多く、この方向で検討するとしている。
また、当期に新たに非継続事業に該当することになった事業について、過年度の損益計算書でも非継続事業として遡及再表示すべきかどうかに関しては、会計基準のコンバージェンスの観点から遡及再表示が妥当と考えられるとしている。
貸借対照表における区分表示も 論点3の売却目的保有の非流動資産および処分グループの貸借対照表における区分表示については、日本貿易会、日本公認会計士協会などから、区分表示することに賛成する意見が寄せられている。このため、事務局では、区分表示を導入する方向で検討するとしている。
中長期的に検討 そのほか、論点4~6については、論点整理の方向性がほぼ支持されており、中長期的な検討を行う方向となっている。
IFRSの非継続事業とは? 平成20年9月にIASBが公表した公開草案「非継続事業(IFRS第5号の改訂案)」では、非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されている企業の構成単位であるとし、そのうえで、①事業セグメントであり、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されているもの、②取得時に売却目的保有としての分類要件を満たしている事業のいずれかの要件を満たすものと定義されている。
財務諸表の表示の論点整理へのコメントと今後の方向性
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月25日、財務諸表表示専門委員会を開催し、9月7日まで意見募集を行っていた「財務諸表の表示に関する論点の整理」(石原宏司・本誌319号13頁参照)に対するコメントについて検討した。包括利益の表示については、現行と同様の当期純利益との併存を前提に、導入する意見が大勢を占めている。今回のスコープでは寄せられたコメントとその後のASBJ事務局の検討方針を紹介する(表参照)。
なお、同委員会では、包括利益の表示や非継続事業等を含む財務諸表の表示に関する会計基準案を今年中に公表し、平成22年3月頃までに正式決定する予定だ。
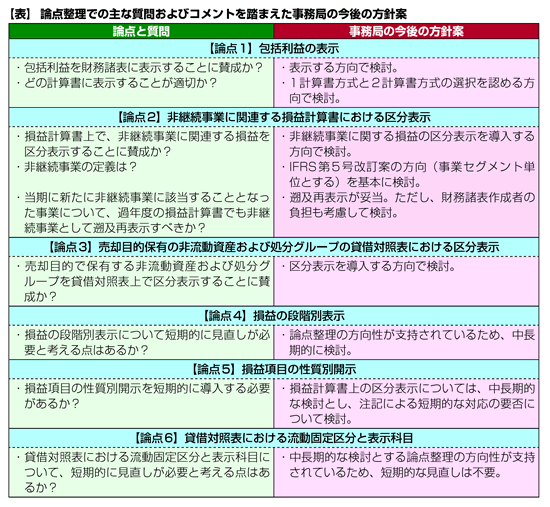
2計算書方式を支持する意見が多数も1計算書方式の選択も可 まず、論点1となる包括利益の表示については、日本公認会計士協会、日本証券アナリスト協会、全国銀行協会など、当期純利益との併存を前提として、包括利益の表示を導入するという論点整理の基本的方向性を支持する意見が大勢を占めている。
また、包括利益を表示する際の計算書については、日本貿易会、日本経済団体連合会、日本公認会計士協会など、2つの計算書(当期純利益の内訳を表示する第1の計算書と、当期純利益から始めてその他の包括利益の内訳を表示する第2の計算書)で表示する第2計算書方式を支持する意見が多かった。
ただし、企業会計基準委員会の事務局では、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準が1計算書方式(単一の包括利益計算書で表示)に1本化する可能性があることなどを考慮し、両者の選択を認める方向で検討するとしている。
非継続事業に関する損益の区分表示を導入する方向 論点2の非継続事業(いわゆる廃止事業)に関連する損益の損益計算書における区分表示については、日本貿易会、日本公認会計士協会など、その開示に賛成する意見が多かった。国際的な比較可能性を高めるだけでなく、投資家の将来予測に資する情報の提供からも必要などとする賛成意見が寄せられている。
事務局でも非継続事業に関する損益の区分表示を導入する方向で検討するとしている。
非継続事業の定義については、論点整理の42項で示されたとおり、IFRS第5号改訂案の方向(事業セグメントを単位とする)を基本とすることに賛成する意見が多く、この方向で検討するとしている。
また、当期に新たに非継続事業に該当することになった事業について、過年度の損益計算書でも非継続事業として遡及再表示すべきかどうかに関しては、会計基準のコンバージェンスの観点から遡及再表示が妥当と考えられるとしている。
貸借対照表における区分表示も 論点3の売却目的保有の非流動資産および処分グループの貸借対照表における区分表示については、日本貿易会、日本公認会計士協会などから、区分表示することに賛成する意見が寄せられている。このため、事務局では、区分表示を導入する方向で検討するとしている。
中長期的に検討 そのほか、論点4~6については、論点整理の方向性がほぼ支持されており、中長期的な検討を行う方向となっている。
IFRSの非継続事業とは? 平成20年9月にIASBが公表した公開草案「非継続事業(IFRS第5号の改訂案)」では、非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されている企業の構成単位であるとし、そのうえで、①事業セグメントであり、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されているもの、②取得時に売却目的保有としての分類要件を満たしている事業のいずれかの要件を満たすものと定義されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.