解説記事2010年03月22日 【巻頭特集】 改正独占禁止法に基づく企業結合規制における実務上の留意点(2010年3月22日号・№347)
巻頭特集
施行後の新実務の確認のために
改正独占禁止法に基づく企業結合規制における実務上の留意点
森・濱田松本法律事務所 弁護士 土屋智弘
Ⅰ はじめに
本稿は、平成21年6月3日に成立し、本年1月1日より施行された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第51号。以下、同法により改正された独占禁止法を「改正法」という)において改正がなされた企業結合規制につき、その実務上の留意点を紹介するものである(脚注1)。
改正法の成立に伴い、平成21年10月28日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成21年政令第253号。以下、同政令により改正された独占禁止法施行令を「改正施行令」という)、同年10月30日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則の一部を改正する規則」(平成21年公正取引委員会規則第13号。以下、同規則によって改正された届出等規則を「改正届出等規則」という)が公布され、いずれも本年1月1日より施行となっている。
また、公正取引委員会(以下「公取委」という)においては「企業結合に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)の一部が改正された(平成21年10月23日公表)ほか、公取委のウェブサイト上には企業結合規制の改正に関するQ&A(以下「届出制度Q&A」という)その他の改正法等に関する情報が掲載されている。
本稿においては、これらの各法令等についても適宜言及することとする。
以下、企業結合規制の改正点のうち実務上の影響が大きいものと思われる①国内売上高基準の導入、②企業結合集団概念の導入および③株式譲渡における事後報告から事前届出への変更の3点について、主に株式取得の場合を念頭に、実務上留意すべき問題点について考察する。
Ⅱ 国内売上高基準の導入
1 国内売上高の考え方 改正法においては、事前届出の基準となる金額が、従前の総資産合計額(脚注2)から「企業結合集団」の国内売上高合計額(脚注3)に変更された。企業結合集団については後述Ⅲで詳しく述べることとし、ここでは国内売上高の考え方について検討する。
国内売上高(脚注4)とは、「国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額」(改正法10条2項)であり、その内容は改正届出等規則によって、会社等(脚注5)の最終事業年度における売上高のうち、以下を合計したもの(ただし、売上値引、戻り高および租税相当額は含まない)とされている。
① 国内の消費者(個人)が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方である場合の売上高(改正届出等規則2条1項1号)(図1参照)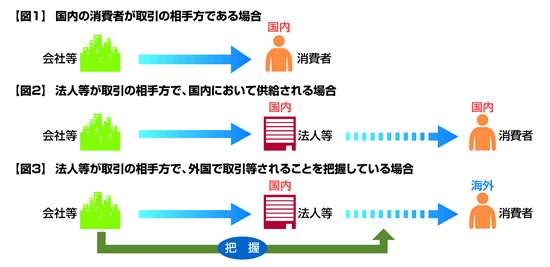 もっとも単純な形態である。なお、国内売上高の算出にあたっては当該商品・役務の供給がどこで行われるかに着目するため、供給を行う会社等の所在地は問題とならない。
もっとも単純な形態である。なお、国内売上高の算出にあたっては当該商品・役務の供給がどこで行われるかに着目するため、供給を行う会社等の所在地は問題とならない。
この点は、以下の各号についても同様である。
② 法人等(脚注6)が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方であって、当該取引に係る商品・役務が国内において供給される場合の売上高(同項2号)(図2参照) たとえば、会社等が国内の卸売業者に商品を供給する場合において、当該商品が国内の消費者に対して提供されるものである場合には、かかる供給による売上高は国内売上高に算入されることになる。
本号には例外規定が置かれており、法人等に商品・役務を供給する取引において、供給を行う会社等が、当該取引に係る契約の締結時に、当該法人等が当該商品の性質または形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること、または当該法人等の外国に所在する営業所等(脚注7)に向けて当該商品を送り出すことを把握している場合の売上高は、国内売上高に含まれない(同号かっこ書)(図3参照)。
したがって、上記の例でいえば供給を行う会社等と卸売業者との間の契約時点において、商品の仕向地が外国であることが、契約書において明記されている等によって当該会社等において認識されているのでなければ、当該取引に係る売上高を国内売上高から除外することは(実際には当該商品が外国で販売されていたとしても)できないことになる(もっとも、供給を行った会社等において、当該商品が外国で販売されていたことが事後明らかになれば、かかる商品についての売上高は国内売上高から除外しても差し支えないものと思われる)。
③ 法人等が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方であって、当該商品が外国において供給され、かつ供給を行う会社等が、当該取引に係る契約の締結時に、当該法人等が当該商品の性質または形状を変更しないで本邦を仕向地としてさらに当該商品を取引すること、または当該法人等の本邦に所在する営業所等に向けて当該商品を送り出すことを把握している場合の売上高(同項3号)(図4参照)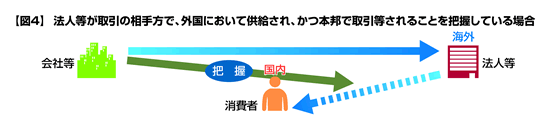 上記②の例外規定と逆の場合である。したがって、上記と同様、契約時点において、商品の仕向地が日本であることが、契約書において明記されている等によって供給を行う会社等において認識されている場合を除けば、当該取引に係る売上高を国内売上高に含める必要は(実際には当該商品が日本で販売されたとしても)ないものと考えられる。
上記②の例外規定と逆の場合である。したがって、上記と同様、契約時点において、商品の仕向地が日本であることが、契約書において明記されている等によって供給を行う会社等において認識されている場合を除けば、当該取引に係る売上高を国内売上高に含める必要は(実際には当該商品が日本で販売されたとしても)ないものと考えられる。
なお、ここにいう「売上高」とは、会計上の勘定科目にかかわらず、当事会社がその商品・役務の提供から得た収益を広く含むと考えるべきである。
たとえば、フランチャイズの運営会社についてはフランチャイジーからのロイヤリティ収入、知的財産権の管理会社についてはライセンシーからのライセンス料がそれぞれ売上高に含まれるものとされる(届出制度Q&A「国内売上高の具体的な事例について」Q7・Q8)。もっとも、これらのフランチャイジーやライセンシーが外国に所在する場合は、ロイヤリティやライセンス料は海外売上高となるので国内売上高には含まれない。
また、企業結合集団に組合が含まれる場合、当該組合の売上高も算定する必要があるが、公取委によれば、投資組合の場合は投資収益、具体的には有価証券売却益等が売上高に含まれるものとしている(同Q4・Q6)。
したがって、たとえば投資組合がその保有するポートフォリオの全部または一部を第三者に売却した場合には当該組合としての売上高が観念しうることになる。この場合も、売却の相手方が海外に所在する場合には国内売上高には算入されないことになろう。
2 企業結合集団における国内売上高
(1)原則的な算出方法 改正法の下では企業結合集団の国内売上高の合計額が事前届出の要否を決定する基準となる。かかる合計額は、基本的には上記に従って企業結合集団の各構成員について算出された国内売上高を合算して得ることになる(改正届出等規則2条の2第1項)。
合算にあたっては、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高を相殺
消去することができる(改正届出等規則2条の2第2項)。
企業結合集団の構成員間で事業年度の末日が異なる場合であっても、改正法は「最終事業年度における合計額」と規定しているだけであるので、同一の日に合わせるために改めて決算等を行う必要はなく、そのまま合算すれば足りる。ただし、上述の相互取引に係る相殺消去を行う場合には、最終親会社の事業年度の末日と異なる子会社(最終親会社・子会社の定義については後述する)は、当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を確定する決算を行うものとされている(ただし、最終親会社と子会社の事業年度の末日が3か月を超えない場合を除く)ので、留意が必要である(改正届出等規則2条の2第3項)。
(2)連結財務諸表等を用いた算出方法 国内売上高合計額の原則的な算出方法は上述(1)のとおりであるが、改正届出等規則によれば、企業結合集団の構成員の中に連結財務諸表提出会社(脚注8)または外国連結財務諸表提出会社(脚注9)がある場合は、改正届出等規則2条の3第1項各号に定める区分に応じて算出された額をもって国内売上高合計額とすることができるとされている。
実際の規定は若干複雑であるが、要約すると、企業結合集団の中に1または2以上の連結財務諸表提出会社および/または外国連結財務諸表提出会社がある場合には、これらの連結対象となっている会社については、個々の国内売上高を算出する必要はなく、各連結財務諸表提出会社・外国連結財務諸表提出会社に係る連結会社全体の国内売上高を算出した上で、連結対象となっていない企業結合集団の構成員に係る国内売上高を合算すれば足りるとすることで、当事会社の負担の軽減を図っている(改正届出等規則2条の3第1項1号~3号)。
なお、原則形態の場合と同様、国内売上高の算出にあたっては当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高を相殺消去することができる(改正届出等規則2条の3第2項)。この場合、事業年度の末日を合わせるための決算が必要となりうる点も原則形態と同じである(同条3項)。
Ⅲ 企業結合集団概念の導入
1 企業結合集団の画定-実質基準 改正法の下では事前届出の可否を企業結合集団を単位として判断することとなるため、当事会社における企業結合集団の画定が実務上重要となる。
企業結合集団とは、最終親会社(会社の親会社であって他の会社の子会社でないものをいう)およびその子会社によって構成される集団である。そして、ここにいう「子会社」とは会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他当該会社がその経営を支配している会社等をいうとされ(改正法10条6項)、「親会社」とは会社等の経営を支配している会社をいうとして(同条7項)、会社法等と同様の実質基準によるものとしている。
この「経営を支配する」の具体的内容については、従前より会社法や金融商品取引法(以下「金商法」という)において導入されている基準を踏襲すべく、改正届出等規則2条の9において会社法施行規則3条の規定とほぼ同様の規定を置いている(脚注10)。
なお、企業結合集団の画定の基準時は、株式取得その他組織再編行為を実行する前日である(届出制度Q&A「届出基準について」Q7)。一方で国内売上高の算定基準は前述のとおり最終事業年度の末日であるが、当該最終事業年度末日から株式取得等の実行日前日までに子会社の範囲に変動があった場合、かかる変動に係る子会社の国内売上高を増減する必要があるので(同Q14・Q15)、注意が必要である。
また、実質基準を用いることにより、議決権比率が過半数に満たなくても親会社に該当する場合があることから、理論上は1つの会社等に対して複数の親会社が存在しうることになるが、この点、公取委により、ある会社等に対して複数の親会社が存在してはならず、また過半数の議決権比率を有する会社がある場合には、改正届出等規則2条の9第1項2号イ~ホに該当する会社がある場合でもかかる会社は親会社とはならない(すなわち、同項1号の適用が2号の適用に優先する)との考え方が示されている(「株式取得に関する計画届出書記載要領」(要件)※3)。しかし、たとえば2社の合弁会社において議決権比率が50:50の場合など、実際には親会社の判定が困難な場合も生じうると思われる。
2 企業結合集団における組合の考え方 改正法は、典型的には投資ファンドによる株式の取得を事前届出の対象に含めることを念頭に、組合(脚注11)が企業結合集団に含まれる場合の規定を置いている。
まず、組合の組合員が組合財産として株式の取得を行う場合には、当該組合の直接の「親会社」が当該株式をすべて取得するものとみなされ、当該株式が当該組合の組合財産に属している場合は、かかる「親会社」が当該株式のすべてを所有するものとみなされる(改正法10条5項)。
したがって、この場合、事前届出の要否判定のための企業結合集団の画定および国内売上高の算定はかかる「親会社」を起点に行うことになる(脚注12)。
そこで組合の「親会社」とは何を指すかが問題となるが、改正届出等規則は、同規則2条の9第3項各号における議決権数の割合を元にした基準を、業務執行を決定する権限の割合と読み替えた上で適用するものとしている(同項第2文)。すなわち、組合における親子関係は当該組合の組合員における出資額ではなく、業務執行権限の有無および割合によって決せられることになる。
したがって、組合における有限責任組合員(LP)は、業務執行権限が与えられていない以上、その出資額の多寡にかかわらず、当該組合の親会社とみなされることはない。一方、当該組合における無限責任組合員(GP)たる会社は通常当該組合の親会社となると考えられるが、GPが複数あるような場合には、GP相互間における業務執行権限の定め方も多岐にわたりうるので、組合における親会社の判定は会社の場合以上に困難な場合がありうる。なお、組合においても親会社が複数あってはならない点は、会社の場合と同様である(「組合による株式取得に関する計画届出書記載要領」(要件)※2)。
以上の考え方は、株式取得会社の株式を組合を通じて保有しているような場合にも当てはまる。
たとえば、図5において、Dが株式取得の主体となる場合、まず(i)の場合はA組合のGPは会社であるXのみであるから、Xに親会社がなければ企業結合集団はX、A、B、C、DおよびEとなる。
これに対して(ii)の場合は、A組合のGPはX個人であるが、親会社はあくまで「会社」である必要があるので(改正法10条6項)、XはA組合の親会社にはなりえない。同様にA組合はBまたはCの親会社とはならない(脚注13)。
したがって、企業結合集団としてはC、DおよびEのみとなる。
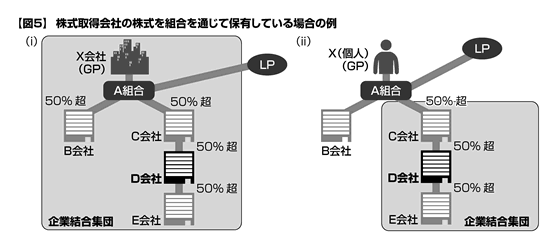
Ⅳ 株式取得における事前届出制度の導入
1 事後報告から事前届出への変更 改正法の下では、株式取得行為において届出の要件を充足する場合には、事前に公取委に当該株式取得に関する計画を届け出た上で、届出の受理後原則として30日間は当該届出に係る株式の取得を実行できないこととなった(改正法10条2項・8項。以下、この株式取得ができない期間を「禁止期間」という)。
従前、株式取得は合併や事業譲渡といった他のM&A取引と異なり、公取委への報告が必要な場合も事後に行えば足りたため、独占禁止法上実質的な問題が生じうる案件で事前相談制度を利用する場合でない限り、独占禁止法が株式取得の実行スケジュールに影響を与えることはなかった。
しかし、今回の改正によって、株式取得が他のM&A取引と同様事前届出となったことで、届出要件を充足する場合には、実質的な問題の有無にかかわらず、スケジュールの策定において禁止期間を考慮する必要が生じる。
特に上場会社の株式取得にあたっては、金商法に基づく公開買付規制との関係で、スケジュール策定上留意すべき点が多く存在するため、項を改めて検討することとする。
2 上場会社の公開買付制度と事前届出との関係
(1)公開買付期間の設定 上述1のとおり、改正法の下では届出受理日の翌日から起算して30日間は株式の取得を実行することができない。そして、公開買付けによる上場会社株式の取得の場合、株式の取得日は公開買付けに係る決済を行った日とされている(届出制度Q&A「禁止期間について」Q3)。
したがって、公開買付者は公開買付期間を20営業日から60営業日の間で自由に設定することができるものの(金商法27条の2第2項、同施行令8条1項)、当該公開買付けによる株式取得が届出要件を充足する場合には、決済予定日までに禁止期間が確実に満了するよう、公開買付期間を設定し、かつ事前届出が受理されるようにスケジュールを策定する必要がある。
特に後者については、届出書の正式な提出に先立ち、公取委の担当者による内容のチェックが行われるのが通例であり、また、届出受理日は公取委によって決定されるもので届出書の実際の提出日と必ずしも一致するものではないため、ある程度余裕を持って日程を組むことが望ましい。
なお、禁止期間は公取委が必要と認める場合には短縮することができるが(改正法10条8項ただし書)、公取委によれば、①競争への影響が明らかに軽微であること、②届出受理の日から30日を経過するまでに公開買付けに係る株式取得の決済が終了することの2要件を満たす場合には、公取委が必要と認めれば禁止期間の短縮が行われるとしている(届出制度Q&A「禁止期間について」Q5)。
これに従えば、たとえば公開買付者と対象会社の事業がまったく重複しないような場合には、禁止期間を考慮せずに公開買付期間を設定できる余地があることになる。もっとも、短縮が認められるか否かは最終的には公取委の裁量によるため、取引の安定性の見地からも、可能な限り禁止期間を考慮して公開買付期間を設定することが望ましい。
なお、公開買付けの検討から実行までに比較的時間の余裕がある場合には、公開買付けの開始までに禁止期間を満了させるべく、前倒しで事前届出を行うことも検討に値しよう。事前届出は決済予定日の6か月前から可能である(届出制度Q&A「届出手続について」Q7)。
ただし、この場合、機関決定に伴う適時開示との関係で、届出時点では届出書の添付書類である株式取得に関する契約書または意思決定を証するに足りる書類(取締役会議事録等)(株式取得に関する計画届出書記載要領II.1.②)を用意できない場合が多いと考えられる。この場合に何らかの代替手段が可能かについては、状況によっては公取委とも事前に協議の上、対応していく必要があると思われる。
(2)排除措置命令・措置期間と公開買付けの撤回 公取委は、事前届出が行われた株式取得に関し、独占禁止法上問題があるとして排除措置(改正法17条の2第1項)を命じようとする場合は、禁止期間(または禁止期間内に公取委が審査に必要な報告、情報または資料(以下「報告等」という)の提出を求めた場合には、届出受理日から120日を経過した日かすべての報告等の受理日から90日を経過した日のいずれか遅く到来した日までの期間。以下、かかる期間を「措置期間」という)に、株式取得会社に対して事前通知を行うものとされている(改正法10条9項)。
したがって、禁止期間を考慮して公開買付期間を設定しても、公開買付期間中に公取委から排除措置命令の事前通知を受けた場合や報告等の提出を求められた場合は、公開買付けの終了までに独占禁止法上のクリアランスが得られない事態となり、取引が著しく不安定なものとなる。
この点、平成21年11月26日発表に係る金融庁総務企画局の「株券等の公開買付けに関するQ&A」(以下「公開買付けQ&A」という)によれば、これらの場合においては、株券等の取得に係る「許可等」(金商法施行令14条1項4号)が得られなかったものとして公開買付けの撤回等を行うことができるものとしている(公開買付けQ&A問7・問8)(脚注14)。ただし、公開買付開始公告および公開買付届出書において、上記事情が生じた場合には公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付している必要がある。
実際には、株式取得会社において公開買付けに係る株式取得が独占禁止法上問題となりうる認識があれば、当該公開買付けの開始に先立ち、公取委への事前相談を行うことが通常であると思われるから、上記のような事態に至る可能性は必ずしも高くないとも考えられる。
ただし、たとえば対象会社の経営陣が株式取得に同意していない場合(いわゆる敵対的買収)において、株式取得会社が対象会社に関する情報を必ずしも十分持ち合わせていないような場合は、独占禁止法上の問題の有無についての判断を誤る可能性も皆無ではないと思われる。
(3)公開買付届出書への記載 上記のとおり、事前通知の受領や報告等の提出要請を理由とする公開買付けの撤回は、その旨の公開買付届出書等への記載が条件となる。
公開買付けQ&Aによれば、独占禁止法上の事前届出については、公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了すること、および公取委に対する事前相談において独占禁止法上問題ない旨の回答を受けることを、公開買付届出書の「株券等の取得に関する許可等」欄における「許可等」に当たるものとして記載すべきであるとしている(公開買付けQ&A問9)。
具体的には、①独占禁止法上の事前届出が必要である旨、②事前届出を行った日または行う予定の日、③禁止期間が終了した日または終了する予定の日、④公取委に対する事前相談を行ったか否か、行った場合にはその結果等を記載する必要がある。
なお、③および④に関し、禁止期間がすでに終了している場合または事前相談を行っている場合には、当該事前相談において独占禁止法上問題がない旨の回答を受けたこと、または公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了したことを確認することができる書面を「許可等があったことを知るに足る書面」(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「他社株府令」という)13条1項9号)として添付する必要がある。
従前、合併等の事前届出において、公取委から禁止期間が終了したことを示す書面が交付されることは原則としてなかったが、公取委によれば、今後は必要に応じて、事前通知を受けることなく法定の期間が経過したことを示す書面を「許可等があったことを知るに足る書面」として交付するとのことである(届出制度Q&A「その他」Q2)。
一方、公開買付期間中に禁止期間が終了した場合、公取委への事前相談の結果独占禁止法上問題がない旨の回答を得ており、かつその点を届出書に記載している場合は、その後の法定の事前届出に係る禁止期間が公開買付期間中に終了したとしても、改めて公開買付届出書の訂正届出書(他社株府令第2号様式「記載上の注意」(8))を提出する必要はないが、公開買付者が事前相談を行っていないかその回答を得ていない場合は、公開買付期間中に公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了したことについて、「許可等」を取得したものとして訂正届出書を、上記書面を添付の上、提出する必要がある(公開買付けQ&A問10)。
この場合、公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書の提出日から10営業日を経過した日まで公開買付期間を延長する必要があるため(金商法27条の8第8項、他社株府令22条2項)、スケジュールの策定にあたってはこの点も留意が必要である。
脚注
1 なお、改正法全体の概要については、小俣栄一郎・松風宏幸「課徴金制度・企業結合規制の見直しに係る独占禁止法の改正の要点」本誌314号25頁以下を、企業結合規制関連の改正の概要については、島袋功一「企業結合規制の見直しに係る政令・公正取引委員会規則・ガイドラインの改正の要点」本誌336号18頁以下をそれぞれ参照。
2 当事会社のほか、その国内における直接の親会社および子会社の総資産を含む。改正前独占禁止法10条2項参照。
3 届出が必要となるのは、当事会社(株式取得会社)においては200億円、相手会社(対象会社)においては50億円である(改正施行令16条1項・2項)。
4 銀行業および保険業を営む会社等については経常利益、第一種金融商品取引業を営む会社等(証券会社など)については営業収益がそれぞれ売上高とされる(改正届出等規則2条1項)。
5 会社のほか、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これらに類似する事業体をいう。改正法10条2項。
6 法人その他の社団もしくは財団または事業としてもしくは事業のために契約の当事者となる個人をいう。改正届出等規則2条1項2号。
7 営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。同号。
8 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)2条1号に規定するものをいう。改正届出等規則2条の3第1項。
9 外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表(連結財務諸表規則1条1項に規定するものをいう)に相当するものを作成する会社をいう。同上。
10 なお、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項(4)は、いわゆるベンチャーキャピタルなどの投資企業については、他の会社の実質支配基準を満たしていた場合であっても、一定の要件の下で子会社に該当しないものとしており、これに従ってベンチャーキャピタルは会社法施行規則3条3項かっこ書の「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」に該当するものと解されているが、公取委によれば、このようなベンチャーキャピタルであっても改正法上の子会社には該当するとの見解が示されている(届出制度Q&A「届出基準について」Q11)。
11 民法上の組合(民法667条1項)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律2条2項)および有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律2条)ならびに外国法令に基づいて設立された団体であってこれらに類似するものをいう(改正法10条5項)。
12 なお、改正法10条5項は組合自体が株式の取得主体のなる場合の規定であり、たとえば投資ファンドが受皿会社(SPC)を設立の上、株式を取得した場合は、当該SPCが当事会社となるので原則どおり改正法10条2項が適用されることになる。
13 改正法10条6項に基づく親会社の定義は会社等の経営を支配している「会社」であって、組合を含む「会社等」ではない。
14 なお、改正法10条1項に違反する疑いのある行為をする者として、裁判所の緊急停止命令(改正法70条の13第1項参照)の申立てを受けた場合も同様である。
施行後の新実務の確認のために
改正独占禁止法に基づく企業結合規制における実務上の留意点
森・濱田松本法律事務所 弁護士 土屋智弘
Ⅰ はじめに
本稿は、平成21年6月3日に成立し、本年1月1日より施行された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第51号。以下、同法により改正された独占禁止法を「改正法」という)において改正がなされた企業結合規制につき、その実務上の留意点を紹介するものである(脚注1)。
改正法の成立に伴い、平成21年10月28日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成21年政令第253号。以下、同政令により改正された独占禁止法施行令を「改正施行令」という)、同年10月30日には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則の一部を改正する規則」(平成21年公正取引委員会規則第13号。以下、同規則によって改正された届出等規則を「改正届出等規則」という)が公布され、いずれも本年1月1日より施行となっている。
また、公正取引委員会(以下「公取委」という)においては「企業結合に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)の一部が改正された(平成21年10月23日公表)ほか、公取委のウェブサイト上には企業結合規制の改正に関するQ&A(以下「届出制度Q&A」という)その他の改正法等に関する情報が掲載されている。
本稿においては、これらの各法令等についても適宜言及することとする。
以下、企業結合規制の改正点のうち実務上の影響が大きいものと思われる①国内売上高基準の導入、②企業結合集団概念の導入および③株式譲渡における事後報告から事前届出への変更の3点について、主に株式取得の場合を念頭に、実務上留意すべき問題点について考察する。
Ⅱ 国内売上高基準の導入
1 国内売上高の考え方 改正法においては、事前届出の基準となる金額が、従前の総資産合計額(脚注2)から「企業結合集団」の国内売上高合計額(脚注3)に変更された。企業結合集団については後述Ⅲで詳しく述べることとし、ここでは国内売上高の考え方について検討する。
国内売上高(脚注4)とは、「国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額」(改正法10条2項)であり、その内容は改正届出等規則によって、会社等(脚注5)の最終事業年度における売上高のうち、以下を合計したもの(ただし、売上値引、戻り高および租税相当額は含まない)とされている。
① 国内の消費者(個人)が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方である場合の売上高(改正届出等規則2条1項1号)(図1参照)
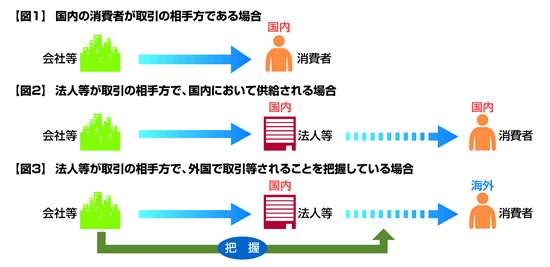 もっとも単純な形態である。なお、国内売上高の算出にあたっては当該商品・役務の供給がどこで行われるかに着目するため、供給を行う会社等の所在地は問題とならない。
もっとも単純な形態である。なお、国内売上高の算出にあたっては当該商品・役務の供給がどこで行われるかに着目するため、供給を行う会社等の所在地は問題とならない。この点は、以下の各号についても同様である。
② 法人等(脚注6)が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方であって、当該取引に係る商品・役務が国内において供給される場合の売上高(同項2号)(図2参照) たとえば、会社等が国内の卸売業者に商品を供給する場合において、当該商品が国内の消費者に対して提供されるものである場合には、かかる供給による売上高は国内売上高に算入されることになる。
本号には例外規定が置かれており、法人等に商品・役務を供給する取引において、供給を行う会社等が、当該取引に係る契約の締結時に、当該法人等が当該商品の性質または形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること、または当該法人等の外国に所在する営業所等(脚注7)に向けて当該商品を送り出すことを把握している場合の売上高は、国内売上高に含まれない(同号かっこ書)(図3参照)。
したがって、上記の例でいえば供給を行う会社等と卸売業者との間の契約時点において、商品の仕向地が外国であることが、契約書において明記されている等によって当該会社等において認識されているのでなければ、当該取引に係る売上高を国内売上高から除外することは(実際には当該商品が外国で販売されていたとしても)できないことになる(もっとも、供給を行った会社等において、当該商品が外国で販売されていたことが事後明らかになれば、かかる商品についての売上高は国内売上高から除外しても差し支えないものと思われる)。
③ 法人等が当該会社等の供給する商品・役務に係る取引の相手方であって、当該商品が外国において供給され、かつ供給を行う会社等が、当該取引に係る契約の締結時に、当該法人等が当該商品の性質または形状を変更しないで本邦を仕向地としてさらに当該商品を取引すること、または当該法人等の本邦に所在する営業所等に向けて当該商品を送り出すことを把握している場合の売上高(同項3号)(図4参照)
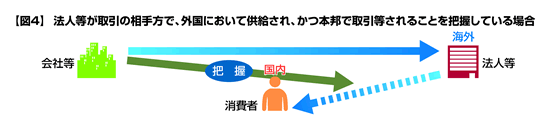 上記②の例外規定と逆の場合である。したがって、上記と同様、契約時点において、商品の仕向地が日本であることが、契約書において明記されている等によって供給を行う会社等において認識されている場合を除けば、当該取引に係る売上高を国内売上高に含める必要は(実際には当該商品が日本で販売されたとしても)ないものと考えられる。
上記②の例外規定と逆の場合である。したがって、上記と同様、契約時点において、商品の仕向地が日本であることが、契約書において明記されている等によって供給を行う会社等において認識されている場合を除けば、当該取引に係る売上高を国内売上高に含める必要は(実際には当該商品が日本で販売されたとしても)ないものと考えられる。なお、ここにいう「売上高」とは、会計上の勘定科目にかかわらず、当事会社がその商品・役務の提供から得た収益を広く含むと考えるべきである。
たとえば、フランチャイズの運営会社についてはフランチャイジーからのロイヤリティ収入、知的財産権の管理会社についてはライセンシーからのライセンス料がそれぞれ売上高に含まれるものとされる(届出制度Q&A「国内売上高の具体的な事例について」Q7・Q8)。もっとも、これらのフランチャイジーやライセンシーが外国に所在する場合は、ロイヤリティやライセンス料は海外売上高となるので国内売上高には含まれない。
また、企業結合集団に組合が含まれる場合、当該組合の売上高も算定する必要があるが、公取委によれば、投資組合の場合は投資収益、具体的には有価証券売却益等が売上高に含まれるものとしている(同Q4・Q6)。
したがって、たとえば投資組合がその保有するポートフォリオの全部または一部を第三者に売却した場合には当該組合としての売上高が観念しうることになる。この場合も、売却の相手方が海外に所在する場合には国内売上高には算入されないことになろう。
2 企業結合集団における国内売上高
(1)原則的な算出方法 改正法の下では企業結合集団の国内売上高の合計額が事前届出の要否を決定する基準となる。かかる合計額は、基本的には上記に従って企業結合集団の各構成員について算出された国内売上高を合算して得ることになる(改正届出等規則2条の2第1項)。
合算にあたっては、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高を相殺
消去することができる(改正届出等規則2条の2第2項)。
企業結合集団の構成員間で事業年度の末日が異なる場合であっても、改正法は「最終事業年度における合計額」と規定しているだけであるので、同一の日に合わせるために改めて決算等を行う必要はなく、そのまま合算すれば足りる。ただし、上述の相互取引に係る相殺消去を行う場合には、最終親会社の事業年度の末日と異なる子会社(最終親会社・子会社の定義については後述する)は、当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を確定する決算を行うものとされている(ただし、最終親会社と子会社の事業年度の末日が3か月を超えない場合を除く)ので、留意が必要である(改正届出等規則2条の2第3項)。
(2)連結財務諸表等を用いた算出方法 国内売上高合計額の原則的な算出方法は上述(1)のとおりであるが、改正届出等規則によれば、企業結合集団の構成員の中に連結財務諸表提出会社(脚注8)または外国連結財務諸表提出会社(脚注9)がある場合は、改正届出等規則2条の3第1項各号に定める区分に応じて算出された額をもって国内売上高合計額とすることができるとされている。
実際の規定は若干複雑であるが、要約すると、企業結合集団の中に1または2以上の連結財務諸表提出会社および/または外国連結財務諸表提出会社がある場合には、これらの連結対象となっている会社については、個々の国内売上高を算出する必要はなく、各連結財務諸表提出会社・外国連結財務諸表提出会社に係る連結会社全体の国内売上高を算出した上で、連結対象となっていない企業結合集団の構成員に係る国内売上高を合算すれば足りるとすることで、当事会社の負担の軽減を図っている(改正届出等規則2条の3第1項1号~3号)。
なお、原則形態の場合と同様、国内売上高の算出にあたっては当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高を相殺消去することができる(改正届出等規則2条の3第2項)。この場合、事業年度の末日を合わせるための決算が必要となりうる点も原則形態と同じである(同条3項)。
Ⅲ 企業結合集団概念の導入
1 企業結合集団の画定-実質基準 改正法の下では事前届出の可否を企業結合集団を単位として判断することとなるため、当事会社における企業結合集団の画定が実務上重要となる。
企業結合集団とは、最終親会社(会社の親会社であって他の会社の子会社でないものをいう)およびその子会社によって構成される集団である。そして、ここにいう「子会社」とは会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他当該会社がその経営を支配している会社等をいうとされ(改正法10条6項)、「親会社」とは会社等の経営を支配している会社をいうとして(同条7項)、会社法等と同様の実質基準によるものとしている。
この「経営を支配する」の具体的内容については、従前より会社法や金融商品取引法(以下「金商法」という)において導入されている基準を踏襲すべく、改正届出等規則2条の9において会社法施行規則3条の規定とほぼ同様の規定を置いている(脚注10)。
なお、企業結合集団の画定の基準時は、株式取得その他組織再編行為を実行する前日である(届出制度Q&A「届出基準について」Q7)。一方で国内売上高の算定基準は前述のとおり最終事業年度の末日であるが、当該最終事業年度末日から株式取得等の実行日前日までに子会社の範囲に変動があった場合、かかる変動に係る子会社の国内売上高を増減する必要があるので(同Q14・Q15)、注意が必要である。
また、実質基準を用いることにより、議決権比率が過半数に満たなくても親会社に該当する場合があることから、理論上は1つの会社等に対して複数の親会社が存在しうることになるが、この点、公取委により、ある会社等に対して複数の親会社が存在してはならず、また過半数の議決権比率を有する会社がある場合には、改正届出等規則2条の9第1項2号イ~ホに該当する会社がある場合でもかかる会社は親会社とはならない(すなわち、同項1号の適用が2号の適用に優先する)との考え方が示されている(「株式取得に関する計画届出書記載要領」(要件)※3)。しかし、たとえば2社の合弁会社において議決権比率が50:50の場合など、実際には親会社の判定が困難な場合も生じうると思われる。
2 企業結合集団における組合の考え方 改正法は、典型的には投資ファンドによる株式の取得を事前届出の対象に含めることを念頭に、組合(脚注11)が企業結合集団に含まれる場合の規定を置いている。
まず、組合の組合員が組合財産として株式の取得を行う場合には、当該組合の直接の「親会社」が当該株式をすべて取得するものとみなされ、当該株式が当該組合の組合財産に属している場合は、かかる「親会社」が当該株式のすべてを所有するものとみなされる(改正法10条5項)。
したがって、この場合、事前届出の要否判定のための企業結合集団の画定および国内売上高の算定はかかる「親会社」を起点に行うことになる(脚注12)。
そこで組合の「親会社」とは何を指すかが問題となるが、改正届出等規則は、同規則2条の9第3項各号における議決権数の割合を元にした基準を、業務執行を決定する権限の割合と読み替えた上で適用するものとしている(同項第2文)。すなわち、組合における親子関係は当該組合の組合員における出資額ではなく、業務執行権限の有無および割合によって決せられることになる。
したがって、組合における有限責任組合員(LP)は、業務執行権限が与えられていない以上、その出資額の多寡にかかわらず、当該組合の親会社とみなされることはない。一方、当該組合における無限責任組合員(GP)たる会社は通常当該組合の親会社となると考えられるが、GPが複数あるような場合には、GP相互間における業務執行権限の定め方も多岐にわたりうるので、組合における親会社の判定は会社の場合以上に困難な場合がありうる。なお、組合においても親会社が複数あってはならない点は、会社の場合と同様である(「組合による株式取得に関する計画届出書記載要領」(要件)※2)。
以上の考え方は、株式取得会社の株式を組合を通じて保有しているような場合にも当てはまる。
たとえば、図5において、Dが株式取得の主体となる場合、まず(i)の場合はA組合のGPは会社であるXのみであるから、Xに親会社がなければ企業結合集団はX、A、B、C、DおよびEとなる。
これに対して(ii)の場合は、A組合のGPはX個人であるが、親会社はあくまで「会社」である必要があるので(改正法10条6項)、XはA組合の親会社にはなりえない。同様にA組合はBまたはCの親会社とはならない(脚注13)。
したがって、企業結合集団としてはC、DおよびEのみとなる。
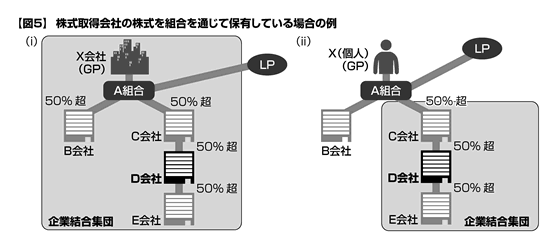
Ⅳ 株式取得における事前届出制度の導入
1 事後報告から事前届出への変更 改正法の下では、株式取得行為において届出の要件を充足する場合には、事前に公取委に当該株式取得に関する計画を届け出た上で、届出の受理後原則として30日間は当該届出に係る株式の取得を実行できないこととなった(改正法10条2項・8項。以下、この株式取得ができない期間を「禁止期間」という)。
従前、株式取得は合併や事業譲渡といった他のM&A取引と異なり、公取委への報告が必要な場合も事後に行えば足りたため、独占禁止法上実質的な問題が生じうる案件で事前相談制度を利用する場合でない限り、独占禁止法が株式取得の実行スケジュールに影響を与えることはなかった。
しかし、今回の改正によって、株式取得が他のM&A取引と同様事前届出となったことで、届出要件を充足する場合には、実質的な問題の有無にかかわらず、スケジュールの策定において禁止期間を考慮する必要が生じる。
特に上場会社の株式取得にあたっては、金商法に基づく公開買付規制との関係で、スケジュール策定上留意すべき点が多く存在するため、項を改めて検討することとする。
2 上場会社の公開買付制度と事前届出との関係
(1)公開買付期間の設定 上述1のとおり、改正法の下では届出受理日の翌日から起算して30日間は株式の取得を実行することができない。そして、公開買付けによる上場会社株式の取得の場合、株式の取得日は公開買付けに係る決済を行った日とされている(届出制度Q&A「禁止期間について」Q3)。
したがって、公開買付者は公開買付期間を20営業日から60営業日の間で自由に設定することができるものの(金商法27条の2第2項、同施行令8条1項)、当該公開買付けによる株式取得が届出要件を充足する場合には、決済予定日までに禁止期間が確実に満了するよう、公開買付期間を設定し、かつ事前届出が受理されるようにスケジュールを策定する必要がある。
特に後者については、届出書の正式な提出に先立ち、公取委の担当者による内容のチェックが行われるのが通例であり、また、届出受理日は公取委によって決定されるもので届出書の実際の提出日と必ずしも一致するものではないため、ある程度余裕を持って日程を組むことが望ましい。
なお、禁止期間は公取委が必要と認める場合には短縮することができるが(改正法10条8項ただし書)、公取委によれば、①競争への影響が明らかに軽微であること、②届出受理の日から30日を経過するまでに公開買付けに係る株式取得の決済が終了することの2要件を満たす場合には、公取委が必要と認めれば禁止期間の短縮が行われるとしている(届出制度Q&A「禁止期間について」Q5)。
これに従えば、たとえば公開買付者と対象会社の事業がまったく重複しないような場合には、禁止期間を考慮せずに公開買付期間を設定できる余地があることになる。もっとも、短縮が認められるか否かは最終的には公取委の裁量によるため、取引の安定性の見地からも、可能な限り禁止期間を考慮して公開買付期間を設定することが望ましい。
なお、公開買付けの検討から実行までに比較的時間の余裕がある場合には、公開買付けの開始までに禁止期間を満了させるべく、前倒しで事前届出を行うことも検討に値しよう。事前届出は決済予定日の6か月前から可能である(届出制度Q&A「届出手続について」Q7)。
ただし、この場合、機関決定に伴う適時開示との関係で、届出時点では届出書の添付書類である株式取得に関する契約書または意思決定を証するに足りる書類(取締役会議事録等)(株式取得に関する計画届出書記載要領II.1.②)を用意できない場合が多いと考えられる。この場合に何らかの代替手段が可能かについては、状況によっては公取委とも事前に協議の上、対応していく必要があると思われる。
(2)排除措置命令・措置期間と公開買付けの撤回 公取委は、事前届出が行われた株式取得に関し、独占禁止法上問題があるとして排除措置(改正法17条の2第1項)を命じようとする場合は、禁止期間(または禁止期間内に公取委が審査に必要な報告、情報または資料(以下「報告等」という)の提出を求めた場合には、届出受理日から120日を経過した日かすべての報告等の受理日から90日を経過した日のいずれか遅く到来した日までの期間。以下、かかる期間を「措置期間」という)に、株式取得会社に対して事前通知を行うものとされている(改正法10条9項)。
したがって、禁止期間を考慮して公開買付期間を設定しても、公開買付期間中に公取委から排除措置命令の事前通知を受けた場合や報告等の提出を求められた場合は、公開買付けの終了までに独占禁止法上のクリアランスが得られない事態となり、取引が著しく不安定なものとなる。
この点、平成21年11月26日発表に係る金融庁総務企画局の「株券等の公開買付けに関するQ&A」(以下「公開買付けQ&A」という)によれば、これらの場合においては、株券等の取得に係る「許可等」(金商法施行令14条1項4号)が得られなかったものとして公開買付けの撤回等を行うことができるものとしている(公開買付けQ&A問7・問8)(脚注14)。ただし、公開買付開始公告および公開買付届出書において、上記事情が生じた場合には公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付している必要がある。
実際には、株式取得会社において公開買付けに係る株式取得が独占禁止法上問題となりうる認識があれば、当該公開買付けの開始に先立ち、公取委への事前相談を行うことが通常であると思われるから、上記のような事態に至る可能性は必ずしも高くないとも考えられる。
ただし、たとえば対象会社の経営陣が株式取得に同意していない場合(いわゆる敵対的買収)において、株式取得会社が対象会社に関する情報を必ずしも十分持ち合わせていないような場合は、独占禁止法上の問題の有無についての判断を誤る可能性も皆無ではないと思われる。
(3)公開買付届出書への記載 上記のとおり、事前通知の受領や報告等の提出要請を理由とする公開買付けの撤回は、その旨の公開買付届出書等への記載が条件となる。
公開買付けQ&Aによれば、独占禁止法上の事前届出については、公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了すること、および公取委に対する事前相談において独占禁止法上問題ない旨の回答を受けることを、公開買付届出書の「株券等の取得に関する許可等」欄における「許可等」に当たるものとして記載すべきであるとしている(公開買付けQ&A問9)。
具体的には、①独占禁止法上の事前届出が必要である旨、②事前届出を行った日または行う予定の日、③禁止期間が終了した日または終了する予定の日、④公取委に対する事前相談を行ったか否か、行った場合にはその結果等を記載する必要がある。
なお、③および④に関し、禁止期間がすでに終了している場合または事前相談を行っている場合には、当該事前相談において独占禁止法上問題がない旨の回答を受けたこと、または公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了したことを確認することができる書面を「許可等があったことを知るに足る書面」(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「他社株府令」という)13条1項9号)として添付する必要がある。
従前、合併等の事前届出において、公取委から禁止期間が終了したことを示す書面が交付されることは原則としてなかったが、公取委によれば、今後は必要に応じて、事前通知を受けることなく法定の期間が経過したことを示す書面を「許可等があったことを知るに足る書面」として交付するとのことである(届出制度Q&A「その他」Q2)。
一方、公開買付期間中に禁止期間が終了した場合、公取委への事前相談の結果独占禁止法上問題がない旨の回答を得ており、かつその点を届出書に記載している場合は、その後の法定の事前届出に係る禁止期間が公開買付期間中に終了したとしても、改めて公開買付届出書の訂正届出書(他社株府令第2号様式「記載上の注意」(8))を提出する必要はないが、公開買付者が事前相談を行っていないかその回答を得ていない場合は、公開買付期間中に公取委から排除措置命令の事前通知を受けることなく措置期間が終了したことについて、「許可等」を取得したものとして訂正届出書を、上記書面を添付の上、提出する必要がある(公開買付けQ&A問10)。
この場合、公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書の提出日から10営業日を経過した日まで公開買付期間を延長する必要があるため(金商法27条の8第8項、他社株府令22条2項)、スケジュールの策定にあたってはこの点も留意が必要である。
脚注
1 なお、改正法全体の概要については、小俣栄一郎・松風宏幸「課徴金制度・企業結合規制の見直しに係る独占禁止法の改正の要点」本誌314号25頁以下を、企業結合規制関連の改正の概要については、島袋功一「企業結合規制の見直しに係る政令・公正取引委員会規則・ガイドラインの改正の要点」本誌336号18頁以下をそれぞれ参照。
2 当事会社のほか、その国内における直接の親会社および子会社の総資産を含む。改正前独占禁止法10条2項参照。
3 届出が必要となるのは、当事会社(株式取得会社)においては200億円、相手会社(対象会社)においては50億円である(改正施行令16条1項・2項)。
4 銀行業および保険業を営む会社等については経常利益、第一種金融商品取引業を営む会社等(証券会社など)については営業収益がそれぞれ売上高とされる(改正届出等規則2条1項)。
5 会社のほか、組合(外国における組合に相当するものを含む)その他これらに類似する事業体をいう。改正法10条2項。
6 法人その他の社団もしくは財団または事業としてもしくは事業のために契約の当事者となる個人をいう。改正届出等規則2条1項2号。
7 営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。同号。
8 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という)2条1号に規定するものをいう。改正届出等規則2条の3第1項。
9 外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表(連結財務諸表規則1条1項に規定するものをいう)に相当するものを作成する会社をいう。同上。
10 なお、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項(4)は、いわゆるベンチャーキャピタルなどの投資企業については、他の会社の実質支配基準を満たしていた場合であっても、一定の要件の下で子会社に該当しないものとしており、これに従ってベンチャーキャピタルは会社法施行規則3条3項かっこ書の「財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合」に該当するものと解されているが、公取委によれば、このようなベンチャーキャピタルであっても改正法上の子会社には該当するとの見解が示されている(届出制度Q&A「届出基準について」Q11)。
11 民法上の組合(民法667条1項)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律2条2項)および有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律2条)ならびに外国法令に基づいて設立された団体であってこれらに類似するものをいう(改正法10条5項)。
12 なお、改正法10条5項は組合自体が株式の取得主体のなる場合の規定であり、たとえば投資ファンドが受皿会社(SPC)を設立の上、株式を取得した場合は、当該SPCが当事会社となるので原則どおり改正法10条2項が適用されることになる。
13 改正法10条6項に基づく親会社の定義は会社等の経営を支配している「会社」であって、組合を含む「会社等」ではない。
14 なお、改正法10条1項に違反する疑いのある行為をする者として、裁判所の緊急停止命令(改正法70条の13第1項参照)の申立てを受けた場合も同様である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















