解説記事2011年09月26日 【ニュース特集】 IFRSの「純額表示」が消費税に及ぼす影響(2011年9月26日号・№420)
会計処理が変われば消費税の課税標準額が変わる可能性も
IFRSの「純額表示」が消費税に及ぼす影響
「売上1兆円企業」などといわれるように、売上の大きさは企業の規模を示すステータスシンボルの1つとなってきた。仮にIFRS(国際会計基準)が導入され売上の「純額表示」が求められることになれば、会計上の売上が大きく減少する企業が出てくることが予想される。そして、この場合に気になるのが、消費税への影響だ。任意適用も含め個別財務諸表にIFRSが導入され、これまで総額表示していた売上を純額表示することとなった場合、消費税の課税標準には総額、純額どちらを採用するのかという問題が生じる。この点については、会計上純額表示が認められることを条件に、消費税法上の課税標準も「純額」とすることも考えられることが本誌取材により確認されている。
在庫リスクない「消化仕入れ」では純額表示が求められる可能性も 売上について「総額表示」を採用している企業が特に多いのは、百貨店やスーパーマーケットをはじめとする小売業だ。以下、百貨店を例にとり、「純額表示」への転換が消費税の課税標準にもたらす影響を整理してみよう。
百貨店には多くのテナントが入っているが、実はテナントに並ぶ商品の所有権は百貨店にはない。百貨店はあえて商品の所有権をテナント側に残しておき、商品が売れるのと同時に(売上とともに)仕入れを計上している。これは一般に「消化仕入れ」といわれており、百貨店にとっては在庫リスクを抱えなくて済むことが大きなメリットとなっている。この消化仕入れにおいては、テナントにおける売上(消費者に対する売上)が百貨店の売上となる(売上の「総額表示」)。そして、消費税法上もこの総額が課税標準となっている(図1参照)。
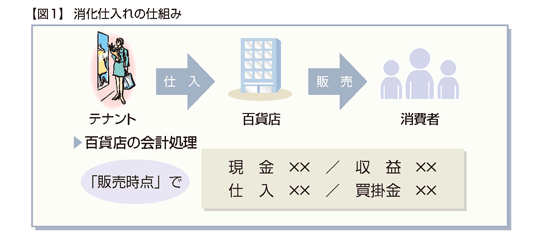
一方、IFRSのなかで売上の計上基準を定めたIAS18号では、企業が自らリスク(在庫リスク等)を保持しておらず、当事者としてではなく、あくまで代理人の立場で販売取引を行っている場合は、「手数料=利益部分」を純額表示しなければならない旨が規定されており、これに照らせば、消化仕入れによる売上には純額表示が求められる可能性が高いといえる。
このように、IFRSの影響で今後わが国においても会計上の売上の純額表示が求められることとなった場合、消費税の課税標準には総額、純額どちらを採用するのかという問題が生じる。仮に純額を採用するとなれば、百貨店のケースでは消化仕入れ方式における売上と仕入れの差額が「純額の売上」として計上されることになり、消費税の課税標準は大幅に圧縮されることになる(図2参照)。
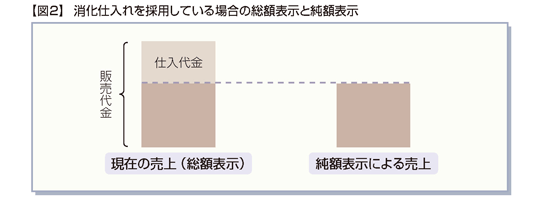
会計処理が「純額」なら、消費税の課税標準も純額に この問題について本誌が当局に取材を行ったところ、仮に売上の会計処理が総額から純額に変更された場合には、消費税法上の課税標準も純額と考えることもできるとの回答を得ている。
たとえば、消費税法基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料)(前頁参照)では、「委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる」と規定している(同通達(2))。
もっとも、この通達はあくまで「委託販売」について定めたものであり、百貨店などが採用する「消化仕入れ」による販売について定めたものではない。商品の販売を自ら行わずに手数料を支払って商品の販売を委託する「委託販売」と消化仕入れは類似しているが、委託販売においては、販売手数料だけが受託者(消化仕入れにおける百貨店)に計上されるのに対し(図3参照)、消化仕入れにおいては、通常の買取り仕入れと同様に、表面上は百貨店に売上と原価が計上されるという点で両者は異なっている。
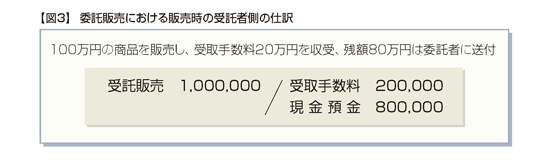
仮に、同通達中の「受託者」の部分を百貨店、「委託者」の部分をテナントと考えると、百貨店がその消化仕入れに係る売上について、仕入れ(テナントからのもの)と売上(消費者に対するもの)を相殺した後の利益(すなわち、百貨店側の手数料)部分のみをもって、課税標準となる対価とみることもできよう。あくまで1つの考え方であり、同通達から消化仕入れに関する取扱いが直接的に導き出されるわけではないが、同通達の考え方を踏まえると、消化仕入れにおいても純額処理が採用された場合には、当該純額をもって課税標準と考えることもできるというわけだ。
ただし当局は、仮に純額をもって消費税の課税標準とする場合には、あくまでその会計処理(経理処理)が企業会計上認められていることが前提になるとしているので注意したい。
仮にIFRSが連結財務諸表のみに適用された場合には、百貨店単体の財務諸表においては総額表示が継続されることになり、その場合、前述の「仮に純額をもって消費税の課税標準とする場合には、あくまでその会計処理(経理処理)が企業会計上認められていることが前提となる」との当局の見解に照らせば、消費税の課税標準もこれまでどおり総額になると考えられる。
一方、現在、日本のASBJ(企業会計基準委員会)では収益の認識に関する論点整理が行われている。可能性としては低いものと想定されるが、国際会計基準とコンバージェンスの観点から、日本国内の基準においてもIAS第18号と同様の考え方が導入されることになれば、日本基準においても消化仕入れは純額表示しなければならないこととなる可能性も少なからずある。その場合には、消費税の課税標準も純額で計上されることになろう。純額表示の問題を含む「収益認識」に関しては、現在IASB(国際会計基準審議会)とFASB(米国財務会計基準審議会)が協議を行っており、両者の協議が確定したうえで、日本国内において、収益認識に関する会計基準が整備されることになろう。消費税の観点からも、議論の行方に注目したいところだ。
IFRSの「純額表示」が消費税に及ぼす影響
「売上1兆円企業」などといわれるように、売上の大きさは企業の規模を示すステータスシンボルの1つとなってきた。仮にIFRS(国際会計基準)が導入され売上の「純額表示」が求められることになれば、会計上の売上が大きく減少する企業が出てくることが予想される。そして、この場合に気になるのが、消費税への影響だ。任意適用も含め個別財務諸表にIFRSが導入され、これまで総額表示していた売上を純額表示することとなった場合、消費税の課税標準には総額、純額どちらを採用するのかという問題が生じる。この点については、会計上純額表示が認められることを条件に、消費税法上の課税標準も「純額」とすることも考えられることが本誌取材により確認されている。
在庫リスクない「消化仕入れ」では純額表示が求められる可能性も 売上について「総額表示」を採用している企業が特に多いのは、百貨店やスーパーマーケットをはじめとする小売業だ。以下、百貨店を例にとり、「純額表示」への転換が消費税の課税標準にもたらす影響を整理してみよう。
百貨店には多くのテナントが入っているが、実はテナントに並ぶ商品の所有権は百貨店にはない。百貨店はあえて商品の所有権をテナント側に残しておき、商品が売れるのと同時に(売上とともに)仕入れを計上している。これは一般に「消化仕入れ」といわれており、百貨店にとっては在庫リスクを抱えなくて済むことが大きなメリットとなっている。この消化仕入れにおいては、テナントにおける売上(消費者に対する売上)が百貨店の売上となる(売上の「総額表示」)。そして、消費税法上もこの総額が課税標準となっている(図1参照)。
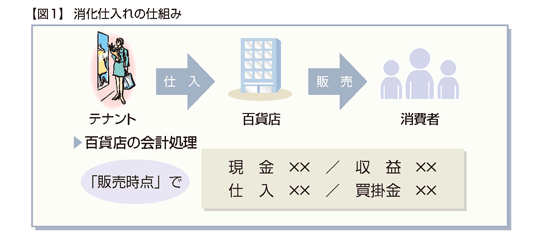
一方、IFRSのなかで売上の計上基準を定めたIAS18号では、企業が自らリスク(在庫リスク等)を保持しておらず、当事者としてではなく、あくまで代理人の立場で販売取引を行っている場合は、「手数料=利益部分」を純額表示しなければならない旨が規定されており、これに照らせば、消化仕入れによる売上には純額表示が求められる可能性が高いといえる。
このように、IFRSの影響で今後わが国においても会計上の売上の純額表示が求められることとなった場合、消費税の課税標準には総額、純額どちらを採用するのかという問題が生じる。仮に純額を採用するとなれば、百貨店のケースでは消化仕入れ方式における売上と仕入れの差額が「純額の売上」として計上されることになり、消費税の課税標準は大幅に圧縮されることになる(図2参照)。
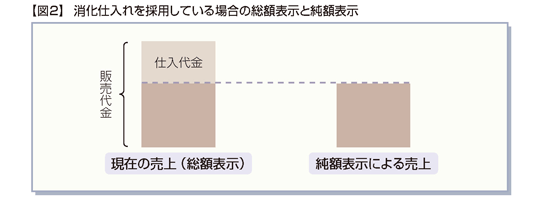
会計処理が「純額」なら、消費税の課税標準も純額に この問題について本誌が当局に取材を行ったところ、仮に売上の会計処理が総額から純額に変更された場合には、消費税法上の課税標準も純額と考えることもできるとの回答を得ている。
たとえば、消費税法基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料)(前頁参照)では、「委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる」と規定している(同通達(2))。
もっとも、この通達はあくまで「委託販売」について定めたものであり、百貨店などが採用する「消化仕入れ」による販売について定めたものではない。商品の販売を自ら行わずに手数料を支払って商品の販売を委託する「委託販売」と消化仕入れは類似しているが、委託販売においては、販売手数料だけが受託者(消化仕入れにおける百貨店)に計上されるのに対し(図3参照)、消化仕入れにおいては、通常の買取り仕入れと同様に、表面上は百貨店に売上と原価が計上されるという点で両者は異なっている。
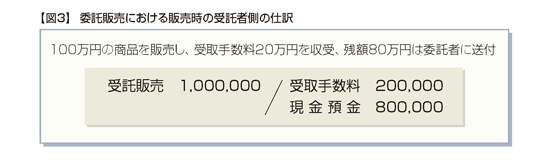
仮に、同通達中の「受託者」の部分を百貨店、「委託者」の部分をテナントと考えると、百貨店がその消化仕入れに係る売上について、仕入れ(テナントからのもの)と売上(消費者に対するもの)を相殺した後の利益(すなわち、百貨店側の手数料)部分のみをもって、課税標準となる対価とみることもできよう。あくまで1つの考え方であり、同通達から消化仕入れに関する取扱いが直接的に導き出されるわけではないが、同通達の考え方を踏まえると、消化仕入れにおいても純額処理が採用された場合には、当該純額をもって課税標準と考えることもできるというわけだ。
ただし当局は、仮に純額をもって消費税の課税標準とする場合には、あくまでその会計処理(経理処理)が企業会計上認められていることが前提になるとしているので注意したい。
仮にIFRSが連結財務諸表のみに適用された場合には、百貨店単体の財務諸表においては総額表示が継続されることになり、その場合、前述の「仮に純額をもって消費税の課税標準とする場合には、あくまでその会計処理(経理処理)が企業会計上認められていることが前提となる」との当局の見解に照らせば、消費税の課税標準もこれまでどおり総額になると考えられる。
一方、現在、日本のASBJ(企業会計基準委員会)では収益の認識に関する論点整理が行われている。可能性としては低いものと想定されるが、国際会計基準とコンバージェンスの観点から、日本国内の基準においてもIAS第18号と同様の考え方が導入されることになれば、日本基準においても消化仕入れは純額表示しなければならないこととなる可能性も少なからずある。その場合には、消費税の課税標準も純額で計上されることになろう。純額表示の問題を含む「収益認識」に関しては、現在IASB(国際会計基準審議会)とFASB(米国財務会計基準審議会)が協議を行っており、両者の協議が確定したうえで、日本国内において、収益認識に関する会計基準が整備されることになろう。消費税の観点からも、議論の行方に注目したいところだ。
| 消費税法基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料) 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。 (1)委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等のすべてについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。 (2)委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。 なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















