解説記事2013年03月18日 【ニュース特集】 “少人数私募節税”のメリットと課税リスク(2013年3月18日号・№491)
28年以降発行分から改正法適用判明で注目集まる
“少人数私募節税”のメリットと課税リスク
本誌既報のとおり、平成25年度税制改正で導入される少人数私募債を利用した節税スキームの“封じ込め措置”の適用開始が、「平成28年1月1日以後に発行された社債」からであることが明らかになったことで、今後3年間弱はその発行が増加しそうだ。
そこで本特集では、金利低迷が継続する中にあっても本スキームに節税メリットがあるのはどのようなケースなのか、また本スキーム実行にあたっての税務上のリスクはどこにあるのかなどについて、関連の法令や規制にも適宜触れながら分析したい。
「27年12月31日以前に発行の社債」は封じ込め措置の適用対象外
平成25年度税制改正で実施される少人数私募債を利用した節税スキームの封じ込め措置の適用開始時期については、少なくとも「28年1月1日以後」であることは本誌でも早々にお伝えしきたところだが(486号8ページ、487号5ページ参照)、それが「28年1月1日以後に支払われるべき利子」からの適用を指すのか、あるいは「28年1月1日以後に発行される社債」からの適用を指すのかは、税制改正大綱からは明らかでなかった。
こうした中、3月1日に国会に提出された平成25年度税制改正法案およびこれに基づく本誌の取材により、今回の節税封じ込め措置は、「平成28年1月1日以後に発行された社債」から適用されることが確認されている(490号7ページに改正条文の読み方の詳細を記載)。
高い利率設定で役員賞与課税も
これまで中小企業のオーナーを中心に利用されてきた少人数私募債の魅力の一つが、その手軽さだ。
「少人数私募債」に該当するための要件は次頁上の図表1のとおりだが、これらの要件を満たすことで有価証券届出書等の提出が不要になる(②③を満たすことで実現)ほか、会社法702条で義務付けられる社債管理者(社債発行会社のために債権保全などを行う。銀行・信託銀行等のみが就任できる)の設置も不要となる(④を満たすことで実現)。
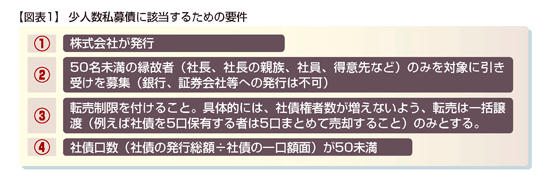
また、少人数私募債は取締役会の承認のみによって発行できる。このような手軽さから、実務上は、税理士が取締役会議事録や社債要項(社債金額や利率、利息の支払い方法、発行価額・償還金額、償還期間等を規定)などの必要書類を内製して節税スキームを実行するケースがほとんどのようだ。
地方自治体の中には、中小企業の資金調達の多様化を支援する観点から、少人数私募債の利子補給を行うなど少人数私募債の発行を支援してきたところもあるが、中小企業のオーナーからすれば、その“節税効果”も発行の目的の一つであることは言うまでもないだろう。
少人数私募債を活用した節税スキームとは、要するに総合課税と源泉分離課税の税率の差を利用したものと言える。仮に社長が会社に金銭を貸し付け、その貸付金について利子を得た場合、当該利子は雑所得として総合課税の対象となる。これに対し、会社が少人数私募債を発行してこれを社長が購入し、社債利子を受け取った場合、現行税法上、当該社債利子は総合課税の対象とはならず、「源泉分離課税」により15%(+住民税5%)の税率が適用されるため(措法3条①)、総合課税の税率がそれより高ければ、その差分が節税できることになる。このため、社長からの借入れを少人数私募債に切り替えるケースがよく見られるようだ。
また、役員給与に対し適用される所得税率が15%より高ければ、役員給与の代わりにその分を少人数私募債の利子として受け取れば、総合課税の税率と15%の差異だけ所得税を節税できることになる(住民税についても、5%(10%-5%)分節税)。
では、この方法により、実際どの程度の節税が可能になるのだろうか。鍵となるのは利率だ。少人数私募債の利率には法的な制限はない。だからと言って、あまり高く利率を設定すれば、適正利率を超える部分に係る利息は役員給与や役員賞与として課税を受ける恐れがある。
これまでの発行例では、銀行の預金金利より少し高めに設定するか、上場会社の社債の金利が参考にされることが多いようだ。ちなみに、2013年2月25日~3月11日までの間に販売されていたソフトバンク株式会社の第41回無担保社債(償還期間4年間)の利率は1.47%(税引前)、2013年3月11日~3月27日を販売期間とする株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの第19回無担保社債(償還期間4年10か月間)の利率は0.21%(税引前)とされている。信用力に劣る中小企業の社債の利率がこれらより高くなることは十分に考えられるが、低金利が続く現在、少人数私募債の利子に明らかに高い利率を設定すれば、それだけ課税リスクは高まると言えるだろう。
少人数私募債の発行のメリットがあるケースとは?
仮に少人数私募債を社長に対し総額6,000万円発行し、その利率が5%(税引前)だとすると、年間の利息は300万円となる。社長の現在の年収を3,000万円とし、少人数私募債の発行を機に、これを利息分の300万円減らして2,700万円に減額すると、上記例①のとおり、90万円の節税メリットが生じることになる。
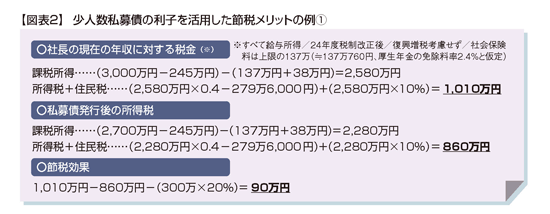
この節税メリットを不十分と考える人もいるだろう。この場合に考えられるのが、少人数私募債の発行総額を引き上げることだ。例えば、発行総額を2億円とした場合、年間の利息は1,000万円になるため、年収を2,000万円に減額すると、上記例②のとおり、節税メリットは285万円に及ぶことになる。
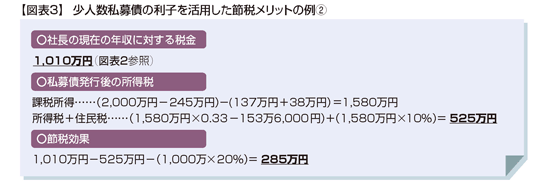
発行総額が1億円以上となる場合には、金商法上「告知義務」が発生することになるが(金商法23条の13④、開示府令14条の15②)、ここでいう告知義務は、下記の事項を社債要項に記入すれば足りる。しかも、告知の相手方となる少人数私募債を引き受ける者は社長本人と親族といったケースが多いため、実質的には特段の負担はないと言っていいだろう。
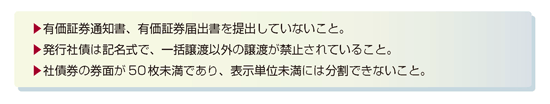
少人数私募債の償還期限は取締役会で自由に設定できるため、償還までの期間を長くすれば、長期に渡り、節税メリットを享受することができる可能性がある。
この点に関し、「ひとたび社債を購入すると、償還期限までは資金を返してもらうことができないので困るのでは」との懸念を抱く実務家もいるが、社債の償還条件は発行会社が自由に決めることができるため、社債要項に「繰上げ償還を認める」旨の規定を入れておけば、償還期限を待たずに資金を回収することも可能だ。
このように、社長が多額の社債を購入するだけの資金力がある場合には節税メリットも大きくなるが、逆に、それほど資金力のない人にとって少人数私募債を発行するメリットはあまりないとの意見もある。ただ、そもそも市中金利が極めて低い中、社長の資産運用という観点からは、保有する現金を銀行預金等にとどめておくよりも、少人数私募債を購入して、一定の節税メリットを受けながら、利息を得た方が得策とも言える。
なお、社債を発行する会社にとっても、社債利子は損金となるほか、支払い日が到来していない利子であっても、当該利子の計算対象期間のうち当該事業年度に属する部分に係る利子は「未払費用」として損金計上することが可能とのメリットがある。
実質的な役員給与と判断される可能性
少人数私募債を活用した節税スキームの封じ込め措置が「平成28年1月1日以後に発行された社債」から適用されることが判明したことに伴い、今後3年弱の期間、少人数私募債を発行する中小企業が増加する可能性は高い。
ただし、節税メリットと同時に、課税上のリスクもある点は認識しておく必要がある。
5ページで述べたように、適正利率を超える部分に係る利息に対する役員給与・賞与課税のほか、少人数私募債の利息そのものが役員給与とみなされる可能性は否定できない。特に、引き受け側が社長一人で、6ページの<少人数私募債の利子を活用した節税メリットの例>のように、利息額と減額された役員給与額の紐付き関係が明確な場合は注意が必要だろう。
こうした課税上のリスクを回避するためには、少人数私募債を発行する理由、すなわち資金調達の必然性が問われることになると考えられる。少人数私募債の発行を支援する自治体があるように、元来、少人数私募債は資金調達の手段であることから、例えば十分なキャッシュがあり資金調達の必然性が低い企業が多額の少人数私募債を発行した場合には、税務当局から「単に役員給与を社債利子に振替えただけではないか」と見られる可能性は否定できない。
少人数私募債発行にあたっては、新規事業の立ち上げや、社長からの借入金を私募債に振り替えることにより、社長と会社との取引関係を明確にするといった何らかの目的、ストーリーが不可欠と言えそうだ。
“少人数私募節税”のメリットと課税リスク
本誌既報のとおり、平成25年度税制改正で導入される少人数私募債を利用した節税スキームの“封じ込め措置”の適用開始が、「平成28年1月1日以後に発行された社債」からであることが明らかになったことで、今後3年間弱はその発行が増加しそうだ。
そこで本特集では、金利低迷が継続する中にあっても本スキームに節税メリットがあるのはどのようなケースなのか、また本スキーム実行にあたっての税務上のリスクはどこにあるのかなどについて、関連の法令や規制にも適宜触れながら分析したい。
「27年12月31日以前に発行の社債」は封じ込め措置の適用対象外
平成25年度税制改正で実施される少人数私募債を利用した節税スキームの封じ込め措置の適用開始時期については、少なくとも「28年1月1日以後」であることは本誌でも早々にお伝えしきたところだが(486号8ページ、487号5ページ参照)、それが「28年1月1日以後に支払われるべき利子」からの適用を指すのか、あるいは「28年1月1日以後に発行される社債」からの適用を指すのかは、税制改正大綱からは明らかでなかった。
こうした中、3月1日に国会に提出された平成25年度税制改正法案およびこれに基づく本誌の取材により、今回の節税封じ込め措置は、「平成28年1月1日以後に発行された社債」から適用されることが確認されている(490号7ページに改正条文の読み方の詳細を記載)。
高い利率設定で役員賞与課税も
これまで中小企業のオーナーを中心に利用されてきた少人数私募債の魅力の一つが、その手軽さだ。
「少人数私募債」に該当するための要件は次頁上の図表1のとおりだが、これらの要件を満たすことで有価証券届出書等の提出が不要になる(②③を満たすことで実現)ほか、会社法702条で義務付けられる社債管理者(社債発行会社のために債権保全などを行う。銀行・信託銀行等のみが就任できる)の設置も不要となる(④を満たすことで実現)。
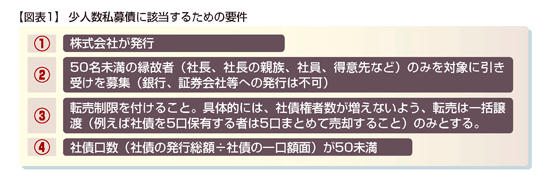
また、少人数私募債は取締役会の承認のみによって発行できる。このような手軽さから、実務上は、税理士が取締役会議事録や社債要項(社債金額や利率、利息の支払い方法、発行価額・償還金額、償還期間等を規定)などの必要書類を内製して節税スキームを実行するケースがほとんどのようだ。
地方自治体の中には、中小企業の資金調達の多様化を支援する観点から、少人数私募債の利子補給を行うなど少人数私募債の発行を支援してきたところもあるが、中小企業のオーナーからすれば、その“節税効果”も発行の目的の一つであることは言うまでもないだろう。
少人数私募債を活用した節税スキームとは、要するに総合課税と源泉分離課税の税率の差を利用したものと言える。仮に社長が会社に金銭を貸し付け、その貸付金について利子を得た場合、当該利子は雑所得として総合課税の対象となる。これに対し、会社が少人数私募債を発行してこれを社長が購入し、社債利子を受け取った場合、現行税法上、当該社債利子は総合課税の対象とはならず、「源泉分離課税」により15%(+住民税5%)の税率が適用されるため(措法3条①)、総合課税の税率がそれより高ければ、その差分が節税できることになる。このため、社長からの借入れを少人数私募債に切り替えるケースがよく見られるようだ。
また、役員給与に対し適用される所得税率が15%より高ければ、役員給与の代わりにその分を少人数私募債の利子として受け取れば、総合課税の税率と15%の差異だけ所得税を節税できることになる(住民税についても、5%(10%-5%)分節税)。
では、この方法により、実際どの程度の節税が可能になるのだろうか。鍵となるのは利率だ。少人数私募債の利率には法的な制限はない。だからと言って、あまり高く利率を設定すれば、適正利率を超える部分に係る利息は役員給与や役員賞与として課税を受ける恐れがある。
これまでの発行例では、銀行の預金金利より少し高めに設定するか、上場会社の社債の金利が参考にされることが多いようだ。ちなみに、2013年2月25日~3月11日までの間に販売されていたソフトバンク株式会社の第41回無担保社債(償還期間4年間)の利率は1.47%(税引前)、2013年3月11日~3月27日を販売期間とする株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの第19回無担保社債(償還期間4年10か月間)の利率は0.21%(税引前)とされている。信用力に劣る中小企業の社債の利率がこれらより高くなることは十分に考えられるが、低金利が続く現在、少人数私募債の利子に明らかに高い利率を設定すれば、それだけ課税リスクは高まると言えるだろう。
少人数私募債の発行のメリットがあるケースとは?
仮に少人数私募債を社長に対し総額6,000万円発行し、その利率が5%(税引前)だとすると、年間の利息は300万円となる。社長の現在の年収を3,000万円とし、少人数私募債の発行を機に、これを利息分の300万円減らして2,700万円に減額すると、上記例①のとおり、90万円の節税メリットが生じることになる。
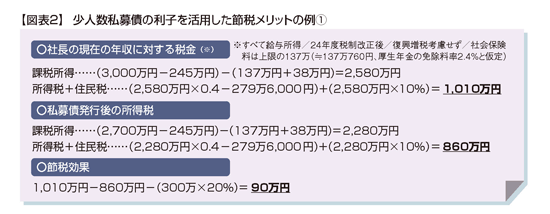
この節税メリットを不十分と考える人もいるだろう。この場合に考えられるのが、少人数私募債の発行総額を引き上げることだ。例えば、発行総額を2億円とした場合、年間の利息は1,000万円になるため、年収を2,000万円に減額すると、上記例②のとおり、節税メリットは285万円に及ぶことになる。
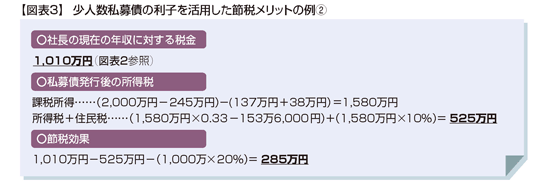
発行総額が1億円以上となる場合には、金商法上「告知義務」が発生することになるが(金商法23条の13④、開示府令14条の15②)、ここでいう告知義務は、下記の事項を社債要項に記入すれば足りる。しかも、告知の相手方となる少人数私募債を引き受ける者は社長本人と親族といったケースが多いため、実質的には特段の負担はないと言っていいだろう。
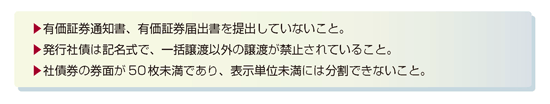
少人数私募債の償還期限は取締役会で自由に設定できるため、償還までの期間を長くすれば、長期に渡り、節税メリットを享受することができる可能性がある。
この点に関し、「ひとたび社債を購入すると、償還期限までは資金を返してもらうことができないので困るのでは」との懸念を抱く実務家もいるが、社債の償還条件は発行会社が自由に決めることができるため、社債要項に「繰上げ償還を認める」旨の規定を入れておけば、償還期限を待たずに資金を回収することも可能だ。
このように、社長が多額の社債を購入するだけの資金力がある場合には節税メリットも大きくなるが、逆に、それほど資金力のない人にとって少人数私募債を発行するメリットはあまりないとの意見もある。ただ、そもそも市中金利が極めて低い中、社長の資産運用という観点からは、保有する現金を銀行預金等にとどめておくよりも、少人数私募債を購入して、一定の節税メリットを受けながら、利息を得た方が得策とも言える。
なお、社債を発行する会社にとっても、社債利子は損金となるほか、支払い日が到来していない利子であっても、当該利子の計算対象期間のうち当該事業年度に属する部分に係る利子は「未払費用」として損金計上することが可能とのメリットがある。
実質的な役員給与と判断される可能性
少人数私募債を活用した節税スキームの封じ込め措置が「平成28年1月1日以後に発行された社債」から適用されることが判明したことに伴い、今後3年弱の期間、少人数私募債を発行する中小企業が増加する可能性は高い。
ただし、節税メリットと同時に、課税上のリスクもある点は認識しておく必要がある。
5ページで述べたように、適正利率を超える部分に係る利息に対する役員給与・賞与課税のほか、少人数私募債の利息そのものが役員給与とみなされる可能性は否定できない。特に、引き受け側が社長一人で、6ページの<少人数私募債の利子を活用した節税メリットの例>のように、利息額と減額された役員給与額の紐付き関係が明確な場合は注意が必要だろう。
こうした課税上のリスクを回避するためには、少人数私募債を発行する理由、すなわち資金調達の必然性が問われることになると考えられる。少人数私募債の発行を支援する自治体があるように、元来、少人数私募債は資金調達の手段であることから、例えば十分なキャッシュがあり資金調達の必然性が低い企業が多額の少人数私募債を発行した場合には、税務当局から「単に役員給与を社債利子に振替えただけではないか」と見られる可能性は否定できない。
少人数私募債発行にあたっては、新規事業の立ち上げや、社長からの借入金を私募債に振り替えることにより、社長と会社との取引関係を明確にするといった何らかの目的、ストーリーが不可欠と言えそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























