解説記事2014年10月20日 【ニュース特集】 事前照会のリスクと活用(2014年10月20日号・№567)
事前照会を受けた事案で否認が発生
事前照会のリスクと活用
大型の組織再編や法令解釈が難しい事例について事前照会制度を活用する企業は多いが、このほど事前照会により「適格現物出資」との確認を受けたにもかかわらず、後の税務調査で適格性について否認を受ける事案が発生し、企業や実務家の間で波紋が広がっている。
ただ、元々わが国の事前照会制度は米国等における「ノーアクションレター」とは異なり、事前照会を経たからといって否認を行わないことを確約するものではなく、利用にあたっては少なからずリスクやデメリットも存在する。
本特集では、今回否認を受けた事案の内容を詳しく分析するとともに、これまであまり注目されてこなかった事前照会制度のリスクやデメリットを明らかにし、その有益な活用方法について検討したい。
事前照会を半ば社内ルール化している企業も
まず、事前照会制度とはどのようなものなのか、整理しておこう。
事前照会というと、高度で複雑な案件のみを対象としているイメージがあるかも知れないが、そうではない。図1のとおり、税務当局では、税務相談室への一般的な内容の電話相談も事前照会の1つに位置付けている。逆に、公開を前提とした文書回答のような大掛かりな照会手続も、事前照会に該当する。
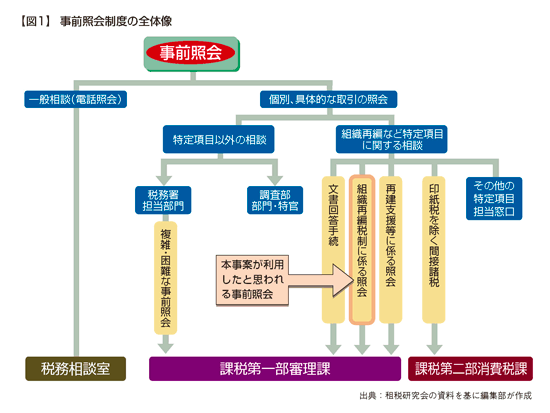
もっとも、企業や実務家にとって事前照会と言えば、組織再編税制がらみのものをはじめ、解釈に疑義が生じやすく、また否認を受けた場合には追徴税額が巨額になりやすい事案を指すのが一般的だろう。
事前照会は企業や実務家に広く利用されており、特に大企業では、解釈に疑義のある重要案件については事前照会を行うことが半ば社内ルール化しているところもある。
こうした中、事前照会手続きを踏んだにもかかわらず、その後の税務調査で、事前照会で確認した内容を覆す形で否認を受ける事例が発生し、企業や実務家の間で大きな波紋が広がっている。
一見すると適格要件を満たしているようにも見えるが……
否認を受けた事案は、日本企業A社が、英国企業B社と50:50の共同出資でケイマンに設立した会社(以下、JV)の持分を、英国にあるA社の100%子会社a社に「税制適格」として現物出資したもの(図2参照)。
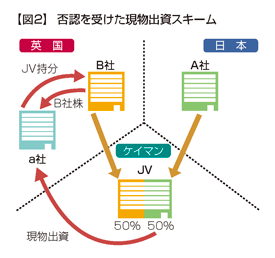
まず、この現物出資の税制上の適格性について検討してみよう。
法人税法上、適格現物出資の範囲からは「外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの」は除かれている(法法2条十二の十四)。そして、これを受けた政令では、「国内にある資産又は負債」とは、「国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債」とされている(法令4条の3⑨)。
この政令の規定を本事案に当てはめると、A社のJVに対して持分50%を保有しているため、当該持分は「国内にある資産又は負債」には該当せず(=カッコ書きの要件に該当せず)、その結果、適格現物出資の範囲から除かれる「外国法人に国内にある資産又は負債の移転を行うもの」にも該当しないと考えられる。
このように、一見すると、当該現物出資は「適格現物出資」に該当するようにも見える。実際、A社は事前照会により、当該現物出資の「適格性」について税務当局の確認を得ていたという。
しかし、税務当局は、事前照会では適格とした現物出資を税務調査で一転「非適格」として、否認を行っている。
JVへの出資持分は株式or資産負債?
では、事前照会で確認を受けたにもかかわらず、なぜ後から否認されることになったのだろうか。
一部の実務家からは、組織再編税制に係る行為計算否認規定である法人税法132条の2が適用されたのではないかとの声も聞かれるが、本事案は同条の適用ケースではない模様だ。
詳細は必ずしも明らかになっていないが、上記法人税法施行令4条の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産又は負債」の解釈が事前照会後に問題化した可能性がある。
A社が有するJVへの出資持分を「株式」と考えれば、上述のとおり、法人税法施行令4条の3第9項では「外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式」は「国内にある事業所に属する資産」から除かれているため、その現物出資は税制適格になると考えられる。
これに対し、出資持分を「個々の資産負債の持分割合」に相当する資産負債ととらえた場合には、本事案は「国内にある資産又は負債」を外国法人に移転したものとして、非適格現物出資に該当すると判断される恐れもある。仮に出資持分が国内の事業所の資産として記帳されていれば、そのリスクは一層高まる。
英国では譲渡益への課税なし
また、本事案のスキームの特殊性も否認を受ける遠因になった可能性は否定できないだろう。
本事案では、A社がa社に(適格で)現物出資したJVの持分は、その後、a社から(A社の共同出資のパートナーである)英国のB社に譲渡され、a社はその対価としてB社の株式の10%を取得している。
A社からa社への現物出資が適格であれば日本の税制上、課税は起こらないが、さらにa社からB社への譲渡は「JVの持分」と「B社の株式」の交換とされ、英国でもこれに係る譲渡益への課税は行われなかったとみられる。
このスキームについて税務当局が、「実態はA社からB社に対するJV持分の譲渡であるにもかかわらず、a社を経由して譲渡することで課税を免れたのではないか」との疑念を抱き、これが否認のきっかけになったことも考えられる。
事実認定に左右される事項の事前照会にリスク
どのような事情・背景があったにせよ、「事前照会で確認を得たにもかかわらず否認を受けた」という事実に対し、企業や実務家は強い懸念を抱いている。なかには、事前照会制度の存在意義が問われかねないとする声もある。
では、本事案をきっかけに、事前照会で確認されたことが容易に覆されるようになるのかというと、それは考えにくい。信義則の観点からも、税務当局が事前照会で「課税されない」と回答したものを理由もなく覆すことはないとみてよい。
もし事前照会の回答を覆すとすれば、それは事前照会の段階では把握されていなかった“新たな事実”が税務調査によって把握されたケースがほとんどと考えられる。
ただ、その一方で、今回の事案が、これまであまり認識されてこなかった事前照会制度のリスクを浮き彫りにしたのも確かであろう。
まず改めて確認しておきたいのは、わが国の事前照会制度は米国などにおける「ノーアクションレター」ではないという点だ。すなわち、事前照会で税務当局から「課税されない」という回答を得たとしても、それは「税務調査で否認しない」ことを確約するものではないということを、企業や実務家は認識しておく必要がある。
また、上述のとおり、事前照会の段階で把握されていなかった“新たな事実”が税務調査で把握されれば事前照会の回答が覆される可能性があるが、税務訴訟等でしばしば事実認定を巡り争いがあるように、「事実」は見る人によっても、視点によっても変わってくる。したがって、事実認定に結論が左右されるような事項については、そもそも事前照会を行うこと自体、それなりのリスクが伴うという点に留意しなければならない。
そう考えると、「租税回避に当たるかどうか」の判断も事実認定に大きく左右される傾向があるだけに、事前照会にはあまり適していないと言えよう。
さらに、税務訴訟等で法令解釈が争われることがあることがあるように、事前照会において示された法令解釈が絶対的なものであるとは限らない。特に解釈が微妙な場合には、今回のA社の例のように、後で解釈が変更されることも、レアケースとはいえ、あり得ないことではないだろう。
「課税されない」との回答がビジネス上の選択肢を限定する結果に
法令解釈が微妙なスキームについて、仮に事前照会で「NG(実行すれば否認される)」との回答が出た場合、企業が当該スキームを実行する道は事実上ふさがれることになる。企業側で法令解釈に自信を持ち、また当該スキームがビジネス上極めて重要な意味を持っていたとしても、否認を受けることが目に見えている中では、スキームの実行は断念せざるを得ないだろう。
後の税務調査で否認を行わないことを確約するものではないとはいえ、一定の“お墨付き”を与えることになる以上、税務当局が事前照会に対して慎重な姿勢で臨むのはやむを得ないところであり、その分、場合によっては通常の税務調査よりも事前照会の方が“保守的”な回答が出やすいとも考えられる。だとすれば、あえて「事前照会を行わない」ということも、選択肢としてはあり得るだろう。
ちなみに、事前照会でNGとなった場合、これが税務調査で是認されることはまずないと考えて間違いない。事前照会における回答は、当然調査担当部署にも回覧されるからだ。
逆に、事前照会で「課税されない」という回答をもらったことで、ビジネス上の柔軟性が失われてしまうことも考えられる。例えば、事前照会により「課税されない」との回答を得たスキームをいざ実行する段階で、実はそのスキームにビジネス上の重大な問題点が発見されたとする。この場合、仮にスキームを変更すれば、税務当局にとっては、まさに上述した「事前照会の段階では把握されていなかった“新たな事実”」が出てきたことになり、否認を受ける可能性が生じる。
最適なビジネススキームは時間の経過やちょっとした環境の変化によって変わり得る。企業や顧問税理士等は、事前照会を行っていなければスキームを変更することは容易であるが、一度事前照会を行って回答を得れば、スキームの変更には大きなリスクが伴うということを踏まえた上で、事前照会を行う必要がある。
「聞き方」を間違えれば答えも変わる
ここまで述べたような事前照会のリスクやデメリットを踏まえると、事前照会は、事業認定とは関係のない個別規定の解釈や適用関係を確認するという使い方が最も適していると言えるだろう。
ただ、実際に事前照会を行った税理士や弁護士からは、「聞き方によって回答が違う」あるいは「聞き方を失敗してしまった」といった声も聞かれる。この結果、意に反する回答をもらってしまった場合、予定していたスキームが実行できなくなる恐れもある。
したがって、事前照会を行う場合には、解釈等を徹底的に詰めた上で、“適切な聞き方”によって、「意図していた回答」を得られるようにすることが、事前照会制度のもっとも有効な活用方法と言える。
そう考えると、事前照会は極めて専門性の高い業務であり、事前照会を行う場合には、その分野について高度な知見を有することはもちろん、実際に事前照会を行い、かつ成功した(予定通りの回答を引き出した)経験を豊富に持つ専門家を活用するのが無難と言えそうだ。
事前照会のリスクと活用
大型の組織再編や法令解釈が難しい事例について事前照会制度を活用する企業は多いが、このほど事前照会により「適格現物出資」との確認を受けたにもかかわらず、後の税務調査で適格性について否認を受ける事案が発生し、企業や実務家の間で波紋が広がっている。
ただ、元々わが国の事前照会制度は米国等における「ノーアクションレター」とは異なり、事前照会を経たからといって否認を行わないことを確約するものではなく、利用にあたっては少なからずリスクやデメリットも存在する。
本特集では、今回否認を受けた事案の内容を詳しく分析するとともに、これまであまり注目されてこなかった事前照会制度のリスクやデメリットを明らかにし、その有益な活用方法について検討したい。
事前照会を半ば社内ルール化している企業も
まず、事前照会制度とはどのようなものなのか、整理しておこう。
事前照会というと、高度で複雑な案件のみを対象としているイメージがあるかも知れないが、そうではない。図1のとおり、税務当局では、税務相談室への一般的な内容の電話相談も事前照会の1つに位置付けている。逆に、公開を前提とした文書回答のような大掛かりな照会手続も、事前照会に該当する。
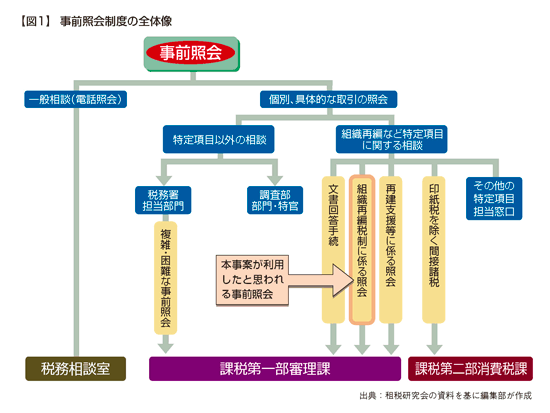
もっとも、企業や実務家にとって事前照会と言えば、組織再編税制がらみのものをはじめ、解釈に疑義が生じやすく、また否認を受けた場合には追徴税額が巨額になりやすい事案を指すのが一般的だろう。
事前照会は企業や実務家に広く利用されており、特に大企業では、解釈に疑義のある重要案件については事前照会を行うことが半ば社内ルール化しているところもある。
こうした中、事前照会手続きを踏んだにもかかわらず、その後の税務調査で、事前照会で確認した内容を覆す形で否認を受ける事例が発生し、企業や実務家の間で大きな波紋が広がっている。
一見すると適格要件を満たしているようにも見えるが……
否認を受けた事案は、日本企業A社が、英国企業B社と50:50の共同出資でケイマンに設立した会社(以下、JV)の持分を、英国にあるA社の100%子会社a社に「税制適格」として現物出資したもの(図2参照)。
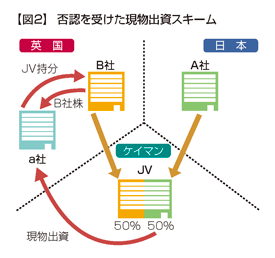
まず、この現物出資の税制上の適格性について検討してみよう。
法人税法上、適格現物出資の範囲からは「外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの」は除かれている(法法2条十二の十四)。そして、これを受けた政令では、「国内にある資産又は負債」とは、「国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債」とされている(法令4条の3⑨)。
この政令の規定を本事案に当てはめると、A社のJVに対して持分50%を保有しているため、当該持分は「国内にある資産又は負債」には該当せず(=カッコ書きの要件に該当せず)、その結果、適格現物出資の範囲から除かれる「外国法人に国内にある資産又は負債の移転を行うもの」にも該当しないと考えられる。
このように、一見すると、当該現物出資は「適格現物出資」に該当するようにも見える。実際、A社は事前照会により、当該現物出資の「適格性」について税務当局の確認を得ていたという。
しかし、税務当局は、事前照会では適格とした現物出資を税務調査で一転「非適格」として、否認を行っている。
JVへの出資持分は株式or資産負債?
では、事前照会で確認を受けたにもかかわらず、なぜ後から否認されることになったのだろうか。
一部の実務家からは、組織再編税制に係る行為計算否認規定である法人税法132条の2が適用されたのではないかとの声も聞かれるが、本事案は同条の適用ケースではない模様だ。
詳細は必ずしも明らかになっていないが、上記法人税法施行令4条の3第9項にいう「国内にある事業所に属する資産又は負債」の解釈が事前照会後に問題化した可能性がある。
A社が有するJVへの出資持分を「株式」と考えれば、上述のとおり、法人税法施行令4条の3第9項では「外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式」は「国内にある事業所に属する資産」から除かれているため、その現物出資は税制適格になると考えられる。
これに対し、出資持分を「個々の資産負債の持分割合」に相当する資産負債ととらえた場合には、本事案は「国内にある資産又は負債」を外国法人に移転したものとして、非適格現物出資に該当すると判断される恐れもある。仮に出資持分が国内の事業所の資産として記帳されていれば、そのリスクは一層高まる。
英国では譲渡益への課税なし
また、本事案のスキームの特殊性も否認を受ける遠因になった可能性は否定できないだろう。
本事案では、A社がa社に(適格で)現物出資したJVの持分は、その後、a社から(A社の共同出資のパートナーである)英国のB社に譲渡され、a社はその対価としてB社の株式の10%を取得している。
A社からa社への現物出資が適格であれば日本の税制上、課税は起こらないが、さらにa社からB社への譲渡は「JVの持分」と「B社の株式」の交換とされ、英国でもこれに係る譲渡益への課税は行われなかったとみられる。
このスキームについて税務当局が、「実態はA社からB社に対するJV持分の譲渡であるにもかかわらず、a社を経由して譲渡することで課税を免れたのではないか」との疑念を抱き、これが否認のきっかけになったことも考えられる。
事実認定に左右される事項の事前照会にリスク
どのような事情・背景があったにせよ、「事前照会で確認を得たにもかかわらず否認を受けた」という事実に対し、企業や実務家は強い懸念を抱いている。なかには、事前照会制度の存在意義が問われかねないとする声もある。
では、本事案をきっかけに、事前照会で確認されたことが容易に覆されるようになるのかというと、それは考えにくい。信義則の観点からも、税務当局が事前照会で「課税されない」と回答したものを理由もなく覆すことはないとみてよい。
もし事前照会の回答を覆すとすれば、それは事前照会の段階では把握されていなかった“新たな事実”が税務調査によって把握されたケースがほとんどと考えられる。
ただ、その一方で、今回の事案が、これまであまり認識されてこなかった事前照会制度のリスクを浮き彫りにしたのも確かであろう。
まず改めて確認しておきたいのは、わが国の事前照会制度は米国などにおける「ノーアクションレター」ではないという点だ。すなわち、事前照会で税務当局から「課税されない」という回答を得たとしても、それは「税務調査で否認しない」ことを確約するものではないということを、企業や実務家は認識しておく必要がある。
また、上述のとおり、事前照会の段階で把握されていなかった“新たな事実”が税務調査で把握されれば事前照会の回答が覆される可能性があるが、税務訴訟等でしばしば事実認定を巡り争いがあるように、「事実」は見る人によっても、視点によっても変わってくる。したがって、事実認定に結論が左右されるような事項については、そもそも事前照会を行うこと自体、それなりのリスクが伴うという点に留意しなければならない。
そう考えると、「租税回避に当たるかどうか」の判断も事実認定に大きく左右される傾向があるだけに、事前照会にはあまり適していないと言えよう。
さらに、税務訴訟等で法令解釈が争われることがあることがあるように、事前照会において示された法令解釈が絶対的なものであるとは限らない。特に解釈が微妙な場合には、今回のA社の例のように、後で解釈が変更されることも、レアケースとはいえ、あり得ないことではないだろう。
「課税されない」との回答がビジネス上の選択肢を限定する結果に
法令解釈が微妙なスキームについて、仮に事前照会で「NG(実行すれば否認される)」との回答が出た場合、企業が当該スキームを実行する道は事実上ふさがれることになる。企業側で法令解釈に自信を持ち、また当該スキームがビジネス上極めて重要な意味を持っていたとしても、否認を受けることが目に見えている中では、スキームの実行は断念せざるを得ないだろう。
後の税務調査で否認を行わないことを確約するものではないとはいえ、一定の“お墨付き”を与えることになる以上、税務当局が事前照会に対して慎重な姿勢で臨むのはやむを得ないところであり、その分、場合によっては通常の税務調査よりも事前照会の方が“保守的”な回答が出やすいとも考えられる。だとすれば、あえて「事前照会を行わない」ということも、選択肢としてはあり得るだろう。
ちなみに、事前照会でNGとなった場合、これが税務調査で是認されることはまずないと考えて間違いない。事前照会における回答は、当然調査担当部署にも回覧されるからだ。
逆に、事前照会で「課税されない」という回答をもらったことで、ビジネス上の柔軟性が失われてしまうことも考えられる。例えば、事前照会により「課税されない」との回答を得たスキームをいざ実行する段階で、実はそのスキームにビジネス上の重大な問題点が発見されたとする。この場合、仮にスキームを変更すれば、税務当局にとっては、まさに上述した「事前照会の段階では把握されていなかった“新たな事実”」が出てきたことになり、否認を受ける可能性が生じる。
最適なビジネススキームは時間の経過やちょっとした環境の変化によって変わり得る。企業や顧問税理士等は、事前照会を行っていなければスキームを変更することは容易であるが、一度事前照会を行って回答を得れば、スキームの変更には大きなリスクが伴うということを踏まえた上で、事前照会を行う必要がある。
「聞き方」を間違えれば答えも変わる
ここまで述べたような事前照会のリスクやデメリットを踏まえると、事前照会は、事業認定とは関係のない個別規定の解釈や適用関係を確認するという使い方が最も適していると言えるだろう。
ただ、実際に事前照会を行った税理士や弁護士からは、「聞き方によって回答が違う」あるいは「聞き方を失敗してしまった」といった声も聞かれる。この結果、意に反する回答をもらってしまった場合、予定していたスキームが実行できなくなる恐れもある。
したがって、事前照会を行う場合には、解釈等を徹底的に詰めた上で、“適切な聞き方”によって、「意図していた回答」を得られるようにすることが、事前照会制度のもっとも有効な活用方法と言える。
そう考えると、事前照会は極めて専門性の高い業務であり、事前照会を行う場合には、その分野について高度な知見を有することはもちろん、実際に事前照会を行い、かつ成功した(予定通りの回答を引き出した)経験を豊富に持つ専門家を活用するのが無難と言えそうだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















