解説記事2016年03月14日 【税理士のための相続法講座】 相続財産と債務(1)-相続財産に属さないもの(2016年3月14日号・№634)
税理士のための相続法講座
第13回
相続財産と債務(1)-相続財産に属さないもの
弁護士 間瀬まゆ子
今回から、「相続財産と債務」のテーマに移ります。その1回目となる今回は、相続財産に含まれないものを採りあげます。
相続人は、被相続人の一身専属権を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。「一切の権利」とありますので、被相続人に関わる財産は全て相続人に移転するようにも思われますが、以下に掲げる財産は相続財産に含まれないとされています。
1 一身専属権 一身専属権にあたることに争いがないのが、扶養請求権や生活保護法に基づく保護受給権等です(ただ、扶養請求権についても、調停が成立する等して金銭債権として具体化していた場合は、一身専属権ではなく相続可能と解されます。)。
かつて、殺された被相続人の慰謝料請求権が、一身専属権であり相続財産性を否定すべきではないかと議論がされた時代がありました。この点、戦前の大審院は、被相続人が何らかの形で請求の意思を表示したときは金銭債権に転化して相続の対象となると判示し、例えば、いわゆる残念事件(大判昭和2年5月30日)において、交通事故の直後に被害者が「残念」と言って死亡した事案につき、この言葉を被相続人の慰謝料請求の意思表示であると捉え、相続財産性を肯定しました。
しかし、被相続人が何らかの意思表示をしたか否かによって結論が異なるというのはいかにも不合理です。そこで、戦後の最高裁は判例を変更し、慰謝料請求権そのものは単純な金銭債権に過ぎないとして一身専属性を否定しました(最大判昭和42年11月1日民集21巻9号2249頁)。そのため、現在では、格別の意思表示を要求せず、相続人が当然に被相続人の慰謝料請求権を相続するとの取扱いがなされています。
2 祭具・墳墓 祭具(位牌、仏壇等)や墳墓(墓石等)については、前掲の民法896条が適用されず、祭祀主宰者が承継することとされます。祭祀主宰者は、①被相続人の指定により(指定の方法は遺言に限らず生前でも可能)、②指定がない場合は慣習に従って、③慣習が明らかでない場合は裁判所の決定により定められることになります(民法897条)。ただ、実務上、当事者間に紛争がなくても、墓地管理者との関係で手続きが面倒になる場合がありますので、祭祀主宰者は遺言で決めておくのが確実です。
なお、墓地は厳密にいうと「墳墓」には含まれませんが、これと同様に取り扱われています。また、遺骨についても、明文はないものの、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとした判例があります(最三小判平成元年7月18日家月41巻10号128頁)。
3 生命保険金 被相続人の死亡によって生じる生命保険金請求権は、被相続人が取得した権利を相続人が承継するものではなく、受取人が固有の権利として取得するものと解されています。したがって、相続財産には含まれません。
この点、受取人が特定の相続人に指定されている場合に限らず、抽象的に「相続人」とのみ指定されている場合や、受取人の指定がなく約款により相続人が受け取ることになる場合においても、当該保険金の請求権は相続財産に属さないことになります。
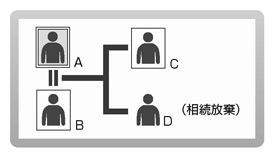
上記の事例で、誰が幾らの保険金を受け取れることになるでしょうか。
受取人は、法定相続人であるB、C及びDです。保険金請求権は相続財産ではなく受取人固有の権利ですので、相続放棄をしたDも権利を失うことはありません。
また、各相続人が取得する割合については、かつて議論が分かれていました。この点、可分債権は各債権者が等分に権利を有する旨定めた民法427条の規定に従い、各受取人の取得割合は平等となるとする下級審裁判例もありましたが(上記の事例にあてはめると、3人の法定相続人が1/3の1,000万円ずつを取得することになります。)、最高裁は、受取人を相続人とする指定には、特段の事情のない限り、相続人が受け取る権利の割合を法定相続分の割合とする旨の指定も含まれるとの判断を下しました(最二小判平成6年7月18日民集48巻5号1233頁)。
したがって、配偶者Bは3,000万円×1/2の1,500万円、子C及びDはそれぞれ3,000万円×1/2×1/2の750万円の保険金請求権を取得することになります。
上記のとおり、生命保険金は相続財産でないと解されています。しかし、そうなると、例えば被相続人が生前に、財産の大部分を払い込んで特定の相続人を受取人とする生命保険に加入したような場合に、当該相続人に比して他の相続人が僅かな財産しか取得できないことになり、相続人間の公平の問題が生じます。
そのため、「第10回 相続分(4)-特別受益」(本誌622号23頁)でも触れたとおり、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定めた民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて死亡保険金も持戻しの対象とするのが判例の立場です(最二小決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。
4 死亡退職金・遺族給付 死亡退職金については、支給規程があるか否かによって場合分けをして考えます。
支給規程がある場合には、支給基準のほか、受給権者の範囲または順位等の規定に従って相続財産性を判断することになります。支給規程があり、受給権者が明確に定められている場合には、受給権者が固有の権利として取得するものであると解され、相続財産には含めないことになります。支給規程があっても、受給権者が明確に定められていない場合については、単に「遺族にこれを支給する。」とのみ定めていた学校法人の事案について、この規程が専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とすると解して、内縁の妻を第一順位の受給権者とした判例が参考になります(最一小判昭和60年1月31日家月37巻8号39頁)。
一方、支給規程がない場合には、支給決定の内容等を踏まえて、事案ごとに相続財産か支給をされた者の固有の財産かを判断することになります。この点、支給規程のない財団法人が、死亡した理事長の妻に対して死亡退職金の支給決定をした上でこれを支払った事案につき、当該死亡退職金は、相続人の代表として妻に支払われたものではなく、相続と無関係に妻個人に支給されたと判断した判例もあります(最三小判昭和62年3月3日家月39巻10号61頁)。
死亡退職金が特別受益に準じて持戻しの対象となるかは、最終的には実質的に相続人間の公平を害することにならないか個別に判断して決めることになるでしょう。ただ、一般的には、受給権者の生活保障を目的として支給されるものであることから、持戻しの対象としないことが多いと思われます。
遺族年金や弔慰金等の遺族給付は、遺族固有の権利であって、相続財産には属さないと解するのが一般的です。
5 ジョイント・アカウント預金
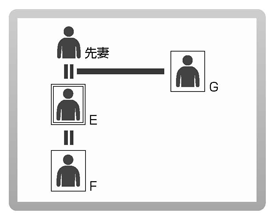
日本では認められていませんが、被相続人が生前に海外でジョイント・アカウント(共同名義口座)を開設している場合があります。ジョイント・アカウントとは、2名以上の名義人で開設する預金口座のことで、一人の名義人が死亡すると自動的に口座残高が生存名義人に移転されることになるのが一般的なようです。
このようなジョイント・アカウントによる預金債権に関して、相続財産に含まれるか訴訟で争われたのが上記の事例です。
この事案で裁判所は、ハワイ州法では共同名義人の一人の死亡により生存名義人が自動的に死亡名義人の財産を所有されていることなどを根拠として、当該ジョイント・アカウントに係る預金債権は被相続人の私法上の相続財産を構成しないと判断し、Gの請求を斥けました(東京地判平成26年7月8日判タ1415号283頁)。
なお、本件で、税務当局は、死因贈与(遺贈)による取得に当たり、相続税の課税対象となると判断したようです。
第13回
相続財産と債務(1)-相続財産に属さないもの
弁護士 間瀬まゆ子
今回から、「相続財産と債務」のテーマに移ります。その1回目となる今回は、相続財産に含まれないものを採りあげます。
相続人は、被相続人の一身専属権を除き、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。「一切の権利」とありますので、被相続人に関わる財産は全て相続人に移転するようにも思われますが、以下に掲げる財産は相続財産に含まれないとされています。
1 一身専属権 一身専属権にあたることに争いがないのが、扶養請求権や生活保護法に基づく保護受給権等です(ただ、扶養請求権についても、調停が成立する等して金銭債権として具体化していた場合は、一身専属権ではなく相続可能と解されます。)。
かつて、殺された被相続人の慰謝料請求権が、一身専属権であり相続財産性を否定すべきではないかと議論がされた時代がありました。この点、戦前の大審院は、被相続人が何らかの形で請求の意思を表示したときは金銭債権に転化して相続の対象となると判示し、例えば、いわゆる残念事件(大判昭和2年5月30日)において、交通事故の直後に被害者が「残念」と言って死亡した事案につき、この言葉を被相続人の慰謝料請求の意思表示であると捉え、相続財産性を肯定しました。
しかし、被相続人が何らかの意思表示をしたか否かによって結論が異なるというのはいかにも不合理です。そこで、戦後の最高裁は判例を変更し、慰謝料請求権そのものは単純な金銭債権に過ぎないとして一身専属性を否定しました(最大判昭和42年11月1日民集21巻9号2249頁)。そのため、現在では、格別の意思表示を要求せず、相続人が当然に被相続人の慰謝料請求権を相続するとの取扱いがなされています。
2 祭具・墳墓 祭具(位牌、仏壇等)や墳墓(墓石等)については、前掲の民法896条が適用されず、祭祀主宰者が承継することとされます。祭祀主宰者は、①被相続人の指定により(指定の方法は遺言に限らず生前でも可能)、②指定がない場合は慣習に従って、③慣習が明らかでない場合は裁判所の決定により定められることになります(民法897条)。ただ、実務上、当事者間に紛争がなくても、墓地管理者との関係で手続きが面倒になる場合がありますので、祭祀主宰者は遺言で決めておくのが確実です。
なお、墓地は厳密にいうと「墳墓」には含まれませんが、これと同様に取り扱われています。また、遺骨についても、明文はないものの、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとした判例があります(最三小判平成元年7月18日家月41巻10号128頁)。
3 生命保険金 被相続人の死亡によって生じる生命保険金請求権は、被相続人が取得した権利を相続人が承継するものではなく、受取人が固有の権利として取得するものと解されています。したがって、相続財産には含まれません。
この点、受取人が特定の相続人に指定されている場合に限らず、抽象的に「相続人」とのみ指定されている場合や、受取人の指定がなく約款により相続人が受け取ることになる場合においても、当該保険金の請求権は相続財産に属さないことになります。
| Aは生前、自らを被保険者とする3,000万円の生命保険に加入していた。受取人は、「相続人」とのみ指定されていた。 |
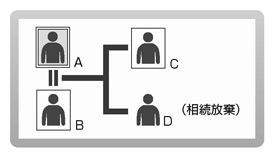
上記の事例で、誰が幾らの保険金を受け取れることになるでしょうか。
受取人は、法定相続人であるB、C及びDです。保険金請求権は相続財産ではなく受取人固有の権利ですので、相続放棄をしたDも権利を失うことはありません。
また、各相続人が取得する割合については、かつて議論が分かれていました。この点、可分債権は各債権者が等分に権利を有する旨定めた民法427条の規定に従い、各受取人の取得割合は平等となるとする下級審裁判例もありましたが(上記の事例にあてはめると、3人の法定相続人が1/3の1,000万円ずつを取得することになります。)、最高裁は、受取人を相続人とする指定には、特段の事情のない限り、相続人が受け取る権利の割合を法定相続分の割合とする旨の指定も含まれるとの判断を下しました(最二小判平成6年7月18日民集48巻5号1233頁)。
したがって、配偶者Bは3,000万円×1/2の1,500万円、子C及びDはそれぞれ3,000万円×1/2×1/2の750万円の保険金請求権を取得することになります。
上記のとおり、生命保険金は相続財産でないと解されています。しかし、そうなると、例えば被相続人が生前に、財産の大部分を払い込んで特定の相続人を受取人とする生命保険に加入したような場合に、当該相続人に比して他の相続人が僅かな財産しか取得できないことになり、相続人間の公平の問題が生じます。
そのため、「第10回 相続分(4)-特別受益」(本誌622号23頁)でも触れたとおり、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定めた民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて死亡保険金も持戻しの対象とするのが判例の立場です(最二小決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。
4 死亡退職金・遺族給付 死亡退職金については、支給規程があるか否かによって場合分けをして考えます。
支給規程がある場合には、支給基準のほか、受給権者の範囲または順位等の規定に従って相続財産性を判断することになります。支給規程があり、受給権者が明確に定められている場合には、受給権者が固有の権利として取得するものであると解され、相続財産には含めないことになります。支給規程があっても、受給権者が明確に定められていない場合については、単に「遺族にこれを支給する。」とのみ定めていた学校法人の事案について、この規程が専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とすると解して、内縁の妻を第一順位の受給権者とした判例が参考になります(最一小判昭和60年1月31日家月37巻8号39頁)。
一方、支給規程がない場合には、支給決定の内容等を踏まえて、事案ごとに相続財産か支給をされた者の固有の財産かを判断することになります。この点、支給規程のない財団法人が、死亡した理事長の妻に対して死亡退職金の支給決定をした上でこれを支払った事案につき、当該死亡退職金は、相続人の代表として妻に支払われたものではなく、相続と無関係に妻個人に支給されたと判断した判例もあります(最三小判昭和62年3月3日家月39巻10号61頁)。
死亡退職金が特別受益に準じて持戻しの対象となるかは、最終的には実質的に相続人間の公平を害することにならないか個別に判断して決めることになるでしょう。ただ、一般的には、受給権者の生活保障を目的として支給されるものであることから、持戻しの対象としないことが多いと思われます。
遺族年金や弔慰金等の遺族給付は、遺族固有の権利であって、相続財産には属さないと解するのが一般的です。
5 ジョイント・アカウント預金
| 被相続人Eが妻Fと共同名義によりハワイの銀行でジョイント・アカウントを開設していた。先妻の子Gは、自らの法定相続分に相当する額を支払えとFを訴えた。 |
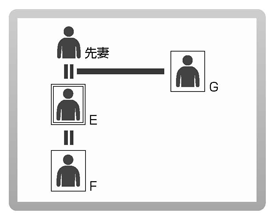
日本では認められていませんが、被相続人が生前に海外でジョイント・アカウント(共同名義口座)を開設している場合があります。ジョイント・アカウントとは、2名以上の名義人で開設する預金口座のことで、一人の名義人が死亡すると自動的に口座残高が生存名義人に移転されることになるのが一般的なようです。
このようなジョイント・アカウントによる預金債権に関して、相続財産に含まれるか訴訟で争われたのが上記の事例です。
この事案で裁判所は、ハワイ州法では共同名義人の一人の死亡により生存名義人が自動的に死亡名義人の財産を所有されていることなどを根拠として、当該ジョイント・アカウントに係る預金債権は被相続人の私法上の相続財産を構成しないと判断し、Gの請求を斥けました(東京地判平成26年7月8日判タ1415号283頁)。
なお、本件で、税務当局は、死因贈与(遺贈)による取得に当たり、相続税の課税対象となると判断したようです。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















