解説記事2017年05月22日 【解説】 「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の解説(2017年5月22日号・№691)
解説
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の解説
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長 安永崇伸
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 松村謙太郎
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 係長 岩脇 潤
Ⅰ はじめに
コーポレートガバナンス改革は日本の成長戦略の最重要課題の一つとされており、「日本再興戦略2016―第四次産業革命に向けて―」(脚注1)において、「攻めの経営」の促進のために新たに講ずべき具体的施策の一つとして、「取締役会の役割・運用方法、CEOの選解任・後継者計画やインセンティブ報酬の導入、任意のものを含む指名・報酬委員会の実務等に関する指針や具体的な事例集を、本年度内を目途に策定する」ことが盛り込まれた。これを受け、経済産業省は、平成28年7月に、法務省及び金融庁からオブザーバとしての参加を得て、CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会。座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授。委員名簿は図表1参照。以下「CGS研究会」という。)を立ち上げ、平成29年2月までに合計9回の研究会を開催した。そして、CGS研究会は検討の成果を報告書「CGS研究会報告書~実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引~」(以下「CGS研究会報告書」という。)として取りまとめ、平成29年3月10日に公表した。その後、経済産業省は、平成29年3月31日、CGS研究会報告書の内容を基本的に引用する形で、実務指針「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン。以下「本ガイドライン」という。)を策定し、公表した(脚注2)。本稿では本ガイドラインの概要について説明する。
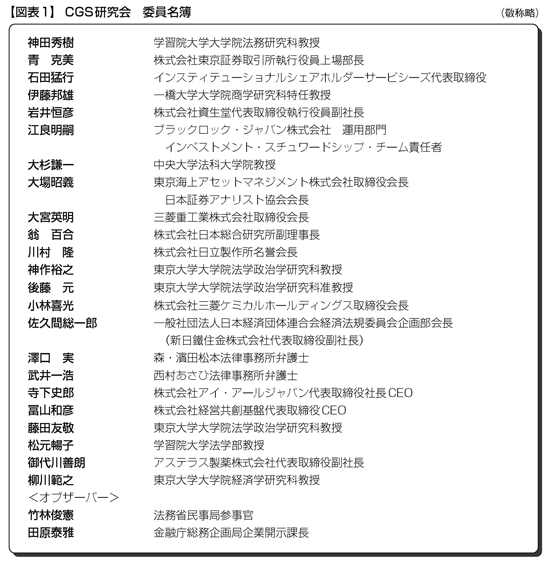
なお、本稿の意見に関する部分は、現時点における筆者らの個人的見解であることを最初にお断りしておく。
Ⅱ 本ガイドラインの概要
1 本ガイドラインの意義 本ガイドラインは、日本再興戦略等を踏まえて経済産業省が策定した、コーポレートガバナンスの実務に関する指針という位置づけであり、企業に取組の検討を求める事項を数多く提示することで、企業におけるコーポレートガバナンスの検討に際して、一定の方向性を示す役割を担うものである。もっとも、本ガイドラインの提言事項は、当該取組の実施を一律に要請するものではない。コーポレートガバナンスにおける企業の自主的な取組の多様性は尊重されるべきであるという考え方の下、あくまで検討を要請するものであり、実施するか否かの判断は各企業の主体的な検討に委ねられている。
2 本ガイドラインの対象 本ガイドラインの対象として主に想定されるのは上場企業である。また、上場企業のなかでも特に、真剣にコーポレートガバナンスに取り組みたいものの企業内での議論の蓄積がなく、実際に何をすれば有益なのか悩んでいる企業群にとって、本ガイドラインの内容は大いに参考となると考えられる。それ以外の企業群においても、たとえば、コーポレートガバナンスにこれまで積極的に取り組んできた先進的な企業群であればこれまでの取組の検証やその独自性を確認する際に、また、コーポレートガバナンスにこれまであまり関心を持っていない企業群やコーポレートガバナンス改革に着手できていない企業群であれば、小さくとも取り組むことのできる事項から順次着手していく際に、本ガイドラインを活用することが期待される。
3 本ガイドラインの基本的な考え方 本ガイドラインでは、実務的に検討すべきコーポレートガバナンスに関する取組についてさまざまな提言を行っているところ、これらの背景にある基本的な考え方は、中長期的な企業価値向上を果たす上で中心的役割を果たすのは社長・CEOら経営陣(脚注3)であるという考え方である。この考え方を出発点とした上で、より具体的な考え方として、第一に、社長・CEOら経営陣が中長期的な企業価値向上を目指して経営を行うためには、経営判断の軸となる戦略が必要であり、その立案にあたっては、社外の視点や知見を取り込んで取締役会で検討することが有益であるという考え方を示している。また、第二に、優れた社長・CEOら経営陣を選び、適切なインセンティブを与えることで適切なリスクテイクを促し、その成果をチェックしていく仕組みを作ることはすべての企業において必須であり、この仕組みの中心は取締役会であるという考え方を示している。
これらの考え方を踏まえて、本ガイドラインは、①経営や監督に関する取締役会の機能の強化、②監督機能の中心の一つとなるべき社外取締役の活用、③経営陣の指名・報酬の在り方、④経営陣のリーダーシップ強化の在り方(相談役・顧問の在り方等)の4つのテーマを取り上げ、それぞれについて提言を行っている。
なお、本ガイドラインには、関連するガイドラインとして、「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」(経済産業省・平成29年3月31日公表)と、「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(競争戦略としてのダイバーシティ経営(ダイバーシティ2.0)の在り方に関する検討会・平成29年3月23日公表)が別添されているが、本稿ではその説明は割愛するので、その内容についてはそれぞれのガイドラインを参照されたい(脚注4)。
また、本ガイドラインのもととなったCGS研究会報告書には、コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査(以下「企業アンケート」という。)の結果が参考資料として添付されている(脚注5)。企業アンケートの調査対象は2016年6月末日時点の東証第一部・第二部上場企業2,502社、企業アンケートの回答期間は2016年8月25日から9月30日までの約1か月間であり、回答期間内に対象企業の34.9%にあたる874社から回答をいただいた。御協力いただいた多くの企業の担当者の方々にこの場を借りて御礼申し上げたい。
Ⅲ 取締役会の在り方
1 取締役会の役割・機能の自覚的整理 企業アンケートにおいて、企業が取締役会での議論が不足していると考えている事項について質問を行ったところ、多かった回答は、社長・CEOの後継者計画・監督(47.4%)や、中長期経営戦略(39.7%)となっている(図表2)。
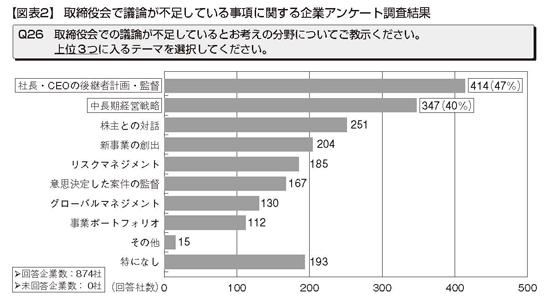
こうした課題に対応しようとしている企業は、取締役会への付議事項の見直しといった取組を行うことが考えられるが、その前提として、取締役会の役割・機能を自覚的に整理し、コーポレートガバナンス改革の方向性に関する会社の意思をしっかりと持つ必要がある。そこで、本ガイドラインは、取締役会の在り方に関して、次の提言を行うとともに、整理の際の視点として、図表3のような視点で検討することを提案している。
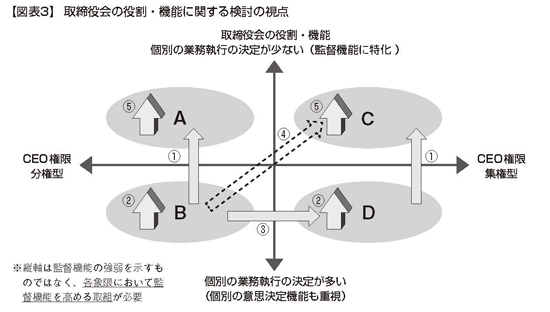
図表3は、企業のコーポレートガバナンスの実効性向上の方法にはさまざまなパターンがあるなかで、どのような選択肢があるかを示すものであり、現在自社はどこにいるのか、改革したいならばどこからどこへ向かうのか、を企業が自覚的に整理する助けとなるために作成されたものである。図表3の特徴的な点は、単に欧米流のモニタリング型のガバナンス体制かそうでないかといった2項対立的な分類にならずに、さまざまな判断軸で会社をみつめ直してみることを提案している点にある。具体的には、(1)取締役会でなるべく個別の意思決定まで行いたいのか否か(縦軸)、(2)経営において社長・CEOに権限を集中させたいのか否か(横軸)、(3)その場合に適合した監督機能の強化の仕方は何か(立体軸)という視点から検討することを提案している(脚注6)。各判断軸を組み合わせて考えることによって、自社の現状把握と今後目指すべきコーポレートガバナンス改革の方向性が見えてくると考えられる。なお、縦軸は、縦軸の上下で監督機能の強弱を表しておらず、縦軸の下に属する場合にも監督機能をおろそかにしてよいという趣旨は含まれていない。いずれの象限に属する企業であっても、それぞれに適した方法で取締役会の監督機能を強化する取組に順次着手していくことが必要である。次の提言は、それを反映したものである。
図表3は、いずれの象限が優れているといった単純な比較をすることは議論の目的ではなく、また、判断軸は他にも考えられ、必ずしもこの4象限で全てを分類できるものではない。そのため、前記の分類が正しいかどうかというよりも、いくつかの視点に分けて自社の経営・取締役会の在り方を検討してはどうかという点に主眼がある。このことを認識した上で、自社の経営や取締役会の在り方を各企業が主体的に検討することが望まれる。
2 取締役会で実質的な議論を行うための工夫等 本ガイドラインは、取締役会で実質的な議論を行うための工夫として、①社外取締役への情報提供や意見交換の方法(取締役会以外の会議体の活用等)や、②取締役会における決議事項・報告事項(あるいは審議事項)の使い分けに関して、参考となる企業における取組例を紹介している。
また、取締役会の運用に関連して、本ガイドラインは、会社の内外のコーポレートガバナンス関連の対応を実効的に行うための体制整備を検討すべきという提言を行っている。コーポレートガバナンスには総務、法務、財務、人事、IRなど多岐にわたる事項が含まれるため、社内の複数の部署が関与する必要が生じることが想定されるが、問題は、それらを統括的に掌握している部署、担当者あるいは会議体等が存在しているかどうかである。コーポレートガバナンスについて統合的な戦略を踏まえて対応していくために、コーポレートガバナンス対応を一元的に統括する部署等を配置するなど、体制整備を検討することが考えられる。
Ⅳ 社外取締役の活用の在り方
1 社外取締役活用のための視点 社外取締役の選任の進展は、日本企業のコーポレートガバナンスの変化を最も象徴する事象の1つであると考えられる。他方で、企業アンケートの調査結果によれば合計46.4%の企業が「社外取締役が十分に期待する役割を果たしている」と回答できておらず、社外取締役を選任したものの十分に活用しきれていない企業が少なからず存在することが窺われる。そこで、本ガイドラインでは、次の提言のとおり、図表4とともに、9つのステップに分けて社外取締役活用のために整理すべきポイントを検討することを提言している。
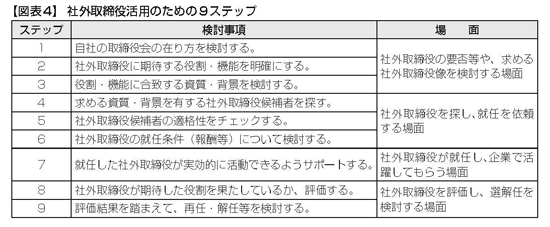
その上で、それぞれのステップにおいて、具体的な提言や取組例の紹介を行っている。
その中からいくつか紹介すると、まず、ステップ2に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
社外取締役に期待する役割・機能を明確にしないまま、漠然と社外取締役を選任すると、社外取締役が役に立っているのかどうか、適切に評価することは困難である。そこで、社外取締役に期待する役割・機能、あるいは逆に期待しない役割・機能を、選任する前に社内で明確にしておくことを検討すべきという考え方を示したのが、この提言である。
この提言で特徴的なのは、社外取締役に期待する役割等だけではなく、期待しない役割等も明確にしておくことを含んでいる点である。重要なのは、これまで社内者が行ってきたことのうち、本来は社内者では適切に判断・評価しにくい事項について社外取締役に任せることであり、社内者が行うべき事項まで社外者に任せることではない。あくまで社内者と社外者の役割分担の問題であることを各企業が認識する必要がある。
次に、ステップ3に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
各企業において、どのような資質・背景を有する社外取締役を選任する必要があるか、また、複数の社外取締役を選任する場合には、どういうバランスで選任するのかという点を十分に検討することが重要である。その検討は各企業の自主的な判断に委ねられるものの、本ガイドラインは、社外取締役に期待される役割・機能に照らして、社外取締役のうち1名は経営経験を有する社外取締役を選任することが、社外取締役の有効活用に際して重要であるという考え方を示している。
また、ステップ6に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
この提言は、社外取締役に対して固定報酬のみを支給している企業が多い日本の現状を踏まえたものである。ここでいうインセンティブ報酬は、業績連動報酬だけを指すものではなく、業績連動ではない自社株報酬も含むものとしている。これまで、ステークホルダーのうち特に株主に対する意識が弱かったとされる日本において、社外取締役が適切に株主の意見を会社に反映する役割を担うためには、社外取締役が株主と同じ目線を持っておくことが効果的に働きうると考えられるため、業績連動のない自社株報酬を日本企業の社外取締役に対する適切なインセンティブ付与の観点から活用することも考えられる。
2 社外取締役の人材市場の拡充に向けて 社外取締役を積極的に活用することを企業が望んでいても、求める資質を有する社外取締役候補者を探すことが難しいという課題が指摘されている。そこで、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
社外取締役の人材市場の拡充が必要となるなかで、実際に経営に携わっていた経営経験者(経営陣から退任した者や、現役の経営陣)は、経営戦略の策定や経営の評価を行う社外取締役の有力候補であり、そういった人材が積極的に他社の社外取締役になることで、社外取締役の人材市場が拡充されていくことが期待される。そのため、本ガイドラインは、経営経験者に対して積極的な社外取締役への就任を呼びかけている。
Ⅴ 経営陣の指名・報酬の在り方
中長期的な企業価値向上を図るうえで中心的な役割を果たすのは、社長・CEOら経営陣である。コーポレートガバナンスにおいて、優れた社長・CEOら経営陣を選び、適切なインセンティブを与えることで適切なリスクテイクを促し、その成果をチェックするとともに、将来を見据えた後継者計画を監督する仕組みを構築し、実効的に機能するように運用することが肝要である。この仕組みの中心は取締役会であり、取締役会の監督機能(社長・CEOら経営陣の指名や報酬の決定を通じて、業務執行を評価することによる監督を行う機能)の強化が重要な課題となる。
そこで、本ガイドラインは、次のとおり、経営陣の指名のうち、特に次期社長・CEOの選定に関する提言と、経営陣の指名プロセスの要となる取締役会の構成員(取締役)自体の指名に関する提言をそれぞれ行っている。
また、中長期的な企業価値向上を図る上で、社長・CEOら経営陣に対して適切なインセンティブを与えることで適切なリスクテイクを促し、その成果をチェックすることがコーポレートガバナンスにおいて重要となる。企業アンケート調査において、経営陣の業績連動報酬の決定のための指標として何を採用しているかについて質問を行ったところ、短期指標の業績連動報酬を導入している企業は61.4%(537社)に達するが、中期指標の業績連動報酬を導入している企業は14%(124社)に過ぎないという結果であった(図表5)。
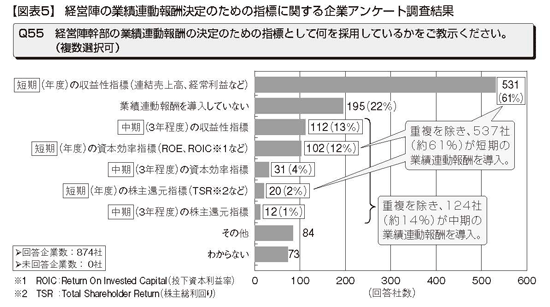
こうした状況も踏まえ、本ガイドラインは、経営陣の報酬に関して、次の2つの提言を行っている。
まず、提言(i)は、特にこれまで固定報酬中心の報酬体系を採用し続けてきた企業に対する提言であり、自社の経営戦略を実現する上で、自社の現在の報酬体系が経営陣に対して適切なインセンティブを付与できているか、改めて検討することを求めている。固定報酬に比べて、業績連動報酬や自社株報酬は、業績や株価の変動に応じて経営陣が得られる経済的利益が変化するため、中長期的な企業価値向上への動機付けとなる場合が多く、さらに自社株報酬は、自社株を保有することにより経営陣と株主の価値共有に資するというメリットもあると考えられる。そこで、本ガイドラインは、そういった報酬を適切な割合で導入することを検討するように求めている。
もっとも、本ガイドラインは、一律に業績連動報酬や自社株報酬の導入を求めているわけではない。報酬体系の設計は、その前提として経営戦略等の基本方針に沿った内容になっていることが必要であり、経営戦略なくして報酬政策だけを検討しても経営陣に対して適切なインセンティブを付与することに必ずしもつながらない。そのため、本ガイドラインでは、経営戦略をまず定め、それを踏まえて具体的な目標となる経営指標(KPI)を設定し、それを実現するための報酬体系という流れで検討を進めることを提案している。
なお、平成29年度税制改正により、各役員給与類型について全体として整合的な税制となるよう見直しが行われ、業績連動給与について複数年度の利益に連動したものや株価に連動したものも損金算入の対象となるなど、大きく枠組みが変更されている。こうしたことも踏まえて、業績連動報酬や自社株報酬の導入について検討することが考えられる。この点に関連して、経済産業省が公表している『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』も検討の一助となると考えられる(脚注7)。
次に、提言(ⅱ)は、企業が経営戦略に沿って策定している報酬体系について積極的に情報発信することを求めている。特に業績連動報酬や自社株報酬の内容は株主等のステークホルダーの関心事であると考えられることから、かかる報酬の導入状況や内容について、企業が積極的に情報発信を行うことを通じて、株主等からの理解や評価を得ることが期待される。企業においては、そういった株主等の理解を得ることが報酬体系の見直しの後押しになると肯定的に捉え、積極的な情報発信を行うことが望ましいと考えられる。
加えて、本ガイドラインは、指名・報酬の決定プロセスとして、社長・CEOの選解任・後継者計画や報酬に関して、社外者中心(社外者が過半数か、社内者・社外者が同数であれば委員長が社外者)の指名委員会・報酬委員会(任意に設置されるものを含む)を活用することを提言している(脚注8)。取締役会が社長・CEOを頂点とする社内者中心の構成の場合には、取締役会で社長・CEOの選解任・後継者計画や報酬について真剣な議論を交わすことが実際上は相当難しいと思われる。そこで、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するために、本ガイドラインは、取締役会の構成の見直しを必ずしも伴わなくとも行うことができる方法として、取締役会の下に社外者中心の法定または任意の委員会を設け、その委員会での独立した客観的な評価を踏まえて、取締役会が最終判断を行うという方法を提言している。
本ガイドラインは、こうして活用されるべき指名委員会・報酬委員会の設計・運用等に関して、本ガイドラインの別紙3「指名委員会・報酬委員会活用の視点」を参照して検討することを提言するとともに(脚注9)、指名委員会・報酬委員会(とりわけ任意のもの)については外部からその実態が把握しにくいことを踏まえて、委員会に関する情報を積極的に発信することを検討すべきことも併せて提言している。
Ⅵ 経営陣のリーダーシップ強化の在り方
退任した自社の社長・CEOや役員が相談役・顧問等の名称で、会社と一定の関係を保持し続ける慣行が存在する会社がある。企業アンケートによれば、回答企業(871社)のうち、77.6%の企業で自社の役員又は役員経験者を相談役・顧問とする制度が存在し、62.5%の企業で現に相談役・顧問が在任中であり、また、現に相談役・顧問が在任中である企業のうち、社長・CEO経験者が相談役・顧問に就任している企業は約58.5%であった(図表6)。
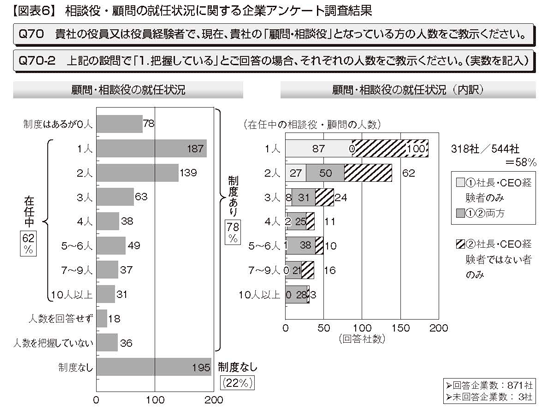
また、企業アンケートにおいて、相談役・顧問制度が存在する企業に対して、相談役・顧問が果たしている役割について質問を行ったところ、現経営陣への指示・指導が最も多く(36.2%)、現経営陣の意思決定に関与している場合があることが示唆される結果となった。また、そもそも役割を把握していない(10.4%)、役割が特にない(7.1%)と回答した企業もあり、その位置づけが不明確になっている企業も一部存在するようである。
企業価値を向上させる上で最も重要な役割を果たすのは、社長・CEOら経営陣であり、経営陣が会社内において適切にリーダーシップを発揮し、過去のしがらみに捉われることなく、迅速果断な意思決定や事業ポートフォリオの見直しなどを行っていくことが重要と考えられる。その際、もし経営陣に対して不当な影響力を行使できる存在が社内にいれば、経営陣のリーダーシップの発揮を阻害しかねない。その観点から、本ガイドラインは、相談役・顧問のあり方に関して、次の6つの事項を提言している。
これらの提言の特徴は大きく4つあると考えられる。
第一に、相談役・顧問のうち、退任した社長・CEO経験者が相談役・顧問に就任する場合に対象を限定している点である(各提言に共通)(脚注10)。
第二に、相談役・顧問の役割が各企業によってさまざまであり、社長・CEO経験者を相談役・顧問とすることが一律に良い・悪いというものではないことから、相談役・顧問を一律に否定するのではなく、各企業における役割の明確化と処遇の適正化を社外者の関与を得ながら検討すべきと提言しているにとどまる点である(提言(i)~(ⅲ))。
第三に、相談役・顧問の人数、役割、処遇等はこれまで外部から認識することが難しく不透明であったことが、相談役・顧問による不当な影響力の行使を疑わせる要因の一つであったと考えられることから、相談役・顧問に関する情報発信を企業が積極的に行うことを期待するとしている点である(提言(ⅳ))。
第四に、相談役・顧問制度の見直しの結果、相談役・顧問の人数や報酬の削減を行う場合も意識した提言を行っている点である(提言(ⅴ)・提言(ⅵ))。
なお、本ガイドラインは、相談役・顧問のあり方に加えて、取締役会長のあり方についても、現社長・CEOに権限を集中させることの是非を踏まえて、取締役会長の権限・肩書(代表権の付与等)を検討すべきであると提言している。
Ⅶ 終わりに
本ガイドラインは、企業の自主的な取組を後押しするためのものである。本ガイドラインは特にコーポレートガバナンスに悩んでいる企業がこれを契機として検討を深めることに主眼があり、本ガイドラインに形式的に従うことは意味がない。本ガイドラインの内容もそれが唯一の正解ではなく、今後のさまざまな議論や実務を踏まえて適宜見直されていくべきものであると考えられる。各企業において、本ガイドラインの提言のうち自社に参考となる事項があれば、それを踏まえて自社のコーポレートガバナンスを実効的なものとするためにどうすべきか、検討する機会を設けることが望まれる。
脚注
1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf 2 CGS研究会報告書とCGSガイドラインの内容は基本的に同様であり、異なる点は、CGS研究会報告書の本文「6. 本研究会で十分に議論できなかった事項」がCGS研究会特有の話であることから、CGSガイドラインでは引用されていない点である。その他はいずれも実務指針化に伴う形式的な調整にとどまるため、本稿におけるCGSガイドラインの解説は、同時にCGS研究会報告書の解説としても当てはまる。
3 本ガイドラインにおいて、「社長・CEO」は、企業の経営のトップに立つ者を指し、また、「経営陣」は、企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役、執行役員その他重要な使用人を指すとされている。
4 http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331012/20170331012.html 5 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170310001.html 6 縦軸・横軸いずれに関しても、会社法上の機関設計とは必ずしも結びつくものではない。どの機関設計を選択していたとしても、その実質に応じていずれの分類にもなり得る。
7 http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007.html 8 本ガイドラインにおいて、「社内者」は、社内取締役、執行役、執行役員その他の従業員を指すとされており、「社外者」は、社外取締役、社外監査役、社外の有識者を指すとされている。
9 詳細については本ガイドライン別紙3「指名委員会・報酬委員会活用の視点」を参照されたい。また、この点に関しては、本ガイドラインのほか、第6回CGS研究会においてプレゼンテーションを行っていただいたエゴンゼンダー株式会社の説明資料や、ウイリス・タワーズワトソンの説明資料もそれぞれ大いに参考になると考えられる。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/006_haifu.html 10 なお、相談役・顧問以外にもさまざまな役職名があるが、本ガイドラインでは、名称のいかんを問わず、退任した社長・CEOが何らかの名称で会社と一定の関係を保持する場合が広く対象になるとされている。
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の解説
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長 安永崇伸
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 松村謙太郎
経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 係長 岩脇 潤
Ⅰ はじめに
コーポレートガバナンス改革は日本の成長戦略の最重要課題の一つとされており、「日本再興戦略2016―第四次産業革命に向けて―」(脚注1)において、「攻めの経営」の促進のために新たに講ずべき具体的施策の一つとして、「取締役会の役割・運用方法、CEOの選解任・後継者計画やインセンティブ報酬の導入、任意のものを含む指名・報酬委員会の実務等に関する指針や具体的な事例集を、本年度内を目途に策定する」ことが盛り込まれた。これを受け、経済産業省は、平成28年7月に、法務省及び金融庁からオブザーバとしての参加を得て、CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会。座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授。委員名簿は図表1参照。以下「CGS研究会」という。)を立ち上げ、平成29年2月までに合計9回の研究会を開催した。そして、CGS研究会は検討の成果を報告書「CGS研究会報告書~実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引~」(以下「CGS研究会報告書」という。)として取りまとめ、平成29年3月10日に公表した。その後、経済産業省は、平成29年3月31日、CGS研究会報告書の内容を基本的に引用する形で、実務指針「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン。以下「本ガイドライン」という。)を策定し、公表した(脚注2)。本稿では本ガイドラインの概要について説明する。
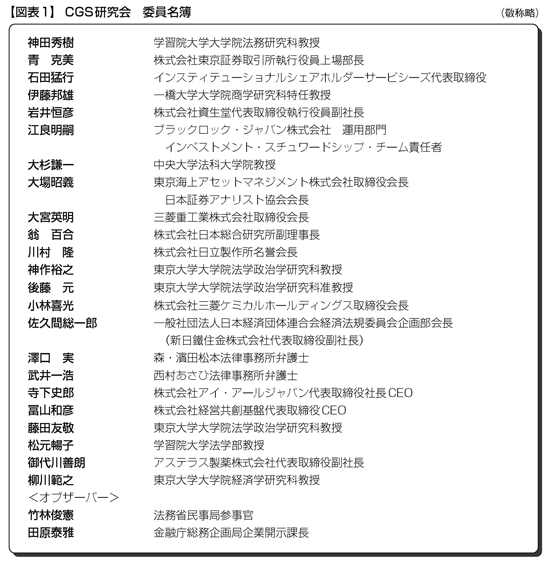
なお、本稿の意見に関する部分は、現時点における筆者らの個人的見解であることを最初にお断りしておく。
Ⅱ 本ガイドラインの概要
1 本ガイドラインの意義 本ガイドラインは、日本再興戦略等を踏まえて経済産業省が策定した、コーポレートガバナンスの実務に関する指針という位置づけであり、企業に取組の検討を求める事項を数多く提示することで、企業におけるコーポレートガバナンスの検討に際して、一定の方向性を示す役割を担うものである。もっとも、本ガイドラインの提言事項は、当該取組の実施を一律に要請するものではない。コーポレートガバナンスにおける企業の自主的な取組の多様性は尊重されるべきであるという考え方の下、あくまで検討を要請するものであり、実施するか否かの判断は各企業の主体的な検討に委ねられている。
2 本ガイドラインの対象 本ガイドラインの対象として主に想定されるのは上場企業である。また、上場企業のなかでも特に、真剣にコーポレートガバナンスに取り組みたいものの企業内での議論の蓄積がなく、実際に何をすれば有益なのか悩んでいる企業群にとって、本ガイドラインの内容は大いに参考となると考えられる。それ以外の企業群においても、たとえば、コーポレートガバナンスにこれまで積極的に取り組んできた先進的な企業群であればこれまでの取組の検証やその独自性を確認する際に、また、コーポレートガバナンスにこれまであまり関心を持っていない企業群やコーポレートガバナンス改革に着手できていない企業群であれば、小さくとも取り組むことのできる事項から順次着手していく際に、本ガイドラインを活用することが期待される。
3 本ガイドラインの基本的な考え方 本ガイドラインでは、実務的に検討すべきコーポレートガバナンスに関する取組についてさまざまな提言を行っているところ、これらの背景にある基本的な考え方は、中長期的な企業価値向上を果たす上で中心的役割を果たすのは社長・CEOら経営陣(脚注3)であるという考え方である。この考え方を出発点とした上で、より具体的な考え方として、第一に、社長・CEOら経営陣が中長期的な企業価値向上を目指して経営を行うためには、経営判断の軸となる戦略が必要であり、その立案にあたっては、社外の視点や知見を取り込んで取締役会で検討することが有益であるという考え方を示している。また、第二に、優れた社長・CEOら経営陣を選び、適切なインセンティブを与えることで適切なリスクテイクを促し、その成果をチェックしていく仕組みを作ることはすべての企業において必須であり、この仕組みの中心は取締役会であるという考え方を示している。
これらの考え方を踏まえて、本ガイドラインは、①経営や監督に関する取締役会の機能の強化、②監督機能の中心の一つとなるべき社外取締役の活用、③経営陣の指名・報酬の在り方、④経営陣のリーダーシップ強化の在り方(相談役・顧問の在り方等)の4つのテーマを取り上げ、それぞれについて提言を行っている。
なお、本ガイドラインには、関連するガイドラインとして、「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」(経済産業省・平成29年3月31日公表)と、「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(競争戦略としてのダイバーシティ経営(ダイバーシティ2.0)の在り方に関する検討会・平成29年3月23日公表)が別添されているが、本稿ではその説明は割愛するので、その内容についてはそれぞれのガイドラインを参照されたい(脚注4)。
また、本ガイドラインのもととなったCGS研究会報告書には、コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査(以下「企業アンケート」という。)の結果が参考資料として添付されている(脚注5)。企業アンケートの調査対象は2016年6月末日時点の東証第一部・第二部上場企業2,502社、企業アンケートの回答期間は2016年8月25日から9月30日までの約1か月間であり、回答期間内に対象企業の34.9%にあたる874社から回答をいただいた。御協力いただいた多くの企業の担当者の方々にこの場を借りて御礼申し上げたい。
Ⅲ 取締役会の在り方
1 取締役会の役割・機能の自覚的整理 企業アンケートにおいて、企業が取締役会での議論が不足していると考えている事項について質問を行ったところ、多かった回答は、社長・CEOの後継者計画・監督(47.4%)や、中長期経営戦略(39.7%)となっている(図表2)。
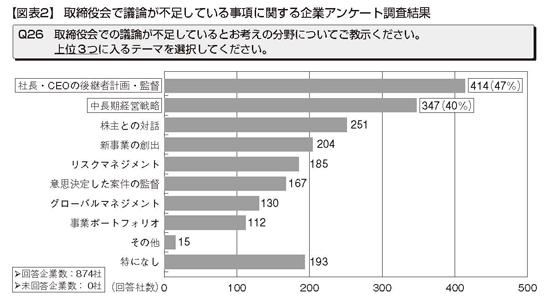
こうした課題に対応しようとしている企業は、取締役会への付議事項の見直しといった取組を行うことが考えられるが、その前提として、取締役会の役割・機能を自覚的に整理し、コーポレートガバナンス改革の方向性に関する会社の意思をしっかりと持つ必要がある。そこで、本ガイドラインは、取締役会の在り方に関して、次の提言を行うとともに、整理の際の視点として、図表3のような視点で検討することを提案している。
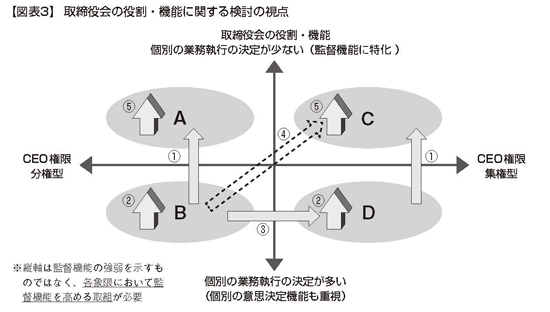
| コーポレートガバナンスを検討する際に、どのような会社を目指すのか、どのような取締役会を目指すのか、検討すべきである。 |
| 取締役会の役割・機能について、機関設計を変更するといった大がかりな改革だけでなく、より漸進的な取組を含めて、監督機能強化への取組を検討すべきである。 |
2 取締役会で実質的な議論を行うための工夫等 本ガイドラインは、取締役会で実質的な議論を行うための工夫として、①社外取締役への情報提供や意見交換の方法(取締役会以外の会議体の活用等)や、②取締役会における決議事項・報告事項(あるいは審議事項)の使い分けに関して、参考となる企業における取組例を紹介している。
また、取締役会の運用に関連して、本ガイドラインは、会社の内外のコーポレートガバナンス関連の対応を実効的に行うための体制整備を検討すべきという提言を行っている。コーポレートガバナンスには総務、法務、財務、人事、IRなど多岐にわたる事項が含まれるため、社内の複数の部署が関与する必要が生じることが想定されるが、問題は、それらを統括的に掌握している部署、担当者あるいは会議体等が存在しているかどうかである。コーポレートガバナンスについて統合的な戦略を踏まえて対応していくために、コーポレートガバナンス対応を一元的に統括する部署等を配置するなど、体制整備を検討することが考えられる。
Ⅳ 社外取締役の活用の在り方
1 社外取締役活用のための視点 社外取締役の選任の進展は、日本企業のコーポレートガバナンスの変化を最も象徴する事象の1つであると考えられる。他方で、企業アンケートの調査結果によれば合計46.4%の企業が「社外取締役が十分に期待する役割を果たしている」と回答できておらず、社外取締役を選任したものの十分に活用しきれていない企業が少なからず存在することが窺われる。そこで、本ガイドラインでは、次の提言のとおり、図表4とともに、9つのステップに分けて社外取締役活用のために整理すべきポイントを検討することを提言している。
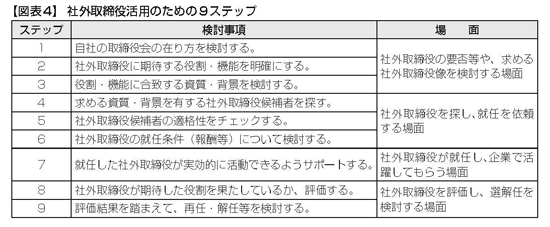
| 企業が社外取締役を活用するために整理すべきポイントは何かを場面ごとに検討すべきである。 |
その中からいくつか紹介すると、まず、ステップ2に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
| 社外取締役に期待する役割・機能、あるいは逆に期待しない役割・機能を、選任する前に社内で明確にしておくことを検討すべきである。 |
この提言で特徴的なのは、社外取締役に期待する役割等だけではなく、期待しない役割等も明確にしておくことを含んでいる点である。重要なのは、これまで社内者が行ってきたことのうち、本来は社内者では適切に判断・評価しにくい事項について社外取締役に任せることであり、社内者が行うべき事項まで社外者に任せることではない。あくまで社内者と社外者の役割分担の問題であることを各企業が認識する必要がある。
次に、ステップ3に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
| 社外取締役の役割・機能に応じて、社外取締役に求める資質・背景やそのバランスを検討すべきである。また、社外取締役のうち1名は、経営経験を有する社外取締役を選任することを検討すべきである。 |
また、ステップ6に関して、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
| 就任を依頼するに際して、社外取締役の就任条件について検討すべきである。特に、社外取締役の報酬について、インセンティブ付与の観点から、固定報酬に加えて、業績によって付与数が変動しない自社株報酬など、インセンティブ報酬を付与することも考えられる。 |
2 社外取締役の人材市場の拡充に向けて 社外取締役を積極的に活用することを企業が望んでいても、求める資質を有する社外取締役候補者を探すことが難しいという課題が指摘されている。そこで、本ガイドラインは、次の提言を行っている。
| 社外取締役の人材市場の拡充のため、経営経験者が積極的に他社の社外取締役を引き受けることを検討すべきである。 |
Ⅴ 経営陣の指名・報酬の在り方
中長期的な企業価値向上を図るうえで中心的な役割を果たすのは、社長・CEOら経営陣である。コーポレートガバナンスにおいて、優れた社長・CEOら経営陣を選び、適切なインセンティブを与えることで適切なリスクテイクを促し、その成果をチェックするとともに、将来を見据えた後継者計画を監督する仕組みを構築し、実効的に機能するように運用することが肝要である。この仕組みの中心は取締役会であり、取締役会の監督機能(社長・CEOら経営陣の指名や報酬の決定を通じて、業務執行を評価することによる監督を行う機能)の強化が重要な課題となる。
そこで、本ガイドラインは、次のとおり、経営陣の指名のうち、特に次期社長・CEOの選定に関する提言と、経営陣の指名プロセスの要となる取締役会の構成員(取締役)自体の指名に関する提言をそれぞれ行っている。
| (社長・CEOの指名) 次期社長・CEOの選定を検討する際に、適当な候補者がいる限り、執行側から複数の候補者を示すことを検討すべきである。 (取締役の指名) 取締役の指名に関しては、取締役会に求める役割と、その実現のための構成(多様性)を指名方針の策定の際に検討すべきである。 |
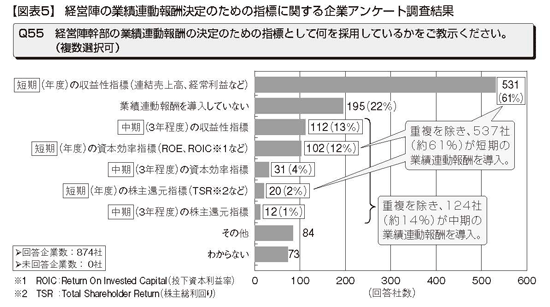
こうした状況も踏まえ、本ガイドラインは、経営陣の報酬に関して、次の2つの提言を行っている。
| (ⅰ)経営陣の報酬体系を設計する際に、業績連動報酬や自社株報酬の導入について、検討すべきである。 (ⅱ)中長期的な企業価値向上に向けた報酬体系についての株主等の理解を促すために、業績連動報酬や自社株報酬の導入状況やその内容について、企業が積極的に情報発信を行うことを検討すべきである。 |
もっとも、本ガイドラインは、一律に業績連動報酬や自社株報酬の導入を求めているわけではない。報酬体系の設計は、その前提として経営戦略等の基本方針に沿った内容になっていることが必要であり、経営戦略なくして報酬政策だけを検討しても経営陣に対して適切なインセンティブを付与することに必ずしもつながらない。そのため、本ガイドラインでは、経営戦略をまず定め、それを踏まえて具体的な目標となる経営指標(KPI)を設定し、それを実現するための報酬体系という流れで検討を進めることを提案している。
なお、平成29年度税制改正により、各役員給与類型について全体として整合的な税制となるよう見直しが行われ、業績連動給与について複数年度の利益に連動したものや株価に連動したものも損金算入の対象となるなど、大きく枠組みが変更されている。こうしたことも踏まえて、業績連動報酬や自社株報酬の導入について検討することが考えられる。この点に関連して、経済産業省が公表している『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』も検討の一助となると考えられる(脚注7)。
次に、提言(ⅱ)は、企業が経営戦略に沿って策定している報酬体系について積極的に情報発信することを求めている。特に業績連動報酬や自社株報酬の内容は株主等のステークホルダーの関心事であると考えられることから、かかる報酬の導入状況や内容について、企業が積極的に情報発信を行うことを通じて、株主等からの理解や評価を得ることが期待される。企業においては、そういった株主等の理解を得ることが報酬体系の見直しの後押しになると肯定的に捉え、積極的な情報発信を行うことが望ましいと考えられる。
加えて、本ガイドラインは、指名・報酬の決定プロセスとして、社長・CEOの選解任・後継者計画や報酬に関して、社外者中心(社外者が過半数か、社内者・社外者が同数であれば委員長が社外者)の指名委員会・報酬委員会(任意に設置されるものを含む)を活用することを提言している(脚注8)。取締役会が社長・CEOを頂点とする社内者中心の構成の場合には、取締役会で社長・CEOの選解任・後継者計画や報酬について真剣な議論を交わすことが実際上は相当難しいと思われる。そこで、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するために、本ガイドラインは、取締役会の構成の見直しを必ずしも伴わなくとも行うことができる方法として、取締役会の下に社外者中心の法定または任意の委員会を設け、その委員会での独立した客観的な評価を踏まえて、取締役会が最終判断を行うという方法を提言している。
本ガイドラインは、こうして活用されるべき指名委員会・報酬委員会の設計・運用等に関して、本ガイドラインの別紙3「指名委員会・報酬委員会活用の視点」を参照して検討することを提言するとともに(脚注9)、指名委員会・報酬委員会(とりわけ任意のもの)については外部からその実態が把握しにくいことを踏まえて、委員会に関する情報を積極的に発信することを検討すべきことも併せて提言している。
Ⅵ 経営陣のリーダーシップ強化の在り方
退任した自社の社長・CEOや役員が相談役・顧問等の名称で、会社と一定の関係を保持し続ける慣行が存在する会社がある。企業アンケートによれば、回答企業(871社)のうち、77.6%の企業で自社の役員又は役員経験者を相談役・顧問とする制度が存在し、62.5%の企業で現に相談役・顧問が在任中であり、また、現に相談役・顧問が在任中である企業のうち、社長・CEO経験者が相談役・顧問に就任している企業は約58.5%であった(図表6)。
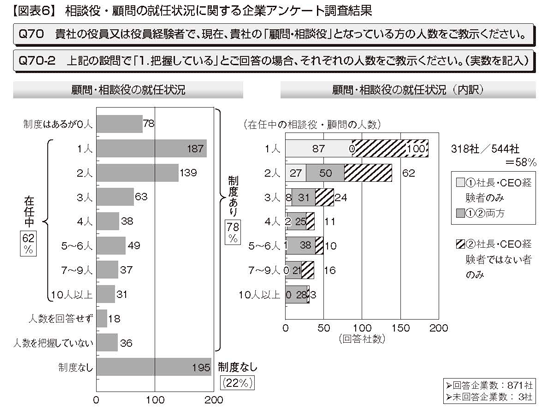
また、企業アンケートにおいて、相談役・顧問制度が存在する企業に対して、相談役・顧問が果たしている役割について質問を行ったところ、現経営陣への指示・指導が最も多く(36.2%)、現経営陣の意思決定に関与している場合があることが示唆される結果となった。また、そもそも役割を把握していない(10.4%)、役割が特にない(7.1%)と回答した企業もあり、その位置づけが不明確になっている企業も一部存在するようである。
企業価値を向上させる上で最も重要な役割を果たすのは、社長・CEOら経営陣であり、経営陣が会社内において適切にリーダーシップを発揮し、過去のしがらみに捉われることなく、迅速果断な意思決定や事業ポートフォリオの見直しなどを行っていくことが重要と考えられる。その際、もし経営陣に対して不当な影響力を行使できる存在が社内にいれば、経営陣のリーダーシップの発揮を阻害しかねない。その観点から、本ガイドラインは、相談役・顧問のあり方に関して、次の6つの事項を提言している。
| (ⅰ)まず社内において、退任した社長・CEO経験者を自社の相談役・顧問とするかどうかを検討する際に、具体的にどういった役割を期待しているかを明確にすることを検討すべきである。 (ⅱ)そのうえで、当該役割に見合った処遇(報酬等)を設定することを検討すべきである。 (ⅲ)以上の検討に際して、法定または任意の指名委員会・報酬委員会を活用するなど、社外者の関与を得ることを検討すべきである。 (ⅳ)社長・CEO経験者を相談役・顧問として会社に置く場合には、自主的に、社長・CEO経験者で相談役・顧問に就任している者の人数、役割、処遇等について外部に情報発信することは意義がある。産業界がこうした取組を積極的に行うことが期待される。 (ⅴ)相談役・顧問として報酬を得ることを前提に、現役時代の社長・CEOの報酬が低く設定されており、報酬の後払いとなっている会社においては、現役の経営陣に対する報酬をインセンティブ報酬の導入などによる報酬の引き上げと、相談役・顧問の位置付けや報酬の見直しを組み合わせて行うことで、全体として適正化を図ることも考えられる。 (ⅵ)会社における相談役・顧問制度の検討の結果、相談役・顧問として会社に残らないこととなった元社長・CEO経験者については、積極的に他社の社外取締役に就任して、その長年の経営で培った経営の知見を活用することが、社会への貢献という観点から期待される。 |
第一に、相談役・顧問のうち、退任した社長・CEO経験者が相談役・顧問に就任する場合に対象を限定している点である(各提言に共通)(脚注10)。
第二に、相談役・顧問の役割が各企業によってさまざまであり、社長・CEO経験者を相談役・顧問とすることが一律に良い・悪いというものではないことから、相談役・顧問を一律に否定するのではなく、各企業における役割の明確化と処遇の適正化を社外者の関与を得ながら検討すべきと提言しているにとどまる点である(提言(i)~(ⅲ))。
第三に、相談役・顧問の人数、役割、処遇等はこれまで外部から認識することが難しく不透明であったことが、相談役・顧問による不当な影響力の行使を疑わせる要因の一つであったと考えられることから、相談役・顧問に関する情報発信を企業が積極的に行うことを期待するとしている点である(提言(ⅳ))。
第四に、相談役・顧問制度の見直しの結果、相談役・顧問の人数や報酬の削減を行う場合も意識した提言を行っている点である(提言(ⅴ)・提言(ⅵ))。
なお、本ガイドラインは、相談役・顧問のあり方に加えて、取締役会長のあり方についても、現社長・CEOに権限を集中させることの是非を踏まえて、取締役会長の権限・肩書(代表権の付与等)を検討すべきであると提言している。
Ⅶ 終わりに
本ガイドラインは、企業の自主的な取組を後押しするためのものである。本ガイドラインは特にコーポレートガバナンスに悩んでいる企業がこれを契機として検討を深めることに主眼があり、本ガイドラインに形式的に従うことは意味がない。本ガイドラインの内容もそれが唯一の正解ではなく、今後のさまざまな議論や実務を踏まえて適宜見直されていくべきものであると考えられる。各企業において、本ガイドラインの提言のうち自社に参考となる事項があれば、それを踏まえて自社のコーポレートガバナンスを実効的なものとするためにどうすべきか、検討する機会を設けることが望まれる。
脚注
1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf 2 CGS研究会報告書とCGSガイドラインの内容は基本的に同様であり、異なる点は、CGS研究会報告書の本文「6. 本研究会で十分に議論できなかった事項」がCGS研究会特有の話であることから、CGSガイドラインでは引用されていない点である。その他はいずれも実務指針化に伴う形式的な調整にとどまるため、本稿におけるCGSガイドラインの解説は、同時にCGS研究会報告書の解説としても当てはまる。
3 本ガイドラインにおいて、「社長・CEO」は、企業の経営のトップに立つ者を指し、また、「経営陣」は、企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役、執行役員その他重要な使用人を指すとされている。
4 http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170331012/20170331012.html 5 http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170310001.html 6 縦軸・横軸いずれに関しても、会社法上の機関設計とは必ずしも結びつくものではない。どの機関設計を選択していたとしても、その実質に応じていずれの分類にもなり得る。
7 http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428007/20170428007.html 8 本ガイドラインにおいて、「社内者」は、社内取締役、執行役、執行役員その他の従業員を指すとされており、「社外者」は、社外取締役、社外監査役、社外の有識者を指すとされている。
9 詳細については本ガイドライン別紙3「指名委員会・報酬委員会活用の視点」を参照されたい。また、この点に関しては、本ガイドラインのほか、第6回CGS研究会においてプレゼンテーションを行っていただいたエゴンゼンダー株式会社の説明資料や、ウイリス・タワーズワトソンの説明資料もそれぞれ大いに参考になると考えられる。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/006_haifu.html 10 なお、相談役・顧問以外にもさまざまな役職名があるが、本ガイドラインでは、名称のいかんを問わず、退任した社長・CEOが何らかの名称で会社と一定の関係を保持する場合が広く対象になるとされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















