資料2017年06月05日 【重要資料】 東京局資産税審理研修資料 相続税の審理上の留意点(2017年6月5日号・№693)
重要資料
H28.7
東京局資産税審理研修資料 相続税の審理上の留意点
1 贈与加算されたことにより相続税額が増加した場合の過少申告加算税の賦課
答 Bには、被相続人甲からAへの贈与(に係る贈与財産)が修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由が認められることから、過少申告加算税は賦課しない。
【理由】
1 過少申告加算税を賦課すべきでない正当な理由がある場合について 国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項は、「……納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由がある場合には……納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して……適用する。」と規定している。すなわち、過少申告となったことについて「正当な理由」があると認められる場合には、納付すべき税額のうち、「正当な理由」がある部分の税額を過少申告加算税の対象税額から控除することとなる。
ところで、当該「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である旨判示されている(最高裁平成18年4月20日判決など)。
また、平成12年7月3日付課資2-264ほか2課合同「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」事務運営指針は、相続税の過少申告加算税における「正当な理由」があると認められる事由を例示し、その一例として、相続税の申告書の提出期限後において、相続税法第51条《延滞税の特則》第2項各号に掲げる事由が生じたことを掲げている。
このうち相続税法第51条第2項第1号イは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知った事由を規定している。
2 当てはめ Aが被相続人甲から贈与により取得した財産で相続税額の基礎とされていなかったものがあることをBが知ったのは、相続税の申告書の提出期限後の調査結果説明時であることから、Bについて「正当な理由」があると認められる相続税法第51条第2項各号に掲げる事由が生じたと認められ、Bに対しては過少申告加算税を課すべきでない。
なお、この場合には延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないこととなる。
2 いわゆる調査手続の導入前の年分に係る更正処分の理由の附記の要否
答 本事例の7の更正処分は、国税通則法第74条の14第1項の規定が適用される平成25年1月1日以後にする不利益処分に該当することから、理由の附記が必要となる。
【理由】 国税に関する法律に基づき行われる処分(以下「国税に関する処分」という。)における行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定は、国税通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項で規定する行政手続法の適用除外規定から除かれるため、国税に関する処分について不利益処分をする場合には、理由を掲示しなければならないこととなる。
そして、国税に関する処分についての不利益処分は、増額更正処分、決定処分、加算税の賦課決定処分、更正をする理由がない旨の通知処分及び更正の請求を一部否認する減額更正処分などがあるところ、本事例の7のAに対する平成26年12月19日の更正処分は、増額更正処分であるため、不利益処分に該当する。
また、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年12月2日法律第114号)附則第41条(以下「本件附則41条」という。)により、国税通則法第74条の14第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用すると規定しているところ、本事例の7のAに対する更正処分が行われたのは平成26年12月19日である。
以上のことから、本事例の7の更正処分には、理由の附記が必要となる。
なお、不利益処分に該当しない職権による減額更正や更正の請求を全部認容する更正処分(本事例の4及び6の減額更正処分)には理由の附記は必要ない。
おって、本件附則41条により、平成25年1月1日前にした旧国税通則法第74条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例によると規定している。そして、この従前の例とは、行政手続法第3条《適用除外》第1項及び上記改正前の旧国税通則法第74条の2第1項の規定により、国税に関する処分については、行政手続法の規定は適用しないこととされていたため、本事例の2の平成23年12月1日の決定処分については、理由の附記は必要ないこととなる。
3 相続が開始した年に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合の課税関係(住宅取得等資金の非課税の場合①)
答 1 相続税について 相続の開始の年に贈与を受けた住宅取得資金のうち、租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、3年内贈与加算の対象から除かれるため、本件資金から非課税限度額1,000万円を差し引いた300万円が3年内贈与加算の対象となる。
2 贈与税について 本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされた300万円を差し引いた1,000万円が本件資金に係る贈与税の対象となり、甲が、租税特別措置法第70条の2第1項の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに同条第8項に規定する事項を記載し、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。
【理由】
1 相続税について
租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項による読替え後の相続税法第19条第1項の規定によれば、いわゆる3年内贈与加算の対象から、相続の開始の年において被相続人から贈与により取得をした住宅取得等資金のうち租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないものが除かれることとなる。
相続の開始した年に被相続人から住宅取得等資金の贈与を受けていた場合には、租税特別措置法施行令第40条の4の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等》第9項の読替え後の相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項の規定により、3年内贈与加算の対象とされない財産には、その住宅取得等資金のうち租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないものが含まれることとなる。
これを本事例についてみると、甲は父乙から住宅取得等資金として本件資金の贈与を受けているところ、本件資金のうち、租税特別措置法第70条の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなる非課税限度額1,000万円が3年内贈与加算の対象とされない財産に該当し、本件資金から3年内贈与加算の対象とされない非課税限度額1,000万円を差し引いた300万円が3年内贈与加算の対象となる。
なお、贈与税の配偶者控除の場合とは異なり、租税特別措置法第70条の2第1項の適用について相続税の申告書に記載すべき事項及び添付すべき書類はない。
2 贈与税の課税関係
相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》第4項は、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産の価額で3年内贈与加算の対象として相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しないこととしている。そのため、本件資金のうち、3年内贈与加算の対象として相続税の課税価格に加算される300万円については、相続税法第21条の2第4項の規定により、贈与税の課税価格に算入しないこととなる。
したがって、本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされた300万円を差し引いた1,000万円が本件資金に係る贈与税の対象となるが、この1,000万円については、租税特別措置法第70条の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない。
なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、当該贈与を受けた年中に贈与者が死亡したときの贈与税の申告書の提出及び提出期限については、法令等に特段の規定が置かれていないことから、租税特別措置法第70条の2第1項の適用を受けるためには、原則どおり、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに同条第8項に規定する事項を記載し、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければならない。
4 相続が開始した年に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合の課税関係(住宅取得等資金の非課税の場合②)
答 本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされなかった1,000万円についても、3年内贈与加算の対象となり、相続税の課税対象となる。
【理由】 問3において、本件資金のうち1,000万円が相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》に規定する3年内贈与加算の対象とならないこととされたのは、租税特別措置法施行令第40条の4の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等》第9項の規定により相続税法第19条第1項が読み替えられたことに基づくものである。
この租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項は、租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者が当該贈与をした年の途中に死亡した場合における規定であることから、当該贈与をした財産が住宅取得等資金に該当しない場合には租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項の適用はないこととなる。
そのため、本件資金が住宅取得等資金に該当しない場合には、租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項の適用はなく、相続税法第19条第1項は読み替えられないことから、本件資金の全てが3年内贈与加算の対象となる。
したがって、甲は、父乙の相続に係る相続税の申告書を提出している場合には、当該相続税の修正申告書を提出する必要がある。
5 相続税額の2割加算の対象者について
答 孫B、孫C及び孫Eが相続税額の2割加算の対象となる。
【理由】
1 甲と養子縁組を行った弟A及び孫B
相続又は遺贈(以下「相続等」という。)により財産を取得した者がその相続等に係る被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、その相続税額の20%に相当する金額を加算した金額とすることとされている(相法18①)。
そして、この2割加算の対象とされていない「一親等の血族」には、代襲相続人である場合を除いて、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫等)が被相続人の養子となっている場合は含まないものとされている(相法18②、相基通18-3)。すなわち、代襲相続人でない孫、ひ孫等が、被相続人の養子になっている場合は、当該養子は一親等の血族に含まれず2割加算の対象となる。
したがって、弟A及び孫Bは、ともに養子ではあるが、直系卑属に該当しない弟Aは2割加算の対象とならず、直系卑属である孫Bは2割加算の対象となる。
2 甲を特定贈与者とする相続時精算課税適用者の孫C
相続時精算課税適用者の孫Cは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者に該当することとなるから、甲から贈与により取得した財産について2割加算の対象となる。
なお、平成27年1月1日以後の贈与については、特定贈与者の推定相続人ではない孫についても相続時精算課税が適用できることとされ(措法70の2の6①)、当該孫が相続時精算課税の適用を受けた後、当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、特定贈与者(被相続人)から当該贈与により取得した財産は遺贈により取得したとみなされることとなる(措法70の2の6⑤、措令40の4の6①、相法21の16②)。
3 相続放棄を行った子D及び代襲相続人の孫E
上記1のとおり、相続により財産を取得した者がその相続等に係る被相続人の「一親等の血族」、「配偶者」及び「代襲相続人となった直系卑属」以外の者である場合に、2割加算の対象とされている(相法18①②)。
そして、相続税法第18条第1項括弧書きはこの「代襲相続人となった直系卑属」について、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」と規定している。
ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれないことから(相法3①)、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、当該直系卑属は、この「代襲相続人となった直系卑属」には該当せず、2割加算の対象となる。
一方、「一親等の血族」には、相続人に限られてはいないことから、相続を放棄した者であっても、2割加算の対象とはならない。
したがって、子Dが相続を放棄したとしても、子Dは「被相続人の一親等の血族」に該当することから、2割加算の対象とはならないが、代襲相続人である孫Eが相続を放棄した場合には、孫Eは「被相続人の一親等の血族」、「配偶者」及び「代襲相続人となった直系卑属」のいずれにも該当しないため、2割加算の対象となる。
6 同居親族が被相続人とともに有料老人ホームに入居した場合における小規模宅地等の特例に係る親族要件の判定
答 妹乙は、本件土地について小規模宅地等の特例を受けることができる。
【理由】 甲は、相続開始日において、要介護認定を受けており、かつ、本件施設に入居しており、租税特別措置法施行令第40条の2第2項《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》に規定する「居住の用に供することができない事由」が認められることから、甲が本件施設に入居する直前において居住の用に供していた本件土地は租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「被相続人(甲)の居住の用に供されていた宅地等」に該当することとなる。
そして、本件土地が「特定居住用宅地等」に該当するためには、被相続人の親族が、租税特別措置法第69条の4第3項第2号イないしハに掲げる要件のいずれかに該当する必要があるところ、同号ロの要件(以下「非同居親族要件」という。)を満たすためには、当該親族が、相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であって、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き小規模宅地等の特例を受けようとする土地を有していなければならない。
本事例において、妹乙は、相続開始前3年以内に妹乙及び妹乙の配偶者の所有する家屋に居住したことがないことから、申告期限まで引き続き本件土地を保有することにより、非同居親族要件を満たすこととなり、妹乙は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる。
なお、妹乙は、甲と同様、要介護認定を受けており、本件家屋から本件施設に入居しているものの、被相続人の親族が特例対象親族に該当するか否かの判断においては、「居住の用に供することができない事由」のような規定は、租税特別措置法の規定上、設けられていないことから、妹乙は租税特別措置法第69条の4第3項第2号イに規定する親族(被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住している親族)には該当しない。
7 遺産分割の審判に係る特別抗告等がされた場合における相続税法第32条に規定する更正の請求期間の起算日について
答 相続税法第32条に規定する更正の請求期間の起算日は高等裁判所の即時抗告に対する決定が相続人らに告知された日(H25.11.X)である。
【理由】 共同相続人間で遺産分割が不調となった場合は、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができるとされている(民法907②)。その場合、家庭裁判所における調停又は審判手続により遺産分割が進められる。そして、家庭裁判所の審判に不服がある者は、高等裁判所に対して即時抗告をすることが認められている(家事事件手続法198)。
さらに、即時抗告に対する高等裁判所の決定に対しては、一定の場合に、①最高裁判所に特別抗告及び②高等裁判所に抗告の許可の申立て(①及び②を併せて、以下「特別抗告等」という。本事例は①。)ができることとされている(家事事件手続法94、97)。
ただし、この特別抗告等がされた場合でも、確定遮断効を有しないことから、即時抗告に対する高等裁判所の決定に係る告知によって審判は確定することとなる(家事事件手続法74④⑤)。
したがって、遺産分割に関する家事審判に係る即時抗告に対する高等裁判所の決定に対して特別抗告等がされた場合における相続税法第32条第1項第1号に規定する事由が生じたことを知った日は、即時抗告に対する高等裁判所の決定に係る告知がされた日であり、当該告知がされた日が同条の規定による更正の請求期間の起算日となる。
8 平成26年分以前に未成年者控除の適用を受けていた場合の平成27年分以後における未成年者控除額の計算について
答 長女Aの未成年者控除額は、80万円となる。
【計算式】 ① 未成年者控除額
10万円×(甲の相続開始時において長女Aが20歳に達するまでの年数)
=10万円×(20歳-12歳)
=80万円
② 平成27年1月1日前に開始した相続に係る相続税について、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」(以下「本件改正法」という。)附則による前回の相続における未成年者控除不足額
10万円×(乙の相続開始時において長女Aが20歳に達するまでの年数)-(既に未成年者控除を受けた金額)
=10万円×(20歳-1歳)-90万円
=100万円
※ ①未成年者控除額80万円は②前回の相続における未成年者控除不足額100万円の範囲内のため、80万円が甲の相続における未成年者控除額となる。
【理由】 未成年者控除の適用を受ける者が、他の相続において既に未成年者控除を受けたことがある者である場合には、その控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が前回の相続時の控除可能額に満たなかった部分の金額の範囲に限られている(相法19の3③)。つまり、今回の相続の際に控除できる未成年者控除額は、最初の相続の際に計算した未成年者控除額から過去に適用した未成年者控除額を控除した金額(前回までの控除不足額)の範囲内となる。
平成27年1月1日以後に開始する相続に係る相続税の計算において、未成年者控除額は、20歳に達するまでの年数に10万円(平成27年1月1日前は6万円)を乗じた金額となる(相法19の3①、平成25年改正法附則12)が、平成27年1月1日以後に相続が開始した場合で、平成26年12月31日以前に開始した相続において未成年者控除を適用していたときの上記の控除不足額の計算をどのように行うべきかについて疑義が生じる。
この点については、経過措置が設けられており、未成年者が、平成27年1月1日前に開始した相続に係る相続税について、本件改正法による改正前の相続税法の規定による未成年者控除の適用を受けたことがある者である場合には、未成年者控除額は当初の相続時における未成年者の20歳に達するまでの年数に10万円を乗じて計算した金額から既に控除を受けた金額を控除した金額に達するまでの金額となる(平成25年改正法附則12)。
H28.7
東京局資産税審理研修資料 相続税の審理上の留意点
1 贈与加算されたことにより相続税額が増加した場合の過少申告加算税の賦課
| A及びBは、被相続人甲の相続に係る相続税について、築地税務署の調査を受け、修正申告(当初申告は期限内申告である。)をした。 当該修正申告は、Aが被相続人甲からの生前贈与財産について、相続税法第19条《相続開始前三年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により当初申告の課税価格に当該贈与財産の価額を加算することを内容とするものである。 そこで、Bが、上記贈与の事実を調査結果の説明で初めて知った場合、Bが当該修正申告により新たに納付すべきこととなった税額に過少申告加算税は賦課されるか。 |
答 Bには、被相続人甲からAへの贈与(に係る贈与財産)が修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由が認められることから、過少申告加算税は賦課しない。
【理由】
1 過少申告加算税を賦課すべきでない正当な理由がある場合について 国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項は、「……納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由がある場合には……納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して……適用する。」と規定している。すなわち、過少申告となったことについて「正当な理由」があると認められる場合には、納付すべき税額のうち、「正当な理由」がある部分の税額を過少申告加算税の対象税額から控除することとなる。
ところで、当該「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である旨判示されている(最高裁平成18年4月20日判決など)。
また、平成12年7月3日付課資2-264ほか2課合同「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」事務運営指針は、相続税の過少申告加算税における「正当な理由」があると認められる事由を例示し、その一例として、相続税の申告書の提出期限後において、相続税法第51条《延滞税の特則》第2項各号に掲げる事由が生じたことを掲げている。
このうち相続税法第51条第2項第1号イは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかったものがあることを知った事由を規定している。
2 当てはめ Aが被相続人甲から贈与により取得した財産で相続税額の基礎とされていなかったものがあることをBが知ったのは、相続税の申告書の提出期限後の調査結果説明時であることから、Bについて「正当な理由」があると認められる相続税法第51条第2項各号に掲げる事由が生じたと認められ、Bに対しては過少申告加算税を課すべきでない。
なお、この場合には延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないこととなる。
2 いわゆる調査手続の導入前の年分に係る更正処分の理由の附記の要否
| 被相続人甲の相続人は、A及びBの2名であり、被相続人甲の相続財産は200である。 課税の経緯は次のとおりであるが、本件において、築地税務署長が行ったAに対する相続税の増額更正処分(次の7に掲げる更正処分)には理由の附記が必要か。 1 平成22年12月1日 Bは、平成20年1月3日付の第1遺言書(A100・B100)に基づき、被相続人甲の相続(相続開始日:平成22年2月10日)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告書を提出した。 なお、Aは本件相続税に係る相続税の申告書を法定申告期限までに提出しなかった。 2 平成23年12月1日 築地税務署長は、Aに対して、本件相続税の決定処分を行った。 3 平成24年2月2日 Bは、平成21年3月2日付の第2遺言書(B200)が見つかったとして、本件相続税の修正申告書を提出した。 4 平成24年4月27日 築地税務署長は、Aが行った平成24年2月2日付の更正の請求に対し、全部認容する内容の減額更正処分を行った。 5 平成26年3月31日 第2遺言書が無効であるとの判決 6 平成26年12月19日 築地税務署長は、第1遺言書が有効であるとしてBが行った平成26年7月2日付の更正の請求に対し、全部認容する内容の減額更正処分を行った。 7 平成26年12月19日 築地税務署長は、上記6のBへの減額更正処分に伴い、Aに対して相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定に基づき本件相続税の増額更正処分を行った。 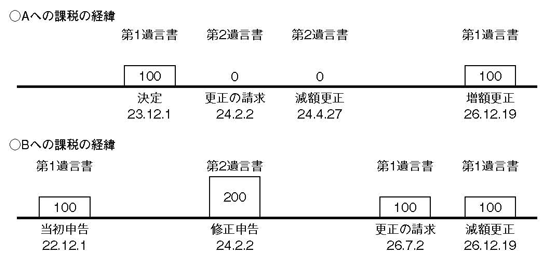 |
答 本事例の7の更正処分は、国税通則法第74条の14第1項の規定が適用される平成25年1月1日以後にする不利益処分に該当することから、理由の附記が必要となる。
【理由】 国税に関する法律に基づき行われる処分(以下「国税に関する処分」という。)における行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定は、国税通則法第74条の14《行政手続法の適用除外》第1項で規定する行政手続法の適用除外規定から除かれるため、国税に関する処分について不利益処分をする場合には、理由を掲示しなければならないこととなる。
そして、国税に関する処分についての不利益処分は、増額更正処分、決定処分、加算税の賦課決定処分、更正をする理由がない旨の通知処分及び更正の請求を一部否認する減額更正処分などがあるところ、本事例の7のAに対する平成26年12月19日の更正処分は、増額更正処分であるため、不利益処分に該当する。
また、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年12月2日法律第114号)附則第41条(以下「本件附則41条」という。)により、国税通則法第74条の14第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用すると規定しているところ、本事例の7のAに対する更正処分が行われたのは平成26年12月19日である。
以上のことから、本事例の7の更正処分には、理由の附記が必要となる。
なお、不利益処分に該当しない職権による減額更正や更正の請求を全部認容する更正処分(本事例の4及び6の減額更正処分)には理由の附記は必要ない。
おって、本件附則41条により、平成25年1月1日前にした旧国税通則法第74条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例によると規定している。そして、この従前の例とは、行政手続法第3条《適用除外》第1項及び上記改正前の旧国税通則法第74条の2第1項の規定により、国税に関する処分については、行政手続法の規定は適用しないこととされていたため、本事例の2の平成23年12月1日の決定処分については、理由の附記は必要ないこととなる。
3 相続が開始した年に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合の課税関係(住宅取得等資金の非課税の場合①)
| 甲は、平成28年1月に父乙から居住用不動産を取得する目的で資金1,300万円(以下「本件資金」という。)の贈与を受け、租税特別措置法第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》の適用を受けようとしていたところ、同年3月に父乙が死亡した。 甲が、父乙の相続により財産を取得し、かつ、本件資金につき租税特別措置法第70条の2第1項の適用を受ける場合における本件資金の相続税及び贈与税の課税関係はどのようになるか。 なお、平成28年8月に甲は、本件資金によって居住用財産を取得しており、租税特別措置法第70条の2第1項の適用がある場合の非課税限度額は1,000万円である。 おって、甲について、父乙から過去に本件資金以外に贈与により取得した財産はない。  |
答 1 相続税について 相続の開始の年に贈与を受けた住宅取得資金のうち、租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、3年内贈与加算の対象から除かれるため、本件資金から非課税限度額1,000万円を差し引いた300万円が3年内贈与加算の対象となる。
2 贈与税について 本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされた300万円を差し引いた1,000万円が本件資金に係る贈与税の対象となり、甲が、租税特別措置法第70条の2第1項の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに同条第8項に規定する事項を記載し、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。
【理由】
1 相続税について
租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項による読替え後の相続税法第19条第1項の規定によれば、いわゆる3年内贈与加算の対象から、相続の開始の年において被相続人から贈与により取得をした住宅取得等資金のうち租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないものが除かれることとなる。
相続の開始した年に被相続人から住宅取得等資金の贈与を受けていた場合には、租税特別措置法施行令第40条の4の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等》第9項の読替え後の相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項の規定により、3年内贈与加算の対象とされない財産には、その住宅取得等資金のうち租税特別措置法第70条の2第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないものが含まれることとなる。
これを本事例についてみると、甲は父乙から住宅取得等資金として本件資金の贈与を受けているところ、本件資金のうち、租税特別措置法第70条の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなる非課税限度額1,000万円が3年内贈与加算の対象とされない財産に該当し、本件資金から3年内贈与加算の対象とされない非課税限度額1,000万円を差し引いた300万円が3年内贈与加算の対象となる。
なお、贈与税の配偶者控除の場合とは異なり、租税特別措置法第70条の2第1項の適用について相続税の申告書に記載すべき事項及び添付すべき書類はない。
2 贈与税の課税関係
相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》第4項は、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産の価額で3年内贈与加算の対象として相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しないこととしている。そのため、本件資金のうち、3年内贈与加算の対象として相続税の課税価格に加算される300万円については、相続税法第21条の2第4項の規定により、贈与税の課税価格に算入しないこととなる。
したがって、本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされた300万円を差し引いた1,000万円が本件資金に係る贈与税の対象となるが、この1,000万円については、租税特別措置法第70条の2第1項の規定により贈与税の課税価格に算入されない。
なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、当該贈与を受けた年中に贈与者が死亡したときの贈与税の申告書の提出及び提出期限については、法令等に特段の規定が置かれていないことから、租税特別措置法第70条の2第1項の適用を受けるためには、原則どおり、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに同条第8項に規定する事項を記載し、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければならない。
4 相続が開始した年に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合の課税関係(住宅取得等資金の非課税の場合②)
問3における甲が、租税特別措置法第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》の適用を受けて平成28年分の贈与税の申告書を提出しようと考えていたところ、平成29年3月15日までに居住用家屋を新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下同じ。)又は取得できなかったため、父乙から贈与を受けた資金1,300万円(以下「本件資金」という。)について、同条第1項の規定の適用を受けられない場合における相続税はどのようになるか。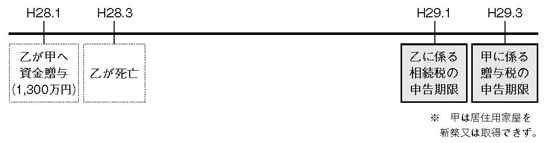 |
答 本件資金のうち3年内贈与加算の対象とされなかった1,000万円についても、3年内贈与加算の対象となり、相続税の課税対象となる。
【理由】 問3において、本件資金のうち1,000万円が相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》に規定する3年内贈与加算の対象とならないこととされたのは、租税特別措置法施行令第40条の4の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等》第9項の規定により相続税法第19条第1項が読み替えられたことに基づくものである。
この租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項は、租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金(以下「住宅取得等資金」という。)の贈与をした者が当該贈与をした年の途中に死亡した場合における規定であることから、当該贈与をした財産が住宅取得等資金に該当しない場合には租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項の適用はないこととなる。
そのため、本件資金が住宅取得等資金に該当しない場合には、租税特別措置法施行令第40条の4の2第9項の適用はなく、相続税法第19条第1項は読み替えられないことから、本件資金の全てが3年内贈与加算の対象となる。
したがって、甲は、父乙の相続に係る相続税の申告書を提出している場合には、当該相続税の修正申告書を提出する必要がある。
5 相続税額の2割加算の対象者について
| 被相続人甲(平成28年6月相続開始)が死亡したことによる相続税額について、相続税法第18条《相続税額の加算》の規定(以下「2割加算」という。)の対象となる者はどの者か。 ① 甲と養子縁組を行った弟A ② 甲と養子縁組を行った孫B ③ 甲からの贈与につき相続時精算課税の適用を受けている孫C ④ 甲から遺贈により財産を取得した甲の子D(相続放棄を行っている) ⑤ 甲から遺贈により財産を取得した代襲相続人である孫E(相続放棄を行っている) 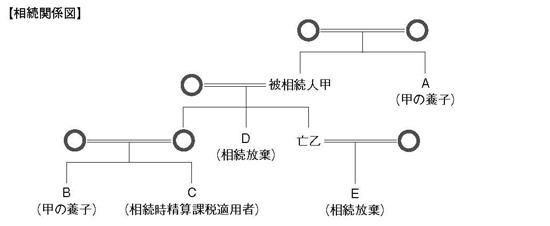 |
答 孫B、孫C及び孫Eが相続税額の2割加算の対象となる。
【理由】
1 甲と養子縁組を行った弟A及び孫B
相続又は遺贈(以下「相続等」という。)により財産を取得した者がその相続等に係る被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、その相続税額の20%に相当する金額を加算した金額とすることとされている(相法18①)。
そして、この2割加算の対象とされていない「一親等の血族」には、代襲相続人である場合を除いて、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫等)が被相続人の養子となっている場合は含まないものとされている(相法18②、相基通18-3)。すなわち、代襲相続人でない孫、ひ孫等が、被相続人の養子になっている場合は、当該養子は一親等の血族に含まれず2割加算の対象となる。
したがって、弟A及び孫Bは、ともに養子ではあるが、直系卑属に該当しない弟Aは2割加算の対象とならず、直系卑属である孫Bは2割加算の対象となる。
2 甲を特定贈与者とする相続時精算課税適用者の孫C
相続時精算課税適用者の孫Cは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者に該当することとなるから、甲から贈与により取得した財産について2割加算の対象となる。
なお、平成27年1月1日以後の贈与については、特定贈与者の推定相続人ではない孫についても相続時精算課税が適用できることとされ(措法70の2の6①)、当該孫が相続時精算課税の適用を受けた後、当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、特定贈与者(被相続人)から当該贈与により取得した財産は遺贈により取得したとみなされることとなる(措法70の2の6⑤、措令40の4の6①、相法21の16②)。
3 相続放棄を行った子D及び代襲相続人の孫E
上記1のとおり、相続により財産を取得した者がその相続等に係る被相続人の「一親等の血族」、「配偶者」及び「代襲相続人となった直系卑属」以外の者である場合に、2割加算の対象とされている(相法18①②)。
そして、相続税法第18条第1項括弧書きはこの「代襲相続人となった直系卑属」について、「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」と規定している。
ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれないことから(相法3①)、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、当該直系卑属は、この「代襲相続人となった直系卑属」には該当せず、2割加算の対象となる。
一方、「一親等の血族」には、相続人に限られてはいないことから、相続を放棄した者であっても、2割加算の対象とはならない。
したがって、子Dが相続を放棄したとしても、子Dは「被相続人の一親等の血族」に該当することから、2割加算の対象とはならないが、代襲相続人である孫Eが相続を放棄した場合には、孫Eは「被相続人の一親等の血族」、「配偶者」及び「代襲相続人となった直系卑属」のいずれにも該当しないため、2割加算の対象となる。
6 同居親族が被相続人とともに有料老人ホームに入居した場合における小規模宅地等の特例に係る親族要件の判定
| 甲(平成28年相続開始)の唯一の相続人である妹乙は、平成24年まで甲及び妹乙が居住の用に供していた家屋(以下「本件家屋」という。)及びその敷地(以下「本件土地」という。)を甲の相続により取得した。 甲及び妹乙は、平成24年中に、老人福祉法第29条《届出等》第1項に規定する有料老人ホーム(以下「本件施設」という。)にそれぞれ入居していたため、甲の相続開始日において、本件家屋は利用されていなかった。 妹乙は、本件土地について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(以下「小規模宅地等の特例」という。)第3項に規定する特定居住用宅地等に該当するとして、同特例の適用を受けることができるか。 なお、甲及び妹乙は介護保険法第19条《市町村の認定》第1項に規定する要介護認定を受けていた。 おって、甲と妹乙の生計は別であり、妹乙は甲の相続開始前3年以内に妹乙又は妹乙の配偶者が所有する家屋には居住していない。 |
答 妹乙は、本件土地について小規模宅地等の特例を受けることができる。
【理由】 甲は、相続開始日において、要介護認定を受けており、かつ、本件施設に入居しており、租税特別措置法施行令第40条の2第2項《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》に規定する「居住の用に供することができない事由」が認められることから、甲が本件施設に入居する直前において居住の用に供していた本件土地は租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「被相続人(甲)の居住の用に供されていた宅地等」に該当することとなる。
そして、本件土地が「特定居住用宅地等」に該当するためには、被相続人の親族が、租税特別措置法第69条の4第3項第2号イないしハに掲げる要件のいずれかに該当する必要があるところ、同号ロの要件(以下「非同居親族要件」という。)を満たすためには、当該親族が、相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であって、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き小規模宅地等の特例を受けようとする土地を有していなければならない。
本事例において、妹乙は、相続開始前3年以内に妹乙及び妹乙の配偶者の所有する家屋に居住したことがないことから、申告期限まで引き続き本件土地を保有することにより、非同居親族要件を満たすこととなり、妹乙は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる。
なお、妹乙は、甲と同様、要介護認定を受けており、本件家屋から本件施設に入居しているものの、被相続人の親族が特例対象親族に該当するか否かの判断においては、「居住の用に供することができない事由」のような規定は、租税特別措置法の規定上、設けられていないことから、妹乙は租税特別措置法第69条の4第3項第2号イに規定する親族(被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住している親族)には該当しない。
7 遺産分割の審判に係る特別抗告等がされた場合における相続税法第32条に規定する更正の請求期間の起算日について
被相続人甲の相続人A及びBは、平成23年3月、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたが、調停は不成立となり審判へ移行した。その後の遺産分割に係る審判等の経緯は次のとおりであるが、相続税法第32条《更正の請求の特則》に規定する更正の請求期間の起算日はいつか。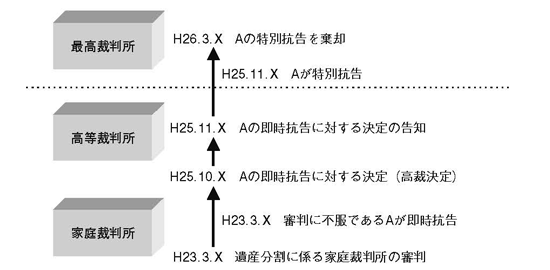 |
答 相続税法第32条に規定する更正の請求期間の起算日は高等裁判所の即時抗告に対する決定が相続人らに告知された日(H25.11.X)である。
【理由】 共同相続人間で遺産分割が不調となった場合は、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求することができるとされている(民法907②)。その場合、家庭裁判所における調停又は審判手続により遺産分割が進められる。そして、家庭裁判所の審判に不服がある者は、高等裁判所に対して即時抗告をすることが認められている(家事事件手続法198)。
さらに、即時抗告に対する高等裁判所の決定に対しては、一定の場合に、①最高裁判所に特別抗告及び②高等裁判所に抗告の許可の申立て(①及び②を併せて、以下「特別抗告等」という。本事例は①。)ができることとされている(家事事件手続法94、97)。
ただし、この特別抗告等がされた場合でも、確定遮断効を有しないことから、即時抗告に対する高等裁判所の決定に係る告知によって審判は確定することとなる(家事事件手続法74④⑤)。
したがって、遺産分割に関する家事審判に係る即時抗告に対する高等裁判所の決定に対して特別抗告等がされた場合における相続税法第32条第1項第1号に規定する事由が生じたことを知った日は、即時抗告に対する高等裁判所の決定に係る告知がされた日であり、当該告知がされた日が同条の規定による更正の請求期間の起算日となる。
8 平成26年分以前に未成年者控除の適用を受けていた場合の平成27年分以後における未成年者控除額の計算について
| 被相続人甲(平成28年1月相続開始)の相続人は、長女A(12歳)の1名であり、同人の算出相続税額は100万円であった。 長女Aは、被相続人乙(平成17年1月相続開始)の相続税の計算において、既に未成年者控除の適用を受けており、その控除額は90万円であった。 この場合、被相続人甲の相続における長女Aの未成年者控除額はいくらとなるか。 |
答 長女Aの未成年者控除額は、80万円となる。
【計算式】 ① 未成年者控除額
10万円×(甲の相続開始時において長女Aが20歳に達するまでの年数)
=10万円×(20歳-12歳)
=80万円
② 平成27年1月1日前に開始した相続に係る相続税について、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」(以下「本件改正法」という。)附則による前回の相続における未成年者控除不足額
10万円×(乙の相続開始時において長女Aが20歳に達するまでの年数)-(既に未成年者控除を受けた金額)
=10万円×(20歳-1歳)-90万円
=100万円
※ ①未成年者控除額80万円は②前回の相続における未成年者控除不足額100万円の範囲内のため、80万円が甲の相続における未成年者控除額となる。
【理由】 未成年者控除の適用を受ける者が、他の相続において既に未成年者控除を受けたことがある者である場合には、その控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が前回の相続時の控除可能額に満たなかった部分の金額の範囲に限られている(相法19の3③)。つまり、今回の相続の際に控除できる未成年者控除額は、最初の相続の際に計算した未成年者控除額から過去に適用した未成年者控除額を控除した金額(前回までの控除不足額)の範囲内となる。
平成27年1月1日以後に開始する相続に係る相続税の計算において、未成年者控除額は、20歳に達するまでの年数に10万円(平成27年1月1日前は6万円)を乗じた金額となる(相法19の3①、平成25年改正法附則12)が、平成27年1月1日以後に相続が開始した場合で、平成26年12月31日以前に開始した相続において未成年者控除を適用していたときの上記の控除不足額の計算をどのように行うべきかについて疑義が生じる。
この点については、経過措置が設けられており、未成年者が、平成27年1月1日前に開始した相続に係る相続税について、本件改正法による改正前の相続税法の規定による未成年者控除の適用を受けたことがある者である場合には、未成年者控除額は当初の相続時における未成年者の20歳に達するまでの年数に10万円を乗じて計算した金額から既に控除を受けた金額を控除した金額に達するまでの金額となる(平成25年改正法附則12)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























