資料2017年07月17日 【重要資料】 東京局資産税審理研修資料 財産評価の審理上の留意点(2017年7月17日号・№699)
重要資料
H28.7
東京局資産税審理研修資料 財産評価の審理上の留意点
1 直前期末の翌日から課税時期までの間に合併等がある場合の類似業種比準方式の適用関係
答 類似業種比準方式を直ちに適用することはできない。
合併後に課税時期がある場合において、類似業種比準方式を適用できるかどうかは、個々の事例ごとに、直前期末における比準3要素について合理的な数値が得られるかを判断する必要があることに留意する。
なお、合併の前後で会社の実態に変化がないと認められ、合併後の会社と吸収合併された会社の配当等を合算して比準要素を算定することにより、1株当たりの①配当金額、②年利益金額及び③純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「比準3要素」という。)それぞれについて合理的な数値を得ることができる場合には、類似業種比準方式を適用することもできる。
【理由】 直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合、合併後の会社は、通常、合併の前後で事業構成や財務内容が大きく変化することから、類似業種比準方式の適用の前提である、「各比準要素の適切な把握」ができない。
そのため、合併後に課税時期がある場合は、類似業種比準方式を適用できるかどうかについて、個々の事例ごとに判断する必要がある。
そこで、合併後の会社の取引相場のない株式を評価するに当たり、どのような算定方法であれば適切な比準要素が得られるかを検討すると、以下のケースが考えられる。
前提
直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合において、仮に、合併後の会社(以下「A法人」という。)、合併存続会社(以下「B法人」という。)及び吸収合併された会社(以下「C法人」という。)とする。
1 A法人株式の評価に当たり、B法人の合併前の決算期の配当等の実績に基づいて比準要素を算定する場合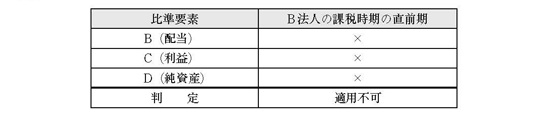
2 A法人株式の評価に当たり、B法人とC法人の合併前の決算期の配当等の実績を合算して比準要素を算定する場合
3 上記1及び2の結果、合併後に課税時期がある場合において、上記1により比準要素を算定すると、合理的な数値を得ることができず、また、上記2により比準要素を算定しても、合併の前後で会社の実態に変化がないと認められる場合を除き、合理的な数値を得ることはできないこととなる。
したがって、合併直後に課税時期がある場合において、合併前後の会社実態に変化がない場合を除いて、適切な比準要素を求めることが困難であることから、類似業種比準方式を適用することはできない。
この場合において、評基通189-4に準じて開業後3年未満の会社等として純資産価額方式により評価することも1つの方法であると考えられる。
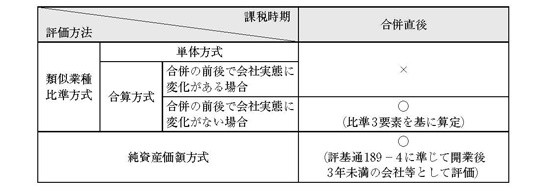
【関係法令通達】 評基通179、180
2 取引相場のない株式等の評価――1株当たりの年利益金額(非経常的な利益)
答 ある利益が経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個々に判定する。
また、非経常的な損益が複数ある場合には、これらを通算した上で、利益金額があれば、これを法人税の課税所得金額から控除する(評基通183(2))。
【理由】 固定資産売却益及び保険差益は、毎期、反復継続して発生する損益ではなく臨時に発生する損益であることから、評基通183(2)かっこ書きにおいて、非経常的な利益として例示されている。
ある利益が経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかの判定に当たっては、その利益が、評価会社の損益計算上、「経常利益」又は「特別利益」のいずれに計上されているか若しくは「固定資産売却益」等の勘定科目の名称で判断するのではなく、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個々に判定する必要がある。
また、評基通183(2)かっこ書きで法人税の課税所得金額から除くこととされている非経常的な利益の金額とは、課税時期の直前期末以前1年間に発生した非経常的な利益全体をいうのであるから、非経常的な損益を全て通算し、利益の金額があればこれを控除することとなる。
なお、非経常的な損益を通算した金額が負数となった場合は、法人税の課税所得金額から控除する非経常的な利益金額は0とする。
【関係法令通達】 評基通183(2)
3 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
答 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、奥行価格補正(評基通15)の定めからがけ地等を有する宅地の評価(評基通20-4)までの定めによって評価した価額から、その価額に下記の算式によって計算した割合(以下「控除割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する(評基通20-5)。
ただし、1画地の宅地のうちに正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低い場合など、控除割合がマイナスになる場合等はこの評価方法は適用しない。
(算式)
【理由】
建築基準法は、道路、公園、上下水道等の公共施設と建築物の規模との均衡を図り、その地域全体の環境を守るために、容積率(建築基準法第52条第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地に対する割合)の最高限度を定めており、この容積率は道路幅員などと同様に、土地の価額に影響を与えるものである。
通常、容積率は、一定の地域ごとに面的な広がりをもって指定されていることから、路線価は、各地域の容積率を反映した価額となっている。
一般的に、1街区のうち表道路に面する地域と裏道路に面する地域とで容積率が異なる場合には、路線価も異なるものとなる。
しかし、1画地の宅地が表道路に面する地域と裏道路に面する地域とで異なる容積率である場合、表道路に面する地域の容積率を反映して決定されている正面路線価を基とし、奥行価格補正などの画地調整を行って評価しただけでは、その宅地が、表道路に面する地域の容積率と異なる容積率の部分を有しているという個別的な要因が評価額に反映されないことになる。
そのため、容積率の異なる2以上の地域にわたる1画地の宅地について、容積率の相違(格差)による個別事情(影響度)を減額調整する評価方法が定められている。
【関係法令通達】 評基通20-5
4 市街化調整区域内にある雑種地の評価
答 評価額は、19,472,000円となる。
【理由】 1 評基通82では、「雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。」と規定している。
2 評基通82に基づく、具体的計算方法は、以下のとおりである。
(1)その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めにより評価した1平方メートル当たりの価額を求める。
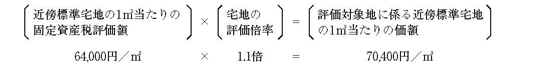
(2)その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
イ 位置、形状の差
雑種地が倍率地域に存する場合には、地区区分の定めが設けられていないので、宅地比準方式によって評価する市街地農地等の取扱いを準用し、普通住宅地区の画地調整率を参考として計算することができる(国税庁ホームページ・質疑応答事例「市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差」参照)。
ロ 法令上の制限
市街化調整区域内所在の近傍標準宅地の固定資産税評価額は、建物の敷地の用に供される土地として建物の建築が可能であることを前提に付されているものと考えられる。
一方、評価対象地は、店舗等の建築は可能であるものの、都市計画法により用途が限定されていることから、この土地利用上の制限を考慮して、▲30%のしんしゃくをするのが相当と考えられる。
ハ 宅地造成費
評価対象地は、整地費600円/㎡が必要な土地であるため、評価対象地の1平方メートル当たりの価額から同金額を控除する。
(3)以上を考慮すると、評価対象地の評価額は、以下の算式により計算した金額となる。
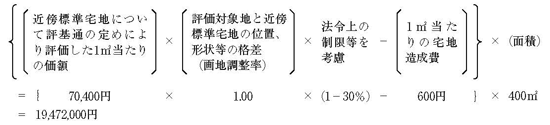
《計算順序の留意点》
宅地造成費の控除の順序については、画地調整率の適用及び法令上の制限のしんしゃくを行った後、控除することに留意する。
宅地造成費を控除した後、法令上の制限のしんしゃくを行うことは、宅地造成費に法令上の制限のしんしゃくを考慮した割合を乗じることとなり、当該宅地造成費相当額をしんしゃく割合で圧縮してしまうこととなるため相当ではない。
【関係法令通達】 評基通 7、82
5 財産評価基本通達第6項
答 評基通6は「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。
これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当」であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる「特別の事情」の有無による旨示されている。
この「特別の事情」の有無の判断に当たっては、次の≪参考≫に掲げる点などに着目しつつ、様々な事実関係を総合考慮することに留意する。
≪裁判例≫
(大阪高裁平成17年5月31日抜粋)
「評価基本通達により画一的に適用すべき評価方法を定めた以上は、当該贈与財産がその評価方法が定められた趣旨に合致する財産の範疇に含まれる財産であり、それに従った評価をすることが、時価の評価として合理性を有する限り、納税者間の公平及び納税者の信頼保護の見地から、原則として、すべての納税者との関係で評価基本通達に基づく評価を行う必要があり、特定の納税者あるいは特定の贈与財産についてのみ評価基本通達に定める方法以外の方法によって評価することは、たとえその方法による評価がそれ自体としては相続税法22条の定める時価として許容できる範囲内のものであったとしても、許されないものと解すべきである。
しかしながら、他方、評価基本通達に定められた評価方法によるべきであるとする趣旨が上記のようなものであることからすると、対象となる贈与財産が形式的には同通達の定める財産であっても、その実質が対象財産と評価することができないものであったり、上記の評価方法を画一的に適用するという形式的平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合など、上記評価方法によらないことが正当と是認される特別の事情がある場合には、別の合理的な評価方法によることが許されるものと解すべきである。このことは、評価基本通達6において、同通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされていることからも明らかである。」
(東京地裁平成17年11月10日抜粋)
「評価の目的は、あくまでも当該財産の客観的交換価値を確定することにあり、本件通達に定められた評価方法により財産を評価すべきであるとする趣旨が以上のとおりであることからすれば、本件通達に定められた評価方法を画一的に適用することによって、明らかに当該財産の容観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなり、そのため、実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び本件通達の趣旨に反することとなるなど、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方式によることが許されると解すべきであり、本件通達6においても、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められている。」
≪参考≫
① 評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
② 評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
③ 評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
④ 上記③の著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
【関係法令通達】 評基通 6
H28.7
東京局資産税審理研修資料 財産評価の審理上の留意点
1 直前期末の翌日から課税時期までの間に合併等がある場合の類似業種比準方式の適用関係
| 取引相場のない株式を評価するに当たり、直前期末の翌日から課税時期までの間に吸収合併がある場合について、類似業種比準方式の適用はどのようになるか。 |
答 類似業種比準方式を直ちに適用することはできない。
合併後に課税時期がある場合において、類似業種比準方式を適用できるかどうかは、個々の事例ごとに、直前期末における比準3要素について合理的な数値が得られるかを判断する必要があることに留意する。
なお、合併の前後で会社の実態に変化がないと認められ、合併後の会社と吸収合併された会社の配当等を合算して比準要素を算定することにより、1株当たりの①配当金額、②年利益金額及び③純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「比準3要素」という。)それぞれについて合理的な数値を得ることができる場合には、類似業種比準方式を適用することもできる。
【理由】 直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合、合併後の会社は、通常、合併の前後で事業構成や財務内容が大きく変化することから、類似業種比準方式の適用の前提である、「各比準要素の適切な把握」ができない。
そのため、合併後に課税時期がある場合は、類似業種比準方式を適用できるかどうかについて、個々の事例ごとに判断する必要がある。
そこで、合併後の会社の取引相場のない株式を評価するに当たり、どのような算定方法であれば適切な比準要素が得られるかを検討すると、以下のケースが考えられる。
前提
直前期末の翌日から課税時期までの間に合併がある場合において、仮に、合併後の会社(以下「A法人」という。)、合併存続会社(以下「B法人」という。)及び吸収合併された会社(以下「C法人」という。)とする。
1 A法人株式の評価に当たり、B法人の合併前の決算期の配当等の実績に基づいて比準要素を算定する場合
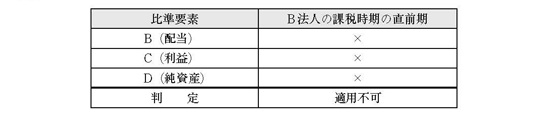
2 A法人株式の評価に当たり、B法人とC法人の合併前の決算期の配当等の実績を合算して比準要素を算定する場合

3 上記1及び2の結果、合併後に課税時期がある場合において、上記1により比準要素を算定すると、合理的な数値を得ることができず、また、上記2により比準要素を算定しても、合併の前後で会社の実態に変化がないと認められる場合を除き、合理的な数値を得ることはできないこととなる。
したがって、合併直後に課税時期がある場合において、合併前後の会社実態に変化がない場合を除いて、適切な比準要素を求めることが困難であることから、類似業種比準方式を適用することはできない。
この場合において、評基通189-4に準じて開業後3年未満の会社等として純資産価額方式により評価することも1つの方法であると考えられる。
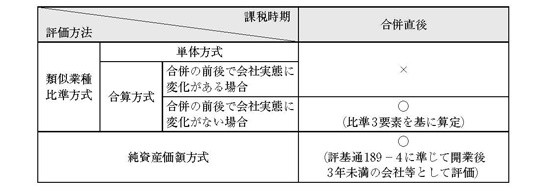
【関係法令通達】 評基通179、180
2 取引相場のない株式等の評価――1株当たりの年利益金額(非経常的な利益)
| 評価会社の直前期末以前1年間の法人税の課税所得金額には、毎期発生している固定資産売却益が含まれている。この固定資産売却益は、「1株当たりの年利益金額=(C)」の計算に当たって、法人税の課税所得金額から控除する非経常的な利益に該当するか。 また、他にも保険差益、有価証券売却損益等の非経常的な損益がある場合は、これらを通算した上で法人税の課税所得金額から控除するか。 |
答 ある利益が経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個々に判定する。
また、非経常的な損益が複数ある場合には、これらを通算した上で、利益金額があれば、これを法人税の課税所得金額から控除する(評基通183(2))。
【理由】 固定資産売却益及び保険差益は、毎期、反復継続して発生する損益ではなく臨時に発生する損益であることから、評基通183(2)かっこ書きにおいて、非経常的な利益として例示されている。
ある利益が経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかの判定に当たっては、その利益が、評価会社の損益計算上、「経常利益」又は「特別利益」のいずれに計上されているか若しくは「固定資産売却益」等の勘定科目の名称で判断するのではなく、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個々に判定する必要がある。
また、評基通183(2)かっこ書きで法人税の課税所得金額から除くこととされている非経常的な利益の金額とは、課税時期の直前期末以前1年間に発生した非経常的な利益全体をいうのであるから、非経常的な損益を全て通算し、利益の金額があればこれを控除することとなる。
なお、非経常的な損益を通算した金額が負数となった場合は、法人税の課税所得金額から控除する非経常的な利益金額は0とする。
【関係法令通達】 評基通183(2)
3 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
| 評価対象地が容積率の異なる2つの地域にわたっている場合はどのように評価するか。 |
答 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、奥行価格補正(評基通15)の定めからがけ地等を有する宅地の評価(評基通20-4)までの定めによって評価した価額から、その価額に下記の算式によって計算した割合(以下「控除割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する(評基通20-5)。
ただし、1画地の宅地のうちに正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低い場合など、控除割合がマイナスになる場合等はこの評価方法は適用しない。
(算式)
控除割合(注1) 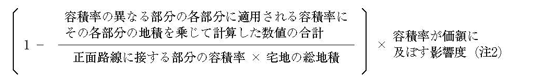 (注)1 小数点以下第3位未満を四捨五入する。 2 容積率が価額に及ぼす影響度
|
【理由】
建築基準法は、道路、公園、上下水道等の公共施設と建築物の規模との均衡を図り、その地域全体の環境を守るために、容積率(建築基準法第52条第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地に対する割合)の最高限度を定めており、この容積率は道路幅員などと同様に、土地の価額に影響を与えるものである。
通常、容積率は、一定の地域ごとに面的な広がりをもって指定されていることから、路線価は、各地域の容積率を反映した価額となっている。
一般的に、1街区のうち表道路に面する地域と裏道路に面する地域とで容積率が異なる場合には、路線価も異なるものとなる。
しかし、1画地の宅地が表道路に面する地域と裏道路に面する地域とで異なる容積率である場合、表道路に面する地域の容積率を反映して決定されている正面路線価を基とし、奥行価格補正などの画地調整を行って評価しただけでは、その宅地が、表道路に面する地域の容積率と異なる容積率の部分を有しているという個別的な要因が評価額に反映されないことになる。
そのため、容積率の異なる2以上の地域にわたる1画地の宅地について、容積率の相違(格差)による個別事情(影響度)を減額調整する評価方法が定められている。
【関係法令通達】 評基通20-5
4 市街化調整区域内にある雑種地の評価
| 次の土地は、どのように評価すればよいか。 <評価対象地の状況> 1 市街化調整区域内にある雑種地(間口:20m、奥行:20m、面積400㎡の整形地)である。 2 駐車場として利用されている。 3 市街化区域との境界付近に所在していることから、市街化の影響は強い。 4 店舗等の建築であれば可能であるが、郊外型店舗等の連たんはなく、また、宅地価格と同等の価格での取引は行われていない(しんしゃく割合は30%とするのが相当な地域に所在)。 5 評価対象地である雑種地の固定資産税評価額は、12,800,000円である。 6 市街化調整区域内所在の近傍標準宅地の固定資産税評価額は64,000円/㎡である。 7 平坦な土地であるため宅地造成費は整地費600円/㎡のみ必要である。 8 評価対象地付近の宅地は、倍率方式(評価倍率1.1倍)によって評価する。 |
答 評価額は、19,472,000円となる。
【理由】 1 評基通82では、「雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。」と規定している。
2 評基通82に基づく、具体的計算方法は、以下のとおりである。
(1)その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めにより評価した1平方メートル当たりの価額を求める。
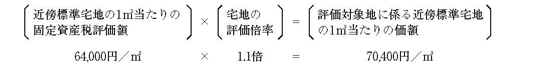
(2)その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
イ 位置、形状の差
雑種地が倍率地域に存する場合には、地区区分の定めが設けられていないので、宅地比準方式によって評価する市街地農地等の取扱いを準用し、普通住宅地区の画地調整率を参考として計算することができる(国税庁ホームページ・質疑応答事例「市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差」参照)。
ロ 法令上の制限
市街化調整区域内所在の近傍標準宅地の固定資産税評価額は、建物の敷地の用に供される土地として建物の建築が可能であることを前提に付されているものと考えられる。
一方、評価対象地は、店舗等の建築は可能であるものの、都市計画法により用途が限定されていることから、この土地利用上の制限を考慮して、▲30%のしんしゃくをするのが相当と考えられる。
ハ 宅地造成費
評価対象地は、整地費600円/㎡が必要な土地であるため、評価対象地の1平方メートル当たりの価額から同金額を控除する。
(3)以上を考慮すると、評価対象地の評価額は、以下の算式により計算した金額となる。
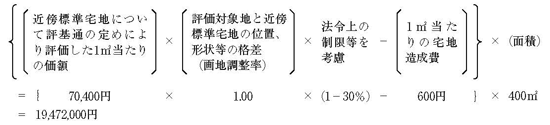
《計算順序の留意点》
宅地造成費の控除の順序については、画地調整率の適用及び法令上の制限のしんしゃくを行った後、控除することに留意する。
宅地造成費を控除した後、法令上の制限のしんしゃくを行うことは、宅地造成費に法令上の制限のしんしゃくを考慮した割合を乗じることとなり、当該宅地造成費相当額をしんしゃく割合で圧縮してしまうこととなるため相当ではない。
【関係法令通達】 評基通 7、82
5 財産評価基本通達第6項
| 財産評価基本通達第6項の定めの適用に当たっては、どのような点に留意すべきか。 |
答 評基通6は「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。
これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当」であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる「特別の事情」の有無による旨示されている。
この「特別の事情」の有無の判断に当たっては、次の≪参考≫に掲げる点などに着目しつつ、様々な事実関係を総合考慮することに留意する。
≪裁判例≫
(大阪高裁平成17年5月31日抜粋)
「評価基本通達により画一的に適用すべき評価方法を定めた以上は、当該贈与財産がその評価方法が定められた趣旨に合致する財産の範疇に含まれる財産であり、それに従った評価をすることが、時価の評価として合理性を有する限り、納税者間の公平及び納税者の信頼保護の見地から、原則として、すべての納税者との関係で評価基本通達に基づく評価を行う必要があり、特定の納税者あるいは特定の贈与財産についてのみ評価基本通達に定める方法以外の方法によって評価することは、たとえその方法による評価がそれ自体としては相続税法22条の定める時価として許容できる範囲内のものであったとしても、許されないものと解すべきである。
しかしながら、他方、評価基本通達に定められた評価方法によるべきであるとする趣旨が上記のようなものであることからすると、対象となる贈与財産が形式的には同通達の定める財産であっても、その実質が対象財産と評価することができないものであったり、上記の評価方法を画一的に適用するという形式的平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合など、上記評価方法によらないことが正当と是認される特別の事情がある場合には、別の合理的な評価方法によることが許されるものと解すべきである。このことは、評価基本通達6において、同通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされていることからも明らかである。」
(東京地裁平成17年11月10日抜粋)
「評価の目的は、あくまでも当該財産の客観的交換価値を確定することにあり、本件通達に定められた評価方法により財産を評価すべきであるとする趣旨が以上のとおりであることからすれば、本件通達に定められた評価方法を画一的に適用することによって、明らかに当該財産の容観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなり、そのため、実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び本件通達の趣旨に反することとなるなど、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方式によることが許されると解すべきであり、本件通達6においても、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められている。」
≪参考≫
① 評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
② 評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
③ 評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
④ 上記③の著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
【関係法令通達】 評基通 6
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























