解説記事2017年09月04日 【ニュース特集】 離婚に伴う財産分与に対する第二次納税義務の適用(2017年9月4日号・№705)
ニュース特集
不相当に過大であるか否かが分岐点に
離婚に伴う財産分与に対する第二次納税義務の適用
離婚に伴う財産分与をめぐり、滞納者である夫から財産分与として宅地を譲り受けた納税者に対する第二次納税義務の適用が問題となった税務訴訟で東京地裁(民事第51部)は平成29年6月27日、納税者に対する第二次納税義務の適用を認める判決を下した。裁判所は、納税者が財産分与として譲り受けた宅地の価額が財産分与相当額の6倍を超えることから、不相当に過大な財産分与として「著しく低い額の対価による譲渡」(徴収法39)に当たると判断した。一方で裁判所は、本件事実関係のもとでは納税者は譲渡時に滞納者の特殊関係者に該当しないと判断。第二次納税義務を負う範囲は「現存利益」の範囲に限られるとしたうえで、納付告知処分の納付限度額約1億900万円のうち、約7,700万円を上回る部分(約3,200万円)は違法であるとして同処分の一部を取り消している。
地裁、財産分与相当額の6倍を超える不動産譲渡は不相当に過大と判断
今回紹介する裁判事例は、夫(滞納者)から協議上の離婚に伴う財産分与を原因として宅地(約1,450㎡)の譲渡(以下「本件譲渡」)を受けた納税者が国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分の取り消しを求めたものである(図表1参照)。
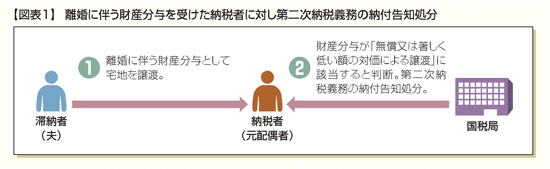
事実関係をみると、相続税など約2億円の国税を滞納していた滞納者は、離婚に伴う財産分与として、相続により取得した宅地(以下「本件不動産」)を納税者に譲り渡した。
国税局徴収職員は、滞納者に対する徴収手続きを進める一方で、納税者が第二次納税義務者に該当するか否かを検討。財産分与を受けた者に対しその財産分与が無償譲渡等(徴収法39条)に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分をした事例が過去になかったため、民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大である部分は無償譲渡等に該当するといえるか否か、同部分の金額を合理的に算定する方法などを検討したうえで、納税者が第二次納税義務者に該当すると判断して納付すべき限度額を約1億900万円とする第二次納税義務の納付告知処分を行った。この処分を不服とした納税者は審査請求を行ったものの、審判所がこれを棄却(平成25年7月4日)したことから、裁判所に対して納付告知処分の取り消しを求める訴訟を提起した。納税者は、本件譲渡は不相当に過大なものではなく無償譲渡等に該当しない旨を主張したほか、仮に第二次納税義務を負うとしても納税者は「特殊関係者」(徴収法39条)に該当しないことからその義務の限度は現存利益である約7,155万円である旨を主張した。
不相当に過大であれば無償譲渡等に該当 裁判所は、滞納者の財産につき行われた譲渡の対価の額が著しく低い額と認められるか否かは、取引の内容や性質等に照らして社会通念上その対価の額が通常の取引に比べて著しく低いものであるかどうかによって判断すべきとした。そして、離婚に伴う財産分与も国税徴収法39条所定の「譲渡」に該当するとしたうえで、財産分与が民法768条3項(家裁は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める旨を規定)の趣旨に反して不相当に過大である場合には、その財産分与の内容や性質等に照らし社会通念上その財産分与により消滅すべき分与義務に係る債務の額(この債務の消滅により得られる経済的利益がその分与を受けた財産に対する対価であるとみることができる)は通常の取引に比べて著しく低いものであると認めることができるとした。
3,000万円を超える部分は不相当に過大 次に裁判所は、本件譲渡が不相当に過大な財産分与といえるか否かを検討。本件不動産の本件譲渡(財産分与)時の時価は、国税局による評価額約1億8,800万円が相当であるとした。そして、財産分与として相当な額について「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」の3つの点から検討。清算的財産分与については、一般に共同形成財産の形成における夫婦の寄与度は平等とされるのが通例であるものの、本件離婚については納税者につき多くとも7割を超える寄与を認めるには至らないと指摘したうえで、多くとも約1,152万円を超えるものではないとした。また、扶養的財産分与については、納税者が一定の資産を有し相当額の清算的財産分与が見込まれ、養育すべき未成年の子がいないなどの事情に鑑みれば、最低生活費(生活保護支給基準)の3年分の合計額432万円を超えるものではないとした。さらに、慰謝料的財産分与については、29年に及ぶ婚姻生活の離婚につき滞納者に有責性が認められるとしても、極めて悪質性の高い有責行為の存在はうかがわれないことなどの事情に鑑みれば、相当な額は1,000万円を超えるものではないとした。以上の点を踏まえ裁判所は、これらの合計額が多くとも約2,584万円を超えるものではないことに照らせば、離婚に伴い滞納者が納税者に対して少なくとも3,000万円を超えて財産分与をすることは民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大なものとの評価を免れないと判断。納税者に対する財産分与としてその3,000万円の6倍を超える約1億8,800万円の本件不動産が譲渡されているから、少なくとも3,000万円を超える約1億5,800万円相当は不相当に過大な財産分与との評価は免れず、本件譲渡は「著しく低い額の対価による譲渡」(徴収法39条)に当たるとした。
納税者は滞納者の特殊関係者に該当せず、納付告知処分の一部を取消し
国税徴収法39条では、滞納者の親族その他の特殊関係者である者は無償譲渡等により受けた利益の限度において第二次納税義務を負うとしつつ、それ以外の者については無償譲渡等により受けた利益が現に存する限度(現存利益)において第二次納税義務を負う旨が規定されている。この点に関し国税局側は、納税者は本件譲渡時に滞納者の特殊関係者に該当すると主張する一方で、納税者側は特殊関係者には該当しないと主張していた。
これに対し裁判所は、納税者が本件譲渡時に滞納者の「特殊関係者」であったか否かの判定については、その譲渡に係る「処分の時」すなわち譲渡の対象とされた財産の移転の原因行為の成立時における上記の関係の有無によって判断すべきとした。そして、著しく低額の譲渡の対象とされた財産の移転の原因行為が財産分与である場合におけるその成立時の認定に当たっては、訴訟上の和解又は調停等において離婚と財産分与の協議が一体として成立した場合や財産分与協議書等の合意書面が作成されておらず諸般の事情から離婚の届出と時期を同じくして財産分与の確定的な協議の成立に至ったと認められる場合など、事案の具体的な事実関係の下における諸事情等に照らし、離婚の成立時において財産分与についても併せて確定的な協議が成立したものと認められる場合には、その離婚の成立時をもってその譲渡に係る「処分の時」と認めるのが相当であるとした。
本件については、離婚の届出と引換えに所有権移転登記の経由が確保されるように、離婚の届出に先立ち、離婚の届出と司法書士に対する登記申請の委任状が離婚の届出(平成12年5月26日)の3日前である5月23日付けで作成され、登記申請と引換えに離婚の届出がされたものということができ、5月30日になされた登記申請に際して本件譲渡に係る登記原因証書(旧不動産登記法)は提出されず、財産分与協議書等の合意書面は作成されていなかったことなどを認定。これらの事情などを踏まえ裁判所は、本件においては財産分与協議書等の合意書面が作成されておらず諸般の事情から離婚の届出と時期を同じくして財産分与の確定的な協議の成立に至ったものと認めるのが相当であるとした(図表2参照)。そのうえで裁判所は、本件においては離婚の成立時に本件譲渡に係る財産分与も併せて確定的な成立に至ったものと認められることから、離婚の成立時をもって本件譲渡に係る「処分の時」と認めるのが相当であると判断。本件譲渡に係る「処分の時」である離婚の成立時において納税者は滞納者の配偶者その他の親族ではなく、国税徴収法39条に現定する「特殊関係者」に該当しないから、納税者が第二次納税義務を負う範囲は「現存利益」の範囲に限られるとした。
納付告知額のうち約3,200万円を取消し そして「現存利益」について裁判所は、納税者が納付告知処分時に所有していた財産の合計約1億1,300万円から、本件不動産の譲り受けの対価として納税者が有していた財産分与に係る債権(不相当に過大とはいえない部分)を消滅させたことにより失った経済的利益3,000万円と納税者が負担した不動産取得税などを控除した約7,700万円を限度として第二次納税義務を負うと判断したうえで、納付告知処分の納付限度額約1億900万円のうち、約7,700万円を上回る部分は違法であるとして同処分の一部を取り消した(なお一部敗訴を不服とした納税者側は控訴を提起している)。
不相当に過大であるか否かが分岐点に
離婚に伴う財産分与に対する第二次納税義務の適用
離婚に伴う財産分与をめぐり、滞納者である夫から財産分与として宅地を譲り受けた納税者に対する第二次納税義務の適用が問題となった税務訴訟で東京地裁(民事第51部)は平成29年6月27日、納税者に対する第二次納税義務の適用を認める判決を下した。裁判所は、納税者が財産分与として譲り受けた宅地の価額が財産分与相当額の6倍を超えることから、不相当に過大な財産分与として「著しく低い額の対価による譲渡」(徴収法39)に当たると判断した。一方で裁判所は、本件事実関係のもとでは納税者は譲渡時に滞納者の特殊関係者に該当しないと判断。第二次納税義務を負う範囲は「現存利益」の範囲に限られるとしたうえで、納付告知処分の納付限度額約1億900万円のうち、約7,700万円を上回る部分(約3,200万円)は違法であるとして同処分の一部を取り消している。
地裁、財産分与相当額の6倍を超える不動産譲渡は不相当に過大と判断
今回紹介する裁判事例は、夫(滞納者)から協議上の離婚に伴う財産分与を原因として宅地(約1,450㎡)の譲渡(以下「本件譲渡」)を受けた納税者が国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分の取り消しを求めたものである(図表1参照)。
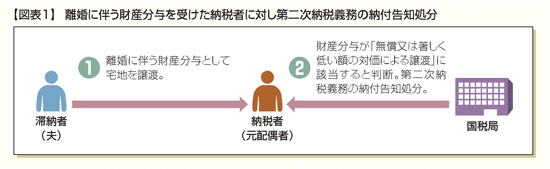
事実関係をみると、相続税など約2億円の国税を滞納していた滞納者は、離婚に伴う財産分与として、相続により取得した宅地(以下「本件不動産」)を納税者に譲り渡した。
国税局徴収職員は、滞納者に対する徴収手続きを進める一方で、納税者が第二次納税義務者に該当するか否かを検討。財産分与を受けた者に対しその財産分与が無償譲渡等(徴収法39条)に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分をした事例が過去になかったため、民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大である部分は無償譲渡等に該当するといえるか否か、同部分の金額を合理的に算定する方法などを検討したうえで、納税者が第二次納税義務者に該当すると判断して納付すべき限度額を約1億900万円とする第二次納税義務の納付告知処分を行った。この処分を不服とした納税者は審査請求を行ったものの、審判所がこれを棄却(平成25年7月4日)したことから、裁判所に対して納付告知処分の取り消しを求める訴訟を提起した。納税者は、本件譲渡は不相当に過大なものではなく無償譲渡等に該当しない旨を主張したほか、仮に第二次納税義務を負うとしても納税者は「特殊関係者」(徴収法39条)に該当しないことからその義務の限度は現存利益である約7,155万円である旨を主張した。
| >国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) |
| 徴収法39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償または著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、または義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨を規定している。 |
不相当に過大であれば無償譲渡等に該当 裁判所は、滞納者の財産につき行われた譲渡の対価の額が著しく低い額と認められるか否かは、取引の内容や性質等に照らして社会通念上その対価の額が通常の取引に比べて著しく低いものであるかどうかによって判断すべきとした。そして、離婚に伴う財産分与も国税徴収法39条所定の「譲渡」に該当するとしたうえで、財産分与が民法768条3項(家裁は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める旨を規定)の趣旨に反して不相当に過大である場合には、その財産分与の内容や性質等に照らし社会通念上その財産分与により消滅すべき分与義務に係る債務の額(この債務の消滅により得られる経済的利益がその分与を受けた財産に対する対価であるとみることができる)は通常の取引に比べて著しく低いものであると認めることができるとした。
3,000万円を超える部分は不相当に過大 次に裁判所は、本件譲渡が不相当に過大な財産分与といえるか否かを検討。本件不動産の本件譲渡(財産分与)時の時価は、国税局による評価額約1億8,800万円が相当であるとした。そして、財産分与として相当な額について「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」の3つの点から検討。清算的財産分与については、一般に共同形成財産の形成における夫婦の寄与度は平等とされるのが通例であるものの、本件離婚については納税者につき多くとも7割を超える寄与を認めるには至らないと指摘したうえで、多くとも約1,152万円を超えるものではないとした。また、扶養的財産分与については、納税者が一定の資産を有し相当額の清算的財産分与が見込まれ、養育すべき未成年の子がいないなどの事情に鑑みれば、最低生活費(生活保護支給基準)の3年分の合計額432万円を超えるものではないとした。さらに、慰謝料的財産分与については、29年に及ぶ婚姻生活の離婚につき滞納者に有責性が認められるとしても、極めて悪質性の高い有責行為の存在はうかがわれないことなどの事情に鑑みれば、相当な額は1,000万円を超えるものではないとした。以上の点を踏まえ裁判所は、これらの合計額が多くとも約2,584万円を超えるものではないことに照らせば、離婚に伴い滞納者が納税者に対して少なくとも3,000万円を超えて財産分与をすることは民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大なものとの評価を免れないと判断。納税者に対する財産分与としてその3,000万円の6倍を超える約1億8,800万円の本件不動産が譲渡されているから、少なくとも3,000万円を超える約1億5,800万円相当は不相当に過大な財産分与との評価は免れず、本件譲渡は「著しく低い額の対価による譲渡」(徴収法39条)に当たるとした。
納税者は滞納者の特殊関係者に該当せず、納付告知処分の一部を取消し
国税徴収法39条では、滞納者の親族その他の特殊関係者である者は無償譲渡等により受けた利益の限度において第二次納税義務を負うとしつつ、それ以外の者については無償譲渡等により受けた利益が現に存する限度(現存利益)において第二次納税義務を負う旨が規定されている。この点に関し国税局側は、納税者は本件譲渡時に滞納者の特殊関係者に該当すると主張する一方で、納税者側は特殊関係者には該当しないと主張していた。
これに対し裁判所は、納税者が本件譲渡時に滞納者の「特殊関係者」であったか否かの判定については、その譲渡に係る「処分の時」すなわち譲渡の対象とされた財産の移転の原因行為の成立時における上記の関係の有無によって判断すべきとした。そして、著しく低額の譲渡の対象とされた財産の移転の原因行為が財産分与である場合におけるその成立時の認定に当たっては、訴訟上の和解又は調停等において離婚と財産分与の協議が一体として成立した場合や財産分与協議書等の合意書面が作成されておらず諸般の事情から離婚の届出と時期を同じくして財産分与の確定的な協議の成立に至ったと認められる場合など、事案の具体的な事実関係の下における諸事情等に照らし、離婚の成立時において財産分与についても併せて確定的な協議が成立したものと認められる場合には、その離婚の成立時をもってその譲渡に係る「処分の時」と認めるのが相当であるとした。
本件については、離婚の届出と引換えに所有権移転登記の経由が確保されるように、離婚の届出に先立ち、離婚の届出と司法書士に対する登記申請の委任状が離婚の届出(平成12年5月26日)の3日前である5月23日付けで作成され、登記申請と引換えに離婚の届出がされたものということができ、5月30日になされた登記申請に際して本件譲渡に係る登記原因証書(旧不動産登記法)は提出されず、財産分与協議書等の合意書面は作成されていなかったことなどを認定。これらの事情などを踏まえ裁判所は、本件においては財産分与協議書等の合意書面が作成されておらず諸般の事情から離婚の届出と時期を同じくして財産分与の確定的な協議の成立に至ったものと認めるのが相当であるとした(図表2参照)。そのうえで裁判所は、本件においては離婚の成立時に本件譲渡に係る財産分与も併せて確定的な成立に至ったものと認められることから、離婚の成立時をもって本件譲渡に係る「処分の時」と認めるのが相当であると判断。本件譲渡に係る「処分の時」である離婚の成立時において納税者は滞納者の配偶者その他の親族ではなく、国税徴収法39条に現定する「特殊関係者」に該当しないから、納税者が第二次納税義務を負う範囲は「現存利益」の範囲に限られるとした。
| 【図表2】現行の不動産登記法では、財産分与に基づく移転登記の際には財産分与協議書等が必要に |
| 裁判所は、現行の不動産登記法の下では、財産分与に基づく所有権移転登記の申請に際して登記原因証明情報の提供が必須のものとされる(同法61条)ため、確定的な協議の成立を内容とする財産分与協議書等の登記原因証明情報の作成を経ないで登記申請を行うことはできないのに対し、旧不動産登記法(平成16年改正前)の下では、申請書の副本のみを提出することで足りることとされていたことから財産分与協議書等の作成を要するものではなく、本件において実際に離婚の届出に至る前に滞納者が翻意して司法書士に対する登記申請の委任を解除した場合には、もはや財産分与に基づく所有権移転登記をすることができなくなる状況にあったと指摘。この点などを踏まえ、登記申請の委任状の作成日の日付(5月23日)の時点で離婚に伴う財産分与の確定的な協議の成立にまで至ったとは直ちに認め難いとした。なお、裁判所は、現行の不動産登記法の下では、確定的な協議の成立を内容とする財産分与協議書等の登記原因証明情報が作成されるため、本件のような事態が生ずることは想定されないとしている。 |
納付告知額のうち約3,200万円を取消し そして「現存利益」について裁判所は、納税者が納付告知処分時に所有していた財産の合計約1億1,300万円から、本件不動産の譲り受けの対価として納税者が有していた財産分与に係る債権(不相当に過大とはいえない部分)を消滅させたことにより失った経済的利益3,000万円と納税者が負担した不動産取得税などを控除した約7,700万円を限度として第二次納税義務を負うと判断したうえで、納付告知処分の納付限度額約1億900万円のうち、約7,700万円を上回る部分は違法であるとして同処分の一部を取り消した(なお一部敗訴を不服とした納税者側は控訴を提起している)。
| Column | 離婚成立前に財産分与の確定的な協議が成立していれば「特殊関係者」に該当 |
| 裁判のなかで納税者側は、一般に財産分与の合意は離婚の成立を停止条件とする合意であり、離婚の成立時に財産分与の当事者はもはや夫婦ではないから、財産分与を受けた者は財産分与者(滞納者)の「親族その他の特殊関係者」(徴収法39条)とはならないと主張していた。これに対し裁判所は、徴収法39条の趣旨に照らせば、無償譲渡等に係る処分の時であるその譲渡の原因とされた財産の移転の原因行為の成立時(例えば、事案の具体的な事実関係の下で離婚の成立前に財産分与の確定的な協議の成立に至ったと認められる場合におけるその成立時)に国税徴収法施行令13条1項各号に掲げる者に該当する以上、「特殊関係者」(徴収法39条)に当たると解するのが相当であるとしたうえで、納税者の主張は一般論としては採用できないと判断している。 | |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















