解説記事2017年10月23日 【特集インタビュー】 BEPSプロジェクトの現在地と今後の課題(2017年10月23日号・№712)
特集インタビュー
~OECD サンタマン局長、BIAC モリス委員長に聞く~
BEPSプロジェクトの現在地と今後の課題
BEPS最終報告書の公表から2年が経過し、国別報告事項の導入、CFC税制の大幅改正など国内法制化が進みつつある。その一方で、日本企業が懸念を抱く評価困難な無形資産、利益分割法、PE帰属利得といった重要論点に関するOECDのガイダンスは策定途上であるなど、BEPSプロジェクトにおいて取り組むべき課題はまだ多く残されている。また、BEPSリスクの低い多国籍企業に課税上の“保証”を与えるICAP(International Compliance Assurance Programme)や、国家間の課税権の配分ルールを曖昧なものとしかねないデジタル・エコノミー(電子経済)への対応など新たな重要テーマも浮上しており、BEPSプロジェクトは次のステージに足を踏み入れようとしている。
こうした中、BEPSプロジェクトのキーパーソンであるOECD(経済協力開発機構)租税政策税務行政センター(CTPA)のパスカル・サンタマン局長、Business at OECD(BIAC:OECD経済産業諮問委員会)のウイリアム・モリス税制・財政委員長が経団連との国際課税に関する会合に参加するため今月上旬、来日した。政府機関、民間と立ち位置の異なるお2人に、BEPSプロジェクトの現在地、そして今後の課題について話を聞いた。
サンタマン局長
税務当局からも期待を集めるICAP
本誌:OECDがBEPS最終報告書を公表してから2年が経ちました。まずこれまでの成果について総括をお願いいたします。
サンタマン:OECDは過去2年間、BEPSプロジェクトの実施に注力してきました。なるべく多くの国にこのプロジェクトの原則を受け入れ、コミットしてもらうことに集中してきた結果、現在は102か国が平等な立場でBEPSに関する包摂的枠組み(inclusive framework)に参加しています。多くの国をカバーできたことで、地理的な範囲の広さのみならず、「深さ」の面でもプロジェクトは成功していると思っています。また、多国間協定には現在、70か国以上が署名しています。1,200以上の租税条約を修正することで、条約漁り(treaty shopping)を防止できるようになりました。
本誌:最近の取り組みについて教えてください。
サンタマン:まず、国別報告書(CbCR)に関する作業を進めています。日本からの要請に基づき、公開しないことが前提です。有害税制への対抗、税の安定性(tax certainty)、相互協議の効果的実施などについても作業が進んでいます。このうち相互協議の効果的実施(行動14)については既に相互審査(peer review)を開始しています。
そしてこれらに加え、新たなイニシアティブの一つとして、税の安定性改善のため、ICAP(International Compliance Assurance Programme)に取り組んでいます。ICAPとは納税者に税の安定性を提供する革新的な手法であり、自主参加をベースにパイロット・プロジェクトとして開始するものです。先週、オスロで開催されたOECD税務長官会議(日本を含む48カ国から税務長官が参加)でプロジェクトが正式に発足しました。このイニシアティブの下では、納税者が自発的に多数の税務当局と討議を行い、税務リスクが評価されることになります。その結果、低リスクと評価されれば、納税者に一種の「保証」が与えられます。すなわち、調査をしない、または限定的な調査にするという保証です。このイニシアティブは、税務行政執行共助条約に依拠するものであり、税務紛争を回避するための我々の取り組みの良い事例となるでしょう。ここで強調したいことは、ICAPは、企業にとって税の安定性を改善し、紛争の回避につながるものとして、各国の税務当局からも大きな期待を集めているということです。現在、10社以上の企業がこのプログラムに参加したいと申し出ており、現在はその中から参加企業を選定するプロセスに入っています。

「ALES」はグローバルな合意に向けたロードマップに賛同しないことへの警告
本誌:今年7月にハンブルグで開催されたG20サミットでも話題になった電子経済についてはいかがでしょうか。
サンタマン:ご承知のように、電子経済への対応はBEPS行動計画1に含まれています。最終報告書には、4つの重要な結論が含まれています。一つは、電子経済そのものよりも「経済のデジタル化」に注目すべきだということです。二番目として、経済のデジタル化によってBEPSの状況そのものは悪化する可能性があるということです。ただし、TECH企業などによるBEPSの活用は、BEPS行動計画のそれぞれの項目で対応し、抑えることができると考えています。三番目として、電子的なサービスを提供する際には、その目的地でVATをいかに確保するかというVATのルールを明確化する必要があるということです。この点については、既に日本を含む100か国がルールを確立し、実施しています。四番目として、直接税における課題を認識する必要があるという点です。TECH企業は、物理的なプレゼンスを持っていない市場においても取引をし、そこから収益を上げることができます。それに対して従来の国際租税体制は十分に適正な対応ができていなかったということを認めることが重要です。様々なオプションを検討する中で、その一つに平衡税(equalisation levy)がありますが、多くの国はまだこれに合意することができない状況であるため、2020年までを目途に状況のモニタリングを続けるということで現時点では合意しています。
このような背景の下、ハンブルグで開催されたG20サミットにおいて、2018年4月までにこの分野で中間報告を作成するようOECDは指示を受けています。我々は現在この報告書の作成を進めているところです。
本誌:今夏にリオデジャネイロで開催されたIFA(International Fiscal Association=国際租税協会)でサンタマン局長は、電子経済問題に対処し得る方法の一つとして、Alternative Levy on Electronic Sales(ALES=代替的電子売上税)に言及したと伝えられています。この点について、OECDではどのような議論がされているのでしょうか。
サンタマン:まずOECDの立場を明確にしておきたいと思いますが、OECDとしてはあくまでも「グローバルなソリューション」が必要だと考えており、いかなる状況においても、場当たり的な対応(quick fix)を我々が提案したり支持したりすることは決してありません。しかし現在は、複数の国が必ずしも忍耐強く作業を待っていない状況であり、もし近い将来においてこの問題に対応するグローバルなソリューションが出て来る見通しがないのであれば、それぞれの国が独自に"quick fix"をとってしまうという可能性も出てきています。特にフランスをはじめとする10か国程度のヨーロッパ諸国は、もし近い将来OECDで合意が達成できないのであれば、例えば売上高をベースにした税制(turnover tax)なども検討すると言っています。こうした動きに半分冗談で私が勝手に名前を付けたのが、リオでの会合で申し上げた"alternative levy on electronic sales(ALES)"(代替的電子売上税)です。もしグローバルな合意に向けたロードマップに賛同できないのであれば、このような場当たり的な対応-これは決して良いものではありませんが-が採用されてしまうこともあり得るという警告の意味も込めて申し上げました。我々は特に米国に対して警告を発しております。
利益分割法のガイダンスはイデオロギーではなく“実務的・実践的”なアプローチで
本誌:日本の与党は、近い将来所得相応性基準の導入を目指していますが、今年5月に公表された「評価困難な無形資産(Hard-to-Value Intangibles)」に関するディスカッション・ドラフトに対し、OECDにはどのようなコメントが寄せられているのでしょうか。また、所得相応性基準の実施ガイダンスはいつ確定するのでしょうか。
サンタマン:所得相応性基準はBEPS最終報告書における提言の一部であり、米国でも実施されているように、無形資産を用いたBEPSを防止するための一つの手段になり得ると考えています。具体的な期日をお伝えすることはできませんが、現在、評価困難な無形資産に関する実施ガイダンスの取りまとめは最終段階に入っています。
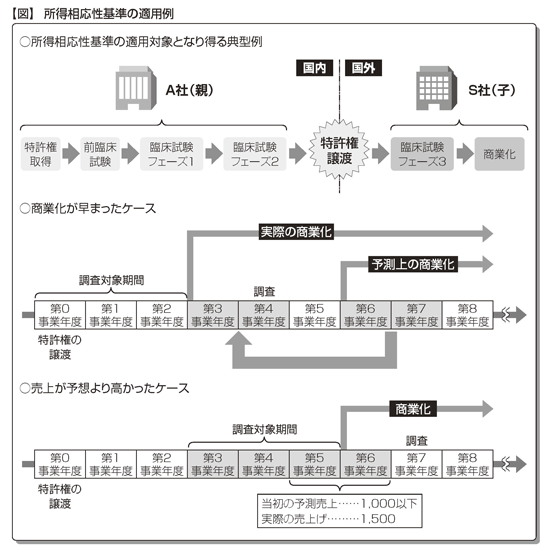
本誌:利益分割法(PS法)も日本企業の関心事項の一つです。日本企業は利益分割法(PS法)が特に新興国によって安易に使われることに懸念を持っています。この点についてはどうお考えでしょうか。また、この分野ではどのようなガイダンスを出したいとお考えですか。
サンタマン:利益分割法を用いる国が増えているというのは事実であり、おっしゃるような懸念が存在することも承知していますが、利益分割法は適切な枠組みの下で、原則に沿った形で活用されるのであれば、効率の良い手法の一つだとは思います。我々はこの利益分割法がより良く活用されるためのガイダンスを出したいと考えており、その作成作業を現在進めているところです。それは困難な作業ではありますが、ガイダンスの取りまとめにあたっては、イデオロギーベースではなく、あくまで実務的・実践的なアプローチが必要だと思っています。
PE帰属利得、金融取引に関する移転価格税制のガイダンスは「近い将来」公表
本誌:6月に公表されたPE帰属利得に関するディスカッション・ドラフトに対しては、その中で述べられていた「簡便性向上のための執行アプローチ」の重要性を指摘するコメントが数多く寄せられているのではないかと思います。PE帰属利得についてより明確かつ詳細なガイダンスを出す予定はありますか。
サンタマン:こちらも今作業を進めている状況です。BEPS行動7(PE認定の人為的回避の防止)に関する最終報告書ではPEに対する租税回避ルールの強化を求めていますが、我々としてはその中でも特にコミッショネア契約(問屋契約)に注目し、これに対応しなければならないと思っています。従来のPEのルールはアップデートが十分にされてこなかったため、現在行っているアップデート作業においてはかなり激しいディスカッションが行われています。決して容易な作業ではありませんが、この分野のガイダンスは相対的に近い将来に出していきたいと考えています。
本誌:最後に、金融取引に関する移転価格税制について、現在どのような作業が行われているのか教えてください。
サンタマン:行動4(利子控除制限)の残された課題であり、既にガイダンスの策定作業を開始しています。次回のOECD租税委員会WP6(第6作業部会)の開催後、すなわち年末あたりにディスカッション・ドラフトが公開されることになるのではないかと思います。そのガイダンスはキャプティブ保険(自社あるいは自社を含む企業グループのリスクを専門に引き受ける保険会社)など特に保険の問題に対応するものです。現在でも、資本負債比率をどのような位置付けの問題とするか、すなわち、これは移転価格の問題なのか、あるいは移転価格の問題とは全く関係のない別の問題としてとらえるべきなのかということに関して、各国の間に意見の食い違いが残っていますが、パブリックコメントを得るためにも、近い将来ディスカッション・ドラフトを公表する予定です。
モリス税制・財政委員長
CbCRの簡素化、利子控除制限の緩和で大きな役割
本誌:最初に、この数年間BIAC(OECD経済産業諮問委員会)がBEPSプロジェクトで果たしてきた役割、また、どのようなプロジェクトで何を達成してきたのかについてお聞かせください。
モリス:我々はグループです。すなわちBIACは日本の経団連を含む多くの国の産業団体とOECDを橋渡しするチャネルとしての役割を果たしてきました。数字で示せば、BIACは2800名の税の専門家にアクセスし、これまでOECDが出した25本のディスカッション・ドラフトのうち23本についてレスポンスを出しています。その過程では41か国からコメントを得ており、BIACメンバーから200の書面意見を得ました。また、12回の公聴会(パブリック・コンサルテーション)にも200人のBIACのメンバーが出席しています。
これまでOECDと討議してきた内容を振り返ると、政治色が濃いテーマも、また国と国との間で紛争になったテーマもありましたが、その中でも我々は影響力を行使してきました。二つ例を挙げると、第一には国別報告書(CbCR)について、各国の税の専門家のみならず、税以外の分野の人達の意見を聞くことで、OECD及び各国の関係者に対して、よりシンプルに、そして実際のビジネスに沿ったより適正な形にするように働きかけました。その結果として、元々考えられていたものよりもだいぶシンプルなものになったのは確かだと思います。もう一つはBEPS行動4(利子控除制限)に関するプロジェクトです。元々のOECDの提案では、企業の純支払利子が当該企業のEBITDAに「10%」を乗じた金額を超える場合、その超える部分に相当する金額を損金不算入とするものでしたが、BIACがかなり幅広い企業へのリサーチに基づき働きかけた結果、最終報告書でも10~30%という回廊(幅)が認められることになりました。
本誌:BIACは現在、国際租税問題においてどこに優先順位を置いているのでしょうか。
モリス:3つの分野に重点を置いています。第一に、BEPSに関するこれまでのOECDの勧告は完全に詳細なところまでは詰められていなかったので、今後は詳細なところまでしっかり分かるような勧告内容を確保するということです。その例として、利益分割法の問題とPE帰属利得の問題が挙げられます。第二に、勧告の内容が世界各地でいかに実施されているかという点です。特に、国によって解釈が異なることなく、どの国においても同じような形で実施されていることが重要だと考えています。なぜなら、クロスボーダーの貿易や投資を行う際、国によって勧告内容の解釈が違うと、税負担にかなり大きな差異が出てきてしまうからです。第三に、将来の方向性です。その中には電子経済の問題もあります(詳細は後述)。
日本もICAPに参加を
本誌:新たな取り組みであるICAPについてはいかがでしょうか。日本企業はパイロットプログラムに参加しているのでしょうか。
モリス:私は幸いにもOECDや加盟国がディスカッションをし始めた時からICAPに関わることができ、最初の段階からその内容を支持してきました。というのも、ICAPによって問題を早期に、しかも一国または二国間ベースではなくより広範囲に解決するチャンスが出て来るからです。今後BEPSを実行するにあたっては必ず紛争や意見の食い違いが出て来るはずなので、なおさら紛争を予防する、すなわち問題や食い違いがあまり深刻になる前に早い段階で対応していくということが重要だと思っています。
私は先週ノルウェーのオスロで開催されたOECD税務長官会議にも参加したのですが、各国の国税長官等によるパネルディスカッションで各国がこの問題に真摯に取り組んでいることが伝わり、強い感銘を受けました。
パイロットプログラムに参加できる企業は本社所在国がパイロットプログラムに参加していなければならないということと、一国一社と参加企業が限られているため、現時点では日本企業はパイロットプログラムには参加していないというのが私の理解ですが、日本が国として将来このプログラムに参加することを本当に強く希望しています。そうすれば、日本企業も参加できると思いますので。
今後10年間はデジタル経済が国際租税における議論を支配する
本誌:先ほどお話が出た電子経済について聞かせてください。重点分野の一つのとのことですが、その理由は何でしょうか。
モリス:少なくとも今後の10年間を見た場合、国際租税問題においては電子経済が支配的なテーマになるのではないかと思うほどの重要分野であると私自身は考えています。現在、米国や中国、日本などのTECH企業は確かに経済に影響を及ぼしていますが、その度合いは将来及ぼすであろう非常に大きな影響と比較すると僅かなものであると思います。例えば多くのサービスがクラウドになったり、AIを活用した自動操縦の実現により道路の整備や管理も現在とは全く違ってきたりということになると、国の税源ベースそのものがどういうものであるかということについて、非常に大きな影響が出て来ることになります。本当に大きな問題になるはずです。
ただ、現在のBEPSプロジェクトにおける討議内容を見ると、将来の問題よりも「過去どうであったか」という既に過ぎ去った状況がベースとなっている傾向があると思います。例えばいまだにイー・コマースに注目していることもそうです。しかも、税制の構造そのものについての議論の多くは、BEPSの前の条件をベースに行われています。いくつかのヨーロッパの国が提案している取引高や売上高をベースにした税制(turnover tax)も古い前提に基づいた議論だと思います。経済性もあまり良くありません。例えば売上高が大きく利益率が低い企業や、控除の対象となる多額の研究開発費を支出している企業などにとっては、あまり都合の良い税制ではありません。立ち上げに経費がかかる新規事業にとっても同様です。
我々は税制を設計する際には、「過去どうであったか」ではなく、「今後どのような方向性が見込まれているのか」あるいは「将来の成長をどのように促進できるのか」ということを頭に入れる必要があると思います。デジタル経済の特性そのものを見ていかなければなりません。現在は、明らかに国によって異なる国益が念頭に置かれています。将来どのように動いていくのか、その方向性について本当に真剣に詳細まで詰めた多国間的な同意が必要だと思います。経済成長にとって、一国単位で動く又は決めるということは決して好ましいことではありません。
デジタル経済は決して限定された特定のセクターにとどまる話ではありません。ほとんどすべての企業が何らかの形でデジタル経済に関わっていますし、将来はさらにその傾向が顕著になるはずです。これは本当に重要なテーマであり、ご承知のようにOECDが2018年4月までに中間報告を出す予定にはなっていますが、いくつかのヨーロッパ諸国は、もっと早いスピードで、独自の動きで前進したいと言っています。しかし、我々としては、本当に重要な分野であるだけに、真剣に、そして全ての側面から見て、全ての当事国が納得できるソリューションが最終的に必要だと思っており、各国をその方向に向けられるように我々も役割を果たしていきたいと考えています。
繰り返しになりますが、デジタル経済は本当に重要なテーマであり、これから10年間、税制についての議論はこのテーマが支配するほど、国際租税上、重要なテーマになると思いますので、十分に時間を確保して、正しい方向付けをした上で、適切な制度を設けるということが極めて重要になります。

所得相応性基準ガイダンスは現段階では不明瞭
本誌:最近BIACでは、評価困難な無形資産に関するOECDのディスカッション・ドラフトついて懸念を表明されています。具体的に聞かせてください。
モリス:評価困難な無形資産については2つの懸念があります。まず、評価困難な無形資産の定義が非常に広くなっているということです。評価困難な無形資産の定義がこれだけ広くなると、無形資産を移転する際にはほとんどが「評価困難な無形資産」の分類に入れられてしまいます。その結果、今後紛争が発生する可能性が高まることになります。定義が広いがゆえに、例えば知的財産の一部である無形資産をどのように切り分けるのかなど、本来存在しなくてもいいような問題まで出てくることになりかねません。
もう一つ、有用と言えるためには現時点では不明瞭と思われるのが事前のプライシングと事後のプライシングの関係、すなわち、どの段階を評価のベースとするべきかという問題です。これには、その事象が起こっている時に評価する、あるいは、後になって以前起こったことを振り返って評価する、という2つのアプローチがあります。例えばある取引が1年目に起こったとします。そして、その取引について10年後に税務調査があったとすると、1年~10年の間に起こったことというのは、1年目の取引や行動が適切だったのかを判断する上で一つの要素になるという考え方があります。ただ、それ(1~10年目に起きたこと)は一つの要素であって、決定的な要素であってはならないと思います。というのも、最初に予測していた状況とは全く違う状況で物事が展開していくということは往々にしてあるからです。したがって、10年目にこういう結果になっているということをベースに、そこから結論を導き出して、1年目の取引や行動が適切であったのかどうかを判断すべきではないと思います。すなわち、第三者が1年目にそのような判断・決定をしたのであれば、それはそれで尊重しなければならないということです。もし、10年目に結果として出てきた内容に基づき、そこから逆算して1年目のことを決定できるのであれば、1年目の行動や取引そのものを測定したり判断する意味が全くなくなってしまいます。繰り返しになりますが、10年目の出来事、状況というのは1年目に起こった取引を評価する一つのエビデンス、一つの評価要素として取り入れるべきだとは思いますが、唯一のものであってはならないということです。10年目に予想もしていなかったような(悪い)結果になったからといって、納税者に対し「では、1年目の取引においてこれだけの損失を計上してよい」とは言わないはずです。
利益分割法のガイダンスでは、「利益分割法=デフォルト方法」でないことを明記すべき
本誌:利益分割法についてはいかがでしょうか。
モリス:我々は今後、確実に、より多く利益分割法の適用を目論む国を目にすることになるでしょう。これまでのOECDガイダンスの内容はおおむね歓迎できるものです。ただし、現在のディスカッション・ドラフトについて懸念するのは、利益分割法は限定的な状況でのみ使うべきという合意があると考えられる一方、恐らくではありますが、利益分割法が最適手法であるという含意があるようにも読み取れます。例えば第三者との取引において利益分割的なプライシングの手法をとるケースは確かにあると思われ、そのような場合には関連者間でも利益分割法を使えるという考え方が出てくる傾向がありますが、実際には第三者の企業間でも利益分割法を使わない事例も多くあります。したがって、これから出されるOECDのガイダンスでは、利益分割法をデフォルトの方法として位置付けるべきではありませんし、この点を文言としてガイダンスに記載するべきだと思います。
従属代理人PEをめぐる状況改善のためには“簡素化された執行アプローチ”も検討を
本誌:PE帰属利得のガイダンスに期待することはどのようなことでしょうか。
モリス:我々はこの分野についてもOECDに是非ガイダンスを出して欲しいと思っていますが、各国が判断しなければならない事柄も多いため、OECDができることにも限界があるという点も認めなければなりません。
一方で、従属代理人PEの閾値を下げればPEの数は増えますので、それに対応する策を考えていかなければならないと思います。ご存知のとおり、新しいルールの下でのPEの多くは利益がゼロかごくわずかしか計上されません。しかしながら、PEとして登録しない、特にVATの分野でPE登録せず報告提出を怠るということは深刻な問題を生みます。したがって、この問題についてはかなり真剣に、また発想を自由にして色々な可能性を検討するべきだと思います。最近、ある事例でイタリアの税務当局が、世界的に売上を計上している企業グループの中で一定の割合を占める売上を有する企業は、VATについてイタリアの税務当局にアプローチして相談できるというルールを示しました。これにより、企業はイタリアの税務当局に対し、従属代理人PEに該当するのかどうかや所得の帰属などについて、税務当局に相談することができようになりました。それをすれば、別途PEの登録やVATのためのPEレポートの提出は必要なくなります。今後はこのような柔軟な発想、考え方がもっと必要になってくると思います。
本誌:日本企業では、OECDがPE帰属利得においてダブル・タックスペイヤー・アプローチを前提としていることを懸念する声も聞かれます。
モリス:もう10年以上前にこのルールができましたが、このようなルールができたために、非常に複雑な状況になってきてしまっています。実務的に考えると、これらのルールを今解消したり、なくすことは非常に難しいと思います。イタリアの例のように、より簡素化された執行アプローチを、発想を自由にして提示することができれば、状況は改善されると思っています。
本件は租税条約の9条(特殊関連企業)と7条(事業所得)の適用にもかかわってきますが、残念ながら、ディスカッション・ドラフトではその2つの間の優先順位や、識別などは必ずもはっきりしていないので、今後その点についてはより明確になることを期待しています。
~OECD サンタマン局長、BIAC モリス委員長に聞く~
BEPSプロジェクトの現在地と今後の課題
BEPS最終報告書の公表から2年が経過し、国別報告事項の導入、CFC税制の大幅改正など国内法制化が進みつつある。その一方で、日本企業が懸念を抱く評価困難な無形資産、利益分割法、PE帰属利得といった重要論点に関するOECDのガイダンスは策定途上であるなど、BEPSプロジェクトにおいて取り組むべき課題はまだ多く残されている。また、BEPSリスクの低い多国籍企業に課税上の“保証”を与えるICAP(International Compliance Assurance Programme)や、国家間の課税権の配分ルールを曖昧なものとしかねないデジタル・エコノミー(電子経済)への対応など新たな重要テーマも浮上しており、BEPSプロジェクトは次のステージに足を踏み入れようとしている。
こうした中、BEPSプロジェクトのキーパーソンであるOECD(経済協力開発機構)租税政策税務行政センター(CTPA)のパスカル・サンタマン局長、Business at OECD(BIAC:OECD経済産業諮問委員会)のウイリアム・モリス税制・財政委員長が経団連との国際課税に関する会合に参加するため今月上旬、来日した。政府機関、民間と立ち位置の異なるお2人に、BEPSプロジェクトの現在地、そして今後の課題について話を聞いた。
サンタマン局長
税務当局からも期待を集めるICAP
本誌:OECDがBEPS最終報告書を公表してから2年が経ちました。まずこれまでの成果について総括をお願いいたします。
サンタマン:OECDは過去2年間、BEPSプロジェクトの実施に注力してきました。なるべく多くの国にこのプロジェクトの原則を受け入れ、コミットしてもらうことに集中してきた結果、現在は102か国が平等な立場でBEPSに関する包摂的枠組み(inclusive framework)に参加しています。多くの国をカバーできたことで、地理的な範囲の広さのみならず、「深さ」の面でもプロジェクトは成功していると思っています。また、多国間協定には現在、70か国以上が署名しています。1,200以上の租税条約を修正することで、条約漁り(treaty shopping)を防止できるようになりました。
本誌:最近の取り組みについて教えてください。
サンタマン:まず、国別報告書(CbCR)に関する作業を進めています。日本からの要請に基づき、公開しないことが前提です。有害税制への対抗、税の安定性(tax certainty)、相互協議の効果的実施などについても作業が進んでいます。このうち相互協議の効果的実施(行動14)については既に相互審査(peer review)を開始しています。
そしてこれらに加え、新たなイニシアティブの一つとして、税の安定性改善のため、ICAP(International Compliance Assurance Programme)に取り組んでいます。ICAPとは納税者に税の安定性を提供する革新的な手法であり、自主参加をベースにパイロット・プロジェクトとして開始するものです。先週、オスロで開催されたOECD税務長官会議(日本を含む48カ国から税務長官が参加)でプロジェクトが正式に発足しました。このイニシアティブの下では、納税者が自発的に多数の税務当局と討議を行い、税務リスクが評価されることになります。その結果、低リスクと評価されれば、納税者に一種の「保証」が与えられます。すなわち、調査をしない、または限定的な調査にするという保証です。このイニシアティブは、税務行政執行共助条約に依拠するものであり、税務紛争を回避するための我々の取り組みの良い事例となるでしょう。ここで強調したいことは、ICAPは、企業にとって税の安定性を改善し、紛争の回避につながるものとして、各国の税務当局からも大きな期待を集めているということです。現在、10社以上の企業がこのプログラムに参加したいと申し出ており、現在はその中から参加企業を選定するプロセスに入っています。

「ALES」はグローバルな合意に向けたロードマップに賛同しないことへの警告
本誌:今年7月にハンブルグで開催されたG20サミットでも話題になった電子経済についてはいかがでしょうか。
サンタマン:ご承知のように、電子経済への対応はBEPS行動計画1に含まれています。最終報告書には、4つの重要な結論が含まれています。一つは、電子経済そのものよりも「経済のデジタル化」に注目すべきだということです。二番目として、経済のデジタル化によってBEPSの状況そのものは悪化する可能性があるということです。ただし、TECH企業などによるBEPSの活用は、BEPS行動計画のそれぞれの項目で対応し、抑えることができると考えています。三番目として、電子的なサービスを提供する際には、その目的地でVATをいかに確保するかというVATのルールを明確化する必要があるということです。この点については、既に日本を含む100か国がルールを確立し、実施しています。四番目として、直接税における課題を認識する必要があるという点です。TECH企業は、物理的なプレゼンスを持っていない市場においても取引をし、そこから収益を上げることができます。それに対して従来の国際租税体制は十分に適正な対応ができていなかったということを認めることが重要です。様々なオプションを検討する中で、その一つに平衡税(equalisation levy)がありますが、多くの国はまだこれに合意することができない状況であるため、2020年までを目途に状況のモニタリングを続けるということで現時点では合意しています。
このような背景の下、ハンブルグで開催されたG20サミットにおいて、2018年4月までにこの分野で中間報告を作成するようOECDは指示を受けています。我々は現在この報告書の作成を進めているところです。
| 平衡税(equalisation levy)とは? 電子経済による租税回避を防止するための課税手法の一つ。国内事業者の利益には課税が行われる一方、国外事業者の利益には課税が行われないという不平等を解消するため、国内事業者と国外事業者に同等の税を課す。インドでは、オンライン広告など特定のサービスを行う外国企業に対して6%の平衡税が導入されている。 |
本誌:今夏にリオデジャネイロで開催されたIFA(International Fiscal Association=国際租税協会)でサンタマン局長は、電子経済問題に対処し得る方法の一つとして、Alternative Levy on Electronic Sales(ALES=代替的電子売上税)に言及したと伝えられています。この点について、OECDではどのような議論がされているのでしょうか。
サンタマン:まずOECDの立場を明確にしておきたいと思いますが、OECDとしてはあくまでも「グローバルなソリューション」が必要だと考えており、いかなる状況においても、場当たり的な対応(quick fix)を我々が提案したり支持したりすることは決してありません。しかし現在は、複数の国が必ずしも忍耐強く作業を待っていない状況であり、もし近い将来においてこの問題に対応するグローバルなソリューションが出て来る見通しがないのであれば、それぞれの国が独自に"quick fix"をとってしまうという可能性も出てきています。特にフランスをはじめとする10か国程度のヨーロッパ諸国は、もし近い将来OECDで合意が達成できないのであれば、例えば売上高をベースにした税制(turnover tax)なども検討すると言っています。こうした動きに半分冗談で私が勝手に名前を付けたのが、リオでの会合で申し上げた"alternative levy on electronic sales(ALES)"(代替的電子売上税)です。もしグローバルな合意に向けたロードマップに賛同できないのであれば、このような場当たり的な対応-これは決して良いものではありませんが-が採用されてしまうこともあり得るという警告の意味も込めて申し上げました。我々は特に米国に対して警告を発しております。
利益分割法のガイダンスはイデオロギーではなく“実務的・実践的”なアプローチで
本誌:日本の与党は、近い将来所得相応性基準の導入を目指していますが、今年5月に公表された「評価困難な無形資産(Hard-to-Value Intangibles)」に関するディスカッション・ドラフトに対し、OECDにはどのようなコメントが寄せられているのでしょうか。また、所得相応性基準の実施ガイダンスはいつ確定するのでしょうか。
サンタマン:所得相応性基準はBEPS最終報告書における提言の一部であり、米国でも実施されているように、無形資産を用いたBEPSを防止するための一つの手段になり得ると考えています。具体的な期日をお伝えすることはできませんが、現在、評価困難な無形資産に関する実施ガイダンスの取りまとめは最終段階に入っています。
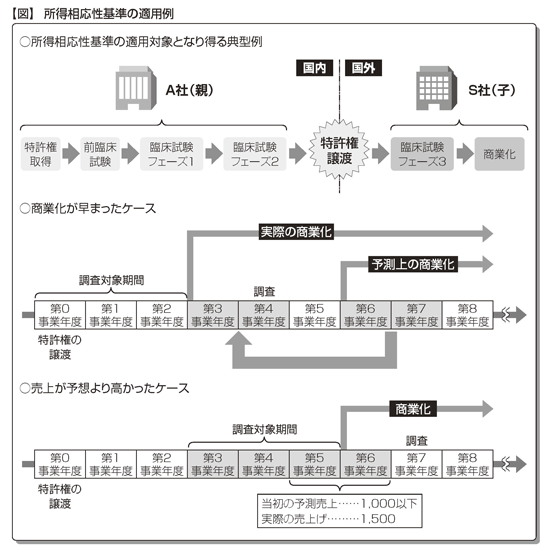
本誌:利益分割法(PS法)も日本企業の関心事項の一つです。日本企業は利益分割法(PS法)が特に新興国によって安易に使われることに懸念を持っています。この点についてはどうお考えでしょうか。また、この分野ではどのようなガイダンスを出したいとお考えですか。
サンタマン:利益分割法を用いる国が増えているというのは事実であり、おっしゃるような懸念が存在することも承知していますが、利益分割法は適切な枠組みの下で、原則に沿った形で活用されるのであれば、効率の良い手法の一つだとは思います。我々はこの利益分割法がより良く活用されるためのガイダンスを出したいと考えており、その作成作業を現在進めているところです。それは困難な作業ではありますが、ガイダンスの取りまとめにあたっては、イデオロギーベースではなく、あくまで実務的・実践的なアプローチが必要だと思っています。
PE帰属利得、金融取引に関する移転価格税制のガイダンスは「近い将来」公表
本誌:6月に公表されたPE帰属利得に関するディスカッション・ドラフトに対しては、その中で述べられていた「簡便性向上のための執行アプローチ」の重要性を指摘するコメントが数多く寄せられているのではないかと思います。PE帰属利得についてより明確かつ詳細なガイダンスを出す予定はありますか。
サンタマン:こちらも今作業を進めている状況です。BEPS行動7(PE認定の人為的回避の防止)に関する最終報告書ではPEに対する租税回避ルールの強化を求めていますが、我々としてはその中でも特にコミッショネア契約(問屋契約)に注目し、これに対応しなければならないと思っています。従来のPEのルールはアップデートが十分にされてこなかったため、現在行っているアップデート作業においてはかなり激しいディスカッションが行われています。決して容易な作業ではありませんが、この分野のガイダンスは相対的に近い将来に出していきたいと考えています。
| コミッショネア 自己名義で契約を行うものの、親会社のために親会社が所有する物品等を販売する者。いわゆる問屋。在庫リスクを負わないのが特徴。 |
本誌:最後に、金融取引に関する移転価格税制について、現在どのような作業が行われているのか教えてください。
サンタマン:行動4(利子控除制限)の残された課題であり、既にガイダンスの策定作業を開始しています。次回のOECD租税委員会WP6(第6作業部会)の開催後、すなわち年末あたりにディスカッション・ドラフトが公開されることになるのではないかと思います。そのガイダンスはキャプティブ保険(自社あるいは自社を含む企業グループのリスクを専門に引き受ける保険会社)など特に保険の問題に対応するものです。現在でも、資本負債比率をどのような位置付けの問題とするか、すなわち、これは移転価格の問題なのか、あるいは移転価格の問題とは全く関係のない別の問題としてとらえるべきなのかということに関して、各国の間に意見の食い違いが残っていますが、パブリックコメントを得るためにも、近い将来ディスカッション・ドラフトを公表する予定です。
モリス税制・財政委員長
CbCRの簡素化、利子控除制限の緩和で大きな役割
本誌:最初に、この数年間BIAC(OECD経済産業諮問委員会)がBEPSプロジェクトで果たしてきた役割、また、どのようなプロジェクトで何を達成してきたのかについてお聞かせください。
モリス:我々はグループです。すなわちBIACは日本の経団連を含む多くの国の産業団体とOECDを橋渡しするチャネルとしての役割を果たしてきました。数字で示せば、BIACは2800名の税の専門家にアクセスし、これまでOECDが出した25本のディスカッション・ドラフトのうち23本についてレスポンスを出しています。その過程では41か国からコメントを得ており、BIACメンバーから200の書面意見を得ました。また、12回の公聴会(パブリック・コンサルテーション)にも200人のBIACのメンバーが出席しています。
これまでOECDと討議してきた内容を振り返ると、政治色が濃いテーマも、また国と国との間で紛争になったテーマもありましたが、その中でも我々は影響力を行使してきました。二つ例を挙げると、第一には国別報告書(CbCR)について、各国の税の専門家のみならず、税以外の分野の人達の意見を聞くことで、OECD及び各国の関係者に対して、よりシンプルに、そして実際のビジネスに沿ったより適正な形にするように働きかけました。その結果として、元々考えられていたものよりもだいぶシンプルなものになったのは確かだと思います。もう一つはBEPS行動4(利子控除制限)に関するプロジェクトです。元々のOECDの提案では、企業の純支払利子が当該企業のEBITDAに「10%」を乗じた金額を超える場合、その超える部分に相当する金額を損金不算入とするものでしたが、BIACがかなり幅広い企業へのリサーチに基づき働きかけた結果、最終報告書でも10~30%という回廊(幅)が認められることになりました。
本誌:BIACは現在、国際租税問題においてどこに優先順位を置いているのでしょうか。
モリス:3つの分野に重点を置いています。第一に、BEPSに関するこれまでのOECDの勧告は完全に詳細なところまでは詰められていなかったので、今後は詳細なところまでしっかり分かるような勧告内容を確保するということです。その例として、利益分割法の問題とPE帰属利得の問題が挙げられます。第二に、勧告の内容が世界各地でいかに実施されているかという点です。特に、国によって解釈が異なることなく、どの国においても同じような形で実施されていることが重要だと考えています。なぜなら、クロスボーダーの貿易や投資を行う際、国によって勧告内容の解釈が違うと、税負担にかなり大きな差異が出てきてしまうからです。第三に、将来の方向性です。その中には電子経済の問題もあります(詳細は後述)。
日本もICAPに参加を
本誌:新たな取り組みであるICAPについてはいかがでしょうか。日本企業はパイロットプログラムに参加しているのでしょうか。
モリス:私は幸いにもOECDや加盟国がディスカッションをし始めた時からICAPに関わることができ、最初の段階からその内容を支持してきました。というのも、ICAPによって問題を早期に、しかも一国または二国間ベースではなくより広範囲に解決するチャンスが出て来るからです。今後BEPSを実行するにあたっては必ず紛争や意見の食い違いが出て来るはずなので、なおさら紛争を予防する、すなわち問題や食い違いがあまり深刻になる前に早い段階で対応していくということが重要だと思っています。
私は先週ノルウェーのオスロで開催されたOECD税務長官会議にも参加したのですが、各国の国税長官等によるパネルディスカッションで各国がこの問題に真摯に取り組んでいることが伝わり、強い感銘を受けました。
パイロットプログラムに参加できる企業は本社所在国がパイロットプログラムに参加していなければならないということと、一国一社と参加企業が限られているため、現時点では日本企業はパイロットプログラムには参加していないというのが私の理解ですが、日本が国として将来このプログラムに参加することを本当に強く希望しています。そうすれば、日本企業も参加できると思いますので。
今後10年間はデジタル経済が国際租税における議論を支配する
本誌:先ほどお話が出た電子経済について聞かせてください。重点分野の一つのとのことですが、その理由は何でしょうか。
モリス:少なくとも今後の10年間を見た場合、国際租税問題においては電子経済が支配的なテーマになるのではないかと思うほどの重要分野であると私自身は考えています。現在、米国や中国、日本などのTECH企業は確かに経済に影響を及ぼしていますが、その度合いは将来及ぼすであろう非常に大きな影響と比較すると僅かなものであると思います。例えば多くのサービスがクラウドになったり、AIを活用した自動操縦の実現により道路の整備や管理も現在とは全く違ってきたりということになると、国の税源ベースそのものがどういうものであるかということについて、非常に大きな影響が出て来ることになります。本当に大きな問題になるはずです。
ただ、現在のBEPSプロジェクトにおける討議内容を見ると、将来の問題よりも「過去どうであったか」という既に過ぎ去った状況がベースとなっている傾向があると思います。例えばいまだにイー・コマースに注目していることもそうです。しかも、税制の構造そのものについての議論の多くは、BEPSの前の条件をベースに行われています。いくつかのヨーロッパの国が提案している取引高や売上高をベースにした税制(turnover tax)も古い前提に基づいた議論だと思います。経済性もあまり良くありません。例えば売上高が大きく利益率が低い企業や、控除の対象となる多額の研究開発費を支出している企業などにとっては、あまり都合の良い税制ではありません。立ち上げに経費がかかる新規事業にとっても同様です。
我々は税制を設計する際には、「過去どうであったか」ではなく、「今後どのような方向性が見込まれているのか」あるいは「将来の成長をどのように促進できるのか」ということを頭に入れる必要があると思います。デジタル経済の特性そのものを見ていかなければなりません。現在は、明らかに国によって異なる国益が念頭に置かれています。将来どのように動いていくのか、その方向性について本当に真剣に詳細まで詰めた多国間的な同意が必要だと思います。経済成長にとって、一国単位で動く又は決めるということは決して好ましいことではありません。
デジタル経済は決して限定された特定のセクターにとどまる話ではありません。ほとんどすべての企業が何らかの形でデジタル経済に関わっていますし、将来はさらにその傾向が顕著になるはずです。これは本当に重要なテーマであり、ご承知のようにOECDが2018年4月までに中間報告を出す予定にはなっていますが、いくつかのヨーロッパ諸国は、もっと早いスピードで、独自の動きで前進したいと言っています。しかし、我々としては、本当に重要な分野であるだけに、真剣に、そして全ての側面から見て、全ての当事国が納得できるソリューションが最終的に必要だと思っており、各国をその方向に向けられるように我々も役割を果たしていきたいと考えています。
繰り返しになりますが、デジタル経済は本当に重要なテーマであり、これから10年間、税制についての議論はこのテーマが支配するほど、国際租税上、重要なテーマになると思いますので、十分に時間を確保して、正しい方向付けをした上で、適切な制度を設けるということが極めて重要になります。

所得相応性基準ガイダンスは現段階では不明瞭
本誌:最近BIACでは、評価困難な無形資産に関するOECDのディスカッション・ドラフトついて懸念を表明されています。具体的に聞かせてください。
モリス:評価困難な無形資産については2つの懸念があります。まず、評価困難な無形資産の定義が非常に広くなっているということです。評価困難な無形資産の定義がこれだけ広くなると、無形資産を移転する際にはほとんどが「評価困難な無形資産」の分類に入れられてしまいます。その結果、今後紛争が発生する可能性が高まることになります。定義が広いがゆえに、例えば知的財産の一部である無形資産をどのように切り分けるのかなど、本来存在しなくてもいいような問題まで出てくることになりかねません。
もう一つ、有用と言えるためには現時点では不明瞭と思われるのが事前のプライシングと事後のプライシングの関係、すなわち、どの段階を評価のベースとするべきかという問題です。これには、その事象が起こっている時に評価する、あるいは、後になって以前起こったことを振り返って評価する、という2つのアプローチがあります。例えばある取引が1年目に起こったとします。そして、その取引について10年後に税務調査があったとすると、1年~10年の間に起こったことというのは、1年目の取引や行動が適切だったのかを判断する上で一つの要素になるという考え方があります。ただ、それ(1~10年目に起きたこと)は一つの要素であって、決定的な要素であってはならないと思います。というのも、最初に予測していた状況とは全く違う状況で物事が展開していくということは往々にしてあるからです。したがって、10年目にこういう結果になっているということをベースに、そこから結論を導き出して、1年目の取引や行動が適切であったのかどうかを判断すべきではないと思います。すなわち、第三者が1年目にそのような判断・決定をしたのであれば、それはそれで尊重しなければならないということです。もし、10年目に結果として出てきた内容に基づき、そこから逆算して1年目のことを決定できるのであれば、1年目の行動や取引そのものを測定したり判断する意味が全くなくなってしまいます。繰り返しになりますが、10年目の出来事、状況というのは1年目に起こった取引を評価する一つのエビデンス、一つの評価要素として取り入れるべきだとは思いますが、唯一のものであってはならないということです。10年目に予想もしていなかったような(悪い)結果になったからといって、納税者に対し「では、1年目の取引においてこれだけの損失を計上してよい」とは言わないはずです。
利益分割法のガイダンスでは、「利益分割法=デフォルト方法」でないことを明記すべき
本誌:利益分割法についてはいかがでしょうか。
モリス:我々は今後、確実に、より多く利益分割法の適用を目論む国を目にすることになるでしょう。これまでのOECDガイダンスの内容はおおむね歓迎できるものです。ただし、現在のディスカッション・ドラフトについて懸念するのは、利益分割法は限定的な状況でのみ使うべきという合意があると考えられる一方、恐らくではありますが、利益分割法が最適手法であるという含意があるようにも読み取れます。例えば第三者との取引において利益分割的なプライシングの手法をとるケースは確かにあると思われ、そのような場合には関連者間でも利益分割法を使えるという考え方が出てくる傾向がありますが、実際には第三者の企業間でも利益分割法を使わない事例も多くあります。したがって、これから出されるOECDのガイダンスでは、利益分割法をデフォルトの方法として位置付けるべきではありませんし、この点を文言としてガイダンスに記載するべきだと思います。
従属代理人PEをめぐる状況改善のためには“簡素化された執行アプローチ”も検討を
本誌:PE帰属利得のガイダンスに期待することはどのようなことでしょうか。
モリス:我々はこの分野についてもOECDに是非ガイダンスを出して欲しいと思っていますが、各国が判断しなければならない事柄も多いため、OECDができることにも限界があるという点も認めなければなりません。
一方で、従属代理人PEの閾値を下げればPEの数は増えますので、それに対応する策を考えていかなければならないと思います。ご存知のとおり、新しいルールの下でのPEの多くは利益がゼロかごくわずかしか計上されません。しかしながら、PEとして登録しない、特にVATの分野でPE登録せず報告提出を怠るということは深刻な問題を生みます。したがって、この問題についてはかなり真剣に、また発想を自由にして色々な可能性を検討するべきだと思います。最近、ある事例でイタリアの税務当局が、世界的に売上を計上している企業グループの中で一定の割合を占める売上を有する企業は、VATについてイタリアの税務当局にアプローチして相談できるというルールを示しました。これにより、企業はイタリアの税務当局に対し、従属代理人PEに該当するのかどうかや所得の帰属などについて、税務当局に相談することができようになりました。それをすれば、別途PEの登録やVATのためのPEレポートの提出は必要なくなります。今後はこのような柔軟な発想、考え方がもっと必要になってくると思います。
本誌:日本企業では、OECDがPE帰属利得においてダブル・タックスペイヤー・アプローチを前提としていることを懸念する声も聞かれます。
モリス:もう10年以上前にこのルールができましたが、このようなルールができたために、非常に複雑な状況になってきてしまっています。実務的に考えると、これらのルールを今解消したり、なくすことは非常に難しいと思います。イタリアの例のように、より簡素化された執行アプローチを、発想を自由にして提示することができれば、状況は改善されると思っています。
本件は租税条約の9条(特殊関連企業)と7条(事業所得)の適用にもかかわってきますが、残念ながら、ディスカッション・ドラフトではその2つの間の優先順位や、識別などは必ずもはっきりしていないので、今後その点についてはより明確になることを期待しています。
| ダブル・タックスペイヤー・アプローチ 子会社がPEとして認定されると、租税条約第9条(特殊関連企業)によって、移転価格税制上、セールス・エージェントとしての子会社の所得が適正に算出される場合であっても、なお同第7条(事業所得)によってPEに利得が帰属するという議論。ダブル・タックスペイヤー・アプローチに対する企業の納得感は低い。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















