解説記事2018年01月22日 【ニュース特集】 平成30年度組織再編税制改正の留意点(2018年1月22日号・№723)
ニュース特集
スピンオフ準備のグループ内再編が適格に、従業者・事業継続要件も緩和
平成30年度組織再編税制改正の留意点
昨年度(平成29年度)税制改正では、従来「譲渡」とされていたスピンオフを税制適格再編の対象とするという画期的な改正が行われたところだが、平成30年度税制改正においても引き続き組織再編税制の“緩和”が実施される。
その主要改正事項の一つが、スピンオフの実施を円滑にするため、スピンオフの「準備」として行うグループ内再編を幅広く適格とするものであり、もう一つが、事業再編を円滑化するための従業者引継(継続)要件及び事業継続要件の緩和だ。
本特集では、税制改正大綱のみだけでは読み取れないこれらの改正の詳細と、本誌の取材で判明した留意点をお伝えする。
スピンオフの「準備」として行うグループ内再編の適格化
許認可の先行取得等のため、100%子会社設立後に親会社事業を吸収分割 昨年度(平成29年度)税制改正で導入されたスピンオフ税制は、従来であればグループ内再編、共同事業を行うための再編のいずれにも該当せず「譲渡」とされていたスピンオフを税制適格再編の対象としたという点で画期的だったと言えるが、企業側からさらなる適格要件の緩和を求める声が上がっていたのが、スピンオフの「準備」のためのグループ内再編だ。
平成29年度税制改正で導入されたスピンオフ税制には、「分割型分割型」と「株式分配型」があるが(図1参照)、平成30年度税制改正で見直されるのはこのうち「株式分配型」である。
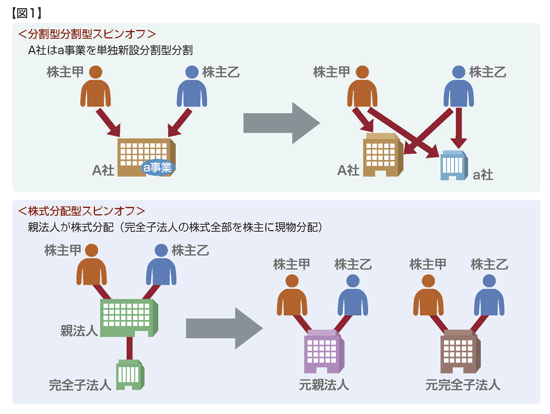
株式分配型スピンオフには、(1)既存の完全子法人株式を現物分配する類型に加え、(2)まずは親法人の事業を単独新設分社型分割あるいは単独新設現物出資(以下、単独新設分社型分割等)により完全子法人として切り出し、その後、当該子法人の株式全部を親法人の株主に現物分配するという類型がある。(2)において、単独新設分社型分割等の後に、分割承継法人あるいは被現物出資法人(以下、分割承継法人等)を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合、親法人と分割承継法人等との完全支配関係継続要件については、単独新設分社型分割等の時から適格株式分配の直前まで完全支配関係が継続することが見込まれていれば足りるとされている(法令4の3⑥一ハ、法令4の3⑬一ロ)。
ただ、企業側には、株式分配型のスピンオフを実施するにあたり、まずは親法人が“受皿会社”となる完全子法人を現金出資により設立した上で、そこに親法人の事業を吸収分割により移管(その後当該子法人の株式全部を親法人の株主に現物分配)したいとのニーズがある。これは、事業に必要な免許や許認可を受皿会社に先行取得させるためだ。
ところが、上記のとおり、現行法人税法上、株式分配型のスピンオフの準備段階の組織再編で完全支配関係継続要件を満たし、税制適格となるのは単独新設分社型分割及び単独新設現物出資に限定されている。そこで平成30年度税制改正では、受皿会社に事業を移転するための吸収分割も税制適格とする。この他、兄弟会社を合併し、1つにまとめた上で適格株式分配することも念頭に置いている。このことを示しているのが、平成30年度税制改正大綱の下記の部分である。
〈スピンオフ税制の拡充 平成30年度税制改正の該当部分(財務省版59頁下部(2)①)〉
株式分配によるスピンオフ準備のためのグループ内再編が幅広く税制適格とされれば、スピンオフ税制の使い勝手は大きく向上することになろう。
従業者引継(継続)要件、事業継続要件の緩和
当初の組織再編と従業者・事業の再移転が“パッケージ”となっている必要 平成30年度税制改正で実施される組織再編税制の見直しのもう一つの目玉が、従業者引継(継続)要件及び事業継続要件の緩和だ。この点について、平成30年度税制改正大綱には下記の記載がある。
〈従業者引継(継続)要件、事業継続要件の緩和 平成30年度税制改正の該当部分(財務省版60頁冒頭の②)〉
この改正は要するに、現行組織再編税制上、組織再編後に従業者や事業の再移転(その再移転が適格合併等である場合を除く)が見込まれている場合には税制非適格再編となってしまうところ、従業者や事業の再移転先が「100%グループ内」であれば、当該組織再編を税制適格再編として取り扱おうというもの。ちなみに、大綱では「従業者従事要件」というこれまで税務当局で使われて来なかった用語が使われている。これが従業者引継(継続)要件のことを指すのは明らかだが、平成30年度税制改正後は、「従業者従事要件」があらゆる組織再編に関する統一的な用語と使われる可能性もある(本稿では実務家にとって馴染み深い「従業者引継(継続)要件」を使うこととする)。
まず従業者引継(継続)要件の改正について説明しよう(図2参照)。現行組織再編税制では、A社にあったa事業がB社に移転した場合、a事業の従業者のおおむね8割以上は「B社」に引き継がれる必要があり、上述のとおり、B社からの再移転が見込まれている場合には、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となってしまう。しかし平成30年度税制改正では、当該従業者の再移転先(C社)がB社と完全支配関係があれば、従業者引継(継続)要件に抵触しないこととされた。
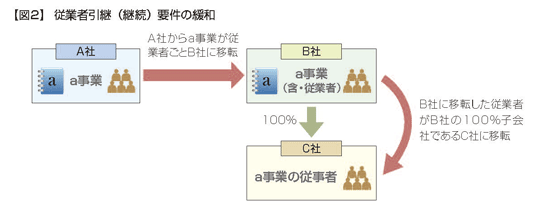 なお、本改正では、「従業者のおおむね8割以上を引き継ぐ」という要件が緩和されたわけではない。したがって、そもそもA社からB社にa事業が移転する際に従業者が5割しかB社に引き継がれなければ、たとえB社に移転した従業者が全員C社に再移転したとしても、現行組織再編税制同様、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となる点に変わりはない。
なお、本改正では、「従業者のおおむね8割以上を引き継ぐ」という要件が緩和されたわけではない。したがって、そもそもA社からB社にa事業が移転する際に従業者が5割しかB社に引き継がれなければ、たとえB社に移転した従業者が全員C社に再移転したとしても、現行組織再編税制同様、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となる点に変わりはない。
事業継続要件の改正も、従業者引継(継続)要件の改正と同様の趣旨となっている。すなわち、図3に示した通り、当初移転した事業(A社からB社に移転したa事業)の再移転先(C社)が100%グループ内であれば、当初の組織再編(A社からB社へのa事業の移転)は事業継続要件に抵触しないことになる。
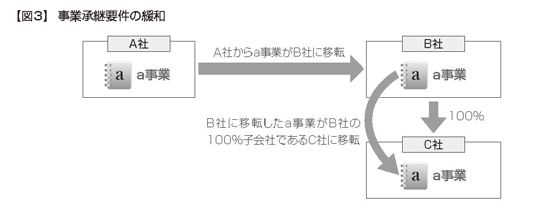
ただし、今回の改正によって当初の組織再編(A社からB社へのa事業の移転)が税制適格再編として取り扱われるためには、当初の組織再編とその後の(100%グループ内での)従業者や事業の移転が一つの“パッケージ”としての組織再編と捉えられるものである必要があろう。逆に言うと、従業者や事業の再移転先が「100%グループ内」であったとしても、これが当初の組織再編と切り離された事象と判断されれば、従来通り、当初の組織再編のみを捉え従業者引継(継続)要件や事業継続要件を充足しているか否かが判定されることになる可能性が高い。例えば、a事業がA社からB社に移転し、すぐにC社に移転するのであれば一連の流れが一つの“パッケージ”としての組織再編と捉えられるものと考えられるが、例えばC社への移転までに相当なタイムラグがあることなどにより、「A社からB社への移転」と「B社からC社への移転」を別々の事象と判断せざるを得ないようなケースは、今回の改正では想定されていないと言えよう。
なお、平成30年度税制改正大綱に「従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも……従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする」と記載されているとおり、a事業だけがC社に移り、従業者はB社に残ったままでも税制適格要件を満たすことになる。もちろん、従業者及び事業がともにC社に移った場合でも税制適格要件を満たすことになるのは言うまでもない。また、B社の従業者50%がC社に移転し、残りの従業者はB社に留まったとしても、従業者が100%グループ内に留まっている状況には変わりはないため、税制適格要件を満たすことになろう。
なお、税制改正大綱には本改正の施行日が明記されていないが、「平成30年4月1日以降に開始する事業年度」からとなろう。
スピンオフ準備のグループ内再編が適格に、従業者・事業継続要件も緩和
平成30年度組織再編税制改正の留意点
昨年度(平成29年度)税制改正では、従来「譲渡」とされていたスピンオフを税制適格再編の対象とするという画期的な改正が行われたところだが、平成30年度税制改正においても引き続き組織再編税制の“緩和”が実施される。
その主要改正事項の一つが、スピンオフの実施を円滑にするため、スピンオフの「準備」として行うグループ内再編を幅広く適格とするものであり、もう一つが、事業再編を円滑化するための従業者引継(継続)要件及び事業継続要件の緩和だ。
本特集では、税制改正大綱のみだけでは読み取れないこれらの改正の詳細と、本誌の取材で判明した留意点をお伝えする。
スピンオフの「準備」として行うグループ内再編の適格化
許認可の先行取得等のため、100%子会社設立後に親会社事業を吸収分割 昨年度(平成29年度)税制改正で導入されたスピンオフ税制は、従来であればグループ内再編、共同事業を行うための再編のいずれにも該当せず「譲渡」とされていたスピンオフを税制適格再編の対象としたという点で画期的だったと言えるが、企業側からさらなる適格要件の緩和を求める声が上がっていたのが、スピンオフの「準備」のためのグループ内再編だ。
平成29年度税制改正で導入されたスピンオフ税制には、「分割型分割型」と「株式分配型」があるが(図1参照)、平成30年度税制改正で見直されるのはこのうち「株式分配型」である。
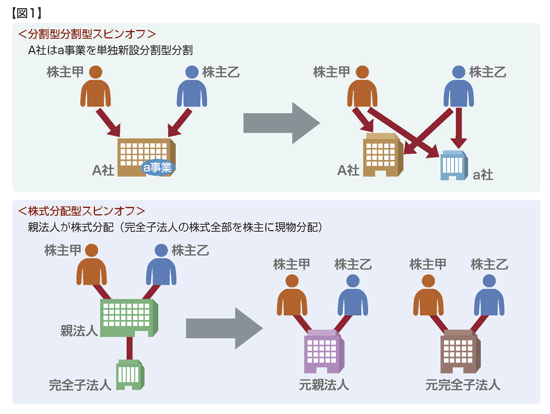
株式分配型スピンオフには、(1)既存の完全子法人株式を現物分配する類型に加え、(2)まずは親法人の事業を単独新設分社型分割あるいは単独新設現物出資(以下、単独新設分社型分割等)により完全子法人として切り出し、その後、当該子法人の株式全部を親法人の株主に現物分配するという類型がある。(2)において、単独新設分社型分割等の後に、分割承継法人あるいは被現物出資法人(以下、分割承継法人等)を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合、親法人と分割承継法人等との完全支配関係継続要件については、単独新設分社型分割等の時から適格株式分配の直前まで完全支配関係が継続することが見込まれていれば足りるとされている(法令4の3⑥一ハ、法令4の3⑬一ロ)。
ただ、企業側には、株式分配型のスピンオフを実施するにあたり、まずは親法人が“受皿会社”となる完全子法人を現金出資により設立した上で、そこに親法人の事業を吸収分割により移管(その後当該子法人の株式全部を親法人の株主に現物分配)したいとのニーズがある。これは、事業に必要な免許や許認可を受皿会社に先行取得させるためだ。
ところが、上記のとおり、現行法人税法上、株式分配型のスピンオフの準備段階の組織再編で完全支配関係継続要件を満たし、税制適格となるのは単独新設分社型分割及び単独新設現物出資に限定されている。そこで平成30年度税制改正では、受皿会社に事業を移転するための吸収分割も税制適格とする。この他、兄弟会社を合併し、1つにまとめた上で適格株式分配することも念頭に置いている。このことを示しているのが、平成30年度税制改正大綱の下記の部分である。
〈スピンオフ税制の拡充 平成30年度税制改正の該当部分(財務省版59頁下部(2)①)〉
| 完全支配関係がある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件のうち完全支配関係の継続要件について、その適格株式分配の直前の時までの関係により判定することとする。 |
従業者引継(継続)要件、事業継続要件の緩和
当初の組織再編と従業者・事業の再移転が“パッケージ”となっている必要 平成30年度税制改正で実施される組織再編税制の見直しのもう一つの目玉が、従業者引継(継続)要件及び事業継続要件の緩和だ。この点について、平成30年度税制改正大綱には下記の記載がある。
〈従業者引継(継続)要件、事業継続要件の緩和 平成30年度税制改正の該当部分(財務省版60頁冒頭の②)〉
| 当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする。 |
まず従業者引継(継続)要件の改正について説明しよう(図2参照)。現行組織再編税制では、A社にあったa事業がB社に移転した場合、a事業の従業者のおおむね8割以上は「B社」に引き継がれる必要があり、上述のとおり、B社からの再移転が見込まれている場合には、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となってしまう。しかし平成30年度税制改正では、当該従業者の再移転先(C社)がB社と完全支配関係があれば、従業者引継(継続)要件に抵触しないこととされた。
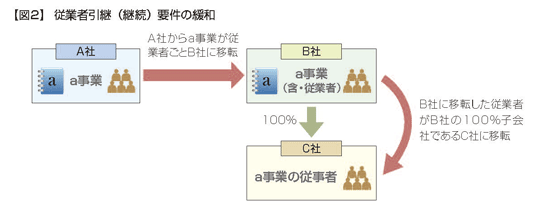 なお、本改正では、「従業者のおおむね8割以上を引き継ぐ」という要件が緩和されたわけではない。したがって、そもそもA社からB社にa事業が移転する際に従業者が5割しかB社に引き継がれなければ、たとえB社に移転した従業者が全員C社に再移転したとしても、現行組織再編税制同様、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となる点に変わりはない。
なお、本改正では、「従業者のおおむね8割以上を引き継ぐ」という要件が緩和されたわけではない。したがって、そもそもA社からB社にa事業が移転する際に従業者が5割しかB社に引き継がれなければ、たとえB社に移転した従業者が全員C社に再移転したとしても、現行組織再編税制同様、A社からB社へのa事業の移転は税制非適格再編となる点に変わりはない。事業継続要件の改正も、従業者引継(継続)要件の改正と同様の趣旨となっている。すなわち、図3に示した通り、当初移転した事業(A社からB社に移転したa事業)の再移転先(C社)が100%グループ内であれば、当初の組織再編(A社からB社へのa事業の移転)は事業継続要件に抵触しないことになる。
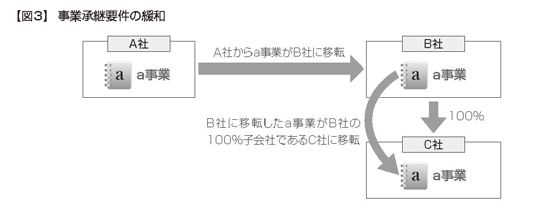
ただし、今回の改正によって当初の組織再編(A社からB社へのa事業の移転)が税制適格再編として取り扱われるためには、当初の組織再編とその後の(100%グループ内での)従業者や事業の移転が一つの“パッケージ”としての組織再編と捉えられるものである必要があろう。逆に言うと、従業者や事業の再移転先が「100%グループ内」であったとしても、これが当初の組織再編と切り離された事象と判断されれば、従来通り、当初の組織再編のみを捉え従業者引継(継続)要件や事業継続要件を充足しているか否かが判定されることになる可能性が高い。例えば、a事業がA社からB社に移転し、すぐにC社に移転するのであれば一連の流れが一つの“パッケージ”としての組織再編と捉えられるものと考えられるが、例えばC社への移転までに相当なタイムラグがあることなどにより、「A社からB社への移転」と「B社からC社への移転」を別々の事象と判断せざるを得ないようなケースは、今回の改正では想定されていないと言えよう。
なお、平成30年度税制改正大綱に「従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも……従業者従事要件及び事業継続要件を満たすこととする」と記載されているとおり、a事業だけがC社に移り、従業者はB社に残ったままでも税制適格要件を満たすことになる。もちろん、従業者及び事業がともにC社に移った場合でも税制適格要件を満たすことになるのは言うまでもない。また、B社の従業者50%がC社に移転し、残りの従業者はB社に留まったとしても、従業者が100%グループ内に留まっている状況には変わりはないため、税制適格要件を満たすことになろう。
なお、税制改正大綱には本改正の施行日が明記されていないが、「平成30年4月1日以降に開始する事業年度」からとなろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















