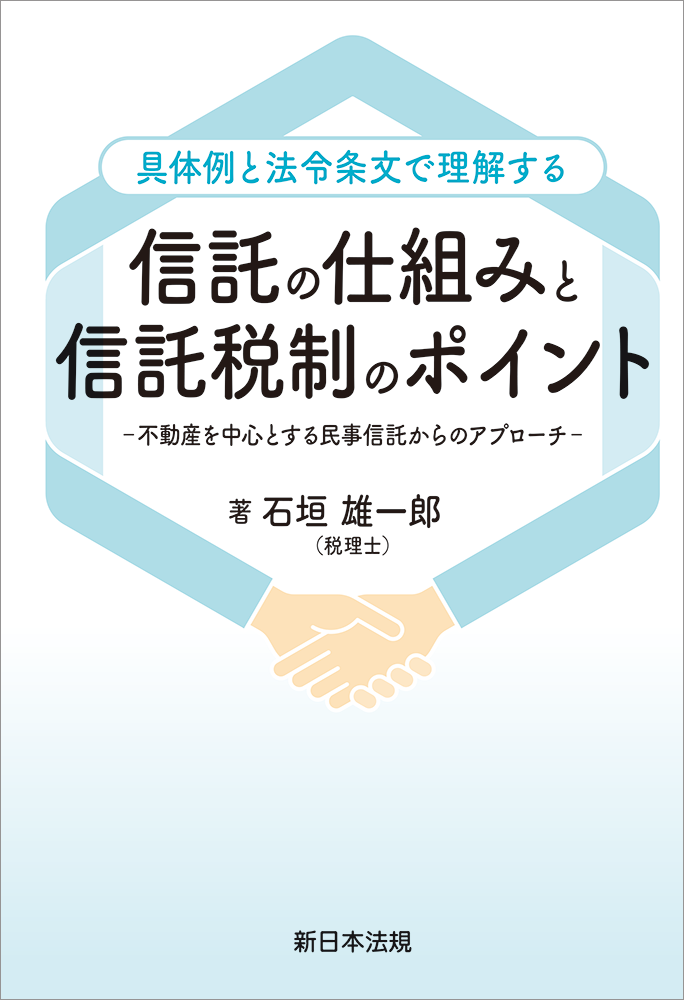解説記事2018年04月30日 【実務解説】 有価証券報告書作成上の留意点(平成30年3月期提出用)(2018年4月30日号・№737)
実務解説
有価証券報告書作成上の留意点(平成30年3月期提出用)
財務会計基準機構 企画・開示室 高野裕郎
Ⅰ はじめに
財務会計基準機構(FASF)では、FASFセミナー「有価証券報告書作成上の留意点」(以下「本セミナー」という。)を4月2日から13日にかけて全国9か所11回にわたり開催した。
本稿は、本セミナーで説明した内容を基に、平成30年3月期の有価証券報告書(以下「有報」という。)における作成上の留意点についてまとめたものである。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえた「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)等の改正に関する留意点や、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を解説する。
なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ DWG報告を踏まえた開示府令の改正に係る留意点
1 概 要 平成30年1月26日に「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)が公布・施行され、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報について適用される。本改正は、DWG報告において、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、開示内容の共通化・合理化や非財務情報の開示充実に向けた提言がなされたことによるものであり、有報においては、主に次の項目について改正が行われた。
①「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
②「新株予約権等の状況」
③「大株主の状況」
本稿においては、上記の3項目のほか、併せて改正された内容についても紹介する。
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理等を行い、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載を求める改正が行われた。
これにより、開示府令第二号様式記載上の注意(32)aにおいて、有報に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載することとされた。
なお、本稿では、経営成績等の状況(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(a))、生産、受注及び販売の実績(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b)から(d))、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(e)及び(f))に区分した場合の記載事例を示しているが、企業の開示内容が投資者にとってより分かりやすくなるのであれば、内容を一体的に記載することも考えられる。
(1)経営成績等の状況の概要
① 経営成績等の状況 開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(a)では、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況について、前年同期と比較して、その概要を記載することとされている。その記載にあたっては、改正前における「業績等の概要」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
記載事例1は、経営成績等の状況の記載事例である。
経営成績及びキャッシュ・フローの状況の記載にあたっては、前年同期の数値との比較に関する説明のほか、その背景、要因等について記載することが適当と考えられる。その場合、表やグラフなどを用いて説明することも差支えないものと考えられる。また、財政状態の状況については、その概要を記載することとされており、記載にあたっては、前年同期と比較して記載することが考えられる。
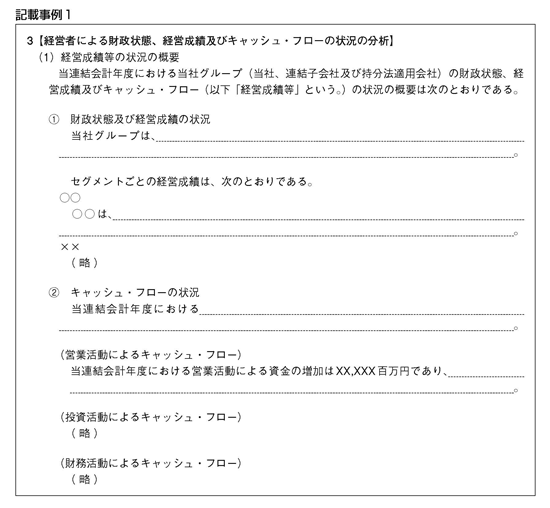
② 生産、受注及び販売の実績 開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b)から(d)において、次の事項を記載することとされている。
a.当連結会計年度における生産、受注及び販売の実績について、前年同期と比較してセグメント情報に関連付けて記載し、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を記載すること(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b))。
b.生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、その他生産、受注、販売等に関して特記すべき事項がある場合には、セグメント情報に関連付けてその内容を記載すること(同記載上の注意(32)a(c))。
c.主要な販売先がある場合には、前連結会計年度及び当連結会計年度における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること(ただし、当該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。)(同記載上の注意(32)a(d))。
なお、その記載にあたっては、改正前における「生産、受注及び販売の状況」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」の記載にあたっては、改正前における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(e)において、経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を記載することとされている。また、資本の財源及び資金の流動性に係る情報についても記載することとされている。
記載事例2は、上記を踏まえた経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載事例である。
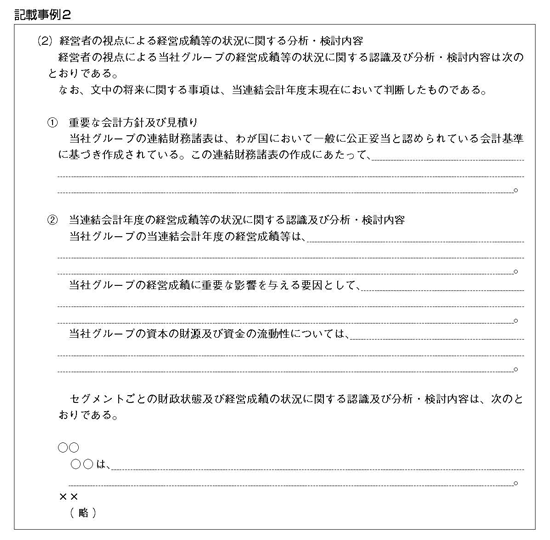
資本の財源及び資金の流動性に係る情報の記載にあたっては、キャッシュ・フロー計算書の内容を単に要約したものを記載するのではなく、企業の経営内容に即して、例えば、重要な資本的支出の予定及びその資金の調達源等について、具体的に記載することが期待されていると考えられる。
また、セグメント情報に記載された区分ごとの認識及び分析・検討内容については、記載事例では、財政状態及び経営成績の状況について記載することを想定しているが、キャッシュ・フローの状況をセグメントごとに把握している場合は、キャッシュ・フローの状況についても記載することが望ましいと考えられる。
なお、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等に照らして、経営者が経営成績等をどのように分析・検討しているかを記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載することとされている(開示府令第二号様式記載上の注意(32)(e)なお書)点にも、留意する必要がある。
(3)指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成する場合 指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成した当連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財規」という。)により作成した場合の当連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を、従来は「業績等の概要」において記載することとされていた。
本改正により、当該事項については、「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、「経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報」の項目を設けて記載することとされている。
また、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成を開始した場合、要約連結財務諸表を記載するとともに、連結財規に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載することとされているが、当該事項については、「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」の記載の後に、「並行開示情報」の項目を設けて記載することとされている。
3 新株予約権等の状況 「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目については、「新株予約権等の状況」に統合される等の改正が行われた。
(1)ストックオプション制度の内容 「ストックオプション制度の内容」においては、取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合には、当該決議に係る決議年月日、並びに付与対象者の区分及び人数を決議ごとに記載し、当該決議がされていない場合には、該当ない旨を記載することとされた(開示府令第二号様式記載上の注意(39)a)。
また、当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、当事業年度の末日における当該新株予約権に係る次に掲げる事項((a)から(i))を記載し、当該決議により新株予約権証券を付与している場合には、有報提出日の属する月の前月末現在における当該事項を併せて記載することとされた(開示府令第二号様式記載上の注意(39)b)。
(a)新株予約権の数
(b)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(c)新株予約権の行使時の払込金額
(d)新株予約権の行使期間
(e)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(f)新株予約権の行使の条件
(g)新株予約権の譲渡に関する事項
(h)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(i)金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額
当事業年度末までに取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議により新株予約権証券を付与している場合の記載事例として、記載事例3を掲げている。
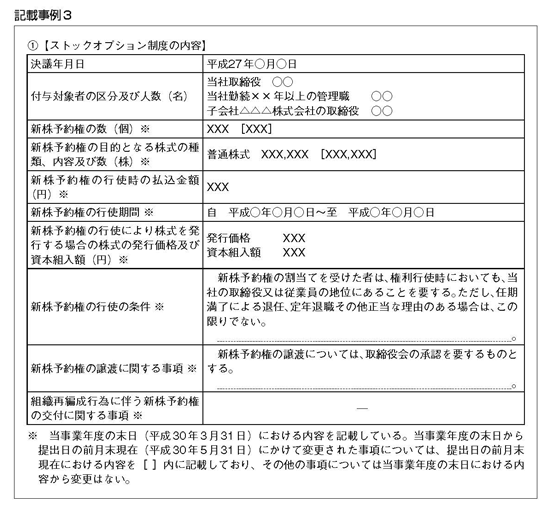
記載事例中「付与対象者の区分及び人数」については、決議日時点の内容を記載することが考えられる。
また、記載事例中「新株予約権の数」等(※が付されている項目)については、改正前と同様に、当事業年度の末日及び有報提出日の属する月の前月末現在における内容の記載が求められているが、本改正により、有報提出日の属する月の前月末現在において、記載すべき内容が、当事業年度の末日における内容から変更がない場合には、その旨を記載することによって、有報提出日の属する月の前月末現在に係る記載を省略することができる(開示府令第二号様式記載上の注意(39)bただし書)とされた。記載事例では、表の欄外において当事業年度の末日における内容から変更がない旨を記載している。
なお、記載事例のケース以外に、当事業年度末後に取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされる場合や新株予約権証券を付与している場合も想定される。
開示府令第二号様式記載上の注意(39)aに掲げる事項については、当事業年度の末日後から有報提出日までの間に取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合においても記載することが考えられる。
開示府令第二号様式記載上の注意(39)b(a)から(i)までに掲げる事項については、当事業年度の末日後から有報提出日の属する月の前月末までの間に新株予約権証券を付与している場合は、有報提出日の属する月の前月末現在における内容を記載することが考えられ、有報提出日の属する月の前月末後から有報提出日までの間に新株予約権証券を付与している場合には、付与した時点の内容を記載することが望ましいと考えられる。
また、「ストックオプション制度の内容」については、現行様式における表が撤廃され、企業の判断により過去発行分を一覧表形式で記載することが可能となったことから、内容が類似した複数のストックオプションを発行している場合には、記載事例3のように記載する方法のほかに、内容が類似した複数のストックオプション制度を集約して記載する方法も考えられる(記載事例4)。
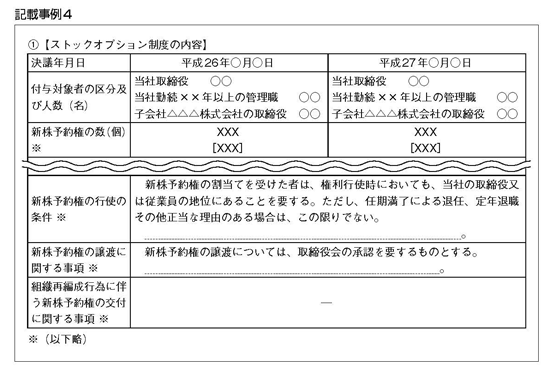
このほか、本改正により、「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部又は一部を、「経理の状況」の「ストック・オプション等関係注記」において集約して記載することができるとされた。ただし、この場合には、「ストックオプション制度の内容」にその旨を記載する必要がある。
(2)ライツプランの内容・その他の新株予約権等の状況 本改正により、「ライツプランの内容」においても、「ストックオプション制度の内容」と同様の改正が行われている。また、「ストックオプション制度の内容」及び「ライツプランの内容」に記載した新株予約権以外の新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、「その他の新株予約権等の状況」において、その内容等を記載することとされている。
4 大株主の状況 「大株主の状況」では、開示府令改正後の様式において「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」を記載することとされ、事業報告と同様に自己株式を控除することとされた。なお、大株主は、提出会社を除く、所有株式数の多い順とされている(開示府令第三号様式記載上の注意(25)c)。
また、提出会社の株主総会又は種類株主総会における議決権行使の基準日現在の「大株主の状況」について記載することとされた。ただし、これにより難い場合にあっては、当事業年度末現在について記載することとされている(開示府令第三号様式記載上の注意(25)a)。「大株主の状況」のほか、「所有者別状況」及び「議決権の状況」についても、「大株主の状況」と同様、議決権行使の基準日現在の内容を記載することとされる等の改正が行われている。
5 その他
(1)役員・従業員株式所有制度の内容 改正前の「従業員株式所有制度の内容」については、改正により「役員・従業員株式所有制度の内容」へと変更されている。開示府令第二号様式記載上の注意(46)においては、このほか、「従業員等持株会」から「役員・従業員持株会」等への変更が行われている。
(2)コーポレート・ガバナンスの状況 取締役等との間で、いわゆる責任限定契約を締結した場合、当該契約の内容の概要として、当該契約によって当該取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含めて記載することとされた(開示府令第二号様式(56)a(a)なお書)。
Ⅲ 会計基準等の改正に係る留意点
1 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が平成29年3月29日にASBJから公表されており、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされている。
本改正により、本実務対応報告の対象範囲に、国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠した財務諸表を作成している在外子会社又は在外関連会社に加えて、指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有報により開示している国内子会社又は国内関連会社についても含めることとしている。
本実務対応報告においては、本実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社又は国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有報により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている。
2 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」
(1)概 要 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下「35号」という。)が平成29年5月2日にASBJから公表されており、平成29年5月31日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用するとされている。
35号は、公共施設等運営事業において、運営権者が公共施設等運営権を取得する取引に関する会計処理及び開示、並びに運営権者が公共施設等に係る更新投資を実施する取引に関する会計処理及び開示に適用するとされている。
(2)公共施設等運営事業等関係注記
記載事例5は、公共施設等運営事業を行っており、かつ、更新投資に関する会計処理について、35号第12項(1)に該当する場合の記載事例である。この場合、連結財規第15条の25第1項及び第2項第1号に定める注記を行うこととなる。
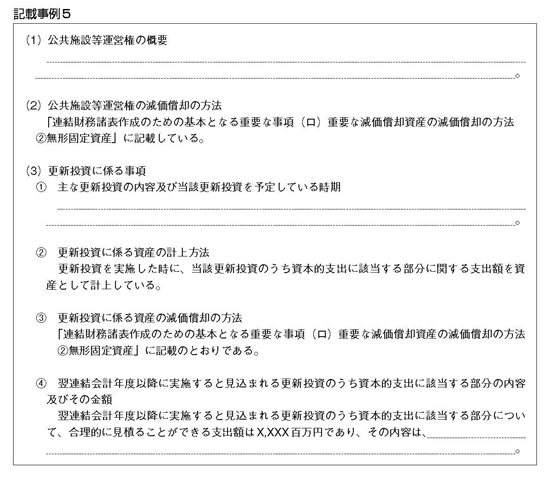
なお、当該記載事例中(2)及び(3)③において、減価償却の方法について会計方針の箇所を参照しているが、この注記において記載する方法も可能である。
3 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等
(1)概 要 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(以下、「36号」という。)等が平成30年1月12日にASBJから公表された。
36号では、企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、新株予約権の付与に伴い従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引を対象とし、この取引について、基本的に、「ストック・オプション等に関する会計基準」等に準拠した会計処理を行うこととされている。
36号は、平成30年4月1日以後適用するとされているが、公表日以後適用することができるとされているため、平成30年3月期における有報において早期適用することができる。
(2)会計方針の変更
記載事例6は、36号等を早期適用し、これまでの会計処理と異なる場合であって、従業員等に対して付与した権利確定条件付き有償新株予約権が行使されている場合の記載事例である。この場合、第1段落の最後の一文にあるように、会計方針の変更について遡及適用を行うこととなる。
また、36号では、36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、36号の会計処理によらず、従来採用していた会計処理を継続することができるとされている。
記載事例7は、36号等を早期適用した場合であって、従来採用していた会計処理を継続するときの記載事例である。
(3)ストックオプション等関係注記 36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引について、36号の会計処理によらず、従来採用していた会計処理を継続する場合、次の事項を注記するとされている。
① 権利確定条件付き有償新株予約権の概要(各会計期間において存在した権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模(付与数等)及びその変動状況(行使数や失効数等))。ただし、付与日における公正な評価単価については、記載を要しない。
② 採用している会計処理の概要
この場合、「ストックオプション等関係注記」の箇所において、追加情報として注記することが考えられる(記載事例8)。なお、当該注記は、個別財務諸表においても追加情報として注記することが考えられる。
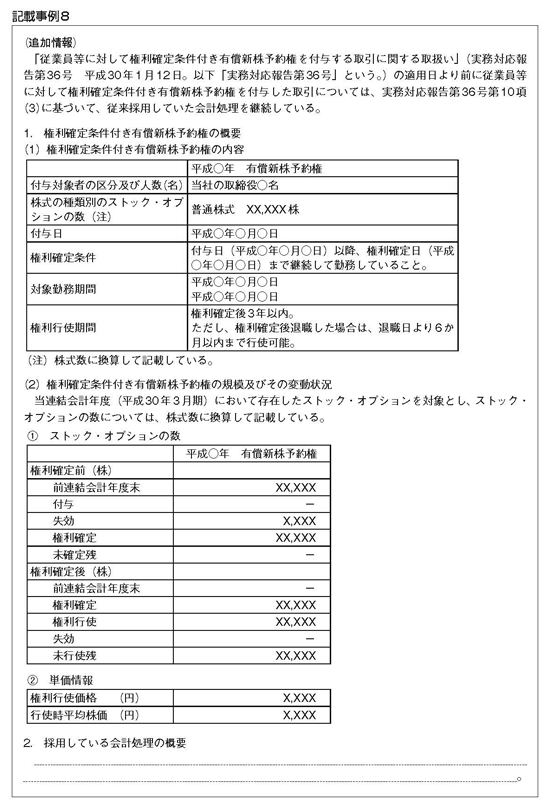
また、36号等を早期適用し、36号に従って会計処理を行う場合(36号第10項(3)の経過措置を除く。)、従業員等に対して付与された権利確定条件付き有償新株予約権は、「ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記」及び「ストック・オプションに関する注記」(連結財規第15条の9及び第15条の10)の対象に含まれるものと考えられる。
4 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
(1)概 要 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(以下「税効果会計基準一部改正」という。)等が平成30年2月16日にASBJから公表され、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされている。ただし、税効果会計基準一部改正については、平成30年3月31日以後最初に終了する連結会計年度及び事業年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとされている。
このため、本稿では、早期適用した場合の表示・注記事項に関する取扱いについて説明する。
表示に関する取扱いについては、貸借対照表における表示について、従来の取扱いでは、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされていたが、改正後においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示するとされている。
注記事項に関する取扱いについては、評価性引当額の内訳に関する情報、税務上の繰越欠損金に関する情報が追加されている。
(2)冒頭記載 改正された会計基準等に関して、経過措置を適用する場合などで、連結財規等の附則に基づいて注記等に係る所要の記載を行った場合には、経理の状況の冒頭にその旨の記載をすることが望ましいと考えられる。税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、当連結会計年度は、附則のただし書により、改正後の連結財規等に基づいて作成し、比較情報については改正前の連結財規等に基づいて作成する旨を記載することが考えられる(個別財務諸表についても同様である。また、(3)、(4)についても同様である)。
(3)貸借対照表の表示 当連結会計年度において税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされている。この場合、前連結会計年度の連結財務諸表について、新たな表示方法に従い連結財務諸表の組替えを行うことになる。
(4)表示方法の変更
記載事例9は、税効果会計基準一部改正を早期適用した場合の注記であり、連結貸借対照表における表示の変更及び税効果会計関係注記における注記事項の追加を行っている旨を記載しているが、第3段落ただし書に示しているように、本記載事例は、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って一定の注記事項に係る比較情報を記載していない場合の記載事例である。
(5)税効果会計関係注記
連結財規等の改正により、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳において、繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、評価性引当額の記載にあたって、繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載するものとされている(「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財規ガイドライン)8の12-2-1)。評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容を記載することが求められている(連結財規第15条の5第2項第2号)。
また、繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、税務上の繰越欠損金に係る次に掲げる事項を記載する。また、繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由を記載することとされている(連結財規第15条の5第3項)。
① 繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
② 繰越欠損金に係る評価性引当額
③ 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
記載事例10は、当連結会計年度において税効果会計基準一部改正を早期適用し、経過的な取扱いに従って一定の注記事項に係る比較情報を記載していない場合における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳の記載事例である。
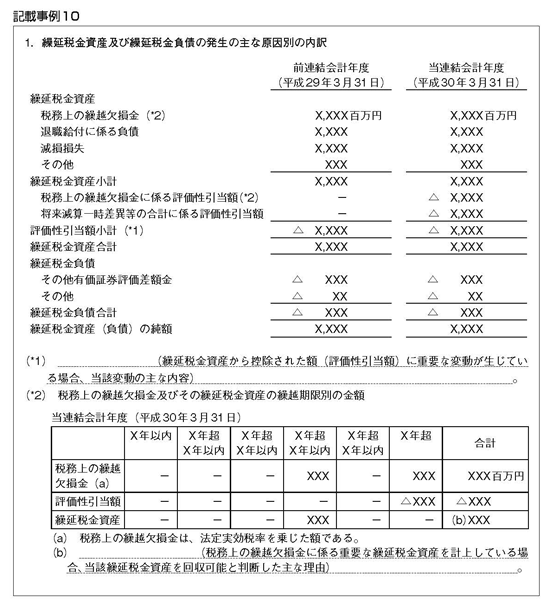
なお、税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、個別財務諸表においても、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、評価性引当額の記載にあたって、繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することとなる。
5 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」
(1)概 要 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「38号」という。)が平成30年3月14日にASBJから公表された。
38号では、「資金決済に関する法律」が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されたことを踏まえ、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いとして、必要最小限の項目について、実務上の取扱いが明らかにされている。
38号は、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用するとされている。ただし、本実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができるとされている。
(2)注 記 38号では、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨、及び仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨について、次の事項を注記するとされている。ただし、仮想通貨交換業者においては、①と②を合算した額が資産総額に比して重要でない場合、また、仮想通貨利用者においては、①が資産総額に比して重要でない場合、注記を省略することができるとされている(38号第17項)。
① 期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
② 預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
③ 期末日において保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができる。
当該注記は追加情報として記載することが考えられ、個別財務諸表においても注記することが考えられる。
記載事例11は、仮想通貨交換業者が38号を早期適用した場合の記載事例である。貸借対照表価額が僅少な仮想通貨について、貸借対照表価額を集約して記載する場合、本記載事例(2)のように「その他」として集約することが考えられる。
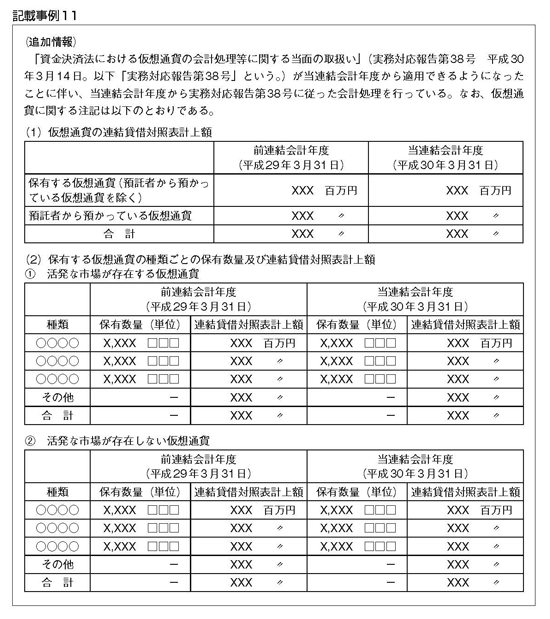
Ⅳ おわりに
本セミナーでは、平成30年3月期における有報の作成上の留意点を説明したほか、FASFが3月30日に公表した「有価証券報告書に関する事項-『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組-」についても併せて紹介した。
当該資料は、以下のURLからダウンロード可能である。
https://www.asb.or.jp/jp/other/web_seminar/kaiji_20180330.html
有価証券報告書作成上の留意点(平成30年3月期提出用)
財務会計基準機構 企画・開示室 高野裕郎
Ⅰ はじめに
財務会計基準機構(FASF)では、FASFセミナー「有価証券報告書作成上の留意点」(以下「本セミナー」という。)を4月2日から13日にかけて全国9か所11回にわたり開催した。
本稿は、本セミナーで説明した内容を基に、平成30年3月期の有価証券報告書(以下「有報」という。)における作成上の留意点についてまとめたものである。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえた「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)等の改正に関する留意点や、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を解説する。
なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ DWG報告を踏まえた開示府令の改正に係る留意点
1 概 要 平成30年1月26日に「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)が公布・施行され、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有報について適用される。本改正は、DWG報告において、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、開示内容の共通化・合理化や非財務情報の開示充実に向けた提言がなされたことによるものであり、有報においては、主に次の項目について改正が行われた。
①「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
②「新株予約権等の状況」
③「大株主の状況」
本稿においては、上記の3項目のほか、併せて改正された内容についても紹介する。
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理等を行い、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載を求める改正が行われた。
これにより、開示府令第二号様式記載上の注意(32)aにおいて、有報に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載することとされた。
なお、本稿では、経営成績等の状況(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(a))、生産、受注及び販売の実績(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b)から(d))、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(e)及び(f))に区分した場合の記載事例を示しているが、企業の開示内容が投資者にとってより分かりやすくなるのであれば、内容を一体的に記載することも考えられる。
(1)経営成績等の状況の概要
① 経営成績等の状況 開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(a)では、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況について、前年同期と比較して、その概要を記載することとされている。その記載にあたっては、改正前における「業績等の概要」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
記載事例1は、経営成績等の状況の記載事例である。
経営成績及びキャッシュ・フローの状況の記載にあたっては、前年同期の数値との比較に関する説明のほか、その背景、要因等について記載することが適当と考えられる。その場合、表やグラフなどを用いて説明することも差支えないものと考えられる。また、財政状態の状況については、その概要を記載することとされており、記載にあたっては、前年同期と比較して記載することが考えられる。
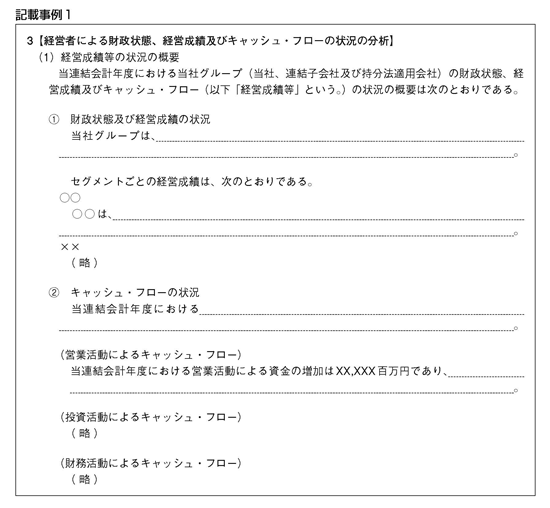
② 生産、受注及び販売の実績 開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b)から(d)において、次の事項を記載することとされている。
a.当連結会計年度における生産、受注及び販売の実績について、前年同期と比較してセグメント情報に関連付けて記載し、生産、受注及び販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を記載すること(開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(b))。
b.生産能力、主要な原材料価格、主要な製商品の仕入価格・販売価格等に著しい変化があった場合、その他生産、受注、販売等に関して特記すべき事項がある場合には、セグメント情報に関連付けてその内容を記載すること(同記載上の注意(32)a(c))。
c.主要な販売先がある場合には、前連結会計年度及び当連結会計年度における相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合を記載すること(ただし、当該割合が100分の10未満の相手先については記載を省略することができる。)(同記載上の注意(32)a(d))。
なお、その記載にあたっては、改正前における「生産、受注及び販売の状況」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」の記載にあたっては、改正前における「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に相当する内容を記載することを出発点に考えると理解しやすいものと考えられる。
開示府令第二号様式記載上の注意(32)a(e)において、経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を記載することとされている。また、資本の財源及び資金の流動性に係る情報についても記載することとされている。
記載事例2は、上記を踏まえた経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載事例である。
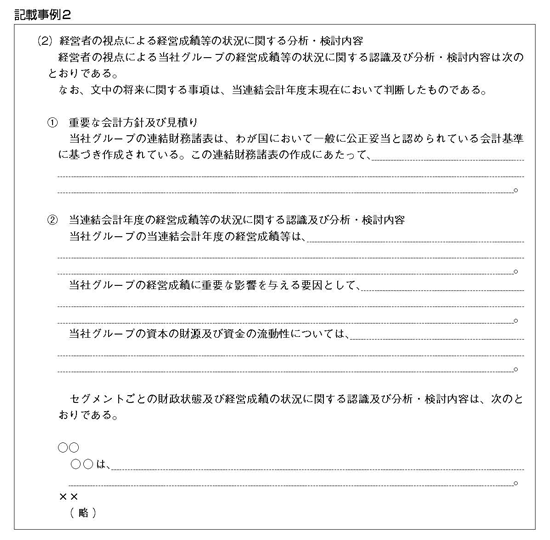
資本の財源及び資金の流動性に係る情報の記載にあたっては、キャッシュ・フロー計算書の内容を単に要約したものを記載するのではなく、企業の経営内容に即して、例えば、重要な資本的支出の予定及びその資金の調達源等について、具体的に記載することが期待されていると考えられる。
また、セグメント情報に記載された区分ごとの認識及び分析・検討内容については、記載事例では、財政状態及び経営成績の状況について記載することを想定しているが、キャッシュ・フローの状況をセグメントごとに把握している場合は、キャッシュ・フローの状況についても記載することが望ましいと考えられる。
なお、経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等に照らして、経営者が経営成績等をどのように分析・検討しているかを記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載することとされている(開示府令第二号様式記載上の注意(32)(e)なお書)点にも、留意する必要がある。
(3)指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成する場合 指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成した当連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財規」という。)により作成した場合の当連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を、従来は「業績等の概要」において記載することとされていた。
本改正により、当該事項については、「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、「経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報」の項目を設けて記載することとされている。
また、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成を開始した場合、要約連結財務諸表を記載するとともに、連結財規に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載することとされているが、当該事項については、「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」の記載の後に、「並行開示情報」の項目を設けて記載することとされている。
3 新株予約権等の状況 「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目については、「新株予約権等の状況」に統合される等の改正が行われた。
(1)ストックオプション制度の内容 「ストックオプション制度の内容」においては、取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合には、当該決議に係る決議年月日、並びに付与対象者の区分及び人数を決議ごとに記載し、当該決議がされていない場合には、該当ない旨を記載することとされた(開示府令第二号様式記載上の注意(39)a)。
また、当該決議により新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、当事業年度の末日における当該新株予約権に係る次に掲げる事項((a)から(i))を記載し、当該決議により新株予約権証券を付与している場合には、有報提出日の属する月の前月末現在における当該事項を併せて記載することとされた(開示府令第二号様式記載上の注意(39)b)。
(a)新株予約権の数
(b)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(c)新株予約権の行使時の払込金額
(d)新株予約権の行使期間
(e)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(f)新株予約権の行使の条件
(g)新株予約権の譲渡に関する事項
(h)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(i)金銭以外の財産を新株予約権の行使の際に出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額
当事業年度末までに取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議により新株予約権証券を付与している場合の記載事例として、記載事例3を掲げている。
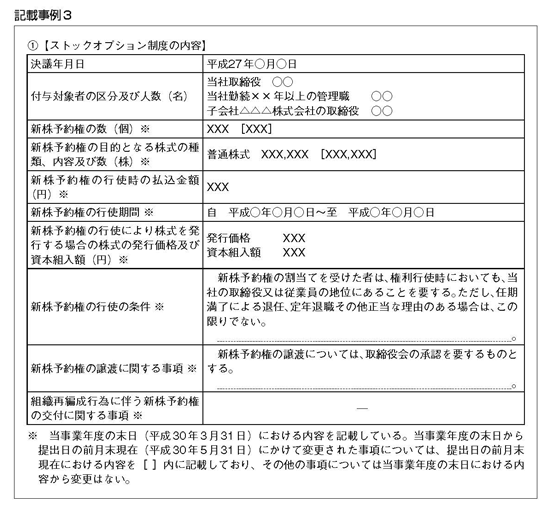
記載事例中「付与対象者の区分及び人数」については、決議日時点の内容を記載することが考えられる。
また、記載事例中「新株予約権の数」等(※が付されている項目)については、改正前と同様に、当事業年度の末日及び有報提出日の属する月の前月末現在における内容の記載が求められているが、本改正により、有報提出日の属する月の前月末現在において、記載すべき内容が、当事業年度の末日における内容から変更がない場合には、その旨を記載することによって、有報提出日の属する月の前月末現在に係る記載を省略することができる(開示府令第二号様式記載上の注意(39)bただし書)とされた。記載事例では、表の欄外において当事業年度の末日における内容から変更がない旨を記載している。
なお、記載事例のケース以外に、当事業年度末後に取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされる場合や新株予約権証券を付与している場合も想定される。
開示府令第二号様式記載上の注意(39)aに掲げる事項については、当事業年度の末日後から有報提出日までの間に取締役、使用人等に対して新株予約権証券を付与する決議がされている場合においても記載することが考えられる。
開示府令第二号様式記載上の注意(39)b(a)から(i)までに掲げる事項については、当事業年度の末日後から有報提出日の属する月の前月末までの間に新株予約権証券を付与している場合は、有報提出日の属する月の前月末現在における内容を記載することが考えられ、有報提出日の属する月の前月末後から有報提出日までの間に新株予約権証券を付与している場合には、付与した時点の内容を記載することが望ましいと考えられる。
また、「ストックオプション制度の内容」については、現行様式における表が撤廃され、企業の判断により過去発行分を一覧表形式で記載することが可能となったことから、内容が類似した複数のストックオプションを発行している場合には、記載事例3のように記載する方法のほかに、内容が類似した複数のストックオプション制度を集約して記載する方法も考えられる(記載事例4)。
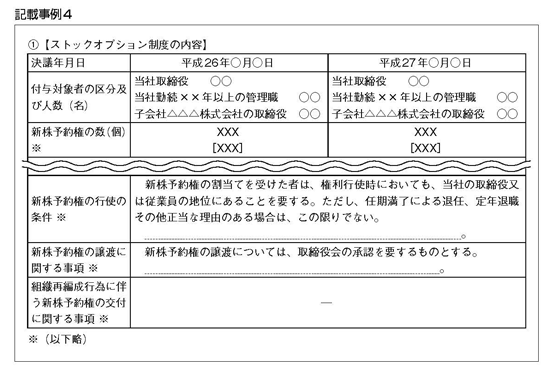
このほか、本改正により、「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部又は一部を、「経理の状況」の「ストック・オプション等関係注記」において集約して記載することができるとされた。ただし、この場合には、「ストックオプション制度の内容」にその旨を記載する必要がある。
(2)ライツプランの内容・その他の新株予約権等の状況 本改正により、「ライツプランの内容」においても、「ストックオプション制度の内容」と同様の改正が行われている。また、「ストックオプション制度の内容」及び「ライツプランの内容」に記載した新株予約権以外の新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、「その他の新株予約権等の状況」において、その内容等を記載することとされている。
4 大株主の状況 「大株主の状況」では、開示府令改正後の様式において「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」を記載することとされ、事業報告と同様に自己株式を控除することとされた。なお、大株主は、提出会社を除く、所有株式数の多い順とされている(開示府令第三号様式記載上の注意(25)c)。
また、提出会社の株主総会又は種類株主総会における議決権行使の基準日現在の「大株主の状況」について記載することとされた。ただし、これにより難い場合にあっては、当事業年度末現在について記載することとされている(開示府令第三号様式記載上の注意(25)a)。「大株主の状況」のほか、「所有者別状況」及び「議決権の状況」についても、「大株主の状況」と同様、議決権行使の基準日現在の内容を記載することとされる等の改正が行われている。
5 その他
(1)役員・従業員株式所有制度の内容 改正前の「従業員株式所有制度の内容」については、改正により「役員・従業員株式所有制度の内容」へと変更されている。開示府令第二号様式記載上の注意(46)においては、このほか、「従業員等持株会」から「役員・従業員持株会」等への変更が行われている。
(2)コーポレート・ガバナンスの状況 取締役等との間で、いわゆる責任限定契約を締結した場合、当該契約の内容の概要として、当該契約によって当該取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含めて記載することとされた(開示府令第二号様式(56)a(a)なお書)。
Ⅲ 会計基準等の改正に係る留意点
1 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が平成29年3月29日にASBJから公表されており、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされている。
本改正により、本実務対応報告の対象範囲に、国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠した財務諸表を作成している在外子会社又は在外関連会社に加えて、指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有報により開示している国内子会社又は国内関連会社についても含めることとしている。
本実務対応報告においては、本実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社又は国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有報により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている。
2 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」
(1)概 要 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下「35号」という。)が平成29年5月2日にASBJから公表されており、平成29年5月31日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用するとされている。
35号は、公共施設等運営事業において、運営権者が公共施設等運営権を取得する取引に関する会計処理及び開示、並びに運営権者が公共施設等に係る更新投資を実施する取引に関する会計処理及び開示に適用するとされている。
(2)公共施設等運営事業等関係注記
記載事例5は、公共施設等運営事業を行っており、かつ、更新投資に関する会計処理について、35号第12項(1)に該当する場合の記載事例である。この場合、連結財規第15条の25第1項及び第2項第1号に定める注記を行うこととなる。
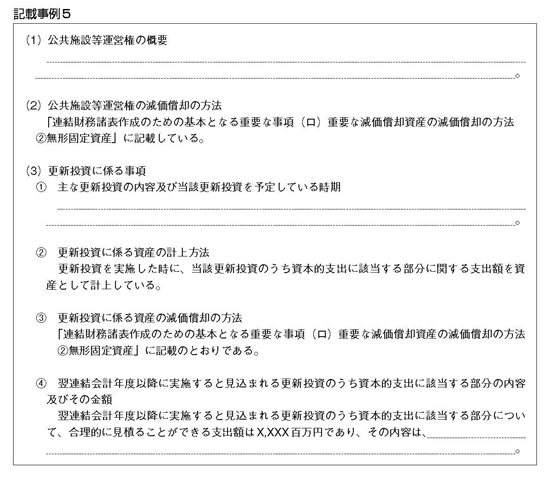
なお、当該記載事例中(2)及び(3)③において、減価償却の方法について会計方針の箇所を参照しているが、この注記において記載する方法も可能である。
3 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等
(1)概 要 実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(以下、「36号」という。)等が平成30年1月12日にASBJから公表された。
36号では、企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、新株予約権の付与に伴い従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引を対象とし、この取引について、基本的に、「ストック・オプション等に関する会計基準」等に準拠した会計処理を行うこととされている。
36号は、平成30年4月1日以後適用するとされているが、公表日以後適用することができるとされているため、平成30年3月期における有報において早期適用することができる。
(2)会計方針の変更
記載事例6は、36号等を早期適用し、これまでの会計処理と異なる場合であって、従業員等に対して付与した権利確定条件付き有償新株予約権が行使されている場合の記載事例である。この場合、第1段落の最後の一文にあるように、会計方針の変更について遡及適用を行うこととなる。
| 記載事例6 |
| (会計方針の変更) 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等が公表日以後適用することができるようになったことに伴い、公表日以後実務対応報告第36号を適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うこととした。当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっている。 この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度における連結貸借対照表は、資本剰余金がXXX百万円増加し、利益剰余金がXXX百万円減少し、新株予約権がXXX百万円増加している。前連結会計年度における連結損益計算書は、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれXX百万円減少している。 前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の遡及適用後の期首残高がXXX百万円増加し、利益剰余金の期首残高がXXX百万円減少し、新株予約権の期首残高がXXX百万円増加している。 前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益がXXX百万円減少し、○○○○がXXX百万円増加している。 なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載している。 |
また、36号では、36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、36号の会計処理によらず、従来採用していた会計処理を継続することができるとされている。
記載事例7は、36号等を早期適用した場合であって、従来採用していた会計処理を継続するときの記載事例である。
| 記載事例7 |
| (会計方針の変更) 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等が公表日以後適用することができるようになったことに伴い、公表日以後実務対応報告第36号を適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うこととした。 ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続している。 |
(3)ストックオプション等関係注記 36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引について、36号の会計処理によらず、従来採用していた会計処理を継続する場合、次の事項を注記するとされている。
① 権利確定条件付き有償新株予約権の概要(各会計期間において存在した権利確定条件付き有償新株予約権の内容、規模(付与数等)及びその変動状況(行使数や失効数等))。ただし、付与日における公正な評価単価については、記載を要しない。
② 採用している会計処理の概要
この場合、「ストックオプション等関係注記」の箇所において、追加情報として注記することが考えられる(記載事例8)。なお、当該注記は、個別財務諸表においても追加情報として注記することが考えられる。
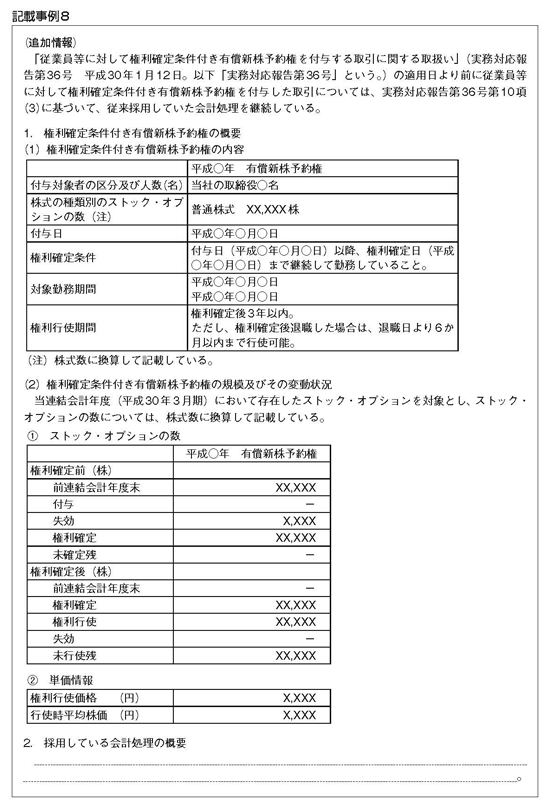
また、36号等を早期適用し、36号に従って会計処理を行う場合(36号第10項(3)の経過措置を除く。)、従業員等に対して付与された権利確定条件付き有償新株予約権は、「ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記」及び「ストック・オプションに関する注記」(連結財規第15条の9及び第15条の10)の対象に含まれるものと考えられる。
4 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
(1)概 要 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(以下「税効果会計基準一部改正」という。)等が平成30年2月16日にASBJから公表され、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされている。ただし、税効果会計基準一部改正については、平成30年3月31日以後最初に終了する連結会計年度及び事業年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとされている。
このため、本稿では、早期適用した場合の表示・注記事項に関する取扱いについて説明する。
表示に関する取扱いについては、貸借対照表における表示について、従来の取扱いでは、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされていたが、改正後においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示するとされている。
注記事項に関する取扱いについては、評価性引当額の内訳に関する情報、税務上の繰越欠損金に関する情報が追加されている。
(2)冒頭記載 改正された会計基準等に関して、経過措置を適用する場合などで、連結財規等の附則に基づいて注記等に係る所要の記載を行った場合には、経理の状況の冒頭にその旨の記載をすることが望ましいと考えられる。税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、当連結会計年度は、附則のただし書により、改正後の連結財規等に基づいて作成し、比較情報については改正前の連結財規等に基づいて作成する旨を記載することが考えられる(個別財務諸表についても同様である。また、(3)、(4)についても同様である)。
(3)貸借対照表の表示 当連結会計年度において税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされている。この場合、前連結会計年度の連結財務諸表について、新たな表示方法に従い連結財務諸表の組替えを行うことになる。
(4)表示方法の変更
記載事例9は、税効果会計基準一部改正を早期適用した場合の注記であり、連結貸借対照表における表示の変更及び税効果会計関係注記における注記事項の追加を行っている旨を記載しているが、第3段落ただし書に示しているように、本記載事例は、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って一定の注記事項に係る比較情報を記載していない場合の記載事例である。
| 記載事例9 |
| (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)が当連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当連結会計年度から税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更した。 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」XXX百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」XXX百万円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負債」XXX百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」XXX百万円に含めて表示している。 また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加している。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していない。 |
また、繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、税務上の繰越欠損金に係る次に掲げる事項を記載する。また、繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由を記載することとされている(連結財規第15条の5第3項)。
① 繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
② 繰越欠損金に係る評価性引当額
③ 繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
記載事例10は、当連結会計年度において税効果会計基準一部改正を早期適用し、経過的な取扱いに従って一定の注記事項に係る比較情報を記載していない場合における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳の記載事例である。
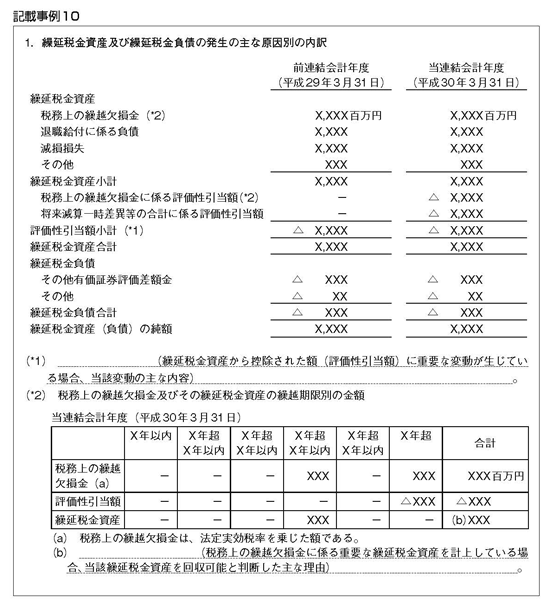
なお、税効果会計基準一部改正を早期適用した場合、個別財務諸表においても、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳に繰越欠損金を記載する場合であって、当該繰越欠損金が重要であるときは、評価性引当額の記載にあたって、繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することとなる。
5 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」
(1)概 要 実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「38号」という。)が平成30年3月14日にASBJから公表された。
38号では、「資金決済に関する法律」が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されたことを踏まえ、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いとして、必要最小限の項目について、実務上の取扱いが明らかにされている。
38号は、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用するとされている。ただし、本実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができるとされている。
(2)注 記 38号では、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨、及び仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨について、次の事項を注記するとされている。ただし、仮想通貨交換業者においては、①と②を合算した額が資産総額に比して重要でない場合、また、仮想通貨利用者においては、①が資産総額に比して重要でない場合、注記を省略することができるとされている(38号第17項)。
① 期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
② 預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
③ 期末日において保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については、貸借対照表価額を集約して記載することができる。
当該注記は追加情報として記載することが考えられ、個別財務諸表においても注記することが考えられる。
記載事例11は、仮想通貨交換業者が38号を早期適用した場合の記載事例である。貸借対照表価額が僅少な仮想通貨について、貸借対照表価額を集約して記載する場合、本記載事例(2)のように「その他」として集約することが考えられる。
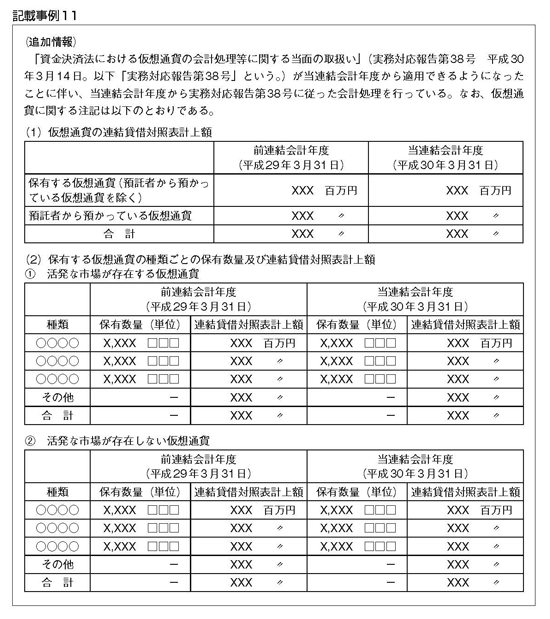
Ⅳ おわりに
本セミナーでは、平成30年3月期における有報の作成上の留意点を説明したほか、FASFが3月30日に公表した「有価証券報告書に関する事項-『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組-」についても併せて紹介した。
当該資料は、以下のURLからダウンロード可能である。
https://www.asb.or.jp/jp/other/web_seminar/kaiji_20180330.html
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -